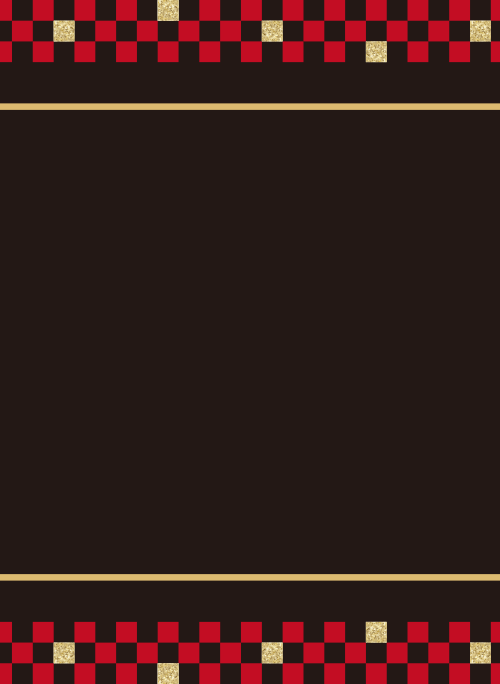数時間後、時計が日付を変えようかという頃合い。
庸介は隣の部屋が妙に騒々しいことにムカついた。本を読んでいたので勉強の邪魔だとは言えないものの、それでもこの時間だ。
しばらく我慢していたが、収まりそうもないので綾の部屋に向かった。
「うっせぇんだよ! 何時だと思ってる!」
ノックもせずに怒鳴り込んだ庸介は、ビールの缶が散らばった中で泣いている綾を見て言葉を失った。
「あ、庸介君、うるさかった? ごめんね」
「…………」
姉が泣くといえば、コンクールで落選した時ぐらいしか思い当たらない。しかし今はコンクールの時期じゃない。本心から驚いて、目を丸くした。
「どうしたの? 旅行の計画、練るんじゃなかったのかよ?」
理衣は困ったように泣きじゃくる綾を抱きしめている。庸介の顔を見たが、すぐに綾をなだめにかかった。
「綾、もう寝ようよ。ね?」
「理衣ぃ~悔しい~」
「わかってるよ。わかってる。私は味方だから、ね?」
「だってぇ~」
酔っ払っているのは明白だ。そんな珍しい綾の姿を黙って見守った。
「綾、綾」
「うえぇぇぇ~ん!」
理衣に抱きついてしばし泣くと、その内に寝てしまった。それを確認し、理衣はホッと息をついた。
「庸介君、悪いけど、手伝って」
「……うん」
二人で綾をベッドに寝かせる。
涙で目元が腫れている顔を見つめた後、理衣は残っている缶ビールに手を伸ばした。
「あのさぁ、綾にカレシがいたの、知ってた?」
「え!」
「って、知らないよね。さっき、できるんなら早く作れって言ってたんだから」
心底驚く庸介にクスッと笑い、理衣は再び思い詰めたような顔をした。
「と、言ってもね、まだつきあって三ヶ月ぐらいなんだけどさ。そのカレシがさぁ、実は綾と競ってる女の子との二股だってわかってね」
「二股?」
「うん。綾に近付いたの、彼女の為みたいでね。ほら、情報を得るっていうか、動向を探るっていうか。綾って作品には純粋じゃない。彼のほうもカノジョのために綾と友達程度にって思っていただろうけど、会ってるうちに傾いたみたいで、それを感じた彼女が反撃に出たのよ」
「反撃……」
「うん」
庸介は言葉もなく理衣の話を聞いていた。
「カレシのほうは、ホントに綾に傾いてたみたいなんだけど、綾ってばキレちゃってさ。一方的に別れるって言って。まぁ、そういう人とは続かないだろうけど。私には愚痴聞いて、一緒に旅行に行ってあげるぐらいしかできないから」
「オトコの方は、どうなったの?」
「さぁ。綾に別れるって言われても、言い返さなかったみたいだから、彼女の方に行ったんじゃない?」
「最低」
「そうだね。でも、そういう面倒臭いトラブルはイヤみたい」
その言葉がズキッと胸に突き刺さった。
「ごめんね、勉強の邪魔はしないって言ったのに」
「なんで謝るの? 騒いでたの姉貴じゃん」
理衣はニコッと笑った。
「友達だから、連帯責任」
「ヘンなの」
理衣は缶ビールを見つめつつ、微笑ましそうに口元を弛めた。
「私、兄弟いないから、綾がいっつもうれしそうに庸介君の話をするのが羨ましかったんだ」
「え?」
「彫刻に進んだのは偶然で、工作ならなんでもよかったって話してね。なにか作って弟に見せると、必ず欲しいってしつこくまとわりつく。それがうれしくて、弟の喜びそうなモノを選んで、親に買ってもらって、作ってたって。いいなぁって思ってた。私も、そんな兄弟欲しいって」
「ウソだよ」
「ホントだよ。そう言って子どもの頃の話をする綾の顔は輝いてるもん」
庸介の脳裏に秀二の言葉が蘇った。
――小さい頃から、工作に打ち込んでる姿はカッコイイって思ってたし、完成した時のうれしそうな顔は輝いていた。
「ますます羨ましくてさ。私も兄弟欲しい! ってこの年になって思ったもん」
「なんでお父さん、いないの? 離婚した?」
「あら、いきなりね」
考えていることと違うことを口にしていた。それが不躾だと察し、小さく「ごめん、いい」と返した。だが理衣は笑って答えた。
「最初からいないの。お腹に中にいる時に事故で死んじゃったらしいわ」
「……ごめん」
「いいのよ。隠すことでもないから。庸介君、明日も学校でしょ? もう寝たほうがいいよ。もう騒がないし、ごめんね」
「……うん」
「おやすみ」
「おやすみ」
綾の部屋から出ようとして一度振り返った。
理衣がニコリと微笑みつつ、小さく手を振っている。そんな姿が清楚に見えた。それが逆に杏子とのことを思い出させて羞恥が起こる。
庸介は逃げるように部屋に戻ってベッドに潜り込んだ。
いろいろなことが起こり、いろいろな考えが浮かぶ。
杏子とのことも、振られてやけ酒食らって泣いている姉も、その面倒を見てつきあっている理衣も。
それぞれに思うことはあるが、煩わしいことは考えないようにと自らに言い聞かせ、ベッドにもぐりこんだのだった。
庸介は隣の部屋が妙に騒々しいことにムカついた。本を読んでいたので勉強の邪魔だとは言えないものの、それでもこの時間だ。
しばらく我慢していたが、収まりそうもないので綾の部屋に向かった。
「うっせぇんだよ! 何時だと思ってる!」
ノックもせずに怒鳴り込んだ庸介は、ビールの缶が散らばった中で泣いている綾を見て言葉を失った。
「あ、庸介君、うるさかった? ごめんね」
「…………」
姉が泣くといえば、コンクールで落選した時ぐらいしか思い当たらない。しかし今はコンクールの時期じゃない。本心から驚いて、目を丸くした。
「どうしたの? 旅行の計画、練るんじゃなかったのかよ?」
理衣は困ったように泣きじゃくる綾を抱きしめている。庸介の顔を見たが、すぐに綾をなだめにかかった。
「綾、もう寝ようよ。ね?」
「理衣ぃ~悔しい~」
「わかってるよ。わかってる。私は味方だから、ね?」
「だってぇ~」
酔っ払っているのは明白だ。そんな珍しい綾の姿を黙って見守った。
「綾、綾」
「うえぇぇぇ~ん!」
理衣に抱きついてしばし泣くと、その内に寝てしまった。それを確認し、理衣はホッと息をついた。
「庸介君、悪いけど、手伝って」
「……うん」
二人で綾をベッドに寝かせる。
涙で目元が腫れている顔を見つめた後、理衣は残っている缶ビールに手を伸ばした。
「あのさぁ、綾にカレシがいたの、知ってた?」
「え!」
「って、知らないよね。さっき、できるんなら早く作れって言ってたんだから」
心底驚く庸介にクスッと笑い、理衣は再び思い詰めたような顔をした。
「と、言ってもね、まだつきあって三ヶ月ぐらいなんだけどさ。そのカレシがさぁ、実は綾と競ってる女の子との二股だってわかってね」
「二股?」
「うん。綾に近付いたの、彼女の為みたいでね。ほら、情報を得るっていうか、動向を探るっていうか。綾って作品には純粋じゃない。彼のほうもカノジョのために綾と友達程度にって思っていただろうけど、会ってるうちに傾いたみたいで、それを感じた彼女が反撃に出たのよ」
「反撃……」
「うん」
庸介は言葉もなく理衣の話を聞いていた。
「カレシのほうは、ホントに綾に傾いてたみたいなんだけど、綾ってばキレちゃってさ。一方的に別れるって言って。まぁ、そういう人とは続かないだろうけど。私には愚痴聞いて、一緒に旅行に行ってあげるぐらいしかできないから」
「オトコの方は、どうなったの?」
「さぁ。綾に別れるって言われても、言い返さなかったみたいだから、彼女の方に行ったんじゃない?」
「最低」
「そうだね。でも、そういう面倒臭いトラブルはイヤみたい」
その言葉がズキッと胸に突き刺さった。
「ごめんね、勉強の邪魔はしないって言ったのに」
「なんで謝るの? 騒いでたの姉貴じゃん」
理衣はニコッと笑った。
「友達だから、連帯責任」
「ヘンなの」
理衣は缶ビールを見つめつつ、微笑ましそうに口元を弛めた。
「私、兄弟いないから、綾がいっつもうれしそうに庸介君の話をするのが羨ましかったんだ」
「え?」
「彫刻に進んだのは偶然で、工作ならなんでもよかったって話してね。なにか作って弟に見せると、必ず欲しいってしつこくまとわりつく。それがうれしくて、弟の喜びそうなモノを選んで、親に買ってもらって、作ってたって。いいなぁって思ってた。私も、そんな兄弟欲しいって」
「ウソだよ」
「ホントだよ。そう言って子どもの頃の話をする綾の顔は輝いてるもん」
庸介の脳裏に秀二の言葉が蘇った。
――小さい頃から、工作に打ち込んでる姿はカッコイイって思ってたし、完成した時のうれしそうな顔は輝いていた。
「ますます羨ましくてさ。私も兄弟欲しい! ってこの年になって思ったもん」
「なんでお父さん、いないの? 離婚した?」
「あら、いきなりね」
考えていることと違うことを口にしていた。それが不躾だと察し、小さく「ごめん、いい」と返した。だが理衣は笑って答えた。
「最初からいないの。お腹に中にいる時に事故で死んじゃったらしいわ」
「……ごめん」
「いいのよ。隠すことでもないから。庸介君、明日も学校でしょ? もう寝たほうがいいよ。もう騒がないし、ごめんね」
「……うん」
「おやすみ」
「おやすみ」
綾の部屋から出ようとして一度振り返った。
理衣がニコリと微笑みつつ、小さく手を振っている。そんな姿が清楚に見えた。それが逆に杏子とのことを思い出させて羞恥が起こる。
庸介は逃げるように部屋に戻ってベッドに潜り込んだ。
いろいろなことが起こり、いろいろな考えが浮かぶ。
杏子とのことも、振られてやけ酒食らって泣いている姉も、その面倒を見てつきあっている理衣も。
それぞれに思うことはあるが、煩わしいことは考えないようにと自らに言い聞かせ、ベッドにもぐりこんだのだった。