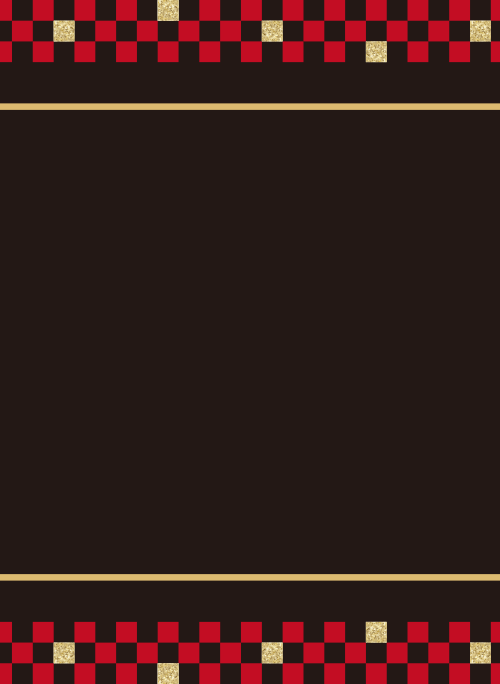家に帰ると、ダイニングに理衣がいる。母と楽しそうに話をしていた。
まだいたのか、そう思った庸介だったが、彼女の髪が濡れ、肌にほのかな赤みがさしていることに気付いてドキリとした。
風呂上がりの理衣は艶っぽくて、さっきとは違う雰囲気だった。
「あ、おかえり」
「……まだいるんだ」
ついさっき思ったことを口にした。
「これ、庸介! 森下さんに失礼じゃない」
すかさず母が窘めたが、無視した。
「今日ね、泊めてもらうの。綾とは学部は同じだけど学科が違うから、あんまり顔を合わせる機会がないのよ。旅行の計画、今夜一晩で決めちゃおうってことになってね。大丈夫、庸介君の邪魔はしないから」
「…………」
「それにしても、よかった。怒って出て行っちゃったから気にしてたんだけどさ。機嫌直ったみたいでホッとした」
「え?」
「なんだかスッキリした顔してるし」
ギョッとして理衣の顔を凝視すると、理衣は愛嬌のある笑みを浮かべて庸介を見返した。
見透かされている? と、一瞬思ったが、家を出てから戻ってくるまでの間、なにがあったかなど理衣が知っているはずもない。ドキドキしながら視線を逸らせるのが精一杯だった。
「庸介君の分のアイスが残ってるから、お風呂あがりでも食べてね」
「う、うん」
そこに綾がやってきた。
「綾、運ぶの手伝って」
「あ、おばさん、私がします」
母は笑って座っているように促した。が、理衣はしつこく食い下がった。
「私、母と二人だったんですけど、その母はずっと働きに出ていたから、いつも一人でご飯食べていたんです。こんなふうに食事の用意をしたり、運んだり、大勢で食べることないから、手伝いたいんです」
「まぁ、そうなの。じゃあ、お願いするわ。焼き上がったものからお皿に盛るから、どんどん運んでちょうだい」
「はい!」
そんなやり取りを庸介は無言で聞いていた。
(父親がいないのか……まぁ、ウチも親父は外国に単身赴任中だから、同じようなもんだけど。ふーん)
うれしそうに母と話をしている理衣は、さっきと違い、子どもっぽかった。
よくしゃべり、よく笑う。半乾きの髪を一つに束ね、化粧を落とした顔は高校生でも通るかもしれない。
(胸はあんま大きくないし、杏子のほうが色っぽいかもしれない)
そんなことを考えた。同時に、公園の茂みで杏子に求められたことを思い出した。
(杏子、怒ってるかな? でも、今回はいいって言ったの、杏子本人だし)
キスの後、杏子に引っ張られて草が茂る隅に潜り込んだ。
さらにキスをし、庸介は杏子のスカートの中に手を入れようとした。だが、それよりも杏子のほうが早かった。ズボンのファスナーを下ろすと、下着の上から触ってきたのだ。
それがなんだか性急すぎて庸介の戸惑いを大きくさせた。
ほとんど反射的に杏子の手を払いのけていた。驚いた杏子は動きを止めて庸介の凝視した。
「なんか……ちょっと」
絞り出すように言うと、杏子は引き攣った笑みを浮かべた。それからなにを思ったのか、庸介のズボンのポケットをまさぐり、スマートフォンを取りだした。
「あけてよ」
言われるままにパスワードを入れて解除する。杏子は再びスマートフォンを取り上げると、チャットアプリを立ち上げ、自分のIDを登録して庸介に返した。
「その気になった連絡してよ」
そう言うと、さっと立ち上がって帰って行った。庸介はしばらく呆然と杏子が歩いて行った方角を見つめていた。
そんな杏子と目の前にいる理衣は、対照的だ。
(杏子はともかく、この女は姉貴の友達で、カメラオタクだ。俺には関係ない。なにをドキドキしてンだか!)
女三人で盛り上がる食卓で、庸介は一人無言で夕食を口にしていた。
しばらく後、皆で手分けをして片付けを終えると、母はコーヒーを淹れ、見たい番組があるからと言ってさっさと自分の部屋に引っ込んでしまった。
それに追随するかのように、庸介もコーヒーを持って部屋に戻った。
まだいたのか、そう思った庸介だったが、彼女の髪が濡れ、肌にほのかな赤みがさしていることに気付いてドキリとした。
風呂上がりの理衣は艶っぽくて、さっきとは違う雰囲気だった。
「あ、おかえり」
「……まだいるんだ」
ついさっき思ったことを口にした。
「これ、庸介! 森下さんに失礼じゃない」
すかさず母が窘めたが、無視した。
「今日ね、泊めてもらうの。綾とは学部は同じだけど学科が違うから、あんまり顔を合わせる機会がないのよ。旅行の計画、今夜一晩で決めちゃおうってことになってね。大丈夫、庸介君の邪魔はしないから」
「…………」
「それにしても、よかった。怒って出て行っちゃったから気にしてたんだけどさ。機嫌直ったみたいでホッとした」
「え?」
「なんだかスッキリした顔してるし」
ギョッとして理衣の顔を凝視すると、理衣は愛嬌のある笑みを浮かべて庸介を見返した。
見透かされている? と、一瞬思ったが、家を出てから戻ってくるまでの間、なにがあったかなど理衣が知っているはずもない。ドキドキしながら視線を逸らせるのが精一杯だった。
「庸介君の分のアイスが残ってるから、お風呂あがりでも食べてね」
「う、うん」
そこに綾がやってきた。
「綾、運ぶの手伝って」
「あ、おばさん、私がします」
母は笑って座っているように促した。が、理衣はしつこく食い下がった。
「私、母と二人だったんですけど、その母はずっと働きに出ていたから、いつも一人でご飯食べていたんです。こんなふうに食事の用意をしたり、運んだり、大勢で食べることないから、手伝いたいんです」
「まぁ、そうなの。じゃあ、お願いするわ。焼き上がったものからお皿に盛るから、どんどん運んでちょうだい」
「はい!」
そんなやり取りを庸介は無言で聞いていた。
(父親がいないのか……まぁ、ウチも親父は外国に単身赴任中だから、同じようなもんだけど。ふーん)
うれしそうに母と話をしている理衣は、さっきと違い、子どもっぽかった。
よくしゃべり、よく笑う。半乾きの髪を一つに束ね、化粧を落とした顔は高校生でも通るかもしれない。
(胸はあんま大きくないし、杏子のほうが色っぽいかもしれない)
そんなことを考えた。同時に、公園の茂みで杏子に求められたことを思い出した。
(杏子、怒ってるかな? でも、今回はいいって言ったの、杏子本人だし)
キスの後、杏子に引っ張られて草が茂る隅に潜り込んだ。
さらにキスをし、庸介は杏子のスカートの中に手を入れようとした。だが、それよりも杏子のほうが早かった。ズボンのファスナーを下ろすと、下着の上から触ってきたのだ。
それがなんだか性急すぎて庸介の戸惑いを大きくさせた。
ほとんど反射的に杏子の手を払いのけていた。驚いた杏子は動きを止めて庸介の凝視した。
「なんか……ちょっと」
絞り出すように言うと、杏子は引き攣った笑みを浮かべた。それからなにを思ったのか、庸介のズボンのポケットをまさぐり、スマートフォンを取りだした。
「あけてよ」
言われるままにパスワードを入れて解除する。杏子は再びスマートフォンを取り上げると、チャットアプリを立ち上げ、自分のIDを登録して庸介に返した。
「その気になった連絡してよ」
そう言うと、さっと立ち上がって帰って行った。庸介はしばらく呆然と杏子が歩いて行った方角を見つめていた。
そんな杏子と目の前にいる理衣は、対照的だ。
(杏子はともかく、この女は姉貴の友達で、カメラオタクだ。俺には関係ない。なにをドキドキしてンだか!)
女三人で盛り上がる食卓で、庸介は一人無言で夕食を口にしていた。
しばらく後、皆で手分けをして片付けを終えると、母はコーヒーを淹れ、見たい番組があるからと言ってさっさと自分の部屋に引っ込んでしまった。
それに追随するかのように、庸介もコーヒーを持って部屋に戻った。