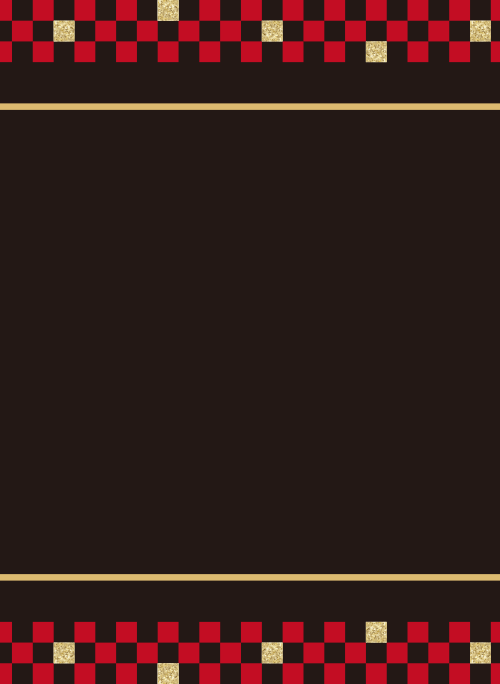むかっ腹を立てて飛び出した庸介は、近くの公園に出向き、芝生の上に寝転がった。
陽が傾いて空が赤らんでいる。そんな様子をぼんやりと眺めた。
(うるせぇんだよ。大人風吹かせてさ。俺は『一生懸命』なんて言葉は大っ嫌いなんだ)
綾と一緒に工作やプラモデルを作っていた頃を次々と思い出し、不愉快度マックス状態だ。
――綾さんが作品と向き合ってる姿はきれいだと思う。
秀二の言葉がぼんやりと浮かんだ。
――小さい頃から、工作に打ち込んでる姿はカッコイイって思ってたし、完成した時のうれしそうな顔は輝いていた。
完成したプラモデルを見せ、笑っている幼い姉の顔を思い出す。とてもきれいに仕上がった作品を、欲しいとせがむなど日常だった。そのたび、綾はうれしそうに「あげる」と言ったものだ。
親と買い物に行っても、綾は庸介の好きな車のプラモデルばかり探し、難しそうな物を選んで買ってもらっていた。それから数日で作り上げ、庸介に渡す。小学生の時は、そんな日々だった。
(輝いていた、か。でもさ、今の姉貴はちっともうれしそうじゃないんだ。楽しくないなら、やめちまえばいいんだ。プロなんか目指さず、女磨いて、イイ男捕まえて、食わしてもらいながらのんびり趣味でやりゃいいじゃん。プロになろうとするから苦しいんだろ?)
なんだかザラつくような、別の嫌な感じが感情が湧いてくるのを感じて視線を泳がせる。
(そりゃあ、今はそんな時代じゃないことはわかってるよ。性別なんて関係ない、デキる人が成功していく時代だよ。中身だってことくらい、俺だってわかってるよ。誰かに食わせてもらう、なんて考えがダサいことくらい)
次第に暮れていく空を見上げながら考える。だが、突然その視界に女の顔が飛び込んできた。
「やほっ、ヨースケ。久しぶり!」
それは中学の時まで親しかった同級生の綾瀬杏子だった。
毛先に細かなカールをかけた明るいブラウンの髪が目を引く。顔に似合わない赤いルージュも、彼女の生活を語っている。
庸介は久しぶりに会った同級生が、この二年間、どんな生活を送ってきたかわかった気がした。
「杏子か。ホント、久しぶり」
起き上がって座る庸介の隣に腰を下ろす。
「こんなところで黄昏て、どうしたの? カノジョとケンカした?」
「俺、つきあってる子、いないし」
「そーなの?」
「あぁ。特定の女は面倒だから」
杏子は目を丸くした。
「はぁ? なんで?」
「だってさ、他の子と仲良くしたら怒るだろ? それにイベントのたびにどっか連れて行けとか、プレゼント欲しいとか。そういうの、煩わしいから」
「ヨースケってそんなタイプだったっけ? へぇ。軽いのがいいんだ? 軽いつきあい」
悪戯っぽい目で覗き込んでくる杏子に向けて、うん、と頷くと、またコロンと横になった。
「暑苦しくてウザいのはイヤなんだよ」
「じゃぁさ。後腐れがなかったら、エッチもオーケイなの?」
いきなりの発言にやや驚くが、意外ではない気もする。しかしながら了解する気にはなれなかった。
(こういうことを言うヤツほど、後がうるさいんだ)
胸の内で呟き、首を横に振った。
「そっちの話は別。なんか、乗らないから」
「ヤってもらっても?」
すごいことを言うなと思うが、そこは深追いしない。
「杏子ってばそういうの、好きなわけ?」
杏子はますます悪戯っぽく微笑んだ。
「一緒に気持ち良くなれる為なら、ご奉仕するよ?」
「好きな相手じゃなくても?」
「じゃない? 心と体は、いつでも一緒とは限らないもん」
「…………」
「好きな人なのにイカないとか、好きじゃないのに燃えるとか、ない? オトコはイケれば一緒? ヨースケ、けっこうお気に入りだったからさ、あたし、大丈夫だけど。どう?」
体を寄せられ、視線が胸元に落ちた。
第二ボタンまで外された胸元は、その谷間をくっきり見せている。庸介は視線を取られ、体の奥がズンッと熱を帯びたことを感じた。
「陽が落ちたらさぁ、そこらの茂みでなにやってても、誰にも見つからないよ? ね?」
「…………」
柔らかな感触が腕に当たった。庸介はその感触に動揺し、衝動的に杏子を抱きしめた。そこにすかさず杏子が唇を重ねてきた。
「ん」
ずいぶん慣れているのか、杏子が上手に舌を入れてくる。
濃厚なキスにますます目が眩み、杏子の腕を必死に掴んでいた。
「ヨースケ、こっち」
艶っぽい顔を見つめてくる杏子の顔を、茫然と見つめる。庸介は自分の中に、流されることを求める自分と、困惑する自分を感じた。
陽が傾いて空が赤らんでいる。そんな様子をぼんやりと眺めた。
(うるせぇんだよ。大人風吹かせてさ。俺は『一生懸命』なんて言葉は大っ嫌いなんだ)
綾と一緒に工作やプラモデルを作っていた頃を次々と思い出し、不愉快度マックス状態だ。
――綾さんが作品と向き合ってる姿はきれいだと思う。
秀二の言葉がぼんやりと浮かんだ。
――小さい頃から、工作に打ち込んでる姿はカッコイイって思ってたし、完成した時のうれしそうな顔は輝いていた。
完成したプラモデルを見せ、笑っている幼い姉の顔を思い出す。とてもきれいに仕上がった作品を、欲しいとせがむなど日常だった。そのたび、綾はうれしそうに「あげる」と言ったものだ。
親と買い物に行っても、綾は庸介の好きな車のプラモデルばかり探し、難しそうな物を選んで買ってもらっていた。それから数日で作り上げ、庸介に渡す。小学生の時は、そんな日々だった。
(輝いていた、か。でもさ、今の姉貴はちっともうれしそうじゃないんだ。楽しくないなら、やめちまえばいいんだ。プロなんか目指さず、女磨いて、イイ男捕まえて、食わしてもらいながらのんびり趣味でやりゃいいじゃん。プロになろうとするから苦しいんだろ?)
なんだかザラつくような、別の嫌な感じが感情が湧いてくるのを感じて視線を泳がせる。
(そりゃあ、今はそんな時代じゃないことはわかってるよ。性別なんて関係ない、デキる人が成功していく時代だよ。中身だってことくらい、俺だってわかってるよ。誰かに食わせてもらう、なんて考えがダサいことくらい)
次第に暮れていく空を見上げながら考える。だが、突然その視界に女の顔が飛び込んできた。
「やほっ、ヨースケ。久しぶり!」
それは中学の時まで親しかった同級生の綾瀬杏子だった。
毛先に細かなカールをかけた明るいブラウンの髪が目を引く。顔に似合わない赤いルージュも、彼女の生活を語っている。
庸介は久しぶりに会った同級生が、この二年間、どんな生活を送ってきたかわかった気がした。
「杏子か。ホント、久しぶり」
起き上がって座る庸介の隣に腰を下ろす。
「こんなところで黄昏て、どうしたの? カノジョとケンカした?」
「俺、つきあってる子、いないし」
「そーなの?」
「あぁ。特定の女は面倒だから」
杏子は目を丸くした。
「はぁ? なんで?」
「だってさ、他の子と仲良くしたら怒るだろ? それにイベントのたびにどっか連れて行けとか、プレゼント欲しいとか。そういうの、煩わしいから」
「ヨースケってそんなタイプだったっけ? へぇ。軽いのがいいんだ? 軽いつきあい」
悪戯っぽい目で覗き込んでくる杏子に向けて、うん、と頷くと、またコロンと横になった。
「暑苦しくてウザいのはイヤなんだよ」
「じゃぁさ。後腐れがなかったら、エッチもオーケイなの?」
いきなりの発言にやや驚くが、意外ではない気もする。しかしながら了解する気にはなれなかった。
(こういうことを言うヤツほど、後がうるさいんだ)
胸の内で呟き、首を横に振った。
「そっちの話は別。なんか、乗らないから」
「ヤってもらっても?」
すごいことを言うなと思うが、そこは深追いしない。
「杏子ってばそういうの、好きなわけ?」
杏子はますます悪戯っぽく微笑んだ。
「一緒に気持ち良くなれる為なら、ご奉仕するよ?」
「好きな相手じゃなくても?」
「じゃない? 心と体は、いつでも一緒とは限らないもん」
「…………」
「好きな人なのにイカないとか、好きじゃないのに燃えるとか、ない? オトコはイケれば一緒? ヨースケ、けっこうお気に入りだったからさ、あたし、大丈夫だけど。どう?」
体を寄せられ、視線が胸元に落ちた。
第二ボタンまで外された胸元は、その谷間をくっきり見せている。庸介は視線を取られ、体の奥がズンッと熱を帯びたことを感じた。
「陽が落ちたらさぁ、そこらの茂みでなにやってても、誰にも見つからないよ? ね?」
「…………」
柔らかな感触が腕に当たった。庸介はその感触に動揺し、衝動的に杏子を抱きしめた。そこにすかさず杏子が唇を重ねてきた。
「ん」
ずいぶん慣れているのか、杏子が上手に舌を入れてくる。
濃厚なキスにますます目が眩み、杏子の腕を必死に掴んでいた。
「ヨースケ、こっち」
艶っぽい顔を見つめてくる杏子の顔を、茫然と見つめる。庸介は自分の中に、流されることを求める自分と、困惑する自分を感じた。