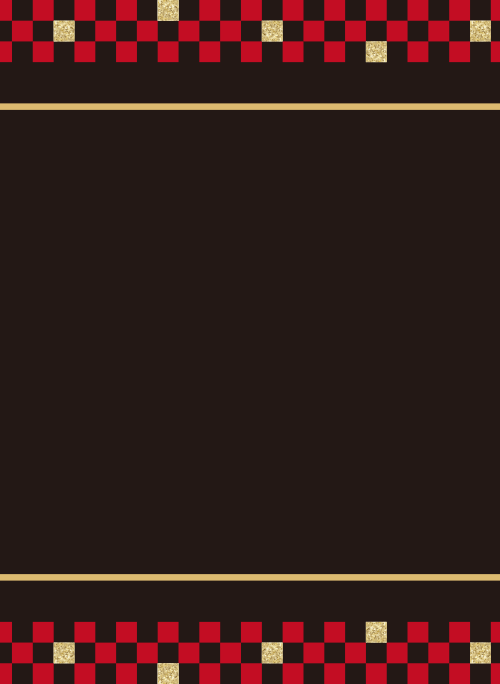家に帰ってきた。
「あれ」
ダイニングに入ると、見知らぬ女が座っていた。あっさりとして小きれいな顔立ちだ。
庸介に気付き、ニコッと微笑んだ。庸介は一瞬視線を取られ、言葉を失った。今時珍しい漆黒のロングストレートの髪、額の部分で切りそろえられた前髪。独特の雰囲気があった。
「はじめまして」
「あ、はぁ。はじめまして」
つられて返事をすると、後ろから姉が現れた。
「あ、庸介、帰ったの」
「うん。友達?」
「そうよ。森下理衣さん」
「この人も彫刻してんの?」
「うぅん、理衣はカメラマン志望」
「カメラマン? 女で?」
その言葉には理衣本人が応えた。
「女性カメラマンってけっこう多いのよ。それに今は、どの職種も性別って関係ないものよ。やる気次第だから」
庸介は気持ちを見透かされたようで、思わず視線を逸らせた。
「別に性別で差別する気はないよ。機材って重いって聞いたことあるから、大変かなぁって」
「うんうん、それは当たってる。だから鍛えられるのよね。ほら」
理衣は腕をまくって力こぶを作ってみせた。細身なのに、なかなか立派だ。
「ゴールデンウイーク、佐賀に行くのよ。その打ち合わせでね」
「佐賀? なんでまた佐賀なわけ? 佐賀のどこに行くんだよ?」
「有田とか、唐津とか、伊万里なんかにね」
「それって焼き物だろ? 姉貴、陶芸家じゃん。なんだよ、上手くいかないから、路線変更?」
やや蔑んだ色を含んだ口調。綾はムッとしたように横を向き、理衣は苦笑した。
この姉と弟、けっして不仲というわけではないが、あまり良好とも言えないことを理衣は知っているようだった。
「閃きのためよ。いろんなタイプの芸術に触れることは良いことだから」
「閃き? 大したことないくせに、エラそうに」
「庸介!」
フン! と横を向く庸介。さらに怒ろうとした綾を、理衣が名を呼んで止めた。
「ねぇ、綾、買ってきたケーキ、食べようよ。やっと庸介君が帰って来たんだからさ」
「こいつは自分の部屋で食べるんだから、待たなくていいのに」
綾はブチブチ言いながら冷蔵庫からケーキを取り出し、コーヒーを入れた。
「これ、あんたの分」
四つあるケーキはどれも種類が異なっていた。フルーツタルト、チョコレートケーキ、チーズケーキ、苺ショート。その中で綾はチョコレートケーキを皿に盛ってそう言った。
「決まってんの?」
「じゃ、どれ選ぶ? いいよ、好きなの選びなよ」
庸介はチラリと理衣を見た。
「私、全部好きだから、残り福でいいわ。っていうか、最初からそのつもりだし」
理衣の言葉を受け、庸介はケーキを見つつ、口を尖らせながらポツリと答えた。
「……チョコケーキ」
「でしょ?」
姉にそう言われ、バツが悪そうな顔をして皿とコーヒーを手にし、ダイニングを後にした。
「綾が言った通りだったね」
「当然よ。これでも姉ですからね。庸介はチビの頃からチョコがなのよ。弟の好みなんて、知り尽くしてるわ」
そんな会話が聞こえてきた。
(うっせーんだよ)
庸介はますますバツが悪そうにチョコレートケーキを見つつ、部屋に向かった。
(ンだよ、知った顔をしやがって)
胸の内で毒づきつつも、チョコレートケーキを口に運ぶ。
(ウゼェってんだ)
庸介は綾が煙たかった。彫刻家を目指して一生懸命な姿が目障りだった。労力のすべてをつぎ込み、必死に打ち込む姿が鬱陶しかった。
子どもの頃、二人で一生懸命工作に打ち込んでいた時期があった。最初は綾に教えてもらい、いろいろ作ってみる。折紙も、プラモデルも、なにもかも、綾に教えてもらって上手にこなした。
だが、どうやっても、綾を越えることができなかった。一時はのめり込んで、プラモデルに凝った時期もあったが、そのうち飽きて嫌になった。綾が彫刻に目覚め、本格的に打ち込んでいく姿を見れば見るほど、虚しさを覚えるようになった。
そして綾が、どうしてもコンクールなどでは入選できない姿を見るのが辛かった。必死に頑張り、落選して泣いている姿は庸介の心に影を落とした。『努力しても仕方がない』『天才や秀才の前では、どんなに努力しても報われない』、そう思うようになった。
どんなに頑張っても、報われない――その思いは綾が一生懸命取り組めば取り組むほど、庸介の心に深く突き刺さるようになっていた。
(なにが彫刻家だよ。入賞もできない癖に、エラそうにさ)
綾の口から『彫刻』という言葉が出るたびに、苦い思いが込み上げる庸介だった。
それからしばらく部屋で本を読んでいたが、飽きてジュースを飲みに下へ降りて行った。ダイニングに入ると、理衣が一人で雑誌を読んでいる。
「あれ。姉貴は?」
「コンビニに行ったけど。アイス、買いに行くって」
「アイス? なんだよ、口を開けば痩せたいとか言ってるくせに。さっきケーキ食って、もうアイスか?」
理衣はそんな庸介に向けてケラケラと笑った。
「なに?」
「綾から聞いてる庸介君の話、ホントにそうだと思ってね。いいよね、兄弟って。羨ましい」
庸介は理衣の前に座り、それから「一人っ子?」と尋ねた。
「うん。母も働いているから、ずっと一人で寂しかったよ。綾、庸介君のこと、ずいぶん気にしててね」
「どんなふうに?」
「子どもの頃は懐いてくれて、すごく仲良しだったのに、中学に入ったくらいから急に避け始めて、寂しいってさ。男の子だから仕方ないよって言ってるんだけどね」
「…………」
庸介は丁度その頃、綾がコンクールで入賞できず、作った作品を叩き割って泣いていた姿にショックを受けたことを思い出した。
「どうでもいいよ、そんなこと」
「そう? そんなこと言って、綾に彼氏がいたら、それはそれで複雑なんじゃないの?」
妙に馴れ馴れしく話しかけてくる理衣に対し、庸介は綾が相当彼女に自分のことを話しているのだと察した。
「彫刻一筋の暑苦しい女じゃん。できっこねぇよ。つか、できるんなら、早く作れって感じ。それよかさ、理衣さんだっけ? 理衣さんはどうなんだよ? オトコいるの?」
「どうでしょう?」
「いないんだ。じゃぁさ、俺とつきあわない? 俺、年上でもぜんぜんオッケイだから。ねぇ、いろいろさせてよ」
軽く言いのけた庸介に対し、理衣はいきなり額をペチリと叩いた。
「って!」
「なに寝言言ってんの。寝言は寝てから言うもんよ」
「はぁ?」
「受験生、世の中を甘く見たらダメよ。ホントはもう受験勉強に必死じゃないといけないんだから」
「大丈夫だよ。無理のないガッコで、推薦取るから――って!」
理衣はもう一度、庸介の額をペチリと叩いた。
「なんか勘違いしてるみたいだけど、世の中、努力しない人間は堕ちるだけなの。しらっとしているように見えて、みんな見えないところで頑張ってるのよ。庸介君、もうちょっと真剣に考えないと、大きな失敗するよ?」
「説教くせぇなぁ。それに初対面なのに、ウザくない?」
「当然よ。三歳も年上のお姉さんだもん。それに庸介君のことは綾からずーーっと聞いているから、初対面の気がしないし」
庸介は明らかにムッとした顔を理衣に向けた。
「こんなことで怒るなんて、まだまだお子ちゃまだね。受験生なら受験生らしく、勉強しなさい。綾が言わないんなら、私が言うわ。勉強しろ、受験生!」
そこへ綾が帰ってきた。
「どうしたの?」
「ん? 別に。庸介君に、軽~く交際申し込まれて、断っただけ」
「!」
いきなり暴露され、庸介は目を剥いた。理衣は悪戯っぽく笑っている。ただでさえ子ども扱いで、説教までされてムカついているところに、この暴露。
庸介は本当に腹が立った。
「残念だけど、理衣はけっこうモテんのよ。あんたなんかお呼びじゃないから。理衣は大事な友達なの。あんたのお気軽な遊び心で傷つけたら許さないからね」
「…………」
「アイス買ってきたんだけど、いる?」
「いらねぇよ!」
庸介は吐き捨て、ダイニングを飛び出した。
「ったく。どうしてあんなに軽いんだろうねぇ。昔は違ったのに」
ため息をつく綾に向け、理衣は微笑むだけだった。
「あれ」
ダイニングに入ると、見知らぬ女が座っていた。あっさりとして小きれいな顔立ちだ。
庸介に気付き、ニコッと微笑んだ。庸介は一瞬視線を取られ、言葉を失った。今時珍しい漆黒のロングストレートの髪、額の部分で切りそろえられた前髪。独特の雰囲気があった。
「はじめまして」
「あ、はぁ。はじめまして」
つられて返事をすると、後ろから姉が現れた。
「あ、庸介、帰ったの」
「うん。友達?」
「そうよ。森下理衣さん」
「この人も彫刻してんの?」
「うぅん、理衣はカメラマン志望」
「カメラマン? 女で?」
その言葉には理衣本人が応えた。
「女性カメラマンってけっこう多いのよ。それに今は、どの職種も性別って関係ないものよ。やる気次第だから」
庸介は気持ちを見透かされたようで、思わず視線を逸らせた。
「別に性別で差別する気はないよ。機材って重いって聞いたことあるから、大変かなぁって」
「うんうん、それは当たってる。だから鍛えられるのよね。ほら」
理衣は腕をまくって力こぶを作ってみせた。細身なのに、なかなか立派だ。
「ゴールデンウイーク、佐賀に行くのよ。その打ち合わせでね」
「佐賀? なんでまた佐賀なわけ? 佐賀のどこに行くんだよ?」
「有田とか、唐津とか、伊万里なんかにね」
「それって焼き物だろ? 姉貴、陶芸家じゃん。なんだよ、上手くいかないから、路線変更?」
やや蔑んだ色を含んだ口調。綾はムッとしたように横を向き、理衣は苦笑した。
この姉と弟、けっして不仲というわけではないが、あまり良好とも言えないことを理衣は知っているようだった。
「閃きのためよ。いろんなタイプの芸術に触れることは良いことだから」
「閃き? 大したことないくせに、エラそうに」
「庸介!」
フン! と横を向く庸介。さらに怒ろうとした綾を、理衣が名を呼んで止めた。
「ねぇ、綾、買ってきたケーキ、食べようよ。やっと庸介君が帰って来たんだからさ」
「こいつは自分の部屋で食べるんだから、待たなくていいのに」
綾はブチブチ言いながら冷蔵庫からケーキを取り出し、コーヒーを入れた。
「これ、あんたの分」
四つあるケーキはどれも種類が異なっていた。フルーツタルト、チョコレートケーキ、チーズケーキ、苺ショート。その中で綾はチョコレートケーキを皿に盛ってそう言った。
「決まってんの?」
「じゃ、どれ選ぶ? いいよ、好きなの選びなよ」
庸介はチラリと理衣を見た。
「私、全部好きだから、残り福でいいわ。っていうか、最初からそのつもりだし」
理衣の言葉を受け、庸介はケーキを見つつ、口を尖らせながらポツリと答えた。
「……チョコケーキ」
「でしょ?」
姉にそう言われ、バツが悪そうな顔をして皿とコーヒーを手にし、ダイニングを後にした。
「綾が言った通りだったね」
「当然よ。これでも姉ですからね。庸介はチビの頃からチョコがなのよ。弟の好みなんて、知り尽くしてるわ」
そんな会話が聞こえてきた。
(うっせーんだよ)
庸介はますますバツが悪そうにチョコレートケーキを見つつ、部屋に向かった。
(ンだよ、知った顔をしやがって)
胸の内で毒づきつつも、チョコレートケーキを口に運ぶ。
(ウゼェってんだ)
庸介は綾が煙たかった。彫刻家を目指して一生懸命な姿が目障りだった。労力のすべてをつぎ込み、必死に打ち込む姿が鬱陶しかった。
子どもの頃、二人で一生懸命工作に打ち込んでいた時期があった。最初は綾に教えてもらい、いろいろ作ってみる。折紙も、プラモデルも、なにもかも、綾に教えてもらって上手にこなした。
だが、どうやっても、綾を越えることができなかった。一時はのめり込んで、プラモデルに凝った時期もあったが、そのうち飽きて嫌になった。綾が彫刻に目覚め、本格的に打ち込んでいく姿を見れば見るほど、虚しさを覚えるようになった。
そして綾が、どうしてもコンクールなどでは入選できない姿を見るのが辛かった。必死に頑張り、落選して泣いている姿は庸介の心に影を落とした。『努力しても仕方がない』『天才や秀才の前では、どんなに努力しても報われない』、そう思うようになった。
どんなに頑張っても、報われない――その思いは綾が一生懸命取り組めば取り組むほど、庸介の心に深く突き刺さるようになっていた。
(なにが彫刻家だよ。入賞もできない癖に、エラそうにさ)
綾の口から『彫刻』という言葉が出るたびに、苦い思いが込み上げる庸介だった。
それからしばらく部屋で本を読んでいたが、飽きてジュースを飲みに下へ降りて行った。ダイニングに入ると、理衣が一人で雑誌を読んでいる。
「あれ。姉貴は?」
「コンビニに行ったけど。アイス、買いに行くって」
「アイス? なんだよ、口を開けば痩せたいとか言ってるくせに。さっきケーキ食って、もうアイスか?」
理衣はそんな庸介に向けてケラケラと笑った。
「なに?」
「綾から聞いてる庸介君の話、ホントにそうだと思ってね。いいよね、兄弟って。羨ましい」
庸介は理衣の前に座り、それから「一人っ子?」と尋ねた。
「うん。母も働いているから、ずっと一人で寂しかったよ。綾、庸介君のこと、ずいぶん気にしててね」
「どんなふうに?」
「子どもの頃は懐いてくれて、すごく仲良しだったのに、中学に入ったくらいから急に避け始めて、寂しいってさ。男の子だから仕方ないよって言ってるんだけどね」
「…………」
庸介は丁度その頃、綾がコンクールで入賞できず、作った作品を叩き割って泣いていた姿にショックを受けたことを思い出した。
「どうでもいいよ、そんなこと」
「そう? そんなこと言って、綾に彼氏がいたら、それはそれで複雑なんじゃないの?」
妙に馴れ馴れしく話しかけてくる理衣に対し、庸介は綾が相当彼女に自分のことを話しているのだと察した。
「彫刻一筋の暑苦しい女じゃん。できっこねぇよ。つか、できるんなら、早く作れって感じ。それよかさ、理衣さんだっけ? 理衣さんはどうなんだよ? オトコいるの?」
「どうでしょう?」
「いないんだ。じゃぁさ、俺とつきあわない? 俺、年上でもぜんぜんオッケイだから。ねぇ、いろいろさせてよ」
軽く言いのけた庸介に対し、理衣はいきなり額をペチリと叩いた。
「って!」
「なに寝言言ってんの。寝言は寝てから言うもんよ」
「はぁ?」
「受験生、世の中を甘く見たらダメよ。ホントはもう受験勉強に必死じゃないといけないんだから」
「大丈夫だよ。無理のないガッコで、推薦取るから――って!」
理衣はもう一度、庸介の額をペチリと叩いた。
「なんか勘違いしてるみたいだけど、世の中、努力しない人間は堕ちるだけなの。しらっとしているように見えて、みんな見えないところで頑張ってるのよ。庸介君、もうちょっと真剣に考えないと、大きな失敗するよ?」
「説教くせぇなぁ。それに初対面なのに、ウザくない?」
「当然よ。三歳も年上のお姉さんだもん。それに庸介君のことは綾からずーーっと聞いているから、初対面の気がしないし」
庸介は明らかにムッとした顔を理衣に向けた。
「こんなことで怒るなんて、まだまだお子ちゃまだね。受験生なら受験生らしく、勉強しなさい。綾が言わないんなら、私が言うわ。勉強しろ、受験生!」
そこへ綾が帰ってきた。
「どうしたの?」
「ん? 別に。庸介君に、軽~く交際申し込まれて、断っただけ」
「!」
いきなり暴露され、庸介は目を剥いた。理衣は悪戯っぽく笑っている。ただでさえ子ども扱いで、説教までされてムカついているところに、この暴露。
庸介は本当に腹が立った。
「残念だけど、理衣はけっこうモテんのよ。あんたなんかお呼びじゃないから。理衣は大事な友達なの。あんたのお気軽な遊び心で傷つけたら許さないからね」
「…………」
「アイス買ってきたんだけど、いる?」
「いらねぇよ!」
庸介は吐き捨て、ダイニングを飛び出した。
「ったく。どうしてあんなに軽いんだろうねぇ。昔は違ったのに」
ため息をつく綾に向け、理衣は微笑むだけだった。