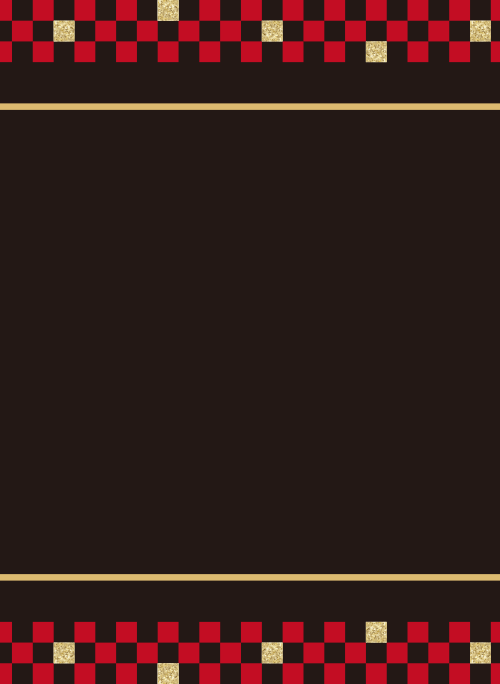学校からの帰り道、庸介は秀二と肩を並べて歩いていた。
家は近すぎる距離でもなければ、遠すぎる距離でもない。
子供の頃は目と鼻の先だったが、小学校を出る頃に庸介の家が引っ越しをした。少々離れたものの、駅は同じだ。
幼なじみで仲が良かったこともあり、今でもツルんでいる。
高校は都内でも有名な進学校だった。
希望したわけではなかったが、秀二が受験すると聞き、「知っているヤツがいたほうが楽しいかな」などと考え、自分も希望することにしたのだ。
真面目に勉強をしていなかった庸介の成績では、秀二と同じ高校は難しいと言われたものの、妙に悔しさを感じて猛勉強に至った。
その結果、無事に合格することができた。
「珍しく必死でやった」
本人自ら白状するほど、その時ばかりは集中して勉強した。だが入ってからは、いつもの『そこそこに』であるが。
上手くどこかの大学の推薦を取って、楽に受験を乗り切ろうと考えている。
世間で名の通っている一流大学に行こうとは考えてはいなかった。
さすがにそこまで秀二を追いかける気もない。というのも、秀二の目標は東大一本で、庸介には興味の欠片もなかったし、そんな難しい大学に入りたいとも思わない。入ってから苦労したくないからだ。もっとも、逆立ちしたって入れないだろうが。
とにかく楽をして、おいしく過ごす、それが庸介のポリシーだ。
「推薦推薦って言うけど、そんなに簡単にはもらえないよ?」
並んで歩く隣の秀二が口にした。
「庸介は甘いんだよ」
「そっかなぁ。お前が目指しているような、ご立派な大学じゃないんだから、どっか、あるんじゃない?」
「そこそこの?」
「あぁ、そこそこの」
秀二は深くため息をついた。
「相変わらず、テキトーなヤツ。ウチの高校に入ったんだから、庸介だって真面目にやれば、良い大学狙えるよ。今年一年ぐらいさ、そのいい加減な考え方捨てて、もう一回必死になったらどうなんだ? 一度はできたんだから、やれるだろ?」
「ヤだよ。立派な大学行ったって、今の世の中じゃどう報われるわけ? 頑張ったって報われやしないんだ。俺は大事な時間を無駄にしたくない。勉強はするよ。でも、全力ではしない。好きなことと、やらないといけないこと、半々ぐらいで楽しく過ごしたいんだ」
黙り込む秀二の顔をチラリと見、それから続けた。
「姉貴見てたら、そう思うだろ? お前の兄貴見てても思うし」
その瞬間、秀二の顔が苦痛に歪んだ。
「兄貴の話はすんなよっ」
「事実だろ。なにもかもほっぽって、必死に頑張ってるってのに、絶対コンクールで入賞できない姉貴。大して頑張ってもいないのに、ひょいひょいっと東大入っちまったお前の兄貴。世の中ってそんなもんだよ。凡人がなにやっても、才能のあるヤツには勝てないんだ。俺は凡人として凡々と生きるんだ。いかに楽をして、いかに楽しく暮らすのか、それに尽きる。必死に頑張る? バカみたいだ」
秀二は俯いたまま無言で聞いている。
「毎日毎日、カレシも作らず、木を削ってなにが楽しいのかと思うけど、青春全部投げ打って取りかかっているってのに、入賞したことがない。今一歩ってとこでコケて、泣いてさ。バッカバカしいよ。そう思わないか?」
秀二はチラリと庸介の顔を見、それからまた俯いた。
「それに比べて、お前の兄貴。参考書だけで一流大学受かっちまってさ。それだけじゃ足りなくて、その大学蹴って、一年予備校行って、東大入っちまうんだもん。デキるヤツは大した努力もせずにコナしちまうもんだ」
「だから、兄貴の話は、すんな」
今度は消えそうな声で言った。庸介は秀二を見もせず、好き勝手に言っている。
「姉貴を見てたらイライラする。お前の兄貴の方が遥かにクールだ。凡人が必死になってる姿って、見苦しいよ。暑苦しいってんだ」
「――でも、綾さんが作品と向き合ってる姿は、きれいだと思う」
「え?」
「真剣で、輝いていると思う」
庸介は目を丸くした。
「秀二」
「勘違いすんなよ。そっちの気があるわけじゃないから。でも、小さい頃から、工作に打ち込んでる姿はカッコイイって思ってたし、完成した時のうれしそうな顔は輝いてきれいだよ」
「マジ?」
「…………」
「やめとけよ、ヘンな女だから」
「だから、違うって言ってるだろ? お前が兄貴を褒めるから、そうじゃないって言いたかっただけだ。兄貴なんかより、綾さんのほうが、クールだって言いたかっただけなんだ」
再び俯いた秀二を、庸介は少しばかり真面目な顔で見、それから口を開いた。
「秀二、お前さ、兄貴に対してつまんねぇ対抗心なんか捨てて、もっと楽にしたらどうだよ」
「対抗心じゃないよ!」
キッと睨んで秀二が怒鳴った。が、庸介は気にした様子もない。
「実際、そうじゃん。お前の目指しているガッコ、なんで希望しているか、言ってみろよ。校風? 就職目的? 日本一だから? それともやりたいことがある? どれも違うじゃん。兄貴より下のガッコに行きたくないだけじゃないか。その学校がどうのってんじゃなく、ただ兄貴に負けたくないだけ。力いっぱい対抗心じゃん」
秀二が泣きそうな目を庸介に向けている。
「もっとさぁ、なんて言うか、気楽に考えられない? 兄貴とは違う人間なんだから、兄貴は兄貴、俺は俺って、割り切っちまえばいいんだよ。一生、兄貴越えのために労力使うの? そんなの、ヘンだよ」
「…………」
「同じことやってるから親の意識ってば兄貴に向くんだよ。違うことして結果出したら、イヤでもお前に意識がいくよ。他のことやれよ」
「うるさい! お前にはわからないよ!」
秀二はそう怒鳴ると、庸介を無視して駆けだしていた。そんな彼の背を眺めて見送る。
「だって、事実だろ」
ポツリと呟いた。しばらく秀二が走り去った方角を見ていたが、バツが悪そうに視線を落とした。
「……ちょい、言い過ぎたかな」
家は近すぎる距離でもなければ、遠すぎる距離でもない。
子供の頃は目と鼻の先だったが、小学校を出る頃に庸介の家が引っ越しをした。少々離れたものの、駅は同じだ。
幼なじみで仲が良かったこともあり、今でもツルんでいる。
高校は都内でも有名な進学校だった。
希望したわけではなかったが、秀二が受験すると聞き、「知っているヤツがいたほうが楽しいかな」などと考え、自分も希望することにしたのだ。
真面目に勉強をしていなかった庸介の成績では、秀二と同じ高校は難しいと言われたものの、妙に悔しさを感じて猛勉強に至った。
その結果、無事に合格することができた。
「珍しく必死でやった」
本人自ら白状するほど、その時ばかりは集中して勉強した。だが入ってからは、いつもの『そこそこに』であるが。
上手くどこかの大学の推薦を取って、楽に受験を乗り切ろうと考えている。
世間で名の通っている一流大学に行こうとは考えてはいなかった。
さすがにそこまで秀二を追いかける気もない。というのも、秀二の目標は東大一本で、庸介には興味の欠片もなかったし、そんな難しい大学に入りたいとも思わない。入ってから苦労したくないからだ。もっとも、逆立ちしたって入れないだろうが。
とにかく楽をして、おいしく過ごす、それが庸介のポリシーだ。
「推薦推薦って言うけど、そんなに簡単にはもらえないよ?」
並んで歩く隣の秀二が口にした。
「庸介は甘いんだよ」
「そっかなぁ。お前が目指しているような、ご立派な大学じゃないんだから、どっか、あるんじゃない?」
「そこそこの?」
「あぁ、そこそこの」
秀二は深くため息をついた。
「相変わらず、テキトーなヤツ。ウチの高校に入ったんだから、庸介だって真面目にやれば、良い大学狙えるよ。今年一年ぐらいさ、そのいい加減な考え方捨てて、もう一回必死になったらどうなんだ? 一度はできたんだから、やれるだろ?」
「ヤだよ。立派な大学行ったって、今の世の中じゃどう報われるわけ? 頑張ったって報われやしないんだ。俺は大事な時間を無駄にしたくない。勉強はするよ。でも、全力ではしない。好きなことと、やらないといけないこと、半々ぐらいで楽しく過ごしたいんだ」
黙り込む秀二の顔をチラリと見、それから続けた。
「姉貴見てたら、そう思うだろ? お前の兄貴見てても思うし」
その瞬間、秀二の顔が苦痛に歪んだ。
「兄貴の話はすんなよっ」
「事実だろ。なにもかもほっぽって、必死に頑張ってるってのに、絶対コンクールで入賞できない姉貴。大して頑張ってもいないのに、ひょいひょいっと東大入っちまったお前の兄貴。世の中ってそんなもんだよ。凡人がなにやっても、才能のあるヤツには勝てないんだ。俺は凡人として凡々と生きるんだ。いかに楽をして、いかに楽しく暮らすのか、それに尽きる。必死に頑張る? バカみたいだ」
秀二は俯いたまま無言で聞いている。
「毎日毎日、カレシも作らず、木を削ってなにが楽しいのかと思うけど、青春全部投げ打って取りかかっているってのに、入賞したことがない。今一歩ってとこでコケて、泣いてさ。バッカバカしいよ。そう思わないか?」
秀二はチラリと庸介の顔を見、それからまた俯いた。
「それに比べて、お前の兄貴。参考書だけで一流大学受かっちまってさ。それだけじゃ足りなくて、その大学蹴って、一年予備校行って、東大入っちまうんだもん。デキるヤツは大した努力もせずにコナしちまうもんだ」
「だから、兄貴の話は、すんな」
今度は消えそうな声で言った。庸介は秀二を見もせず、好き勝手に言っている。
「姉貴を見てたらイライラする。お前の兄貴の方が遥かにクールだ。凡人が必死になってる姿って、見苦しいよ。暑苦しいってんだ」
「――でも、綾さんが作品と向き合ってる姿は、きれいだと思う」
「え?」
「真剣で、輝いていると思う」
庸介は目を丸くした。
「秀二」
「勘違いすんなよ。そっちの気があるわけじゃないから。でも、小さい頃から、工作に打ち込んでる姿はカッコイイって思ってたし、完成した時のうれしそうな顔は輝いてきれいだよ」
「マジ?」
「…………」
「やめとけよ、ヘンな女だから」
「だから、違うって言ってるだろ? お前が兄貴を褒めるから、そうじゃないって言いたかっただけだ。兄貴なんかより、綾さんのほうが、クールだって言いたかっただけなんだ」
再び俯いた秀二を、庸介は少しばかり真面目な顔で見、それから口を開いた。
「秀二、お前さ、兄貴に対してつまんねぇ対抗心なんか捨てて、もっと楽にしたらどうだよ」
「対抗心じゃないよ!」
キッと睨んで秀二が怒鳴った。が、庸介は気にした様子もない。
「実際、そうじゃん。お前の目指しているガッコ、なんで希望しているか、言ってみろよ。校風? 就職目的? 日本一だから? それともやりたいことがある? どれも違うじゃん。兄貴より下のガッコに行きたくないだけじゃないか。その学校がどうのってんじゃなく、ただ兄貴に負けたくないだけ。力いっぱい対抗心じゃん」
秀二が泣きそうな目を庸介に向けている。
「もっとさぁ、なんて言うか、気楽に考えられない? 兄貴とは違う人間なんだから、兄貴は兄貴、俺は俺って、割り切っちまえばいいんだよ。一生、兄貴越えのために労力使うの? そんなの、ヘンだよ」
「…………」
「同じことやってるから親の意識ってば兄貴に向くんだよ。違うことして結果出したら、イヤでもお前に意識がいくよ。他のことやれよ」
「うるさい! お前にはわからないよ!」
秀二はそう怒鳴ると、庸介を無視して駆けだしていた。そんな彼の背を眺めて見送る。
「だって、事実だろ」
ポツリと呟いた。しばらく秀二が走り去った方角を見ていたが、バツが悪そうに視線を落とした。
「……ちょい、言い過ぎたかな」