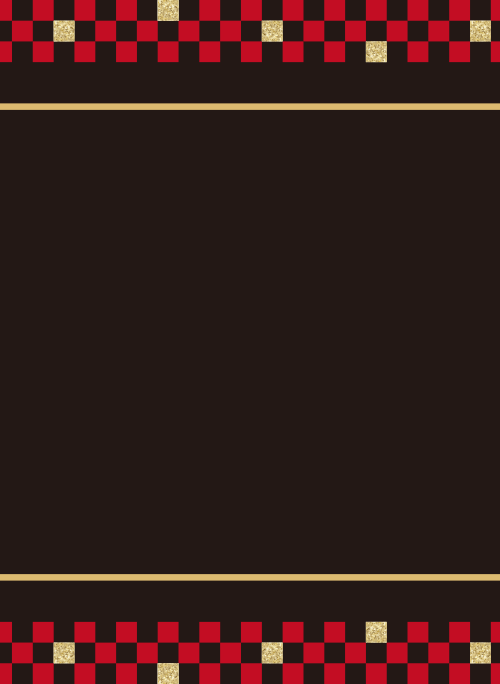数か月後。
文字通り寝る間も惜しんで勉強した庸介は、日本で一番難しいと言われる東京大学の合格発表の場に、一人立っていた。
すでに別の学校で合格を得ていた彼だったが、秀二を思いつつ、最後の難関の結果に向かっていた。
立て掛けられた合格発表のボードを食い入るように見つめる。一年ほどの勉強期間では、とても受かるとは思えなかった。だから結果についてはダメでも落ち込まないつもりでいた。
それでも死に物狂いで勉強した毎日だ。落ちたくはない。合格したいと切実に願った。
やがて庸介は、震える手でスマートフォンの番号をタップした。
『もしもし、庸介君!』
「あ、理衣? あの、俺、う、う、受かった」
『え! ええーー! ホント? やったー! おめでとう! すごいよっ、すごいっ!』
理衣の甲高い声が耳に響いた。
『庸介君!』
「うん。うん……うん」
スマートフォンを耳に当てて、何度も頷く。
驚きと感激。
感極まって息が喉に詰まり、うまく言葉が出てこなかった。
「庸介君!」
スマートフォンから理衣の声が聞こえたが、後方からも聞こえた。驚いて振り返ると、理衣が立っていた。
「理衣」
「実は我慢できなくて、学校の外で待ってたの」
見つめる庸介の視線を照れ臭そうに受け止める。
理衣は毎晩、必ず決まった時間に『負けるな!』という短いメールを送っていた。
長々書いて時間を裂かせてはいけない、けれども励ましたい。
理衣らしいと庸介は思った。
その気持ちはなににも増して励みとなった。
たった一言、『負けるな!』
この一言に理衣のすべての気持ちが詰まっている――そう思うと、胸が熱くなり、意地でもやり通すという気にさせた。
ずっと励まし続けてくれた理衣が、目にいっぱいの涙を貯めて、自分を見つめている。
「落ち着かなくて、でも、庸介君の、『一人で確認したい』って気持ちもわかるし。朝一番、湯島で手を合わせて、で、そこでずっと待ってたの」
その瞬間、庸介は理衣を抱きしめていた。庸介の腕の中で理衣もうれしそうに涙ぐみ、そして背に腕を回して抱きしめ返した。
「おめでとう。頑張ったもんね」
「…………」
「すごく頑張って、カッコ良かったよ! 庸介君、私のほうがうれしい。おめでとう!」
「うん、うん、うん……」
涙声の庸介を抱きしめながら、理衣もやがて言葉を失った。ただうれしくて抱きしめるばかりだった。
そんな二人を、スマートフォンのメロディが包んだ。庸介が取ると、綾からの電話だった。
「え? 何だって!? もう一回!」
『秀二君の容態に変化があったのよっ。早く病院に来て!』
「え? 秀二? 秀二がどうしたんだ!」
『さっき、おばさんがお母さんに電話してきて、庸介君に伝えてくださいって。瞼が少し動き出したんだって!』
「ほっ、ほんとに?」
『もしかしたら、目を覚ますかもしれないって! 庸介、早く!』
「わかった、すぐ行く!」
「どうしたの? 秀二君になにかあったの?」
理衣に顔を向け、頷く。
「もしかしたら、目を覚ますかもって」
「えぇ!」
「奇蹟が起こるかもしれない! 行こう!」
「うん!」
庸介と理衣は手を繋いで駆け出していた。
病室には秀二の家族と、綾と母親まで集まっていた。そこに庸介と理衣が飛び込んだ。
「秀二! 秀二は?」
一斉に注目される。が、すぐに視線はベッドに落ちた。
「秀二!」
焦点の合わないような目をした秀二が、茫然と天井を見つめていた。
「秀二!」
声をかけても、反応はない。だが、目を開けていることは確かだ。そんな秀二に庸介は怒鳴るように話しかけた。
「秀二、秀二! 聞いてくれ! 俺、東大に受かったぞ!」
庸介の言葉に皆が息をのんだ。秀二の目が少し動いたからだ。
庸介はかまわず怒鳴った。
「お前が目指した東大を受けたんだ。俺さ、死に物狂いで勉強したんだ。寝る間も惜しんで、ずっと、ずっと、ずっと! お前の分までもと思って! 秀二、聞いてるか? 今日は合格発表の日だ。お前は東大の合格発表の日がいつか知ってるだろ? 目指してるんだから。俺、受かったんだっ。受かったんだよ! なぁ、秀二、お前なら、俺なんかより遥かに楽に合格するはずだ。だから先に行って待ってる! 秀二、来年はお前だっ。聞いてるか!?」
秀二の目がゆっくりと動き、庸介を捉えた。なにか言いたげなまなざしだ。
「東大だ! 秀二、東大だよ。早く治して、来年、受けるんだ。俺でもできたんだから、お前だったら楽勝だ! 一緒に行こう、秀二。待ってるから! いつまでも、待ってるから!」
秀二は微かに、本当に微かに、笑った。
口元が少し弛んだような感じだったが、それでも皆、笑ったと思った。
表情があるだけで、皆を驚かせ、そして喜ばせた。
「秀二!」
秀二はそのまま目を閉じた。リズムカルな寝息が聞こえてくる。気持ちよさそうな寝顔だった。
庸介はその寝顔に、自分たちの未来があるような気がした。
終
文字通り寝る間も惜しんで勉強した庸介は、日本で一番難しいと言われる東京大学の合格発表の場に、一人立っていた。
すでに別の学校で合格を得ていた彼だったが、秀二を思いつつ、最後の難関の結果に向かっていた。
立て掛けられた合格発表のボードを食い入るように見つめる。一年ほどの勉強期間では、とても受かるとは思えなかった。だから結果についてはダメでも落ち込まないつもりでいた。
それでも死に物狂いで勉強した毎日だ。落ちたくはない。合格したいと切実に願った。
やがて庸介は、震える手でスマートフォンの番号をタップした。
『もしもし、庸介君!』
「あ、理衣? あの、俺、う、う、受かった」
『え! ええーー! ホント? やったー! おめでとう! すごいよっ、すごいっ!』
理衣の甲高い声が耳に響いた。
『庸介君!』
「うん。うん……うん」
スマートフォンを耳に当てて、何度も頷く。
驚きと感激。
感極まって息が喉に詰まり、うまく言葉が出てこなかった。
「庸介君!」
スマートフォンから理衣の声が聞こえたが、後方からも聞こえた。驚いて振り返ると、理衣が立っていた。
「理衣」
「実は我慢できなくて、学校の外で待ってたの」
見つめる庸介の視線を照れ臭そうに受け止める。
理衣は毎晩、必ず決まった時間に『負けるな!』という短いメールを送っていた。
長々書いて時間を裂かせてはいけない、けれども励ましたい。
理衣らしいと庸介は思った。
その気持ちはなににも増して励みとなった。
たった一言、『負けるな!』
この一言に理衣のすべての気持ちが詰まっている――そう思うと、胸が熱くなり、意地でもやり通すという気にさせた。
ずっと励まし続けてくれた理衣が、目にいっぱいの涙を貯めて、自分を見つめている。
「落ち着かなくて、でも、庸介君の、『一人で確認したい』って気持ちもわかるし。朝一番、湯島で手を合わせて、で、そこでずっと待ってたの」
その瞬間、庸介は理衣を抱きしめていた。庸介の腕の中で理衣もうれしそうに涙ぐみ、そして背に腕を回して抱きしめ返した。
「おめでとう。頑張ったもんね」
「…………」
「すごく頑張って、カッコ良かったよ! 庸介君、私のほうがうれしい。おめでとう!」
「うん、うん、うん……」
涙声の庸介を抱きしめながら、理衣もやがて言葉を失った。ただうれしくて抱きしめるばかりだった。
そんな二人を、スマートフォンのメロディが包んだ。庸介が取ると、綾からの電話だった。
「え? 何だって!? もう一回!」
『秀二君の容態に変化があったのよっ。早く病院に来て!』
「え? 秀二? 秀二がどうしたんだ!」
『さっき、おばさんがお母さんに電話してきて、庸介君に伝えてくださいって。瞼が少し動き出したんだって!』
「ほっ、ほんとに?」
『もしかしたら、目を覚ますかもしれないって! 庸介、早く!』
「わかった、すぐ行く!」
「どうしたの? 秀二君になにかあったの?」
理衣に顔を向け、頷く。
「もしかしたら、目を覚ますかもって」
「えぇ!」
「奇蹟が起こるかもしれない! 行こう!」
「うん!」
庸介と理衣は手を繋いで駆け出していた。
病室には秀二の家族と、綾と母親まで集まっていた。そこに庸介と理衣が飛び込んだ。
「秀二! 秀二は?」
一斉に注目される。が、すぐに視線はベッドに落ちた。
「秀二!」
焦点の合わないような目をした秀二が、茫然と天井を見つめていた。
「秀二!」
声をかけても、反応はない。だが、目を開けていることは確かだ。そんな秀二に庸介は怒鳴るように話しかけた。
「秀二、秀二! 聞いてくれ! 俺、東大に受かったぞ!」
庸介の言葉に皆が息をのんだ。秀二の目が少し動いたからだ。
庸介はかまわず怒鳴った。
「お前が目指した東大を受けたんだ。俺さ、死に物狂いで勉強したんだ。寝る間も惜しんで、ずっと、ずっと、ずっと! お前の分までもと思って! 秀二、聞いてるか? 今日は合格発表の日だ。お前は東大の合格発表の日がいつか知ってるだろ? 目指してるんだから。俺、受かったんだっ。受かったんだよ! なぁ、秀二、お前なら、俺なんかより遥かに楽に合格するはずだ。だから先に行って待ってる! 秀二、来年はお前だっ。聞いてるか!?」
秀二の目がゆっくりと動き、庸介を捉えた。なにか言いたげなまなざしだ。
「東大だ! 秀二、東大だよ。早く治して、来年、受けるんだ。俺でもできたんだから、お前だったら楽勝だ! 一緒に行こう、秀二。待ってるから! いつまでも、待ってるから!」
秀二は微かに、本当に微かに、笑った。
口元が少し弛んだような感じだったが、それでも皆、笑ったと思った。
表情があるだけで、皆を驚かせ、そして喜ばせた。
「秀二!」
秀二はそのまま目を閉じた。リズムカルな寝息が聞こえてくる。気持ちよさそうな寝顔だった。
庸介はその寝顔に、自分たちの未来があるような気がした。
終