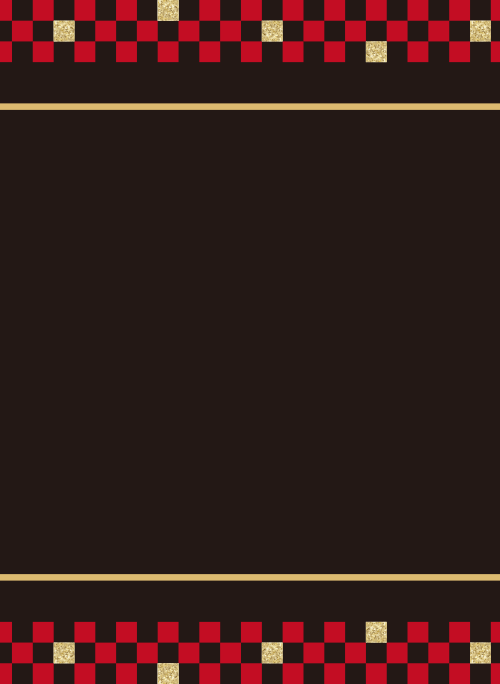秀二がいない教室、学校。
庸介には別の場所のような気を起こさせた。
自殺未遂の出来事は学校を震撼させ、生徒、クラスメートたちを激しく動揺させた。
一命を取り留めたという知らせに安堵したものの、それでも事件のショックは大きかった。
とはいえ、時間が過ぎれば少しずつ日常を取り戻し、秀二がいないことに違和感を与えなくなりつつあった。
だが、庸介は違う。秀二のいない教室は色褪せて見えた。
当たり前のように傍にいた友達がいない現実。当たり前だと思っていた日々が壊れた現実。それは庸介の心を深く傷つけた。
自分にできること、自分にしかできないこと――それがなにか考えつつも、どうしようもない虚空感を覚えて仕方がなかった。
(俺には、なにができるんだろう)
庸介はそんなことばかりを考えていた。この日も家の近くの公園で、茫然としつつ空を眺めていた。
「ヨースケ」
杏子だ。学校の違う杏子は秀二のことを知らない。
「あのお姉さんは一緒じゃないの?」
「うっせぇなぁ」
うふふと色っぽく微笑み、庸介の隣に座った。
「ねぇ、あの時の続き、しない? 今度は最後までヤろうよ」
「悪いけど、今はそんな気分じゃない」
「どうして?」
「杏子、お前さ、好きでもないオトコとヤりまくって、それで幸せなわけ?」
突然の真面目な質問に、杏子は驚きつつも顔を強張らせた。
「妊娠したらどうしようとか、ホントに惚れた時にそのオトコに遍歴バレたらどうしようとか、思わない?」
「どうしたの? ヨースケ、そういう固い話は嫌いじゃなかった?」
「あぁ。そうだよ。でもさ、こういうの、オンナのほうがリスク高いだろ。それでもエッチしたいわけ?」
杏子の顔に明らかな怒りが浮かんでいた。
「勘違いすんなよ。別にバカにしてるわけじゃないんだ。俺も楽に生きたいって思ってたから。でもさ、そうじゃないヤツらも多いだろ? お前はどうなんだろうと思って。将来とか、考えてる?」
「別に、そんなの関係ないし」
「…………」
「先のことなんかわかんないじゃん。今、楽しいことが大事だもん。エッチは気持ちいいし」
「……そうだな」
「あっちの相性って大きいんだもん。離れられなくなるっての? それはそれでちゃんと結びついてると思うんだけどなぁ」
杏子との会話に虚しさを覚えるばかりだ。庸介は立ち上がった。
「ヨースケ?」
「俺、帰るわ。やっぱ、お前の相手はできそうもない。悪いけど、他当たってくれよ」
「えぇ!」
「最近、真面目にやろうかと考えてるんだ。だから、ごめん」
杏子がなにか怒鳴っているが、庸介は気にならなかった。
(秀二があんなことにならなかったら、『あ、そういうのもアリかな』って言えただろうけど、今は虚しいだけだ。俺は……バカだった)
家に帰ると、庭でいつものように綾が木を彫っている。目が鋭い。こういう顔の綾は話しかけようがなにをしようが、こちらに気付くことはなかった。
(相変わらずだな、姉貴は)
そう思い、家に入ろうとしてもう一度見た。その顔は子どもの頃、必死にプラモデルを作っていた姉の顔だった。
秀二が『輝いている』と言った言葉と、姉の必死の顔が重なった。
(俺は、勝手に姉貴が苦しみながら打ち込んでいると思っていたのかな)
なにかが込み上げてくるのを感じた。
幼い頃からずっと見ていた姉の顔は、なにかを教えてくれているような気がした。
(輝いている――それは楽しいってことだけじゃないかもしれない。好きなことだけやっていれば、楽しくて、輝いていられると思っていたけど、楽しいだけじゃ、人は輝けないのかもしれない)
玄関を開け、家の中に入る。
(自分が楽をしたいばっかりに、その人の本当の気持ちとか考えず、都合のいいように、勝手に脚色して解釈していたのかもしれない。自分が傷つかないように。自分が惨めじゃないように……)
部屋に入って机に鞄を置き、中から教科書を取り出す。
(俺が秀二にできること。いや、反対だ。まずは秀二に信用してもらうことから始めないと。あいつは誰よりも俺を知っている。俺がいい加減なことを、誰よりも。じゃあ、どうすれば知られきってるあいつを信用させられる?)
視線は教科書の表紙に落ちている。
――庸介は甘いんだよ。
(そうだ。俺は、甘いんだ。今頃、痛感してる。こんな俺に相談したってマトモなアドバイスなんかされっこないって、秀二でなくても思うよな)
――相変わらず、テキトーなヤツ。ウチの高校に入ったんだから、庸介だって真面目にやれば、いい大学狙えるよ。今年一年ぐらいさ、そのいい加減な考え方捨てて、必死になったらどうなんだ?
(ホントかよ、秀二。こんな俺でも、必死になったら、お前が目指した所を狙えるのか?)
――そのいい加減な考え方捨てて、必死になったらどうなんだ?
(必死に……俺が一番嫌いだと言い続けた言葉だ。俺が必死になったら、お前は俺を認めてくれる? 秀二、認めてくれるのか?)
ギュッと握りしめた拳。その拳の上に、一粒、雫が落ちた。
(秀二、どうしたら、お前は目を開けてくれるんだよ。ずっと一緒だったのに。どうしたらお前を助けられるんだ。どうしたら、悩みが相談できるような存在になれるんだよ、秀二! 眠ってないで、教えてくれよ)
庸介には別の場所のような気を起こさせた。
自殺未遂の出来事は学校を震撼させ、生徒、クラスメートたちを激しく動揺させた。
一命を取り留めたという知らせに安堵したものの、それでも事件のショックは大きかった。
とはいえ、時間が過ぎれば少しずつ日常を取り戻し、秀二がいないことに違和感を与えなくなりつつあった。
だが、庸介は違う。秀二のいない教室は色褪せて見えた。
当たり前のように傍にいた友達がいない現実。当たり前だと思っていた日々が壊れた現実。それは庸介の心を深く傷つけた。
自分にできること、自分にしかできないこと――それがなにか考えつつも、どうしようもない虚空感を覚えて仕方がなかった。
(俺には、なにができるんだろう)
庸介はそんなことばかりを考えていた。この日も家の近くの公園で、茫然としつつ空を眺めていた。
「ヨースケ」
杏子だ。学校の違う杏子は秀二のことを知らない。
「あのお姉さんは一緒じゃないの?」
「うっせぇなぁ」
うふふと色っぽく微笑み、庸介の隣に座った。
「ねぇ、あの時の続き、しない? 今度は最後までヤろうよ」
「悪いけど、今はそんな気分じゃない」
「どうして?」
「杏子、お前さ、好きでもないオトコとヤりまくって、それで幸せなわけ?」
突然の真面目な質問に、杏子は驚きつつも顔を強張らせた。
「妊娠したらどうしようとか、ホントに惚れた時にそのオトコに遍歴バレたらどうしようとか、思わない?」
「どうしたの? ヨースケ、そういう固い話は嫌いじゃなかった?」
「あぁ。そうだよ。でもさ、こういうの、オンナのほうがリスク高いだろ。それでもエッチしたいわけ?」
杏子の顔に明らかな怒りが浮かんでいた。
「勘違いすんなよ。別にバカにしてるわけじゃないんだ。俺も楽に生きたいって思ってたから。でもさ、そうじゃないヤツらも多いだろ? お前はどうなんだろうと思って。将来とか、考えてる?」
「別に、そんなの関係ないし」
「…………」
「先のことなんかわかんないじゃん。今、楽しいことが大事だもん。エッチは気持ちいいし」
「……そうだな」
「あっちの相性って大きいんだもん。離れられなくなるっての? それはそれでちゃんと結びついてると思うんだけどなぁ」
杏子との会話に虚しさを覚えるばかりだ。庸介は立ち上がった。
「ヨースケ?」
「俺、帰るわ。やっぱ、お前の相手はできそうもない。悪いけど、他当たってくれよ」
「えぇ!」
「最近、真面目にやろうかと考えてるんだ。だから、ごめん」
杏子がなにか怒鳴っているが、庸介は気にならなかった。
(秀二があんなことにならなかったら、『あ、そういうのもアリかな』って言えただろうけど、今は虚しいだけだ。俺は……バカだった)
家に帰ると、庭でいつものように綾が木を彫っている。目が鋭い。こういう顔の綾は話しかけようがなにをしようが、こちらに気付くことはなかった。
(相変わらずだな、姉貴は)
そう思い、家に入ろうとしてもう一度見た。その顔は子どもの頃、必死にプラモデルを作っていた姉の顔だった。
秀二が『輝いている』と言った言葉と、姉の必死の顔が重なった。
(俺は、勝手に姉貴が苦しみながら打ち込んでいると思っていたのかな)
なにかが込み上げてくるのを感じた。
幼い頃からずっと見ていた姉の顔は、なにかを教えてくれているような気がした。
(輝いている――それは楽しいってことだけじゃないかもしれない。好きなことだけやっていれば、楽しくて、輝いていられると思っていたけど、楽しいだけじゃ、人は輝けないのかもしれない)
玄関を開け、家の中に入る。
(自分が楽をしたいばっかりに、その人の本当の気持ちとか考えず、都合のいいように、勝手に脚色して解釈していたのかもしれない。自分が傷つかないように。自分が惨めじゃないように……)
部屋に入って机に鞄を置き、中から教科書を取り出す。
(俺が秀二にできること。いや、反対だ。まずは秀二に信用してもらうことから始めないと。あいつは誰よりも俺を知っている。俺がいい加減なことを、誰よりも。じゃあ、どうすれば知られきってるあいつを信用させられる?)
視線は教科書の表紙に落ちている。
――庸介は甘いんだよ。
(そうだ。俺は、甘いんだ。今頃、痛感してる。こんな俺に相談したってマトモなアドバイスなんかされっこないって、秀二でなくても思うよな)
――相変わらず、テキトーなヤツ。ウチの高校に入ったんだから、庸介だって真面目にやれば、いい大学狙えるよ。今年一年ぐらいさ、そのいい加減な考え方捨てて、必死になったらどうなんだ?
(ホントかよ、秀二。こんな俺でも、必死になったら、お前が目指した所を狙えるのか?)
――そのいい加減な考え方捨てて、必死になったらどうなんだ?
(必死に……俺が一番嫌いだと言い続けた言葉だ。俺が必死になったら、お前は俺を認めてくれる? 秀二、認めてくれるのか?)
ギュッと握りしめた拳。その拳の上に、一粒、雫が落ちた。
(秀二、どうしたら、お前は目を開けてくれるんだよ。ずっと一緒だったのに。どうしたらお前を助けられるんだ。どうしたら、悩みが相談できるような存在になれるんだよ、秀二! 眠ってないで、教えてくれよ)