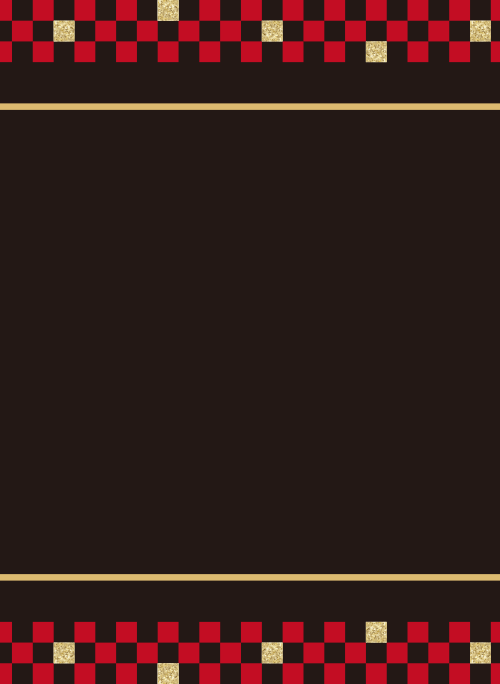「庸介君、庸介君の責任じゃないわ」
あれから一週間が経った。
秀二の容態は安定していたが、意識は未だ戻らなかった。庸介は毎日見舞いに行ったが、秀二が目を開けることはなかった。
この日、理衣が心配して家にやって来た。
綾の落ち込みも大きかったし、親友である庸介はもっとひどい状態だと聞いて、心配したのだ。
庸介の部屋で、ベッドの側面に並んで凭れかかり、落ち込む庸介を励ました。
「庸介君が自分を責めても仕方のないことよ」
庸介は声をかける理衣を無視していたが、やがてようやくポツリと「違う」と零した。
「違わないよ。どんなにつらくっても、悩みは自分で解決しなきゃいけないわ。それが人とのトラブルじゃなく、自分のことだったら尚更そうよ。庸介君が自分を責めても、なんの解決にもならないよ」
「一番あいつのことをわかっているはずの俺が、子どもの時からずっと一緒だった俺が、あいつのつらさをわかっていなかった! 俺が、もっと! もっと、しっかりしてさえいれば、あいつを助けてやれたはずなんだ! 俺が!」
両手で頭を抱え、泣き崩れる。理衣はそんな庸介を抱きしめた。
「お互いよくわかっている関係のはずだった。なのに俺は親友ヅラして、わかったような顔して、全然……全然信用されてなかった。こんなちゃらんぽらんだから、秀二に信用されなくて、だから救えなかったんだ」
「どんなに近くにいる人でも、どんなに信頼していると思っている人でも、その人じゃないんだから、わからないわよ。それに、近いからこそ、言えないこともある」
「どうしてどんなことが言えるんだよ!」
「お友達の悩みは私にはわからないけど、私もつらくてよく泣いたもん。でも、一番の味方のはずの母には言えなかった。心を許してるはずの人だから言えないこともあるのよ。庸介君、誰も悪くないよ」
「――理衣」
「私は、どうして理衣にはパパがいないの? その一言が言えなかった。どうしても聞けなかった。中学に入る時、その理由を知ったわ。だからますます大事なことほど、母には言えなくなった。なにもかも、自分で考えるようになった。お友達は、なにに悩んでいたの?」
庸介の口から「兄弟」と小さく漏れた。
「兄弟?」
「あいつは、優秀な兄貴を越えようと、いつも必死だったんだ。両親が賢い兄貴を溺愛して、あいつはいつも傷ついていた。よく言ってた。どんなに試験で良い点を取っても相手にしてくれないって。『隆一がいるから、秀二は無理に勉強しなくていい、好きなことをしろって言われる』って。だから兄貴を越えて、自分のほうが優秀だって思わせたいんだって。俺がもっと話を聞いて、相談に乗ってやれば、秀二は追い詰められたりしなかったはずだ!」
「…………」
「俺が、軽いノリで、真剣さが足りなくて、いい加減だから、だから秀二は相談できなかったんだ! そればかりじゃない。兄貴は兄貴だから、それでいいじゃないかって、対抗心なんか捨てちまえって言ったんだ。秀二の気持ちもわかってやらず、そんなことを言って傷つけた。俺が、俺がもっと、ちゃんとしていたら――」
胸の中で顔を覆って叫ぶ庸介を、理衣は抱きしめるだけだ。
「俺が、俺が、俺が」
「庸介君」
「俺がっ」
泣きながら同じ言葉を繰り返す庸介に、理衣はそっと唇を重ねた。
「理、衣」
「私の顔を見て。ねぇ、私の話、聞いて」
焦点の合っていないような、呆然とした様子で理衣の顔を見つめる。理衣はもう一度軽く唇を重ねると、ゆっくりと話し出した。
「私さ、私、不倫の子なの」
「――え?」
「母親が不倫して、身ごもって、そのまま産んだの。下ろしてくれたらよかったのに――人の家庭を壊して、周囲の反対を押し切って、産んだのよ、私を」
庸介が言葉なく理衣を見つめる。
「自分はいいわよ。好きだかなんだか知らないけど、妻子のある人に手を出して、子どもが欲しいからって産んで。結局その人は、私が生まれる前に、飲酒運転の末に壁に激突して死んじゃったんだって。好き勝手してさ。そのおかげで生活は苦しくて、ずっと働いて、私はずっと一人ぼっちだった。寂しかったよ。ある時、知らない子たちが家の前にいて、人のお父さんを取った、殺した、ろくでなし! って叫ばれたわ。お前なんかきょうだいじゃない! って。その時、父がいない本当の理由がわかった。死んだって教えられてたの。『お母さんにまで騙されていた』って思って、すごく傷ついた。不倫の子って周囲にバレた時があったわ。汚いもモノを見るような目で見られた。ハッキリ、『うちの子に近付かないで』って言われたこともあった。私のせい? って思った。悔しかった。すごくつらかったけど、母には言えなかった。母を苦しめたくないってんじゃなく、つらすぎて、言葉にするのがイヤだった。大人は嘘ばかりだって思った。自分勝手で、嘘ばっかりで……誰も、何も信じられないって思った。自分がすごく汚くて、穢れている気もした。『お母さんが普通の恋をして、普通の結婚をしてくれたらこんなに傷つかなかったのに』って、母を一番恨んだ。だけど、恨みきれなった。やっぱり母だから。そんな時、学校の行事で写真展に行ったの。すごく感動したわ。そこからよ、カメラマンになりたいって思ったのは」
理衣は囁くように語っていた。
「空も、木も、花も、海も、風も、二度と同じものはない。だけど、どの一瞬も真実で、不変で、美しい。カメラは真実を映す。言葉もいらない。偽りなんか存在しない。真実の一瞬を切り取って、永遠に残す。きれいなものも、汚いものも、すべて。区別もしない。差別もしない。傷つけることもない。裏切らない。そう思って取り憑かれたように没頭した。心の逃げ道になった。祖父母に頼んで、安いカメラを買ってもらってね。写真を撮っている時だけ、生きてる気がした」
「…………」
「会ったこともない人の、自分とは違う種類の悩みに、『わかる』なんて言う気はない。けどさ、でも、なんとなく、お友達の孤独というか、寂しさというか、苦しさ、やっぱり『わかる』ような気がする。本当に苦しい時って、やっぱり言えないよ。言ったら、ますます惨めな気がするもの。全部、失いそうで、怖い。言える時は、自分なりの答えを見つけた時だよ。もう大丈夫って思えた時に、やっと口に出して言えるんだと思う。庸介君がスーパーマンだったとしても、お友達は絶対相談なんかしなかったと思う」
「理衣」
「なんでわかってやれなかったって悩むより、これからどうしてあげられるのか、それを考えるほうが大事なんじゃない?」
「これから?」
「そうよ。お友達が目を覚ました時、でもって覚ました後。お友達の為に、庸介君ができること、なに?」
庸介は俯き、黙り込んだ。
「庸介君にしかできないことがあるはず」
ギュッと目を閉じる庸介の目からは大粒の涙が零れた。
あれから一週間が経った。
秀二の容態は安定していたが、意識は未だ戻らなかった。庸介は毎日見舞いに行ったが、秀二が目を開けることはなかった。
この日、理衣が心配して家にやって来た。
綾の落ち込みも大きかったし、親友である庸介はもっとひどい状態だと聞いて、心配したのだ。
庸介の部屋で、ベッドの側面に並んで凭れかかり、落ち込む庸介を励ました。
「庸介君が自分を責めても仕方のないことよ」
庸介は声をかける理衣を無視していたが、やがてようやくポツリと「違う」と零した。
「違わないよ。どんなにつらくっても、悩みは自分で解決しなきゃいけないわ。それが人とのトラブルじゃなく、自分のことだったら尚更そうよ。庸介君が自分を責めても、なんの解決にもならないよ」
「一番あいつのことをわかっているはずの俺が、子どもの時からずっと一緒だった俺が、あいつのつらさをわかっていなかった! 俺が、もっと! もっと、しっかりしてさえいれば、あいつを助けてやれたはずなんだ! 俺が!」
両手で頭を抱え、泣き崩れる。理衣はそんな庸介を抱きしめた。
「お互いよくわかっている関係のはずだった。なのに俺は親友ヅラして、わかったような顔して、全然……全然信用されてなかった。こんなちゃらんぽらんだから、秀二に信用されなくて、だから救えなかったんだ」
「どんなに近くにいる人でも、どんなに信頼していると思っている人でも、その人じゃないんだから、わからないわよ。それに、近いからこそ、言えないこともある」
「どうしてどんなことが言えるんだよ!」
「お友達の悩みは私にはわからないけど、私もつらくてよく泣いたもん。でも、一番の味方のはずの母には言えなかった。心を許してるはずの人だから言えないこともあるのよ。庸介君、誰も悪くないよ」
「――理衣」
「私は、どうして理衣にはパパがいないの? その一言が言えなかった。どうしても聞けなかった。中学に入る時、その理由を知ったわ。だからますます大事なことほど、母には言えなくなった。なにもかも、自分で考えるようになった。お友達は、なにに悩んでいたの?」
庸介の口から「兄弟」と小さく漏れた。
「兄弟?」
「あいつは、優秀な兄貴を越えようと、いつも必死だったんだ。両親が賢い兄貴を溺愛して、あいつはいつも傷ついていた。よく言ってた。どんなに試験で良い点を取っても相手にしてくれないって。『隆一がいるから、秀二は無理に勉強しなくていい、好きなことをしろって言われる』って。だから兄貴を越えて、自分のほうが優秀だって思わせたいんだって。俺がもっと話を聞いて、相談に乗ってやれば、秀二は追い詰められたりしなかったはずだ!」
「…………」
「俺が、軽いノリで、真剣さが足りなくて、いい加減だから、だから秀二は相談できなかったんだ! そればかりじゃない。兄貴は兄貴だから、それでいいじゃないかって、対抗心なんか捨てちまえって言ったんだ。秀二の気持ちもわかってやらず、そんなことを言って傷つけた。俺が、俺がもっと、ちゃんとしていたら――」
胸の中で顔を覆って叫ぶ庸介を、理衣は抱きしめるだけだ。
「俺が、俺が、俺が」
「庸介君」
「俺がっ」
泣きながら同じ言葉を繰り返す庸介に、理衣はそっと唇を重ねた。
「理、衣」
「私の顔を見て。ねぇ、私の話、聞いて」
焦点の合っていないような、呆然とした様子で理衣の顔を見つめる。理衣はもう一度軽く唇を重ねると、ゆっくりと話し出した。
「私さ、私、不倫の子なの」
「――え?」
「母親が不倫して、身ごもって、そのまま産んだの。下ろしてくれたらよかったのに――人の家庭を壊して、周囲の反対を押し切って、産んだのよ、私を」
庸介が言葉なく理衣を見つめる。
「自分はいいわよ。好きだかなんだか知らないけど、妻子のある人に手を出して、子どもが欲しいからって産んで。結局その人は、私が生まれる前に、飲酒運転の末に壁に激突して死んじゃったんだって。好き勝手してさ。そのおかげで生活は苦しくて、ずっと働いて、私はずっと一人ぼっちだった。寂しかったよ。ある時、知らない子たちが家の前にいて、人のお父さんを取った、殺した、ろくでなし! って叫ばれたわ。お前なんかきょうだいじゃない! って。その時、父がいない本当の理由がわかった。死んだって教えられてたの。『お母さんにまで騙されていた』って思って、すごく傷ついた。不倫の子って周囲にバレた時があったわ。汚いもモノを見るような目で見られた。ハッキリ、『うちの子に近付かないで』って言われたこともあった。私のせい? って思った。悔しかった。すごくつらかったけど、母には言えなかった。母を苦しめたくないってんじゃなく、つらすぎて、言葉にするのがイヤだった。大人は嘘ばかりだって思った。自分勝手で、嘘ばっかりで……誰も、何も信じられないって思った。自分がすごく汚くて、穢れている気もした。『お母さんが普通の恋をして、普通の結婚をしてくれたらこんなに傷つかなかったのに』って、母を一番恨んだ。だけど、恨みきれなった。やっぱり母だから。そんな時、学校の行事で写真展に行ったの。すごく感動したわ。そこからよ、カメラマンになりたいって思ったのは」
理衣は囁くように語っていた。
「空も、木も、花も、海も、風も、二度と同じものはない。だけど、どの一瞬も真実で、不変で、美しい。カメラは真実を映す。言葉もいらない。偽りなんか存在しない。真実の一瞬を切り取って、永遠に残す。きれいなものも、汚いものも、すべて。区別もしない。差別もしない。傷つけることもない。裏切らない。そう思って取り憑かれたように没頭した。心の逃げ道になった。祖父母に頼んで、安いカメラを買ってもらってね。写真を撮っている時だけ、生きてる気がした」
「…………」
「会ったこともない人の、自分とは違う種類の悩みに、『わかる』なんて言う気はない。けどさ、でも、なんとなく、お友達の孤独というか、寂しさというか、苦しさ、やっぱり『わかる』ような気がする。本当に苦しい時って、やっぱり言えないよ。言ったら、ますます惨めな気がするもの。全部、失いそうで、怖い。言える時は、自分なりの答えを見つけた時だよ。もう大丈夫って思えた時に、やっと口に出して言えるんだと思う。庸介君がスーパーマンだったとしても、お友達は絶対相談なんかしなかったと思う」
「理衣」
「なんでわかってやれなかったって悩むより、これからどうしてあげられるのか、それを考えるほうが大事なんじゃない?」
「これから?」
「そうよ。お友達が目を覚ました時、でもって覚ました後。お友達の為に、庸介君ができること、なに?」
庸介は俯き、黙り込んだ。
「庸介君にしかできないことがあるはず」
ギュッと目を閉じる庸介の目からは大粒の涙が零れた。