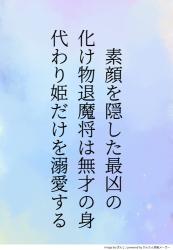これは、要約すると、マッチングアプリで出会った男に告白をされた話である。
当たり前じゃんって思うでしょ?
そう思ったあなたには、あたしが経験したこの話を、ぜひ最後まで聞いてほしい。
*
あたし——遠藤沙里は、今年で社会人五年目の二十七歳。
リフォーム会社の営業事務職として、日々、真面目に働いているOLだ。
さすがに仕事には慣れてきた。よほどのイレギュラー事態でない限り、大抵のことはこなせている。
会社に入社したばかりの頃は、毎朝六時半には起きて、週五日八時間以上も勤務するなんて人間の所業とは思えなかったけど、今ではそれが当たり前。習慣の力ってすごいよね。
仕事は順調。
でも、恋の方は、ずっとご無沙汰。
大学時代に長く付き合っていた彼氏と卒業間近に別れたきり、ずっと、そういう気になれなかったから。
最近、『久しぶりに恋がしたいなぁ』とぼやいたあたしに、友人は職場恋愛がおすすめだと言った。でもさ、職場恋愛って、冷静にけっこうハードル高くない? 会社の規模にもよるかもだけど、うまくいっている時より、うまくいかなかった未来を先に思い描いてしまうタイプの人間にはなんにせよ厳しいと思うのよ。ちなみにあたしは後者。
そんなわけで、出会いを求めて、マッチングアプリを始めることにした。
今日は、マッチングしてメッセージのやりとりを数週間続けていた男性との、初デートの日だ。
「あの……もしかして、遠藤沙里さんですか?」
遠慮がちに話しかけてきたネイビーのテーラードジャケットに細身のデニムジーンズを着た男性を見て、ピンときた。
「はい、遠藤です! 初めまして、会田さん」
お辞儀をすると、彼――会田信也さんはホッとしたように笑顔を見せた。
まずは、現実では顔を合わせたことがない者同士で、ちゃんと待ち合わせができたことに安堵する。
会田さん、実物で見ても、澄んだ瞳が印象的な好青年だなぁ。背丈は、聞いていた情報からの想像よりもすこしばかり低い気がするけれど……、だめだめ初っ端から細かいことは気にしないようにしよう!
ネット上には、アプリに載せている写真が加工されすぎていて実物と全然違った話もありふれている。はたまた、待ち合わせ場所まで行き、遠目から相手の姿を確認したところ、実物とかけ離れていたから会わずに帰ったという最低な話も目にしたことがあったから、実のところ少々不安だった。
会田さんの場合は、一目見てすぐに本人だとわかったし、それほど違和感もない。好感度一アップ。
「なんか、緊張しますね」
「そうですね」
ぽつぽつと会話をしながら、目的のイタリアンレストランへと向かう。最初は無難にランチデート。
会田さんは、アプリのプロフィールに書いてあったとおりで、メーカーの営業職。第一印象は、物腰柔らかで、紳士的。実際に会ってみても良いひとそうに思えた。
ランチを終えて、小洒落たレストランを出る頃には、同い年という親近感も募って、くだけた口調になっていて。
「ぜひ、また会おうね!」
もうちょっと話していたかったなぁ。
そう思いながら帰宅するデートが一番の成功だというけれど、正にそんな感じで、最初のデートは良い雰囲気で幕を閉じた。
✳︎
二回目のデートは映画館。
それも、すごく楽しかった。
燃えるような恋情ではないけれど、会うと話が弾んで楽しい。仕事ばかりの繰り返しだった毎日に、小さな花が咲いたような感じがした。
会田さんと、このまま付き合うのかもしれないなぁ。
そんな、ぼんやりとした薄桃色の予感は、三回目のデートの帰り際で完全にひっくり返ることになる。
その日は、まず水族館に行った。洋食のレストランで美味しいご飯を食べて、すこしお酒も嗜んで。ふわふわと楽しい気分のまま帰ろうとした、その矢先だった。
「実はさ、二人きりになれる場所があるんだ。すこし寄っていかない?」
「うん? 良いよ」
アルコールで多少テンションが上がっていたのもあって、二つ返事だった。
「どこに行くの?」
尋ねても、会田さんは「いけばわかるよ」と穏やかに微笑むばかり。
繁華街を通り抜け、アダルティなネオンが煌く建物が並びはじめたとき、ふわふわとした気持ちが泡のようにパンッと弾けた。
「ここ」
柔和に微笑んだまま会田さんが指差す先は、どう見ても、ラブホテルだ。それ以外の何者でもない。
「い、嫌!」
「なんで?」
なんで? じゃない。
付き合ってもいないのに、行き先も告げずにラブホテルを案内するなんて、どうかしている。大人の恋愛だからとか、そういう問題じゃないでしょ?
目の前の彼が、急にネットを介して出会っただけの素性のしれない人間に思えて、後ずさる。
「……彼氏じゃないひとと、ここには入れないです。あたしは、そういう価値観のひととはお付き合いできないです」
どうにかして毅然と言い放ち、逃げるように踵を返そうとしたその瞬間、引き止めるように手を握られた。
恐怖が、背筋を駆け上る。
こんな場面で手を握ってこられても、ときめくどころか、恐怖でしかない。
「はなしてっ」
「実はさ、おれ……」
なに。
まさか、こんな状況で、告白しようとしてる⁉︎
ときめきではなく、恐ろしさで胸が押しつぶされそうになりながら、抵抗を続けるあたしに彼は告げた。
「前科があるんだ」
は……?
いま、なんて言った?
聞こえてきた言葉のあまりのインパクトの大きさに、思わず動きを止めた。
ぜんか、ぜんか、前科。
良くも悪くも、平和で退屈な日常生活を送っているあたしには、テレビの中のニュースキャスターからや物語の中でしか聞かない言葉だった。
彼は、戸惑うあたしから手を放すと、なにもかもがどうでも良くなったかのように、投げやりな態度になった。
「更生施設に通ってたこともあるよ」
「……は、はあ」
あたしは一体なにを聞かされているのだろうか?
突然、宇宙空間に放り投げられてしまったかのような気分だ。
「それって、どんな罪……?」
恐怖と戸惑いと、非日常的事態へのほんの少しの好奇心が、あたしの足を完全に地面へと縫いつける。
「性犯罪。どお、失望した?」
絶句した。
相変わらず穏やかに微笑んだまま淡々と告げる会田さんが、人間ではない何者かに見えて、眩暈がする。
もはや、詳細を聞く気にもなれない。
「……なんで、あたしに話したの?」
態度の急変とカミングアウトの内容は最低であるものの、真実を告げずに、あのまま純粋な良い人の皮をかぶって付き合うこともできたはずだ。
会田さんは、首をかしげた。
「沙里はさ、おれのこと、好きだったよね?」
果たして、どうだっただろう。
数時間前の自分の気持ちを、完全に思い出せなくなっている。もう、会田さんを、やさしい好青年として見ることは永久に叶わなくなったのだ。過去は変わらないというけれど、今が、過去の記憶と当時の感情を捻じ曲げることは往々にしてよくあることだと思う。
なにも答えられないでいるあたしに、彼は神妙な顔つきで言った。
「前科がなかったら、付き合ってたでしょ? でもね、隠して付き合っても意味がない。おれは、おれの全てを受け入れてくれるひとを探しているんだよ」
心の中に、ありえんほどの寒風が吹いた瞬間だった。
ごめん。
なんか良い感じに言いくるめようとしてるけど、ふっっっっつうにキモいから!
ひとえに前科があるというカミングアウトでも、罪の種類や、共に過ごした時間の長さによっては受け入れられる場合もあるのかもしれない。でも、あなたは性犯罪なわけでしょ? はい、論外ー! たかが数回デートしただけの謂わばほぼ他人に、なにを期待して、なにを背負わせようとしてくれてんだ? 現実の恋をなめてんじゃねえぞ!
心の中で息切れしそうなほどまくしたてたあと、あたしは丁重に頭を下げて、会田さんに、今後二度と会うことはないと告げたのだった。
✳︎
「あっはっはっ! 沙里のその話、マジでうけるんだけど!」
「笑い事じゃないからっ!!」
「でも、暴力振るわれたり、無理やりラブホに連れ込まれたりはされなかったんだし。その、会田さん、だっけ? 彼は、マジのマジでゲスクズ野郎ってわけではなかったんじゃん?」
それに関しては、友人の言う通りなのだけど……。
涙が出かるかるほどウケてくれた友人の笑い声に、荒んでいた心がすこしだけ和む。あんなことがあったばかりだから、またしばらく恋愛はいいかなぁって気持ちだけどね。
これは要約すると、マッチングアプリで出会った男に告白をされた話だ。
ね、あたしの言っている意味が、よくわかったでしょ?【完】
当たり前じゃんって思うでしょ?
そう思ったあなたには、あたしが経験したこの話を、ぜひ最後まで聞いてほしい。
*
あたし——遠藤沙里は、今年で社会人五年目の二十七歳。
リフォーム会社の営業事務職として、日々、真面目に働いているOLだ。
さすがに仕事には慣れてきた。よほどのイレギュラー事態でない限り、大抵のことはこなせている。
会社に入社したばかりの頃は、毎朝六時半には起きて、週五日八時間以上も勤務するなんて人間の所業とは思えなかったけど、今ではそれが当たり前。習慣の力ってすごいよね。
仕事は順調。
でも、恋の方は、ずっとご無沙汰。
大学時代に長く付き合っていた彼氏と卒業間近に別れたきり、ずっと、そういう気になれなかったから。
最近、『久しぶりに恋がしたいなぁ』とぼやいたあたしに、友人は職場恋愛がおすすめだと言った。でもさ、職場恋愛って、冷静にけっこうハードル高くない? 会社の規模にもよるかもだけど、うまくいっている時より、うまくいかなかった未来を先に思い描いてしまうタイプの人間にはなんにせよ厳しいと思うのよ。ちなみにあたしは後者。
そんなわけで、出会いを求めて、マッチングアプリを始めることにした。
今日は、マッチングしてメッセージのやりとりを数週間続けていた男性との、初デートの日だ。
「あの……もしかして、遠藤沙里さんですか?」
遠慮がちに話しかけてきたネイビーのテーラードジャケットに細身のデニムジーンズを着た男性を見て、ピンときた。
「はい、遠藤です! 初めまして、会田さん」
お辞儀をすると、彼――会田信也さんはホッとしたように笑顔を見せた。
まずは、現実では顔を合わせたことがない者同士で、ちゃんと待ち合わせができたことに安堵する。
会田さん、実物で見ても、澄んだ瞳が印象的な好青年だなぁ。背丈は、聞いていた情報からの想像よりもすこしばかり低い気がするけれど……、だめだめ初っ端から細かいことは気にしないようにしよう!
ネット上には、アプリに載せている写真が加工されすぎていて実物と全然違った話もありふれている。はたまた、待ち合わせ場所まで行き、遠目から相手の姿を確認したところ、実物とかけ離れていたから会わずに帰ったという最低な話も目にしたことがあったから、実のところ少々不安だった。
会田さんの場合は、一目見てすぐに本人だとわかったし、それほど違和感もない。好感度一アップ。
「なんか、緊張しますね」
「そうですね」
ぽつぽつと会話をしながら、目的のイタリアンレストランへと向かう。最初は無難にランチデート。
会田さんは、アプリのプロフィールに書いてあったとおりで、メーカーの営業職。第一印象は、物腰柔らかで、紳士的。実際に会ってみても良いひとそうに思えた。
ランチを終えて、小洒落たレストランを出る頃には、同い年という親近感も募って、くだけた口調になっていて。
「ぜひ、また会おうね!」
もうちょっと話していたかったなぁ。
そう思いながら帰宅するデートが一番の成功だというけれど、正にそんな感じで、最初のデートは良い雰囲気で幕を閉じた。
✳︎
二回目のデートは映画館。
それも、すごく楽しかった。
燃えるような恋情ではないけれど、会うと話が弾んで楽しい。仕事ばかりの繰り返しだった毎日に、小さな花が咲いたような感じがした。
会田さんと、このまま付き合うのかもしれないなぁ。
そんな、ぼんやりとした薄桃色の予感は、三回目のデートの帰り際で完全にひっくり返ることになる。
その日は、まず水族館に行った。洋食のレストランで美味しいご飯を食べて、すこしお酒も嗜んで。ふわふわと楽しい気分のまま帰ろうとした、その矢先だった。
「実はさ、二人きりになれる場所があるんだ。すこし寄っていかない?」
「うん? 良いよ」
アルコールで多少テンションが上がっていたのもあって、二つ返事だった。
「どこに行くの?」
尋ねても、会田さんは「いけばわかるよ」と穏やかに微笑むばかり。
繁華街を通り抜け、アダルティなネオンが煌く建物が並びはじめたとき、ふわふわとした気持ちが泡のようにパンッと弾けた。
「ここ」
柔和に微笑んだまま会田さんが指差す先は、どう見ても、ラブホテルだ。それ以外の何者でもない。
「い、嫌!」
「なんで?」
なんで? じゃない。
付き合ってもいないのに、行き先も告げずにラブホテルを案内するなんて、どうかしている。大人の恋愛だからとか、そういう問題じゃないでしょ?
目の前の彼が、急にネットを介して出会っただけの素性のしれない人間に思えて、後ずさる。
「……彼氏じゃないひとと、ここには入れないです。あたしは、そういう価値観のひととはお付き合いできないです」
どうにかして毅然と言い放ち、逃げるように踵を返そうとしたその瞬間、引き止めるように手を握られた。
恐怖が、背筋を駆け上る。
こんな場面で手を握ってこられても、ときめくどころか、恐怖でしかない。
「はなしてっ」
「実はさ、おれ……」
なに。
まさか、こんな状況で、告白しようとしてる⁉︎
ときめきではなく、恐ろしさで胸が押しつぶされそうになりながら、抵抗を続けるあたしに彼は告げた。
「前科があるんだ」
は……?
いま、なんて言った?
聞こえてきた言葉のあまりのインパクトの大きさに、思わず動きを止めた。
ぜんか、ぜんか、前科。
良くも悪くも、平和で退屈な日常生活を送っているあたしには、テレビの中のニュースキャスターからや物語の中でしか聞かない言葉だった。
彼は、戸惑うあたしから手を放すと、なにもかもがどうでも良くなったかのように、投げやりな態度になった。
「更生施設に通ってたこともあるよ」
「……は、はあ」
あたしは一体なにを聞かされているのだろうか?
突然、宇宙空間に放り投げられてしまったかのような気分だ。
「それって、どんな罪……?」
恐怖と戸惑いと、非日常的事態へのほんの少しの好奇心が、あたしの足を完全に地面へと縫いつける。
「性犯罪。どお、失望した?」
絶句した。
相変わらず穏やかに微笑んだまま淡々と告げる会田さんが、人間ではない何者かに見えて、眩暈がする。
もはや、詳細を聞く気にもなれない。
「……なんで、あたしに話したの?」
態度の急変とカミングアウトの内容は最低であるものの、真実を告げずに、あのまま純粋な良い人の皮をかぶって付き合うこともできたはずだ。
会田さんは、首をかしげた。
「沙里はさ、おれのこと、好きだったよね?」
果たして、どうだっただろう。
数時間前の自分の気持ちを、完全に思い出せなくなっている。もう、会田さんを、やさしい好青年として見ることは永久に叶わなくなったのだ。過去は変わらないというけれど、今が、過去の記憶と当時の感情を捻じ曲げることは往々にしてよくあることだと思う。
なにも答えられないでいるあたしに、彼は神妙な顔つきで言った。
「前科がなかったら、付き合ってたでしょ? でもね、隠して付き合っても意味がない。おれは、おれの全てを受け入れてくれるひとを探しているんだよ」
心の中に、ありえんほどの寒風が吹いた瞬間だった。
ごめん。
なんか良い感じに言いくるめようとしてるけど、ふっっっっつうにキモいから!
ひとえに前科があるというカミングアウトでも、罪の種類や、共に過ごした時間の長さによっては受け入れられる場合もあるのかもしれない。でも、あなたは性犯罪なわけでしょ? はい、論外ー! たかが数回デートしただけの謂わばほぼ他人に、なにを期待して、なにを背負わせようとしてくれてんだ? 現実の恋をなめてんじゃねえぞ!
心の中で息切れしそうなほどまくしたてたあと、あたしは丁重に頭を下げて、会田さんに、今後二度と会うことはないと告げたのだった。
✳︎
「あっはっはっ! 沙里のその話、マジでうけるんだけど!」
「笑い事じゃないからっ!!」
「でも、暴力振るわれたり、無理やりラブホに連れ込まれたりはされなかったんだし。その、会田さん、だっけ? 彼は、マジのマジでゲスクズ野郎ってわけではなかったんじゃん?」
それに関しては、友人の言う通りなのだけど……。
涙が出かるかるほどウケてくれた友人の笑い声に、荒んでいた心がすこしだけ和む。あんなことがあったばかりだから、またしばらく恋愛はいいかなぁって気持ちだけどね。
これは要約すると、マッチングアプリで出会った男に告白をされた話だ。
ね、あたしの言っている意味が、よくわかったでしょ?【完】