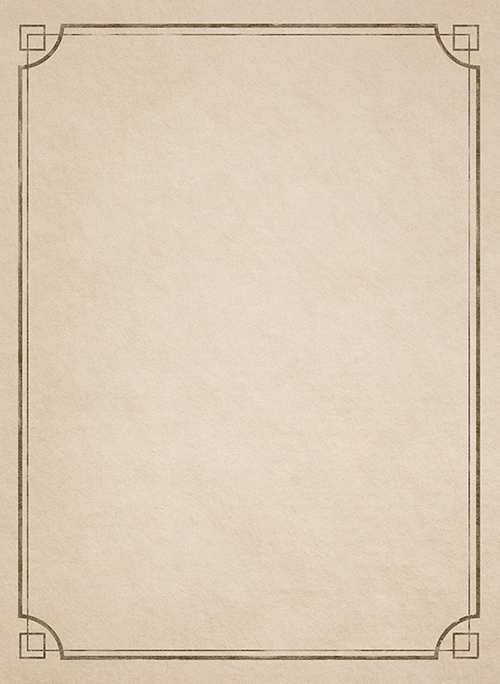無だ。
目の前には薄い膜が張っていて、その手前では繭の中、誰かがうずくまっている。
私だ。
この繭の中にいるのが私。
膜の向こうにいるのは――――。
夕暮れの空が、まるで燃え盛る炎のように赤く染まっていた。その炎は、ゆっくりと、しかし確実に教室の窓ガラスに映り込み、静寂に包まれた空間を赤い光で満たしていく。その中に佇む一人の少女がいた。桐島奏、17歳。彼女は窓際に立ち、遠くを見つめていた。
教室の空気は、放課後特有の静けさに満ちていた。黒板の文字や机の上に置かれた教科書たちが、一日の喧騒を終えてほっと息をついているかのようだ。しかし、その静寂とは裏腹に、奏の胸の内は激しく波打っていた。
「桐島さん、今日も生徒会の仕事お疲れ様」
突然の声に、奏は我に返った。振り返ると、そこには担任の高橋先生が立っていた。柔和な微笑みを浮かべ、優しい目で奏を見つめている。
「ありがとうございます。明日の朝礼の原稿も、もう仕上げました」
奏は作り笑いを浮かべて答えた。その表情は、まるで完璧に作られた仮面のようだった。
高橋先生は満足げに頷き、「さすが桐島さんだね。君がいてくれて本当に助かるよ」と言って教室を後にした。その背中が見えなくなるまで、奏は笑顔を保ち続けた。
しかし、先生の足音が廊下の向こうで消えると同時に、奏の表情が一変した。先生の言葉を耳にした瞬間、彼女の内なる何かが軋むような音を立てた。「さすが」「頼りになる」「優等生」……そんな言葉が彼女を縛り付けていく。そう、まるで蜘蛛の糸のように。
奏は深く息を吐き出すと、ゆっくりと鞄を手に取った。教室を出る前に、もう一度窓の外を見やる。夕焼け空の下、校庭では部活動を終えた生徒たちが楽しげに談笑しながら下校していく姿が見えた。
奏は窓際に立ち、校庭で汗を流す部活動の生徒たちを見つめていた。その光景は、彼女に一年前の自分を思い出させた。高校入学直後、奏にもあんな風に青春を謳歌する時期があったのだ。
文武両道は、彼女にとって既定路線だった。両親も当然のように運動部への入部を勧めてきた。「うちの娘なら、勉強も部活も両立できるはず」という期待の言葉が、今でも耳に残っている。
奏が進学したのは、家からバスで一時間半以上もかかる進学校。朝早くに家を出て、夜遅くに帰宅する日々が続いた。最初のうちは、その生活にも充実感を感じていた。しかし、時が経つにつれ、勉強と部活動の両立が徐々に厳しくなっていった。
夜遅くまで続く部活動。帰宅後の勉強。睡眠時間を削って課題をこなす日々。奏の顔には、日に日に疲労の色が濃くなっていった。それでも、周囲の期待に応えようと必死だった。
しかし、一年生の終わり頃、奏は一つの決断をする。「これ以上は無理だ」という思いが、彼女の心の中で大きくなっていった。そして、ついに退部を決意したのだった。
その決断は、奏にとって大きな転換点となった。両親の失望した表情、先生たちの心配そうな眼差し、部活仲間からの「裏切り者」の烙印。それらに耐えながら、奏は自分を守る道を選んだのだ。
今、窓際に立つ奏の目には、かすかな後悔の色が浮かんでいた。しかし同時に、自分の選択が間違っていなかったという確信も芽生えていた。彼女の瞳に映る部活動の光景は、もはや憧れではなく、自分とは別の世界のものになっていた。
廊下に出た奏は、静かに歩を進めた。靴音が空っぽの廊下に響き、それが彼女の心の空虚さを強調しているかのようだった。ふと、窓の外に目をやると、そこに課外のタレントスクールに通う生徒たちの姿を見つけた。
彼らの生き生きとした表情、自由に笑い合う姿。それを見た瞬間、奏の心に鋭い痛みが走った。
(本当は私も...)
その思いを振り払うように、奏は首を振った。しかし、その願望は簡単には消えてくれない。
学校を出た奏は、いつものように近くの公園に足を向けた。誰もいない公園で、彼女はブランコに腰を下ろした。錆びついた鎖が軋む音が、彼女の心の叫びのように聞こえた。
「本当は……」
言葉が喉元まで上がってきたが、そこで止まってしまう。
(本当は、声優になりたい。でも、それは……)
頬を伝う涙。しかし、すぐに拭い去った。幼い頃から演技に憧れていた。テレビの中で生きるアニメキャラクターたちを見て、心が躍った。だが、両親や先生たちの期待に応えるため、その夢を胸の奥深くに封印していたのだ。
夕陽が茜色に空を染め、その光が奏の顔を柔らかく照らしている。しかし、その温かな光とは裏腹に、奏の胸の内には冷たいものが渦巻いていた。
子供の頃から、奏の家は厳格そのものだった。両親は教育熱心というよりも、むしろ偏狭と呼ぶべき価値観の持ち主だった。アニメやゲーム、漫画といった娯楽は一切許されず、「勉強に関係のないものは無駄」という考えが家中を支配していた。
奏の目は、自室の本棚に並ぶ無機質な背表紙に向けられた。そこには百科事典や図鑑ばかりが整然と並び、その光景は奏の心を締め付けるようだった。友達の家に遊びに行くたびに、そこにある漫画の単行本やアニメのDVDを羨ましそうに眺めていたことを思い出す。しかし、自分の家にそれらを持ち込むことは決して許されなかった。
両親のサブカルチャーへの偏見は、まるで化石のように固まっていた。テレビで声優や若手俳優のドキュメンタリーが流れると、両親は鼻で笑い、「オタク」だの「人生の落伍者」だのと罵った。奏は今でも鮮明に覚えている。ある日のニュース番組で声優養成所の特集が流れた時のことを。
「気持ち悪い」と父が呟いた。
「いい歳してキンキンした声を出して」と母が嘲笑した。
その時、奏の心の中で何かが凍りついた。なぜなら、彼女の心の奥底には、声優になりたいという小さな夢が芽生えていたからだ。アニメの登場人物に命を吹き込む声優たちの姿に、奏は密かに憧れを抱いていた。しかし、両親の反応を目の当たりにし、その夢を口にすることさえ恐ろしくなった。
奏は深いため息をつき、再び頭上を見上げた。空には薄い雲が流れ、どこか物悲しい雰囲気を醸し出している。彼女の心も、その曇り空のように霞んでいた。
「言えない。絶対に言えない」
そう自分に言い聞かせながら、奏は立ち上がった。家に帰れば、また「優等生」の仮面を被らなければならない。その思いが、彼女の心を重くしていく。
夕焼けに染まる空を見上げながら、奏は心の中でつぶやいた。
(誰かに相談したい。私の本当の気持ちを聞いてくれる人はいないのかな? 私の夢を、笑わずに聞いてくれる人は……)
その問いかけは、誰にも届かないまま、夕暮れの風に消えていった。ブランコから立ち上がる時、奏は一瞬だけ、舞台に立つ自分の姿を想像した。しかし、すぐにその想像は罪悪感に変わっていく。
家路につく奏の背中は、まるで重い鎧を背負っているかのように見えた。彼女の周りの世界は、徐々に暗さを増していく。それは、彼女の心の中の闇を映し出しているかのようだった。
奏は歩みを進めながら、自分の人生がまるで暗い迷宮のようだと感じていた。出口が見えない。自分の本当の姿を見失いそうで怖い。でも、その迷宮から抜け出す勇気も持てない。
そんな彼女の頭上で、最初の星が瞬き始めた。その小さな光は、奏の心の中にある、まだ消えていない希望の光のようでもあった。
花壇の花の香りが、朝の空気を甘く染めていた。その香りは、桐島奏の記憶の奥底に眠る何かを揺さぶるようだった。二時間目と三時間目の間の休み時間。教室の窓から差し込む柔らかな日差しが、奏の机の上で静かに踊っている。その光の中に、少女の繊細な指先が浮かび上がっていた。
奏は、いつものように静かに席に座り、次の授業の準備をしていた。クラスメイトたちの賑やかな声が教室中に響き渡る。その喧騒の中で、彼女だけが孤島のように静寂を纏っていた。奏にとって、この静けさは安らぎであると同時に、孤独の象徴でもあった。
「桐島さん」
突然、その声が奏の耳に飛び込んできた。顔を上げると、そこには担任の高橋先生が立っていた。優しい笑顔を浮かべながら、先生は奏の机に近づいてきた。その姿は、まるで奏の心の中に差し込む一筋の光のようだった。
「ちょっといいかな?」
高橋先生の声には、いつもの温かみがあった。その声は、奏の心の奥底に眠る何かを揺り起こすようだった。
奏は慌てて立ち上がる。「はい、何でしょうか?」
その声には、普段の冷静さとは裏腹な、かすかな期待が混じっていた。
高橋先生は、一枚の紙を取り出した。「実は、来週の薬物乱用防止教室の講師への挨拶文なんだけど、ちょっと添削してもらえないかな?」
その言葉に、奏の心臓が小さく跳ねた。先生から頼まれるということは、自分が信頼されているということ。その認識が、彼女の胸を温かく満たした。それは、長い間凍りついていた何かが、少しずつ溶け始めるような感覚だった。
「はい、喜んで」
奏は微笑みながら答えた。その表情には、普段見せない柔らかさがあった。それは、彼女の心の奥底に眠る本当の自分が、ほんの少しだけ顔を覗かせたかのようだった。
高橋先生は安堵の表情を浮かべ、紙を奏に手渡した。「ありがとう。君なら適切なアドバイスをくれると思ってね」
その言葉に、奏の心は静かに揺れた。信頼されることの喜びと、それに応えなければならないという責任感が、彼女の中で交錯する。
奏は紙を受け取り、目を通し始めた。文章を読みながら、彼女の脳裏には様々な言葉が浮かんでは消えていく。適切な言葉選び、文の構成、全体の流れ。奏は無意識のうちに、ペンを手に取り、紙の余白にメモを書き始めていた。その姿は、まるで長い間封印されていた才能が、今まさに解き放たれようとしているかのようだった。
教室の窓の外では、秋の風が木々の葉を優しく揺らしていた。その光景は、奏の心の中の静かな喜びを映し出しているかのようだった。しかし、その瞬間、奏の心に小さな影が差した。自分がこんなにも文章を書く――――延いては自己表現するということそのものが好きだということ、そしてそれが両親の期待する「いい子」の姿から少しずつ逸れていくのではないかという不安。その思いは、空に浮かぶ薄い雲のように、奏の心を覆い始めた。
「桐島さん?」
高橋先生の声が、奏の思考を現実に引き戻した。
「あ、はい」奏は慌てて答える。「少し考えていただけです」
高橋先生は優しく微笑んだ。「君の意見をしっかり聞かせてもらえると嬉しいよ」
その言葉に、奏は勇気づけられた。彼女は深呼吸をし、自分の考えを整理し始めた。それは、長い間閉ざされていた扉が、少しずつ開いていくような感覚だった。
「はい。まず、導入部分ですが...」
奏は丁寧に、しかし自信を持って自分の意見を述べ始めた。文章の構成や言葉の選び方について、彼女なりの見解を伝える。その姿は、普段の「いい子」の仮面を被った奏とは少し違っていた。目には輝きがあり、声には熱が込められていた。それは、長い間封印されていた彼女の本当の姿が、今まさに目覚めようとしているかのようだった。
高橋先生は熱心に聞き入りながら、時折頷いていた。「さすが桐島さんだね。的確な指摘ばかりだ」
その言葉に、奏の頬がほんのりと赤くなる。普段は冷静を装っている彼女だが、この瞬間、素直に嬉しさを感じていた。それは、長い間凍りついていた彼女の心が、少しずつ溶け始めているような感覚だった。
しかし、その喜びとともに、奏の心の奥底では別の感情が渦巻いていた。こんな風に自分の意見を述べ、認められることの喜び。そして同時に、そんな自分を両親が知ったらどう思うだろうかという不安。奏の心の中で、「いい子」でいたいという思いと、本当の自分を表現したいという願望が激しくぶつかり合う。その葛藤は、教室の窓から見える空の明暗のように、彼女の心を揺さぶっていた。
「ありがとう、桐島さん」高橋先生の声が、再び奏を現実に引き戻す。「君のアドバイスを参考に、もう一度書き直してみるよ」
奏は小さく頭を下げた。「いいえ、お役に立てて良かったです」
その言葉の裏には、言葉にできない複雑な思いが隠されていた。
高橋先生が去った後、奏は再び自分の席に座った。周りでは相変わらずクラスメイトたちの賑やかな声が響いているが、奏の心の中は静かな波が広がっていた。それは、長い間凪いでいた海に、小さな波紋が広がり始めたかのようだった。
彼女は窓の外を見つめた。花壇の花の香りが再び鼻をくすぐる。その香りは、奏の心に小さな希望の種を蒔いているようだった。いつか、こんな風に自分の言葉で、自分の思いを自由に表現できる日が来るかもしれない。そんな未来への期待が、奏の心を静かに、しかし確実に温めていった。
チャイムが鳴り、次の授業の始まりを告げる。奏は深呼吸をし、再び「いい子」の仮面をかぶる。しかし、その仮面の下で、小さな変化の芽が確かに育ち始めていた。それは、長い冬を越えて、ようやく芽吹き始めた春の花のようだった。
教室の窓から差し込む夕陽が、桐島奏の顔を柔らかく照らしていた。その光は、彼女の繊細な横顔を浮かび上がらせ、まるで舞台の上の役者のように見せていた。放課後の静けさが教室を包み込む中、奏は一人、教室の隅で立ち尽くしていた。その手には、たった今拾った声優雑誌が握られている。表紙に踊る華やかな文字と写真が、彼女の心を密かに揺さぶっていた。
教室の反対側では、文芸部の数人が熱心に話し込んでいた。彼女たちの声が、静かな空間に響いていく。その声は、奏の耳には遠い世界からの呼び声のように聞こえた。
「ねえねえ、今度の『星空の調べ』のイベント、行く?」
「行きたい!水野優子さんと佐藤美雪さんが来るんでしょ?」
「うん!それに岡田誠也さんも来るらしいよ」
奏は、その会話に耳を傾けていた。声優の名前を聞くたびに、彼女の心臓は高鳴る。それは、幼い頃から密かに抱いていた夢の鼓動だった。声優になりたいという思い。それは、厳格な両親の前では決して口にできない秘密だった。その思いは、まるで小さな火種のように、奏の心の奥深くで燃え続けていた。
窓の外では、夕焼け空が刻一刻と色を変えていく。オレンジから紫へ、そして深い青へ。その色彩の変化は、奏の心の中の葛藤を映し出しているかのようだった。
ふと、文芸部の子たちが立ち上がり、教室を出ようとする。その時、一人が手に持っていた雑誌を落としてしまった。床に広がる雑誌の頁は、奏の目には夢への扉のように映った。
奏は思わず声をかけた。「これ……」
その一言を発するのに、どれほどの勇気が必要だったことか。奏の声は、かすかに震えていた。雑誌を拾い上げ、差し出す奏。文芸部の子たちは驚いたように振り返る。その瞬間、奏は自分が普段どれほど無口で、クラスメイトとの距離が遠かったかを痛感した。
「ごめんなさい!拾ってもらってありがとう」
一人が慌てて謝りながら、雑誌を受け取る。その手の動きは、まるで奏から逃げるかのようだった。奏は、この機会に会話に加わろうと思った。声優の話題で盛り上がる彼女たちに、自分も仲間入りできるかもしれない。そう思った瞬間、奏の心は希望に満ちていた。それは、長い間閉ざされていた扉が、少しだけ開いたような感覚だった。
「あのさ……」
奏が口を開こうとした瞬間、文芸部の子たちの表情が変わった。その変化は、奏の心に冷たい風を吹き込んだ。
「話うるさかった?ごめんね、ごめんね……!」
彼女たちは、奏の言葉を遮るように謝り始めた。奏は言葉を失った。自分の意図が全く伝わっていないことに気づいたのだ。その瞬間、奏は自分と周りの世界との間に、見えない壁があることを痛感した。
「いえ、そうじゃなくて……」
奏は必死に説明しようとしたが、文芸部の子たちは既に謝罪モードに入っていた。奏の言葉は、彼女たちの心に届く前に、空中で消えていくようだった。
「私たち、声が大きくなっちゃって。迷惑だったよね」
「本当にごめんなさい。気をつけます」
奏は、自分の立場が実はクラスで孤立していることを痛感した。いつも「いい子」を演じ、周りの期待に応えようとしてきた彼女。その姿が、クラスメイトたちに冷たい印象を与えていたのかもしれない。その認識は、奏の心に深い傷を残した。
文芸部の子たちは、深々と頭を下げると、そそくさと教室を出て行った。奏は、その後ろ姿を見つめながら、言葉を失ったまま立ち尽くしていた。彼女たちの足音が廊下に消えていく音が、奏の耳には自分の夢が遠ざかっていく音のように聞こえた。
教室に残されたのは、奏一人。夕陽に照らされた彼女の影が、長く伸びていく。その影は、奏の心の中の孤独を具現化したかのようだった。その瞬間、奏は自分の孤独を強く感じた。声優の夢。それを誰かと共有したいという思い。しかし、その思いを伝える勇気さえ持てない自分。その矛盾が、奏の心を引き裂いていた。
奏は深いため息をつき、窓の外を見た。夕焼け空が、彼女の複雑な心情を映し出しているかのようだった。空の色彩の変化は、奏の心の中の希望と絶望の揺れ動きを表現しているようだった。
「いつか……」
奏は小さくつぶやいた。その言葉には、希望と諦めが混在していた。いつか、本当の自分を表現できる日が来ることを願いながら。そして、その日まで、彼女は再び「いい子」の仮面をかぶり、教室を後にしたのだった。その背中には、夢を諦めきれない少女の切ない思いが、重くのしかかっていた。
夜の闇が深まり、街の喧騒が遠のいていく。桐島家の二階、奏の部屋だけが、微かな緊張感に包まれていた。窓の外では、冬の冷たい風が木々を揺らし、かすかな葉擦れの音が聞こえる。その音さえも、奏の耳には大きく響いた。
時計の針が午後11時を指す頃、奏は息を潜め、両親の寝室からの物音に神経を尖らせていた。耳を澄ませば、父の微かないびきが聞こえてくる。母の寝息はまだ聞こえない。奏は、母がまだ起きているのではないかと、不安に駆られた。
深呼吸を一つ。胸の鼓動が、自分の耳に響くほどだ。奏はおそるおそる自分のノートパソコンに手を伸ばした。指先が震えている。起動ボタンに触れる瞬間、奏は一瞬躊躇した。しかし、心の奥底に潜む欲求が、その手を押し進める。
電源を入れる。起動音が響かないよう、あらかじめスピーカーをミュートにしている。それでも、キーボードに触れる指先からの振動が、全身に伝わるようだった。画面が明るくなる瞬間、奏は思わず身を縮めた。その光が廊下にもれないよう、慎重にカーテンを引き直す。カーテンの布地が擦れる音さえ、この静寂の中では大きく感じられた。
パソコンが起動し、奏は密かに保存していた音声ファイルを開いた。それは、彼女が憧れる声優たちの演技が収録された貴重な音源だった。イヤホンを耳に装着する。その感触が、まるで罪の証のように感じられた。
奏は小さな声で呟いた。「よし……」
その一言には、不安と期待が入り混じっていた。声を出した瞬間、自分の声が廊下に漏れていないか、奏は息を殺して耳を澄ませた。
再生ボタンを押す。お気に入りの声優の演技が、イヤホンを通して耳に届く。その声は、奏の心に直接響いてくるようだった。目を閉じ、深く息を吸う。胸の中で、何かが熱く燃え上がるのを感じた。
奏は声真似を始めた。「わたし……本当は……」
最初の一言は、か細く震えていた。自分の声が両親に聞こえてしまうのではないかという恐怖が、奏の喉を締め付ける。しかし、憧れの声優の演技を聴きながら、少しずつ奏の声に力が宿っていく。
「わたし、本当は声優になりたいの!」
奏は驚いた。自分の声が、こんなにも感情を込めて出せるなんて。それは、普段の「いい子」を演じる奏からは想像もつかない声だった。その瞬間、奏は自分の中に眠っていた何かが目覚めたような感覚に襲われた。
しかし、すぐに現実に引き戻される。廊下に軋む音が聞こえた気がして、奏は慌てて声を潜める。心臓が激しく鼓動を打つ。両親に見つかったらどうしよう。そんな不安が頭をよぎる。冷や汗が背中を伝う。
数秒間、奏は息を殺して耳を澄ませた。しかし、家の中は相変わらず静寂に包まれていた。安堵のため息をつきながら、奏は再び声真似に挑戦する。
今度は、アニメのヒロインの感動的なシーンだ。「たとえ世界中が敵に回っても、私は諦めない!」
奏の声が、部屋の中で小さく、しかし確かに響く。これが本当の自分の声なのかもしれない。そう思うと、胸が熱くなる。
しかし、同時に罪悪感も湧き上がってくる。両親の期待に背いているような気がして、奏の心は揺れる。「いい子」でいなければならないという呪縛と、本当の自分を表現したいという欲求が激しくぶつかり合う。
それでも、奏は声真似を続けた。様々なキャラクターの声を真似ながら、奏は自分の可能性を探っていく。時には笑い、時には泣き、時には怒る。それは、日常の奏からは想像もつかない表情の数々だった。
窓の外では、月が雲間から顔を覗かせ、その柔らかな光が部屋に差し込む。まるで、奏の秘密の行為を見守るかのように。
ふと、時計を見ると、気づかないうちに1時間以上が経っていた。奏は慌てて音声ファイルを閉じ、パソコンの電源を切る。深夜の静寂が、再び部屋を支配する。
奏はベッドに横たわり、天井を見つめた。心臓はまだ高鳴ったままだ。今夜の経験が、彼女の中に新たな何かを芽生えさせたことは確かだった。しかし、その芽を大きく育てることができるのか。それとも、このまま枯れさせてしまうのか。
奏は目を閉じ、今夜演じた様々な声を思い出す。それは、彼女の中に眠る無数の可能性の声だった。いつか、その声を堂々と出せる日が来るだろうか。そんな思いを胸に、奏は静かに目を閉じた。
明日になれば、また「いい子」の仮面をかぶらなければならない。しかし、今夜の経験は、その仮面の下で確実に育っていくだろう。それは、奏の心の中で、小さいながらも強い光となって輝いていた。
窓の外では、夜が更けていく。街の灯りが一つ、また一つと消えていく。しかし、奏の心の中では、新たな光が灯り始めたのだった。
朝靄が晴れ始めた朝、教室の窓から差し込む柔らかな光が、桐島奏の机の上で静かに踊っていた。その光は、奏の整然と並べられた教科書や筆記用具の上を優しく撫でるように動き、彼女の日常の一コマを照らし出していた。いつもなら静寂に包まれるこの時間、今日は何か違う空気が漂っていた。
奏は、いつものように早めに登校し、静かに席に着いていた。しかし、周囲のクラスメイトたちの間では、小さな噂が蜂の巣をつついたかのように飛び交っていた。その声が、奏の耳に届く。
「ねえ、聞いた? 転校生が来るんだって」
「えー、マジ? 男の子? 女の子?」
「さあ、わかんない。でも、面白い子らしいよ」
奏は静かにその会話を聞いていた。転校生。その二文字が、彼女の心に小さな波紋を広げる。新しい風が吹き込むのかもしれない。そう思う一方で、奏の心の中では、そんな期待よりも不安の方が大きかった。
変化を恐れる気持ち。それは、長年「いい子」を演じ続けてきた奏にとって、当然の反応だった。新しい人間関係。新しい環境。それは、彼女が築き上げてきた繊細なバランスを崩す可能性を秘めていた。奏は、自分の中に芽生えたその不安を、静かに押し殺した。
朝のホームルームを告げるチャイムが鳴り、担任の高橋先生が教室に入ってきた。先生の足音が、奏の心臓の鼓動と重なる。
「はい、静かに。今日は皆さんに紹介したい人がいます」
高橋先生の声が、教室に響き渡る。その瞬間、クラス全体が水を打ったように静まり返った。奏は、自分の呼吸さえ聞こえそうな静寂の中で、ゆっくりと顔を上げた。
そして、ドアが開いた。
一人の少年が入ってきた。その姿を見た瞬間、奏の心臓が大きく跳ねた。
「八神空です。よろしく」
その一言で、教室の空気が一変した。八神空。彼の姿は、まるで舞台の上の役者のようだった。凛とした立ち姿、そして周囲を見渡す鋭い眼差し。しかし、その表情には少し茶目っ気のある笑みが浮かんでいた。その笑顔が、奏の心に直接響いてくるようだった。
「八神君は海外から帰国したばかりです。みんな、仲良くしてあげてください」
高橋先生の言葉に、クラスメイトたちがざわめき始めた。その反応は、まるで静かな湖面に小石を投げ入れたかのようだった。しかし、空はそんな反応を気にする様子もなく、堂々と自己紹介を始めた。
「八神空です」
そのよく通る声に教室からは「イケメーン」だの、「趣味は?」だの声が飛ぶ。
「僕は、演劇が大好きです。特に好きな作品はシェイクスピアの作品です。『ハムレット』の "To be, or not to be" のセリフ、知っていますか?」
突然、空は演技を始めた。その瞬間、教室が即席の舞台と化した。空の声が、教室中に響き渡る。
"To be, or not to be, that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take Arms against a Sea of troubles,
And by opposing end them..."
クラスメイトたちは驚きの表情を浮かべていた。その表情は、まるで突然の雷鳴に驚いた小鳥のようだった。しかし、奏の目には、空の姿が輝いて見えた。自由に、堂々と自分を表現する空。その姿に、奏の心の中で、何かが揺れ動いた。
それは、長い間押し殺してきた自分の本当の姿。声優になりたいという夢。両親や周囲の期待に応えるため、ずっと隠してきた自分の本当の願い。それが、空の姿を見ることで、少しずつ目を覚まし始めたのだ。
空の演技が終わると、教室は静寂に包まれた。その静寂は、まるで時が止まったかのようだった。そして次の瞬間、拍手が沸き起こった。その音は、奏の心の中で鳴り響く鼓動と重なった。
「すごい! 本当に演技が上手いんだね!」
「えー、かっこよ……」
クラスメイトたちの反応に、空は満足げな笑みを浮かべた。その笑顔は、まるで太陽のように明るく輝いていた。そして、空は奏の方をちらりと見た。その瞬間、奏は自分の心臓が高鳴るのを感じた。それは、まるで小鳥が羽ばたくような、軽やかで不思議な感覚だった。
「じゃあ、八神君は……そうだな、桐島さんの隣の席に座ってください。彼女はとても優秀だからなんでも教えてくれますよ」
高橋先生の言葉に、奏は思わず身を強張らせた。空が奏の隣に座る。その距離の近さに、奏は戸惑いを覚えた。それは、まるで突然、強い光に照らされたような感覚だった。
「よろしくね、桐島さん」
空の声が、奏の耳元で響く。その声には、どこか不思議な魅力があった。まるで、遠い異国の風のような、新鮮で心地よい響きだった。奏は小さく頷くことしかできなかった。その仕草は、まるで風に揺れる小さな花のようだった。
授業が始まり、空は周囲の目を気にすることなく、積極的に発言を続けた。時には先生の意見にも異を唱える。その姿に、クラスメイトたちは驚きと戸惑いを隠せなかった。その反応は、まるで穏やかな湖面に突然の風が吹いたかのようだった。
しかし、奏の目には、空の姿が眩しく映った。自由に、自分の意見を言える空。そんな空を見ていると、奏の心の中で、何かが芽生え始めているのを感じた。それは、長い冬を越えて、ようやく芽吹き始めた春の花のようだった。
昼休み、空は奏に声をかけた。その声は、静かな教室に響く鐘の音のようだった。
「ねえ、桐島さん。一緒にお昼食べない?」
その言葉に、奏は驚きを隠せなかった。しかし、何かに突き動かされるように、奏は頷いた。その仕草は、まるで風に吹かれて揺れる柳の枝のようだった。
二人で屋上に向かう。階段を上がるにつれ、奏の心臓の鼓動が早くなっていく。それは、まるで高い山を登るように、息が上がるような感覚だった。
屋上に着くと、そこには広大な空が広がっていた。その青さは、奏の心の中の小さな希望のようだった。そこで空は、再び演技を始めた。今度は『ロミオとジュリエット』の一場面だ。
空の声が、青空に向かって響き渡る。その声は、まるで鳥の歌のように自由で美しかった。奏は、その姿に魅了された。自由に、自分を表現できる空。そんな空を見ていると、奏の心の中で、長い間押し殺していた何かが、少しずつ目覚め始めるのを感じた。
それは、声優になりたいという夢。両親の期待に応えるため、ずっと隠してきた自分の本当の願い。それが、空の姿を見ることで、少しずつ形を取り始めたのだ。
これが、奏と空の出会いだった。この出会いが、奏の人生を大きく変えていくことになる。そして、奏の中に眠っていた「本当の自分」が、少しずつ目を覚ましていくのだった。
その瞬間、奏の心の中で、小さな花が咲いたような気がした。それは、まだ小さく、か弱いものだったが、確かに存在していた。そして、その花は、これから様々な試練を乗り越えながら、大きく美しく咲いていくのだろう。
奏は、空の演技を見ながら、自分の中に芽生えたその小さな希望を、大切に育てていこうと決意した。それは、まだ誰にも言えない、奏だけの秘密の花だった。しかし、いつかはその花を、堂々と世界に向けて咲かせる日が来るかもしれない。そんな未来を、奏は密かに、しかし強く願った。
夜の帳が静かに降りた夜、桐島家のリビングは深い静寂に包まれていた。窓の外では、冷たい冬の風が木々の枝を揺らし、かすかな音を立てている。その音さえも、この静寂を破るには至らなかった。
時計の針が午後10時を指す頃、リビングのテーブルを挟んで、母と娘が向かい合っていた。夕食後の団らんという温かな時間はなく、そこにあるのは重苦しい空気だけだった。テーブルの上には、奏が返却されたばかりの定期テストの答案用紙が無造作に置かれている。その用紙に記された赤い点数が、まるで生き物のように蠢き、奏を責め立てているかのようだった。
「最近、成績が落ちてるわね」
母親の声は静かだったが、その静けさには冷たい棘が潜んでいた。その言葉は、凍てつく冬の夜気のように、奏の心に突き刺さった。奏は俯き加減で、何も言わずにその言葉を受け止めた。言い訳をする気力も湧いてこない。ただ、その沈黙が母親をさらに苛立たせていることだけは感じ取れた。空気が凍りつくような緊張感が、二人の間に漂っていた。
「それにね、最近夜遅くまで部屋に電気がついているけれど、あれは何をしているの? 勉強しているんじゃないの?」
母親の声が少し鋭くなる。その言葉に、奏は一瞬だけ顔を上げた。心臓が大きく跳ねる。その鼓動が、自分の耳に響くほどだった。夜中にこっそり声真似をしていることなど、絶対に知られてはいけない。あれだけは、自分だけの秘密だ。それは、奏にとって唯一の逃げ場であり、夢への小さな一歩だった。
「勉強に決まってるよ。他にすることないし」
自分でも驚くほど冷静な声で答えたつもりだった。しかし、その声には微かな震えが混じっていた。その震えは、まるで風に揺れる蝋燭の炎のように、奏の内なる不安を表していた。
「じゃあ、今度からお母さんの部屋でやりなさい」
その言葉に、奏は思わず顔を上げた。「え?」と短く声を漏らす。その瞬間、奏の心の中で何かが凍りついたような感覚があった。
「自分の部屋だったら、休憩したり、スマホ見たりできるじゃないの。お母さんの部屋だったら気が引き締まるでしょ?」
母親は淡々と言い放つ。その提案は、一見すると娘を思いやるものにも聞こえる。しかし、奏にはそれが自分の唯一の自由な時間を奪う宣告にしか思えなかった。それは、まるで鳥かごの扉が閉じられるような感覚だった。
「そんなの……お母さんに悪いよ。遅くまで起きててもらうのも悪いし。迷惑かけるし」
奏は必死に言葉を絞り出した。その言葉は、まるで乾いた砂漠に落ちる水滴のように、すぐに消えてしまいそうだった。それでも、自分でもその言葉が説得力を欠いていることを感じていた。
「あなたのためですから、お母さんは何も迷惑じゃないわよ?」
母親は微笑みながら答える。その笑顔には優しさというよりも、決定事項として押し付けるような強さが含まれていた。その笑顔は、まるで氷の仮面のようだった。
奏は何も言えずに黙り込んだ。ただ俯きながら、自分の胸の中で渦巻く感情と戦っていた。このままでは、本当に夜中の声真似の時間まで奪われてしまう。それだけは絶対に避けたい。あれだけが、自分自身でいられる唯一の時間なのだ。それは、奏にとって小さな光明であり、夢への細い糸だった。
(どうしてこんなにも自由がないんだろう)
胸の奥から湧き上がる苛立ちと悲しみ。それは、まるで胸の中で渦巻く嵐のようだった。それでも、それを口に出すことなどできない。厳格な両親に育てられた奏には、「いい子」でいること以外の選択肢など与えられてこなかった。その「いい子」という鎧は、奏を守ると同時に、彼女を縛り付けていた。
本当ならば、自分の時間の全てを俳優や声優になるための練習に使いたい。それなのに現実では、それすら許されない。都会で恵まれた環境にいる子たちは、小さいころからレッスンに通い、夢への道筋を着実に歩んでいるという話を聞くたび、自分との違いが痛感される。その差は、まるで越えられない深い谷のようだった。
(私は何をしているんだろう)
その思いが胸を締め付ける。自分には夢を見る資格すらないのではないかという絶望感。それは、まるで深い闇の中に沈んでいくような感覚だった。それでも夜中、一人で声真似をする時間だけは、その絶望から逃れるための小さな希望だった。それは、暗闇の中でかすかに輝く星のようだった。それすら奪われてしまったら、自分はどうなってしまうだろう。
「わかったわね?」
母親の声が現実へと引き戻す。その声は、まるで鋭い刃物のように、奏の思考を切り裂いた。奏は小さく頷くしかなかった。その仕草には反抗心もなく、ただ従順さだけが滲んでいた。それは、まるで折れた花のようだった。
しかし、その内側では小さな炎が燃えていた。その炎は、どんなに小さくとも、決して消えることはなかった。
(絶対に諦めたりしない)
心の中で静かに誓った。その誓いだけが、この瞬間、彼女自身を支える唯一の支柱だった。そしてその炎は、小さくとも確実に彼女自身を温め続けていた。それは、冬の寒さの中で咲く梅の花のように、強くたくましかった。
リビングの静寂が、再び二人を包み込む。窓の外では、冬の夜空に星々が瞬いていた。その星々は、奏の心の中の小さな希望のように、かすかに、しかし確かに輝いていた。この夜は、奏にとって長く厳しいものになるだろう。しかし、その心の奥底で燃える小さな炎は、決して消えることはないだろう。それは、奏の夢への道を照らす、小さくとも力強い光なのだから。
教室の窓から差し込む午後の柔らかな日差しが、八神空の姿を優しく包み込んでいた。その光の中で、空の朗読は一層輝きを増していた。シェイクスピアの『ハムレット』の一節が、流暢な英語で教室に響き渡る。
"To be, or not to be, that is the question..."
空の声は、まるで古い劇場で響く名優の声のように、深みと力強さを秘めていた。クラスメイトたちは、その声に魅了され、息を呑んで聞き入っている。その姿は、まるで一幅の絵画のようだった。
隣の席に座る桐島奏は、空を横目で見つめながら、胸の奥に湧き上がる複雑な感情と静かに戦っていた。確かに空の演技は素晴らしい。その才能は紛れもない事実だった。しかし、奏の心の中では、別の感情が静かに、しかし確実に芽生え始めていた。
「どうせこの人は家族の理解に恵まれているんだ」
その思いが頭をよぎった瞬間、奏の心に小さな嫉妬の種が蒔かれた。きっと空の両親は、彼の才能を認め、全面的に応援しているに違いない。高価な演劇のスクールにも通わせてもらっているのだろう。そう考えると、自分との境遇の違いが、まるで深い谷のように感じられた。
奏は、自分の家庭を思い出した。厳格な両親の顔が脳裏に浮かぶ。リビングの本棚に整然と並ぶ百科事典の背表紙。そして、声優になりたいという夢を打ち明けられない現実。その光景が、奏の心を重く圧迫した。
「ずるい。私なんか...」
心の中でつぶやいた言葉が、まるで鋭い刃物のように奏自身を傷つけた。その痛みは、胸の奥深くで静かに、しかし確実に広がっていった。
空の朗読が終わると、教室に大きな拍手が沸き起こった。英語教師までをも巻き込んだその音は、奏の耳には遠く、どこか虚ろに聞こえた。拍手の波が教室を満たす中、奏の胸の中では嫉妬の炎がさらに大きくなっていくのを感じた。その炎は、まるで乾いた草原に落ちた火の粉のように、瞬く間に広がっていった。
しかし、奏はその感情を必死に押し殺そうとした。「いい子」でいなければならない。そう自分に言い聞かせながら、奏は平静を装った。その表情は、まるで能面のように無表情だった。
だが、その心の奥底では、別の感情が静かに渦を巻いていた。自分も空のように自由に演技ができたら、どんなに素晴らしいだろうか。その思いは、長い間押し殺してきた奏の本当の姿だった。声優になりたいという夢。両親や周囲の期待に応えるため、ずっと隠してきた本当の願い。それは、まるで地下深くに埋もれた宝石のように、奏の心の奥深くに眠っていた。
奏は、空の演技を見ながら、自分の中に芽生えたその小さな希望と嫉妬の炎を、どう扱えばいいのか分からずにいた。それは、まだ誰にも言えない、奏だけの秘密の葛藤だった。その葛藤は、まるで静かな湖面下で渦巻く激流のようだった。
教室の窓の外では、空が静かに広がっていた。その青さは、奏の心の中の小さな希望を映し出しているようだった。しかし同時に、その広大さは奏の現実との距離を象徴しているようにも感じられた。
奏は深く息を吐いた。その吐息には、言葉にできない複雑な思いが込められていた。これからどうすればいいのか。その答えは、まだ見つからない。しかし、この日の出来事が、奏の心に小さな変化の種を蒔いたことは確かだった。
その種が、いつか大きな花を咲かせる日が来るのだろうか。奏は、そんな未来を密かに、しかし強く願った。それは、まだ誰にも言えない、奏だけの小さな夢だった。
夕方の光が教室の窓から差し込み、机の上に長い影を落としていた。冬の日差しは弱々しく、空気にはまだ冷たさが残っている。放課後の教室は、昼間の喧騒が嘘のように静まり返り、その静けさが奏の心にもじんわりと染み込んでくるようだった。
桐島奏は、机に頬杖をつきながら窓の外をぼんやりと眺めていた。校庭では部活動中の生徒たちが走り回り、その掛け声が遠くからかすかに聞こえてくる。夕陽が校舎を赤く染め、空には薄い雲が浮かんでいる。その景色はどこか物寂しく、奏の心をさらに沈ませていた。
教室にはもうほとんど誰もいない。机や椅子が整然と並ぶ中で、奏だけが取り残されたように感じていた。自分だけがこの空間に閉じ込められているような感覚。それでも、この静けさが彼女にとっては少しだけ心地よかった。
突然、教室のドアが勢いよく開いた。その音に奏は驚き、顔を上げる。
「奏ー!待たせた!」
元気な声とともに入ってきたのは佐藤茉莉だった。肩まで伸びた髪をポニーテールにまとめ、リュックを片方の肩に無造作に引っかけている。その姿はどこか無邪気で、まるで冬の日差しを跳ね返すような明るさを持っていた。
「別に待ってないけど」
奏は軽く笑いながら答えた。その声にはほんの少しだけ安堵が混じっていた。茉莉と話す時間は、彼女にとって心が軽くなる瞬間でもあった。
茉莉は奏の隣の席にどさっと腰を下ろすと、机に肘をついて顔を近づける。その仕草には親しみと無防備さがあり、それが奏には心地よかった。
「ねえねえ、今日さ、先生に褒められたんだよ!数学の小テストで80点取ったの!」
茉莉は嬉しそうに話す。その瞳はキラキラと輝き、その明るさが教室全体を照らしているようだった。
「へえ、すごいじゃん」
奏はそう言いながらも、心の中で少しだけ違和感を覚えた。80点。それは彼女にとって「普通」ではない点数だった。自分が同じ点数を取れば、きっと母親から厳しく叱責されるだろう。しかし茉莉は、その80点を誇らしげに語る。その違いが胸の奥で小さな棘となって刺さった。
「茉莉はいいよね。80点でも親に怒られないし」
思わず口をついて出た言葉だった。それがどれほど自分勝手なものか、自分でもわかっていた。しかし、その棘はどうしても飲み込むことができなかった。
茉莉は一瞬だけ表情を曇らせた。しかし、それもほんの一瞬だった。すぐにいつもの明るい笑顔に戻り、「まあねー。でも私だって大変なんだから!」と軽やかに返した。その言葉には明るい調子があったが、その裏側には何か隠されているようにも感じられた。
奏はそれ以上追及することなく、「そっか」とだけ答えた。そして再び窓の外へ視線を向けた。夕陽は少しずつ沈み始め、空には濃いオレンジ色が広がっている。その美しい景色も、今の彼女には何も感じさせてくれなかった。
冬の夕暮れ時、街路樹の影が長く伸び、その先端が奏と茉莉の足元をかすめていく。二人は肩を並べて歩いていたが、その間には目に見えない壁があるようだった。奏は時折、茉莉の横顔を盗み見ては、胸の奥で渦巻く複雑な感情と向き合っていた。
茉莉との関係は、奏にとって温かな光であると同時に、重い鎖でもあった。明るく元気な茉莉との時間は、確かに楽しい。その笑顔は、まるで冬の曇り空を突き抜ける一筋の陽光のようだった。しかし、その光の裏側に潜む影を、奏は感じずにはいられなかった。
(茉莉だって、本当はいろいろあるんだろう)
そう思いながらも、奏は自分自身の心の闇と向き合わざるを得なかった。本音を隠し合う二人の関係。それは、まるで薄氷の上を歩くようなものだった。一歩踏み外せば、その関係は簡単に崩れ去ってしまうかもしれない。そんな恐れが、奏の心を縛り付けていた。
冷たい風が二人の頬を撫でていく。街灯がぽつぽつと点灯し始め、街全体が夜の帳に包まれていくようだった。その光景は、奏の心の中の闇と光の境界線を象徴しているかのようだった。
「ねえ茉莉」
ふと思い出したように奏が口を開いた。その声には、微かな震えが混じっていた。
「昨日さ、お母さんから『母親の部屋で勉強しろ』って言われたんだよ」
その言葉を口にした瞬間、奏の胸の奥で何かが締め付けられるような感覚があった。母親との会話を思い出すだけで、喉が渇くような感覚に襲われる。
茉莉は驚いたような顔で振り返った。その瞳には、純粋な驚きと疑問が浮かんでいた。
「え? 奏、自分の部屋ないの?」
「あるよ。でも、『集中できないだろうから』とか言われてさ」
その言葉には、自分でも気づかないうちに苛立ちが滲んでいた。奏の声は、まるで凍えた冬の枝のようにかすかに震えていた。
「いいお母さんじゃん」
茉莉は軽く笑いながらそう言った。その言葉を聞いた瞬間、奏の胸の中で何かが弾けたような感覚があった。まるで、胸の奥に隠していた小さな希望の種が、一瞬にして砕け散ったかのようだった。
(何もわかってないくせに)
心の中でそう呟いた自分に驚いた。その思いは、まるで鋭い刃物のように奏の心を切り裂いた。茉莉には悪気などないことくらいわかっている。それでも、その無邪気な一言がどうしても許せなかった。その怒りは、奏の中で静かに、しかし確実に燃え上がっていった。
「そんなことないよ」
奏は短く答え、それ以上何も言わなかった。その声には、氷のような冷たさが滲んでいた。そして二人とも、それ以上深く話すことなく帰路についた。沈黙が二人の間に広がり、それは冬の夜空のように果てしなく続いていくようだった。
その夜、一人になった奏はベッドに横になりながら天井を見つめていた。窓から差し込む月明かりが、部屋の中に薄い影を作り出している。今日一日の出来事が頭の中でぐるぐると回る。特に茉莉との会話が心に引っかかったままだった。
(どうしてあんな風に思っちゃったんだろう)
罪悪感と苛立ち。その二つの感情が入り混じり、自分自身でも整理できないままだった。それは、まるで濁った水のように、奏の心の中を混濁させていた。一方で、自分とは違う家庭環境で育つ茉莉への羨望も消えることなく残っている。その感情は、冷たい月明かりのように、奏の心を静かに照らし続けていた。
奏は深いため息をつき、目を閉じた。瞼の裏に浮かぶのは、茉莉の笑顔だった。その笑顔は、奏にとって眩しすぎるほどだった。本当ならば、自分だってもっと自由になりたい。本当の夢について語りたい。しかし、それを口にする勇気が湧いてこない。その思いは、まるで重い鎖のように奏の心を縛り付けていた。
一方その頃、茉莉も布団に横になりながら天井を見上げていた。彼女の部屋は弟と共同で、壁には所々にシミがあった。布団に潜って一人になる時間だけが彼女自身でいられる瞬間だった。しかし、その短い時間ですら、自分自身について深く考える余裕などない。ただ、「明日も頑張ろう」と自分自身に言い聞かせることでやっと一日を終えている。
茉莉の瞳には、疲れと決意が混じり合っていた。その表情は、奏が普段見ている明るい茉莉とは全く違うものだった。しかし、それを誰かに見せることはない。それは、茉莉だけの秘密だった。
冬の冷たい風が、学校の屋上を吹き抜けていった。空は澄み切っているが、その青さはどこか冷たく、孤独を感じさせるものだった。奏はコンクリートの床に座り、膝の上に置いた弁当箱を開けた。冷たい風が指先をかすめ、思わず身震いする。隣では茉莉が、いつもの明るい調子で話している。その声は快活で、まるで冬の寒さを跳ね返そうとしているかのようだった。
少し離れたところでは、八神空が黙って空を見上げている。彼の背中はどこか孤高で、奏にはその沈黙が重く感じられた。この三人で屋上で昼食を取るようになってから、一週間が過ぎていた。教室の息苦しさから逃れたい一心でいたあの日。空が転校してきたあの日だ。そのとき空が「屋上で食べない?」と誘ってくれたのが始まりだった。茉莉も自然とついてきて、なんとなくこのメンバーが固定化していた。
屋上での昼食は、奏にとって安らぎの場所であると同時に、小さな緊張を強いられる時間でもあった。特に茉莉との関係がぎこちなくなってから、その思いはさらに強くなっていた。
奏は弁当のふたを開けながら、茉莉の横顔を盗み見た。相変わらず明るく楽しそうに話す茉莉。その笑顔はいつも通りだ。しかし、その裏側に何か隠されているような気がしてならない。あの日、帰り道で何気なく口にした一言。それが二人の間に見えない溝を作ってしまったのかもしれない。
(本当は、もっと話したいことがあるんじゃないか)
奏はそう思いながらも、言葉を飲み込んだ。口を開けば、また何かを傷つけてしまうかもしれない。それならば、このまま沈黙を守っている方がマシだと思った。自分自身も、本当の気持ちを伝えられないでいる。その歯がゆさが胸の奥でじわじわと広がり、重くのしかかる。
「ねえ、奏。聞いてる?」
茉莉の声にハッとして顔を上げた。慌てて作り笑いを浮かべる。
「ごめん、ちょっとボーッとしてた」
「もう、聞いてよ。今度の土曜日、みんなでカラオケ行かない?」
茉莉は弾むような声で言った。その瞳には期待と楽しさが宿っている。しかし、その提案に奏は一瞬躊躇した。カラオケ――声を出すこと。それは奏にとって憧れであり、同時に恐れでもあった。人前で歌うことなど考えただけでも身震いする。
「う、うん……行けたら行く」
曖昧な返事しかできなかった。その言葉には、自分でも隠しきれない不安が滲んでいた。行きたい。でも怖い。その二つの感情が彼女の中で激しくぶつかり合い、自分自身を混乱させていた。
その様子を空がじっと見つめていた。その瞳には、奏の心の奥底まで見透かすような鋭さがあるように感じられる。それに気づいた瞬間、奏は居心地の悪さを覚えた。
「僕も行くよ。楽しそうだし」
空が静かに言った。その言葉には特別な感情は込められていないようだったが、それでも茉莉は嬉しそうに笑った。その笑顔を見ると、奏の胸に小さな痛みが走る。
(私もあんな風に素直に笑えたらいいのに)
昼食が終わり、三人は教室へ戻るため階段を降り始めた。その間も微妙な沈黙が続いていた。茉莉との距離感、空への複雑な感情、自分自身の夢への葛藤――それら全てが絡み合い、奏の心を重くしている。
空は何も言わずに奏の隣を歩いていた。その沈黙は心地よくもあり、不安でもあった。ただ一緒に歩いているだけなのに、その存在感が大きすぎて息苦しくなる。
(どうしてこんなにも苦しいんだろう)
奏は自問自答した。しかし、その答えはまだ見つからない。ただ、このままではいけないということだけは分かっていた。それでも、一歩踏み出す勇気が湧いてこない自分自身にもどかしさを覚える。
教室へ戻ると茉莉はすぐ他のクラスメイトと話し始めた。その姿を見ると、自分だけ取り残されているような気持ちになる。奏は自分の席へ戻りながら窓際へ目線を移した。冬の日差しは弱々しく、それでも窓ガラス越しに冷たい光を落としている。
外を見ると灰色の曇り空が広がっていた。その空模様はまるで今の自分自身――晴れることなく曇り続ける心そのものだった。
授業開始を告げるチャイムが鳴り響き、生徒たちはそれぞれ席についた。先生の声だけが教室内に響いている。しかし奏にはその声すら遠く感じられる。教科書を開きながらも上の空だった。頭の中では茉莉との会話や空から向けられる視線、自分自身への問いかけ――それら全てがぐるぐると渦巻いていた。
(いつか、この苦しみから解放される日なんて来るんだろうか)
そんな思いだけが胸中に漂う。それでも授業中という状況下ではその感情さえ押し殺さざる得なかった。ただ静かに深呼吸することで自分自身をごまかすしか方法はなかった。その息遣いすらどこまでも冷たく重かった。
放課後になり校舎内から生徒達姿消える頃…再び屋上戻り一人静寂味わう事しか出来無かった。
冬の冷たい風が、奏の頬を刺すように吹き抜けていった。夜の帳が降り始めた空は、深い群青色に染まり、遠くの山々の輪郭をぼんやりと浮かび上がらせている。奏はマフラーをぎゅっと首元に押し当てながら、目の前に広がる風景に足を止めた。
「ここだよ」
隣を歩いていた八神空が、静かにそう言った。彼の声は冷えた空気に溶け込むようで、まるでこの場所自体が空の声に応えるかのようだった。奏が顔を上げると、そこには古びた天文台が佇んでいた。雪化粧をまとったその姿は、どこか幻想的で、現実から切り離された異世界のようだった。
「これ…使われてないよね?」
奏は少し不安そうに尋ねた。天文台の壁にはひび割れが走り、ところどころ塗装が剥げ落ちている。それでも、その姿には不思議な威厳があった。かつてここで星々を見上げ、人々が何を考えていたのだろうと想像すると、胸の奥が少しだけ温かくなる。
「大丈夫、崩れたりしないから」
空は微笑みながら答えた。その笑顔には、不思議と安心感があった。奏は小さく頷き、空についていくことにした。
二人は慎重に階段を上っていった。一段一段踏みしめるごとに、古びた木材が軋む音を立てる。その音が静寂を切り裂き、奏の心臓の鼓動をさらに高めた。冷たい手すりに触れる指先から、冬の冷気がじんわりと伝わってくる。
「怖い?」
空が振り返って尋ねた。その瞳には優しさと少しの茶目っ気が混じっている。
「別に…大丈夫」
そう答えながらも、奏の声は少し震えていた。しかし、その震えには恐怖だけではなく、小さな期待も混じっていた。この場所で何か特別なものを見ることができるかもしれないという期待感。それは、自分でも気づかないうちに胸の奥で膨らんでいた。
天文台の屋上に辿り着くと、奏は思わず息を呑んだ。目の前には広大な夜空が広がっていた。街明かりから遠く離れたこの場所では、星々がまるで手を伸ばせば届きそうなほど近く感じられる。その輝きは寒ささえ忘れさせるほど美しく、言葉では表現できないほどだった。
「すごい…」
奏は無意識にそう呟いていた。その声は白い息となって夜空へ溶けていく。
「きれいだろ?」
空が隣で言った。その声もまた静かで、この場所にぴったりと馴染んでいた。二人は屋上の端に腰を下ろした。コンクリート越しにも冷気が伝わってくるが、それでもこの景色を前にすると寒さなどどうでもよく思えた。
足元には街の灯りが小さく瞬いている。そして頭上には無数の星々。それらすべてが、この一瞬だけ二人だけのものになったような気がした。
「ねえ、奏」
空が静かに口を開いた。その声にはいつもの軽やかさとは違う真剣さが滲んでいる。
「君は、本当にやりたいことってある?」
その問いに、奏は戸惑った。本当にやりたいこと。それは彼女自身もずっと心の奥底に封印してきた言葉だった。この問いを投げかけられること自体、自分には許されないと思っていた。
「私は…」
言葉に詰まる奏。その視線は膝元へ落ち、その手はぎゅっと握られている。その様子を見て、空は優しく微笑んだ。
「無理に答えなくていいよ。でもね、自分らしく生きることって、とても大切なんだ」
その言葉はまっすぐで、それでいて柔らかかった。その一言一言が、凍てついた冬空から降り注ぐ雪のように静かに奏の心へ降り積もっていく。
「僕ね、昔は周りの期待ばっかり気にしてたんだ。でも、それじゃ本当の自分なんてどこにもなくなっちゃう」
空の声にはどこか寂しさと決意が混じっていた。その言葉には重みがあった。彼自身もまた、自分と戦いながらここまで来たということを感じさせるものだった。
「だから今は、自分の心に正直になろうとしてる。たとえそれが周りからどう見えるとしてもね」
その言葉に、奏の胸の奥で何かが揺れ動いた。自分らしく生きる。それは彼女自身ずっと避けてきたテーマだった。でも、この瞬間、その意味について考えずにはいられなかった。
夜が深まるにつれ、星々はさらに輝きを増していった。冬特有の澄んだ空気のおかげで、一つ一つの星が際立って見える。その光景を見つめながら、奏は自分自身と向き合おうとしていた。
「ねえ、空」
奏は小さな声で呼びかけた。その声には微かな震えと決意が混じっていた。
「私ね、本当は…声優になりたい」
その言葉を口にした瞬間、自分でも驚くほど胸が軽くなった。それまで誰にも言えなかった夢。それを初めて誰かに伝えることができた喜びと解放感。そして、それ以上に、その夢を口にすることで自分自身を認められたような気持ちになった。
空は優しく微笑んだ。その笑顔には何も否定するものなどなく、ただ純粋な応援だけが込められていた。
「素敵な夢だね。その夢、大切にしてほしい。一歩ずつでいいから進んでいけばいい」
その言葉に、奏の目から涙がこぼれ落ちた。それまで押し殺してきた思い、それまで隠してきた自分自身。それら全てが溢れ出すようだった。
「でも…親には絶対反対されると思う」
涙声でそう呟く奏。その肩越しから見える星々もまた揺れているようだった。しかし空は穏やかな声で続けた。
「大丈夫。一気に変える必要なんてないよ。少しずつ、自分の思いを伝えていけばいいんだ」
その一言一言が暖かな灯火となり、凍えていた奏の心をそっと温めていった。この夜、この天文台という特別な場所で交わされた会話。それは彼女自身にとって、新しい一歩への扉となった。
星降る天文台――その夜空には無数の星々だけではなく、小さな希望という名の光もまた輝いていた。そして、その光こそ奏自身への贈り物だった。
冬の夜空が、再び奏と空を包み込んだ。前回訪れた時よりも寒さが増し、二人の吐く息は白く凍りついて消えていく。それでも、奏の心は温かさに満ちていた。前回の訪問で、自分の夢を初めて口にした解放感が、まだ胸の中で余韻を残していたからだ。
天文台の階段を上りながら、奏は空の横顔をちらりと見た。その姿は、まるで星空に溶け込んでいくかのようだった。
屋上に辿り着くと、二人は無言で夜空を見上げた。星々は前回よりも輝きを増しているように見えた。しばらくの沈黙の後、奏は勇気を出して口を開いた。
「ねえ、空」
「うん?」
「空の夢は何?やっぱり俳優?」
空は少し驚いたような表情を見せたが、すぐに柔らかな笑みを浮かべた。
「天文学者だよ」
「天文学者?」
奏の声には驚きが滲んでいた。空は夜空を見上げながら、静かに語り始めた。
「星が好きなんだ。今見えている星の光は、実は何年、何十年、何万年と昔の光なんだよ」
「へえ……」
奏は思わず感嘆の声を上げた。空の言葉に、夜空がより神秘的に見えてきた。
「だから、もしかしたら今見えているこの光を放つ星は、もうその場所にはいないかもしれないし……消えてなくなっているかもしれない」
その言葉に、奏はドキッとした。何か重要なことを聞いているような気がした。
「消えて……なくなる」
奏の声は震えていた。それは寒さのせいだけではなかった。
「星の生命の終わりだね」空は静かに続けた。「でも、死んでなお、輝きを届けるって素敵だよね」
その言葉に、奏は深く考え込んだ。星の一生。そして、その死後も続く輝き。それは何か、人生について大切なことを教えてくれているような気がした。
しばらくの沈黙の後、空が突然奏に向き直った。
「ねえ、奏。僕と一緒に声優のレッスンをしないか?」
「え?」奏は驚いて目を丸くした。「どこで?」
「この天文台で」
空の提案に、奏は戸惑いを覚えた。しかし、同時に心の奥で小さな希望の火が灯るのを感じた。
「でも、こんな場所で……」
「大丈夫だよ。ここなら誰にも邪魔されないし、星空を見ながらの練習は、きっと特別なものになるはずだ」
空の言葉には確信があった。奏は迷いながらも、少しずつその提案に心が傾いていくのを感じた。
「わかった。やってみる」
その言葉を口にした瞬間、奏の中で何かが変わった気がした。これが、自分の夢に向かっての第一歩なのだと。
それから毎晩、奏と空は天文台で会うようになった。奏の母親には「茉莉のところで一緒に勉強する」と伝えてある。茉莉にお願いして、口裏を合わせてもらったのだ。
茉莉に相談した時、彼女は複雑そうな表情を浮かべた。しかし、最後には「いいよ」と言ってくれた。その言葉の裏に隠された思いを、奏は感じ取っていた。でも、今はこの機会を逃したくなかった。
天文台での練習は、奏にとって特別なものだった。星空を見上げながら、様々な感情を込めて声を出す。時には笑い、時には泣き、時には怒る。その度に、星々が奏の感情に呼応するかのように輝きを変えるように感じられた。
空は優しく、時に厳しく奏を指導した。その姿は、まるでプロの声優のようだった。
「もっと感情を込めて。星々に届くくらいの声で」
そんな空の言葉に励まされ、奏は少しずつ成長していった。
ある夜、練習を終えた後、二人は星空を見上げながら話をしていた。
「ねえ、空」
「うん?」
「私、少しずつだけど、自分の声に自信が持てるようになってきたの」
空は優しく微笑んだ。
「それは良かった。君の声は、きっと星々にも届いているよ」
その言葉に、奏は胸が熱くなるのを感じた。
「でも、まだ親には言い出せない」
「大丈夫。焦る必要はないんだ。星の光が地球に届くまでに、何年もかかることだってあるんだから」
空の言葉に、奏は少し安心した。そう、焦る必要はない。自分のペースで、少しずつ前に進めばいい。
星空の下、二人の姿は小さく見えた。しかし、その心の中には大きな夢が広がっていた。奏は、これからも空と一緒に、この特別な場所で練習を続けていくのだろう。そして、いつかきっと自分の声で、多くの人々の心に届く日が来ることを信じていた。
天文台は、奏にとって単なる練習場所ではなくなっていた。それは、夢への扉であり、自分自身と向き合う場所。そして何より、大切な人と共に過ごす、かけがえのない時間を紡ぐ場所になっていたのだ。
冬の夜空は、まるで黒いビロードのカーテンに無数のダイヤモンドを散りばめたかのように輝いていた。奏と空は、古びた天文台の屋上に腰を下ろし、息を呑むような美しさの星空を見上げていた。冷たい風が二人の頬を撫でていったが、それでも二人の心は温かさに満ちていた。
空が静かに口を開いた。「ねえ、奏。冬の星座って知ってる?」
奏は首を横に振った。「あまり詳しくないの」
空は優しく微笑んだ。その笑顔は、星明かりに照らされてより柔らかく見えた。「じゃあ、教えてあげるね」
空は右手を伸ばし、夜空の一点を指さした。「あそこに見える明るい星が3つ並んでいるのが分かる?あれがオリオン座の三つ星だよ」
奏は目を凝らして空の指す方向を見つめた。確かに、3つの明るい星が一直線に並んでいるのが見えた。「わぁ、本当だ」
空は続けた。「オリオン座は冬の代表的な星座なんだ。ギリシャ神話の狩人オリオンをかたどっているんだよ」
奏は空の言葉に聞き入りながら、星々を見つめていた。空の声は、静かな夜空に溶け込むように柔らかく、でも確かな情熱を秘めていた。
「そして、オリオン座の左上にある明るい星。あれがシリウスっていう星なんだ。全天で一番明るい恒星なんだよ」
奏はその星を見つけ、その輝きの美しさに息を呑んだ。「すごく綺麗...」
空は嬉しそうに頷いた。「そうだね。シリウスは『大犬座』の主星なんだ。オリオンの忠実な猟犬を表しているんだよ」
奏は空の解説に聞き入りながら、ふと疑問が湧いてきた。空がこんなにも星のことを熱心に語る姿を見て、ある違和感を覚えたのだ。
「ねえ、空」奏は少し躊躇いながら口を開いた。「空はなぜ、みんなの前で自己紹介をするときに星が好きだって言わなかったの?」
空は少し驚いたような表情を見せたが、すぐに柔らかな笑みを浮かべた。その瞳には、星空が映り込んでいるようだった。
「それはね...」空は少し言葉を選ぶように間を置いた。「本当に好きなものは、大事な人とだけ共有したいから」
その言葉に、奏は胸が高鳴るのを感じた。自分が空にとって「大事な人」なのだと知った喜びと、同時に何か切ない感情が胸の中で渦巻いた。
空は続けた。「星のことを語るのは、僕にとってとても特別なことなんだ。だから、本当に大切な人と、こうして静かな夜に二人きりで共有したかったんだ」
奏は言葉を失った。空の言葉の一つ一つが、冬の夜空の星のように、彼女の心に深く刻まれていくのを感じた。
「それに」空は少し照れくさそうに言った。「君と一緒に星を見ながら話すのが、すごく楽しいんだ」
奏は顔が熱くなるのを感じた。寒い冬の夜なのに、頬が火照るのが分かった。「私も...すごく楽しい」
二人は再び夜空を見上げた。星々は以前よりも明るく、近くに感じられた。奏は、この瞬間を永遠に記憶に留めておきたいと思った。
空が再び星座の解説を始めた。「あそこに見える、W字型の星の並びが『カシオペア座』だよ」
奏はその形を見つけ、小さく歓声を上げた。「本当だ!Wの形に見える!」
空は嬉しそうに頷いた。「ギリシャ神話に出てくる美しい王妃をかたどった星座なんだ」
奏は空の横顔を見つめた。星空を語る時の空の表情は、いつもより生き生きとしていて、目が輝いていた。その姿に、奏は心を奪われていた。
「ねえ、空」奏は小さな声で呼びかけた。「私も、もっと星のことを知りたいな」
空は優しく微笑んだ。「うん、一緒に勉強しよう。星のこと、宇宙のこと、もっともっと」
その言葉に、奏は心が温かくなるのを感じた。二人で共に学び、成長していく。その未来が、とても眩しく感じられた。
夜が更けていく中、二人は星座や星の話に夢中になった。時折吹く冷たい風も、二人の間に芽生えた温かな感情を冷ますことはできなかった。
奏は、この天文台での時間が、自分にとってかけがえのないものになっていることを実感していた。声優の練習だけでなく、空との対話、そして星空との出会い。全てが彼女を少しずつ変えていっているような気がした。
「ありがとう、空」奏は心からの感謝を込めて言った。
空は少し驚いたような顔をしたが、すぐに優しい笑顔を見せた。「何のお礼?」
「こんな素敵な世界を見せてくれて」奏は星空を指さしながら言った。「そして、私だけに教えてくれて」
空は照れくさそうに頭をかいた。「僕こそ、君と一緒にこの景色を見られて幸せだよ」
二人は再び夜空を見上げた。無数の星が、まるで二人を祝福するかのように輝いていた。奏は、この瞬間が永遠に続けばいいのにと思った。
しかし、現実の時間は容赦なく過ぎていく。やがて帰る時間が近づいてきた。
「そろそろ帰らないと」空が静かに言った。
奏は少し寂しそうに頷いた。「うん...」
二人は立ち上がり、最後にもう一度夜空を見上げた。
「また明日も来るよね?」奏が期待を込めて尋ねた。
空は微笑んで頷いた。「もちろん。君と一緒に星を見るのが、毎日の楽しみになってるから」
その言葉に、奏の心は喜びで満たされた。明日への期待が、彼女の中で大きく膨らんでいった。
天文台を後にする二人の背中に、星々は優しく光を投げかけていた。それは、まるで二人の未来を照らす道標のようだった。
奏は空を見上げ、小さくつぶやいた。「明日も、素敵な星空が見られますように」
冬の陽光が教室の窓から差し込み、奏の机の上で淡い光の模様を作っていた。昼休みを告げるチャイムが鳴り、クラスメイトたちが賑やかに立ち上がる中、奏はゆっくりと弁当箱を取り出した。その瞬間、茉莉が軽やかな足取りで近づいてきた。
「ねえ、奏。今日も屋上で食べる?」茉莉の声には、いつもの明るさがあった。
奏は小さく頷いた。「うん、そうしよう」
二人が教室を出ようとしたとき、空が静かに近づいてきた。彼は特に何も言わず、ただ二人についてくるだけだった。この三人で屋上で昼食を取るのは、最近では珍しくないことになっていた。
階段を上がりながら、奏は空の後ろ姿を見つめていた。学校では、空は特別奏と親しげにすることはなかった。それでも、この昼食の時間だけは一緒に過ごす。その関係が、奏の心に微妙な揺らぎを与えていた。
屋上に出ると、冷たい風が三人を迎えた。空は高い柵に寄りかかり、遠くを見つめている。茉莉は明るく話しかけながら、弁当箱を開いた。奏は二人の間に座り、静かに箸を取った。
しばらくの間、三人は穏やかな空気の中で食事を楽しんでいた。遠くから聞こえる運動場の声や、時折吹く風の音だけが、この静寂を彩っていた。
突然、茉莉が奏に向かって尋ねた。「ねえ、奏。空くんとの仲、どうなの?」
その質問に、奏は一瞬息を飲んだ。箸を持つ手が微かに震える。「え?どういうこと?」
茉莉は少し首を傾げ、「だって、毎晩空くんと二人で会ってるじゃん。実際何してんの?」と、興味深そうに尋ねた。
奏は言葉に詰まった。確かに、天文台での夜の時間は特別なものだった。しかし、それをどう表現すればいいのか。自分でも、空との関係をどう定義すればいいのか分からなかった。
「別に...何もないよ」奏は曖昧に答えた。その声には、自分でも気づかない戸惑いが混じっていた。
茉莉はさらに追及するように、「でも、なんだか二人の間に秘密があるみたいじゃない?」と言った。
その言葉に、奏は心臓が高鳴るのを感じた。確かに秘密はあった。でも、それは声優の練習のことだけではない。星空の下で交わした言葉、共有した時間。それらは全て、奏の心の奥深くにしまわれた大切な宝物だった。
「そんなことないよ」奏は微かに頬を赤らめながら答えた。「ただの...友達だよ」
その言葉を口にした瞬間、奏は自分の心の中で何かが引っかかるのを感じた。「友達」という言葉で表現できるほど単純なものではない。でも、かといって他の言葉で表現することもできない。
空は、この会話の間ずっと黙って遠くを見つめていた。時折、奏の方をちらりと見る。その視線に気づくたびに、奏の心はさらに混乱した。
茉莉は、まだ納得していない様子だったが、それ以上は追及しなかった。「そっか。でも、何かあったら教えてね」
奏は小さく頷いた。胸の中では、言葉にできない感情が渦巻いていた。
昼食が終わり、三人は教室に戻る。階段を降りながら、奏は自分の気持ちを整理しようとしていた。空との関係。それは友情なのか、それとも別の何かなのか。答えが見つからないまま、奏の心は揺れ続けていた。
教室に戻ると、空はいつものように自分の席に座り、周りのクラスメイトと普通に会話を始めた。その姿を見て、奏は少し寂しさを感じた。学校では、空は特別奏と親しくしているわけではない。それなのに、なぜ夜の天文台では違うのか。
授業が始まり、奏は教科書を開いた。しかし、頭の中は空のことでいっぱいだった。黒板の文字も、先生の声も、どこか遠くに聞こえる。
窓の外を見ると、冬の空が広がっていた。その青さが、天文台で見た夜空を思い出させる。星々の輝き、空の優しい声、共に過ごした時間。それらの記憶が、奏の心を温かく包み込む。
(私と空の関係って、なんなんだろう)
その問いは、授業が終わっても、放課後になっても、奏の心から離れなかった。
帰り道、奏は一人で歩いていた。いつもなら茉莉と一緒なのに、今日は何となく一人になりたかった。冷たい風が頬を撫でていく。その感触が、天文台での夜を思い出させる。
空を見上げると、まだ薄明るい空に、かすかに星が見え始めていた。その光が、奏の心に小さな希望を灯す。
(きっと、いつかわかるはず)
そう思いながら、奏は家路を急いだ。今夜も、天文台で空と会う約束がある。その時間が、少しずつ自分の中の答えを導いてくれるかもしれない。
家に着くと、奏は急いで部屋に向かった。鏡の前に立ち、自分の姿を見つめる。そこには、少しずつ変わりつつある自分の姿があった。声優になりたいという夢。空との特別な時間。それらが、奏を少しずつ、でも確実に変えていっているのを感じた。
夜になり、奏は再び家を出た。母には茉莉と勉強すると伝えてある。その嘘が胸に引っかかるが、今はそれしか方法がない。
天文台に向かう道すがら、奏は自分の気持ちと向き合おうとしていた。空との関係。それは単なる友情ではない。でも、恋とも違う。それは、お互いの夢を共有し、支え合う特別な絆。
天文台が見えてきた。そこに立つ空の姿が、奏の心を高鳴らせる。
「やあ、奏」空の声が、夜の静けさを優しく破る。
「うん」奏は小さく返事をした。
二人は並んで星空を見上げる。その瞬間、奏は思った。この関係に名前をつける必要はないのかもしれない。ただ、こうして一緒にいられることが大切なんだと。
星々が、二人の上で静かに輝いていた。その光は、奏の心の中にある答えを、少しずつ照らし出しているようだった。
冬の夜空が、天文台の屋上を優しく包み込んでいた。星々の輝きは、まるで奏と空の会話を見守るかのように、静かに瞬いていた。二人は肩を寄せ合い、冷たい風を感じながら、互いの吐く息が白く凍りつくのを眺めていた。
空が静かに口を開いた。「奏は何で声優になりたいの?」
その質問に、奏は少し驚いたような表情を見せた。しかし、すぐに柔らかな微笑みを浮かべ、遠い記憶を辿るように目を細めた。
「小さいころに音読をしていて楽しいって思ったんだ。あと……」奏は少し言葉を詰まらせた。「私一人っ子だったから、一人で人形遊びしていて。人形は何人もいるけど、全部演じるのは自分だったの。演じ分けるって楽しいなってその時思って、それで」
奏の言葉には、懐かしさと同時に、どこか切なさも混じっていた。幼い頃の純粋な喜びと、それを今まで誰にも打ち明けられなかった寂しさが、その声に滲んでいた。
空は静かに頷いた。「そうか」
その言葉には、奏の思いを全て受け止めるような温かさがあった。
しばらくの沈黙の後、空が再び口を開いた。「ご両親にはまだ話せない?」
その問いに、奏の表情が曇った。両親の顔を思い浮かべると、胸が締め付けられるような感覚に襲われた。声優のことを気持ち悪いと吐き捨てた記憶が、鮮明によみがえる。
「だって……」奏は言葉を選びながら、ゆっくりと続けた。「言える……雰囲気じゃないよ」
その言葉の裏には、言い尽くせない思いが隠されていた。小学生の頃、ケーキ屋さんの前でケーキ職人になりたいと言ったときの記憶が蘇る。母親の冷たい声が、今でも耳に残っていた。「あんなの、勉強に失敗した人がやる仕事よ」
その言葉が、奏の心に深い傷を残していた。夢を語ることさえ許されない環境。それが、奏の心を縛り付けていたのだ。
空はそっと奏の肩に手を置いた。「そっか……」それ以上は何も言わなかったが、その沈黙には深い理解が込められていた。
しばらくの間、二人は無言で星空を見上げていた。やがて空が、いつものように星の解説を始めた。その声は、奏の心を少しずつ和ませていった。
解説が終わると、空が突然奏の名を呼んだ。「奏」
「何?」奏は少し驚いて空を見た。
空の目には、真剣な光が宿っていた。「奏はね、すごく魅力的な人だよ。わかってる?」
その言葉に、奏は思わず目を逸らした。「そんなこと……」
「あるよ」空の声は、揺るぎない確信に満ちていた。
奏は小さく首を振った。「空に比べたらたいしたことないよ」
空はそっと奏の顔を覗き込むように身を寄せた。「じゃあ、それでいい。君が認めてくれる八神空が認めた桐島奏はすごい人だよ。僕が証明する」
その言葉に、奏は思わず顔を赤らめた。「突然何? 変だよ、空」
しかし、その言葉とは裏腹に、奏の心の中で何かが温かく広がっていくのを感じた。
空は真剣な眼差しで奏を見つめ続けた。「奏、自分らしく生きて」
「え」奏は、その言葉の重みに息を呑んだ。
「自信をもって。不安になったときは、僕が傍にいるから」
空の言葉は、冬の夜空に響く鐘の音のように、奏の心に深く刻まれていった。それは、これまで誰からも言われたことのない、温かく、力強い言葉だった。
奏は、目に涙が浮かぶのを感じた。それは悲しみの涙ではなく、長い間押し殺してきた自分自身を、やっと解放できたような喜びの涙だった。
「ありがとう、空」奏はかすれた声で言った。
空は優しく微笑んだ。その笑顔は、まるで夜空に輝く一番星のように、奏の心を照らしていた。
二人は再び星空を見上げた。無数の星々が、まるで二人の未来を祝福するかのように輝いていた。奏は深く息を吸い込んだ。冷たい夜気が肺に染み渡る。しかし、今はその冷たささえも、新しい始まりを告げるものに感じられた。
「空」奏は小さな声で呼びかけた。
「うん?」
「私、頑張る。自分の夢に向かって、一歩ずつでも進んでいく」
空は静かに頷いた。「うん、一緒に頑張ろう」
その言葉に、奏は心の中で固く誓った。たとえ周りの理解が得られなくても、自分の道を歩んでいこうと。そして、いつか必ず、自分の声で多くの人々の心に届けられる日が来ることを。
天文台を後にする二人の背中に、星々は優しく光を投げかけていた。それは、まるで二人の未来を照らす道標のようだった。奏は空を見上げ、小さくつぶやいた。
「これからも、こんな素敵な星空が見られますように」
その願いは、きっと星々に届いたに違いない。そして、その星々の光は、奏の心の中に灯された小さな希望の炎を、優しく包み込んでいた。
冬の朝の冷たい空気が、奏の頬を刺すように撫でていった。息を吐くたびに白い霧が立ち昇り、すぐに消えていく。学校への道すがら、奏の足取りは普段よりも少し速かった。心の中で、空との再会を期待していたからだ。
教室に入ると、奏の目は自然と空の席を探していた。しかし、そこには空の姿はなかった。机の上には誰の荷物も置かれておらず、椅子は整然と机の下に収まったままだった。奏の胸に、小さな不安が芽生える。
「八神くんは風邪で休みです」
担任の先生の言葉が、教室に響いた瞬間、奏の心に落胆が広がった。風邪。たった二文字の言葉が、奏の胸に重くのしかかる。それは単なる病気の名前以上の意味を持っていた。空との大切な時間が、一時的にせよ奪われてしまったのだ。
窓の外では、灰色の空が広がっていた。細かな雪が、静かに舞い落ちている。その光景が、奏の心の中の寂しさを映し出しているかのようだった。雪の結晶一つ一つが、空との思い出のかけらのように感じられた。
(空、大丈夫かな...)
その思いが、奏の心を占めていた。授業中も、奏の心はどこか上の空だった。黒板に書かれる文字も、先生の声も、どこか遠くに聞こえる。まるで水中にいるかのような感覚だった。頭の中は、空のことでいっぱいだった。
昼休み、いつもの屋上での食事。しかし、空がいない今、その場所は妙に広く、寒々しく感じられた。いつもは三人で分け合っていた空間が、今は二人きりになってしまった。風が吹くたびに、奏は身を縮めた。それは寒さからだけではなく、空の不在が作り出す心の隙間を埋めようとする無意識の動きだった。
茉莉が明るく話しかけてくるが、奏の返事は上の空だった。言葉の意味は理解しているのに、それに対する適切な反応ができない。まるで、自分の心と体が別々に動いているかのようだった。
「奏、大丈夫?」茉莉の声に、奏は我に返った。その声には、心配と優しさが混ざっていた。
「ごめん、ちょっと考え事してて」奏は小さく微笑んだが、その笑顔は心からのものではなかった。
茉莉は心配そうな目で奏を見つめた。「空くんのこと?」
その言葉に、奏は思わず顔を上げた。自分の気持ちがそんなに簡単に読み取られてしまったことに、少し戸惑いを覚える。同時に、自分の感情があまりにも表に出ていることに気づき、頬が熱くなるのを感じた。
「うん...ちょっと心配で」奏は小さな声で答えた。その声には、隠しきれない不安が滲んでいた。
茉莉は優しく微笑んだ。「きっと大丈夫だよ。ただの風邪なんでしょ?」
奏は小さく頷いた。しかし、心の中では別の思いが渦巻いていた。
(私のせいかもしれない...)
その思いが、奏の心を重く圧迫する。毎晩、寒い夜に天文台で過ごしていたこと。空が自分の練習に付き合ってくれていたこと。それらの記憶が、奏の心を重くしていく。自分の夢のために、大切な人を犠牲にしてしまったのではないか。その罪悪感が、奏の心を蝕んでいった。
放課後、奏は決心した。空の家に行こう。お見舞いに。その決断には、心配だけでなく、自分の気持ちを確かめたいという思いも込められていた。
しかし、すぐに壁にぶつかった。空の家がわからないのだ。その事実に気づいた瞬間、奏は自分がいかに空のことを知らないかを痛感した。
「ねえ、空……八神くんの家知ってる?」
クラスメイトに聞いても、誰も知らないという。その度に、奏の心は沈んでいく。まるで、空という人物が幻だったかのような不安さえ感じ始めた。
(私、空のこと何も知らないんだ...)
その気づきが、奏の胸を締め付けた。毎晩一緒に過ごし、大切な時間を共有してきたはずなのに。空は奏のことをよく知っているのに、奏は空のことを何も知らない。その不均衡さに、奏は深い後悔を覚えた。
夕暮れ時、奏は一人で帰路についた。街路樹の影が長く伸び、その先端が奏の足元をかすめていく。その影は、奏の心の中の不安の影のようにも見えた。空を見上げると、まだ薄明るい空に、かすかに星が見え始めていた。その星々が、奏に何かを語りかけているようにも感じられた。
(空、今頃何してるんだろう...)
その思いが、奏の心を占めていた。家に着くと、奏は急いで部屋に向かった。窓から見える夜空は、いつもより寂しく感じられた。天文台での時間を思い出す。空の優しい声、星々の輝き、二人で過ごした特別な時間。それらの記憶が、今は奏を苦しめるものとなっていた。
奏は深いため息をついた。胸の中で、後悔と心配が入り混じる。もっと空のことを知ろうとすべきだった。もっと空に聞くべきことがあった。その思いが、奏の心を重くしていく。
ベッドに横たわり、天井を見つめる。そこには、空との思い出が映し出されているかのようだった。星座の話、声優の練習、そして何より、空が奏に向けてくれた優しい言葉。
「自分らしく生きて」
その言葉が、今も奏の心に響く。しかし同時に、その言葉の重みを感じる。自分らしく生きるとは何なのか。それは他人を犠牲にしてもいいということなのか。そんな疑問が、奏の心を揺さぶる。
(私は、本当に自分らしく生きられているのかな...)
その問いかけが、奏の心の中で繰り返し響く。答えは見つからないまま、奏は眠りについた。
翌朝、奏は早めに家を出た。いつもより少し遠回りをして、空の家があるかもしれない地域を歩いてみる。朝もやの立ち込める街を、奏は必死に探し回った。しかし、どの家も見知らぬ家ばかり。空の姿は見つからない。その事実が、奏の心にさらなる寂しさを植え付けた。
学校に着くと、またしても空の席は空いたままだった。奏の心に、さらなる不安が広がる。その空席が、奏の心の中の空白を象徴しているかのようだった。
授業中、奏は窓の外を見つめていた。冬の陽光が、教室の中に淡い光の模様を作っている。その光が、まるで空からのメッセージのように感じられた。光の粒子一つ一つが、空の言葉を運んでいるかのように。
(空、早く元気になって...)
その祈りが、奏の心の中でずっと繰り返されていた。
放課後、奏は再び天文台に向かった。空がいなくても、ここなら空との繋がりを感じられるような気がした。それは奏にとって、空との約束の場所であり、二人だけの秘密の空間だった。
天文台に着くと、奏は深く息を吸い込んだ。冷たい空気が肺に染み渡る。その冷たさが、奏の心の熱を少し和らげてくれるようだった。星々が、少しずつその姿を現し始めていた。それぞれの星が、空との思い出を象徴しているかのように輝いていた。
奏は静かに声を出した。まるで空に聞かせるかのように。
「空、私ね、あなたのことをもっと知りたいの。だから、早く元気になって戻ってきて」
その言葉が、夜空に吸い込まれていくようだった。星々が、その願いを受け止めてくれたような気がした。奏の心に、小さな希望の灯りが灯った。
奏は再び家路についた。明日は、きっと空が戻ってくる。そう信じながら歩を進める。その信念が、奏の足取りを少し軽くした。
家に着くと、奏は窓辺に立ち、夜空を見上げた。そこには、いつもの星々が輝いていた。その光が、奏の心に小さな希望を灯す。それぞれの星が、空からのメッセージを運んでいるかのように感じられた。
(きっと大丈夫。空は必ず戻ってくる)
そう思いながら、奏は静かに目を閉じた。明日への期待と不安が入り混じる中、奏の心は少しずつ落ち着いていった。空との再会を信じる気持ちが、奏の心を温かく包み込んでいく。
星々の光が、奏の顔を優しく照らしている。それは、まるで空からの励ましのようだった。その光の中に、奏は明日への希望を見出していた。
冬の朝、冷たい風が校庭を吹き抜け、奏の頬を刺すように撫でていった。その冷たさに思わずマフラーを引き寄せながら、奏は学校への道を急いだ。胸には小さな期待が膨らんでいた。今日こそ、空が学校に戻ってきているかもしれない。三日間、空の姿を見ないだけで、こんなにも心がざわつくものなのかと、自分でも驚いていた。
教室の扉を開けると、奏の目は自然と空の席を探した。そして、そこには確かに空が座っていた。三日ぶりに見るその後ろ姿は、どこか頼りなく見えたが、それでもそこに空がいるという事実だけで奏の胸は温かくなった。
「おはよう、八神くん!」
クラスメイトたちが明るく声をかける中、空は軽く手を挙げて応えた。その仕草はいつも通りだったが、奏には何か違和感があった。彼の肩はどこか力なく落ちていて、その顔色も優れないように見えた。
奏は自分の席につきながら、ちらりと空を見やった。彼と目が合うと、空は少し照れくさそうに微笑んだ。その笑顔はいつものように柔らかかったが、その奥に隠された疲労感を奏は見逃さなかった。 昼休みになり、いつものように茉莉と三人で屋上へ向かった。冬の冷たい風が吹き抜ける中、奏は空の隣に座りながら、おそるおそる尋ねた。
「八神くん、大丈夫?まだ顔色がよくないよ」
その言葉に、空は一瞬だけ目を伏せ、それから曖昧な笑みを浮かべた。「大丈夫だよ。ただちょっと寝不足なだけ」
その答えに、奏はさらに不安を覚えた。寝不足というには、その顔色はあまりにも悪すぎた。しかし、それ以上追及することもできず、彼女は小さく頷くだけだった。
弁当を食べながらも、奏の視線は何度も空へ向かった。茉莉が明るい声で話しかけても、空はどこか上の空で、それでも無理に笑顔を作って応じている。その姿を見るたびに、奏の胸には小さな棘が刺さるような痛みが広がっていった。 昼食を終えた後、屋上から教室へ戻る途中で、奏は意を決して言葉を口にした。
「ねえ、空。本当に無理してない?まだ全快していないなら、夜会うのはしばらくやめようか」
その提案には、自分自身への戸惑いも含まれていた。天文台で過ごす時間。それは奏にとって特別なものであり、大切なひとときだった。それでも、それ以上に空の体調が心配だった。
しかし、その言葉を聞いた瞬間、空の表情が一瞬だけ硬くなった。そしてすぐに笑顔を浮かべ、「大丈夫だよ」と力強く答えた。その声には妙な説得力があり、それ以上反論する余地を与えてくれなかった。
「でも...」奏が続けようとすると、空は軽く手を振って遮った。「本当に大丈夫だから。むしろ早く天文台で星を見たいよ」
その言葉には確信めいたものがあった。しかし、その頑なな態度にはどこか違和感も感じられた。それでも奏はそれ以上何も言えず、小さく頷くだけだった。 夜になり、冷たい風が街路樹の枝を揺らしていた。月明かりが雪道を淡く照らし、その光景はどこか幻想的だった。奏はマフラーを巻き直しながら天文台へ向かった。
(本当に大丈夫なのかな...)
歩きながらも、その思いが頭から離れなかった。昼間の空の様子。その曖昧な笑顔。その頑なな態度。それら全てが心配となって胸に残っていた。しかし、それでも天文台へ向かわずにはいられなかった。あの場所で過ごす時間。それは彼女にとって欠かせないものになっていた。
天文台に着くと、そこにはすでに空の姿があった。彼は柵にもたれかかりながら夜空を見上げていた。その背中にはいつもの余裕や落ち着きではなく、一抹の疲労感が漂っているようにも見えた。
「遅かったね」振り返った空は柔らかな笑みを浮かべた。その笑顔を見るだけで、奏の胸には安堵感と同時に新たな不安が広がった。
「ごめんね。でも、本当に大丈夫なの?」奏は思わず問い詰めるような口調になった。
「大丈夫だよ」空は軽く肩をすくめて答えた。「星を見る時間を減らすなんて考えられないからね」
その言葉には確かに情熱が込められていた。しかし、その情熱の裏側には何か無理をしているようにも感じられた。それでも奏はそれ以上何も言えず、小さく頷くだけだった。 二人で並んで星空を見上げる。その光景はいつも通り美しく、それだけで心が満たされるようだった。しかし、その美しさとは裏腹に、奏の胸には妙な重さが残っていた。
「今日も星座教えてよ」奏がそう促すと、空は少し考える素振りを見せ、それから夜空を指差した。「あそこに見える五角形。それが『ぎょしゃ座』だよ」
「ぎょしゃ座?」奏は初めて聞く名前に興味津々だった。
「そう。馬車使いという意味なんだ。この五角形の中でもひときわ明るい星、『カペラ』っていうんだよ。この星座全体では王様エリクトニウスという人物ともされていてね」
「王様...?」奏の目には驚きと好奇心が混じっていた。「そんな星座もあるんだ」
「うん。そしてこのカペラって星ね、人類史上最初期から観測されている星なんだよ」
その説明にはいつもの情熱的な語り口調が戻っていて、一瞬だけ安心した。しかし、その声にも微かな疲労感が混ざっていることに気づいてしまう自分もいた。 夜風が二人の間を吹き抜ける。その冷たい風にも負けず、星々は静かに輝いていた。その光景を見るだけで、不思議と心が落ち着いていく。しかし、その落ち着きとは裏腹に、奏の胸には新たな決意も芽生えていた。
(もっと空のこと知りたい...)
それは単なる好奇心ではなく、大切な人として彼を支えたいという願いから生まれた思いだった。そしてその思いこそ、この夜空よりも深く広いものだということを感じていた。 帰り道、一緒に歩く二人。それぞれ抱える想いとは裏腹に、その光景だけを見る限りでは穏やかなひと時だった。しかし、その穏やかな時間とは裏腹に、それぞれ胸の中では新しい物語への扉が開こうとしていた。
冬の冷たい風が、教室の窓を揺らしていた。外では灰色の空が広がり、時折ちらちらと雪が舞っている。奏は教科書を開きながらも、どこか集中できないでいた。窓の外に目を向けるたびに、心の中に小さなざわめきが広がる。空のことが気になって仕方がなかった。
その時だった。教室の後ろで誰かが「八神くん、大丈夫?」と声を上げた。振り返ると、空が机に突っ伏している姿が目に入った。その肩は小刻みに震えていて、顔は見えないが、その様子から明らかに体調が悪いことが伝わってきた。
「八神くん、大丈夫ですか?」
担任の高橋先生も気づき、急いで駆け寄った。クラスメイトたちの視線が一斉に空に集まる中、奏は胸の奥で何か鋭いものに刺されたような感覚を覚えた。
「保健室へ行きましょう」
先生の言葉に促されて、空はゆっくりと立ち上がった。その顔は蒼白で、いつもの柔らかな笑顔などどこにもなかった。奏はその姿を見つめながら、胸の中で不安が膨らんでいくのを感じていた。 授業が終わり、昼休みになると、担任の先生から声をかけられた。「桐島さん、学級委員として八神くんの様子を見てきてもらえるかな?」
その言葉に、奏は小さく頷いた。理由は学級委員という名目だったが、本当は自分自身も空の様子を知りたかった。それ以上に、彼のそばにいたいという気持ちがあった。
保健室へ向かう廊下は静まり返っていた。冬特有の冷たい空気が漂い、その中を歩く奏の足音だけが響いている。保健室の扉を開けると、中には養護教諭の先生と数枚の白いカーテンだけが目に入った。
「ああ、八神くんなら奥で休んでいますよ」
養護教諭の先生は優しく微笑みながら指差した。その先には、一枚のカーテンで仕切られたベッドがあった。
「ちょっと職員室に行ってくるので、八神くんのこと見ててくれますか?」
「あ、はい」
奏は小さくお辞儀をして、そのカーテンへと近づいた。カーテン越しには何も見えない。ただ、その向こう側には確かに空がいる。その事実だけで、胸の奥からじんわりと温かさと緊張感が広がっていった。 「空...大丈夫かな」
小さな声で呟きながら、奏はカーテン越しに立ち尽くした。彼女は一歩踏み出すべきかどうか迷っていた。その距離はほんの数十センチしかないはずなのに、その一歩が果てしなく遠いものに感じられた。
カーテン越しには微かな寝息だけが聞こえてくる。それは規則正しいものではなく、ときおり途切れるような浅い呼吸だった。それでも、その音だけで空がそこにいることを感じ取ることができた。
(こんなにも近くにいるのに...)
奏は手を伸ばせば触れられる距離にいる空を前にして、不思議な感覚に囚われていた。カーテン一枚隔てただけなのに、その存在はどこか遠い宇宙の向こう側にあるような気持ちになった。その距離感は物理的なものではなく、心と心との間にある見えない壁のようだった。 奏はそっと椅子を引き寄せて座り込んだ。そしてカーテン越しに静かに語りかけるような声で言った。「空、本当に無理してない?」
もちろん返事など返ってこない。彼女もそれを期待していたわけではなかった。ただ、自分自身の心を整理するためにも、この言葉を口にする必要があった。
(どうしてこんなにも無理をするんだろう...)
天文台で過ごした夜々の記憶が頭をよぎる。星座について語る時の情熱的な表情。そしてその裏側には隠しきれない疲労感。それでも無理して笑顔を作り続ける彼。それら全てが今、この保健室という静寂の中で鮮明によみがえってきた。 ふと、カーテン越しから微かな動きが伝わってきた。寝返りでも打ったのだろうか。その音だけで奏の心臓は跳ね上がるようだった。この狭い空間には自分と空しかいない。その事実だけでも胸が高鳴る。
(もっと近づいてもいいんだろうか...)
そんな思いと同時に、自分には踏み込む資格などないという思いも湧き上がる。それでも奏はそっと手を伸ばし、カーテン越しに自分の指先をそっと触れさせた。その布越しから伝わる温度や感覚など何もない。ただ、それでもその行為自体になぜか安心感を覚えた。 その時、不意に養護教諭が戻ってきた。「桐島さん、八神くん大丈夫そうですか?」
その声にはっと我に返った奏は慌てて椅子から立ち上がった。「はい、多分大丈夫だと思います」
養護教諭からのお礼を受けつつ、奏は保健室を後にした。しかし、その足取りにはまだ迷いや不安、それ以上に何とも言えない温かな余韻も残されていた。 教室へ戻る途中、廊下から見える冬の日差しは弱々しく、それでも透明感ある輝きを放っていた。その光景を見るだけで少しだけ心が軽くなる気もした。しかし同時に、自分自身への問いも浮かび上がってきた。
(私は空に支えられて生きているけど、私は空を支えられているんだろうか...)
その問いへの答えはまだ見つからない。それでも、恩返しのために、自分なりのできることを探していこうという決意だけは胸の中で静かに芽生えていた。そしてその決意こそ、この日保健室で感じ取ったものなのだと思えた。 冬の日差しと冷たい風。それら全てが混ざり合うこの季節。その中で奏と空との関係性もまた少しずつ変化していこうとしていた。それはまだ形にならないものだったとしても、それでも確実な何かだった。そしてその何かこそ、この先二人だけしか知らない物語への扉となるものなのだろうと思えた。
冬の冷たい風が、教室の窓を揺らし、微かな震えをもたらしていた。窓ガラスに触れる冷気が、奏の指先にまで届くような気がした。彼女は机に向かいながら、空の席をじっと見つめていた。そこには3日前から誰も座っていない。その空席は、まるで奏の心の中にぽっかりと空いた穴のようだった。
高橋先生から聞かされた「体調不良」という言葉が、奏の耳の中で何度もこだまする。それ以上の情報は得られず、先生も多くを語ろうとはしなかった。ただ、その一言だけで、奏の胸には不安が渦を巻いていた。窓の外では灰色の空が広がり、時折舞い落ちる雪が、奏の心の中にある寂しさを映し出しているようだった。
(空の家、どこにあるんだろう...)
その思いが、胸を締め付ける。自分から聞き出さなかったことを後悔する気持ちが、胸の奥で重くのしかかっていた。下心があるように思われたくない。そんな些細な恐れが、今となっては大きな障壁となっていた。
教室の空気は重く感じられた。クラスメイトたちが談笑する声も、どこか遠くで聞こえているようだった。黒板に書かれた文字もぼんやりとしか見えない。全ての焦点が空の不在に向けられているかのようだった。 放課後、奏は重い足取りで家路についた。街路樹の枝々は雪に覆われ、その白さが夕暮れ時の街を幻想的に彩っていた。しかし、その美しさも奏には空虚に映った。ただ一人、空との思い出が詰まった天文台へと向かう。
天文台に着くと、そこには誰もいなかった。当たり前のことなのに、奏は深い失望感を覚えた。冷たい風が頬を撫で、その冷たさが心の中まで染み渡るようだった。
星空を見上げると、そこにはいつもと変わらない星々が輝いていた。しかし、空がいないその光景はどこか色あせて見えた。星々は変わらずそこにあるという事実だけが、逆に彼女を切なくさせた。
「空、元気かな...」
小さく呟いたその言葉は夜空へ吸い込まれていった。返事など返ってくるはずもない。それでも奏はその静寂に耳を澄ませていた。星々はただ黙って輝いている。それなのに、その光には何か語りかけてくるものがあるような気がした。 家に帰ると、母親が待ち構えていた。その表情からして、良い話ではないことはすぐに分かった。最近返却されたテスト結果を見せながら、「塾に通うべきだ」と言われた瞬間、奏の心臓は跳ね上がった。
「夜に佐藤さんの家で勉強しているんでしょう? なんで成果が出ないの? 実は遊んでいるんじゃないの?」
母親から投げかけられる言葉は鋭く刺さった。その一つ一つが、自分自身への責任感や罪悪感を呼び起こす。
「そんなことないよ……茉莉と一緒に勉強してるから」
「だったらなんで成果が出ないのって聞いているのよ!」
母親の声には苛立ちと失望が混じっていた。その視線から逃れるようにして俯きながらも、奏は自分自身を奮い立たせるように言葉を絞り出した。
「次の試験では平均90点以上を取ります」
その言葉を口にした瞬間、自分でも驚くほど強い決意を感じた。それでも、不安も同時に胸を占めていた。この約束を守れなければどうなるだろう。母親との関係だけでなく、自分自身への信頼も崩れてしまうかもしれない。
母親は少し驚いた表情を浮かべたものの、「それならいいわ」とだけ言って部屋を出て行った。その背中を見送りながら、奏は自分自身への責任感とプレッシャーを感じていた。 夜になり、ベッドに横たわりながら天井を見つめていた。目を閉じれば浮かぶのは空との思い出ばかりだった。星座について語り合った時間。声優になる夢について話したこと。そして何より、「自分らしく生きて」と語りかけてくれたあの日の優しい声。
(空、早く元気になって...)
その祈りだけが胸いっぱいに広がっていた。それでも答えなど得られるわけではなく、不安と期待だけが入り混じったまま眠りについた。 翌朝早く目覚めた奏は、一つ決意したことがあった。少し遠回りしてでも、空の家につながる手掛かりを探そうと思った。朝もや立ち込める街並み。その中で懸命に探し続けても、それらしい場所には辿り着けなかった。ただ歩き続ける足音だけが、自分自身への焦燥感として響いていた。
放課後、奏は図書館へ向かった。母親との約束を守るため、そして空が戻ってきたときに胸を張って会えるように。冷たい風が校舎の窓を叩き、冬の夕暮れが静かに街を包み込んでいく中、奏は重い足取りで図書館の扉を開けた。
中は暖房の効いた温かな空気に満ちていたが、それでも奏の心には冷たいものが残っていた。静寂に包まれた空間には、ページをめくる音や鉛筆が紙を擦る音だけが響いている。奏は窓際の席に座り、カバンからノートと教科書を取り出した。
目の前には解かなければならない問題が並んでいる。しかし、その文字列はどこか遠くにあるように感じられた。頭の中では、空のことばかりが渦巻いている。
(空、今何をしているんだろう...)
その思いが、何度も何度も胸の中で繰り返される。体調不良と聞いてから3日間。彼がどんな状態なのかもわからないまま、ただ時間だけが過ぎていく。その無力感が、奏の心を締め付けていた。
窓の外を見ると、夕焼けが街を赤く染めていた。その光景は美しいはずなのに、奏にはどこか切なく映った。空と一緒に見た星空を思い出す。あの日々の輝きが、今は遠い記憶のように感じられる。
(もっと早く聞いておけばよかった...)
空の家の場所を知らない自分への後悔。あの日、「家どこなの?」と軽く尋ねていれば、今こんなにも悩むことはなかっただろう。しかし、その時はそんなことを聞く勇気もなかった。下心があると思われたらどうしようという小さなプライド。それが今、大きな壁となって自分を苦しめている。
「次の試験では平均90点以上を取ります」という母親との約束。その言葉だけが今、自分を支えているようだった。この約束を守ることで、自分自身に価値を見出せる気がした。そして、それが空との再会への一歩になるような気もしていた。 ノートに目を戻し、問題を解こうとする。しかしペンを握る手は止まり続けた。頭では理解しているはずなのに、心は別の場所にある。それでも奏は必死に集中しようとした。母親との約束だけではない。これは自分自身への挑戦でもあると思ったからだ。
ふと窓越しに夜空を見ると、一番星が輝き始めていた。その光は小さくても力強く、まるで奏に語りかけているようだった。
(頑張らなくちゃ...)
その星の輝きを見つめながら、奏は深呼吸した。そしてペンを握り直し、一つずつ問題に向き合い始めた。その動作はぎこちなくても、一歩ずつ進んでいる感覚があった。 図書館を出る頃には、街はすっかり夜の帳に包まれていた。雪道には街灯の明かりが反射し、淡い光の道筋を作っている。その光景はどこか幻想的で、美しくも儚げだった。
奏は星空を見上げた。そこには無数の星々が瞬いている。その一つ一つに空との思い出が重なるようだった。
(きっと空も、この星空を見ているよね...)
そう思うだけで少しだけ心が温かくなる。同じ星空を見ることで、自分たちが繋がっているような気持ちになれる。それだけでも十分だと思おうとした。 家路につく途中、奏はふと天文台へ足を向けた。そこには誰もいないことなどわかっている。それでも、その場所へ行きたいという衝動に駆られた。
天文台へ続く道は雪で覆われており、その上についた自分の足跡だけが続いていく。その足跡を見るたびに、自分自身の孤独さを感じる。それでもその先には、大切な思い出が詰まった場所がある。それだけで足取りは少し軽くなった。
天文台に着くと、一面に広がる星空が迎えてくれた。その光景はいつも通り美しく、それだけで心が洗われるようだった。しかし、その美しさとは裏腹に、胸には切なさも広がっていた。
「空...早く元気になって戻ってきて」
小さな声で呟いたその言葉は、夜空へ吸い込まれていった。その静寂の中で耳を澄ませても、返事など返ってこない。それでも、その言葉を口にすることで少しだけ心が軽くなった気がした。 家へ帰る途中、奏はふと思った。(もう少し頑張ろう)それは勉強だけではなく、自分自身への励ましでもあった。この冬という厳しい季節を乗り越えるためには、自分自身も強くならなくてはいけない。そう思うことで、小さな希望の光が胸の中に灯った気がした。
家へ着き、自室へ入ると真っ先に窓辺へ向かった。そこから見える夜空には、一番星から広がる無数の星々。その光景を見るだけで、不思議と心が落ち着いていった。
(明日はもっといい日になるよね)
そう自分に言い聞かせながらベッドへ横たわった。そして目を閉じると同時に浮かんできたのは、やっぱり空との思い出だった。その記憶一つ一つが、自分自身への力となっていることを感じながら眠りについた。 この冬という季節。その冷たさや厳しさの中にも、小さな温もりや希望が隠されていること。それら全てを抱えながら、奏の日々は続いていく。そしてその先には必ず、新しい朝、新しい出会い、新しい物語が待っていることを信じながら――。