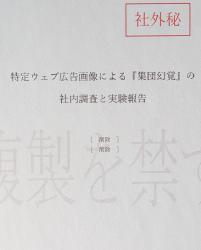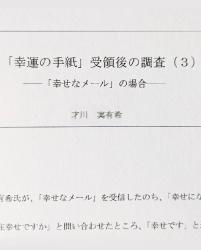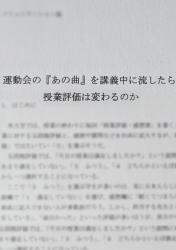わたしとカナミの家族について説明する。
父・高橋カツヒコ(五十代・教員)
母・ユキエ(五十代・飲食店パート)
わたし・ナツミ(三十代・事務)
妹・カナミ(当時十代・学生)
この四人家族である。(※1)
あえて仲がいいと触れ回るような関係性ではないが、「ありふれた」家族関係と言えるだろう。この場合の「ありふれた」とは、楽しいことを共有する場合もあればしない場合もある、家族の振る舞いに苛立ちは覚えるが大きな喧嘩に発展するようなことはない、という程度である。客観的に見れば「仲がいい家族」類に入るだろう。(※2)
子供のころのカナミはやや空想的な部分が多く、いわゆる「ぼーっとしている子」であった。突然走り出すようなことはなく、仮に迷子になったとしてもその場で動かず迎えを待つ子だった。姉であるわたしのほうが落ち着きがなく、両親からすれば妹よりも目を離せない子供だっただろう。(※3)
「カナミは昔からよく笑う子だよね」と母は言う。カナミは泣く、怒るといった感情表現の中でも、笑うことが最も多かった印象である。カナミは以前、「怒りかたがよくわからなくて」と笑っていた。優しい性格なのだ。しかし機嫌が悪いときは、相応に態度も悪くなる。カナミは怒りを覚えると黙り込む性格で、わたしとも対話が困難になる。(※4)
父は教員ではあるが、勉強を強いることはなかった。「(自分自身が)宿題をやらない子供だった」と、わたしたち姉妹がゲームや雑誌ばかりにかまけていても、勉強をするようにと叱られた覚えはない。一方で人に迷惑をかけたり、約束を守らなかったりした場合、当然のことであるが父は怒りをあらわにしていた(※5)
わたしとカナミの年齢差は四歳だ。彼女はわたしの真似をすることが多かった。中学高校も、カナミはわたしと同じ学校(私立■■■■中学高等学校)に入学した。中高一貫校であるため、四歳差でも同じ校舎内で過ごせたのはいい思い出である。(※6)
家族みな心身は健康であり、冬になればインフルエンザにかかることもあったが大病をしたことはない。カナミの怪我も幼い頃のことであり、成長してからは問題なく暮らしていた。親類にも大きな病気を患った者はおらず、あまり病気とは無縁の家系なのかもしれない。(※7)
わたしにとっての妹は、大切な存在である。まれにある両親の喧嘩の際、よく部屋にこもって二人で遊んでいた。カナミはわたしが小学校を卒業したとき、一緒に通学できないことをひどく残念がった。同じ中学に進学したことで再びともに通学できるようになったときは、本当に喜んでいた。休日には二人で衣服を買いに行くこともあれば、映画を見に行くこともしていた。親の知らない話を二人だけで共有し面白がることもあった。カナミもまた姉であるわたしのことを慕ってくれていたのだろう。(※8)
カナミがいなくなってしまったことで、わたしは大きな喪失感と日常の違和感、そして憤りを抱くようになった。何故カナミがいなくならなければならなかったのか。この気持ちは誰にもわかるものではないだろう。わたしはカナミを誰よりも大切に思っていたのだ。カナミがカナミらしく生きているのであれば、そばにいる必要はない。ただ以前と同じように、元気に生きてくれていればいいだけだったのだ。(※9)
次の節ではカナミがいなくなった当日の流れをたどっていく。
※1 二〇■■年現在、三人となった。
※2 二〇■■年現在、破綻している。
※3 最期まで落ち着きはなかった。
※4 姉との対話は困難であった。
※5 父は姉に対し、叱責することを諦めたようだった。
※6 当時学校内において、筆者は姉の奇行により迷惑をこうむっていた。
※7 姉が主な原因で、母は患っている。
※8 現在では考えられない。
※9 筆者は健在である。