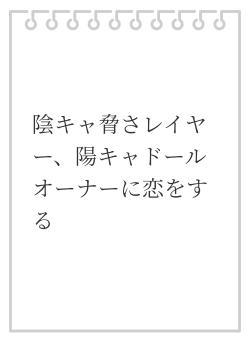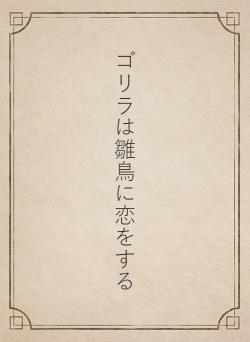横島こころは手に持つ名刺と目の前にある病院の看板を見比べる。「七不市総合病院」と大きな看板。それには様々な診療科目。隅には消えかけた――心霊科。
「本当にあったんだ」
こころはごくりとつばを飲むと病院へ一歩踏み出した。
事の始まりは三日前。こころは今よりマシな会社への転職を考えているがうまくいかない。無職になるわけにも行かず、仕方なく今のブラック企業で働いている。疲労で死にそうになりながらも残業を終え、終電の時間もとっくに過ぎてしまった駅へタクシーを拾いに行った。いつもこの時間はしん、と静まりかえった駅だが今日は珍しくお仲間の社畜が沢山いる。皆死んだ様な目でタクシー乗り場に並んでいる。そんな日もあるだろうとこころは列に加わった。
「貴方はどこへ行くの?」
後ろからどこか興奮したような声が聞こえ、振り向くとやけにわくわくした様子で微笑む白いワンピースとカーデガンのシンプルなコーデの女。あぁ、春だからな。と見て見ぬふりをしたが空気が読めない女は続ける。
「あ、ごめんなさい。生身の人間がこのタクシーに乗ろうなんて仲間なのかなって」
これ以上この女を無視したら面倒だと思ったこころは振り向く。
「家に帰るに決まってるじゃないですか」
目の前の女は予想外の返答なのか豆鉄砲を食らったような顔をして目を見開いていた。
「駄目です。貴方は乗っちゃ……」
女はこころの腕を掴み、列から外そうとする。流石に異常だと思い叫ぶ。
「離してください! 警察呼びますよ!」
ふと気づく。こんな騒ぎだと言うのに周囲の人たちは一切こちらを気にかけない事に。
「だ、誰か!」
こころは叫ぶが列に並ぶ者は来るタクシーに乗っていくだけであった。
「落ち着いて。落ち着いてください」
女は腕を放さない。こころは恐怖の絶頂を迎えた。
「いやぁあああああああ!」
こころは叫ぶだけ叫び、恐怖が去っている事を祈りながら恐る恐る目を開ける。そこはいつもの静まりかえった駅。目の前には空気の読めない女。こころは気づいた。さっき見たものは幽霊。女は困ったようにこちらを見ている。
「残念。皆驚いてタクシー乗り場もろともどこかへ行ってしまいました……。貴女は貴女であんな幽霊の団体さん見ちゃったら怖いですよね。無事でよかった」
幽霊の団体が怖いのではなく、目の前の女が恐ろしくて悲鳴をあげたのだが、結果的に恐ろしいものは見えなくなったので結果オーライであった。こころは今抱えている悩みをこの人ならと、意を決した。
「あ、貴女も幽霊みえる、の?」
「見えますよ」
「生きている人と幽霊の区別もつくの?」
「勿論ですよ」
「わ、私を、助けて……もう幽霊なんてこりごりなんです」
「あぁ、成る程。じゃ、後日こちらにいらしてください」
女は名刺を差し出した。七不市総合病院の花井透子と書いてある。
「私の頭がおかしいっていうんですか?」
「病院の名刺渡されたら精神科って思っちゃいますよね。わかります。私は心霊科って霊障を専門に治療する診療科で働いているんですよ」
「心霊科」
「お力になれると思いますよ」
もう一度名刺に視線を戻す。確かに心霊科と書いてある。
「あの!」
顔を上げると花井の姿はなかった。
普通の病院と変わらない受付で心霊科の事を訪ねれば四階北病棟に案内された。番号札は42番。とても不吉な番号にこころはすっかり気持ちが沈んでしまった。
自分の番号が呼ばれて診察室に通される。そこは薄暗く、こんなに薄暗くて診察なんてできるのだろうかと疑問に思う。そこには椅子に座った医師と横に立つ花井がいた。
医師は三十代半ばに見える。そこそこ整った顔立ちで笑顔から優しさが滲み出ている。椅子に腰掛けると医師が口を開いた。
「はじめまして。僕は太田一郎って言います。今日はどうなさいました?」
診察お決まりの医師の台詞だ。
「先月、今のアパートに引っ越してきてからその、幽霊が見えるようになってしまって。事故物件なんです」
「うん。霊に深く関わってしまって霊感に目覚めてしまう方って沢山いますよ。ほら、心霊スポットに行ったら見えるようになったなんて聞いたことありませんか?」
「家の中でも外でも幽霊が見えて生きている人だと思ったら幽霊だとか。だから、他の人に見えないから私一人でしゃべっている様に見えて……この前なんて花井さんに助けてもらわなければどうなっていたか」
太田はふんふんと頷きながらさらさらとカルテに書き込んでいる。
「あぁ、透子ちゃんが言ってた方ってこの……えと、お名前伺っていませんでしたね」
「横島こころです。助けてください。あんな気持ち悪いもの、見たくないんです。おかしくなりそう」
「お辛いですね。うん。うん。今は便利なお薬あるんで大丈夫ですよ」
「薬で解決できるんですか?」
「えぇ、最初は弱いお薬から試してみましょうか。処方箋出しますので奥の薬局で貰っていってくださいね」
太田は変わらず柔らかい笑顔でこころに処方箋を手渡した。あの地獄から解放されると思うと緊張が解ける感覚がした。
「お薬は用法用量を守って正しくお使いくださいね」
診察が始まる前に聞くべきであったがある疑問が頭をよぎった。
「あの、心霊科は自由診療ですか?」
「あぁ、お金の心配ですね? 心霊科なんて胡散臭いって言われているのは承知なので全て終わったらお支払いして貰ってます」
それなら安心とこころは安堵した。
薬を処方して貰うために同じ棟の更に奥へ行くと薬局があった。小さな窓口から細く白い手がにょきっと出てきた。それに処方箋を渡すとさっと奥に引っ込み、直ぐに薬が出された。
自宅に戻り薬の説明書を読む。『一日朝食後に一錠。飲むと貴方に悪い影響を与える幽霊が赤く見えます。呪文を唱えると消えていなくなります』翌朝一錠飲む。小さな錠剤だったため飲みやすい。悩みのきっかけとなったもう一人の住人が赤く見える。呪文を唱えると見えなくなった。
「す、凄い!」
こころは悩みから解放された。毎朝薬を飲み、赤い幽霊を消す。しかし、あることに気づき、もう一度心霊科へ足を運んだ。
「いつまで飲まなきゃいけないんですか?」
「一生ですよ」
「花井さんも生きている人と幽霊の区別はこの薬で?」
「私は違いますよ」
「私も花井さんと同じになりたい」
「無理ですよ。花井さんは特別なんです」
「じゃ、お薬変えてください! 強い薬なら一生見えなくなるんでしょ?」
まずは弱い薬からと処方箋を出されたことをこころは忘れておらず、太田に食ってかかる。
「まぁ、そうですが、ちゃんと使わないと副作用すごいですよ?」
「見えなくなるならどんな苦しみにでも耐えるわ」
「はい……あの。霊感って金儲けとか自分の欲望のために使うと無くなってしまうんですよ」
「金儲けが出来る上にあんな忌々しいものが見えなくなるなんて最高ね! はやく処方箋ちょうだい!」
「わかりました。強い副作用のあるお薬なので僕が直接説明しますね。霊が見えなくなったら金儲けを辞めること。人様の守護霊を傷つける真似をしないこと。これ、絶対ですよ」
「簡単よ。問題ないわ」
短期アルバイトだと思えば何も問題ないとこころは考えた。
処方された薬は赤い錠剤と『霊能者としての生き方』とだけ表紙に書かれた本だった。『毎食後に一錠。悪霊が赤、地縛霊が青、浮遊霊が黄色、守護霊が白……』霊の種類を見分けられる薬のようだ。呪文も色別に書かれており、最後に最終手段として最強の呪文も書かれていた。念を押すように『どうにもならないときのみご使用ください。尚、全ての呪文は霊が見えない人でも使うことが出来ますがおすすめしません』と注意書きも添えて。同封された本はどのように金儲けするべきか書かれており、色々ある中、ユーチューバーとして活動することにした。最初こそ再生数は伸び悩んだが、薬の力を借りて有名な曰く付きの心霊スポットから幽霊を消して行くと徐々に「あの曰く付き物件から怖さを感じなくなった」「取り壊せず悩んでいたが何も事故が起こらなかった」など評判が評判を呼び本物の霊能者として取材やテレビ出演で財布が潤って行った。
「あんなブラック企業とはおさらばね」
当然残業で辛い思いをしていた会社も辞め、霊能者一本で生きていくと決めた。マシな企業ではなく霊能者に転職とは予想外だったが。
アパートから引っ越し、少しリッチな物件に住んでみたり、ブランド品を買いあさってみたりすっかり太田の忠告を忘れていた。
ある日こころは薬の効力が弱まっている事に気づいた。薬を飲んでも色がはっきり認識出来なくなってしまったのだ。薬を飲まずに霊を見に行くと霊が霊だとはっきりわかる。なぜなら以前なら普通の人間と区別がつかなかった幽霊さえも透けて見える。下手すれば目をこらさなければわからない幽霊さえもいる
「ちょ、どうして……」
こころは焦った。見えなくなってしまったらこんな贅沢な暮らしは出来ない。久々に『霊能者としての手引き』を読み、一つの答えを出した。
『幸せになれないとお困りの皆さん! 私がお守りを作りました! 購入してくださった皆様限定に私の除霊方法を教えちゃいますよ! 霊を消すことによって人生をハッピーに生きましょう!』動画でそう宣伝すると今まで積み重ねて来た活躍もあってか若干高めのお守りは飛ぶように売れた。
「この方法ならまだまだ稼げる。次はどうしようかしら」
口座に振り込まれた売り上げを見る度に幸せを噛みしめる。
「副作用なんてないじゃない。この薬がなくても私はこれからも幸せでいられる」
しかし、その幸せは長く続かなかった。霊感商法。つまり詐欺師として逮捕されたのである。
「私の力は本物よ! 霊感商法なんて言いがかりはよして!」
取り調べでそう訴えるが信じる者はいなかった。そればかりか
「最近不審死が相次いでいましてね、貴方のお守りを持っている方が多かったので調べないわけにはいかないのですよ」
「お守りとそれの何の関係があると言うの! 私は何もやっていないわよ」
「それを調べるのが我々の仕事です」
留置所で何故こうなったのかと何度も考えるがわからない。頭を抱え、髪をわしゃわしゃとかきむしる。誰もいないはずの留置所に人の気配。顔を上げるといないはずの人がいた。
『霊能者ユーチューバーこころ、霊感商法の件で取り調べを……』
お昼休憩中、花井は昼食をとりながらテレビを見ていた。
「先生。お代もらいはぐっちゃいましたね……って先生? 全くどこいっちゃったんですか! もう!」
「こんにちは。こころさん」
顔を上げるとそこにいたのは太田だった。勝ち誇ったような満面の笑みを浮かべている。「え? どうして先生がここに?」
「お代をいただきに参りました」
言っている意味がわからない。お金なんて今手元にあるわけもない。
「私はどうやってここに入ってきたのかを聞いているのよ!」
「ほら、僕はお医者さんですから何でも出来るんですよ」
「答えになっていない!」
「そんなことどうだっていいじゃないですか。こころさん。貴女がやらかしたことに比べたら不法侵入なんてたいしたことじゃないですよ」
「わ、私が一体何をしたというの!」
本当に自分が何をしたのかわからず無駄だと思いながらも太田に八つ当たりした。
「僕、忠告しましたよね? お薬は用法用量を守って正しく使ってくださいって」
「私はちゃんと守ったわよ!」
「ねぇ、こころさん。最終手段の呪文使っちゃったでしょ?」
「それがどうしたって言うのよ」
「人様の守護霊を消してはいけない。貴方はやってはいけないことをやってしまったのですよ」
「私は呪文を教えただけよ!」
「でも結果的に守護霊が消えてしまった人が不幸な死に方をした。貴方は罰を受けなければなりません」
「もう充分に受けているじゃないの!」
太田は優しい笑顔から引きつった様な笑顔になる。声のトーンも段々と低くなり、人ならざる声に聞こえる。まるで地獄の底から響く様な。
「人間界での話をしているのではありません。貴方は善良な霊も殺した罪を償う必要があると言っているのです」
太田の後ろにはぽっかりと黒い空間があり、白く細い手が何本もこころ目掛けて伸びてくる。
「ちょ、何!? きゃぁあああ! 誰か、だれ……か」
この世の者とは思えない手が自分の首に触れた所で意識が途切れた。
「あ、先生。おかえりなさい。どこ行ってたんですか?」
花井は診察室のほこりをハタキで落としていた。
「お代をいただきに行ってました」
「あぁ、そうでしたか。どうでしたか?」
太田は懐から白いもやが入った小瓶を取り出すとニヤニヤしながら頬ずりした。
「欲まみれの人間の魂、こってりしてて好物なんですよ。いつ食べようかなぁ」
「そ、そうですか」
「そうそう。透子ちゃん。霊界タクシーのチケットなんて持ち出して何処へ行こうとしていたんですか?」
太田は返せと言わんばかりに指先をくいくいと動かす。
「あ、バレてました? 昨年死んだ猫に会いたくて虹の橋まで行けないかなって」
透子は鞄からチケットを出し、返却した。
「そんなことしなくても近くにいますよ」
太田はチケットの枚数を数えると机の引き出しにしまった。
「どこです?」
花井はきょろきょろと周囲を見回すが何もいない。
「鈴の音が聞こえるでしょう?」
耳を澄ませばちりん、ちりんと小さな鈴の音がする。
「ウチの猫、鈴なんてつけてませんでしたけど」
「あら? ここでも心霊現象が? 怖いですねぇ」
花井は鈴の音なんて無かったかのように話題を変える。
「そろそろ午後の診察の時間ですよ」
「少し早いけど患者さんお呼びして」
「はーい。午後の診察始まります。66番の方どうぞ!」
花井が番号を読むと患者がゆらりと入ってくる。
「今日はどうなさいましたか?」
太田はにっこりと笑った。
翌日、留置所でこころが心不全で死亡したとニュースが流れた。
「本当にあったんだ」
こころはごくりとつばを飲むと病院へ一歩踏み出した。
事の始まりは三日前。こころは今よりマシな会社への転職を考えているがうまくいかない。無職になるわけにも行かず、仕方なく今のブラック企業で働いている。疲労で死にそうになりながらも残業を終え、終電の時間もとっくに過ぎてしまった駅へタクシーを拾いに行った。いつもこの時間はしん、と静まりかえった駅だが今日は珍しくお仲間の社畜が沢山いる。皆死んだ様な目でタクシー乗り場に並んでいる。そんな日もあるだろうとこころは列に加わった。
「貴方はどこへ行くの?」
後ろからどこか興奮したような声が聞こえ、振り向くとやけにわくわくした様子で微笑む白いワンピースとカーデガンのシンプルなコーデの女。あぁ、春だからな。と見て見ぬふりをしたが空気が読めない女は続ける。
「あ、ごめんなさい。生身の人間がこのタクシーに乗ろうなんて仲間なのかなって」
これ以上この女を無視したら面倒だと思ったこころは振り向く。
「家に帰るに決まってるじゃないですか」
目の前の女は予想外の返答なのか豆鉄砲を食らったような顔をして目を見開いていた。
「駄目です。貴方は乗っちゃ……」
女はこころの腕を掴み、列から外そうとする。流石に異常だと思い叫ぶ。
「離してください! 警察呼びますよ!」
ふと気づく。こんな騒ぎだと言うのに周囲の人たちは一切こちらを気にかけない事に。
「だ、誰か!」
こころは叫ぶが列に並ぶ者は来るタクシーに乗っていくだけであった。
「落ち着いて。落ち着いてください」
女は腕を放さない。こころは恐怖の絶頂を迎えた。
「いやぁあああああああ!」
こころは叫ぶだけ叫び、恐怖が去っている事を祈りながら恐る恐る目を開ける。そこはいつもの静まりかえった駅。目の前には空気の読めない女。こころは気づいた。さっき見たものは幽霊。女は困ったようにこちらを見ている。
「残念。皆驚いてタクシー乗り場もろともどこかへ行ってしまいました……。貴女は貴女であんな幽霊の団体さん見ちゃったら怖いですよね。無事でよかった」
幽霊の団体が怖いのではなく、目の前の女が恐ろしくて悲鳴をあげたのだが、結果的に恐ろしいものは見えなくなったので結果オーライであった。こころは今抱えている悩みをこの人ならと、意を決した。
「あ、貴女も幽霊みえる、の?」
「見えますよ」
「生きている人と幽霊の区別もつくの?」
「勿論ですよ」
「わ、私を、助けて……もう幽霊なんてこりごりなんです」
「あぁ、成る程。じゃ、後日こちらにいらしてください」
女は名刺を差し出した。七不市総合病院の花井透子と書いてある。
「私の頭がおかしいっていうんですか?」
「病院の名刺渡されたら精神科って思っちゃいますよね。わかります。私は心霊科って霊障を専門に治療する診療科で働いているんですよ」
「心霊科」
「お力になれると思いますよ」
もう一度名刺に視線を戻す。確かに心霊科と書いてある。
「あの!」
顔を上げると花井の姿はなかった。
普通の病院と変わらない受付で心霊科の事を訪ねれば四階北病棟に案内された。番号札は42番。とても不吉な番号にこころはすっかり気持ちが沈んでしまった。
自分の番号が呼ばれて診察室に通される。そこは薄暗く、こんなに薄暗くて診察なんてできるのだろうかと疑問に思う。そこには椅子に座った医師と横に立つ花井がいた。
医師は三十代半ばに見える。そこそこ整った顔立ちで笑顔から優しさが滲み出ている。椅子に腰掛けると医師が口を開いた。
「はじめまして。僕は太田一郎って言います。今日はどうなさいました?」
診察お決まりの医師の台詞だ。
「先月、今のアパートに引っ越してきてからその、幽霊が見えるようになってしまって。事故物件なんです」
「うん。霊に深く関わってしまって霊感に目覚めてしまう方って沢山いますよ。ほら、心霊スポットに行ったら見えるようになったなんて聞いたことありませんか?」
「家の中でも外でも幽霊が見えて生きている人だと思ったら幽霊だとか。だから、他の人に見えないから私一人でしゃべっている様に見えて……この前なんて花井さんに助けてもらわなければどうなっていたか」
太田はふんふんと頷きながらさらさらとカルテに書き込んでいる。
「あぁ、透子ちゃんが言ってた方ってこの……えと、お名前伺っていませんでしたね」
「横島こころです。助けてください。あんな気持ち悪いもの、見たくないんです。おかしくなりそう」
「お辛いですね。うん。うん。今は便利なお薬あるんで大丈夫ですよ」
「薬で解決できるんですか?」
「えぇ、最初は弱いお薬から試してみましょうか。処方箋出しますので奥の薬局で貰っていってくださいね」
太田は変わらず柔らかい笑顔でこころに処方箋を手渡した。あの地獄から解放されると思うと緊張が解ける感覚がした。
「お薬は用法用量を守って正しくお使いくださいね」
診察が始まる前に聞くべきであったがある疑問が頭をよぎった。
「あの、心霊科は自由診療ですか?」
「あぁ、お金の心配ですね? 心霊科なんて胡散臭いって言われているのは承知なので全て終わったらお支払いして貰ってます」
それなら安心とこころは安堵した。
薬を処方して貰うために同じ棟の更に奥へ行くと薬局があった。小さな窓口から細く白い手がにょきっと出てきた。それに処方箋を渡すとさっと奥に引っ込み、直ぐに薬が出された。
自宅に戻り薬の説明書を読む。『一日朝食後に一錠。飲むと貴方に悪い影響を与える幽霊が赤く見えます。呪文を唱えると消えていなくなります』翌朝一錠飲む。小さな錠剤だったため飲みやすい。悩みのきっかけとなったもう一人の住人が赤く見える。呪文を唱えると見えなくなった。
「す、凄い!」
こころは悩みから解放された。毎朝薬を飲み、赤い幽霊を消す。しかし、あることに気づき、もう一度心霊科へ足を運んだ。
「いつまで飲まなきゃいけないんですか?」
「一生ですよ」
「花井さんも生きている人と幽霊の区別はこの薬で?」
「私は違いますよ」
「私も花井さんと同じになりたい」
「無理ですよ。花井さんは特別なんです」
「じゃ、お薬変えてください! 強い薬なら一生見えなくなるんでしょ?」
まずは弱い薬からと処方箋を出されたことをこころは忘れておらず、太田に食ってかかる。
「まぁ、そうですが、ちゃんと使わないと副作用すごいですよ?」
「見えなくなるならどんな苦しみにでも耐えるわ」
「はい……あの。霊感って金儲けとか自分の欲望のために使うと無くなってしまうんですよ」
「金儲けが出来る上にあんな忌々しいものが見えなくなるなんて最高ね! はやく処方箋ちょうだい!」
「わかりました。強い副作用のあるお薬なので僕が直接説明しますね。霊が見えなくなったら金儲けを辞めること。人様の守護霊を傷つける真似をしないこと。これ、絶対ですよ」
「簡単よ。問題ないわ」
短期アルバイトだと思えば何も問題ないとこころは考えた。
処方された薬は赤い錠剤と『霊能者としての生き方』とだけ表紙に書かれた本だった。『毎食後に一錠。悪霊が赤、地縛霊が青、浮遊霊が黄色、守護霊が白……』霊の種類を見分けられる薬のようだ。呪文も色別に書かれており、最後に最終手段として最強の呪文も書かれていた。念を押すように『どうにもならないときのみご使用ください。尚、全ての呪文は霊が見えない人でも使うことが出来ますがおすすめしません』と注意書きも添えて。同封された本はどのように金儲けするべきか書かれており、色々ある中、ユーチューバーとして活動することにした。最初こそ再生数は伸び悩んだが、薬の力を借りて有名な曰く付きの心霊スポットから幽霊を消して行くと徐々に「あの曰く付き物件から怖さを感じなくなった」「取り壊せず悩んでいたが何も事故が起こらなかった」など評判が評判を呼び本物の霊能者として取材やテレビ出演で財布が潤って行った。
「あんなブラック企業とはおさらばね」
当然残業で辛い思いをしていた会社も辞め、霊能者一本で生きていくと決めた。マシな企業ではなく霊能者に転職とは予想外だったが。
アパートから引っ越し、少しリッチな物件に住んでみたり、ブランド品を買いあさってみたりすっかり太田の忠告を忘れていた。
ある日こころは薬の効力が弱まっている事に気づいた。薬を飲んでも色がはっきり認識出来なくなってしまったのだ。薬を飲まずに霊を見に行くと霊が霊だとはっきりわかる。なぜなら以前なら普通の人間と区別がつかなかった幽霊さえも透けて見える。下手すれば目をこらさなければわからない幽霊さえもいる
「ちょ、どうして……」
こころは焦った。見えなくなってしまったらこんな贅沢な暮らしは出来ない。久々に『霊能者としての手引き』を読み、一つの答えを出した。
『幸せになれないとお困りの皆さん! 私がお守りを作りました! 購入してくださった皆様限定に私の除霊方法を教えちゃいますよ! 霊を消すことによって人生をハッピーに生きましょう!』動画でそう宣伝すると今まで積み重ねて来た活躍もあってか若干高めのお守りは飛ぶように売れた。
「この方法ならまだまだ稼げる。次はどうしようかしら」
口座に振り込まれた売り上げを見る度に幸せを噛みしめる。
「副作用なんてないじゃない。この薬がなくても私はこれからも幸せでいられる」
しかし、その幸せは長く続かなかった。霊感商法。つまり詐欺師として逮捕されたのである。
「私の力は本物よ! 霊感商法なんて言いがかりはよして!」
取り調べでそう訴えるが信じる者はいなかった。そればかりか
「最近不審死が相次いでいましてね、貴方のお守りを持っている方が多かったので調べないわけにはいかないのですよ」
「お守りとそれの何の関係があると言うの! 私は何もやっていないわよ」
「それを調べるのが我々の仕事です」
留置所で何故こうなったのかと何度も考えるがわからない。頭を抱え、髪をわしゃわしゃとかきむしる。誰もいないはずの留置所に人の気配。顔を上げるといないはずの人がいた。
『霊能者ユーチューバーこころ、霊感商法の件で取り調べを……』
お昼休憩中、花井は昼食をとりながらテレビを見ていた。
「先生。お代もらいはぐっちゃいましたね……って先生? 全くどこいっちゃったんですか! もう!」
「こんにちは。こころさん」
顔を上げるとそこにいたのは太田だった。勝ち誇ったような満面の笑みを浮かべている。「え? どうして先生がここに?」
「お代をいただきに参りました」
言っている意味がわからない。お金なんて今手元にあるわけもない。
「私はどうやってここに入ってきたのかを聞いているのよ!」
「ほら、僕はお医者さんですから何でも出来るんですよ」
「答えになっていない!」
「そんなことどうだっていいじゃないですか。こころさん。貴女がやらかしたことに比べたら不法侵入なんてたいしたことじゃないですよ」
「わ、私が一体何をしたというの!」
本当に自分が何をしたのかわからず無駄だと思いながらも太田に八つ当たりした。
「僕、忠告しましたよね? お薬は用法用量を守って正しく使ってくださいって」
「私はちゃんと守ったわよ!」
「ねぇ、こころさん。最終手段の呪文使っちゃったでしょ?」
「それがどうしたって言うのよ」
「人様の守護霊を消してはいけない。貴方はやってはいけないことをやってしまったのですよ」
「私は呪文を教えただけよ!」
「でも結果的に守護霊が消えてしまった人が不幸な死に方をした。貴方は罰を受けなければなりません」
「もう充分に受けているじゃないの!」
太田は優しい笑顔から引きつった様な笑顔になる。声のトーンも段々と低くなり、人ならざる声に聞こえる。まるで地獄の底から響く様な。
「人間界での話をしているのではありません。貴方は善良な霊も殺した罪を償う必要があると言っているのです」
太田の後ろにはぽっかりと黒い空間があり、白く細い手が何本もこころ目掛けて伸びてくる。
「ちょ、何!? きゃぁあああ! 誰か、だれ……か」
この世の者とは思えない手が自分の首に触れた所で意識が途切れた。
「あ、先生。おかえりなさい。どこ行ってたんですか?」
花井は診察室のほこりをハタキで落としていた。
「お代をいただきに行ってました」
「あぁ、そうでしたか。どうでしたか?」
太田は懐から白いもやが入った小瓶を取り出すとニヤニヤしながら頬ずりした。
「欲まみれの人間の魂、こってりしてて好物なんですよ。いつ食べようかなぁ」
「そ、そうですか」
「そうそう。透子ちゃん。霊界タクシーのチケットなんて持ち出して何処へ行こうとしていたんですか?」
太田は返せと言わんばかりに指先をくいくいと動かす。
「あ、バレてました? 昨年死んだ猫に会いたくて虹の橋まで行けないかなって」
透子は鞄からチケットを出し、返却した。
「そんなことしなくても近くにいますよ」
太田はチケットの枚数を数えると机の引き出しにしまった。
「どこです?」
花井はきょろきょろと周囲を見回すが何もいない。
「鈴の音が聞こえるでしょう?」
耳を澄ませばちりん、ちりんと小さな鈴の音がする。
「ウチの猫、鈴なんてつけてませんでしたけど」
「あら? ここでも心霊現象が? 怖いですねぇ」
花井は鈴の音なんて無かったかのように話題を変える。
「そろそろ午後の診察の時間ですよ」
「少し早いけど患者さんお呼びして」
「はーい。午後の診察始まります。66番の方どうぞ!」
花井が番号を読むと患者がゆらりと入ってくる。
「今日はどうなさいましたか?」
太田はにっこりと笑った。
翌日、留置所でこころが心不全で死亡したとニュースが流れた。