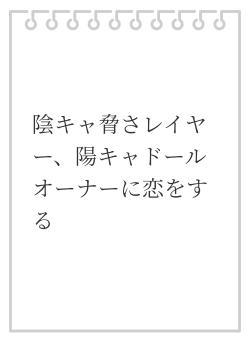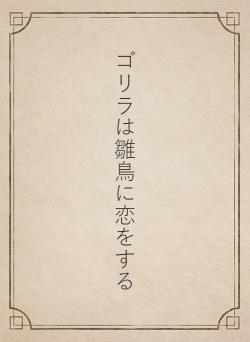僕には二人の父がいる。母の遺品整理をしていた時、写真と手紙を見つけ、あの頃を思い出した。
「いってぇ……思いっきり殴りやがって」
昭和18年の夏。僕、岩村正(いわむらただし)は近所のガキ大将に理不尽な理由で殴られた。僕は細く背も低かったため立派な兵士になれないと非国民扱いされたのである。父もまた健康であるがド近眼で貧弱な体形であったため未だ赤紙が来ていない。しかし、そんな理由なら日本国民のどれほどが非国民となるだろうかと殴られた頬を押さえながら家へ帰った。やり返したいなんて思うが、あの体格差では勝てる気がしない。
「おかえりなさい。またいじめられたの?」
母親が庭で洗濯物を干していた。
「あいつ、本当に酷いやつだよ」
僕は井戸で顔を洗った。
「もう学校行かなくていいわよ? どうせ空襲警報で禄に授業できないんでしょ?」
普段母親は勉強は無駄にならないからちゃんと学校へ行きなさいなんて言う。何か裏がありそうだ。訝しげに母親を見る僕の様子を察してか言葉を続ける。
「あのね、近所のお野菜をお裾分けしてくれる田中さんっているでしょ? 怪我をして日常生活が不安だからとお手伝いが必要だそうよ」
つまり、僕に行けって事なのか。
「何処を怪我したの?」
「……肥溜めに落ちて足を少しね」
「おえ……」
肥溜め。畑の肥料にするための糞尿を貯めておく場所。想像するだけで鼻がねじ曲がりそうだ。
「嫌とは言わせないわよ。母さん恩を仇で返すのは嫌いなのよ。それにお前の体は半分田中さんの野菜で出来ているんだからね」
いつもなら母さんが行けばなんて言いたいが、身重の母親を動かすわけには行かない。
「わかったよ」
渋々承知するしかなかった。
「田中さーん!」
僕の両手はお盆で塞がっている。当然田中さんに食べさせるためのものだ。田中さんちの玄関で大声で叫ぶと「あがってこーい」と返ってくる。
「おじゃまします」
玄関で靴を脱ぎ、揃える。「こっちだ」と部屋から手がにゅっと出てきた。
「こんにちは」
肥溜めに落ちたと聞いたから覚悟していたが、特におかしな臭いがするわけでもなく、普通だった。部屋はお一人様らしくちゃぶ台と簡素な家具にラジオ。
「正、よくきてくれたなぁ、俺、足をひねってしまってな。家事がなかなか思うようにいかないんだ」
田中さんは日焼けした浅黒い肌をしていて垂れ目の優しい雰囲気を纏う人だ。結婚しようと思えばいつでも出来そうな容姿で子供の僕から見ても色気すら感じるくらいだ。
「ん。昼飯」
「ありがとう。たえさんのご飯久しぶりだなぁ」
たえとは僕の母親の名前なのだが、久しぶりとはどういう事だろう。前にもこんな事があったのだろうか疑問に思う。
「また後で茶碗取りに来るね」
田中さんは幸せそうな顔で芋の雑炊をずずっとかき込んでいる。
「待て、茶でも飲んでいけ」
そう言いながら急須を傾け、湯飲みにお茶を汲んでくれた。断る理由もなかったのでいただくことにした。
「正、たえさんから聞いたよ。いじめられているんだって?」
「げほっ……!」
引き留めておいてそんな話題を出すのか。さっさと帰れば良かったとむせながら後悔した。
「睨むなよ。小さい頃から正を見てきたから心配なだけなんだよ」
「母さんから何かお願いされているの?」
「別に。どうせ学校行ってもいじめられるなら俺の面倒みて楽しく過ごさないか?」
「田中さんの暇つぶしの相手って事?」
「正も一緒に楽しく過ごすんだ」
「……期待してもいいの?」
「あぁ、勿論さ!」
うまく丸め込まれた気がしたが学校へ行くより全然マシだと思った。それに田中さんの足に巻かれた包帯が痛々しく放っておけないのもあった。
母親が作った食事をお盆に乗せて運ぶ。時々買い物を頼まれたり、配給切符を預かり、田中さん日用品や食料の確保。他にも細々と手伝いをした。いつの間にか一緒に食事をとるまでになった。田中さんの話は面白い物で、僕の楽しみの一つとなっていった。特にアメリカに住んでいた時の話ときたら地元の事しか知らない正にとっておとぎ話の様に聞こえた。それだけでなく、僕に勉強を教えてくれたり。悩みの相談にものってくれたのだ。
「僕、強くなりたいな。この前話してくれたキングコングみたいな」
「そうだな。体はそう簡単には難しいが心なら考え方次第で強くなれるぞ」
「どうするの?」
「正、両親やこれから生まれてくる下の子に不安な思いはさせたくないだろう?」
「う、うん」
「人間命さえあればどうにかなるもんだ。大丈夫、大丈夫と笑って言うんだ。そうすると大丈夫な気がしてくるもんだ」
僕は気づいた。田中さんの口癖が「大丈夫」だと言うことに。
勉強で分からないところがあって聞いても「大丈夫。正ならわかる」
外国に行ってみたいと言っても「大丈夫。いつか行けるさ」
「大丈夫」
確認するようにぼそりと呟く。
「そう。正なら大丈夫だ」
田中さんは白い歯を見せながら僕の頭を撫でた。
田中さんの足が治っても僕は何かと理由を作って学校が終わると遊びに行った。
「また田中さんが肥溜めにハマってないか心配できたんだ。暇つぶしに将棋くらいなら付き合ってやってもいいぞ」
「おぉ、来たか。上がれ上がれ」
畑仕事をしていれば中断して僕につきあってくれるものだから、学校でいじめられてもたいしたことないように思えてきた。
しかし、その幸せも長くは続かなかった。いつものように遊びに行くと田中さんは暗い顔で「そこへ座れ」と言った。
「どうしたの?」
「赤紙。召集令状が来た」
僕は頭が殴られたかの様な衝撃を受けた。
「い、いつ行っちゃうの? 無事に帰ってくるよね?」
「……大丈夫だ」
田中さんは無理矢理その言葉を言っているように感じた。自分自身に言い聞かせるように。そして重い口を開く。
「正、約束してくれないか? いじめられても、もうお前を慰めてそばにいてやることも出来ない。戦地でお前のことが気になって敵を倒すどころじゃない。俺を安心して行かせてくれ」
僕は何て答えればいいかわからなかった。だけどこれ以上心配をかけてはいけない。僕の回答次第で田中さんの生死が決まってしまうかもしれない。大げさかもしれないけれどそう感じた。
「僕は、大丈夫! いじめっこになんて負けやしないよ!」
引きつった笑顔だったかもしれない。だけど、僕が出来る事は嘘でも安心させることだった。
「あと、両親を大事にな。みんなお前のことを心配しているんだぞ」
「うん……」
その日は田中さんの家へ泊まることにした。泊まったからと言ってもいつもの日常に夜更かしが追加されたくらいで川の字になって寝ただけだった。布団で田中さんはぼやいた。
「やっぱり横に誰かがいるのはいいものだね」
「田中さんはどうして結婚しなかったの? 凄くかっこいいのに」
「かっこいい? 嬉しい事言ってくれるね。そうだな。縁はあったが、縁が切られてしまった。そんな所だ」
「フラれちゃったの?」
「フラれた訳ではないが、一緒にいられない事情ができたんだ」
「ふうん……」
田中さんはそれだけ言うと寝てしまった様で静かな寝息が聞こえてくるだけだった。
朝起きると田中さんの姿は既に無く、枕元に手紙と鍵が2つあった。手紙の内容は『家を出る際に鍵をかけて正が保管すること。俺が戦死したら金庫を開けなさい。戦死の知らせがなく、戦争が終わって3年たって戻って来なくても同様に金庫を開けなさい。いじめっこに絶対負けるんじゃないぞ。正なら大丈夫だ。サヨウナラ』鍵は家と金庫のものだった。
さようならくらい直接言いたかった。だけど僕の事だから泣いてしまうだろう。田中さんはそれを見越して独り出て行ってしまったのかもしれない。僕は無理矢理そう思うことにした。
心にぽっかりと穴が開いてしまった状態でもいつか田中さんが帰って来た時がっかりさせないように学校へ行く。当然授業なんて上の空だった。そんな上の空の僕をからかうように放課後、ガキ大将が絡んできた。
「体は貧弱。それに授業が上の空とかお前はどうしようもないな。根性たたき直してやる!」
ガキ大将が指をバキッと鳴らし、僕に殴りかかってきた。いつも通りに顔面でその拳を受け止める。
「大丈夫。大丈夫」
僕はふらふらになりながらも田中さんに教えて貰った通りに笑いながら「大丈夫」を唱えた。
「頭がおかしくなってしまったのか? どちらにしろ俺に殴られるのは変わりないがな!」
また拳が顔面目掛けて飛んでくる。
「僕は、大丈夫!」
偶然かどうかはわからないが、避けられた。「お前は黙って殴られればいいんだ!」
「僕は田中さんが心配するからもう逃げない! 大丈夫! お前に勝てる! 大丈夫!」
僕は初めて拳を振り上げた。体格差があるから当然当たるはずもなく、空振りばかりだった。初めての反撃、殴られても立ち上がる。それに恐れおののいたのかガキ大将が「気持ち悪い奴!」と逃げていった。
ボロボロの顔のまま空を見上げ
「僕は大丈夫だよ」
世界のどこかで戦っているであろう田中さんに語りかけた。
いつも以上にボロボロになって帰ってきた僕を見て両親は酷く驚いたが僕はニッと笑い
「大丈夫!」
とだけ言い、井戸で顔を洗った。染みて痛かったが、初めての反撃に胸がスッとした気持ちの方が上回った。
昭和20年戦争は終わった。僕が住んでいたところは米軍の艦載機による機銃掃射がたまにあったくらいで恐ろしかったが東京大空襲、広島と長崎の原爆、沖縄戦に比べたらたいした事なかったのかもしれない。18年の秋に生まれた妹も元気に成長して僕もお兄ちゃんらしくなった気がする。戦争は終わったが、田中さんは帰ってこない。約束の時期が来るまでなるべく考えないようにしていた。
3年後。田中さんは帰ってこなかった。僕が強くなろうがなるまいが、戦争は田中さんを奪ったのだ。顔をくしゃくしゃにして泣きたかったが、無理矢理「大丈夫」と自分に言い聞かせた。
僕はあの時預かった家の鍵と金庫の鍵を手に、田中さんの家へ向かった。ほこり舞う以外何も変わっておらず、今にも「正、来たのか」と田中さんが出てきそうな雰囲気だった。ほこりに咳き込みながら金庫がある部屋へ向かい鍵を開ける。その中には預金通帳と印鑑。そして「たえさんへ」と書かれた手紙が一通。その手紙を母に渡したら母は部屋に隠り、わんわんと泣き始めた。何事かと泣き声漏れる部屋へ行こうとしたが、父が僕の肩を掴み首を横へ振った。僕は聞いてはいけないことだと思い、それ以上詮索できなかった。
昭和40年、父が亡くなった。母はやはり泣いたがあの時の様に泣くことはせず静かに肩を震わせていた。
「母さん。大丈夫だよ。大丈夫」
僕がこれからは僕が母さんを助けるから安心してと背中をさすってやる。
「あの人にそっくりだねぇ」
妙な事を言い出した。
「あの人って……」
これ以上は聞いてはいけない。何となくそう思った僕はそれ以降の言葉を飲み込んだ。
そして昭和60年には母が亡くなり葬儀やら相続やら落ち着いた頃、遺品整理をしていた。母の箪笥の奥に隠されるように置いてあった桐の箱。何か良い物でも入っているのではないかと年甲斐もなくわくわくしながら開けた。そこには数枚の写真と見覚えのある手紙。どれも二人で写っているもので一人は母。しかも結婚前の10代後半であることは一目でわかる幼さがある。もう一人。それが問題だったのだ。妙な色気を醸し出すその男。田中さんだったのだ。僕が知っている田中さんより若い。
僕はもしかして。と考えた。田中さんの未婚。母をたえさんと呼んだ。母が号泣した。そして、父の葬儀でのあの人にそっくり……。次に見覚えのある手紙。そうあの金庫と一緒に入っていたものだ。それを開き何となく察した。
『俺にも子育てさせてくれてありがとう。少ないですが生活の足しにしてください』
母と田中さんはかつて結婚を約束していたが、反対にあった。田中さんは諦めきれずに母を近くで見守っていた。母も田中さんに近づきたかったが、結婚して父を夫としてしまった手前、いかがわしい事なんてできない。肥溜めに落ちたのはおそらく偶然だが、それを利用して僕を田中さん家へ通わせた。父はそれを知っていたのだろうか。たとえそうだったとして僕は田中さんの「大丈夫」に救われたのだから嫌な気持ちにはならなかった。感謝しているくらいだ。田中さんとの交流は人生の肥やしになったのだ。
察したが真実を知る者は誰もいない。妹なんて余計にわかるはずもない。もしも天国があるのなら3人は幸せなのだろうか。もう一度写真を眺め、手紙と共にそっと箱に戻した。僕には二人父がいる。一人は寡黙だが僕を健康な遺伝子をくれた実の父。もう一人は田中さん。「大丈夫」と野菜で僕を完成させてくれた人。何て幸せ者なんだろう。僕はそう思うことにした。
「いってぇ……思いっきり殴りやがって」
昭和18年の夏。僕、岩村正(いわむらただし)は近所のガキ大将に理不尽な理由で殴られた。僕は細く背も低かったため立派な兵士になれないと非国民扱いされたのである。父もまた健康であるがド近眼で貧弱な体形であったため未だ赤紙が来ていない。しかし、そんな理由なら日本国民のどれほどが非国民となるだろうかと殴られた頬を押さえながら家へ帰った。やり返したいなんて思うが、あの体格差では勝てる気がしない。
「おかえりなさい。またいじめられたの?」
母親が庭で洗濯物を干していた。
「あいつ、本当に酷いやつだよ」
僕は井戸で顔を洗った。
「もう学校行かなくていいわよ? どうせ空襲警報で禄に授業できないんでしょ?」
普段母親は勉強は無駄にならないからちゃんと学校へ行きなさいなんて言う。何か裏がありそうだ。訝しげに母親を見る僕の様子を察してか言葉を続ける。
「あのね、近所のお野菜をお裾分けしてくれる田中さんっているでしょ? 怪我をして日常生活が不安だからとお手伝いが必要だそうよ」
つまり、僕に行けって事なのか。
「何処を怪我したの?」
「……肥溜めに落ちて足を少しね」
「おえ……」
肥溜め。畑の肥料にするための糞尿を貯めておく場所。想像するだけで鼻がねじ曲がりそうだ。
「嫌とは言わせないわよ。母さん恩を仇で返すのは嫌いなのよ。それにお前の体は半分田中さんの野菜で出来ているんだからね」
いつもなら母さんが行けばなんて言いたいが、身重の母親を動かすわけには行かない。
「わかったよ」
渋々承知するしかなかった。
「田中さーん!」
僕の両手はお盆で塞がっている。当然田中さんに食べさせるためのものだ。田中さんちの玄関で大声で叫ぶと「あがってこーい」と返ってくる。
「おじゃまします」
玄関で靴を脱ぎ、揃える。「こっちだ」と部屋から手がにゅっと出てきた。
「こんにちは」
肥溜めに落ちたと聞いたから覚悟していたが、特におかしな臭いがするわけでもなく、普通だった。部屋はお一人様らしくちゃぶ台と簡素な家具にラジオ。
「正、よくきてくれたなぁ、俺、足をひねってしまってな。家事がなかなか思うようにいかないんだ」
田中さんは日焼けした浅黒い肌をしていて垂れ目の優しい雰囲気を纏う人だ。結婚しようと思えばいつでも出来そうな容姿で子供の僕から見ても色気すら感じるくらいだ。
「ん。昼飯」
「ありがとう。たえさんのご飯久しぶりだなぁ」
たえとは僕の母親の名前なのだが、久しぶりとはどういう事だろう。前にもこんな事があったのだろうか疑問に思う。
「また後で茶碗取りに来るね」
田中さんは幸せそうな顔で芋の雑炊をずずっとかき込んでいる。
「待て、茶でも飲んでいけ」
そう言いながら急須を傾け、湯飲みにお茶を汲んでくれた。断る理由もなかったのでいただくことにした。
「正、たえさんから聞いたよ。いじめられているんだって?」
「げほっ……!」
引き留めておいてそんな話題を出すのか。さっさと帰れば良かったとむせながら後悔した。
「睨むなよ。小さい頃から正を見てきたから心配なだけなんだよ」
「母さんから何かお願いされているの?」
「別に。どうせ学校行ってもいじめられるなら俺の面倒みて楽しく過ごさないか?」
「田中さんの暇つぶしの相手って事?」
「正も一緒に楽しく過ごすんだ」
「……期待してもいいの?」
「あぁ、勿論さ!」
うまく丸め込まれた気がしたが学校へ行くより全然マシだと思った。それに田中さんの足に巻かれた包帯が痛々しく放っておけないのもあった。
母親が作った食事をお盆に乗せて運ぶ。時々買い物を頼まれたり、配給切符を預かり、田中さん日用品や食料の確保。他にも細々と手伝いをした。いつの間にか一緒に食事をとるまでになった。田中さんの話は面白い物で、僕の楽しみの一つとなっていった。特にアメリカに住んでいた時の話ときたら地元の事しか知らない正にとっておとぎ話の様に聞こえた。それだけでなく、僕に勉強を教えてくれたり。悩みの相談にものってくれたのだ。
「僕、強くなりたいな。この前話してくれたキングコングみたいな」
「そうだな。体はそう簡単には難しいが心なら考え方次第で強くなれるぞ」
「どうするの?」
「正、両親やこれから生まれてくる下の子に不安な思いはさせたくないだろう?」
「う、うん」
「人間命さえあればどうにかなるもんだ。大丈夫、大丈夫と笑って言うんだ。そうすると大丈夫な気がしてくるもんだ」
僕は気づいた。田中さんの口癖が「大丈夫」だと言うことに。
勉強で分からないところがあって聞いても「大丈夫。正ならわかる」
外国に行ってみたいと言っても「大丈夫。いつか行けるさ」
「大丈夫」
確認するようにぼそりと呟く。
「そう。正なら大丈夫だ」
田中さんは白い歯を見せながら僕の頭を撫でた。
田中さんの足が治っても僕は何かと理由を作って学校が終わると遊びに行った。
「また田中さんが肥溜めにハマってないか心配できたんだ。暇つぶしに将棋くらいなら付き合ってやってもいいぞ」
「おぉ、来たか。上がれ上がれ」
畑仕事をしていれば中断して僕につきあってくれるものだから、学校でいじめられてもたいしたことないように思えてきた。
しかし、その幸せも長くは続かなかった。いつものように遊びに行くと田中さんは暗い顔で「そこへ座れ」と言った。
「どうしたの?」
「赤紙。召集令状が来た」
僕は頭が殴られたかの様な衝撃を受けた。
「い、いつ行っちゃうの? 無事に帰ってくるよね?」
「……大丈夫だ」
田中さんは無理矢理その言葉を言っているように感じた。自分自身に言い聞かせるように。そして重い口を開く。
「正、約束してくれないか? いじめられても、もうお前を慰めてそばにいてやることも出来ない。戦地でお前のことが気になって敵を倒すどころじゃない。俺を安心して行かせてくれ」
僕は何て答えればいいかわからなかった。だけどこれ以上心配をかけてはいけない。僕の回答次第で田中さんの生死が決まってしまうかもしれない。大げさかもしれないけれどそう感じた。
「僕は、大丈夫! いじめっこになんて負けやしないよ!」
引きつった笑顔だったかもしれない。だけど、僕が出来る事は嘘でも安心させることだった。
「あと、両親を大事にな。みんなお前のことを心配しているんだぞ」
「うん……」
その日は田中さんの家へ泊まることにした。泊まったからと言ってもいつもの日常に夜更かしが追加されたくらいで川の字になって寝ただけだった。布団で田中さんはぼやいた。
「やっぱり横に誰かがいるのはいいものだね」
「田中さんはどうして結婚しなかったの? 凄くかっこいいのに」
「かっこいい? 嬉しい事言ってくれるね。そうだな。縁はあったが、縁が切られてしまった。そんな所だ」
「フラれちゃったの?」
「フラれた訳ではないが、一緒にいられない事情ができたんだ」
「ふうん……」
田中さんはそれだけ言うと寝てしまった様で静かな寝息が聞こえてくるだけだった。
朝起きると田中さんの姿は既に無く、枕元に手紙と鍵が2つあった。手紙の内容は『家を出る際に鍵をかけて正が保管すること。俺が戦死したら金庫を開けなさい。戦死の知らせがなく、戦争が終わって3年たって戻って来なくても同様に金庫を開けなさい。いじめっこに絶対負けるんじゃないぞ。正なら大丈夫だ。サヨウナラ』鍵は家と金庫のものだった。
さようならくらい直接言いたかった。だけど僕の事だから泣いてしまうだろう。田中さんはそれを見越して独り出て行ってしまったのかもしれない。僕は無理矢理そう思うことにした。
心にぽっかりと穴が開いてしまった状態でもいつか田中さんが帰って来た時がっかりさせないように学校へ行く。当然授業なんて上の空だった。そんな上の空の僕をからかうように放課後、ガキ大将が絡んできた。
「体は貧弱。それに授業が上の空とかお前はどうしようもないな。根性たたき直してやる!」
ガキ大将が指をバキッと鳴らし、僕に殴りかかってきた。いつも通りに顔面でその拳を受け止める。
「大丈夫。大丈夫」
僕はふらふらになりながらも田中さんに教えて貰った通りに笑いながら「大丈夫」を唱えた。
「頭がおかしくなってしまったのか? どちらにしろ俺に殴られるのは変わりないがな!」
また拳が顔面目掛けて飛んでくる。
「僕は、大丈夫!」
偶然かどうかはわからないが、避けられた。「お前は黙って殴られればいいんだ!」
「僕は田中さんが心配するからもう逃げない! 大丈夫! お前に勝てる! 大丈夫!」
僕は初めて拳を振り上げた。体格差があるから当然当たるはずもなく、空振りばかりだった。初めての反撃、殴られても立ち上がる。それに恐れおののいたのかガキ大将が「気持ち悪い奴!」と逃げていった。
ボロボロの顔のまま空を見上げ
「僕は大丈夫だよ」
世界のどこかで戦っているであろう田中さんに語りかけた。
いつも以上にボロボロになって帰ってきた僕を見て両親は酷く驚いたが僕はニッと笑い
「大丈夫!」
とだけ言い、井戸で顔を洗った。染みて痛かったが、初めての反撃に胸がスッとした気持ちの方が上回った。
昭和20年戦争は終わった。僕が住んでいたところは米軍の艦載機による機銃掃射がたまにあったくらいで恐ろしかったが東京大空襲、広島と長崎の原爆、沖縄戦に比べたらたいした事なかったのかもしれない。18年の秋に生まれた妹も元気に成長して僕もお兄ちゃんらしくなった気がする。戦争は終わったが、田中さんは帰ってこない。約束の時期が来るまでなるべく考えないようにしていた。
3年後。田中さんは帰ってこなかった。僕が強くなろうがなるまいが、戦争は田中さんを奪ったのだ。顔をくしゃくしゃにして泣きたかったが、無理矢理「大丈夫」と自分に言い聞かせた。
僕はあの時預かった家の鍵と金庫の鍵を手に、田中さんの家へ向かった。ほこり舞う以外何も変わっておらず、今にも「正、来たのか」と田中さんが出てきそうな雰囲気だった。ほこりに咳き込みながら金庫がある部屋へ向かい鍵を開ける。その中には預金通帳と印鑑。そして「たえさんへ」と書かれた手紙が一通。その手紙を母に渡したら母は部屋に隠り、わんわんと泣き始めた。何事かと泣き声漏れる部屋へ行こうとしたが、父が僕の肩を掴み首を横へ振った。僕は聞いてはいけないことだと思い、それ以上詮索できなかった。
昭和40年、父が亡くなった。母はやはり泣いたがあの時の様に泣くことはせず静かに肩を震わせていた。
「母さん。大丈夫だよ。大丈夫」
僕がこれからは僕が母さんを助けるから安心してと背中をさすってやる。
「あの人にそっくりだねぇ」
妙な事を言い出した。
「あの人って……」
これ以上は聞いてはいけない。何となくそう思った僕はそれ以降の言葉を飲み込んだ。
そして昭和60年には母が亡くなり葬儀やら相続やら落ち着いた頃、遺品整理をしていた。母の箪笥の奥に隠されるように置いてあった桐の箱。何か良い物でも入っているのではないかと年甲斐もなくわくわくしながら開けた。そこには数枚の写真と見覚えのある手紙。どれも二人で写っているもので一人は母。しかも結婚前の10代後半であることは一目でわかる幼さがある。もう一人。それが問題だったのだ。妙な色気を醸し出すその男。田中さんだったのだ。僕が知っている田中さんより若い。
僕はもしかして。と考えた。田中さんの未婚。母をたえさんと呼んだ。母が号泣した。そして、父の葬儀でのあの人にそっくり……。次に見覚えのある手紙。そうあの金庫と一緒に入っていたものだ。それを開き何となく察した。
『俺にも子育てさせてくれてありがとう。少ないですが生活の足しにしてください』
母と田中さんはかつて結婚を約束していたが、反対にあった。田中さんは諦めきれずに母を近くで見守っていた。母も田中さんに近づきたかったが、結婚して父を夫としてしまった手前、いかがわしい事なんてできない。肥溜めに落ちたのはおそらく偶然だが、それを利用して僕を田中さん家へ通わせた。父はそれを知っていたのだろうか。たとえそうだったとして僕は田中さんの「大丈夫」に救われたのだから嫌な気持ちにはならなかった。感謝しているくらいだ。田中さんとの交流は人生の肥やしになったのだ。
察したが真実を知る者は誰もいない。妹なんて余計にわかるはずもない。もしも天国があるのなら3人は幸せなのだろうか。もう一度写真を眺め、手紙と共にそっと箱に戻した。僕には二人父がいる。一人は寡黙だが僕を健康な遺伝子をくれた実の父。もう一人は田中さん。「大丈夫」と野菜で僕を完成させてくれた人。何て幸せ者なんだろう。僕はそう思うことにした。