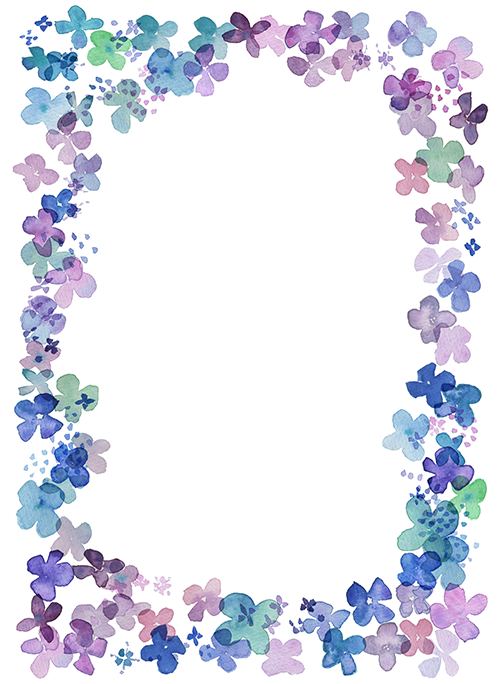放課後の美術室。
美術部に所属している私は、絵を描いていた。
私のいる美術室には、大きな長机が幾つも並んでおり、壁際には何台もの画架が立て掛けられていた。その一つ一つに生徒たちの描きかけの作品が置かれており、窓際の棚には、石膏像や静物画のモチーフが並んでいた。その隣には絵の具やパレット、筆などの画材が整然と収められていた。
教室の後ろには、文化祭に向けて制作中の大きなキャンバスが置かれ、その前には小型の画架が数台、無造作に立てかけられていた。机の上には、未だ未完成の作品たちが、重ねられていた。
美術室は静まり返っていた。
何しろ美術部の部室となっている美術室には、私と美術部顧問のサユリ先生の二人しかないのだ。
私は、美術室の後方にある長机の近くに、いつものように画架を立ててキャンバスをセットし、描きかけの絵に向き合っていた。
そして、サユリ先生は私の隣に座り、長机の上で書類を広げていた。
私は、サユリ先生をチラリと見る。
長机で書類をめくるサユリ先生の姿が視界に入る。先生は、じっと何かの書類を読み込んでいる。そんな先生は以前と変わらないように見える。
だけれど、このサユリ先生は――。
数か月前、突然、サユリ先生は、これまでの記憶を失ってしまったらしい。
それは悲しいことだったけれど、とりあえず先生が無事で良かった、と私は思った。
しばらく療養をしていた先生は、つい最近、復職した。
そして、今、こうして私とサユリ先生は再び、部活動を行えることになったのだ。
この美術部は、名簿上は部員はそれなりにいるはず、だったのだが。
実際に、この部室に来ている生徒となると、私しかいなかった。
だから、このようにサユリ先生と私だけで過ごす時間が長かった。
先生がいない間、一人で部活動をしていたのだけれど。それはどこか心細かった。
…ああ、先生が職場復帰できて、本当に良かった。
私は心の底からそう思った。
けれど、職場復帰してからの先生は、以前と比べて、どこか変わってしまったように感じることもあるけれど。
まあ、それはしょうがないことかもしれない。なにしろ記憶を失ったのだ。
しかし、ここにいる先生の様子からは、とても最近、記憶を失ったようには見えなかった。
「美術部って、高梨さんしか来ないのね。」
先生の声は、以前と変わらず柔らかい。むしろ、これまで以上に丁寧な口調になったような感じだ。
「ええ、そうです。いつもこんな感じです。」
私はそう答えながら、絵を描く。
その時、ふと、先生の座っている長机の上に置かれたパレットが目に入った。そのパレットには、アクリル絵の具が出されている。
記憶を失う前、先生はアクリル絵の具にアレルギーがあって、使えなかった。生徒たちの作品の指導も、いつも手袋をして行っていた。
すると、先生は何の躊躇もなく、素手でアクリル絵の具が出されたパレットを手に取った。
「先生、そのアクリル絵の具、大丈夫なんですか?」
「え?」
「その…アクリルにアレルギーがあって使えないって、そう聞いていたんですけど…。」
「ああ、そう。」
先生は、手にしたパレット上にある絵の具を見つめ、少し考え込んだ。
「申し訳ないのだけど、そんな症状が出ないのよ。記憶を失った影響かしら?もしかしたら、体質が変わることもあるかもしれないわね。」
先生は穏やかな笑みを浮かべながら、そのまま、アクリル絵の具で汚れてしまっているパレットを机の隅に置いた。その置き方はとても自然で、違和感はなかった。記憶喪失で、アレルギーのことを忘れているのだろう。でも、体質が変わることもあるなんて、そんなことがあるのだろうか?
私は疑問に思ったけれど。それ以上の追求をやめた。
「それはそうと、今、描いているのが、あなたの新作かしら?」
先生は、私の作品に興味を持ったようだった。
「はい。先日から描き始めたものなんです。先生、どう思われますか。」
手を止めた先生は、じっと黙って私の作品を見つめていた。絵の細部まで丁寧に観察している。その真剣な眼差しは教師として完璧すぎて、むしろ以前の先生とは違う人のように感じられた。
もしかしたら、これは記憶喪失になった先生が感じているプレッシャーのせいかもしれない。
記憶を失った先生は、きちんと教師らしい指導をしなければという気負いがあるのかもしれない。そう考えれば、この不自然なほどの完璧さも理解できる気がした。
「構図が独特ね。もう少し基本に忠実な方がいいかもしれないわ。」
「基本、というと…。」
「そうね。例えば黄金比とか、教科書で学んだ構図の基礎があるでしょう。」
「でも先生、以前は、既成概念にとらわれずにって…。」
「ええ、個性も大切よ。でも、基礎があってこその個性だと思うのよ。」
私は黙ってうなずいた。先生の言葉は正論で、むしろ、以前より教師としては正しいことを言っているようにも思える。けれど、なぜだかしっくりとこなかった。
私は描きかけの絵を眺めながら、この違和感の正体を探っていた。
「そういえば高梨さん、進路のことだけど。」
先生は、私の作品から視線を外して、私のほうへ向き直った。
「調査書によれば、ですが。高梨さんは、美術大学を考えているんでしたよね。」
「はい、以前にも相談させていただいて、その時は…。」
「ええ、でもね。」
先生はじっと私のほうを見ながら、話を続けた。
「美術大学は狭き門よ。実技も大切だけど、まずは模試の結果を見て、現実的な選択肢も考えておいた方がいいと思うのよ。」
私は先生の動きを追っていた。
身振り、素振りで先生は私へ、現実的な提案をしてくれている。
提案はたしかに参考になるものだった。けれど、違和感はある。以前の先生とはどこか違うような…。
そんなことを考えていた時、私の目が先生の手首に留まった。そこには、カッターで深く切ってしまったはずの傷跡があるはずだった。でも、跡が見当たらない。
「先生? その右手の手首の傷、治ったんですか。」
私の言葉に、先生は一瞬動きを止めた。
「右手首の傷?」
「昨年、講評会の時、壇上で転んで、持っていたカッターで右手の手首を深く切って…。」
「ええっと、そうなのね。でも、記憶がないのよ。その傷のことは、よく覚えていないの。」
先生は、右手首をそっと撫でながら答えた。
「美術の講評会の時だったんですけど。」
「そう、昨年の講評会…。ごめんなさい。まだ記憶が曖昧で。」
先生の声は穏やかだけれど、私の中で引っかかるものがどんどん大きくなっていく。
仮に記憶が完全になくなっても、身体にある傷はなくならないはずだ。
そもそも、私は先生の動きについて何か違和感を感じていた。
それをなんと表現にすればいいのだろう。それほどにそれは微かな、違和感だった。
私は、その正体を確かめるため、先生の動きをじっと観察することにした。
「先生、そういえば。」
私は、さりげなく話しかけた。
「去年の文化祭の作品を覚えていらっしゃいますか。」
先生は一瞬、考え込むような表情を見せた。
「ごめんなさい。分からないわ。」
「先生が最初の一筆を入れて、それから私たちが描き加えていったんです。『光の中の翼』って作品で。」
「ああ、そう…。」
先生は曖昧に答えた。
そして、そのまま先生は職員室から持ち込んでいる書類の整理、そして、採点作業を始めた。
私はじっと、隣にいる先生への観察を続けていた。先生は、長机の上にある書類を両手で整理し、右手でペンを持ち替えることなく採点を続けていた。
先生の右手がペンを握り、まるで長年の習慣のように自然に動いていた。
ああ、そうか。
私は違和感の正体に気がついた。
書類のページをめくる手が右手だったのだ。
さっき、先生が机の上にあったパレットをとった時、右手で持ったからだ。
そして、そして、今や…。
でも、私の記憶の中のサユリ先生は、いつも左手で絵筆を持ち、絵を描いていた。
黒板の文字を書くとき、何かモノを取るとき、絵を描くとき。全て左手だった。左利きの先生の特徴的な描き方は、美術部の誰もが知っていた。手が画用紙を汚さないように、左から右に手を滑らせながら描く独特の描き方。
だからこそ、文化祭の時も、最初の一筆を先生に入れてもらうことで、私たちだけでは、描けないような絵画を目指したのだ。
なのに、目の前の先生は。
まるで生まれながらの右利きのように、ペンを右手で持ち、自然に採点をしている。
それにしても、人間が記憶を失うことで、左利きが右利きになることなんてあるのだろうか。
それだけではない。絵の具のアレルギーや消えてしまった傷跡。
小さな違和感が、積み重なっていく。
「先生?」
美術室後方にある、長机。
そこで採点作業をしていたサユリ先生は、長机の上に置かれている答案から目を離し、静かにこちらを向いた。
そこには先生らしい穏やかさがあった。
でも、目の前の先生は、以前とは絶対に何かが違う。
腕時計の秒針の音が、やけに耳についた。
隣にいる先生が、私を見つめている。
「なぁに、高梨さん?」
先生の声は、柔らかい。
けれど。
「先生は、本物のサユリ先生じゃないですね。」
先生の表情が、微かに強張った。
「どういうことかしら?」
先生は穏やかな声を保とうとしているように見えた。私は、ゆっくりと話し始めた。
「本物の先生は左利きでした。絵を描くときも、字を書くときも、全部左手でした。それに講評会の時の傷跡…。」
私の言葉が、まるで証拠品のように発せられる。私は、視線を美術室にあった、一枚一枚の絵へと向けながら続けた。
「それに、本物の先生は、アクリル絵の具のアレルギーがありました。でも今の先生は、平気で扱っている。」
私は、そっと椅子から立ち上がった。先生は答案の置かれている長机に両手をつき、深くため息をついた。
「ずいぶん想像力豊かな推理ね。」
その声には、もう温かみが感じられなかった。
「でも、記憶喪失という説明で、全て片付くと思わない?」
先生がゆっくりと立ち上がる。一歩一歩と私のほうへと近づく先生。
その動作は、これまでに見たことのない、別人のような鋭さがあった。
「いいえ、先生…。」
私は、意を決して話を続けた。
「私はただ、本物のサユリ先生がどこにいるのかを知りたいだけなんです。」
「ねぇ、高梨さん。」
先生の声が、急に低くなった。
「あなた、そんなに熱心にサユリのことを見ていたのね。」
その瞬間、先生の手が素早く動いた。
長机の上へ伸びる手が、カッターナイフを探り当てた。
カッターナイフを握る先生の手が、カチカチと音を出して、その刃を出していた。
だが、その目は冷たく、私を捉えて離さない。
「私は、姉さんになりたかっただけよ。」
先生の声が、私に語り掛ける。その声には、これまで聞いたことのない調子だった。
どこか疲れたような響き。
それは憎しみか、それとも悲しみなのか、私には分からない。
「才能に恵まれて、生徒たちに慕われて、充実した人生を送る…。そんな姉さんが、羨ましかった。」
私は気づかれないよう、ゆっくりと後ずさる。少しでも離れるように移動をする。
「サユリ先生は、生徒一人一人の個性を大切にしていました。芸術は型にはめるものじゃないって、いつも仰っていて…。」
「うるさい!」
先生の叫び声が、密閉された美術室の中で反響した。その声に私は思わずビクっとした。
「あなたに何が分かるの?」
激高した先生が迫ってくる。私は壁際まで追い詰められていく。このまま逃げられない、なにせ、美術室の出入口側に先生がいるのだから。
「姉さんは、ただ才能があっただけ。でも、私の方が上手いはずだった。画家として、先生としても。」
先生の持っているカッターナイフの切っ先が私に向けられた。私の目は、必死で周囲の状況を確認していた。美術室の備品、画材、そして――。
「生徒のことなんて、本当は分かっていなかったんだから。ただの感性任せの指導で、基礎もろくに教えないで。」
私の視線に、近くに立てかけられた小型の画架が入った。
「私は違う。基礎から教える。理論的に指導する。感性なんて、後からついてくるもの。それなのに…。」
先生の声が途切れる。その瞬間を見逃すまいと、私は画架に手を伸ばす。
「でも、姉さんは聞かなかった。『あなたには芸術が分かっていない』って。分かっていないのは、あなたの方でしょう?」
先生は独り言のように言葉を続けていた。
その隙を使って、私は画架を掴み、身を守るように構えた。美術室に置かれた様々な作品が、私たちの姿を見つめているようだった。
「あんなに才能があっても、今となってはね。」
カッターナイフを持った、偽の先生はそう言った。画架を持ち、身構えた私の前で、彼女は不気味な笑みを浮かべていた。
「それなのに、なぜ? あなたは、そんな姉を庇うの?」
先生の姿をした、先生ではない存在が、ゆっくりと私へと近づいてきた。
それはまるで獲物を追い詰める捕食者のようにも感じた。
私は画架を構えたまま、一瞬たりとも目を離さずにその動きを追う。
私たちの間に重苦しい沈黙が流れた。
その静寂を破るように、彼女が不意に口を開いた。
「あなたは、剥製について詳しいかしら?」
声音には、どこか愉しむような響きがあった。
その突然の話題の転換に、私は一瞬、戸惑いを覚えた。
「いいえ。まったく」
意図は分からなかったが、それでも私は画架を盾のように固く構え続けた。
次の動きを、細心の注意を払って見守るほかない。
「そう?では、説明するわね?剥製はね、皮を剥ぐのよ、だから、剥製というの。腐敗する臓物や血は捨てて、作り物の新しい身体に皮をかぶせるの。」
不気味な笑みを浮かべながら、まるで授業をするように話を続けた。
「鳥や小さな動物なら、それでもまだ、簡単だわ。でも、人間でやろうとすると…。大変なのよ?まず、大きいでしょう? でも、私は姉さんをちゃんと残したかった。永遠に、ね。」
その言葉の意味を理解した時、私は恐ろしさで身体が震えた。目の前にいる存在が、もはや先生だと認識できない。
「私は、姉さんの全てを奪うことにしたの。姉さんの人生を、才能を、全部……。」
先生の声ではあったけれど、その言葉には確実に本物の先生からは聞けないはずの憎悪と悲しみが滲んでいた。私に聞かせるわけでもない、独り言のように語っている。これは言うならば、独白だろうか?
私は、なおも画架を盾しながら、ここから逃げ出すタイミングを探っていた。
「あなたにも体験させてあげましょうか? 人間が最終的にはどうなるのか?一度、そうなってしまったら、もう才能なんて関係ないことを、ね。幸い、最近の私は、ナイフの使い方に、とっても慣れているわ。……とっても、ねぇ!!!」
突然の叫びとともに、カッターナイフが私めがけて振り下ろされた。
私は咄嗟に画架――イーゼルとも呼ばれる木製の絵画立てを、盾のように突き出している。三脚のような脚に支えられた木の盾が、私の最後の防御となる。
ガッ――。
金属と木がぶつかり合う鈍い音が響いた。画架の上部が大きく揺れ、支柱に伝わる衝撃が私の腕を貫く。だが、木材は確かにその一撃を受け止めていた。
「邪魔をするな!」
攻撃を阻まれた彼女は、今度は画架の隙間を狙ってカッターナイフを振り下ろしてきた。私は決死の覚悟で画架を動かし、必死に防御を続ける。
刃が勢いよく振り下ろされる。
私を狙った刃は、幸いにも私の身体には届かず、代わりに木材の表面に打ち付けられ、そのまま折れた。
それでも彼女は、折れたカッターナイフを何度も振り下ろし続ける。
「なんでみんな、姉さんの味方をするのよ! 美術の基礎も教えないような人が、どうして!どうして!どうしてなの!」
彼女は狂ったように叫びながら、なおもカッターナイフを振り回していた。
その時、一瞬の隙が見えた。
――今だ。
私は渾身の力で画架を彼女に向かって押し出した。
「きゃっ!」
彼女は後ろによろめき、机にもたれかかる。手から滑り落ちたカッターナイフが、冷たい音を立てて床に転がった。
その一瞬の隙を逃すまいと、私は美術室から廊下へと飛び出した。
「待ちなさい!」
後ろから、サユリ先生に似た声が聞こえた。
私は一目散に廊下をかけていく。
校舎内を逃げる。
後ろからは、足音が聞こえる。追いかけてきているようだ。
けれど、私のほうが足は速いはず。
私は昇降口まで一気に走る。靴を履き替えずに、そのまま、校舎の外へと出る。
校舎から飛び出した瞬間、私は目が眩むような強い光を感じた。そのまま、校庭へと向かう。そこには部活が終わり、後片付けをしている生徒たちがいた。その中に、テニス部の友人の姿も見える。
「助けて!」
そこで、振り返ると、もう、偽物のサユリ先生の姿はなかった。それに追ってくる気配すらなかった。
間違いなく、私は助かったのだ。
◇
後日、私は警察官の取り調べを受けた。
そこで初めて、事件の真相を知った。
本物のサユリ先生は、すでにこの世を去っていた。
そして、先生を名乗っていた人物は、サユリ先生の双子の妹だった。一卵性双生児として生まれながら、幼い頃に生き別れていたその妹は、偶然の再会で姉の存在を知り、その人生に強い執着を抱くようになっていったという。
芸術の才能に恵まれ、生徒たちから慕われる姉。対して、芸術家として大成できなかった妹。その違いは、妹の心に深い傷を生んでしまった。
一卵性双生児ゆえに、同じ容姿を持っていた。そして、『記憶喪失』という隠れ蓑。それらは、違和感や矛盾を全て説明できる言葉だった。
警察の話では、本物の先生は自宅で殺害され、遺体は先生の家にあった、と説明された。それによれば、サユリ先生の遺体は妹によって加工され、剥製にされており、その遺体は、まるで生きているようだったという。
それは彼女の猟奇性を物語る事象だった。
そんな彼女は、自分自身の失踪事件から数ヶ月後、姉の記憶を失ったと偽って職場に復帰し、成り済ましたのだった。もちろん、これは完璧な計画のはずだった。
しかし、体の傷やアレルギー反応が消えることはなく、利き手が変わることもない。そして何より、芸術に対する姿勢が、本物の先生とは全く違うものだった。それらの違和感に気づいたのは、毎日のように一緒にいた私だけだった。
私は衝撃を受けながらも、取り調べを受けた次の日も、変わらずに美術室へと向かった。
私は描いている途中の自分の絵を見つめた。
きっと、これを見たサユリ先生なら、こう言ったことだろう。
「芸術とはね。あなたの感じたものを、そのまま描くことなのよ。」
私は静かに筆を取り、その絵に向き合うことにした。
美術部に所属している私は、絵を描いていた。
私のいる美術室には、大きな長机が幾つも並んでおり、壁際には何台もの画架が立て掛けられていた。その一つ一つに生徒たちの描きかけの作品が置かれており、窓際の棚には、石膏像や静物画のモチーフが並んでいた。その隣には絵の具やパレット、筆などの画材が整然と収められていた。
教室の後ろには、文化祭に向けて制作中の大きなキャンバスが置かれ、その前には小型の画架が数台、無造作に立てかけられていた。机の上には、未だ未完成の作品たちが、重ねられていた。
美術室は静まり返っていた。
何しろ美術部の部室となっている美術室には、私と美術部顧問のサユリ先生の二人しかないのだ。
私は、美術室の後方にある長机の近くに、いつものように画架を立ててキャンバスをセットし、描きかけの絵に向き合っていた。
そして、サユリ先生は私の隣に座り、長机の上で書類を広げていた。
私は、サユリ先生をチラリと見る。
長机で書類をめくるサユリ先生の姿が視界に入る。先生は、じっと何かの書類を読み込んでいる。そんな先生は以前と変わらないように見える。
だけれど、このサユリ先生は――。
数か月前、突然、サユリ先生は、これまでの記憶を失ってしまったらしい。
それは悲しいことだったけれど、とりあえず先生が無事で良かった、と私は思った。
しばらく療養をしていた先生は、つい最近、復職した。
そして、今、こうして私とサユリ先生は再び、部活動を行えることになったのだ。
この美術部は、名簿上は部員はそれなりにいるはず、だったのだが。
実際に、この部室に来ている生徒となると、私しかいなかった。
だから、このようにサユリ先生と私だけで過ごす時間が長かった。
先生がいない間、一人で部活動をしていたのだけれど。それはどこか心細かった。
…ああ、先生が職場復帰できて、本当に良かった。
私は心の底からそう思った。
けれど、職場復帰してからの先生は、以前と比べて、どこか変わってしまったように感じることもあるけれど。
まあ、それはしょうがないことかもしれない。なにしろ記憶を失ったのだ。
しかし、ここにいる先生の様子からは、とても最近、記憶を失ったようには見えなかった。
「美術部って、高梨さんしか来ないのね。」
先生の声は、以前と変わらず柔らかい。むしろ、これまで以上に丁寧な口調になったような感じだ。
「ええ、そうです。いつもこんな感じです。」
私はそう答えながら、絵を描く。
その時、ふと、先生の座っている長机の上に置かれたパレットが目に入った。そのパレットには、アクリル絵の具が出されている。
記憶を失う前、先生はアクリル絵の具にアレルギーがあって、使えなかった。生徒たちの作品の指導も、いつも手袋をして行っていた。
すると、先生は何の躊躇もなく、素手でアクリル絵の具が出されたパレットを手に取った。
「先生、そのアクリル絵の具、大丈夫なんですか?」
「え?」
「その…アクリルにアレルギーがあって使えないって、そう聞いていたんですけど…。」
「ああ、そう。」
先生は、手にしたパレット上にある絵の具を見つめ、少し考え込んだ。
「申し訳ないのだけど、そんな症状が出ないのよ。記憶を失った影響かしら?もしかしたら、体質が変わることもあるかもしれないわね。」
先生は穏やかな笑みを浮かべながら、そのまま、アクリル絵の具で汚れてしまっているパレットを机の隅に置いた。その置き方はとても自然で、違和感はなかった。記憶喪失で、アレルギーのことを忘れているのだろう。でも、体質が変わることもあるなんて、そんなことがあるのだろうか?
私は疑問に思ったけれど。それ以上の追求をやめた。
「それはそうと、今、描いているのが、あなたの新作かしら?」
先生は、私の作品に興味を持ったようだった。
「はい。先日から描き始めたものなんです。先生、どう思われますか。」
手を止めた先生は、じっと黙って私の作品を見つめていた。絵の細部まで丁寧に観察している。その真剣な眼差しは教師として完璧すぎて、むしろ以前の先生とは違う人のように感じられた。
もしかしたら、これは記憶喪失になった先生が感じているプレッシャーのせいかもしれない。
記憶を失った先生は、きちんと教師らしい指導をしなければという気負いがあるのかもしれない。そう考えれば、この不自然なほどの完璧さも理解できる気がした。
「構図が独特ね。もう少し基本に忠実な方がいいかもしれないわ。」
「基本、というと…。」
「そうね。例えば黄金比とか、教科書で学んだ構図の基礎があるでしょう。」
「でも先生、以前は、既成概念にとらわれずにって…。」
「ええ、個性も大切よ。でも、基礎があってこその個性だと思うのよ。」
私は黙ってうなずいた。先生の言葉は正論で、むしろ、以前より教師としては正しいことを言っているようにも思える。けれど、なぜだかしっくりとこなかった。
私は描きかけの絵を眺めながら、この違和感の正体を探っていた。
「そういえば高梨さん、進路のことだけど。」
先生は、私の作品から視線を外して、私のほうへ向き直った。
「調査書によれば、ですが。高梨さんは、美術大学を考えているんでしたよね。」
「はい、以前にも相談させていただいて、その時は…。」
「ええ、でもね。」
先生はじっと私のほうを見ながら、話を続けた。
「美術大学は狭き門よ。実技も大切だけど、まずは模試の結果を見て、現実的な選択肢も考えておいた方がいいと思うのよ。」
私は先生の動きを追っていた。
身振り、素振りで先生は私へ、現実的な提案をしてくれている。
提案はたしかに参考になるものだった。けれど、違和感はある。以前の先生とはどこか違うような…。
そんなことを考えていた時、私の目が先生の手首に留まった。そこには、カッターで深く切ってしまったはずの傷跡があるはずだった。でも、跡が見当たらない。
「先生? その右手の手首の傷、治ったんですか。」
私の言葉に、先生は一瞬動きを止めた。
「右手首の傷?」
「昨年、講評会の時、壇上で転んで、持っていたカッターで右手の手首を深く切って…。」
「ええっと、そうなのね。でも、記憶がないのよ。その傷のことは、よく覚えていないの。」
先生は、右手首をそっと撫でながら答えた。
「美術の講評会の時だったんですけど。」
「そう、昨年の講評会…。ごめんなさい。まだ記憶が曖昧で。」
先生の声は穏やかだけれど、私の中で引っかかるものがどんどん大きくなっていく。
仮に記憶が完全になくなっても、身体にある傷はなくならないはずだ。
そもそも、私は先生の動きについて何か違和感を感じていた。
それをなんと表現にすればいいのだろう。それほどにそれは微かな、違和感だった。
私は、その正体を確かめるため、先生の動きをじっと観察することにした。
「先生、そういえば。」
私は、さりげなく話しかけた。
「去年の文化祭の作品を覚えていらっしゃいますか。」
先生は一瞬、考え込むような表情を見せた。
「ごめんなさい。分からないわ。」
「先生が最初の一筆を入れて、それから私たちが描き加えていったんです。『光の中の翼』って作品で。」
「ああ、そう…。」
先生は曖昧に答えた。
そして、そのまま先生は職員室から持ち込んでいる書類の整理、そして、採点作業を始めた。
私はじっと、隣にいる先生への観察を続けていた。先生は、長机の上にある書類を両手で整理し、右手でペンを持ち替えることなく採点を続けていた。
先生の右手がペンを握り、まるで長年の習慣のように自然に動いていた。
ああ、そうか。
私は違和感の正体に気がついた。
書類のページをめくる手が右手だったのだ。
さっき、先生が机の上にあったパレットをとった時、右手で持ったからだ。
そして、そして、今や…。
でも、私の記憶の中のサユリ先生は、いつも左手で絵筆を持ち、絵を描いていた。
黒板の文字を書くとき、何かモノを取るとき、絵を描くとき。全て左手だった。左利きの先生の特徴的な描き方は、美術部の誰もが知っていた。手が画用紙を汚さないように、左から右に手を滑らせながら描く独特の描き方。
だからこそ、文化祭の時も、最初の一筆を先生に入れてもらうことで、私たちだけでは、描けないような絵画を目指したのだ。
なのに、目の前の先生は。
まるで生まれながらの右利きのように、ペンを右手で持ち、自然に採点をしている。
それにしても、人間が記憶を失うことで、左利きが右利きになることなんてあるのだろうか。
それだけではない。絵の具のアレルギーや消えてしまった傷跡。
小さな違和感が、積み重なっていく。
「先生?」
美術室後方にある、長机。
そこで採点作業をしていたサユリ先生は、長机の上に置かれている答案から目を離し、静かにこちらを向いた。
そこには先生らしい穏やかさがあった。
でも、目の前の先生は、以前とは絶対に何かが違う。
腕時計の秒針の音が、やけに耳についた。
隣にいる先生が、私を見つめている。
「なぁに、高梨さん?」
先生の声は、柔らかい。
けれど。
「先生は、本物のサユリ先生じゃないですね。」
先生の表情が、微かに強張った。
「どういうことかしら?」
先生は穏やかな声を保とうとしているように見えた。私は、ゆっくりと話し始めた。
「本物の先生は左利きでした。絵を描くときも、字を書くときも、全部左手でした。それに講評会の時の傷跡…。」
私の言葉が、まるで証拠品のように発せられる。私は、視線を美術室にあった、一枚一枚の絵へと向けながら続けた。
「それに、本物の先生は、アクリル絵の具のアレルギーがありました。でも今の先生は、平気で扱っている。」
私は、そっと椅子から立ち上がった。先生は答案の置かれている長机に両手をつき、深くため息をついた。
「ずいぶん想像力豊かな推理ね。」
その声には、もう温かみが感じられなかった。
「でも、記憶喪失という説明で、全て片付くと思わない?」
先生がゆっくりと立ち上がる。一歩一歩と私のほうへと近づく先生。
その動作は、これまでに見たことのない、別人のような鋭さがあった。
「いいえ、先生…。」
私は、意を決して話を続けた。
「私はただ、本物のサユリ先生がどこにいるのかを知りたいだけなんです。」
「ねぇ、高梨さん。」
先生の声が、急に低くなった。
「あなた、そんなに熱心にサユリのことを見ていたのね。」
その瞬間、先生の手が素早く動いた。
長机の上へ伸びる手が、カッターナイフを探り当てた。
カッターナイフを握る先生の手が、カチカチと音を出して、その刃を出していた。
だが、その目は冷たく、私を捉えて離さない。
「私は、姉さんになりたかっただけよ。」
先生の声が、私に語り掛ける。その声には、これまで聞いたことのない調子だった。
どこか疲れたような響き。
それは憎しみか、それとも悲しみなのか、私には分からない。
「才能に恵まれて、生徒たちに慕われて、充実した人生を送る…。そんな姉さんが、羨ましかった。」
私は気づかれないよう、ゆっくりと後ずさる。少しでも離れるように移動をする。
「サユリ先生は、生徒一人一人の個性を大切にしていました。芸術は型にはめるものじゃないって、いつも仰っていて…。」
「うるさい!」
先生の叫び声が、密閉された美術室の中で反響した。その声に私は思わずビクっとした。
「あなたに何が分かるの?」
激高した先生が迫ってくる。私は壁際まで追い詰められていく。このまま逃げられない、なにせ、美術室の出入口側に先生がいるのだから。
「姉さんは、ただ才能があっただけ。でも、私の方が上手いはずだった。画家として、先生としても。」
先生の持っているカッターナイフの切っ先が私に向けられた。私の目は、必死で周囲の状況を確認していた。美術室の備品、画材、そして――。
「生徒のことなんて、本当は分かっていなかったんだから。ただの感性任せの指導で、基礎もろくに教えないで。」
私の視線に、近くに立てかけられた小型の画架が入った。
「私は違う。基礎から教える。理論的に指導する。感性なんて、後からついてくるもの。それなのに…。」
先生の声が途切れる。その瞬間を見逃すまいと、私は画架に手を伸ばす。
「でも、姉さんは聞かなかった。『あなたには芸術が分かっていない』って。分かっていないのは、あなたの方でしょう?」
先生は独り言のように言葉を続けていた。
その隙を使って、私は画架を掴み、身を守るように構えた。美術室に置かれた様々な作品が、私たちの姿を見つめているようだった。
「あんなに才能があっても、今となってはね。」
カッターナイフを持った、偽の先生はそう言った。画架を持ち、身構えた私の前で、彼女は不気味な笑みを浮かべていた。
「それなのに、なぜ? あなたは、そんな姉を庇うの?」
先生の姿をした、先生ではない存在が、ゆっくりと私へと近づいてきた。
それはまるで獲物を追い詰める捕食者のようにも感じた。
私は画架を構えたまま、一瞬たりとも目を離さずにその動きを追う。
私たちの間に重苦しい沈黙が流れた。
その静寂を破るように、彼女が不意に口を開いた。
「あなたは、剥製について詳しいかしら?」
声音には、どこか愉しむような響きがあった。
その突然の話題の転換に、私は一瞬、戸惑いを覚えた。
「いいえ。まったく」
意図は分からなかったが、それでも私は画架を盾のように固く構え続けた。
次の動きを、細心の注意を払って見守るほかない。
「そう?では、説明するわね?剥製はね、皮を剥ぐのよ、だから、剥製というの。腐敗する臓物や血は捨てて、作り物の新しい身体に皮をかぶせるの。」
不気味な笑みを浮かべながら、まるで授業をするように話を続けた。
「鳥や小さな動物なら、それでもまだ、簡単だわ。でも、人間でやろうとすると…。大変なのよ?まず、大きいでしょう? でも、私は姉さんをちゃんと残したかった。永遠に、ね。」
その言葉の意味を理解した時、私は恐ろしさで身体が震えた。目の前にいる存在が、もはや先生だと認識できない。
「私は、姉さんの全てを奪うことにしたの。姉さんの人生を、才能を、全部……。」
先生の声ではあったけれど、その言葉には確実に本物の先生からは聞けないはずの憎悪と悲しみが滲んでいた。私に聞かせるわけでもない、独り言のように語っている。これは言うならば、独白だろうか?
私は、なおも画架を盾しながら、ここから逃げ出すタイミングを探っていた。
「あなたにも体験させてあげましょうか? 人間が最終的にはどうなるのか?一度、そうなってしまったら、もう才能なんて関係ないことを、ね。幸い、最近の私は、ナイフの使い方に、とっても慣れているわ。……とっても、ねぇ!!!」
突然の叫びとともに、カッターナイフが私めがけて振り下ろされた。
私は咄嗟に画架――イーゼルとも呼ばれる木製の絵画立てを、盾のように突き出している。三脚のような脚に支えられた木の盾が、私の最後の防御となる。
ガッ――。
金属と木がぶつかり合う鈍い音が響いた。画架の上部が大きく揺れ、支柱に伝わる衝撃が私の腕を貫く。だが、木材は確かにその一撃を受け止めていた。
「邪魔をするな!」
攻撃を阻まれた彼女は、今度は画架の隙間を狙ってカッターナイフを振り下ろしてきた。私は決死の覚悟で画架を動かし、必死に防御を続ける。
刃が勢いよく振り下ろされる。
私を狙った刃は、幸いにも私の身体には届かず、代わりに木材の表面に打ち付けられ、そのまま折れた。
それでも彼女は、折れたカッターナイフを何度も振り下ろし続ける。
「なんでみんな、姉さんの味方をするのよ! 美術の基礎も教えないような人が、どうして!どうして!どうしてなの!」
彼女は狂ったように叫びながら、なおもカッターナイフを振り回していた。
その時、一瞬の隙が見えた。
――今だ。
私は渾身の力で画架を彼女に向かって押し出した。
「きゃっ!」
彼女は後ろによろめき、机にもたれかかる。手から滑り落ちたカッターナイフが、冷たい音を立てて床に転がった。
その一瞬の隙を逃すまいと、私は美術室から廊下へと飛び出した。
「待ちなさい!」
後ろから、サユリ先生に似た声が聞こえた。
私は一目散に廊下をかけていく。
校舎内を逃げる。
後ろからは、足音が聞こえる。追いかけてきているようだ。
けれど、私のほうが足は速いはず。
私は昇降口まで一気に走る。靴を履き替えずに、そのまま、校舎の外へと出る。
校舎から飛び出した瞬間、私は目が眩むような強い光を感じた。そのまま、校庭へと向かう。そこには部活が終わり、後片付けをしている生徒たちがいた。その中に、テニス部の友人の姿も見える。
「助けて!」
そこで、振り返ると、もう、偽物のサユリ先生の姿はなかった。それに追ってくる気配すらなかった。
間違いなく、私は助かったのだ。
◇
後日、私は警察官の取り調べを受けた。
そこで初めて、事件の真相を知った。
本物のサユリ先生は、すでにこの世を去っていた。
そして、先生を名乗っていた人物は、サユリ先生の双子の妹だった。一卵性双生児として生まれながら、幼い頃に生き別れていたその妹は、偶然の再会で姉の存在を知り、その人生に強い執着を抱くようになっていったという。
芸術の才能に恵まれ、生徒たちから慕われる姉。対して、芸術家として大成できなかった妹。その違いは、妹の心に深い傷を生んでしまった。
一卵性双生児ゆえに、同じ容姿を持っていた。そして、『記憶喪失』という隠れ蓑。それらは、違和感や矛盾を全て説明できる言葉だった。
警察の話では、本物の先生は自宅で殺害され、遺体は先生の家にあった、と説明された。それによれば、サユリ先生の遺体は妹によって加工され、剥製にされており、その遺体は、まるで生きているようだったという。
それは彼女の猟奇性を物語る事象だった。
そんな彼女は、自分自身の失踪事件から数ヶ月後、姉の記憶を失ったと偽って職場に復帰し、成り済ましたのだった。もちろん、これは完璧な計画のはずだった。
しかし、体の傷やアレルギー反応が消えることはなく、利き手が変わることもない。そして何より、芸術に対する姿勢が、本物の先生とは全く違うものだった。それらの違和感に気づいたのは、毎日のように一緒にいた私だけだった。
私は衝撃を受けながらも、取り調べを受けた次の日も、変わらずに美術室へと向かった。
私は描いている途中の自分の絵を見つめた。
きっと、これを見たサユリ先生なら、こう言ったことだろう。
「芸術とはね。あなたの感じたものを、そのまま描くことなのよ。」
私は静かに筆を取り、その絵に向き合うことにした。