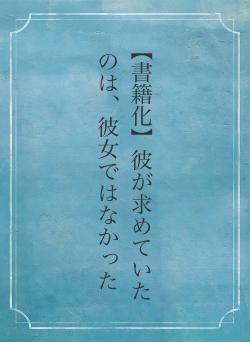いつだって、物事の終わりは突如として何気ない日常にやってくる。
母が死んだ日も、王宮に呼ばれ田舎を離れた日も、その瞬間まではいつもと変わらぬ毎日だった。
この日だって、それが来るまではいつもと変わらない日を過ごしていた。
午前に薬草を取りに王宮の裏庭へと足を運び、昼頃に所持していったサンドイッチで軽めの昼食。
そしてまだ陽が傾く前、ある程度の薬草が採取出来たところに王宮使用人たちの子供ら四人が現れた。
男の子三人と女の子一人。五歳から七歳くらいの子たち。
「マナ様、またここにいたんですね」
「今日は何して遊びますか?」
「僕、鬼ごっこしたい!」
「マナ様のお仕事の邪魔しちゃダメでしょ!」
子供たちは思い思いの言葉をかけながらマナを囲む。
その無邪気な瞳や仕草がとても愛らしかった。それに騎士たちと違い、「聖女」ではなく「一人の人間」として見てくれているようで嬉しくもある。
兄弟のいないマナにとって子供たちは弟や妹のような存在で、子供たちからしてもマナは良き姉のような存在であった。
「ありがとう、もう薬草も必要分は取れてるから大丈夫。……じゃあ、鬼ごっこ、する?」
マナは子供たちに負けないくらい元気で、にんまりとした笑顔を返す。
その笑顔を見た子供たちは「やったー!」と飛び跳ね、すぐに誰からともなく声が上がる。
「いつも通り、マナ様が鬼ね!」
「はいはい! ちゃんと逃げないと、すぐに捕まえちゃうからね!」
一斉に駆け出した子供たちに、マナは元気よく叫んだ。
楽しい時間はあっという間に過ぎていく。
まもなく夕飯の時間になるからと、空がうっすらオレンジ色になろうかという頃に子供たちと別れることになった。
「マナ様またね!」
「次こそは負けないんだから!」
みんな弾けるような笑顔で大きく手を降ってくれた。
マナは汗ばむ額を拭いながら、小さな手のひらが見えなくなるまで手を振り続ける。
心地よい疲労感と裏庭に残った明るい声に心が温かくなって、明日は何して遊ぼうかなと、童心に戻りながら裏庭を後にした。
自室へ戻ったマナは、真っ先にシャワーを浴びることにした。
それから髪を乾かし聖女服から私服に着替えると、「さあ、やるぞ」と気持ちを新たに採取した薬草の仕分けに取り掛かる。
始めてから数分後、コンコンと自室の扉をノックする音が響いた。
そのノックが、物事の終わりを告げる合図だった。
「はあい。今開けまーす」
手に持っていた仕分け前の薬草をカゴの中に戻し、軽やかに扉へと向かう。
こんな時間に珍しい誰だろうと、首を傾げながらドアノブに手をかけた。
「……!」
予想外の訪問者に思わず目が丸くなり、身体に緊張が走る。
そこにいたのはフェアラートの側近である、あの執事。
糸で吊られているんじゃないかと思うほどの真っ直ぐな姿勢で、なんの感情も乗っていない微笑を浮かべていた。
「お疲れ様です。……えと、私になにか?」
「ええ。この度、新しい聖女を迎え入れる運びとなりました。マナ様におかれましては、明日朝にはご退室いただきますよう、ご準備のほどよろしくお願いいたします」
「え……?」
「ご苦労様でした」
淡々と告げることだけ告げた執事は同じ姿勢のまま扉から離れていく。
無駄なことは決してしない、完璧主義で効率重視な執事の人格が滲み出ている歩き方だった。
それを見ているマナは、ただ呆然としていた。
晴天の霹靂、とはこういうことなのか。
本当に頭上へ雷が落ちたような衝撃で、頭と気持ちの処理が追いつかず執事を引き止める言葉すらすぐに出てこなかった。
扉の前で立ち尽くし、虚無の時間がしばらく流れる。
そうしているとなんとなく実感が湧いてきて、ふらふらとベッドまで歩くと勢いよく横たわった。
「しょうがないか。みんなの期待に添えなかった私が駄目だったんだろうし……」
納得がいかないという不満よりも、当然の結末なんだろうという、やるせなさの方が大きかった。
それと、もう暴言も言われなくなるんだという安堵感。
呼ばれたのが突然なら追われるのも突然だなと、ぼんやりと考えていたら自然と涙が溢れていた。
それを拭う手から薬草の匂いがして、今度は声を出して泣いていた。
…………
……
…
一通り泣いたマナは放心状態でベッドに横たわっている。
「お母さんの名前にも傷を付けちゃったな……」
いつも胸元にしまっている小さな絹の袋を取り出すと、その中に入れている母の形見である青いダイヤモンドを手のひらに乗せた。
深海のような深い青色をしていて、動かすたびに結晶内で輝きを変える。中に満天の星を詰め込み、見たものを虜にしてしまうような煌めき。
そんなブルーダイヤモンドだった。
────この宝石には不思議な力があるの。心からマナが何かを望んだ時、いつかマナの力になってくれるわ
今から十三年前、当時二歳だった自分に母が残していった手紙にはそう書かれていた。
不思議な力のこともわからなければ、今何を心から望んでいるのか自分自身にもわからない。
「お母さん……」
弱々しく呟くとダイヤモンドを強く握りしめ、身体を丸めた。
…………
……
…
泣き疲れたのかどうやらそのまま眠りについてしまったようで、気がついたら夜になっていた。
せめて最後にフェアラートにお礼がしたいと、また聖女服に着替え王室へと足を運ばせる。
長い廊下を足音が立たないよう慎重に、そして最後になんと言われるのだろうと緊張しながら歩いていた。
王室の前は不気味なほど静かだった。
いつも扉の前にはあの執事が立っているのだが、どうやら今日はいないようだ。
──まあ、そういう時もあるよね。
深くは考えず、ノックをする前に深呼吸をし、気持ちを落ち着かせる。
すると、中での会話が僅かに聞こえてきた。
「我が国が威厳を取り戻すのも時間の問題だな」
フェアラートの声だった。
「はい。二十年前のあの日、そして大聖女様が亡くなってからのネームルア国の評判は地に落ちる一方でしたからね。明日、正式に迎え入れる聖女の力とフェアラート様の天性の才能をもってさえすれば容易いことかと」
「必ずこの国を蘇らせ、昔以上のものにする。父上の無念……、きっと空から見守ってくれているはずだ」
あの執事と会話をしているようだ。
聞いてはまずいものだとは思いながらも、引き返そうという一歩も、ノックをしようと扉にかざした手も動かせずにいる。
いけないことなのは重々承知しているが、彼らの会話に少しだけ興味を持ってしまった。
「新しい聖女の働きには期待をしてよろしいかと。私は先に力を拝見させていただきましたが、あれは『落ちこぼれ』よりも使えますね」
執事の言葉で心音が乱れ始める。
不意に聞かされる『落ちこぼれ』はけっこう堪えた。
そして、新しい聖女。執事がそこまで言うなんてどれほどの力なのだろう。
「そうか。それにしても、マナは期待外れだったな。ドロシア様の娘だというから、わざわざ田舎から連れてきたというのに……」
「あの聖女は最後までフェアラート様の寵愛にお気づきになりませんでしたね」
「偽りの寵愛だけどな」
──偽り?
心臓の音が鼓膜を突き破りそうなほど大きく聞こえる。
これ以上はここにいない方がいい、全身がそう叫んでいた。
だが、心だけはその先を知りたがっている。マナは苦虫を噛み潰したような顔をしながらも、そこから動かずにいた。
「大聖女ドロシアの伝承だと、『皆を守りたい』という強い思いがきっかけとなって、結果魔女を封印できたんだろう?」
「はい、そのように。聖女の力の根源は他者を思いやる心だと聞きますからね」
「『なら、思いやる相手は俺でもいいはず』とわざと落ちこぼれという評判を広め、そこで俺が助け舟を出して惚れさせて、それから国のため存分に力を発揮してもらう、というシナリオだったが……。田舎育ちのじゃじゃ馬には無駄だったな」
表情こそは見えないが、それは鼻で笑ったかのような物言いで、普段のフェアラートの声色からは想像もできないものだった。
──やっぱり、あれ以上は聞くべきじゃなかったんだ。
マナは愕然とし自分のとった行動を後悔すると、聖女服を胸の上からぎゅっと強く握り扉の前から離れた。
誰かが言い出した『落ちこぼれ』はフェアラートから始まったもの。王子様のように現れ、優しくしてくれたのも全部惚れさせるため。
王子様のようなあの笑顔に射られないようにしておいてよかったと冷静に考えていながらも、大粒の涙を流しながら長い廊下を走っていた。
マナは裏庭で膝をかかえ、月明かりに照らされながら一人泣いていた。
「……お母さん。私、どうしたらいいの……」
力のないことがこんなにも悔しく惨めに感じるなんて思わなかった。
自分だって他者を思いやる気持ちは持っている。それが足りないのが原因なのか。思い詰めても答えは見つからない。
それでも延々と泣いていると不思議なもので、こんなにも悲しく辛いと思っていながらも、もう一滴の涙も流れなくなっていた。
大きなため息をつき夜空を見上げる。いつもと同じ夜空なのに、乾いた目で見る星々の光は目に刺さるようだ。
「部屋に戻ろう……」
ゆっくりと立ち上がり、この裏庭も今日で最後だったのかと名残惜しむように周囲をくるりと見渡す。
ふとあるところで視線が止まった。
数メートル先、裏庭の一部が円を描くように黒ずんでいる。マナは不審に思いながら駆け寄った。
「なに……これ……」
そう言うマナの顔は蒼白としていた。
幅一メートルくらいに黒ずんだその一帯だけ薬草や花々が枯れている。枯れているというよりは、腐っていると言った方が正しい表現かもしれない。闇の中で異様な気配を放っていた。
しかもその一箇所だけではなく、また数メートル離れた場所で同じように黒ずんでいる場所が数ヶ所もある。
──昼間にはこんなものなかったのに。
とにかく今自分に出来ることをと、マナは黒ずんだ草花を前に正座し、胸の前で手を組んだ。
「お願い……。もう一度咲いて……」
マナの身体が光に包み込まれ、その光が草花へと広がっていく。光が触れたところから草花は息を吹き返し、元あった緑々しい姿へと戻っていった。
「よかった……」
生気を取り戻したとこに一安心して、その後も黒ずんでいる一帯に祈りを捧げ続けた。
…………
……
…
蘇った薬草や花々についた露が月明かりを反射させ、裏庭を星屑のように輝かせている。
その景色を見てやっと胸を撫で下ろせた反面、大きな胸騒ぎが襲ってきた。
──あの感じ……、邪悪な魔力が込められていた。でも一体誰が……。
꧁——————————꧂
胸騒ぎが消えないまま朝になった。
昨日執事に指示された通り、朝には退去できるよう最後の整理をしている。
忘れ物がないか執拗に引き出しの中を何度も確かめた。どうせ洗濯するだろうがベッドも綺麗に整えた。聖女服もハンガーにかけシワが出来ないように仕舞った。
自分がいたという形跡を一つも残したくなかった。
身支度を終えた私服姿の自分の姿を鏡越しに見て、眉を下げながら鏡に向かって微笑む。
「……お疲れ様でした」
コットンリネンのワンピースと大きな鞄が一つ。
半年ほど前に王宮へやってきた時と同じ格好で元自室を後にした。
うつむき加減で長い廊下を歩いていると、反対側から数人の騎士を従えた白いドレス姿の女性が歩いてくるのが視界に入った。
その女性はマナと同じほどの背丈であったが体つきは全く異なっていて、豊満な胸と妖艶にくびれた腰回りをしている。紫がかった黒髪は毛先までサラッとしていて、視線を逸らせない大きい目、そして綺麗と可愛いを凝縮させた小さい顔。
マナは瞬時にこの女性が新しい聖女なのだと理解できた。
女性が来ているドレスを着たことがある。それは半年ほど前、王宮で行われた聖女就任式の時に着たドレスに違いなかった。
使い回してたのかと怪訝な顔にもなったが、その女性の美貌と身体の曲線美から同じドレスとは思えないほどだった。
女性は嘲笑った顔でマナと目を合わせ、そのまま優雅に横を通りすぎていく。
きっとフェアラートか執事から旧聖女のことを聞かされたんだろう、それは『落ちこぼれの聖女』を見る表情だった。
これからあの女性、新聖女の就任式が行われる。でも、マナには何も告げられていない。
それはまるで、「初めからいなかった者」として扱われているようだった。
「……最後に裏庭だけ見ておこう」
昨晩の異変が気掛かりで、マナはまた裏庭へと向かった。
………
……
…
裏庭自体はいつも通り綺麗な緑の絨毯が広がっている。
「良かった……」
そう胸をなでおろしたのは束の間でしかない。
昨晩よりも、もっと異変なことが起きていた。裏庭と繋がった数キロメートル先にある森の方だけ夜のように暗い。
普段は基本立ち入り禁止になっている森。あの森の奥深くで、母は魔女を封印したと言われている。
「昨日から何かがおかしい……」
昨晩の比にならない胸騒ぎが全身を脈打つ。
不安と恐怖で足が震えたが、意を決して森へと足を踏み入れる覚悟を決めた。
꧁——————————꧂
マナが森へと動いたその頃、王宮内にある教会では新聖女の就任式が開かれていた。
主祭壇の中心ではフェアラートが椅子に腰掛け、その右隣にいる近衛騎士が起立しながら式を進めている。
執事はフェアラートの真後ろで直立しており、左隣ではあの聖女が手を前に組んではんなりと立っていた。
「この女性こそが此度正式に迎え入れた我が王宮の新しい聖女、リリィ=フレイヤ様である!」
近衛騎士が張り上げた声で新聖女──リリィを紹介する。
リリィはゆっくりと足音を立てずに前に出ると優美な一礼をし、すぅと息を吸い込む。
「ただいまご紹介にあずかりました。新たにこの地区を守護させていただきます、私リリィ、と申します。『あの大聖女』が守ったこの地区を私が守護させていただけるなんて、恐れ多くも感謝でしかごさいません。皆様と力を合わせ更にこの地区を、そして王国を、良きものへと変えていく手助けが出来ればと思っております。不束者ではございますが、何卒よろしくお願いいたします」
教会に集められた人々は盛大な拍手をリリィに送る。男女問わず、皆見惚れていた。
リリィの完璧な抑揚と言葉の間、そしてお辞儀までの所作。国が国なら、この立ち振る舞いで天下を取れてしまうんじゃないかと思うほど美しいものだった。
見惚れていた近衛騎士も我に返り「ごほん」と咳払いをして司会を続ける。
「昨日、すでにリリィ様から『聖なる光』を授かった者もいる。その者にはリリィ様のお力がどれ程なのか伝わっていると思うが、きっと皆、リリィ様こそが第二のドロシア様に相応しいと実感しているだろう。その聖力、包容力、そしてこの美貌。我が王国に偉大なる功績をもたらす聖女……いや、大聖女となるだろう!」
近衛騎士が手を振りかざしたと同時に、教会内に大きな歓声と拍手が響き渡った。皆リリィを歓迎している。
しかし。
天使のように微笑んでいたリリィの顔が冷たく奸悪なものへと変わったことに、誰一人として気がつかなかった。
「木が……腐ってる……」
森の様子を見たマナは途方に暮れた。
見渡す限りの木々は腐り落ちるよう変色し、一切の光が遮断された不気味な光景が広がっている。
「私の力でどうにかできる話じゃ……」
あまりにもひどい有り様を目の前にして自分の無力感に胸を締め付けられたが、大きく首を振って深く息を吸い込んだ。
自分が諦めてしまったら、この森はもう元には戻らない。
「……やらなきゃ! 私にしか出来ない!」
ぐっと拳を握り気を引き締める。
──大丈夫、出来る。
自分を信じ、その場で膝をつくと、マナは目をつむり祈りを捧げ始めた。
…………
……
…
「なあんだ、落ちこぼれの聖女じゃない」
正面から聞こえた声は、小馬鹿にした笑みを含んだ女の声だった。
祈りを遮られたマナは驚きを隠せず目を見開く。
「……!!」
そして、言葉を失い凝然としてしまう。
その声の主が、さっき王宮内ですれ違ったあの白いドレスを身にまとっている聖女だったからだ。
その聖女はマナに近づき、見下すよう前に立った。
「言葉が出てこないのかしら? それもそうね。じゃあ、自己紹介をしましょう。私はリリィ。この地区の新しい聖女よ」
また嘲笑った顔で、捲くし立てるようにリリィは喋る。
「……あなたは……、なに?」
唾を飲み込み、やっとの思いで口を開いた。
その聖女に恐怖心と不快感を抱き、後退りするように立ち上がり距離を取る。
「なにって、新しい聖女だって……」
「……違う! あなたからは聖力を感じられない! 今のあなたから感じるのは、昨日と今日この場所に残されている魔力、それと同じ!」
マナは視線を鋭くし、息を荒くしながらリリィの言うことを否定する。
はっきりとわかった。あのどうしようもない胸騒ぎの原因は、この女性が作り出したものだった。
その視線を見たリリィは肩を小さく震わせ始める。
「……っ、ふふっ……」
「何が……おかしいの?」
「……っ、あははははは」
リリィの高笑いが響く。
その綺麗さと忌ましさに足がすくんでしまいそうだ。
「そうね、確かに私がやったことだわ」
「……あなた、何者なの!?」
目の前にいるマナに心底興味がなさそうなリリィは、ふうとため息をついて着ているドレスをつまみ上げた。
「ねえ。聖女って、どうしてこう白い衣服を着せられるのかしら。神に仕える? 高潔で清純? 本当、馬鹿馬鹿しいしきたりよね」
「……何言って」
「どうせ着飾るなら……」
言葉を遮ってきたリリィは、自分の着ているドレスを撫で始める。
彼女が手をかざしたところから、漆黒の水に染まるようドレスが黒くなっていく。
「こういう何もかもを飲み込む黒が良いと思わない?」
同意を求めるよう、こちらに向かって微笑んでくる。
その魔力と笑顔の悍ましさに一つだけ、この女性がなんなのか思い当たることがあった。
「あなた……、魔女……?」
戸惑っているマナにリリィは呆れ顔をしてみせた。
「あんまり言いたくはないけど、封印された魔女の名前くらい覚えておくものじゃない?」
ふんっと軽く息を吐き髪をかき上げたリリィは、また饒舌に話し始める。
「……まあいいわ。そうよ。私ね、昔この奥で封印されてしまったの。あの忌々しい聖女ドロシアに。でもあいつ、私にトドメを刺さなかった。だからこうして復活出来た。つくづく馬鹿な女よね」
あははと笑うリリィに心底腹が立つ。
「……お母さんを! 馬鹿にしないで!」
先ほどよりも鋭い双眸で睨みつけるマナを、リリィは上から下まで舐めるようにじっと見つめ
「……、そう。あなた、あの女の娘なの。似ても似つかないわね」
と、鼻で笑う。
「で、『お母さん』は今どこにいるのかしら? わざわざ聖女のフリまでして余興を仕込んできたの。そろそろドロシアと本番といきたいんだけど」
「お母さんはもう……いない。この地区に結界を張って、それからしばらくして……」
「あら、あの女本当に死んでたの。にわかには信じられなかったけど、娘がそう言うなら事実ってことね。この手で復讐出来なかったのは残念だけど、私はこうしてまた地上に降り立った。私の勝ちね」
魔女はどこまでも逆撫でしてくる。
リリィの勝ち誇ったかのような笑い声は、マナの胸を怒りで満たすのには十分すぎるほどだった。
「それ以上お母さんを侮辱しないで!」
封印は無理でも結界を張るくらいは、そう思いながら怒りに任せて聖力を放つ。
だがそれをリリィは涼しい顔で受け流した。
「なあにそれ? そんなちっぽけな聖力で私に結界を張れるとでも思った? 無理に決まってるじゃない。まず魔女を倒したいのなら……、そうね、悪魔かドロシア並みの聖力を持ってからにしなさい? ねえ、ドロシアはそんなことも教えてくれなかったの?」
リリィはわざとマナを煽っている。
「ドロシアの娘に復讐したい」という思惑ではなく、ただただリリィ本人が楽しみたいというだけの理由だった。
「いい加減にして……!」
リリィの言葉に乗せられたマナは我を忘れて、無駄だと分かっていてもまた聖力を放ってしまう。
マナの聖力を正面で受け絶望させるように弾き飛ばすと、リリィはまたひと笑いをした。
「そんな聖力じゃ、結界どころか傷一つだってつけられはしないわよ」
力の差を痛感し、マナはその場でうなだれてしまう。
──どうやっても、今の自分ではリリィに勝てない。
マナの力量の程度がわかったリリィは態度を急変させた。彼女の顔から笑みが消える。
所詮はただの娘、リリィにとって何の楽しみにもならない存在だった。
「……もういいわ。あなたと遊ぶのにも飽きた」
ため息をついたリリィは冷たい目と声で蔑むと、そのままパチンと指を鳴らしマナを囲うよう結界を張り巡らせた。
「結界魔法っていうのはこうやって使うのよ。あなたはそこで国が滅ぶ様を見てるといいわ。まずはあの女が守ったこの地区から殲滅させるの。そして今度こそ私の国にする……! ああ、考えただけでゾクゾクしちゃう」
「……そんなことさせない!」
「今のあたなに何が出来るの? その結界も壊せないでしょう? じゃあね、落ちこぼれの聖女様」
リリィは手のひらをひらひらと振り、笑い声だけ残して消えていった。
꧁——————————꧂
就任式の行われた教会では、先ほどの歓声が悲鳴と怒号に変わっていた。それは教会の外まで続いており、剣の混じり合う音が耳をつんざくように鳴り響き、獣のような呻き声が轟いている。
騎士と、かろうじて人間の形をしている魔物が戦っていた。
「あらあら、なかなかいい余興じゃない」
マナといた森から戻って来たリリィはフェアラートのそばに寄り、その様子を見て満足そうに微笑んでいる。
「リリィ! 今までどこに! それにその服! ……いや、手を貸してくれ! 騎士たちの一部が急に魔物に姿を変え襲い始めてきた!」
剣を持ち切羽詰まった様子で情願するフェアラートにリリィは素知らぬ顔をすると、するりと彼の腕に自身の腕を絡ませ、なまめかしい瞳でフェアラートを見つめた。
「何を……!」
「ああ、なんて可哀想な国王様。自分の従者と戦うはめになるなんて。でも最高のシナリオね、いいわ」
「何を言っているんだ!? 聖女なら今こそ力を示す時だろう!?」
余裕のないフェアラートは険しい顔をしていて、いつも以上に口調が荒々しい。
その追い詰められた姿はとても王子様とは言い難いものだった。そしてそれをリリィは「美しいものが歪んでいるのもまた美」だと光悦し、くすりと笑う。
「残念。私、聖女じゃなくて魔女なの」
「……魔女だと!?」
フェアラートは腕を振り払おうと試みるが、リリィの腕はそこからぴくりとも動かない。
「そうね、最後に良いことを教えてあげる。魔物になった騎士たち、昨日私から『聖なる光』とやらを受けた奴らよ。ふふっ、聖なる光……。笑っちゃったわ」
「……初めから騙していたのか!?」
「おかげさまで楽しい余興になったわ。本番のお楽しみがなくなった分、しばらく高みの見物でもさせてもらおうかしら」
「ふざけ……」
るな、と言い切るより前にリリィがフェアラートの脇腹を短剣で刺していた。
そのままふわりとフェアラートに抱きつき耳元で囁く。
「やっぱりいいわ。鍛えられた男の若い肉、そしてその中に入っていく感触……。短剣だとね、魔力よりも原始的で直接的にヒトの感触を味わえるの。それに秀麗なものが崩壊していく瞬間……。生きてるって実感する」
リリィは片手でフェアラートの身体を押し、ゆっくり短剣を抜き取る。
勢いよく血を吐き跪くフェアラートの姿にリリィはまた興奮した。
「今刺したところは腎臓なの。人間って腎臓が二つあるでしょう? だから一つ潰れても大丈夫。あなたは綺麗だからすぐには殺さないわ。真紅の薔薇のように染まっていく国王様……、その顔を少しでも長く見せてね」
リリィが上空へ浮かび上がると同時にフェアラートはその場に倒れ込む。
すぐそばで戦っていた騎士がその姿を目撃し声を荒げた。
「誰か! あの聖女を! マナ様を早く呼んでこい!」
マナは結界を破ろうと必死に足掻いていた。
治癒魔法、鎮静魔法、解毒魔法、浄化。
いろいろなことを試みているが結界は破れずにいる。あの魔女の言った通りなのが悔しくてたまらない。
どうやっても打破できない現状が、マナの目を腫れさせている。
王宮の方から何度目かの衝撃音が聞こえた。空気を振動させて地面さえも揺らしているかのような音。
「一体なにが起きているの……!?」
マナは息を呑んだ。
一刻も早くこの結界から出なくては。
しかし、感情の赴くまま結界を叩いても破れることはない。
為す術のなくなったマナの耳に、聞き馴染みのある声が微かに入ってきた。
「……怖いよお」
「……なんでこんなことに」
「……助けてよお」
「……マナ様どこぉぉ」
あの四人の子供たちの声だった。
精一杯恐怖に立ち向かう、怯えたような声。
「あなたたち!」
マナは思わず大きな声を出した。
最年長の男の子が何かに気付いたような素振りを見せていたので、もう一度大声で呼びかける。
今度ははっきりと気が付いてくれたようで、子供たちが必死に駆け寄ってきてくれた。
最年長の男の子を除いた三人が泣きじゃくり、男の子はマナを見上げて潤んだ瞳ですがりついた。
「マナ様! 助けてください! 王宮の周りが真っ暗になっていて、いま魔物と騎士たちが戦っているんです!」
「そんな……」
──リリィの仕業に違いない。
ぎゅっと唇を噛み締める。
「……『マナ様を呼べ』っていろんなところから声が聞こえて……、また裏庭にいるかと思って……。それで、裏庭まで来たら……森の様子がおかしいって……入っちゃって……うわああん」
嗚咽まじりに話した男の子も張り詰めていた糸が切れたようで、他の子供たちと同じようにわあわあと泣きはじめた。
──許せない。
静かに沸々と怒りがこみ上がってきた。
リリィは二十年前の続きを楽しんでいる。それだけじゃない。母に封印され阻止された国盗りを再開しようとしている。
自分ではリリィに攻撃することすら叶わない。
それでも、母が守ったこの地区が崩壊していく瞬間を、指を咥えて我慢しているだけなんて出来るはずがない。
「……わかった! 私がなんとかする! こんな結界すぐに壊してみんなを助ける! 教えてくれてありがとう!」
子供たちを励まし勇気づけるため笑顔に努める。少しでも不安を取り除きたかった。
「ここは危ないから、森から出て裏庭のもっと遠くへ逃げて。全部終わったら、また一緒に鬼ごっこしようね」
マナの優しい微笑みに子供たちは頷いて涙を拭く。最年長の子が皆を率いて森の外へと走っていった。
「私に力がないばっかりに……。ごめんなさい……」
マナは胸元に手を当て、形見であるブルーダイヤモンドを取り出した。
両手で強く握りしめ、母のことを思い出す。
───心からマナが何かを望んだ時、いつかマナの力になってくれるわ
母の言葉が響く。
心から何を望んでいるか、今ならわかる。
「お母さんお願い……。お母さんのように、私もみんなを助けたい。守りたい……! だから、私に全てを守れる力を……」
祈りと共に手を合わせると、ブルーダイヤモンドから青白く強い光が溢れだす。
その眩しさにマナは思わず目をつむってしまった。
…………
……
…
恐る恐る目を開けてみると、何をしても破れなかった魔女結界が破れていた。
「結界が……。お母さんの力……?」
マナは不思議そうに辺りを見回す。
「俺の力だ」
耳にしたことのない声が頭上から聞こえた。
見上げた先の空に浮いていたのは、大きな漆黒の翼を広げている男だった。
黒く長い髪をなびかせ、騎士のような服装で身を包んでいる。そして、その服さえも黒い。
切れ長で鋭い目つきの奥にある瞳は、ブルーダイヤモンドのように鮮やかで深みのある青い輝きをしていた。
「俺を召喚したのはお前か?」
男はいぶかしげにマナに問う。
──召喚……? この男の言っている意味がわからない。でも、結界を破ってくれたのも……この男?
マナは状況の整理が追いつかなく困惑していた。恐々と言葉を選びながら、手中にあるダイヤに祈っただけだと伝える。
「ダイヤか。見せてみろ」
男はゆっくりと空から降り立ち、マナの握っているブルーダイヤモンドを見て瞬時に答えを出した。
「この中には魔法陣が描かれている。召喚の魔法陣だ」
「……そんなの見えたことない」
改めてダイヤモンドを凝視したが、やはり中に見えるのは煌めいている結晶だけだった。
「魔法しか知らないお前らでは見えんだろうな。これは魔術、全くの別物だ」
───魔術。
大昔に禁忌とされ、使うものは誰もいない。
母の形見になぜ魔術が?
男の言葉にマナの困惑は深みを増していく。
顔をしかめながら手のひらのブルーダイヤモンドを眺めるが、やはりマナからしたら綺麗な宝石でしかない。
「で、聖女様が悪魔を召喚してまで叶えたい願いとは何だ?」
男は機嫌が悪そうに腕を組んでいたが、マナは状況を整理するので精一杯だった。
──悪魔?
男は確かにそう言った。感じたことのない魔力に黒い翼で空を飛んでいたことから、普通の人間ではないと思ってはいた。
でも、それがよりによって悪魔だなんて。
───いつかマナの力になってくれるわ
母の言葉が脳内をよぎる。
力? この悪魔が? どんどんと頭の中がごちゃごちゃになっていく。
「さて、何を願うか決まったか? 力か、金か、あるいは死か……。なんでも叶えてやる。ただし、これは契約。その代償はしっかりいただいていく」
マナの心情など知るはずもない悪魔は青色の瞳をぎらつかせ、いやらしく笑っていた。
「私は……、あなたを召喚したつもりはないし、あなたに叶えてほしいこともない……!」
マナは強張った顔で悪魔を見つめる。
わからないことだらけだ。それでも、聖女が悪魔と契約だなんて、そんなことあってはならない。それだけははっきりとしている。
すると、悪魔はいらやしい笑みを浮かべたまま近寄ってきた。
「強情な女は嫌いじゃないが、お前が俺を召喚したのは事実だ。それに……」
悪魔はマナのあごを人差し指ですくい上げ
「聖女の血肉、特に心臓は他の人間のそれよりも美味だと聞く。どんな味なのか……先に堪能してしまおうか」
と、人差し指を左胸に滑らせた。
身体にゾクッと恐怖が駆け巡る。それはまるで、心臓にナイフを突きつけられているような感覚。
悪魔の青い瞳は吸い込まれそうになるほど不気味で、澄み切った星空のようにまばゆい。そして、笑った口の中に鋭どく尖った歯が見えたことがまた恐怖心を煽られた。
マナの身体が恐怖で硬直した直後、再度王宮の方から衝撃音がした。
その音で正気を取り戻す。そうだ、早く王宮へ行かなければと、悪魔の手を振り払った。今本当に困っているのは自分ではなく、王宮にいる人たちだ。
マナは一目散に王宮へと走り出す。
「……なるほど、この気配は魔女か」
悪魔は不敵に笑いながら、走っていくマナの後ろ姿を眺めていた。
普段見ていた場所の変わり果てた姿に、マナは言葉を失った。
子供たちが言っていたように、王宮は森と同じく闇のように暗い。瓦礫が重なる王宮、理性がなくなり暴れている人型の魔物、負傷してうめき声を上げる騎士たち。
地獄があるとするならばこういう場所なのだろう。
その上空では、あの魔女が愉快犯のように笑っている。
怒りで眉を吊り上ながらリリィに視線を向けるも、彼女に出来るのは憎しみを向けることだけ。
悔しさと怒りを押し殺し、今出来ることをと、倒れている騎士たちの治癒を始める。
「お願い……死なないで……! もう大丈夫ですから! 頑張って!」
マナは必死に声をかけ続けながら、手当たり次第に負傷している人たちの治療をしていく。
次に目に入った騎士は仰向けで倒れ込んでいて意識がないように見えた。
すぐに近寄って心音を確認する。
「……! まだ息がある!」
急いで治癒魔法をかけると、騎士はぴくりと身体を震わせて意識を取り戻した。
「…………っがは!」
「良かった! 気が付きました!?」
「…………マナ……様?」
意識を取り戻した騎士は虚ろな目をしていて喋るのもやっとそうだ。
「大丈夫ですか?」
その問いに、騎士は小さく首を縦に振って答える。
心の傷は治癒魔法では治せない。
なるべくその傷が悪化しないようにと、マナは明るく穏やかに振る舞う。
「なら良かったです。動けるようになったら、すぐに避難してくださいね」
「…………マナ様……」
騎士は朦朧とし震えながら手をこちらに差し伸べてきた。
指先は力が入らないようでだらんとしている。
──感謝の握手? それとも他に?
意図はわからなかったが彼を不安にさせないよう微笑み続けていると、彼の口が微かに動いた。
「………う、しろ……に」
警告に気づき急いで振り返る。
そこには一匹の魔物がいた。長く大きく鋭利な爪を、こちらに振り降ろそうとしている。
助けを求める間も神に祈る間もなく、反射的にぎゅっと強く目をつぶるしかできなかった。
────ギィィィンッという鈍い金属音が耳を刺す。
鼓膜に響く音だったが、引っかかれるか最悪切り裂かれるかと身構えた身体はどこも痛くない。
眉を寄せたまま右目からそろりと開く。
目に入ってきたのは剣を持って立っているあの悪魔と、倒れて微動だにしていない魔物の姿だった。
「もしかして、助けてくれたの……?」
「契約前に死なれては元も子もないからな」
どうやら善意で助けたというわけではなさそうだ。悪魔らしいと言えば悪魔らしい。
それでも助けられたのは事実であり、その行動に少し驚きつつも感謝をするしかなかった。
「……ありがとう。これでまだ傷ついた人たちを助けられる」
「随分とご立派な聖女様だ。お前ごときの力でなんとかなるとでも?」
悪魔は薄ら笑い皮肉めく。
なんと言われてもいい。力のあるないではない。
聖女として、母の娘として、一人の人間として、出来ることをやらなければ。
「……私には、この人たちを助ける役目がある……! だから悪魔……、あなたにはあの魔女を倒してきてほしい!」
意思の固まったマナの顔に怯えや恐怖の色は見えなかった。
その言葉を聞いた悪魔はにやりと笑い口元から牙のような歯をのぞかせる。
「それは契約か?」
悪魔はまたあごを持ち上げてきた。
「……悪魔と契約はしない。これは『お願い』。悪魔なら倒せるんでしょう? 悔しいけど、もうあなたにしか出来ない」
なにがあっても皆を守る、助けると心を決めたマナの言葉は力強く、己の信念と悪魔への信頼感で満ちている。
悪魔は食い入るように瞳を覗き込んでくる。そして、こちらもじっと悪魔の瞳を見つめ返す。
数秒ほどし、悪魔の方から手を離すとふっと微笑んだ。
「悪魔に指図とは、どこまでも強情な女だ。いいだろう、せっかくの地上だ。俺も楽しみたいと思っていた」
「悪魔……!」
マナの表情が自然と綻ろぶ。
「ただの気まぐれだ。それと、俺の名は『悪魔』ではない」
悪魔は剣を握り直し、静かに告げる。
「レイ=ディアダマス」
そう名乗った悪魔は上空へと飛び立った。
꧁——————————꧂
レイが空へ飛んだ後も、マナはひたすらに治療を続けている。
さすがに疲労の色が見えていた。
連続して治癒魔法を使っているのもあるが、模擬戦の時と違い皆損傷が激しく、一人あたりに費やす聖力が増えていたのも原因だった。
「いたぞ! こっちだ!」
少し先の方から騎士の急き込む声が聞こえてくる。
ただならない様子でこちらに駆け寄ってくる騎士の動揺や声色から、只事ではないことはすぐに察せられた。
「マナ様……!」
「どうしたんですか!?」
「フェアラート様が……!」
騎士は顔面蒼白で息を切らしながら助けを求めてきた。
教会の方でフェアラートが倒れている、重症だ、早く来てくれと、騎士に手を引っ張られその場へと駆け出した。
うずくまるようにして倒れているフェアラートからは生気を感じられず、血の気もありそうにない。
彼の純白の貴族衣装が真っ赤に染まり、おびただしい出血は地面までも赤くしている。
かろうじて意識はあるようだが目は焦点が合っておらず、だらしなく開いた口からは血を垂れ流していた。
その光景に一瞬顔が引きつってしまう。
見るからに、この戦場でフェアラートが一番死に近かった。
「……できる限りのことはやってみます!」
気を張り直し、フェアラートのそばで膝をつき治癒魔法をかけ始める。
昨夜聞こえたフェアラートと執事の会話が脳裏をちらつく。
この王宮で虐げられる発端を作ったのはこの人。優しくしてくれていたのも嘘。それを知った時どんなに辛く悲しかったか。
それでもマナは治癒魔法を止めなかった。
「絶対に死なせない……!」
みんなを助け守るために自分はここにいるんだと、さらに聖力を込めた。
マナが騎士に手を引かれフェアラートの元へ走っている頃、リリィは上空で大きなため息をついていた。
その表情はどこか退屈そうだ。
「フェアラートの顔も見飽きたし、そろそろこの余興もおしまいかしら」
リリィは持っている短剣を手持ち無沙汰な様子でくるくる回している。
その瞬間、彼女の前に一人の男が現れた。
「ならば俺と違う余興でもするか?」
男は挑発的な笑みを浮かべている。
リリィは突如現れた男に驚きながらも、すぐにそれが何者であるかを理解したようだ。
「……これはまた珍しいわね。悪魔が地上にいるなんて、どういう成り行きなのかしら。でもそうね、本番のお楽しみはないわけだし、貴方と殺り合うっていうのも素敵かもね」
リリィはレイの挑発に乗り、楽しげな表情をしながら唇に手を当てる。
「ずいぶんと舌が回る魔女だ」
「だってニ十年ぶりの地上よ! 楽しくないわけがないじゃない! ずーっと魔法を使えなかった分、魔力も溢れているの。そう! 今なら悪魔にだって負ける気がしないわ」
リリィはますます饒舌になり、高揚しながら笑ってみせる。
「封印され己の力量すら測れなくなったか。魔女ごときが悪魔に勝てるはずないだろう」
「……やってみなきゃわからないじゃない!」
「無理だな。まあ、精々しらけさせないようにしてくれよ」
痺れを切らしたようにぎりっと奥歯を噛んだリリィは、勢いよく手のひらを前にかざす。
「そうやって……! 余裕ぶってられるのも今だけよっ!」
黒い渦と雷が合わさった魔法が、凄まじい速さと威力でレイの方へと向かっていった。
──やっぱり魔力が溢れている。
そう実感したリリィは自分の手を眺め、色香のある吐息を漏らす。
だがレイは冷静にその魔法を見据え、剣を盾にして防ぐ。まるで何事もなかったように無表情だ。
「ふふっ。そうよね、あんなくらいじゃ倒れないわよね。……でも次はどうかしら!?」
リリィは愉悦に浸りながら微笑み、先ほどの魔法を今度はレイの四方を取り囲むように放った。
レイの周囲は黒い渦に巻かれ黒光りする雷で充満していく。その光景と大きくうねりを上げる大気にリリィは恍惚とした。
「あはっ、綺麗ね。さすがの悪魔も跪いたんじゃない?」
クスクスと笑うリリィだったが、放った魔法が何かに吸い込まれるようにして消滅していくのを目の当たりにし、その笑みの横でじわりと冷や汗をかいた。
「終いだな」
レイは嘲笑う。
「……そんなわけないじゃない! まだ全力じゃないわ!」
リリィがまた手をかざしたと同時に、レイは瞬間移動したかの如く距離を詰め彼女の手首を掴んだ。
「もう少し楽しめると思ったんだが」
「……っ!!」
冷たい手の感触にリリィは動揺を見ると、レイは冷酷な笑みを浮かべ、囁く。
「魔女の肉は腐敗臭がして不味い。そして俺は不味いものは食わない主義だ。良かったな、魔女で」
「はあ!?」
「死を理解する間もなく死ねるぞ」
「だから! そうやって余裕ぶっ…………」
レイが音もなく振り下ろした剣は、すでにリリィの身体を二つに分けていた。
そのままリリィは塵となり消えてく。
彼の言葉通り、リリィは自分が斬られたと理解するよりも前に消滅した。
「魔術を使うまでもない。余興にもならなかったな」
魔女の消えていく様を鼻で笑い、マナのいる方向を探した。
꧁——————————꧂
マナはフェアラートを救うため、騎士たちが見守る中祈りを続けている。
治癒を初めてから一分ほどだろうか、フェアラートが勢いよく吐血し咽せるように咳き込んだ。
息を吹き返したことに安堵しつつ、そのまま治癒を継続する。
「……マ、ナ…………」
フェアラートが口を開き意識を取り戻した。おぉ、と騎士たちの安堵した小さな歓声が漏れた。
虚けながらも目の焦点にブレはなかったので、もう峠は越えただろう。
マナのこわばっていた顔から力が抜けていく。
「はい。意識が戻ってよかったです。でももう喋らないでくださいね。内蔵の損傷が酷くて、あと少しかかりますから」
「……すまない」
「とんでもない」
にこりと微笑むと、フェアラートはゆっくりと目を閉じた。
…………
……
…
「……もう大丈夫です」
大まかな治癒を終えたマナは息をつく。
額に大量の汗をかいている。そのくらいフェアラートに聖力を尽くしていた。
完治にはまだ時間と治癒魔法が必要だが、ひとまず血の気の戻った彼の寝顔にやっと心から安心できた。
騎士たちは歓声を上げ、次々とマナに感謝の言葉を述べ始める。
「おい、これはなんの騒ぎだ?」
その喧騒に、レイが怪訝な顔をしながら寄ってきた。
「マナ様、この方は……?」
見慣れない顔と服装に騎士たちがざわめく。
当然悪魔だとは言えず、
「知り合いです! 目が覚めるまでフェアラート王のそばに!」
と不自然な作り笑顔で言うと、レイの背中を押して逃げるようにその場から離れた。
「……魔女は?」
「お前の『お願い』通りだ」
「本当……?」
疑いの言葉をかけたものの、レイが一人で戻ってきたということは、そういうことなんだろう。
確かにあの魔女の魔力は感じられない。
レイの言う通り、魔女は消えた。
しかし、闇のような空間は一向に晴れず、魔物に変えられた騎士たちも人間に戻らない。
そんな困惑を察したのか、レイがその答えを呟いた。
「魔女の残痕か」
「残痕…?」
聞いたことのない言葉だった。
「呪いみたいなものだ」
「……どうしたらその呪いは解けるの?」
「普通の呪いならばかけた本人に解かせたりもできるが、残痕となれば誰かが浄化するしかあるまい」
「浄化……」
浄化は治癒や解毒魔法などより高度な魔法で聖力の消費も激しい。
今の自分にそれだけの聖力が残っているのか、仮に全快だったとしても王宮全体を囲んでいるこの空間を浄化できるのか。
マナの顔が曇っていく。
「レイは……浄化の魔術とか使えないの?」
「悪魔がそんな神聖な魔術を使うと思うか? 消滅ならすぐにでもやってやるが」
小馬鹿にしたようにレイが答えてきた瞬間、自分がどれだけ愚かな質問をしたのかに気がついた。
焦燥感に駆られ口にしてしまった言葉、それがまた自分の無力さを痛感させられる。
──今の私にできることって何?
そう思い詰めていると、ふとマナとレイの間隙を縫うように「お願い! しっかりして!」という女の人の悲痛な叫びが割り込んできた。
聖力が残っておらず体力も底を尽きそうだったが、その切実な声にマナの身体は自然と反応していた。
「どうされました?」
マナは女性の肩に手を添えて、落ち着かせるようにゆっくりと話しかけた。
「夫が……魔物になって倒れたまま……。夫だけじゃありません、就任式の途中で騎士たちが変貌していって……」
女性は顔を手で覆い、さめざめと泣き始める。
この夫婦以外にも大事な家族、恋人、友人がリリィの被害にあっているに違いない。
魔女が消えても傷痕は残り続ける。残痕とはよく言ったものだ。
そしてその傷痕を消せるのが聖女であるならば、答えは一つ。
「安心してください。私がなんとかしてみせます」
マナは王宮の中心となる場所を探す。
おおよその目星をつけ、そこに膝をつけると胸の前で手を組み静かに目をつむった。
治癒魔法の時とは違った、真珠のような虹彩をした清澄な光がマナの身体を包み、その浄化の光はマナを中心にして拡大していく。
──もっと広く、もっとたくさんの人まで。
眉間にしわを寄せ強く目をつぶり一層聖力を強める。
しかし限界に近いマナは半径三メートルくらいしか浄化域を拡大できず、状況が変わったとは言い難いものだった。
当然マナもわかっていた。
自分の無力さに心が挫けそうになる。そんな時、消え入るようなか細い声が聞こえた。
「マナ様……。どうか、我らが同胞を、皆の家族を……お救いください……」
治癒魔法で意識を取り戻した騎士だった。崩れた壁にもたれかかりながら切実に訴えてくる。
それを皮切りに、次々と助けを求める声が胸に響き渡った。
「マナ様……どうか」
「助けてください……」
「仲間を戻してやってください!」
「マナさまああああ!」
ここにはいない倒れた騎士たち、それを救助している人たち、子供たち。
幻聴かもしれない。でもみんな助けを待っている。自分ならやってくれると信じてくれている。
──諦めない!
マナは今一度強く祈る。レイは腕組みをし、冷笑しながらそれを見ていた。
「実に滑稽だな。お前の力では浄化は無理だ」
「それでも! 助けを必要としている人たちが大勢いる!」
「何故そこまでして助けようとする? 魔女を引き入れたのはこいつらだろう? 諦めて、他の国にでも移った方が楽じゃないか?」
レイの言うことだって痛いほどわかる。
でも、目の前で傷ついて泣いている人たちのことを見て見ぬふりなんて出来ない。仮にそうしたとしても、いつか絶対に後悔する。
母が大聖女だからとか自分が聖女だからとか、そういうのは関係ない。
この気持ちは根源的で昔から心の底にあるもの。それを曲げてしまったら、きっと自分ではなくなってしまう。
「……この人たちは何も知らなかっただけ。子供たちともまた遊ぶって約束をしたの。それに、この場所はずっとお母さんが守ってきた場所! それを見捨てるなんて、私が許さない!」
聖女として、してはいけないこと。悪魔と契約?
ううん、違う。
────覚悟を決めた。
もう迷いはない。
潤みながらも力強さのある真っ直ぐな瞳でレイに告げる。
「レイ! 私に力を貸して! これは命令、契約よ! 大聖女になったら……私の心臓をあなたにあげるわ!!」
レイは不敵に笑い、問う。
「二言はないな?」
一度、大きく頷く。
「いいだろう。契約成立だ」
その瞬間──、レイは唇を重ねてきた。
「……!!」
「美味いな。やはり聖女の生気も人間のそれとは違うようだ」
唇を離したレイはそう言いうと、自身の唇を親指で拭った。
「なんで……、キスなんか……!」
「命令通り、お前に力を分けてやった。この辺り一帯なら浄化できるだろう」
────確かに身体から発せられている聖力が増している。今までに感じたことのない力が溢れてくるのがわかる。
これほどの力があればきっと浄化も出来る。
「足りなければもう一度分けてやるが?」
視線をこちらに下げて舌なめずりをするレイに心臓が高鳴った。
青い瞳が妖美に煌めいていて、また吸い込まれそうになってしまう。
「っ、十分だから!」
そうなる前にと、急いでレイから目を逸らした。
マナはゆっくりと深呼吸をし、もう一度目をつむる。
そして、全聖力を捧げ祈った。
マナを中心として、浄化の光が王宮一体を包み込んでいく。
しんしんと舞い散る雪のように、淡い輝きをした粒子が降り注いだ。
「ありがとうございます!」
「聖女様のおかげです!」
歓呼《かんこ》の声が王宮内に響く。
上空には爽やかな青空が広がり、もうあの魔物の姿をした人もいない。
魔女の残痕はなくなった。
「……マナ!」
執事の肩に腕を回しながら歩いてくるフェアラートが彼女の名を呼んだ。
「光の中心を探して来てみたが、やはりマナだったか……。本当に助かった、ありがとう」
「とんでもないです、私は私の役目を全うしただけですから」
満身創痍に近いマナは目を細めてうっすらと微笑む。
その顔は疲労と達成感が交差していた。
「皆の命とこの国の危機を救ってくれたんだ……、何かお礼をさせてほしい。欲しいものはないか? 俺に出来ることならなんでも……」
なんでもいいのなら、やりたいことはもう決まっている。
「では、一つだけ。フェアラート王を……、引っ叩かせてください」
聖女の微笑みから出たとは思えない願いに周りはどよめく。
「田舎育ちのじゃじゃ馬とは言え、しがない女の子の気持ちを弄んだ罪は大きいですよ。……なので、それで『落ちこぼれ』もなかったことにします」
半分本音で半分強がりだった。
だから、ちょっと強気になって笑顔を交えながら言ってみせた。
フェアラートと執事は顔を合わせ、マナがそう言った意味を悟る。
「マナ様……。貴女の行いには感謝しておりますが、王を叩くなんて……」
そう口を挟んできた騎士をフェアラートは制止する。
「わかった。大変申し訳ないことをした。……本来なら叩かれて済む話ではないな。目の覚めるような一発を頼むよ」
執事の肩から腕を取り、その場に片膝をついたフェアラートは深々と頭を下げて謝罪をすると、マナが叩きやすいように顔を上げすっと目を閉じた。
「じっとしててくださいね」
マナは穏やかに微笑んでいる。
そうして腕を軽く上げ、手のひらを彼の顔へと振り下ろす。その瞬間に、周囲は固唾を呑んだ。
──ぺちん、という柔らかい音がフェアラートの頬から響く。
そしてそのまま、そっと彼の頬を包んで治癒魔法をかけ始めた。
「……マナ?」
「まだ完治してないのに動いちゃ駄目じゃないですか」
「どうして?」
手痛いビンタが飛んでくると構えていたフェアラートは眉をひそめている。
マナだって本当なら思いっきり引っ叩いてやるつもりでいた。
しかし昨晩の王室内での会話を思い出し、「きっとこの人も父親の影を追いながら国を良くするためにがむしゃらだったんだろうな」なんて思ったら叩く手に力が入らなかった。
「……フェアラート王は『この国を救いたい』って一心だったんですよね。やり方はどうあれ、その気持ちには賛同したんです。フェアラート王なら、きっとこの国を変えられると思います」
続けて悪戯っぽく笑ってみせる。
「それに、リリィが私の代わり以上にやってくれたみたいですしね」
「……ありがとう」
それ以上の言葉はいらないだろうと、二人は互いに微笑み合った。
穏やかな雰囲気だったが、なんの前触れもなくマナの治癒魔法の光が空気に溶け込むよう消えいく。
フェアラートの頬からマナの手が滑り落ち、身体を支えきれなくなった膝が勢いよく曲がる。あわや地面に倒れ込んでしまうというところをレイが抱き抱えた。
「何が起きた……?」
「力の使いすぎだな」
「マナは大丈夫なのか?」
「寝ているだけだ」
それだけ言うと、レイはマナを抱き抱えたままフェアラートたちに背を向けた。
「待ってくれ……! マナをどうするつもりだ?」
「こいつは俺の主だ。俺が連れて行く」
「マナは恩人だ。そう易々と連れてかれるわけには……!」
「安心しろ、悪いようにはしない。こいつがいないと俺も困るからな」
ふっと笑ったレイは、それ以降のフェアラートの言葉に聞く耳を持たず瞬時に姿を消してしまった。
꧁——————————꧂
「……ここは?」
心地よい陽だまりの中で目を覚ます。
周囲には生命力あふれる木々が立ち並んでいて、生い茂った草花の匂いが鼻をくすぐる。
「気がついたか。ここは俺を召喚したあの森の中だ」
「良かった……。森も緑を取り戻したのね」
マナはゆっくりと上半身を起こし、全て終わったのだと安堵の息を漏らす。
「レイと契約したのは不本意だけど、ああしてなかったら今の景色だって見れてないんだよね。一応、お礼はしておく。……ありがとう」
「悪魔に礼を言う聖女なんて聞いたことないな」
「っ! 人がせっかく感謝してあげてるって言うのに!」
素直に「どういたしまして」と言わないところが悪魔らしい。
「これからどうするつもりだ?」
「……このまま田舎に戻ろうと思う。お母さんの書物を調べたいの。あのブルーダイヤモンドについて何か書いてあるかもしれない」
「そうか」
森を吹き抜けていく風が気持ちよかった。
「それで、レイはどうするの?」
「どうするもなにも、お前が大聖女になるまでそばにいるだけだ。契約したからな」
──レイと契約したことに後悔なんてない。
そうしなければみんなを守れなかった。
きっとそちらの方を後悔していただろう。
「わかった。その時まで力を貸してね、レイ」
花が咲いたような笑顔をしたマナの頬に、レイは軽く唇を当てた。
「…………っ!! なんでまたキスするの!?」
顔を熱くしながらキスされた頬を手で覆う。
レイは意地悪そうに笑っていた。
「聖女の生気が思っていた以上に美味でな。心臓をいただくまではこれで我慢してやろう」
扇情的に微笑んだレイがまたキスをしようとしてくる。
だから、思いっきり言ってやった。
「……命令よ! 私から離れなさぁぁい!」
召喚された先は魔女の魔力で満ちた、どこか先ほどまでいた場所に似ている景観をしていた。
そんな仄暗い森の中、目の前にいたのは涙を溜めた小娘だった。
茶色い髪に茶色い瞳、それに貧相な身体付き。溢れている生気から聖女だとはわかった。
──予想外だ。こんな小娘が俺を召喚した?
どうせ恋敵を消してくれだの若返らせてくれだの夫に復讐してくれだの、よくある女のくだらない理由で召喚させられたのかと思った。
だが今にも泣き出しそうな顔をしているこの小娘は、そうではなさそうだった。
召喚したのはお前かと尋ねたら睨まれた。恐怖と不安が入り混じっている瞳は嫌いではない。
どうやら小娘にも召喚したという自覚がないようだ。握り締めている手から漏れている青白い光、そこから魔力を感じる。
小娘が握っていたブルーダイヤモンドには召喚の魔術が刻まれていた。
ご丁寧にも召喚主と契約を交わせという魔術付き。
この小娘がやったとは考えにくい。様子からして、真相はこの小娘にもわからないだろう。
何にせよ、代わり映えのない下界にも飽き飽きしていたところにやってきた召喚。
それも相手が聖女とは、なんとも愉快。
聖女の生気は他の人間のそれよりも格段に美味いと聞く。特に心臓は唸るほどらしい。
さっさと契約を交わして生気を、欲を言えば心臓をいただいてしまおう。
なんせ契約を交わせということ以外は何も記されていない。
なら契約の代償を支払ってもらうのも不条理ではないし、その先はこちらの自由だ。
しかし小娘は一向に契約を交わそうとしない。まあ聖女が進んで悪魔と契約なんてしないだろう。
なら少し脅してみるかと、小娘の心臓を突いてみた。
小娘の瞳が恐怖一色に染まっていく。
強情だった女が恐怖に慄いていく瞬間はいつ見ても飽きない。
が、それも束の間で、衝撃音がしたと共に小娘の瞳に輝きが戻り手を振り払われた。
走っていった方向から魔女の気配がする。
やはり地上は面白い。小娘の後を辿った。
どうやら魔女が好き勝手やっているようだ。封印でもされていたのか魔力が乱れている。
少し前であの小娘が倒れている人間を治癒していたが、背後の魔物に気がついていないようだ。
契約の前に死なれては困る。それを食い止めるため間に入った。
小娘は「ありがとう」と礼を言ってきた。
そしてここにいる人間を助けるのだと。だから悪魔は魔女を倒してこいと『お願い』された。
強情な瞳を覗き込むも、今度はその色を変えずにいる。
この小娘が何をきっかけに契約を交わすのか少し興味が湧く。それに魔女と対峙するのも何年ぶりか。
気まぐれでその『お願い』とやらを聞いてやることにした。
「悪魔……!」とほころんだ顔でこちらを見てくる。悪魔悪魔と呼ばれる続けるのもそろそろ鬱陶しくなってきた。
「レイ=ディアダマス」
そう名乗って魔女の元へと向かった。
魔女は弱く、すぐに興醒めした。封印を破るために魔力を垂れ流しにしていたんだろう。
二十年ぶりに表に出て力の制御もできない魔女、赤子の手をひねるようなものだ。
小娘のいる場所は何やら騒がしかった。一人の男が小娘のことを「マナ様」と呼んだ。
それでこの女の名前を知った。まあどうでもいい。人間の名など記号のようなもの。
覚えたところで、この小娘から代償をもらえば、もう会うこともない。
そして、そのまま魔女の残痕を浄化させる言い出し、祈るように浄化魔法を使い始めた。
その姿は実に滑稽だった。王宮全体を浄化したかったようだが、それには力不足。
本人だってわかっているだろうに。
それでも小娘はやめなかった。
俺なら見捨てる。ただただ面倒だからだ。さっさと消滅魔術でも使って更地にでもするかもしれない。
それをしないのは聖女だからか? 悪魔にはない思考、不思議な人間だ。
「何故そこまでして助けようとする? 魔女を引き入れたのはこいつらだろう? 諦めて、他の国にでも移った方が楽じゃないか?」
興味本位でそう聞いた。すると小娘の目の色が変わる。
希望? 信念? 決意?
よくわからないが、その時の茶色い瞳の輝きは少し綺麗だと思った。
こいつらを見捨てないのは「聖女だから」というよりは、この小娘の性分なように見える。
なんて甘い、俺から言わせてもらえばただの偽善者だ。
ただ、その偽善のおかげで小娘と契約を交わせた。
自分のためではなく他人のために力を求めて契約するとは、なんとも度し難い。しかも心臓を代償にしての契約。
本当に甘い。もはや阿呆なのかとすら思える。
それでも抜かりないと思ったのは、「自分が大聖女になったら」という代償の条件を付けてきたことだった。
それまで力を貸せということだろう。
ほとほと面倒にも感じたが、この機を逃したらたぶん小娘との契約の機会はまた先延ばしになる。
契約もせずにちんたらと小娘と過ごすのならば、さっさと契約を交わしてしまった方がまだマシだ。
だから受け入れた。
力を分け与える代わりに生気をもらった。
聖女の生気は予想以上に美味かった。
蜜のように濃厚で、酒でも入っているのかと思うくらい酔いしれてしまう甘美。雑味のない滑らかさは確かに他の人間とは違う。
思わず唇に残った余韻をなぞるよう指で拭ったくらいだ。
「なんで……、キスなんか……!」
小娘は顔を真っ赤にして狼狽えている。
──この反応。こいつ、処女か。
別にそうであってもそうでなくても人間の味に変わりはない。
ただ、生娘の反応は面白いものがある。
「足りなければもう一度分けてやるが?」
そう言うと更に顔を赤くして目を逸らした。
実にわかりやすい。新しい玩具を手に入れた気分だった。
小娘が浄化しきったところに金髪のイタチ男が来た。
どうやら国王らしい。こんな青二才が国王とは。そう思ったりもしたが、この国の歴史に全く興味はない。
二人のやり取りを傍観していたら、力を使い果たし立っているのもやっとなはずの小娘がイタチ男にまで治癒魔法をかけ始めた。
偽善にしては行き過ぎている。他人のためにそこまでやれるのか。
そして案の定、小娘は倒れた。
抱き抱えているとイタチ男が何やら騒々しく鳴いていたが、これ以上付き合う義理もない。
小娘が起きないことにはどうしようもないと、とりあえず召喚された森へと連れていくことにした。
しばらくして小娘は目を覚ました。
すぐに礼をしてくる。悪魔にまで礼を言うとは。どこまでも不思議な人間だ。
「その時まで力を貸してね、レイ」
名を呼び微笑んでいる顔に引き込まれる。
ふわっとあの甘い匂いがして、気がついたら頬に唇を当てていた。
「…………っ!! なんでまたキスするの!?」
かぐわしい生気の香りは本能を刺激するかのように魅惑的だ。
隙しかない小娘からならいつでも生気を奪えるだろう。
それにまあ、この反応も見ていて飽きないものがある。心臓をいただくまでの繋ぎとしては、それなりに楽しめそうだ。
そう思いながら、今度は口から直接生気をもらおうと顔を近づけると、わなわなと唇を震わせた小娘が口を開く。
「……命令よ! 私から離れなさぁぁい!」
甲高い声で、思いきり叫ばれた。
この作家の他の作品
表紙を見る
⭐︎★和風恋愛ファンタジー×忌み子★⭐︎
妖が災厄をもたらしていた時代。
滅妖師《めつようし》が妖を討ち、巫女がその穢れを浄化することで、人々は平穏を保っていた──。
巫女の一族に生まれた結月は、銀色の髪の持ち主だった。
その銀髪ゆえに結月は「忌巫女」と呼ばれ、義妹や叔母、侍女たちから虐げられる日々を送る。
黒髪こそ巫女の力の象徴とされる中で、結月の銀髪は異端そのものだったからだ。
さらに幼い頃から、「義妹が見合いをする日に屋敷を出ていけ」と命じられていた結月。
その日が訪れるまで、彼女は黙って耐え続け、何も望まない人生を受け入れていた。
そして、その見合いの日。
義妹の見合い相手は、滅妖師の名門・霧生院家の次期当主だと耳にした。
しかし自分には関係のない話だと、屋敷最後の日もいつものように淡々と過ごしていた。
そんな中、ふと一頭の蝶が結月の前に舞い降りる──。
表紙を見る
二十七歳の麻衣は、友人・理沙のすすめでマッチングアプリに登録する。
軽い気持ちで始めたものの、誠実そうな男性・隼人と出会い、デートを重ねるうちに彼に惹かれていく。
隼人は終始紳士的で優しく、手すら繋いでこないほどだった。
その誠実さに安心感を抱き、麻衣は次第に彼への気持ちを深めていった。
そして迎えた四度目のデート。
ロマンチックな夜景の見えるレストランで、ついに告白の瞬間が訪れる……。
と思いきや、隼人の口から出たのは衝撃の言葉だった。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…