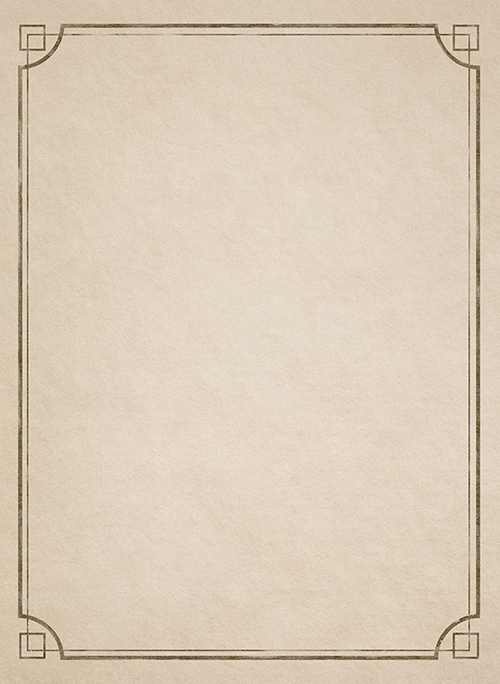「―失礼します。父上、お聞きしたいことがあるのですが、少しだけお時間を頂けないでしょうか?」
『本家』から帰った後、屋敷へと戻った俺は書斎で書類と向き合っていた父上へと声を掛けた。
理由はもちろん、『本家』の長女であり、『忌み子』と呼ばれているらしいユミィのことだ。
あの後、改めてリーヴに部屋に戻ってリーヴの相手をしていたが、どう考えてもあんな奴とは似ても似つかない彼女に興味を抱いた俺は、両家にもっとも詳しい父上から話を聞こうと思ったわけだ。
ちなみに、その時にリーヴから父上がすでに知っていることは確認済みだ。
父上は頭を下げる俺を見ると書類を読み進めていた手を止め、その顔を綻ばせて返してくれる。
「アシックか。どうした?」
「実は『本家』の長女のことで、少しお話を伺いたいと思いまして……」
「何……?」
俺の言葉に驚いた顔を見せる父上。すると、父上は俺に軽く手招きして近くに来るように促して来る。
それに従って父上の座っている机へと来ると、緊張感を伴った声を俺へと投げ掛けてきた。
「……誰から聞いた?」
「いえ、聞いたというより、実は直接顔を合わせました」
「……そうか」
まあ、ここで素直に「リーヴに聞きました」とか言っても良いが、一応はリーヴから聞かされた話は内密にすると約束しているし、とりあえずそういう風に話しておく。
俺の言葉を聞いた父上は椅子に深く腰掛けながら大きくため息を吐いていた。
そして、こめかみを手で押さえると、難しい顔をしながら俺の言葉に返してくれる。
「……お前が『分家』の当主になる少し前には話しておこうと思っていたが……もう彼女と顔を合わせてしまったのだな」
「はい。ユミィ・ユーグと名乗っていました」
「……ならば、正真正銘、彼女が『本家』の長女で間違いないだろう。何せ、『本家』の人間や私の他に、彼女の存在は『本家』の使用人の中でも限られた者しか知らないのだからな」
父上はそう言うと、椅子から腰を上げて背中越しにあった窓へと目を向ける。
そして、ため息交じりに話を続けていく。
「……彼女のことについてはどこまで聞いている?」
「はい。『本家』の長女であること、それと魔力がない呪いの『忌み子』として幽閉されていることです」
「……なるほど。そこまで知ってしまったのなら、もう誤魔化しはきかないな」
そう言って、父上は再び深いため息を吐いてみせると、俺の方に振り返りながら真意を探るようにその目を細め少し強い口調で問いただしてきた。
「では、アシック。その上で聞きたいこととはなんだ?」
「はい。彼女の現状と今後について詳しく伺いたいと思い、お尋ねしました」
「ユミィ様の現状と今後について……? それを聞いてどうするんだ?」
俺の質問に疑問を抱いた父上は訝しげな顔を見せる。しかし、そんな父に俺はふと感じていたことを口にしていく。
「彼女は魔力がないという呪いに掛かっているとお話されていました。それが理由で誰にも知られることの無いまま『本家』に幽閉されているわけですが……魔法が使えないという意味では私と同じような立場です。そんな彼女がどうなるか気になったのです」
「それは同情か?」
「それもあります。ただ、それとは別に純粋な興味もあるのです。自分と似たような存在を気に掛けるというのは不思議なことでしょうか?」
そう言うと、父上は考え込むように顎に手を当て、やがて肩の荷を下ろすように息を吐いた。
そして、眉間に寄せていたシワを無くし、いつものように穏やかな口調で言葉を返してくれる。
「……いや、すまない。少しばかり意地が悪過ぎたな。まさか、お前がユミィ様のことをこんなにも早く知ることになるとは思っていなくてな」
「いえ、彼女の存在が私達『ユーグ家』にとって、それだけ機密性の高いことなのだと改めて再認識出来ました」
「アシック……。本当にお前のような出来過ぎた息子を持って嬉しいこともあるが、末恐ろしい時もあるよ。まだ十にも満たない子供に諭されてしまうとは、父としては情けない限りだ」
「そんなことはありません。こうした考えや意識を持てるのも全て父上や母上からの教育あってのものですから」
「まったく……まあ良い。それよりも、ユミィ様のことだったな」
そう言うと、父上は書斎の椅子へと再び座り、ユミィのことについて語り始めてくれた。
「まず、彼女の現状についてだが……見ての通り、外出はおろか屋敷内を自由に歩き回ることすらも難しい。それもこれも、『本家』の両親が彼女の存在を外部にもれることを恐れているからだ」
そうして、机の上で腕を組みながら話してくれる父上の言葉に、その先の意味を理解した俺はそんな父上へと言葉を返した。
「魔力を持たない『忌み子』……貴族としては自分達の名前を汚しかねない致命的な存在になり得るということですね?」
「そうだ。お前の場合は『分家』ということもあり、こう言ってはなんだが『本家』と比較し、嘲笑する為にあえてその存在を『本家』が認めているだけに過ぎん。現に、我々『分家』の人間は他の街の貴族達の前に姿を出すことを許されていないのだからな」
改めてその事実を聞かされてみると、『本家』の当主様の心は相当腐っていることがよく分かる。そんな『本家』に対して『分家』ってまともだよな、とかつくづく思ってしまうが。
そんな俺の考えをよそに、父上の話は続けられていく。
「しかし、『本家』の長女―ユミィ様の場合は話が違ってくる。先ほどお前も言っていた通り、『本家』の長女が魔力を持たない『忌み子』だと知られれば、周囲の貴族から嘲笑を受けるのは間違いない。お前はあくまでもまだ魔法を使えてないだけで、将来的に使うことは出来るだろうが、彼女の場合は魔力が無い以上、未来永劫使えないと言われている。実際、他の貴族達にも稀にそういった者達が生まれるそうだが……そういった者は女であれば他の家に嫁がされ、男であれば最悪の場合は家から追放される……どちらにしろ、貴族としては永遠に日を浴びることは許されん」
「追放……」
もし、俺が『分家』の人間ではなく、『本家』の人間だった場合はそうなっていたかもしれないってことか。
そんな俺の心にある不安を察したのか、父上はいつものような朗らかな笑みを向けてくれた。
「心配しなくても、お前は最初から『分家』の人間だ。『本家』から冷遇されることはあっても、下手を踏まない限りは我々が追放されることはない。何せ、我々を追放すれば、ただでさえ無法地帯であるこの地を治めるものが居なくなってしまうのだからな」
「それもそうですね」
俺の不安を抑える為にあえて冗談交じりにそう言ってくれる父上に感謝すると、父上は再び表情を引き締めてユミィのことについて話を続けてくれる。
「ただ、この話からも分かる通り、ユミィは将来的には他の貴族へ嫁がされ……加えて、完全に縁も切られるだろう。『本家』からすれば、それで『忌み子』は消え、体裁を維持できるのだからな。つまり、将来ユミィはこの『ユーグ家』から追放されることがすでに決まっている。これは覆しようのない事実だ」
「それではあまりに彼女が報われないと思います」
「その通り……しかし、これが貴族だ。一般人でも魔力を持たない『忌み子』は毛嫌われるが、貴族ではそういう次元ではない。……可哀想だが、これが現実なのだ」
そうして肩を落とす父上の雰囲気を見ると、心の底から彼女に同情しているのは明らかだった。だが、『分家』の人間の立場は『本家』からすれば明らかに弱い。
父上は俺や母上を守る為に自分の正義感を押し殺し、その罪を一人で背負おうとしていたのだ。
「父上、一つだけ良いでしょうか?」
「なんだ?」
そんな父上を見た俺は、ある提案をすることにした。
その提案とは―
「彼女―ユミィが『忌み子』として『本家』から疎まれているのは、『忌み子』の特徴として銀色の髪と金色の目を持っており、言い伝え通り魔力を持っていないから……という事で間違いないでしょうか?」
「ああ。お前の言う通り、魔力を持たない『忌み子』は親からの遺伝など関係なくその容姿が変わってしまう。魔力も持たず、見た目も違う子を向こうの親達は愛することが出来なかったのだろう。……せめて魔法さえ使うことが出来れば、貴族としては最低限の扱いは受けられただろうにな」
なるほど……だったら、ここで俺の出番だ。
今まで父上や母上にすらずっと黙っていたことを、今こそ話すべきだろう。これまで『魔導書』で培ってきた技術をここで使わないで、いつ使うんだ?
そうして、気落ちする父を見ていた俺は、覚悟を決めてその提案を口にした。
「なら、僕が彼女に魔法を教えます。そして、ユミィに魔法を使わせることさえ出来れば、問題は解決するのではないでしょうか?」
「なんだと……?」
十歳にも満たない俺からの提案に、父上は再び驚いた顔を見せた。
ユミィと出会った時、実は一つだけ気付いたことがある。
『忌み子』と呼ばれている人間に共通している銀色の髪と金色の目。それを持って生まれる者は魔力を持っておらず、未来永劫魔法を使うことは出来ないと言い伝えられている存在。
しかし、実際に『忌み子』である彼女を目にした時、俺はあることを思い出したのだ。
俺が読んでいる魔導書にその存在が記されていること―そして、何より世の中の常識が根本的に間違っているということだ。
「父上、これを見て下さい」
「これは……」
「書斎に置かれていた『魔導書』です。父上達には秘密にしていましたが、実を言うと僕はこれを使って様々な魔法を勉強させてもらっていました」
俺は今までその存在を隠し続けていた例の『魔導書』を父の目の前へと置くと、それを見た父は驚いた顔を見せていた。
「『魔導書』? これがか? 確かに先祖から代々受け継いでいる本ではあったが……勉強させてもらっていた、ということはお前はずっとこれを読んでいたというのか?」
「はい。黙っていて申し訳ありませんでした。しかし、『分家』の人間とはいえ、このまま魔法を使うことが出来なければ、父上や母上にも恥をかかせてしまいます。僕自身はまだしも、それで父上や母上の尊厳が傷付けられるなどあってはなりません。それゆえに、これを書斎で見つけてからというもの一人で持ち出し、勉強させて頂いておりました」
「……では、先日の落雷やそれがすぐに消化されたのもお前の仕業だったということか?」
そう言うと、父上は真剣な表情を俺へと向けてきた。恐らく俺を怒るつもりだろう。
まあ、怒られて当然のことをしてしまったんだ、ここは甘んじて受け入れるしかない。
「はい。父上の言う通り、あれは僕が試しに行ったことです。周囲に誰も居ないことを確認し、木に向かって雷の魔法を放ち、消化の為に水の魔法を使いました。すぐに対応を行ったとはいえ、それでも許されることではないと思います。申し訳ありません」
「……何という事だ」
父上は俺の言葉にこめかみを抑えてしまう。
次に飛んでくる説教に冷や冷やするが、今は我慢するしかない。何故なら、この『魔導書』にはユミィを救うことが出来る可能性が書かれているのだから。
反省を見せている俺の前でしばらく考え込むようにしていた父上だが、ようやく口を開くと同時に重い口調で驚くべきことを口にしてきたのだ。
「―アシック、お前にはこの本に何かが書かれているように見えるのか?」
「それはどういう事でしょうか……?」
「何かが書かれているように見える」って……それじゃあ、まるで父上には本に何も書かれていないように見える、って言ってるように聞こえるんだが。
真っ先に怒られることを警戒していた俺が驚いていると、父上は俺の考えを肯定するように話を続けてきた。
「どうも何も……そのままの意味だ。私にはただの白紙にしか見えないが……その反応を見るに、悪戯で私をからかっているわけではないのか?」
「このような状況で、父上に対してそのような失礼なことはいたしません。例えば、ここに描かれている内容ですが、これは基礎的な魔法制御のことについて書かれています」
「……やはり、私にはただの白紙にしか見えないな」
「これは一体……」
つまり、最初から俺しか読めなかったってことか?
俺が魔導書を前に困惑していると、父上は「ふむ」と一つ置いてその魔導書について話してくれた。
「もしかすると、一定の魔力を持たない者には読めない本だったのかもしれないな」
「そんなことが可能なんですか?」
「さて……私の魔力はそれほど多くはないから分からないが、実際お前には見えているのだろう?」
「はい。例えば、ここの通りに魔法を使うと―このように、手から火を出すこと可能になりました」
そう言って、本に描かれている手順で手の平に火を灯す。すると、それを見た父上は驚いた様子で口を開いた。
「アシック……本当に魔法を使うことが出来るようになったのか? あれだけ色々と試しても出来なかったというのに……」
「はい。この『魔導書』には魔力が強過ぎる者の制御方法も記載されていましたが、それを見て勉強しているうちに使えるようになりました」
「いつの間に……」
「すぐに父上や母上に報告させて頂きたいとは思っていたのですが、ただ使えるだけではリーヴと変わりません。その為、もう少し色々と制御出来るようになってから成果を報告するつもりでした」
「なるほど、そういうことだったのか……」
ついでに言うと、「こんな『魔導書』があったら危険だ」と取り上げられる可能性もあったから、吸収できるうちに吸収しておきたかったというのもあるけど。
そうして『魔導書』を見ながら考え込むような表情を見せていた父だが、魔導書から目を離すと真剣な表情を俺へと向けてきた。
「しかし驚いたな……。この本は先祖代々から受け継いでいたものなのだが、内容は白紙な上、魔法で守られているせいかペンなどで上から書くこともできず、メモとして使うこともできないから骨董品屋でも引き取ってもらえなかったそうだ。だが、それがまさか『魔導書』だったとは……」
「僕には文字や絵がぎっしりと詰まっているように見えるのですが……本当に父上には白紙に見えているのですか?」
「残念だが、な……だが、いくら私達の為とはいえ、危険な魔法を一人で練習していたことは許されることではないぞ?」
「はい。申し訳ありません」
俺は父の言うことに素直に頭を下げた。
実際、普通の子供が一人でやったらどうなるか分からないし、この場合は父上の言っていることは正しい。
そうして俺が素直に謝罪をしたことで父上はため息を吐くと、俺に続きを促す。
「……まあ良い。怪我もなかったようだからな。それについての説教は後で改めて行うとして……お前は先ほどユミィ様へ魔法の指南を行うと話していたな? それはつまり、この『魔導書』を使って彼女に魔法を使えるようにする、ということか?」
「それもあります。それと、この『魔導書』に記載されていたのですが……僕達は『忌み子』という存在について、大きな勘違いをしていた可能性があり、それを父上に話しておこうと思ったのです」
「大きな勘違い……? それは何だ?」
俺の言葉に座っていた椅子に深く腰掛ける父上。そんな父上に、俺は衝撃的な事実を告げた。
「―『忌み子』は魔力を持たない子供ではありません。むしろその逆です。『忌み子』とは、魔力を持ち過ぎて容姿にまでその影響を与えてしまったとても貴重な存在なのです」
『本家』から帰った後、屋敷へと戻った俺は書斎で書類と向き合っていた父上へと声を掛けた。
理由はもちろん、『本家』の長女であり、『忌み子』と呼ばれているらしいユミィのことだ。
あの後、改めてリーヴに部屋に戻ってリーヴの相手をしていたが、どう考えてもあんな奴とは似ても似つかない彼女に興味を抱いた俺は、両家にもっとも詳しい父上から話を聞こうと思ったわけだ。
ちなみに、その時にリーヴから父上がすでに知っていることは確認済みだ。
父上は頭を下げる俺を見ると書類を読み進めていた手を止め、その顔を綻ばせて返してくれる。
「アシックか。どうした?」
「実は『本家』の長女のことで、少しお話を伺いたいと思いまして……」
「何……?」
俺の言葉に驚いた顔を見せる父上。すると、父上は俺に軽く手招きして近くに来るように促して来る。
それに従って父上の座っている机へと来ると、緊張感を伴った声を俺へと投げ掛けてきた。
「……誰から聞いた?」
「いえ、聞いたというより、実は直接顔を合わせました」
「……そうか」
まあ、ここで素直に「リーヴに聞きました」とか言っても良いが、一応はリーヴから聞かされた話は内密にすると約束しているし、とりあえずそういう風に話しておく。
俺の言葉を聞いた父上は椅子に深く腰掛けながら大きくため息を吐いていた。
そして、こめかみを手で押さえると、難しい顔をしながら俺の言葉に返してくれる。
「……お前が『分家』の当主になる少し前には話しておこうと思っていたが……もう彼女と顔を合わせてしまったのだな」
「はい。ユミィ・ユーグと名乗っていました」
「……ならば、正真正銘、彼女が『本家』の長女で間違いないだろう。何せ、『本家』の人間や私の他に、彼女の存在は『本家』の使用人の中でも限られた者しか知らないのだからな」
父上はそう言うと、椅子から腰を上げて背中越しにあった窓へと目を向ける。
そして、ため息交じりに話を続けていく。
「……彼女のことについてはどこまで聞いている?」
「はい。『本家』の長女であること、それと魔力がない呪いの『忌み子』として幽閉されていることです」
「……なるほど。そこまで知ってしまったのなら、もう誤魔化しはきかないな」
そう言って、父上は再び深いため息を吐いてみせると、俺の方に振り返りながら真意を探るようにその目を細め少し強い口調で問いただしてきた。
「では、アシック。その上で聞きたいこととはなんだ?」
「はい。彼女の現状と今後について詳しく伺いたいと思い、お尋ねしました」
「ユミィ様の現状と今後について……? それを聞いてどうするんだ?」
俺の質問に疑問を抱いた父上は訝しげな顔を見せる。しかし、そんな父に俺はふと感じていたことを口にしていく。
「彼女は魔力がないという呪いに掛かっているとお話されていました。それが理由で誰にも知られることの無いまま『本家』に幽閉されているわけですが……魔法が使えないという意味では私と同じような立場です。そんな彼女がどうなるか気になったのです」
「それは同情か?」
「それもあります。ただ、それとは別に純粋な興味もあるのです。自分と似たような存在を気に掛けるというのは不思議なことでしょうか?」
そう言うと、父上は考え込むように顎に手を当て、やがて肩の荷を下ろすように息を吐いた。
そして、眉間に寄せていたシワを無くし、いつものように穏やかな口調で言葉を返してくれる。
「……いや、すまない。少しばかり意地が悪過ぎたな。まさか、お前がユミィ様のことをこんなにも早く知ることになるとは思っていなくてな」
「いえ、彼女の存在が私達『ユーグ家』にとって、それだけ機密性の高いことなのだと改めて再認識出来ました」
「アシック……。本当にお前のような出来過ぎた息子を持って嬉しいこともあるが、末恐ろしい時もあるよ。まだ十にも満たない子供に諭されてしまうとは、父としては情けない限りだ」
「そんなことはありません。こうした考えや意識を持てるのも全て父上や母上からの教育あってのものですから」
「まったく……まあ良い。それよりも、ユミィ様のことだったな」
そう言うと、父上は書斎の椅子へと再び座り、ユミィのことについて語り始めてくれた。
「まず、彼女の現状についてだが……見ての通り、外出はおろか屋敷内を自由に歩き回ることすらも難しい。それもこれも、『本家』の両親が彼女の存在を外部にもれることを恐れているからだ」
そうして、机の上で腕を組みながら話してくれる父上の言葉に、その先の意味を理解した俺はそんな父上へと言葉を返した。
「魔力を持たない『忌み子』……貴族としては自分達の名前を汚しかねない致命的な存在になり得るということですね?」
「そうだ。お前の場合は『分家』ということもあり、こう言ってはなんだが『本家』と比較し、嘲笑する為にあえてその存在を『本家』が認めているだけに過ぎん。現に、我々『分家』の人間は他の街の貴族達の前に姿を出すことを許されていないのだからな」
改めてその事実を聞かされてみると、『本家』の当主様の心は相当腐っていることがよく分かる。そんな『本家』に対して『分家』ってまともだよな、とかつくづく思ってしまうが。
そんな俺の考えをよそに、父上の話は続けられていく。
「しかし、『本家』の長女―ユミィ様の場合は話が違ってくる。先ほどお前も言っていた通り、『本家』の長女が魔力を持たない『忌み子』だと知られれば、周囲の貴族から嘲笑を受けるのは間違いない。お前はあくまでもまだ魔法を使えてないだけで、将来的に使うことは出来るだろうが、彼女の場合は魔力が無い以上、未来永劫使えないと言われている。実際、他の貴族達にも稀にそういった者達が生まれるそうだが……そういった者は女であれば他の家に嫁がされ、男であれば最悪の場合は家から追放される……どちらにしろ、貴族としては永遠に日を浴びることは許されん」
「追放……」
もし、俺が『分家』の人間ではなく、『本家』の人間だった場合はそうなっていたかもしれないってことか。
そんな俺の心にある不安を察したのか、父上はいつものような朗らかな笑みを向けてくれた。
「心配しなくても、お前は最初から『分家』の人間だ。『本家』から冷遇されることはあっても、下手を踏まない限りは我々が追放されることはない。何せ、我々を追放すれば、ただでさえ無法地帯であるこの地を治めるものが居なくなってしまうのだからな」
「それもそうですね」
俺の不安を抑える為にあえて冗談交じりにそう言ってくれる父上に感謝すると、父上は再び表情を引き締めてユミィのことについて話を続けてくれる。
「ただ、この話からも分かる通り、ユミィは将来的には他の貴族へ嫁がされ……加えて、完全に縁も切られるだろう。『本家』からすれば、それで『忌み子』は消え、体裁を維持できるのだからな。つまり、将来ユミィはこの『ユーグ家』から追放されることがすでに決まっている。これは覆しようのない事実だ」
「それではあまりに彼女が報われないと思います」
「その通り……しかし、これが貴族だ。一般人でも魔力を持たない『忌み子』は毛嫌われるが、貴族ではそういう次元ではない。……可哀想だが、これが現実なのだ」
そうして肩を落とす父上の雰囲気を見ると、心の底から彼女に同情しているのは明らかだった。だが、『分家』の人間の立場は『本家』からすれば明らかに弱い。
父上は俺や母上を守る為に自分の正義感を押し殺し、その罪を一人で背負おうとしていたのだ。
「父上、一つだけ良いでしょうか?」
「なんだ?」
そんな父上を見た俺は、ある提案をすることにした。
その提案とは―
「彼女―ユミィが『忌み子』として『本家』から疎まれているのは、『忌み子』の特徴として銀色の髪と金色の目を持っており、言い伝え通り魔力を持っていないから……という事で間違いないでしょうか?」
「ああ。お前の言う通り、魔力を持たない『忌み子』は親からの遺伝など関係なくその容姿が変わってしまう。魔力も持たず、見た目も違う子を向こうの親達は愛することが出来なかったのだろう。……せめて魔法さえ使うことが出来れば、貴族としては最低限の扱いは受けられただろうにな」
なるほど……だったら、ここで俺の出番だ。
今まで父上や母上にすらずっと黙っていたことを、今こそ話すべきだろう。これまで『魔導書』で培ってきた技術をここで使わないで、いつ使うんだ?
そうして、気落ちする父を見ていた俺は、覚悟を決めてその提案を口にした。
「なら、僕が彼女に魔法を教えます。そして、ユミィに魔法を使わせることさえ出来れば、問題は解決するのではないでしょうか?」
「なんだと……?」
十歳にも満たない俺からの提案に、父上は再び驚いた顔を見せた。
ユミィと出会った時、実は一つだけ気付いたことがある。
『忌み子』と呼ばれている人間に共通している銀色の髪と金色の目。それを持って生まれる者は魔力を持っておらず、未来永劫魔法を使うことは出来ないと言い伝えられている存在。
しかし、実際に『忌み子』である彼女を目にした時、俺はあることを思い出したのだ。
俺が読んでいる魔導書にその存在が記されていること―そして、何より世の中の常識が根本的に間違っているということだ。
「父上、これを見て下さい」
「これは……」
「書斎に置かれていた『魔導書』です。父上達には秘密にしていましたが、実を言うと僕はこれを使って様々な魔法を勉強させてもらっていました」
俺は今までその存在を隠し続けていた例の『魔導書』を父の目の前へと置くと、それを見た父は驚いた顔を見せていた。
「『魔導書』? これがか? 確かに先祖から代々受け継いでいる本ではあったが……勉強させてもらっていた、ということはお前はずっとこれを読んでいたというのか?」
「はい。黙っていて申し訳ありませんでした。しかし、『分家』の人間とはいえ、このまま魔法を使うことが出来なければ、父上や母上にも恥をかかせてしまいます。僕自身はまだしも、それで父上や母上の尊厳が傷付けられるなどあってはなりません。それゆえに、これを書斎で見つけてからというもの一人で持ち出し、勉強させて頂いておりました」
「……では、先日の落雷やそれがすぐに消化されたのもお前の仕業だったということか?」
そう言うと、父上は真剣な表情を俺へと向けてきた。恐らく俺を怒るつもりだろう。
まあ、怒られて当然のことをしてしまったんだ、ここは甘んじて受け入れるしかない。
「はい。父上の言う通り、あれは僕が試しに行ったことです。周囲に誰も居ないことを確認し、木に向かって雷の魔法を放ち、消化の為に水の魔法を使いました。すぐに対応を行ったとはいえ、それでも許されることではないと思います。申し訳ありません」
「……何という事だ」
父上は俺の言葉にこめかみを抑えてしまう。
次に飛んでくる説教に冷や冷やするが、今は我慢するしかない。何故なら、この『魔導書』にはユミィを救うことが出来る可能性が書かれているのだから。
反省を見せている俺の前でしばらく考え込むようにしていた父上だが、ようやく口を開くと同時に重い口調で驚くべきことを口にしてきたのだ。
「―アシック、お前にはこの本に何かが書かれているように見えるのか?」
「それはどういう事でしょうか……?」
「何かが書かれているように見える」って……それじゃあ、まるで父上には本に何も書かれていないように見える、って言ってるように聞こえるんだが。
真っ先に怒られることを警戒していた俺が驚いていると、父上は俺の考えを肯定するように話を続けてきた。
「どうも何も……そのままの意味だ。私にはただの白紙にしか見えないが……その反応を見るに、悪戯で私をからかっているわけではないのか?」
「このような状況で、父上に対してそのような失礼なことはいたしません。例えば、ここに描かれている内容ですが、これは基礎的な魔法制御のことについて書かれています」
「……やはり、私にはただの白紙にしか見えないな」
「これは一体……」
つまり、最初から俺しか読めなかったってことか?
俺が魔導書を前に困惑していると、父上は「ふむ」と一つ置いてその魔導書について話してくれた。
「もしかすると、一定の魔力を持たない者には読めない本だったのかもしれないな」
「そんなことが可能なんですか?」
「さて……私の魔力はそれほど多くはないから分からないが、実際お前には見えているのだろう?」
「はい。例えば、ここの通りに魔法を使うと―このように、手から火を出すこと可能になりました」
そう言って、本に描かれている手順で手の平に火を灯す。すると、それを見た父上は驚いた様子で口を開いた。
「アシック……本当に魔法を使うことが出来るようになったのか? あれだけ色々と試しても出来なかったというのに……」
「はい。この『魔導書』には魔力が強過ぎる者の制御方法も記載されていましたが、それを見て勉強しているうちに使えるようになりました」
「いつの間に……」
「すぐに父上や母上に報告させて頂きたいとは思っていたのですが、ただ使えるだけではリーヴと変わりません。その為、もう少し色々と制御出来るようになってから成果を報告するつもりでした」
「なるほど、そういうことだったのか……」
ついでに言うと、「こんな『魔導書』があったら危険だ」と取り上げられる可能性もあったから、吸収できるうちに吸収しておきたかったというのもあるけど。
そうして『魔導書』を見ながら考え込むような表情を見せていた父だが、魔導書から目を離すと真剣な表情を俺へと向けてきた。
「しかし驚いたな……。この本は先祖代々から受け継いでいたものなのだが、内容は白紙な上、魔法で守られているせいかペンなどで上から書くこともできず、メモとして使うこともできないから骨董品屋でも引き取ってもらえなかったそうだ。だが、それがまさか『魔導書』だったとは……」
「僕には文字や絵がぎっしりと詰まっているように見えるのですが……本当に父上には白紙に見えているのですか?」
「残念だが、な……だが、いくら私達の為とはいえ、危険な魔法を一人で練習していたことは許されることではないぞ?」
「はい。申し訳ありません」
俺は父の言うことに素直に頭を下げた。
実際、普通の子供が一人でやったらどうなるか分からないし、この場合は父上の言っていることは正しい。
そうして俺が素直に謝罪をしたことで父上はため息を吐くと、俺に続きを促す。
「……まあ良い。怪我もなかったようだからな。それについての説教は後で改めて行うとして……お前は先ほどユミィ様へ魔法の指南を行うと話していたな? それはつまり、この『魔導書』を使って彼女に魔法を使えるようにする、ということか?」
「それもあります。それと、この『魔導書』に記載されていたのですが……僕達は『忌み子』という存在について、大きな勘違いをしていた可能性があり、それを父上に話しておこうと思ったのです」
「大きな勘違い……? それは何だ?」
俺の言葉に座っていた椅子に深く腰掛ける父上。そんな父上に、俺は衝撃的な事実を告げた。
「―『忌み子』は魔力を持たない子供ではありません。むしろその逆です。『忌み子』とは、魔力を持ち過ぎて容姿にまでその影響を与えてしまったとても貴重な存在なのです」