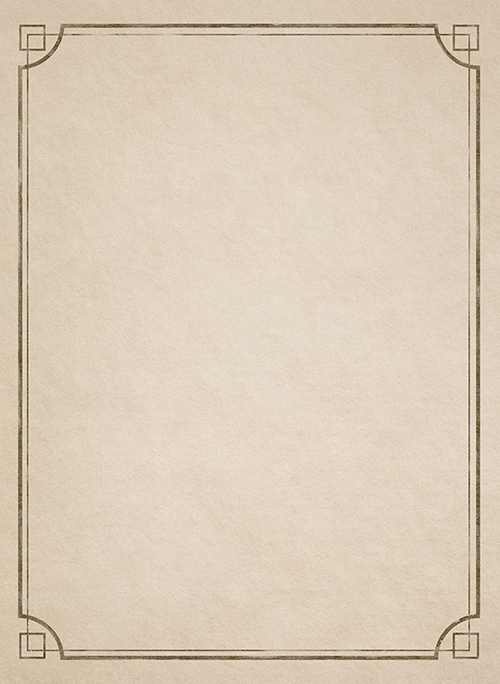その後、俺はリーヴからその妹について色々なことを聞いた。
実は魔法が使えず、生まれながらにして魔力を持たない呪いを受けているらしいということ。
『分家』の人間や他の貴族達にそれを知られると舐められかねないと屋敷内にずっと閉じ込め、その存在そのものを秘密にしているということ。
そして、それが『忌み子』と言われている存在だという事だ。
(知らなかった……まさか、リーヴに妹が居たなんてな。もしかしたら、父上は知っているかもしれなけど……じゃあ、さっき俺を見ていたのはその妹ってことになるのか?)
リーヴから話を聞いた後、俺は一度トイレへと向かった帰りに彼から聞かされた話を思い出しつつ、リーヴの部屋へと戻ろうと廊下を歩く。
この廊下を渡れば、すぐにリーヴの部屋だ。
しかし、俺は少しばかりその妹の存在が気になっていた。
(……ちょっとくらい良いよな?)
リーヴの話では、その妹はリーヴの部屋のさらに先、屋敷の奥にある部屋に居るそうだ。
普段はあまり部屋の外に出ないらしいが、屋敷内に来客が来た時は気になって自分の部屋の窓から様子を見ていたらしい。
特に『分家』の俺達が屋敷に招かれた時は、小さい頃から必ず部屋から眺めていたらしく、向こうは俺や父上の顔を知っているそうだ。
とはいえ、バレたらマズいと『本家』の母親から止められており、これまでは窓の外から見るくらいだったらしいが、今日はあいにくとその母親が不在らしく、それで廊下まで出て来て様子を見に来たんじゃないか、とリーヴは言っていた。
向こうは俺を知っていて、でも俺の方は知らないというのも違和感があるよな。
だったら、少しだけ様子を見てからリーヴの部屋へ戻ってもそこまで時間は掛からないし、これくらいは許されるだろ。
(リーヴのことだ。どうせ、トイレの時間を待たせただけでも文句を言われるわけだし、ちょっとだけ遅れても問題無いだろ)
そうして、俺はリーヴの部屋の前を通り過ぎると、例の『本家』の長女の部屋の方へと向かうことにした。
(それにしても、リーヴの妹か……。リーヴや当主様に似て、やっぱり『本家』らしく嫌な人間に育ってるのかな? というか、今までずっと一人っ子だと思ってたから、リーヴに妹が居るとか言われても実感が湧かないよな……)
ともかく、少しその姿を見てみるか。俺にとっては一応親類ってことになるんだし。
そうして、俺がその妹の部屋へ向かおうと、廊下の角を曲がろうした時だった。
「あ……」
すると、そこに居た存在と目が合い、その相手から声がもれると同時に……俺は言葉を失ってしまった。
そこに居たのは見たこともない少女だった。
長く白い髪と細い体は目を奪われてしまうほど美しく、少なくとも生まれてからこれほど綺麗な人間と出会ったことはない。
そして、さらに俺が声を失った理由はその独特な目の色だった。
(髪が白い……? それに、目が金色に光ってる?)
俺達ユーグ家の特徴として、髪は金色で目は全員青い。
嫁いできた母上や『本家』の奥様はともかく、多少の濃さに違いはあれど、その血を引いた者は全員そうだった。
しかし、目の前の子供は違った。
顔立ちはどこか『本家』の面々の面影はあるものの、金色の目や白い髪をしているところは全く違う。
(もしかして……この子がリーヴの言ってた妹なのか?)
まさか、こんなにも簡単に出会うとは……少し様子を見て帰るくらいの予定だったから突然顔を正面から突き合わせてしまい、少々戸惑ってしまう。
「……」
だが、そんな俺よりも驚いた顔を見せたまま立ち止まっている少女を前に、とりあえず俺は外行き用の人の良さそうな笑顔を作ると、戸惑う少女へと声を掛けた。
「ごめん、人が居るとは思っていなかったんだ。怪我は無いか?」
「―よね?」
「ん? 何か言ったかい?」
すると、何やら目の前の少女が小さく呟いたことに気付き、俺は咄嗟に聞き返すように返事をしてしまう。
俺よりも小さい少女を怖がらせまいとした態度に、少女は睨み付けるような視線と共にこんなことを口走ってきた。
「あなたは『分家』の方……ですよね?」
そう言うと、目の前の少女はどうにか姿勢を立て直しながらパッパッと服の誇りを払うようにして佇まいを正し始める。
しかし、冷静なようでいて動揺の方が大きいらしく、一度大きく深呼吸をしていた。
そんな少女を前に、俺は普段父上と仕事をしている時のように貴族然とした振る舞いで少女へと挨拶する。
「申し遅れました。私の名前はアシック・ユーグ。仰る通り、『分家』の長男です。あなたはリーヴ様の妹君でお間違いないでしょうか?」
「あ……は、はい……。その、ユミィ・ユーグ……と申します」
「これは失礼いたしました。知らなかったとはいえ、『本家』の方に失礼な態度を取ってしまっておりました。無知な私をどうかお許し下さい」
「あ……えっと……」
俺が恭しく頭を下げてみせると、慌てたように戸惑いを見せるユミィ。
ずっと幽閉されていたという話だし、恐らくあまり人と接したことがなくてこういう時の対応が分からないのかもしれない。
このまま困らせたままというのもなんだし、一応はリーヴを待たせている手前、助け舟を出しておくことにしよう。
「そうでした。ユミィ様、お怪我などは無かったでしょうか?」
「怪我……ですか? は、はい、特には……」
「それは良かったです。『本家』の方である前に、初対面の方に怪我をさせてしまうなど、父上に顔向け出来なくなってしまいますから」
「そう……なんですか?」
「ええ。『本家』の方々はもちろん尊敬しておりますが、『分家』の人間であるとはいえ、私は父のことも尊敬しております。その父は貴族としての誇りを非常に強く持っている方なので礼儀作法には少々厳しく、万が一、父の耳に他の方を私が傷付けたと入ってしまうようなことがあれば、父に怒られてしまいますから」
俺は冗談交じりそう言ってユミィへと笑みを向ける。
実際には話の通じる父は不可抗力だった場合などには注意はするだろうが、そこまで怒ることはないし、あくまでも場を和ます為の冗談だ。
そんな俺の言葉にユミィは驚いた顔を浮かべると、どこか羨むような声をこぼした。
「……そんなにお父様を尊敬なさっているということは、仲が良いのですね」
「どうなのでしょう? ただ、父はもちろん、母も尊敬しているのは間違いありません」
改まって「仲が良い」とか言われると、どう答えたものか悩んでしまう。ファザコンとかマザコンとか言われても嫌だしね。
俺が心の中でそんな葛藤と戦っていると、ふとユミィが俯いていることに気が付く。
「……羨ましい」
「羨ましい……ですか?」
そんな呟きが聞こえ、思わず俺が聞き返すとユミィが顔を上げてキッと睨み返されてしまう。
若干、目に涙を溜めていることに気付いて俺が声を掛けようとするが―
「えっと、大丈夫―」
「私に構わないで下さい!」
そう言って、すごい剣幕で返されてしまった。
「あ……す、すいません」
すると、すぐに自分の失態に気付いたのかユミィは慌てて訂正するも、気まずそうに顔を歪ませていた。
「……では、私はこれで失礼いたします」
「あ、ちょっと―」
そんなユミィにどう声を掛けようか悩んでいると、背中を向けて自分の部屋の方へと帰っていってしまった。
(……なんか、思ってた感じとだいぶ違う子だったな。間違っても、あれがリーヴの妹だとか思えないよな)
制止も聞かずに去って行く背中を見ながら、俺はそう思ってならなかったのだった。
実は魔法が使えず、生まれながらにして魔力を持たない呪いを受けているらしいということ。
『分家』の人間や他の貴族達にそれを知られると舐められかねないと屋敷内にずっと閉じ込め、その存在そのものを秘密にしているということ。
そして、それが『忌み子』と言われている存在だという事だ。
(知らなかった……まさか、リーヴに妹が居たなんてな。もしかしたら、父上は知っているかもしれなけど……じゃあ、さっき俺を見ていたのはその妹ってことになるのか?)
リーヴから話を聞いた後、俺は一度トイレへと向かった帰りに彼から聞かされた話を思い出しつつ、リーヴの部屋へと戻ろうと廊下を歩く。
この廊下を渡れば、すぐにリーヴの部屋だ。
しかし、俺は少しばかりその妹の存在が気になっていた。
(……ちょっとくらい良いよな?)
リーヴの話では、その妹はリーヴの部屋のさらに先、屋敷の奥にある部屋に居るそうだ。
普段はあまり部屋の外に出ないらしいが、屋敷内に来客が来た時は気になって自分の部屋の窓から様子を見ていたらしい。
特に『分家』の俺達が屋敷に招かれた時は、小さい頃から必ず部屋から眺めていたらしく、向こうは俺や父上の顔を知っているそうだ。
とはいえ、バレたらマズいと『本家』の母親から止められており、これまでは窓の外から見るくらいだったらしいが、今日はあいにくとその母親が不在らしく、それで廊下まで出て来て様子を見に来たんじゃないか、とリーヴは言っていた。
向こうは俺を知っていて、でも俺の方は知らないというのも違和感があるよな。
だったら、少しだけ様子を見てからリーヴの部屋へ戻ってもそこまで時間は掛からないし、これくらいは許されるだろ。
(リーヴのことだ。どうせ、トイレの時間を待たせただけでも文句を言われるわけだし、ちょっとだけ遅れても問題無いだろ)
そうして、俺はリーヴの部屋の前を通り過ぎると、例の『本家』の長女の部屋の方へと向かうことにした。
(それにしても、リーヴの妹か……。リーヴや当主様に似て、やっぱり『本家』らしく嫌な人間に育ってるのかな? というか、今までずっと一人っ子だと思ってたから、リーヴに妹が居るとか言われても実感が湧かないよな……)
ともかく、少しその姿を見てみるか。俺にとっては一応親類ってことになるんだし。
そうして、俺がその妹の部屋へ向かおうと、廊下の角を曲がろうした時だった。
「あ……」
すると、そこに居た存在と目が合い、その相手から声がもれると同時に……俺は言葉を失ってしまった。
そこに居たのは見たこともない少女だった。
長く白い髪と細い体は目を奪われてしまうほど美しく、少なくとも生まれてからこれほど綺麗な人間と出会ったことはない。
そして、さらに俺が声を失った理由はその独特な目の色だった。
(髪が白い……? それに、目が金色に光ってる?)
俺達ユーグ家の特徴として、髪は金色で目は全員青い。
嫁いできた母上や『本家』の奥様はともかく、多少の濃さに違いはあれど、その血を引いた者は全員そうだった。
しかし、目の前の子供は違った。
顔立ちはどこか『本家』の面々の面影はあるものの、金色の目や白い髪をしているところは全く違う。
(もしかして……この子がリーヴの言ってた妹なのか?)
まさか、こんなにも簡単に出会うとは……少し様子を見て帰るくらいの予定だったから突然顔を正面から突き合わせてしまい、少々戸惑ってしまう。
「……」
だが、そんな俺よりも驚いた顔を見せたまま立ち止まっている少女を前に、とりあえず俺は外行き用の人の良さそうな笑顔を作ると、戸惑う少女へと声を掛けた。
「ごめん、人が居るとは思っていなかったんだ。怪我は無いか?」
「―よね?」
「ん? 何か言ったかい?」
すると、何やら目の前の少女が小さく呟いたことに気付き、俺は咄嗟に聞き返すように返事をしてしまう。
俺よりも小さい少女を怖がらせまいとした態度に、少女は睨み付けるような視線と共にこんなことを口走ってきた。
「あなたは『分家』の方……ですよね?」
そう言うと、目の前の少女はどうにか姿勢を立て直しながらパッパッと服の誇りを払うようにして佇まいを正し始める。
しかし、冷静なようでいて動揺の方が大きいらしく、一度大きく深呼吸をしていた。
そんな少女を前に、俺は普段父上と仕事をしている時のように貴族然とした振る舞いで少女へと挨拶する。
「申し遅れました。私の名前はアシック・ユーグ。仰る通り、『分家』の長男です。あなたはリーヴ様の妹君でお間違いないでしょうか?」
「あ……は、はい……。その、ユミィ・ユーグ……と申します」
「これは失礼いたしました。知らなかったとはいえ、『本家』の方に失礼な態度を取ってしまっておりました。無知な私をどうかお許し下さい」
「あ……えっと……」
俺が恭しく頭を下げてみせると、慌てたように戸惑いを見せるユミィ。
ずっと幽閉されていたという話だし、恐らくあまり人と接したことがなくてこういう時の対応が分からないのかもしれない。
このまま困らせたままというのもなんだし、一応はリーヴを待たせている手前、助け舟を出しておくことにしよう。
「そうでした。ユミィ様、お怪我などは無かったでしょうか?」
「怪我……ですか? は、はい、特には……」
「それは良かったです。『本家』の方である前に、初対面の方に怪我をさせてしまうなど、父上に顔向け出来なくなってしまいますから」
「そう……なんですか?」
「ええ。『本家』の方々はもちろん尊敬しておりますが、『分家』の人間であるとはいえ、私は父のことも尊敬しております。その父は貴族としての誇りを非常に強く持っている方なので礼儀作法には少々厳しく、万が一、父の耳に他の方を私が傷付けたと入ってしまうようなことがあれば、父に怒られてしまいますから」
俺は冗談交じりそう言ってユミィへと笑みを向ける。
実際には話の通じる父は不可抗力だった場合などには注意はするだろうが、そこまで怒ることはないし、あくまでも場を和ます為の冗談だ。
そんな俺の言葉にユミィは驚いた顔を浮かべると、どこか羨むような声をこぼした。
「……そんなにお父様を尊敬なさっているということは、仲が良いのですね」
「どうなのでしょう? ただ、父はもちろん、母も尊敬しているのは間違いありません」
改まって「仲が良い」とか言われると、どう答えたものか悩んでしまう。ファザコンとかマザコンとか言われても嫌だしね。
俺が心の中でそんな葛藤と戦っていると、ふとユミィが俯いていることに気が付く。
「……羨ましい」
「羨ましい……ですか?」
そんな呟きが聞こえ、思わず俺が聞き返すとユミィが顔を上げてキッと睨み返されてしまう。
若干、目に涙を溜めていることに気付いて俺が声を掛けようとするが―
「えっと、大丈夫―」
「私に構わないで下さい!」
そう言って、すごい剣幕で返されてしまった。
「あ……す、すいません」
すると、すぐに自分の失態に気付いたのかユミィは慌てて訂正するも、気まずそうに顔を歪ませていた。
「……では、私はこれで失礼いたします」
「あ、ちょっと―」
そんなユミィにどう声を掛けようか悩んでいると、背中を向けて自分の部屋の方へと帰っていってしまった。
(……なんか、思ってた感じとだいぶ違う子だったな。間違っても、あれがリーヴの妹だとか思えないよな)
制止も聞かずに去って行く背中を見ながら、俺はそう思ってならなかったのだった。