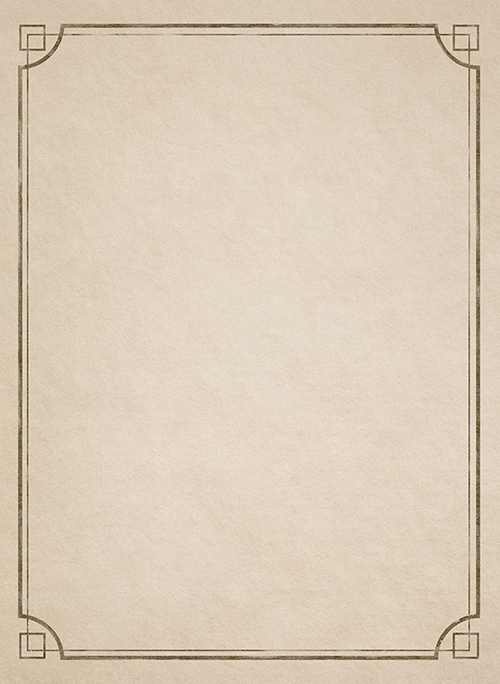「―相変わらず、情けない顔をしているなあ? レナルド」
そう言って、部屋に入った俺達を迎えたのは、『本家』の当主であり、この街の領主ということになっているデバット・ユーグだ。
情けなく肥え太った様子は、それだけ領地の人間達から過剰に搾取していることの現れでもあり、そうしたことが人々からの信頼を下げている。
実際、俺達『分家』があらゆる手段を使って領地の人々から信頼を勝ち取るようにしているが、ほとんど手が回っておらず、はっきり言って『ユーグ家』に不満を持っている人間の方が圧倒的に多い。
その怒りの矛先が向けられているのが、今、目の前に要るオーク……じゃなかった、当主様だ。
あまりにも人間離れした情けない当主様を見ていると、ギロリと睨み付けられてしまう。
「ん~? 何かと思えば、『分家』の『無能』な長男アシックか。あまりにも魔力が無さ過ぎて居ることにすら気付かなかったぞ?」
魔力を感じ取る技術も持ってない癖によく言うよ……。
とはいえ、ここで本音を口にしたところで、父上や母上達の生活が脅かされるだけなので、あくまでも俺は『分家』の長男として毅然とした態度で返す。
「当主様、いつもお世話になっております。魔力を操ることの出来ない点については、『ユーグ家』の恥とならぬよう、今後も改善することに尽力したいと思っております」
「はっはっは! 『無能』が何をしたところで『無能』だ。所詮は『分家』の人間、生まれた時からその存在そのものが恥よ。お前達は私の代わりに領地の面倒事を解決していれば良いのだ。ただし、少しくらい魔法を使ってもらわんと『本家』である我々の評判も下げかねん。そう考えると、さっさと魔法の一つでも使って欲しいものだがなぁ?」
「はい、より一層尽力したいと思います」
「俺に師匠を付けたい」って提案した時に癇癪起こしておいてよく言うよ……。
まあ、実際には『魔導書』のおかげで魔法は使えるようになってるけどね。まだ言わないけど。
そんな俺に、父上は視線を送ると当主様の前だと言うこともあり、いつもより鋭さを増した声で俺を促してきた。
「アシック、そろそろリーヴ様にご挨拶してきなさい。後は私が当主様へ報告しておこう」
「分かりました、父上。では、当主様、失礼いたします」
父上からの提案に乗り、俺は当主様へと頭を下げた後に部屋を出て行く。
これも毎度のことで、この後は性悪リーヴにわざわざ挨拶に行かなければならないわけだ。ただ、何故か父上は当主様と話す時は俺に席を外させるんだよな……。
(まあ、良いか。気乗りしないけど、さっさと終わらせ―ん?)
そうして、俺が当主様の部屋から出た後、リーヴの部屋へと向かっていた時のことだ。
突然、後ろから視線を感じて振り返ってみるも……そこには誰も居なかった。
(……気のせいか?)
どこか不思議な感覚を覚えつつも、俺はリーヴの部屋へと向かいながら重い足を動かし始めた。
◇
「―よお、アシック。相変わらず、ぼーっとしたツラしてるじゃないか」
リーヴの部屋へ入ると、いかにもガキ大将らしいニヤニヤとした表情で俺を迎えてきた。しかも、顔を合わすなり、自分の父親と同じようなことを言ってくるところを見ると、改めてこいつらは親子だなと思うね。
俺はそんな『本家』の長男に対して、挨拶だけはきちんとしておくことにする。
「おはようございます、リーヴ様」
「やめろよな、そういう気持ち悪ぃの。俺がそういうの嫌いだってことは知ってるだろ?」
そう言って、露骨に顔を歪めるリーヴ。
リーヴは容姿端麗とか言われているが、すぐにこういう顔をしたりするから街の人々からはあまりそう思われていない。
そんな噂が立っているのはあくまでも街の外で行われている貴族パーティに参加している時だけで、領地以外の人間達からの受けが良いだけだ。
領地のお坊ちゃんとして育てられていたリーヴは、正直に言えば礼儀とは無縁の男だ。
体裁的に貴族同士では取り繕ってはいるものの、敬語など畏まった場がとにかく苦手でガサツだ。
俺はそんなリーヴに分からないようにため息を吐くと、普通の口調へと戻すことにする。
「敬語が気持ち悪い」というリーヴと「敬語を外しては良いが、口答えは許さない」というなんとも面倒な取り決めをされており、それをどうにか守る努力をしながら言葉を返す。
「それじゃあ……おはよう、リーヴ」
「それで良い。お前達『分家』の人間はそうやって素直に俺達に従ってれば良いんだ。ロクに魔法も使えない『無能』のお前でも、将来は俺の下に付いて役に立ってもらうつもりだからな。次期当主様の言うことはしっかり聞いてもらわないとな?」
そう言って、リーヴは「ふふん」と偉そうに胸を張る。
街の人間を困らせたりする時の悪知恵だけは働くリーヴは、こんな風にいつも俺を馬鹿にして来るのだ。
何かにつけて俺と比較してくるリーヴは面倒ではあったが、適当に首を縦に振ってご機嫌取りをしていれば割と流せるから我慢するしかない。
「さて、アシック。俺は暇で仕方がない。俺が暇にならないように話題を提供しろ」
「いきなりそんなことを言われてもね……」
とりあえず、今は命令された通り敬語は使わず、かつ口答えしないような会話を心掛けておくか。それと、話題の提供ついでに、ついさっき感じた視線のことでも聞いておくことにしよう。
「そういえば、リーヴ。この屋敷内でさっき誰かに見られていたような気がしたんだ」
「誰か? どうせ使用人だろ」
「いや、当主様の部屋から出てからすぐだったんだけど、部屋の周りには用も無いのに使用人は近付けないだろうから違うと思うんだよ」
「何だ~? じゃあ、お前、もしかして昼間に幽霊でも見たって言うのか? そんなわけ―」
俺が怖がっていると思ったのか、意地の悪い笑みを浮かべながら続きを話そうとしていたリーヴ。
しかし、突然思い詰めたような顔になると、俺の方へと視線を向けてきた。
「どうかした?」
「お前……見たのか?」
「見た、って何を?」
勝手に何かを察し始めたリーヴに付いて行けず、俺は首を傾げる。
それを見たリーヴは「なんだ、見たわけじゃねぇのか……」と安堵の息を吐くも、今度は取り巻き達を連れている時のような悪ガキの笑みを浮かべてきた。
「……良いか? 本ッ当は内緒なんだが、お前は将来俺の下で働いてもらう予定だから特別に教えてやる。他の奴らには絶対に言うなよな?」
「まあ、良いけど……」
妙に楽しげに言ってくるリーヴに違和感を抱きつつも、ここで機嫌を損ねるもの面倒だと思い俺がそう答えると、リーヴは悪ガキらしい意地の悪い笑みを深めながらこんなことを教えてくれたのだ。
「『本家』の子供は俺一人って事になってるけど―この家にはな、実は俺の妹が居るんだよ」
そう言って、部屋に入った俺達を迎えたのは、『本家』の当主であり、この街の領主ということになっているデバット・ユーグだ。
情けなく肥え太った様子は、それだけ領地の人間達から過剰に搾取していることの現れでもあり、そうしたことが人々からの信頼を下げている。
実際、俺達『分家』があらゆる手段を使って領地の人々から信頼を勝ち取るようにしているが、ほとんど手が回っておらず、はっきり言って『ユーグ家』に不満を持っている人間の方が圧倒的に多い。
その怒りの矛先が向けられているのが、今、目の前に要るオーク……じゃなかった、当主様だ。
あまりにも人間離れした情けない当主様を見ていると、ギロリと睨み付けられてしまう。
「ん~? 何かと思えば、『分家』の『無能』な長男アシックか。あまりにも魔力が無さ過ぎて居ることにすら気付かなかったぞ?」
魔力を感じ取る技術も持ってない癖によく言うよ……。
とはいえ、ここで本音を口にしたところで、父上や母上達の生活が脅かされるだけなので、あくまでも俺は『分家』の長男として毅然とした態度で返す。
「当主様、いつもお世話になっております。魔力を操ることの出来ない点については、『ユーグ家』の恥とならぬよう、今後も改善することに尽力したいと思っております」
「はっはっは! 『無能』が何をしたところで『無能』だ。所詮は『分家』の人間、生まれた時からその存在そのものが恥よ。お前達は私の代わりに領地の面倒事を解決していれば良いのだ。ただし、少しくらい魔法を使ってもらわんと『本家』である我々の評判も下げかねん。そう考えると、さっさと魔法の一つでも使って欲しいものだがなぁ?」
「はい、より一層尽力したいと思います」
「俺に師匠を付けたい」って提案した時に癇癪起こしておいてよく言うよ……。
まあ、実際には『魔導書』のおかげで魔法は使えるようになってるけどね。まだ言わないけど。
そんな俺に、父上は視線を送ると当主様の前だと言うこともあり、いつもより鋭さを増した声で俺を促してきた。
「アシック、そろそろリーヴ様にご挨拶してきなさい。後は私が当主様へ報告しておこう」
「分かりました、父上。では、当主様、失礼いたします」
父上からの提案に乗り、俺は当主様へと頭を下げた後に部屋を出て行く。
これも毎度のことで、この後は性悪リーヴにわざわざ挨拶に行かなければならないわけだ。ただ、何故か父上は当主様と話す時は俺に席を外させるんだよな……。
(まあ、良いか。気乗りしないけど、さっさと終わらせ―ん?)
そうして、俺が当主様の部屋から出た後、リーヴの部屋へと向かっていた時のことだ。
突然、後ろから視線を感じて振り返ってみるも……そこには誰も居なかった。
(……気のせいか?)
どこか不思議な感覚を覚えつつも、俺はリーヴの部屋へと向かいながら重い足を動かし始めた。
◇
「―よお、アシック。相変わらず、ぼーっとしたツラしてるじゃないか」
リーヴの部屋へ入ると、いかにもガキ大将らしいニヤニヤとした表情で俺を迎えてきた。しかも、顔を合わすなり、自分の父親と同じようなことを言ってくるところを見ると、改めてこいつらは親子だなと思うね。
俺はそんな『本家』の長男に対して、挨拶だけはきちんとしておくことにする。
「おはようございます、リーヴ様」
「やめろよな、そういう気持ち悪ぃの。俺がそういうの嫌いだってことは知ってるだろ?」
そう言って、露骨に顔を歪めるリーヴ。
リーヴは容姿端麗とか言われているが、すぐにこういう顔をしたりするから街の人々からはあまりそう思われていない。
そんな噂が立っているのはあくまでも街の外で行われている貴族パーティに参加している時だけで、領地以外の人間達からの受けが良いだけだ。
領地のお坊ちゃんとして育てられていたリーヴは、正直に言えば礼儀とは無縁の男だ。
体裁的に貴族同士では取り繕ってはいるものの、敬語など畏まった場がとにかく苦手でガサツだ。
俺はそんなリーヴに分からないようにため息を吐くと、普通の口調へと戻すことにする。
「敬語が気持ち悪い」というリーヴと「敬語を外しては良いが、口答えは許さない」というなんとも面倒な取り決めをされており、それをどうにか守る努力をしながら言葉を返す。
「それじゃあ……おはよう、リーヴ」
「それで良い。お前達『分家』の人間はそうやって素直に俺達に従ってれば良いんだ。ロクに魔法も使えない『無能』のお前でも、将来は俺の下に付いて役に立ってもらうつもりだからな。次期当主様の言うことはしっかり聞いてもらわないとな?」
そう言って、リーヴは「ふふん」と偉そうに胸を張る。
街の人間を困らせたりする時の悪知恵だけは働くリーヴは、こんな風にいつも俺を馬鹿にして来るのだ。
何かにつけて俺と比較してくるリーヴは面倒ではあったが、適当に首を縦に振ってご機嫌取りをしていれば割と流せるから我慢するしかない。
「さて、アシック。俺は暇で仕方がない。俺が暇にならないように話題を提供しろ」
「いきなりそんなことを言われてもね……」
とりあえず、今は命令された通り敬語は使わず、かつ口答えしないような会話を心掛けておくか。それと、話題の提供ついでに、ついさっき感じた視線のことでも聞いておくことにしよう。
「そういえば、リーヴ。この屋敷内でさっき誰かに見られていたような気がしたんだ」
「誰か? どうせ使用人だろ」
「いや、当主様の部屋から出てからすぐだったんだけど、部屋の周りには用も無いのに使用人は近付けないだろうから違うと思うんだよ」
「何だ~? じゃあ、お前、もしかして昼間に幽霊でも見たって言うのか? そんなわけ―」
俺が怖がっていると思ったのか、意地の悪い笑みを浮かべながら続きを話そうとしていたリーヴ。
しかし、突然思い詰めたような顔になると、俺の方へと視線を向けてきた。
「どうかした?」
「お前……見たのか?」
「見た、って何を?」
勝手に何かを察し始めたリーヴに付いて行けず、俺は首を傾げる。
それを見たリーヴは「なんだ、見たわけじゃねぇのか……」と安堵の息を吐くも、今度は取り巻き達を連れている時のような悪ガキの笑みを浮かべてきた。
「……良いか? 本ッ当は内緒なんだが、お前は将来俺の下で働いてもらう予定だから特別に教えてやる。他の奴らには絶対に言うなよな?」
「まあ、良いけど……」
妙に楽しげに言ってくるリーヴに違和感を抱きつつも、ここで機嫌を損ねるもの面倒だと思い俺がそう答えると、リーヴは悪ガキらしい意地の悪い笑みを深めながらこんなことを教えてくれたのだ。
「『本家』の子供は俺一人って事になってるけど―この家にはな、実は俺の妹が居るんだよ」