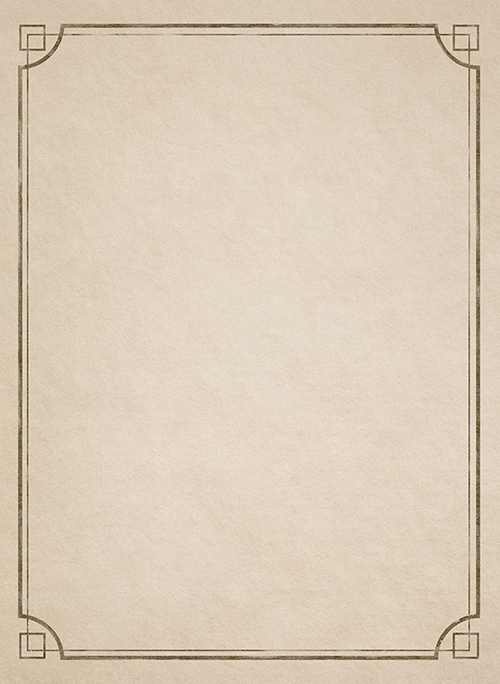―『分家』とは何か。
色々な理由で本来の血筋とは別の家系として成り立ったものだ。
それぞれ理由はあるだろうが、俺の家系である『ユーグ家』の場合は遠い先祖の誰かが親の反対を押し切って結婚したとかなんとかで、それで本家とは別の『分家』として生まれたそうだ。
子孫からしてみたら良い迷惑以外の何物でもないが、おかげさまで俺は立場の弱い『分家』の人間として『本家』の奴らから良い目で見られていない。
まあ、先祖の話はともかくとして、理由はどうあれ『本家』と『分家』では立場が全く違っている。
例えば、今俺の目の前で取り巻きと一緒に笑っている男―リーヴ・ユーグが何を言おうが、立場の弱い『分家』の俺―アシック・ユーグはどんな理不尽なことを言われても言い返すことが許されないそうだ。
「お前みたいな無能は分家がお似合いだ」
だから、こんなことを言われても言い返すことはできないし、実際に『本家』の人間からすれば、魔法も使えない俺は、確かに『無能』には違いないだろう。
しかし、リーヴが笑っていられるのも俺達が小さい頃までだった。
才能に溺れ、俺達『分家』の人間を嘲笑うことしかしてこなかったリーヴ達は知らない。
俺が家に置かれていた魔導書を研究し続けて、誰も到達しえない魔法の力を手に入れていたことを。
そして、まともに領地を統治していない怠け者の『本家』に代わって領地を保っていた『分家』の方が街の人間達から支持を集めていることを。
そんな中、リーヴはその手に魔法で炎を作って見せると、いわゆるドヤ顔で俺を見下すように口を開いた。
「これくらいの魔法を使うのもアシックには難しいだろうな? 何せ、『分家』の人間だ。お前達みたいな『無能』は、せいぜい俺達『本家』の人間の代わりに働くくらいしか出来ないだろ?」
リーヴが笑いながらそう口にすると、取り巻き達もそれにつられるようにして笑い始める。
まあ、そろそろ良いだろ。
魔法は完全に習得したし、俺が実は魔法を使えるってことをバラすには丁度良い頃合いだ。
いい加減、何も出来ない『無能』のフリは疲れたし、こいつの驚いた顔を見てやりたいと思ってたしな。
すると、俺はリーヴが魔法で作り、その手のひらの上で踊る小さな炎を見る。
そして、同じように手をリーヴ達へと向けると―その瞬間、空にも届きそうな勢いで俺の手のひらから炎が噴き出した。
「な、なんだ!?」
驚きのあまり、自分の手のひらで燃やしていた炎を消してしまうリーヴ。
そんな『本家』の長男に向け、『分家』の長男である俺は業火のごとく燃える炎を手に宿しながらニヤリとした笑みを返してやった。
「―それで? リーヴ、誰が『無能』だって?」
◇
まず、俺達『分家』がどんな立場に置かれているか。
色々とあるが、その最たるものが貴族の集まりに呼ばれないことだ。
年に一度、貴族達はパーティを催して各々貴族同士の交流を図り、利益ある話に興じるのだが、俺はそのパーティに参加した事は一度もなかった。
実際は『分家』だからと言って参加が許されていないわけじゃない。
他の貴族でも『分家』で参加が許されているところはたくさんあるし、少なくとも俺達『ユーグ家』よりも『分家』の扱いは格段に良い。
だから、俺達『分家』が参加を許されていないのは、ただ単に『本家』の人間達の嫌がらせに過ぎなかった。
貴族においてパーティに参加するというのは「自分達がその場に立つことができる優秀な貴族である」ということの証明であり、本来であれば貴族にとっての誇りを再認識できる場所でもある。
まあ、平たく言えば、そのパーティに参加出来ない貴族っていうのは貴族として認められないわけで、おかげで長い間、俺達『分家』は周囲の貴族達からもまともに存在を認知されていないわけだ。
「ま、そんなことするくらいなら、この『魔導書』でも読んで時間潰すから良いけどさ」
そう言って、俺は地下の書庫から取り出した魔導書をペラペラとめくっていく。
小さい頃から俺は『本家』の人間達から『無能』と呼ばれ続けていた。
『本家』の人間達は俺達『分家』を嫌っており、とりわけ魔法の才能がなかった俺をよく見下していた。
向こうの長男のリーヴが特にそれが強く、同世代だということもあって俺を目の敵にしてくるんだよな。
とはいえ、魔法が使えないんじゃ、あいつに言い返すこともできないわけだ。
そうは言っても、実際は完全に魔法が使えないわけじゃない。ぶっちゃけて言うと、制御の仕方が分からず、加減が出来ないから怖い、というのが一番大きい理由だったりする。
リーヴの場合、本家の金を使ってかなり優秀な師匠を雇ったおかげで、小さい頃から魔法を使う事が出来たわけだが、俺達『分家』は『本家』から目を付けられている所為で、まともに師匠を雇うことも出来なかった。
実際、師匠を雇おうとしたところ―
「『分家』の分際で師匠を迎え入れるなど……まさか、『本家』を乗っ取るつもりか!?」
とか何とか言って、向こうのご当主様がキレてしまい、手が付けられなくなったからだそうだ。
いやはや、まともに領地のことも管理しない上に『分家』であるうちに任せっきりのお飾り当主様は相変わらず心が狭い。
まあ、そんなこんなで、小さい頃から『分家』の人間として『本家』の代わりに色々なことをさせられてきたから実年齢以上に老けてしまった。
そんな俺の唯一の楽しみが、この『魔導書』の存在だ。
「頭の中でイメージを強めて、それを自分の体から出すような感じか。魔力の多い人間の場合は暴走してしまう可能性がある為、炎の場合は小さいロウソクくらいのものを想像する……と。こんな感じか?」
頭の中でロウソクをイメージすると、手のひらに魔力を集中させる。
俺は生まれながらにして魔力の量が普通の人間とは桁違いだったらしい。
その所為で、制御を知らずに魔法を出すと暴走し掛けてしまい、それを反射的に抑えようとして魔法を出すのを俺が拒否してしまっているのだそうだ。
とはいえ、父も母もそこまでの魔力を持っていなかったから俺の魔力の制御の仕方が分からず、おまけに師匠も雇えないからお手上げ状態だった。
しかし、そんな中で出会ったのがこの『魔導書』だ。
俺は分厚い『魔導書』の最初の方に載っていた初歩的な魔力制御のやり方に沿って、魔力を集中させたのだが―
「こ、これが俺の魔法……?」
手のひらからまるで太陽のように強い光を放つ炎が生まれ、俺は驚きと喜びのあまり言葉を失ってしまった。
それを目にした俺は、『魔導書』の最初の方に書かれていた言葉を思い出し、興奮とも驚きとも取れない感覚に高揚するのを隠せなかった。
『最初に炎の魔法で太陽のようなものを作れた子供の魔力は、普通の子供とは比べ物にならないほどに大きく、また誰よりも優秀な魔法使いになれる素質がある』
◇
その日から、俺はひたすら魔法の勉強に励み続けた。
相変わらず本家からの扱いは酷かったが、それでも関係なく俺はただ家にある『魔導書』で勉強を続け、色々な魔法をそこから学んでいた。
例えば、今日は雷の魔法を生み出す為に『魔導書』を読み込んでいたところだ。
俺は書庫にある机の上で例の『魔導書』を開きながら、それを頭に叩き込む為に独りごちながら『魔導書』の中身を読み進めていく。
「なになに、『雷の魔法を使用する場合、まずは対象となるものに雷が落ちることを想像するのがもっとも大切である』……か。対象に落ちる……雷が木に落ちるようなイメージをすれば良いのか?」
そんなことをぼやきつつ、前に一度起きた嵐で雷が遠くで光っているのを目にした時のことを頭の中に思い浮かべる。
そして、試しに窓を開いて家の前に生えていた木を目標に手を構えてみた。
(あの木に雷が落ちるのをイメージして―)
と、目を瞑って軽く頭の中でイメージをした時だった。
「うわっ!?」
突然、轟音が鳴り響いて目の前の木に落雷が浴びせられてしまう。
目の前にあった木が丸焦げになり、さらにパチパチと音を立てながら少しばかり火が立ち上っていた。
「やば……もしかして、俺がやっちゃった? とりあえず、水の魔法を使って消さないと!」
火の魔法の後、『魔導書』で水の魔法を学んでいた俺はすぐに頭の中で水をイメージして、それを手から放ち、小さな火を灯している木へと窓から水を放った。すると、火は音を立てて消え、ひとまずの危機を凌いだ俺は「ふぅ……」と安堵の息を吐いていた。
「……考えてみたら、俺の魔力だとちょっと強力過ぎるかもな。水の魔法を覚えてなかったら、今頃入れ物に水を大量に入れて消火しに行かないといけなかったし……もう少し制御出来るように工夫しておかないと」
改めて、自分の魔力量が多過ぎることにため息をついていると、扉の向こうからドタバタとすごい音が聞こえてきた。
「大丈夫か、アシック!? 今、家の前に雷が落ちたそうだが……はぁ、無事だったようだな……」
「父上……」
そう言って、血眼になりながら扉を開いて顔を出したのは我が家で一番の苦労人である父―レナルド・ユーグだった。
父は血相を変えて俺の近くまで来て無事を確認した後、窓から見える木を眺めながらため息交じりに口を開いた。
「お前が無事で良かった……。まさか、こんな天気で落雷が起こるとは思ってもみなかったからな。この後もまた雷が落ちる可能性がある。私と母さんで屋敷を魔法で防御しておくから、今日は外出禁止だ。良いな?」
「はい。分かりました、父上」
俺は机の上に置いてあった『魔導書』を机の下へと隠しつつそう答える。
危ない危ない……この状況で「実は僕の魔法でした」なんて知られたら、危険だからと『魔導書』を取り上げられるかもしれないもんな。
そんな俺の心境など知らず、父上はため息交じりに外へと目を落とした後、俺の方へと視線を戻すと感心したように声を上げた。
「それにしても、今日も勉強に励んでいるのか。お前の勤勉さには父として誇りを感じるよ」
「はい。誇り高き『ユーグ家』の人間として、また父上のように民に慕われるような人間になりたいと常に思っておりますから」
「はっはっは、アシックは褒め上手だな。だが、私は所詮『分家』の人間だ。私を目標とするより、『本家』の人間のようになりたいと思う、という方が正しいだろう」
そう言って謙虚に微笑む父だが、そこには無理をしている様子が伺えた。
まあ、そもそもこの領地の主である『本家』の人間はまともに仕事なんてしていないし、それを目標とするのもおかしい話だ。
実質的にこの地を統治しているのは目の前で父であり、また『分家』である俺達だった。
幼い頃から父の手伝いで『分家』の長男として一緒に仕事をする機会もあり、俺はその事実をよく知っている為、父も冗談交じりにそう口にするしかないのだ。
だから、俺はそんな父に対してしっかりとした口調で返す。
「父上、私は『本家』の人間のようになるつもりはありません。私達『分家』の人間にばかり仕事を押し付ける彼らを模範とするのは、誇り高き貴族としてあるまじきことだと思いますから」
「よく言った―と、言いたいところだが、『本家』の者達の前でそれを口にすることは厳禁だ。税の管理だけは彼らが行っている以上、迂闊なことを言えば、私達の生活も苦しくなってしまう。アシック、お前はとても優秀な子だ。しかし、だからこそ、『本家』の人間から目を付けられていることを忘れてはならないぞ」
「はい、もちろんです、父上。しかし、私が一番尊敬しているのは父上や母上のように、人々から信頼されている人間であることに変わりはありません」
「ははっ、まったく……出来過ぎる息子というのも考えものだな。そう言われては父として返す言葉もない。ならば、『分家』の人間としてではなく、誇り高き『ユーグ家』の人間としてもっと精進なさい。そうして、我々が居なければ『ユーグ家』が成り立たない……『本家』や『分家』など関係なく、我々こそが『ユーグ家』であると証明すれば良い」
「はい!」
そう言って、俺は決意を込めた声を返した。
『魔導書』の存在を知られない為、少しばかり誇張し過ぎたところはあるものの、本音はもちろん『本家』の連中に負けたくはない。
何はともあれ、こうして魔法の勉強を続けていくのだった。
そんなこんなである程度、俺が魔法を学んで少し経ったある日のことだ。
俺と父上、そして母上の三人で仲良く朝食の為に食卓を囲んでいたところ、食事の手を止めた父が真剣な表情で俺に声を向けてきた。
「アシック。分かっていると思うが、今日は定期連絡の日だ。この後、お前も『本家』へ向かう為の支度をなさい」
「はい、父上」
父の言う定期連絡とは、『本家』の代わりに領地を統治している父が『本家』の当主にその様子を報告する日だ。
まあ、そんな御大層なことを言っているが、要は適当に理由を付けて俺達『分家』の人間をいびりたいが為のタチの悪い呼び出しみたいなものだが。
父を呼び出してはその度に嫌味を言ってくるのだから、『本家』のだだっ広い屋敷で食って寝るだけの生活をしている『本家』の方々はさぞ暇なんだろう。
とはいえ、これも長年行われてきた『ユーグ家』の『本家』と『分家』の恒例の習わしでもある為、父も断ることはできない。
ついでに言うと、毎回俺も一緒に行くのだが……その度に向こうの長男であるリーヴから嫌味を言われるのも恒例となっていた。
リーヴ・ユーグ。
『ユーグ家』の『本家』の長男であり、幼い頃から魔法の才覚を表し、容姿端麗、文武両道と謳われる天才……というのは他の貴族への表向きの顔。
実際にはその才能に溺れるあまり、努力とは無縁に育ってしまったお金持ちの性悪お坊ちゃんだ。
自分で言うのもなんだが、父の仕事で老成してしまった俺に対して、向こうは逆に歳の割に子供だ。
よく近所の悪ガキを連れては、そこら中で悪さをして領地の人間達から嫌われているし、典型的なガキ大将という奴だったりする。
そして、その標的にされているうちの一人が『分家』の長男である俺だ。
まあ、苦労も知らないお坊ちゃん相手にいちいち怒っても仕方ないし、あんなもの街の苦情処理に比べれば些細なものだ。そうは言っても、自分からいびられに行くのは気乗りしないが。
「あら、もうそんな時期なのね」
そう口にするのは俺の母―ミーファ・ユーグだ。
威厳のある父に対して、おっとりしたお嬢様然とした母だが、実際この家に嫁いでくる前はまさに『深窓の令嬢』といった感じのお嬢様だったらしい。
そして、この母も例外ではなく『本家』の人間―特に向こうの母親と交流があり、顔を合わす度に散々嫌味を言われているそうだが、全く気にする素振りがないのだから驚きだ。
父曰く、「肝が据わっている素敵な女性だ」ということらしいが、あの口うるさい『本家』の母の話を聞き流せるのはそういうのを逸していると思う。
しかし、そんなおっとりした母だが、『分家』の人間として『本家』の人間の代わりに街の人間を相手にしても臆することなく、また父の右腕として上がってくる不満や提案を処理する様は流石だとしか言いようがない。
向こうの母親からは「お飾り」とか言われているらしいが、実際に「お飾り」なのはあんただろ、と言い返してやりたいもんだ。
「呼び出される度に当主様に文句を言われるなんて、本当に損な仕事よね」
「そう言うな、ミーファ。これも立派な『ユーグ家』の仕事だ」
「だって、その度にうちのアシックも悪く言われるじゃない。こんなに優秀で良い子に育ったのに、魔法が使えないからって理由で酷いことを言うんだから嫌になっちゃうわよね」
そう言って、俺の代わりに怒ってくれる母上。
普段からおっとしている母だが、こうして家族が馬鹿にされている時はきちんと怒ってくれるのは、息子としては少しむずがゆいところだが同時に嬉しくもあった。
そんな母に心配を掛けまいと、俺は父にならって母を落ち着かせるように言葉を続ける。
「大丈夫ですよ、母上。実際、僕が魔法を使うことが出来ないのは事実ですから。その分、父上や母上の仕事を手伝い、領地の管理に向き合うように尽力しますが、『本家』の方々からはやはり下に見られてしまうのは諦めています。ですが、父上や母上の仕事を手伝っているおかげで街の人々からは信頼されていますから、『本家』の方々から少し文句を言われるくらいのこと、僕は気にしませんよ」
「アシック……本当に良い子に育って母は嬉しいです。やっぱり、こんな優秀な子が『本家』の人間から文句を言われるのは納得がいかないわ」
「母上、ありがとうございます。父上や母上が僕の味方をしてくれるだけでも、僕は充分に幸せ者です」
「アシック……」
「ははっ、本当にアシックは子供とは思えないほどに達観してしまったな。とはいえ、それを嬉しく感じる反面、親としてはもう少し子供らしさを持ってもらった方が良いとさえ思ってしまうものだが。やはり、私達の仕事を手伝わせるのはもう少し減らした方が良いかもしれんな」
俺の言葉に笑いながらも複雑な顔を作る父に対し、俺は父上や母上から学んだ礼儀正しさと謙虚さを保ちつつ、極めて貴族然とした振る舞いで返していく。
「いえ、父上や母上から学ぶことはまだまだ多いので、このままお手伝いさせて下さい。街の人々との交流は、今後『分家』の当主となる際に役立つと父上も仰っていましたし、僕としては良い経験になっていますから」
「しかし、勉強の方は良いのか? 最近は書庫に籠って勉強をしているようだが、私達に付いてばかりいては集中出来ないのではないか?」
「ご心配には及びません。勉強については母上から日頃教わっていることの復習をしているだけですし、それほど時間は取りませんから」
本当は書庫にある『魔導書』で密かに魔法を学んでいるわけだが、それをバレないようにするにはなるべく良い子を演じる必要がある。遊ぶものが少なかった俺にとって、あの『魔導書』はどんなものよりも魅力的だ。
こういう風に話しておけば、書庫で勉強している時は父上や母上もそっと様子を見守ってくれるだろう。
そんな俺の熱心さが伝わったのか、父はゆっくりと頷いてみせると落ち着いた様子で俺に言葉を向けてくる。
「……分かった。アシック、お前はとても優秀に育ってくれた。勉強については私からはもう口を挟まん。今後も『ユーグ家』の長男として、己を磨いてゆけ」
「はい、父上。ありがとうございます」
「では、食事を終えた後は『本家』へ顔を出すぞ。これも立派な『分家』の長男としての務めだからな」
「はい!」
尊敬する父を見て俺は心から頷いてみせると、そんな俺達を母が嬉しそうに見ていたのだった。
色々な理由で本来の血筋とは別の家系として成り立ったものだ。
それぞれ理由はあるだろうが、俺の家系である『ユーグ家』の場合は遠い先祖の誰かが親の反対を押し切って結婚したとかなんとかで、それで本家とは別の『分家』として生まれたそうだ。
子孫からしてみたら良い迷惑以外の何物でもないが、おかげさまで俺は立場の弱い『分家』の人間として『本家』の奴らから良い目で見られていない。
まあ、先祖の話はともかくとして、理由はどうあれ『本家』と『分家』では立場が全く違っている。
例えば、今俺の目の前で取り巻きと一緒に笑っている男―リーヴ・ユーグが何を言おうが、立場の弱い『分家』の俺―アシック・ユーグはどんな理不尽なことを言われても言い返すことが許されないそうだ。
「お前みたいな無能は分家がお似合いだ」
だから、こんなことを言われても言い返すことはできないし、実際に『本家』の人間からすれば、魔法も使えない俺は、確かに『無能』には違いないだろう。
しかし、リーヴが笑っていられるのも俺達が小さい頃までだった。
才能に溺れ、俺達『分家』の人間を嘲笑うことしかしてこなかったリーヴ達は知らない。
俺が家に置かれていた魔導書を研究し続けて、誰も到達しえない魔法の力を手に入れていたことを。
そして、まともに領地を統治していない怠け者の『本家』に代わって領地を保っていた『分家』の方が街の人間達から支持を集めていることを。
そんな中、リーヴはその手に魔法で炎を作って見せると、いわゆるドヤ顔で俺を見下すように口を開いた。
「これくらいの魔法を使うのもアシックには難しいだろうな? 何せ、『分家』の人間だ。お前達みたいな『無能』は、せいぜい俺達『本家』の人間の代わりに働くくらいしか出来ないだろ?」
リーヴが笑いながらそう口にすると、取り巻き達もそれにつられるようにして笑い始める。
まあ、そろそろ良いだろ。
魔法は完全に習得したし、俺が実は魔法を使えるってことをバラすには丁度良い頃合いだ。
いい加減、何も出来ない『無能』のフリは疲れたし、こいつの驚いた顔を見てやりたいと思ってたしな。
すると、俺はリーヴが魔法で作り、その手のひらの上で踊る小さな炎を見る。
そして、同じように手をリーヴ達へと向けると―その瞬間、空にも届きそうな勢いで俺の手のひらから炎が噴き出した。
「な、なんだ!?」
驚きのあまり、自分の手のひらで燃やしていた炎を消してしまうリーヴ。
そんな『本家』の長男に向け、『分家』の長男である俺は業火のごとく燃える炎を手に宿しながらニヤリとした笑みを返してやった。
「―それで? リーヴ、誰が『無能』だって?」
◇
まず、俺達『分家』がどんな立場に置かれているか。
色々とあるが、その最たるものが貴族の集まりに呼ばれないことだ。
年に一度、貴族達はパーティを催して各々貴族同士の交流を図り、利益ある話に興じるのだが、俺はそのパーティに参加した事は一度もなかった。
実際は『分家』だからと言って参加が許されていないわけじゃない。
他の貴族でも『分家』で参加が許されているところはたくさんあるし、少なくとも俺達『ユーグ家』よりも『分家』の扱いは格段に良い。
だから、俺達『分家』が参加を許されていないのは、ただ単に『本家』の人間達の嫌がらせに過ぎなかった。
貴族においてパーティに参加するというのは「自分達がその場に立つことができる優秀な貴族である」ということの証明であり、本来であれば貴族にとっての誇りを再認識できる場所でもある。
まあ、平たく言えば、そのパーティに参加出来ない貴族っていうのは貴族として認められないわけで、おかげで長い間、俺達『分家』は周囲の貴族達からもまともに存在を認知されていないわけだ。
「ま、そんなことするくらいなら、この『魔導書』でも読んで時間潰すから良いけどさ」
そう言って、俺は地下の書庫から取り出した魔導書をペラペラとめくっていく。
小さい頃から俺は『本家』の人間達から『無能』と呼ばれ続けていた。
『本家』の人間達は俺達『分家』を嫌っており、とりわけ魔法の才能がなかった俺をよく見下していた。
向こうの長男のリーヴが特にそれが強く、同世代だということもあって俺を目の敵にしてくるんだよな。
とはいえ、魔法が使えないんじゃ、あいつに言い返すこともできないわけだ。
そうは言っても、実際は完全に魔法が使えないわけじゃない。ぶっちゃけて言うと、制御の仕方が分からず、加減が出来ないから怖い、というのが一番大きい理由だったりする。
リーヴの場合、本家の金を使ってかなり優秀な師匠を雇ったおかげで、小さい頃から魔法を使う事が出来たわけだが、俺達『分家』は『本家』から目を付けられている所為で、まともに師匠を雇うことも出来なかった。
実際、師匠を雇おうとしたところ―
「『分家』の分際で師匠を迎え入れるなど……まさか、『本家』を乗っ取るつもりか!?」
とか何とか言って、向こうのご当主様がキレてしまい、手が付けられなくなったからだそうだ。
いやはや、まともに領地のことも管理しない上に『分家』であるうちに任せっきりのお飾り当主様は相変わらず心が狭い。
まあ、そんなこんなで、小さい頃から『分家』の人間として『本家』の代わりに色々なことをさせられてきたから実年齢以上に老けてしまった。
そんな俺の唯一の楽しみが、この『魔導書』の存在だ。
「頭の中でイメージを強めて、それを自分の体から出すような感じか。魔力の多い人間の場合は暴走してしまう可能性がある為、炎の場合は小さいロウソクくらいのものを想像する……と。こんな感じか?」
頭の中でロウソクをイメージすると、手のひらに魔力を集中させる。
俺は生まれながらにして魔力の量が普通の人間とは桁違いだったらしい。
その所為で、制御を知らずに魔法を出すと暴走し掛けてしまい、それを反射的に抑えようとして魔法を出すのを俺が拒否してしまっているのだそうだ。
とはいえ、父も母もそこまでの魔力を持っていなかったから俺の魔力の制御の仕方が分からず、おまけに師匠も雇えないからお手上げ状態だった。
しかし、そんな中で出会ったのがこの『魔導書』だ。
俺は分厚い『魔導書』の最初の方に載っていた初歩的な魔力制御のやり方に沿って、魔力を集中させたのだが―
「こ、これが俺の魔法……?」
手のひらからまるで太陽のように強い光を放つ炎が生まれ、俺は驚きと喜びのあまり言葉を失ってしまった。
それを目にした俺は、『魔導書』の最初の方に書かれていた言葉を思い出し、興奮とも驚きとも取れない感覚に高揚するのを隠せなかった。
『最初に炎の魔法で太陽のようなものを作れた子供の魔力は、普通の子供とは比べ物にならないほどに大きく、また誰よりも優秀な魔法使いになれる素質がある』
◇
その日から、俺はひたすら魔法の勉強に励み続けた。
相変わらず本家からの扱いは酷かったが、それでも関係なく俺はただ家にある『魔導書』で勉強を続け、色々な魔法をそこから学んでいた。
例えば、今日は雷の魔法を生み出す為に『魔導書』を読み込んでいたところだ。
俺は書庫にある机の上で例の『魔導書』を開きながら、それを頭に叩き込む為に独りごちながら『魔導書』の中身を読み進めていく。
「なになに、『雷の魔法を使用する場合、まずは対象となるものに雷が落ちることを想像するのがもっとも大切である』……か。対象に落ちる……雷が木に落ちるようなイメージをすれば良いのか?」
そんなことをぼやきつつ、前に一度起きた嵐で雷が遠くで光っているのを目にした時のことを頭の中に思い浮かべる。
そして、試しに窓を開いて家の前に生えていた木を目標に手を構えてみた。
(あの木に雷が落ちるのをイメージして―)
と、目を瞑って軽く頭の中でイメージをした時だった。
「うわっ!?」
突然、轟音が鳴り響いて目の前の木に落雷が浴びせられてしまう。
目の前にあった木が丸焦げになり、さらにパチパチと音を立てながら少しばかり火が立ち上っていた。
「やば……もしかして、俺がやっちゃった? とりあえず、水の魔法を使って消さないと!」
火の魔法の後、『魔導書』で水の魔法を学んでいた俺はすぐに頭の中で水をイメージして、それを手から放ち、小さな火を灯している木へと窓から水を放った。すると、火は音を立てて消え、ひとまずの危機を凌いだ俺は「ふぅ……」と安堵の息を吐いていた。
「……考えてみたら、俺の魔力だとちょっと強力過ぎるかもな。水の魔法を覚えてなかったら、今頃入れ物に水を大量に入れて消火しに行かないといけなかったし……もう少し制御出来るように工夫しておかないと」
改めて、自分の魔力量が多過ぎることにため息をついていると、扉の向こうからドタバタとすごい音が聞こえてきた。
「大丈夫か、アシック!? 今、家の前に雷が落ちたそうだが……はぁ、無事だったようだな……」
「父上……」
そう言って、血眼になりながら扉を開いて顔を出したのは我が家で一番の苦労人である父―レナルド・ユーグだった。
父は血相を変えて俺の近くまで来て無事を確認した後、窓から見える木を眺めながらため息交じりに口を開いた。
「お前が無事で良かった……。まさか、こんな天気で落雷が起こるとは思ってもみなかったからな。この後もまた雷が落ちる可能性がある。私と母さんで屋敷を魔法で防御しておくから、今日は外出禁止だ。良いな?」
「はい。分かりました、父上」
俺は机の上に置いてあった『魔導書』を机の下へと隠しつつそう答える。
危ない危ない……この状況で「実は僕の魔法でした」なんて知られたら、危険だからと『魔導書』を取り上げられるかもしれないもんな。
そんな俺の心境など知らず、父上はため息交じりに外へと目を落とした後、俺の方へと視線を戻すと感心したように声を上げた。
「それにしても、今日も勉強に励んでいるのか。お前の勤勉さには父として誇りを感じるよ」
「はい。誇り高き『ユーグ家』の人間として、また父上のように民に慕われるような人間になりたいと常に思っておりますから」
「はっはっは、アシックは褒め上手だな。だが、私は所詮『分家』の人間だ。私を目標とするより、『本家』の人間のようになりたいと思う、という方が正しいだろう」
そう言って謙虚に微笑む父だが、そこには無理をしている様子が伺えた。
まあ、そもそもこの領地の主である『本家』の人間はまともに仕事なんてしていないし、それを目標とするのもおかしい話だ。
実質的にこの地を統治しているのは目の前で父であり、また『分家』である俺達だった。
幼い頃から父の手伝いで『分家』の長男として一緒に仕事をする機会もあり、俺はその事実をよく知っている為、父も冗談交じりにそう口にするしかないのだ。
だから、俺はそんな父に対してしっかりとした口調で返す。
「父上、私は『本家』の人間のようになるつもりはありません。私達『分家』の人間にばかり仕事を押し付ける彼らを模範とするのは、誇り高き貴族としてあるまじきことだと思いますから」
「よく言った―と、言いたいところだが、『本家』の者達の前でそれを口にすることは厳禁だ。税の管理だけは彼らが行っている以上、迂闊なことを言えば、私達の生活も苦しくなってしまう。アシック、お前はとても優秀な子だ。しかし、だからこそ、『本家』の人間から目を付けられていることを忘れてはならないぞ」
「はい、もちろんです、父上。しかし、私が一番尊敬しているのは父上や母上のように、人々から信頼されている人間であることに変わりはありません」
「ははっ、まったく……出来過ぎる息子というのも考えものだな。そう言われては父として返す言葉もない。ならば、『分家』の人間としてではなく、誇り高き『ユーグ家』の人間としてもっと精進なさい。そうして、我々が居なければ『ユーグ家』が成り立たない……『本家』や『分家』など関係なく、我々こそが『ユーグ家』であると証明すれば良い」
「はい!」
そう言って、俺は決意を込めた声を返した。
『魔導書』の存在を知られない為、少しばかり誇張し過ぎたところはあるものの、本音はもちろん『本家』の連中に負けたくはない。
何はともあれ、こうして魔法の勉強を続けていくのだった。
そんなこんなである程度、俺が魔法を学んで少し経ったある日のことだ。
俺と父上、そして母上の三人で仲良く朝食の為に食卓を囲んでいたところ、食事の手を止めた父が真剣な表情で俺に声を向けてきた。
「アシック。分かっていると思うが、今日は定期連絡の日だ。この後、お前も『本家』へ向かう為の支度をなさい」
「はい、父上」
父の言う定期連絡とは、『本家』の代わりに領地を統治している父が『本家』の当主にその様子を報告する日だ。
まあ、そんな御大層なことを言っているが、要は適当に理由を付けて俺達『分家』の人間をいびりたいが為のタチの悪い呼び出しみたいなものだが。
父を呼び出してはその度に嫌味を言ってくるのだから、『本家』のだだっ広い屋敷で食って寝るだけの生活をしている『本家』の方々はさぞ暇なんだろう。
とはいえ、これも長年行われてきた『ユーグ家』の『本家』と『分家』の恒例の習わしでもある為、父も断ることはできない。
ついでに言うと、毎回俺も一緒に行くのだが……その度に向こうの長男であるリーヴから嫌味を言われるのも恒例となっていた。
リーヴ・ユーグ。
『ユーグ家』の『本家』の長男であり、幼い頃から魔法の才覚を表し、容姿端麗、文武両道と謳われる天才……というのは他の貴族への表向きの顔。
実際にはその才能に溺れるあまり、努力とは無縁に育ってしまったお金持ちの性悪お坊ちゃんだ。
自分で言うのもなんだが、父の仕事で老成してしまった俺に対して、向こうは逆に歳の割に子供だ。
よく近所の悪ガキを連れては、そこら中で悪さをして領地の人間達から嫌われているし、典型的なガキ大将という奴だったりする。
そして、その標的にされているうちの一人が『分家』の長男である俺だ。
まあ、苦労も知らないお坊ちゃん相手にいちいち怒っても仕方ないし、あんなもの街の苦情処理に比べれば些細なものだ。そうは言っても、自分からいびられに行くのは気乗りしないが。
「あら、もうそんな時期なのね」
そう口にするのは俺の母―ミーファ・ユーグだ。
威厳のある父に対して、おっとりしたお嬢様然とした母だが、実際この家に嫁いでくる前はまさに『深窓の令嬢』といった感じのお嬢様だったらしい。
そして、この母も例外ではなく『本家』の人間―特に向こうの母親と交流があり、顔を合わす度に散々嫌味を言われているそうだが、全く気にする素振りがないのだから驚きだ。
父曰く、「肝が据わっている素敵な女性だ」ということらしいが、あの口うるさい『本家』の母の話を聞き流せるのはそういうのを逸していると思う。
しかし、そんなおっとりした母だが、『分家』の人間として『本家』の人間の代わりに街の人間を相手にしても臆することなく、また父の右腕として上がってくる不満や提案を処理する様は流石だとしか言いようがない。
向こうの母親からは「お飾り」とか言われているらしいが、実際に「お飾り」なのはあんただろ、と言い返してやりたいもんだ。
「呼び出される度に当主様に文句を言われるなんて、本当に損な仕事よね」
「そう言うな、ミーファ。これも立派な『ユーグ家』の仕事だ」
「だって、その度にうちのアシックも悪く言われるじゃない。こんなに優秀で良い子に育ったのに、魔法が使えないからって理由で酷いことを言うんだから嫌になっちゃうわよね」
そう言って、俺の代わりに怒ってくれる母上。
普段からおっとしている母だが、こうして家族が馬鹿にされている時はきちんと怒ってくれるのは、息子としては少しむずがゆいところだが同時に嬉しくもあった。
そんな母に心配を掛けまいと、俺は父にならって母を落ち着かせるように言葉を続ける。
「大丈夫ですよ、母上。実際、僕が魔法を使うことが出来ないのは事実ですから。その分、父上や母上の仕事を手伝い、領地の管理に向き合うように尽力しますが、『本家』の方々からはやはり下に見られてしまうのは諦めています。ですが、父上や母上の仕事を手伝っているおかげで街の人々からは信頼されていますから、『本家』の方々から少し文句を言われるくらいのこと、僕は気にしませんよ」
「アシック……本当に良い子に育って母は嬉しいです。やっぱり、こんな優秀な子が『本家』の人間から文句を言われるのは納得がいかないわ」
「母上、ありがとうございます。父上や母上が僕の味方をしてくれるだけでも、僕は充分に幸せ者です」
「アシック……」
「ははっ、本当にアシックは子供とは思えないほどに達観してしまったな。とはいえ、それを嬉しく感じる反面、親としてはもう少し子供らしさを持ってもらった方が良いとさえ思ってしまうものだが。やはり、私達の仕事を手伝わせるのはもう少し減らした方が良いかもしれんな」
俺の言葉に笑いながらも複雑な顔を作る父に対し、俺は父上や母上から学んだ礼儀正しさと謙虚さを保ちつつ、極めて貴族然とした振る舞いで返していく。
「いえ、父上や母上から学ぶことはまだまだ多いので、このままお手伝いさせて下さい。街の人々との交流は、今後『分家』の当主となる際に役立つと父上も仰っていましたし、僕としては良い経験になっていますから」
「しかし、勉強の方は良いのか? 最近は書庫に籠って勉強をしているようだが、私達に付いてばかりいては集中出来ないのではないか?」
「ご心配には及びません。勉強については母上から日頃教わっていることの復習をしているだけですし、それほど時間は取りませんから」
本当は書庫にある『魔導書』で密かに魔法を学んでいるわけだが、それをバレないようにするにはなるべく良い子を演じる必要がある。遊ぶものが少なかった俺にとって、あの『魔導書』はどんなものよりも魅力的だ。
こういう風に話しておけば、書庫で勉強している時は父上や母上もそっと様子を見守ってくれるだろう。
そんな俺の熱心さが伝わったのか、父はゆっくりと頷いてみせると落ち着いた様子で俺に言葉を向けてくる。
「……分かった。アシック、お前はとても優秀に育ってくれた。勉強については私からはもう口を挟まん。今後も『ユーグ家』の長男として、己を磨いてゆけ」
「はい、父上。ありがとうございます」
「では、食事を終えた後は『本家』へ顔を出すぞ。これも立派な『分家』の長男としての務めだからな」
「はい!」
尊敬する父を見て俺は心から頷いてみせると、そんな俺達を母が嬉しそうに見ていたのだった。