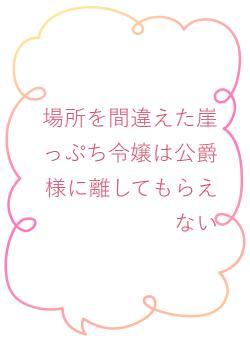世界なんか滅びてしまえばいいのにと思うことがあった。
人間など、いない方がいいのではないかと。
その中には自分も、私の大切な人も含まれてしまうというのに。
くだらない理由で命が失われ、くだらない理由で世界が悲しみに包まれている時代。優しさだ愛だと言うけれど、そんなのはいつも言葉だけで、人間はどこまでも愚かで救いようがなかった。神など信じてはいないが、もし自分が神なら、とっくに世界を滅ぼしているだろうと、五郎は思っていた。
理不尽なことが多すぎる。
そしてその理不尽は、いつだって弱い者にのみ、向けられるのだ。
五郎には五歳年の離れた妹がいる。そしてその妹は、ある病気を患っている。臓器移植が必要だが、自分は適合者ではなかった。両親はおらず、母方の祖母も不適合。父方の親類は両親の結婚に反対だったせいで付き合いがなかった。もちろん、一縷の望みをかけ頼みに行った。検査を受けてほしい、と。しかし父方の祖父母は、勝手に家を出て行った息子夫婦のことなど知ったことかと言わんばかりに追い返されたのだ。妹が母親に似ていたことも気に入らなかったらしい。自分の息子をたぶらかした女狐、とでも思っていたに違いない。
孫だぞ?
五郎は何度もそう叫んだが、聞き入れてはもらえなかった。もちろん、適合者ではない可能性だって大いにあるのだが、妹の体調を考えればどんなに小さい望みだとしても試さずにはいられなかったのだ。
人の命が掛かっているというのに、知らんぷりだ。
そんな人間が……身内に、だ。
「仕方ないよ」
妹はそう言って笑ったが、五郎にはそう思えなかった。
「スノードロップがいたら、ぎゃふんと言わせてやるんだけどね」
あはは、と笑う妹の手は、小刻みに震えていた。
スノードロップ、というのは妹が書いた小説に出てくる登場人物だ。孤高の殺し屋で、暗い過去を持つハードボイルドな男。病気がちで学校に行けないことが多い彼女は、よくノートに物語を綴っていた。綺麗な令嬢でもイケメンのヒーローでもない、人間味のある話が多かった。
「マツユキソウってすごく可憐で可愛い花なのにさ、花言葉が『あなたの死を望みます』だなんて、すごくない? 殺し屋のコードネームにぴったりじゃない?」
キャッキャしながら殺し屋の話を語る一風変わった妹を、何とか救ってやれる手立てが欲しかった。
両親の死後、幼い兄妹は一度、親類の家に預けられた。しかし預けられた先で両親の残してくれた遺産を使い込まれ、挙句、逃げられたのだ。その後、母方の祖母が保護者になっているが、今は体を壊し施設にいる。祖父母のいた家にひっそりと身を置き、兄妹で寄り添うように暮らしていた矢先、今度は元々体の弱かった妹の病気が発覚。五郎は大学を中退してがむしゃらに働いたが、とても追いつかないところまで来ていた。
「ねぇ、お兄ちゃん。私ね、誰のことも恨んでないからね?」
症状の悪化で入院を余儀なくされた妹が、ある日そう切り出した。
「みんな生きることに必死なんだよ。だからお兄ちゃんも、誰かを恨んだりしないでね? 私がいなくなっても、お兄ちゃんは笑って生きて」
無理だ、と思った。
「それと、私ドナー登録してるから、忘れないで。もし私が死んじゃっても、私の一部が誰かの命を繋ぐの。それってすごいでしょ?」
どうして妹の命を救えないのか。
「私は誰かの中で生きられるんだよ」
こんな残酷な世界、存続させる意味があるのか?
「お兄ちゃんは頭いいんだからさ、いつか世界を変えられると思うな」
妹の言葉にハッとする。
世界を変える。
ああ、そうだ。
世界を変えることを……考えればいいんだ。
そんな風に考えていた矢先、蘭が現れたのだ。
『あなたは、世界を滅ぼそうとしている』
まさに、その通りだった。
*****
睨み合いが続く中、不意に電話が鳴る。五郎が一瞬だけ、ひどく辛そうな顔をしたのを蘭は見逃さなかった。
「もしもしっ……はい……ええ、すぐ行きます」
電話を切るころには、その辛そうな顔は絶望へと変わってゆく。
「……どうかした?」
蘭が心配そうに顔を覗き込むと、
「お前には関係ない」
と背を向け、財布を片手に外へ出ようとする。蘭は慌ててボストンバッグを手に後を追った。
「どこいくの? 私もっ」
「ついてくるなっ!」
「そうはいかないっ」
なにかがあったのだ、と蘭は思った。過去の記憶を手繰り寄せる。蓮見五郎の身に起きた、人生を変える、なにか。そして思い出す。彼に、妹がいたということを。
そう。蓮見五郎には妹がいた。しかしそれは公式には知られていない。複雑な家庭で育った兄妹は、確か叔母夫婦に引き取られ、後に母方の祖母に預けられている。その際、幼かった妹だけ祖母の養子になっていた。だから蓮見五郎とは苗字も違っているし、戸籍上は五郎の叔母に当たる。
「もしかして、妹さんに何かあったのっ?」
先を行く五郎の腕を取り、強引に引っ張ると、五郎は苦虫を嚙み潰したような顔をし、
「ドナーが現れなければ、助からない」
とだけ、告げた。
「ドナー……」
かつて自分もそうだった。どこかの誰かが臓器を提供してくれたから、生きているのだ。けれど、適合者が現れる可能性というのは、なかなかに難しい。同じ血の通った家族でもなかなか適合しなかったりするのだ。それに、もし適合者が見つかった場合でも、いざという段になって断られてしまうケースもあると聞く。
『世界を救える可能性があるの、あなただけなんですよねぇ』
唐突に、女神の言葉が蘇る。
世界を……救う。
可能性があるのはあなただけ、と言われた、その意味がわからなかった。でも、もしかしたら、と気付く。
蓮見五郎にとっての、世界。それは、唯一の肉親と言ってもいいくらい大切な、妹のことだったのではないのか? そう仮定するなら、自分がここに返された意味とはつまり、
「それだ~~~!!」
蘭は五郎を指しながら、声を上げた。
これですべてが繋がった。どうして自分がここにいるのか。どうして猶予が一週間なのか。
「なんだよ、突然っ」
声を荒げる蘭に五郎がビクつく。
「私だ! 私が妹さんを助けるんだわ!」
「はぁ?」
「大丈夫! 私、多分臓器提供できるの!」
目をギラギラさせながら語る蘭。
「いきなり何を、」
「いいから、行くわよ!」
蘭は五郎の腕をぐいぐい引っ張ると、走り出した。
*****
病院でのやり取りは、順調だった。女神は蘭の身分証だけでなく、ドナーになるために必要なすべてを揃えていたようだ。バッグにはしてもいない検査資料まで入っており、神の御業に驚かされる。それにしても、これが答えなら最初からそう言ってくれればよかったのに、と思うほど答えはすぐそばにあった。
いくつかの追加検査を済ませると、病室へ向かう。そこには力なくベッドに沈む五郎の妹の姿があった。蘭を見て、不思議そうに首を傾げる。
「杏里、具合は?」
五郎が兄の顔になりベッドに近付く。妹の名は、市村杏里。母方の祖父母の姓を名乗っているのだ。
「おにい……ちゃん? と、……彼女さん?」
「ばっ、違うっ」
五郎がムキになって訂正する。
「初めまして。私は篠宮蘭。私はあなたのドナーになるの」
血縁以外でドナーがドナーを名乗ることなど普通は有り得ないが、まぁ、いいだろう、と、蘭は自己紹介をする。
「えっ? 本当に……?」
杏里が驚いたような、それでいてホッとしたような顔を見せる。
「ええ、大丈夫よ。私があなたと、彼を救うわ」
振り返り、五郎を見た。
「救う……、すごい! お姉さん、カッコいい!」
興奮気味に顔を輝かせる杏里。
「私もね、もし死んだらそうやって誰かを救いたいって思ってた。私の体、使えるところ全部使ってもらって誰かを助けるの! でも、実際死が近いんだってわかると……カッコいいことなんか一つも言えなくて」
俯き、涙ぐむ。
「当たり前じゃない! 誰だって死にたくなんかないもの!」
きゅ、っと杏里の手を握る。
ぐるん、と脳内が反転するようなおかしな感覚に襲われ、一瞬目を閉じる。
その瞬間、すべて理解した。頭の中に流れ込んでくるこの映像が、これから先の『未来』なのだと。
差し戻された意味。
やるべきこと。
蘭は、すべてを飲み込む。一度失くした命だ。今更惜しんだ所でどうなるものでもない。それより、本当に自分は世界を救うのだ、という使命感の方がずっと大切で、大きくなっていた。
それでも、少し残念なこともある。今、ここでのやり取りを、自分は忘れてしまうのだ。出来ることなら持っていきたい。未来の自分に、教えてあげたい。けれど……。
「必ず元気になるわ。大丈夫だからね」
蘭は杏里の頭をポンと軽く叩くと、
「蓮見さん、ちょっと話がある」
と、病室の外へと連れ出した。
*****
屋上では洗濯物が風にはためいていた。
「お前、本当に……いいのか? その……ドナーの件」
五郎がぼそぼそと訊ねる。
「もちろん、いいわよ。それより、聞いてほしいことがあるの」
「なに?」
オブラートに包んで伝えることも考えたが、無理そうだ。仕方ないからそのままズバリを言ってしまう。
「私、多分だけど、もうすぐ死ぬ」
「はっ?」
五郎の目が真ん丸になる。当然だろう。出会ってからというもの、おかしなことしか口にしていないのだ。今はその最高峰。杏里のドナーになるだけなら死ななくてもいいだろうに、何故この命が絶たれるのか。理由が、ちゃんとある。
「なに言い出すんだ、お前っ?」
「言ったでしょ? 私はここに死に戻ったの。理由はあなたを落として未来を救うため……って言われたけど違うわね。杏里ちゃんのドナーになるため。それと、私自身のドナーになるためなんだわ」
面白い話だ。これに気付いた時は、ちょっと感心してしまった。
「なんの話だ?」
「この世界にはもう一人私が存在する。今、この世界の私は十一歳。そして杏里ちゃんと同じように、ドナーを待ってる」
そう。蘭もまた、ドナーが現れなければ死ぬ運命だった。しかし、まさか自分が自分のドナーになるなんてこと、考えもしなかった。
「さっき杏里ちゃんの手を握った時にすべてが視えた。私の名前は篠宮蘭じゃない。これは女神さまが用意した仮の器なのね。だから一週間しか持たないんだ」
「おい、」
早口で捲し立てる蘭に、五郎が声をかけるが、
「お願いがある。私が死んだら、花柳凛って子を探して。そして私の臓器が彼女に渡るようにしてほしい。私ったら、自分が贈った自分の臓器に感動して警察官目指すのね。笑っちゃうわ」
手摺を掴み空を見上げ、ふふ、と笑みを浮かべる。
「警察?」
「そ。私ね、ドナーに命を救われてから、人の命を救う仕事がしたいって考えるようになるの。で、とある国家の秘密機関に入って正義の名のもとに活動するわけ。カッコいいでしょ?」
「恋人も作らず、結婚もせず、ってやつか?」
「……余計なことは覚えてるのね」
チッと舌打ちを返す。
「とにかく、私が死んで、花柳凛は生きる。それでいい」
五郎は半信半疑のようだ。当然だろうが。
「それと、この話もしておくわ。スノードロップの花言葉は『あなたの死を望みます』だけじゃない。『逆境の中の希望』ってのもあるの。ちゃんと調べたんだからねっ? ……私が、あなたの希望になれたならよかったのだけど。残念ながらタイムオーバーだわ」
「なにを言って、」
杏里さえ死ななければ、きっと五郎は悪い道にそれることもなくなるはずだ。それでも、妹の面倒を見ながら二人で生きていくのはきっと大変なこと。そんな五郎の、心の支えになってあげられるだけの時間はない。
「もうすぐ心臓発作で倒れるわ」
「誰が?」
「だから、私が! さっき視えたの!」
まるで走馬灯のようだった。倒れる蘭を抱き留める五郎。名を呼び続ける五郎。それはまるで映画のワンシーンのようで、思わずニヤついてしまうほどだった。
「王子様のキスでもありゃ、生き返るのかしらね」
肩を竦めると、体に異変を感じる。来る!
ドクンッ、と心臓を掴まれるような息苦しさが襲い、その場にしゃがみ込む。
「おい!」
五郎が駆け寄り、跪いた。
「時間だわ。あっという間だったわね。一週間どころか、一日で片付いたじゃない。私ったら……優秀な……」
「おい、しっかりしろ!」
遠ざかる意識の中、五郎の声がこだまする――。
*****
「おい! しっかりしろ! おい!」
耳元で誰かが叫んでいる。何故だか一瞬、懐かしさを感じた。
「おい!」
何度目かの『おい』で目を開けると、教官の顔が間近にあった。
「……あ、れ?」
「あれ? じゃないだろうっ。しっかりしろ、花柳凛!」
全身ずぶ濡れで、髪からも水が滴っている。見れば、教官もまた同じように全身ずぶ濡れ。その姿を見て、思わず凛は、
「水も滴る……なんとやら、ですね」
と口走った。
「ふざけるな! どれだけ心配したと思ってるんだっ」
そう言って凛を見つめる瞳は、真剣そのものだった。
「すみません」
特殊な機関に身を置くための特別カリキュラムを受けている最中だった。遠泳中に、足が攣った。波に押し流され沈みそうになったところで救助されたらしい。
「今、医療班を呼んでくる! 上陸したら医者に診てもらえ! いいなっ?」
そう言って去って行く。
と、近くにいた先輩が、
「あの鬼教官があんなに狼狽えるとこ初めて見た」
と、何故かニヤニヤしながら話し掛けてきたのだ。
「え?」
聞き返すと、
「花柳って、教官のなに?」
と質問で返される。
「なにって……部下、ですよね?」
他になんと言えばいいのかわからない。入所当時から目を掛けてもらっているのはなんとなく感じてはいたが、知り合いではない。
「ただの部下にあんなこと言わないだろ」
「……何か言ってたんですか?」
眉を寄せ、声を落とす。と、先輩は少し悩んだ顔をした後、凛の耳元に口を寄せ、
「『目を覚ませ、花柳凛! 王子様のキスで目を覚ますんじゃないのか!』って言いながら必死に人工呼吸してたぞ?」
と説明してくれた。
「はぁぁぁぁ?」
一気に心臓が跳ね上がり、頭に血が上るのを感じる。
「あの、蓮見五郎にそんなセリフ言わせるお前って、何者だよ」
ニヤニヤが止まらない先輩と、ドキドキが止まらない凛。蓮見五郎といえば、泣く子も黙る鬼教官で、文武両道、クールでセクシーで、凛の憧れでもあるのだ。この機関に入った時から、凛は蓮見五郎のことがずっと気になっていた。歳も離れているし、決して好みのタイプではないはずなのだが、何故か惹かれるのだ。その、蓮見が人工呼吸……。
「ま、とにかく無事で何よりだったけどな。お前、無茶しすぎるなよ?」
「あ、はい。すみませんでした」
頭を下げると、そこに再び蓮見五郎が現れる。どんな顔をすればいいかわからず、思わず目を逸らしてしまった。急に心臓の音がうるさく感じられる。
「担架が出せないらしい。救護室まで連れていく」
片膝を立て、凛をひょいと抱き上げる。
「ひょわぁぁぁっ。あ、あああ歩けますよ、教官!」
「黙って抱かれてろ!」
とんでもない台詞を吐く五郎の顔を、チラ、と見上げる。そしてつい、出来心で口にしてしまう。
「……教官は、王子だったんですか?」
一瞬ぎょっとした顔で凛を見た五郎は、すぐに真顔に戻ると、言った。
「こんな話、お前は信じないだろうがな、俺が今こうしてここにいるのはお前のおかげだ。十年前、俺はお前に落とされてんだよ」
「……へ? なんの話……じゅ、十年前って……私、しょうがっ……教官て、ロリコ……」
カタコトになりながら言葉を返す。十年前の凛は、蓮見のことなど知らない。
「違うっ」
「だって、今の発言……え? ストーカー?」
「違うと言っているだろう! ……いつか話してやる。お前は……間違いなく俺の希望だったよ」
「へ?」
おかしな声を上げる凛に向かって、五郎は更にこう付け加えた。
「今度は俺が、お前を落とす番だ」
腕の中にいる凛を見つめ、優しく笑ったのである――。
おしまい
人間など、いない方がいいのではないかと。
その中には自分も、私の大切な人も含まれてしまうというのに。
くだらない理由で命が失われ、くだらない理由で世界が悲しみに包まれている時代。優しさだ愛だと言うけれど、そんなのはいつも言葉だけで、人間はどこまでも愚かで救いようがなかった。神など信じてはいないが、もし自分が神なら、とっくに世界を滅ぼしているだろうと、五郎は思っていた。
理不尽なことが多すぎる。
そしてその理不尽は、いつだって弱い者にのみ、向けられるのだ。
五郎には五歳年の離れた妹がいる。そしてその妹は、ある病気を患っている。臓器移植が必要だが、自分は適合者ではなかった。両親はおらず、母方の祖母も不適合。父方の親類は両親の結婚に反対だったせいで付き合いがなかった。もちろん、一縷の望みをかけ頼みに行った。検査を受けてほしい、と。しかし父方の祖父母は、勝手に家を出て行った息子夫婦のことなど知ったことかと言わんばかりに追い返されたのだ。妹が母親に似ていたことも気に入らなかったらしい。自分の息子をたぶらかした女狐、とでも思っていたに違いない。
孫だぞ?
五郎は何度もそう叫んだが、聞き入れてはもらえなかった。もちろん、適合者ではない可能性だって大いにあるのだが、妹の体調を考えればどんなに小さい望みだとしても試さずにはいられなかったのだ。
人の命が掛かっているというのに、知らんぷりだ。
そんな人間が……身内に、だ。
「仕方ないよ」
妹はそう言って笑ったが、五郎にはそう思えなかった。
「スノードロップがいたら、ぎゃふんと言わせてやるんだけどね」
あはは、と笑う妹の手は、小刻みに震えていた。
スノードロップ、というのは妹が書いた小説に出てくる登場人物だ。孤高の殺し屋で、暗い過去を持つハードボイルドな男。病気がちで学校に行けないことが多い彼女は、よくノートに物語を綴っていた。綺麗な令嬢でもイケメンのヒーローでもない、人間味のある話が多かった。
「マツユキソウってすごく可憐で可愛い花なのにさ、花言葉が『あなたの死を望みます』だなんて、すごくない? 殺し屋のコードネームにぴったりじゃない?」
キャッキャしながら殺し屋の話を語る一風変わった妹を、何とか救ってやれる手立てが欲しかった。
両親の死後、幼い兄妹は一度、親類の家に預けられた。しかし預けられた先で両親の残してくれた遺産を使い込まれ、挙句、逃げられたのだ。その後、母方の祖母が保護者になっているが、今は体を壊し施設にいる。祖父母のいた家にひっそりと身を置き、兄妹で寄り添うように暮らしていた矢先、今度は元々体の弱かった妹の病気が発覚。五郎は大学を中退してがむしゃらに働いたが、とても追いつかないところまで来ていた。
「ねぇ、お兄ちゃん。私ね、誰のことも恨んでないからね?」
症状の悪化で入院を余儀なくされた妹が、ある日そう切り出した。
「みんな生きることに必死なんだよ。だからお兄ちゃんも、誰かを恨んだりしないでね? 私がいなくなっても、お兄ちゃんは笑って生きて」
無理だ、と思った。
「それと、私ドナー登録してるから、忘れないで。もし私が死んじゃっても、私の一部が誰かの命を繋ぐの。それってすごいでしょ?」
どうして妹の命を救えないのか。
「私は誰かの中で生きられるんだよ」
こんな残酷な世界、存続させる意味があるのか?
「お兄ちゃんは頭いいんだからさ、いつか世界を変えられると思うな」
妹の言葉にハッとする。
世界を変える。
ああ、そうだ。
世界を変えることを……考えればいいんだ。
そんな風に考えていた矢先、蘭が現れたのだ。
『あなたは、世界を滅ぼそうとしている』
まさに、その通りだった。
*****
睨み合いが続く中、不意に電話が鳴る。五郎が一瞬だけ、ひどく辛そうな顔をしたのを蘭は見逃さなかった。
「もしもしっ……はい……ええ、すぐ行きます」
電話を切るころには、その辛そうな顔は絶望へと変わってゆく。
「……どうかした?」
蘭が心配そうに顔を覗き込むと、
「お前には関係ない」
と背を向け、財布を片手に外へ出ようとする。蘭は慌ててボストンバッグを手に後を追った。
「どこいくの? 私もっ」
「ついてくるなっ!」
「そうはいかないっ」
なにかがあったのだ、と蘭は思った。過去の記憶を手繰り寄せる。蓮見五郎の身に起きた、人生を変える、なにか。そして思い出す。彼に、妹がいたということを。
そう。蓮見五郎には妹がいた。しかしそれは公式には知られていない。複雑な家庭で育った兄妹は、確か叔母夫婦に引き取られ、後に母方の祖母に預けられている。その際、幼かった妹だけ祖母の養子になっていた。だから蓮見五郎とは苗字も違っているし、戸籍上は五郎の叔母に当たる。
「もしかして、妹さんに何かあったのっ?」
先を行く五郎の腕を取り、強引に引っ張ると、五郎は苦虫を嚙み潰したような顔をし、
「ドナーが現れなければ、助からない」
とだけ、告げた。
「ドナー……」
かつて自分もそうだった。どこかの誰かが臓器を提供してくれたから、生きているのだ。けれど、適合者が現れる可能性というのは、なかなかに難しい。同じ血の通った家族でもなかなか適合しなかったりするのだ。それに、もし適合者が見つかった場合でも、いざという段になって断られてしまうケースもあると聞く。
『世界を救える可能性があるの、あなただけなんですよねぇ』
唐突に、女神の言葉が蘇る。
世界を……救う。
可能性があるのはあなただけ、と言われた、その意味がわからなかった。でも、もしかしたら、と気付く。
蓮見五郎にとっての、世界。それは、唯一の肉親と言ってもいいくらい大切な、妹のことだったのではないのか? そう仮定するなら、自分がここに返された意味とはつまり、
「それだ~~~!!」
蘭は五郎を指しながら、声を上げた。
これですべてが繋がった。どうして自分がここにいるのか。どうして猶予が一週間なのか。
「なんだよ、突然っ」
声を荒げる蘭に五郎がビクつく。
「私だ! 私が妹さんを助けるんだわ!」
「はぁ?」
「大丈夫! 私、多分臓器提供できるの!」
目をギラギラさせながら語る蘭。
「いきなり何を、」
「いいから、行くわよ!」
蘭は五郎の腕をぐいぐい引っ張ると、走り出した。
*****
病院でのやり取りは、順調だった。女神は蘭の身分証だけでなく、ドナーになるために必要なすべてを揃えていたようだ。バッグにはしてもいない検査資料まで入っており、神の御業に驚かされる。それにしても、これが答えなら最初からそう言ってくれればよかったのに、と思うほど答えはすぐそばにあった。
いくつかの追加検査を済ませると、病室へ向かう。そこには力なくベッドに沈む五郎の妹の姿があった。蘭を見て、不思議そうに首を傾げる。
「杏里、具合は?」
五郎が兄の顔になりベッドに近付く。妹の名は、市村杏里。母方の祖父母の姓を名乗っているのだ。
「おにい……ちゃん? と、……彼女さん?」
「ばっ、違うっ」
五郎がムキになって訂正する。
「初めまして。私は篠宮蘭。私はあなたのドナーになるの」
血縁以外でドナーがドナーを名乗ることなど普通は有り得ないが、まぁ、いいだろう、と、蘭は自己紹介をする。
「えっ? 本当に……?」
杏里が驚いたような、それでいてホッとしたような顔を見せる。
「ええ、大丈夫よ。私があなたと、彼を救うわ」
振り返り、五郎を見た。
「救う……、すごい! お姉さん、カッコいい!」
興奮気味に顔を輝かせる杏里。
「私もね、もし死んだらそうやって誰かを救いたいって思ってた。私の体、使えるところ全部使ってもらって誰かを助けるの! でも、実際死が近いんだってわかると……カッコいいことなんか一つも言えなくて」
俯き、涙ぐむ。
「当たり前じゃない! 誰だって死にたくなんかないもの!」
きゅ、っと杏里の手を握る。
ぐるん、と脳内が反転するようなおかしな感覚に襲われ、一瞬目を閉じる。
その瞬間、すべて理解した。頭の中に流れ込んでくるこの映像が、これから先の『未来』なのだと。
差し戻された意味。
やるべきこと。
蘭は、すべてを飲み込む。一度失くした命だ。今更惜しんだ所でどうなるものでもない。それより、本当に自分は世界を救うのだ、という使命感の方がずっと大切で、大きくなっていた。
それでも、少し残念なこともある。今、ここでのやり取りを、自分は忘れてしまうのだ。出来ることなら持っていきたい。未来の自分に、教えてあげたい。けれど……。
「必ず元気になるわ。大丈夫だからね」
蘭は杏里の頭をポンと軽く叩くと、
「蓮見さん、ちょっと話がある」
と、病室の外へと連れ出した。
*****
屋上では洗濯物が風にはためいていた。
「お前、本当に……いいのか? その……ドナーの件」
五郎がぼそぼそと訊ねる。
「もちろん、いいわよ。それより、聞いてほしいことがあるの」
「なに?」
オブラートに包んで伝えることも考えたが、無理そうだ。仕方ないからそのままズバリを言ってしまう。
「私、多分だけど、もうすぐ死ぬ」
「はっ?」
五郎の目が真ん丸になる。当然だろう。出会ってからというもの、おかしなことしか口にしていないのだ。今はその最高峰。杏里のドナーになるだけなら死ななくてもいいだろうに、何故この命が絶たれるのか。理由が、ちゃんとある。
「なに言い出すんだ、お前っ?」
「言ったでしょ? 私はここに死に戻ったの。理由はあなたを落として未来を救うため……って言われたけど違うわね。杏里ちゃんのドナーになるため。それと、私自身のドナーになるためなんだわ」
面白い話だ。これに気付いた時は、ちょっと感心してしまった。
「なんの話だ?」
「この世界にはもう一人私が存在する。今、この世界の私は十一歳。そして杏里ちゃんと同じように、ドナーを待ってる」
そう。蘭もまた、ドナーが現れなければ死ぬ運命だった。しかし、まさか自分が自分のドナーになるなんてこと、考えもしなかった。
「さっき杏里ちゃんの手を握った時にすべてが視えた。私の名前は篠宮蘭じゃない。これは女神さまが用意した仮の器なのね。だから一週間しか持たないんだ」
「おい、」
早口で捲し立てる蘭に、五郎が声をかけるが、
「お願いがある。私が死んだら、花柳凛って子を探して。そして私の臓器が彼女に渡るようにしてほしい。私ったら、自分が贈った自分の臓器に感動して警察官目指すのね。笑っちゃうわ」
手摺を掴み空を見上げ、ふふ、と笑みを浮かべる。
「警察?」
「そ。私ね、ドナーに命を救われてから、人の命を救う仕事がしたいって考えるようになるの。で、とある国家の秘密機関に入って正義の名のもとに活動するわけ。カッコいいでしょ?」
「恋人も作らず、結婚もせず、ってやつか?」
「……余計なことは覚えてるのね」
チッと舌打ちを返す。
「とにかく、私が死んで、花柳凛は生きる。それでいい」
五郎は半信半疑のようだ。当然だろうが。
「それと、この話もしておくわ。スノードロップの花言葉は『あなたの死を望みます』だけじゃない。『逆境の中の希望』ってのもあるの。ちゃんと調べたんだからねっ? ……私が、あなたの希望になれたならよかったのだけど。残念ながらタイムオーバーだわ」
「なにを言って、」
杏里さえ死ななければ、きっと五郎は悪い道にそれることもなくなるはずだ。それでも、妹の面倒を見ながら二人で生きていくのはきっと大変なこと。そんな五郎の、心の支えになってあげられるだけの時間はない。
「もうすぐ心臓発作で倒れるわ」
「誰が?」
「だから、私が! さっき視えたの!」
まるで走馬灯のようだった。倒れる蘭を抱き留める五郎。名を呼び続ける五郎。それはまるで映画のワンシーンのようで、思わずニヤついてしまうほどだった。
「王子様のキスでもありゃ、生き返るのかしらね」
肩を竦めると、体に異変を感じる。来る!
ドクンッ、と心臓を掴まれるような息苦しさが襲い、その場にしゃがみ込む。
「おい!」
五郎が駆け寄り、跪いた。
「時間だわ。あっという間だったわね。一週間どころか、一日で片付いたじゃない。私ったら……優秀な……」
「おい、しっかりしろ!」
遠ざかる意識の中、五郎の声がこだまする――。
*****
「おい! しっかりしろ! おい!」
耳元で誰かが叫んでいる。何故だか一瞬、懐かしさを感じた。
「おい!」
何度目かの『おい』で目を開けると、教官の顔が間近にあった。
「……あ、れ?」
「あれ? じゃないだろうっ。しっかりしろ、花柳凛!」
全身ずぶ濡れで、髪からも水が滴っている。見れば、教官もまた同じように全身ずぶ濡れ。その姿を見て、思わず凛は、
「水も滴る……なんとやら、ですね」
と口走った。
「ふざけるな! どれだけ心配したと思ってるんだっ」
そう言って凛を見つめる瞳は、真剣そのものだった。
「すみません」
特殊な機関に身を置くための特別カリキュラムを受けている最中だった。遠泳中に、足が攣った。波に押し流され沈みそうになったところで救助されたらしい。
「今、医療班を呼んでくる! 上陸したら医者に診てもらえ! いいなっ?」
そう言って去って行く。
と、近くにいた先輩が、
「あの鬼教官があんなに狼狽えるとこ初めて見た」
と、何故かニヤニヤしながら話し掛けてきたのだ。
「え?」
聞き返すと、
「花柳って、教官のなに?」
と質問で返される。
「なにって……部下、ですよね?」
他になんと言えばいいのかわからない。入所当時から目を掛けてもらっているのはなんとなく感じてはいたが、知り合いではない。
「ただの部下にあんなこと言わないだろ」
「……何か言ってたんですか?」
眉を寄せ、声を落とす。と、先輩は少し悩んだ顔をした後、凛の耳元に口を寄せ、
「『目を覚ませ、花柳凛! 王子様のキスで目を覚ますんじゃないのか!』って言いながら必死に人工呼吸してたぞ?」
と説明してくれた。
「はぁぁぁぁ?」
一気に心臓が跳ね上がり、頭に血が上るのを感じる。
「あの、蓮見五郎にそんなセリフ言わせるお前って、何者だよ」
ニヤニヤが止まらない先輩と、ドキドキが止まらない凛。蓮見五郎といえば、泣く子も黙る鬼教官で、文武両道、クールでセクシーで、凛の憧れでもあるのだ。この機関に入った時から、凛は蓮見五郎のことがずっと気になっていた。歳も離れているし、決して好みのタイプではないはずなのだが、何故か惹かれるのだ。その、蓮見が人工呼吸……。
「ま、とにかく無事で何よりだったけどな。お前、無茶しすぎるなよ?」
「あ、はい。すみませんでした」
頭を下げると、そこに再び蓮見五郎が現れる。どんな顔をすればいいかわからず、思わず目を逸らしてしまった。急に心臓の音がうるさく感じられる。
「担架が出せないらしい。救護室まで連れていく」
片膝を立て、凛をひょいと抱き上げる。
「ひょわぁぁぁっ。あ、あああ歩けますよ、教官!」
「黙って抱かれてろ!」
とんでもない台詞を吐く五郎の顔を、チラ、と見上げる。そしてつい、出来心で口にしてしまう。
「……教官は、王子だったんですか?」
一瞬ぎょっとした顔で凛を見た五郎は、すぐに真顔に戻ると、言った。
「こんな話、お前は信じないだろうがな、俺が今こうしてここにいるのはお前のおかげだ。十年前、俺はお前に落とされてんだよ」
「……へ? なんの話……じゅ、十年前って……私、しょうがっ……教官て、ロリコ……」
カタコトになりながら言葉を返す。十年前の凛は、蓮見のことなど知らない。
「違うっ」
「だって、今の発言……え? ストーカー?」
「違うと言っているだろう! ……いつか話してやる。お前は……間違いなく俺の希望だったよ」
「へ?」
おかしな声を上げる凛に向かって、五郎は更にこう付け加えた。
「今度は俺が、お前を落とす番だ」
腕の中にいる凛を見つめ、優しく笑ったのである――。
おしまい