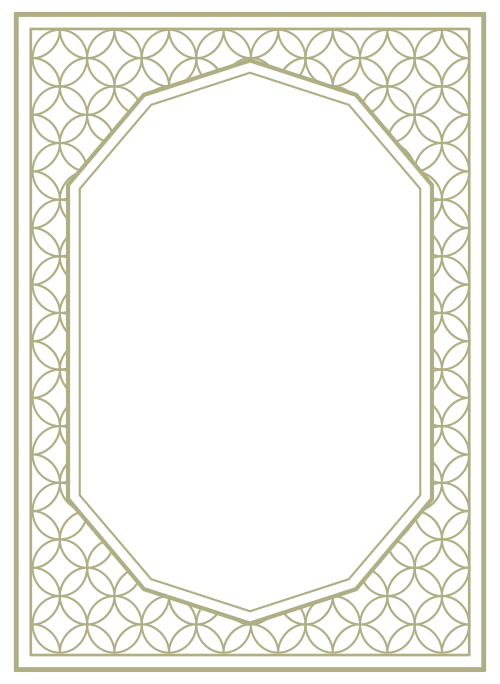★
『特別支援学校』
そのキーワードは、なにかしらの不幸を背負った人間の姿を想像させる。不自由なのは目か耳か、それとも肢体か、あるいは知能の発達か。
音楽教師の話によると、訪れるのは視覚不自由者のクラスの生徒だということだ。確かに、視覚が不自由なことは歌う上で支障なさそうだ。楽譜を見なくたって歌は覚えられるし歌うことはできる。
くだんの特別支援学校のある場所は隣町のさらに隣で、車でゆうに三十分はかかる場所にあるらしい。なぜこの中学校がお披露目の場として選ばれたのかは不可解だけど、きっと大人の事情なのだろう。
合唱祭では一年生から順に歌い、最後が三年生で、合唱終了後に教師陣が採点をするのだが、採点にはほどほどの時間が必要なので、待っている生徒は退屈してしまう。だから、採点中の余興として特別支援学校の生徒が歌を披露するらしい。
僕らのクラスが大トリとなるはずだったが、他校の身体障害者に水を差された形となったから、不満を抱くクラスメートもいるようだった。五体満足でも不満は飛びだすものだな、と思い冷ややかな視線でクラスメートを見てしまう。
当日、合唱祭が始まった。体育館にパイプ椅子が並べられ、席順通りにおとなしく腰を据える。定型のプログラムは淡々と進んでゆく。
どのクラスにもピアノが上手な生徒はひとりやふたりいて、そんな生徒がピアノの伴奏を請け負っている。かたや歌い手は際立って上手いクラスも下手なクラスもない。
校内の生徒とすれば最後である、僕のクラスの順番が回ってきた。僕らの課題曲は「大地讃頌」、自由曲は「雑草」だった。
その二曲の合間で、舞台袖で出番を待つ他校の生徒の存在に気づいた。横目で観察すると、おそろいの紺色のブレザーを着ていて、人数は男女合わせて十一名。皆で円陣を組んでいるが、気遣ってか声をひそめている。作戦会議のつもりらしい。僕らとは違ってやる気満々のように感じられた。彼らにとって校外活動は数少ない活躍の機会なのだろう。
生徒たちは背の高さにだいぶ個人差があったから、中学一年から三年までの生徒全員でひとつの合唱グループを作っているようだった。特別支援学校の生徒は人数が少ないだろうから納得できる。
そばには指導員が三名ついていたが、おおむね見守っているだけで、主導権はあくまで生徒のようだ。
ふと、赤みのかかったくせっ毛の、快活そうな女子の背中が目に入った。その子が御一行様を仕切っているリーダーらしい。たぶん三年生、ということは僕と同い年なのだろう。
僕のクラスが二曲を歌い終わり、舞台を後にすると本校のプログラムは終了となる。そこでアナウンスが流れる。
『これから点数を集計しますが、その間、お越しくださいました光陽特別支援学校の生徒さんに歌を披露していただきます。皆さん、静かに待っていてください』
僕が席に着くと、ゲストの生徒たちはすでに舞台に登壇していた。
「盲学校」と聞いていたので先日、すこしだけ下調べをしてみたが、そこに通う生徒は目がまったく見えないとは限らないらしい。
眼の病気で視野が極端に狭いとか、あるいは解像度が悪いとか、とにかく見えていても日常生活に支障をきたすレベルだと盲学校に通うことになるらしい。
どの程度見えているかはわからないものの、ほとんどの生徒は開眼していた。
けれど、舞台の中央に佇むくせっ毛の女の子だけは、まぶたを完全に閉じていた。あえてそうしているのか、それとももしかしたら――眼球自体が失われているのか。そう考えると恐ろしくて背筋が冷たくなった。
ただ、僕がどんな推測をしようが、その女の子の世界は暗闇のままなのだ。絶望に襲われたりしないのだろうか?
僕の懸念をよそに、その女の子はマイクを受け取り、代表としての挨拶をはきはきとする。
「みなさん、はじめまして。今日はお招きいただきありがとうございます。いままで練習してきた私たちの歌をお楽しみください」
僕ら生徒の間には気だるい雰囲気が漂っている。特別支援学校の生徒たちの目に否定的な表情が映らないのはさいわいだなと安堵する。
曲が始まり、オーケストラ調の伴奏がスピーカーから流れだす。どこかで耳にしたことのあるメロディだけれど、曲の題名は思いだせない。
舞台の中央に並んだ生徒たちは、息を吸い込み歌声を放った。
とたん、皆の視線が壇上に集中する。その歌声は、一瞬にして会場の空気を鮮やかに塗り替えた。
――quando sono sola(ひとりのとき)
――sogno all'orizzonte(水平線の夢を見て)
曲は最初、女子のパートから始まった。おおっ、と周囲から驚きの声が上がる。皆、予想だにしなかった伸びやかな美声に目を丸くしていた。そのうちの誰かが曲の題名をこぼす。
『Time To Say Goodbye』
そうだ、盲目の男性歌手が女性のソプラノ歌手とデュエットで歌っていた曲だ。
――e mancan le parole(言葉は失われて)
――si lo so che non c'? luce(太陽のない宵闇の部屋で)
異国の言葉で紡がれたその歌は自由な音色を醸していた。生徒たちは皆、舞台上から発せられる美声に釘付けになっている。僕自身も固唾を呑んで歌に聴き入る。
――che sei con me con me(きみが僕と一緒にいること)
――tu mia luna tu sei qui con me(きみは僕の月、僕とともにある)
男子のパートもまた、重厚で包容力のある声調に感じられる。すでに声変わりを終えた男子生徒が多いようで、男女間の音調のバランスも絶妙だ。
彼らは視覚が弱いぶん、音を聴き分ける感覚が鋭敏なのだろう。そうとしか思えないくらい、皆、そろいもそろってすばらしい歌い手だったのだ。
曲が終焉に近づいて、最後の聴かせどころを迎えると、そのタイミングで生徒たちは皆、はたと歌声をひそめた。あれ、と不思議に思ったとき、リーダーを務めていた女の子が一歩、前に歩みだした。
最後のパートは、彼女の独唱らしい。
でも、ここから先はデュエットで盛り上がるはずなのに。僕はそう懸念したけれど、彼女が口を開いた瞬間、抱いていた不安は一瞬にして消し去られた。
彼女の独唱は、中学生の女の子から放たれた声とは思えないほどに力強く、そして気高かったのだ。薄紅色の唇からあふれだす歌声は、体育館の窓を震わせ、天井を穿ち、この会場の空気を彼女一色に塗り替えてしまった。
『特別支援学校』
そのキーワードは、なにかしらの不幸を背負った人間の姿を想像させる。不自由なのは目か耳か、それとも肢体か、あるいは知能の発達か。
音楽教師の話によると、訪れるのは視覚不自由者のクラスの生徒だということだ。確かに、視覚が不自由なことは歌う上で支障なさそうだ。楽譜を見なくたって歌は覚えられるし歌うことはできる。
くだんの特別支援学校のある場所は隣町のさらに隣で、車でゆうに三十分はかかる場所にあるらしい。なぜこの中学校がお披露目の場として選ばれたのかは不可解だけど、きっと大人の事情なのだろう。
合唱祭では一年生から順に歌い、最後が三年生で、合唱終了後に教師陣が採点をするのだが、採点にはほどほどの時間が必要なので、待っている生徒は退屈してしまう。だから、採点中の余興として特別支援学校の生徒が歌を披露するらしい。
僕らのクラスが大トリとなるはずだったが、他校の身体障害者に水を差された形となったから、不満を抱くクラスメートもいるようだった。五体満足でも不満は飛びだすものだな、と思い冷ややかな視線でクラスメートを見てしまう。
当日、合唱祭が始まった。体育館にパイプ椅子が並べられ、席順通りにおとなしく腰を据える。定型のプログラムは淡々と進んでゆく。
どのクラスにもピアノが上手な生徒はひとりやふたりいて、そんな生徒がピアノの伴奏を請け負っている。かたや歌い手は際立って上手いクラスも下手なクラスもない。
校内の生徒とすれば最後である、僕のクラスの順番が回ってきた。僕らの課題曲は「大地讃頌」、自由曲は「雑草」だった。
その二曲の合間で、舞台袖で出番を待つ他校の生徒の存在に気づいた。横目で観察すると、おそろいの紺色のブレザーを着ていて、人数は男女合わせて十一名。皆で円陣を組んでいるが、気遣ってか声をひそめている。作戦会議のつもりらしい。僕らとは違ってやる気満々のように感じられた。彼らにとって校外活動は数少ない活躍の機会なのだろう。
生徒たちは背の高さにだいぶ個人差があったから、中学一年から三年までの生徒全員でひとつの合唱グループを作っているようだった。特別支援学校の生徒は人数が少ないだろうから納得できる。
そばには指導員が三名ついていたが、おおむね見守っているだけで、主導権はあくまで生徒のようだ。
ふと、赤みのかかったくせっ毛の、快活そうな女子の背中が目に入った。その子が御一行様を仕切っているリーダーらしい。たぶん三年生、ということは僕と同い年なのだろう。
僕のクラスが二曲を歌い終わり、舞台を後にすると本校のプログラムは終了となる。そこでアナウンスが流れる。
『これから点数を集計しますが、その間、お越しくださいました光陽特別支援学校の生徒さんに歌を披露していただきます。皆さん、静かに待っていてください』
僕が席に着くと、ゲストの生徒たちはすでに舞台に登壇していた。
「盲学校」と聞いていたので先日、すこしだけ下調べをしてみたが、そこに通う生徒は目がまったく見えないとは限らないらしい。
眼の病気で視野が極端に狭いとか、あるいは解像度が悪いとか、とにかく見えていても日常生活に支障をきたすレベルだと盲学校に通うことになるらしい。
どの程度見えているかはわからないものの、ほとんどの生徒は開眼していた。
けれど、舞台の中央に佇むくせっ毛の女の子だけは、まぶたを完全に閉じていた。あえてそうしているのか、それとももしかしたら――眼球自体が失われているのか。そう考えると恐ろしくて背筋が冷たくなった。
ただ、僕がどんな推測をしようが、その女の子の世界は暗闇のままなのだ。絶望に襲われたりしないのだろうか?
僕の懸念をよそに、その女の子はマイクを受け取り、代表としての挨拶をはきはきとする。
「みなさん、はじめまして。今日はお招きいただきありがとうございます。いままで練習してきた私たちの歌をお楽しみください」
僕ら生徒の間には気だるい雰囲気が漂っている。特別支援学校の生徒たちの目に否定的な表情が映らないのはさいわいだなと安堵する。
曲が始まり、オーケストラ調の伴奏がスピーカーから流れだす。どこかで耳にしたことのあるメロディだけれど、曲の題名は思いだせない。
舞台の中央に並んだ生徒たちは、息を吸い込み歌声を放った。
とたん、皆の視線が壇上に集中する。その歌声は、一瞬にして会場の空気を鮮やかに塗り替えた。
――quando sono sola(ひとりのとき)
――sogno all'orizzonte(水平線の夢を見て)
曲は最初、女子のパートから始まった。おおっ、と周囲から驚きの声が上がる。皆、予想だにしなかった伸びやかな美声に目を丸くしていた。そのうちの誰かが曲の題名をこぼす。
『Time To Say Goodbye』
そうだ、盲目の男性歌手が女性のソプラノ歌手とデュエットで歌っていた曲だ。
――e mancan le parole(言葉は失われて)
――si lo so che non c'? luce(太陽のない宵闇の部屋で)
異国の言葉で紡がれたその歌は自由な音色を醸していた。生徒たちは皆、舞台上から発せられる美声に釘付けになっている。僕自身も固唾を呑んで歌に聴き入る。
――che sei con me con me(きみが僕と一緒にいること)
――tu mia luna tu sei qui con me(きみは僕の月、僕とともにある)
男子のパートもまた、重厚で包容力のある声調に感じられる。すでに声変わりを終えた男子生徒が多いようで、男女間の音調のバランスも絶妙だ。
彼らは視覚が弱いぶん、音を聴き分ける感覚が鋭敏なのだろう。そうとしか思えないくらい、皆、そろいもそろってすばらしい歌い手だったのだ。
曲が終焉に近づいて、最後の聴かせどころを迎えると、そのタイミングで生徒たちは皆、はたと歌声をひそめた。あれ、と不思議に思ったとき、リーダーを務めていた女の子が一歩、前に歩みだした。
最後のパートは、彼女の独唱らしい。
でも、ここから先はデュエットで盛り上がるはずなのに。僕はそう懸念したけれど、彼女が口を開いた瞬間、抱いていた不安は一瞬にして消し去られた。
彼女の独唱は、中学生の女の子から放たれた声とは思えないほどに力強く、そして気高かったのだ。薄紅色の唇からあふれだす歌声は、体育館の窓を震わせ、天井を穿ち、この会場の空気を彼女一色に塗り替えてしまった。