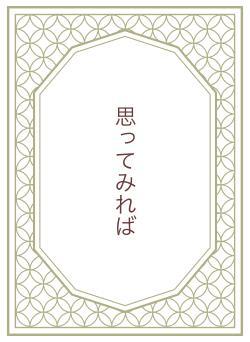私はとにかく、お昼が食べられればよかった。
購買で限定100個、1個50円の特売カップ麺を手に入れたのはいいものの、今日は一緒に授業を受けている同じ学科の友達たちとはお昼が食べられない水曜日。他の曜日は生協食堂で食べている。まさか、ただ椅子と机があるだけの学生会館こんなに混んでいるとは知らなかった。
大学には、色々な人がいる。
大学会館の中は大学生であふれていた。いくつもならんでいるはずの、動かせばギーギー音が鳴る机と椅子は、空席を探さないと座れなさそうだった。
おひとりさまが珍しくないこの時代にも関わらずカウンター席などなく、ではひとりでも座りやすい長机はというと、こちらも集団で埋まっていて。どこかに4人掛けか2人掛けの席を探した。
奇跡的に窓辺の四角い4人掛けテーブルが丸っと空いていた。真四角の白い天板に銀色の丸い足が四つ角から伸びていて、それぞれの辺に無造作に置かれた椅子には、背もたれがついていて、ビニールに近い黒い合皮の布が張ってある。
背負っていた重たいリュックサックを椅子にのせ、隣の席にお湯の入ったカップ麺を置く。もうお湯を入れてから5分以上経っている。
「おとなり、いい?」
黒ブチの四角いメガネをかけて、天然パーマの髪をおさげに結んでいる女の子に声をかけられた。
「いいですよ。」
「ありがとう。」
彼女はえくぼができるニコニコの笑顔で、私が座ろうとしている席の正面の椅子を引いた。
「私、あゆみっていうの。あなたは?」
「私は、寿実佳っていいます。文学部の1年生です。」
「あら、大人っぽい1年生ね。私は看護学科の3年生。」
それからも彼女は根掘り葉掘り私のことを聞いてくる。初対面の、ただのびのびのカップ麺が食べられればいい私にはこの時間は無駄に思えた。
食べられればいい。そこに美味しさとか、健康とか、出会いとか、求めていない。あゆみさんは逆だった。私に話しかけながらトートバッグから出したお弁当は彩り豊かで健康的で美味しそうだった。不味くはないだけの特売カップ麺で済ませようとしている私とは真逆だ。
「3年生ですか、先輩だ。」
こうしてあゆみさんの相手をしている間にもラーメンはどんどん伸びていく。
「すみません! ここ、いいっすか? いいっすよね! 失礼しまーす。」
先に座っている私たちが返事をする前にボサボサ頭の多分女子がどかっと腰を下ろした。
「い、いいんですけど。」
「せめてOKもらってから座ったらどう?」
なかなか言えなかった本音をあゆみさんがサクッと言ってくれた。タイミングも私が一息で言ったようにピッタリだ。
「すんません。」
あとからやってきた彼女は口では謝っているが、やはり心ここにあらずで、慌ててリュックの中から紙の束を出し、ポケットの中から茶色い棒状のものを出して口に入れた。
「ちょっとあなた、それがお昼なの?」
「はい。3限の課題が終わってなくて、とりあえずお腹に入ればいいかなって。」
あゆみさんが心配する彼女が食べていたのは、チョコレートプロテインバーのようなものだった。右手でそれを口に入れ、右肘でプリントを押さえ、左手で器用にレポートを書いている。その横であゆみさんもカバンの中をあさっていた。
「ほら、これ。ちゃんと食べなきゃ力が出ないでしょ。私看護学科の3年生であゆみって言います。あなたは?」
あゆみさんのカバンから出てきたのはアルミ箔に包まれた丸いおにぎりだった。今初めて会った学生に食べ物を恵まれて、さすがに彼女も手を止めてあゆみさんと私のことを交互に見つめていた。
「すみません。やー、初めてのレポートなのにうまく書けないままこんな時間になっちゃってて。やっぱどんなときも食べないとダメっすよね。私、理学部のゆいかって言います。」
「私は文学部1年の寿実佳です。」
「寿実佳ちゃん1年生なの! うちもなの。よろしく。」
「よろしく。」
意図せず私とあゆみさんの「よろしく」がハモった。タイミングも声の感じも、全く同じだった。お互い「ふふふ」と笑ってしまっている。その間でゆいかちゃんがキョロキョロしながら笑っていた。
「ほら、急いでるんでしょ。食べて食べて。」
「うん。じゃなかった、はい! あ…。」
あゆみさんにうながされてゆいかちゃんがアルミ箔の包みを開ける。ノリが全面についた、丸い球状のおにぎりだった。一口食べて、その手が止まってしまっていた。
「どうしたの? お口に合わなかったかしら?」
「いや…。」
ゆいかちゃんは目に涙をためておにぎりをほおばっている。
「これ、おばあちゃんと一緒の味がする、あ、するんです。味噌が入った甘辛い味。」
「うん、味噌入れたけど。そんな、おばあさまみたいに美味しいの? よかった。」
ゆいかちゃんは涙をボロボロこぼしながら、味噌味のおにぎりをほおばっている。あゆみさんはニコニコしながら自分のお弁当をひとくちふた口、口に運んでいる。さて、私のカップ麺に目を落としてみると。
私のカップ麺は、麺だけになっていた。いいだけ汁を吸って、ちょっとフクヨカになった麺を2人に悟られないように口の中にかきこんでいく。
「寿実佳ちゃん、めっちゃおにぎり食べたそう。」
「いや、そんなこと、ないよ!」
ゆいかちゃんは大きなひとくちを飲み込むと私の視線に気づいたらしい。私はそんな自覚、全くなかったが、ずっと大きめの丸いおにぎりを見つめていたらしい。
「じゃあ、こうしましょう。」
あゆみさんが私のほうをキリッと見つめて続けた。
「次に会ったときは寿実佳ちゃんにおにぎりあげるね。いつお腹が空いてもいいようにおにぎり持ってるから。また会ったら一緒にご飯食べましょう。」
「ありがとうございます。」
あゆみさんはニコニコしながらカバンから手帳を取り出して万年筆でメモをとりはじめた。
「大事なことは、こうして書いておかないと、ね。」
「万年筆じゃないっすか! カッコイイ。」
「そうでしょ。彼から20歳のお誕生日にいただいたの。」
ゆいかちゃんの反応に対して、あゆみさんは大事そうに赤い軸の万年筆を抱いて桃のような上品な紅潮を見せている。
あゆみさんにならって私もメモをとる。新入生の流行りに乗って買った学生手帳に、高校の卒業祝いにもらった4色ボールペンの青で。
「あゆみさん ゆいかちゃん また会ったらご飯食べる」
学生手帳に初めて記入した文字が、この手帳を私のものたらしめてくれる。
「ところで2人とも3限は大丈夫? 私はもう5限までないけど。」
学生会館の壁についている大きなアナログ時計は12時45分を少し過ぎたところを指していた。
「あ、やべ! あとは教室で仕上げるっす!」
ゆいかちゃんはおにぎりを飲み込んで、広げたレポートをかき集めてカバンに突っ込み、バタバタと出て行った。
私は3限もなく、急ぎの用事もなかった。でも、しょっぱいラーメンの後に甘いアイスが食べたくなっていた。
「私はコンビニでアイス買おうかと思うんですが、あゆみさんもどうですか?」
「コンビニ? あ、そういうことか。ううん。私はいいの。また会いましょう、絶対ね。」
あゆみさんはニコニコほほえみながらまたカバンの中からデザートが入った小さなタッパーを取り出した。
「すみません、ここ座っていいですか?」
「いいですよ。私もう行くんで。え?」
声をかけてきたのは、バレリーナみたいにきちっとした高めのお団子を結んで楕円のピンクっぽいメガネをかけたお姉さんだった。私はこの人の名前を知っている。
「真智子ちゃん!? じゃない、真智子先生?」
「あら、私は真智子だけど先生じゃないですよ。会ったことあったかしら?」
でも、やっぱり真智子先生だ。まだ1回しか授業を受けていないけれど、人生で初めて古典を面白そうだと感じさせてくれた、私の基礎ゼミ担当の先生だ。
「やっぱり真智子先生ですよね。私、先生の授業で初めて古典が面白そうだなって感じたんです。」
「あら、そうなの。私の専門は児童文学なんだけど。」
真智子先生らしき人が持っていた冊子には「教育実習」と書かれていた。教育学部の3年生が使うやつだ。
「それに、ここは学生しか入れない学生会館でしょ。あなたの世界には真智子さんは先生かもしれないけど、ここにいる私は先生じゃないわ。でも、ここで出会えたのも何かの縁だから、よろしくね。」
「真智子さん? お久しぶり。覚えていますか?」
「あら、あゆみさんじゃない。お久しぶり。」
真智子先生らしき人はあゆみさんと知り合いだったらしい。さっきまでゆいかちゃんが座っていたところに腰をおろして仲良く談笑しはじめた。たぶん同い年くらいなのだろうけど、お互いに丁寧で品を感じるしゃべり方だ。例えるなら昔のガチお嬢様のような感じ。
そんな2人に軽く会釈で別れを告げ、出口を目指した。
購買で限定100個、1個50円の特売カップ麺を手に入れたのはいいものの、今日は一緒に授業を受けている同じ学科の友達たちとはお昼が食べられない水曜日。他の曜日は生協食堂で食べている。まさか、ただ椅子と机があるだけの学生会館こんなに混んでいるとは知らなかった。
大学には、色々な人がいる。
大学会館の中は大学生であふれていた。いくつもならんでいるはずの、動かせばギーギー音が鳴る机と椅子は、空席を探さないと座れなさそうだった。
おひとりさまが珍しくないこの時代にも関わらずカウンター席などなく、ではひとりでも座りやすい長机はというと、こちらも集団で埋まっていて。どこかに4人掛けか2人掛けの席を探した。
奇跡的に窓辺の四角い4人掛けテーブルが丸っと空いていた。真四角の白い天板に銀色の丸い足が四つ角から伸びていて、それぞれの辺に無造作に置かれた椅子には、背もたれがついていて、ビニールに近い黒い合皮の布が張ってある。
背負っていた重たいリュックサックを椅子にのせ、隣の席にお湯の入ったカップ麺を置く。もうお湯を入れてから5分以上経っている。
「おとなり、いい?」
黒ブチの四角いメガネをかけて、天然パーマの髪をおさげに結んでいる女の子に声をかけられた。
「いいですよ。」
「ありがとう。」
彼女はえくぼができるニコニコの笑顔で、私が座ろうとしている席の正面の椅子を引いた。
「私、あゆみっていうの。あなたは?」
「私は、寿実佳っていいます。文学部の1年生です。」
「あら、大人っぽい1年生ね。私は看護学科の3年生。」
それからも彼女は根掘り葉掘り私のことを聞いてくる。初対面の、ただのびのびのカップ麺が食べられればいい私にはこの時間は無駄に思えた。
食べられればいい。そこに美味しさとか、健康とか、出会いとか、求めていない。あゆみさんは逆だった。私に話しかけながらトートバッグから出したお弁当は彩り豊かで健康的で美味しそうだった。不味くはないだけの特売カップ麺で済ませようとしている私とは真逆だ。
「3年生ですか、先輩だ。」
こうしてあゆみさんの相手をしている間にもラーメンはどんどん伸びていく。
「すみません! ここ、いいっすか? いいっすよね! 失礼しまーす。」
先に座っている私たちが返事をする前にボサボサ頭の多分女子がどかっと腰を下ろした。
「い、いいんですけど。」
「せめてOKもらってから座ったらどう?」
なかなか言えなかった本音をあゆみさんがサクッと言ってくれた。タイミングも私が一息で言ったようにピッタリだ。
「すんません。」
あとからやってきた彼女は口では謝っているが、やはり心ここにあらずで、慌ててリュックの中から紙の束を出し、ポケットの中から茶色い棒状のものを出して口に入れた。
「ちょっとあなた、それがお昼なの?」
「はい。3限の課題が終わってなくて、とりあえずお腹に入ればいいかなって。」
あゆみさんが心配する彼女が食べていたのは、チョコレートプロテインバーのようなものだった。右手でそれを口に入れ、右肘でプリントを押さえ、左手で器用にレポートを書いている。その横であゆみさんもカバンの中をあさっていた。
「ほら、これ。ちゃんと食べなきゃ力が出ないでしょ。私看護学科の3年生であゆみって言います。あなたは?」
あゆみさんのカバンから出てきたのはアルミ箔に包まれた丸いおにぎりだった。今初めて会った学生に食べ物を恵まれて、さすがに彼女も手を止めてあゆみさんと私のことを交互に見つめていた。
「すみません。やー、初めてのレポートなのにうまく書けないままこんな時間になっちゃってて。やっぱどんなときも食べないとダメっすよね。私、理学部のゆいかって言います。」
「私は文学部1年の寿実佳です。」
「寿実佳ちゃん1年生なの! うちもなの。よろしく。」
「よろしく。」
意図せず私とあゆみさんの「よろしく」がハモった。タイミングも声の感じも、全く同じだった。お互い「ふふふ」と笑ってしまっている。その間でゆいかちゃんがキョロキョロしながら笑っていた。
「ほら、急いでるんでしょ。食べて食べて。」
「うん。じゃなかった、はい! あ…。」
あゆみさんにうながされてゆいかちゃんがアルミ箔の包みを開ける。ノリが全面についた、丸い球状のおにぎりだった。一口食べて、その手が止まってしまっていた。
「どうしたの? お口に合わなかったかしら?」
「いや…。」
ゆいかちゃんは目に涙をためておにぎりをほおばっている。
「これ、おばあちゃんと一緒の味がする、あ、するんです。味噌が入った甘辛い味。」
「うん、味噌入れたけど。そんな、おばあさまみたいに美味しいの? よかった。」
ゆいかちゃんは涙をボロボロこぼしながら、味噌味のおにぎりをほおばっている。あゆみさんはニコニコしながら自分のお弁当をひとくちふた口、口に運んでいる。さて、私のカップ麺に目を落としてみると。
私のカップ麺は、麺だけになっていた。いいだけ汁を吸って、ちょっとフクヨカになった麺を2人に悟られないように口の中にかきこんでいく。
「寿実佳ちゃん、めっちゃおにぎり食べたそう。」
「いや、そんなこと、ないよ!」
ゆいかちゃんは大きなひとくちを飲み込むと私の視線に気づいたらしい。私はそんな自覚、全くなかったが、ずっと大きめの丸いおにぎりを見つめていたらしい。
「じゃあ、こうしましょう。」
あゆみさんが私のほうをキリッと見つめて続けた。
「次に会ったときは寿実佳ちゃんにおにぎりあげるね。いつお腹が空いてもいいようにおにぎり持ってるから。また会ったら一緒にご飯食べましょう。」
「ありがとうございます。」
あゆみさんはニコニコしながらカバンから手帳を取り出して万年筆でメモをとりはじめた。
「大事なことは、こうして書いておかないと、ね。」
「万年筆じゃないっすか! カッコイイ。」
「そうでしょ。彼から20歳のお誕生日にいただいたの。」
ゆいかちゃんの反応に対して、あゆみさんは大事そうに赤い軸の万年筆を抱いて桃のような上品な紅潮を見せている。
あゆみさんにならって私もメモをとる。新入生の流行りに乗って買った学生手帳に、高校の卒業祝いにもらった4色ボールペンの青で。
「あゆみさん ゆいかちゃん また会ったらご飯食べる」
学生手帳に初めて記入した文字が、この手帳を私のものたらしめてくれる。
「ところで2人とも3限は大丈夫? 私はもう5限までないけど。」
学生会館の壁についている大きなアナログ時計は12時45分を少し過ぎたところを指していた。
「あ、やべ! あとは教室で仕上げるっす!」
ゆいかちゃんはおにぎりを飲み込んで、広げたレポートをかき集めてカバンに突っ込み、バタバタと出て行った。
私は3限もなく、急ぎの用事もなかった。でも、しょっぱいラーメンの後に甘いアイスが食べたくなっていた。
「私はコンビニでアイス買おうかと思うんですが、あゆみさんもどうですか?」
「コンビニ? あ、そういうことか。ううん。私はいいの。また会いましょう、絶対ね。」
あゆみさんはニコニコほほえみながらまたカバンの中からデザートが入った小さなタッパーを取り出した。
「すみません、ここ座っていいですか?」
「いいですよ。私もう行くんで。え?」
声をかけてきたのは、バレリーナみたいにきちっとした高めのお団子を結んで楕円のピンクっぽいメガネをかけたお姉さんだった。私はこの人の名前を知っている。
「真智子ちゃん!? じゃない、真智子先生?」
「あら、私は真智子だけど先生じゃないですよ。会ったことあったかしら?」
でも、やっぱり真智子先生だ。まだ1回しか授業を受けていないけれど、人生で初めて古典を面白そうだと感じさせてくれた、私の基礎ゼミ担当の先生だ。
「やっぱり真智子先生ですよね。私、先生の授業で初めて古典が面白そうだなって感じたんです。」
「あら、そうなの。私の専門は児童文学なんだけど。」
真智子先生らしき人が持っていた冊子には「教育実習」と書かれていた。教育学部の3年生が使うやつだ。
「それに、ここは学生しか入れない学生会館でしょ。あなたの世界には真智子さんは先生かもしれないけど、ここにいる私は先生じゃないわ。でも、ここで出会えたのも何かの縁だから、よろしくね。」
「真智子さん? お久しぶり。覚えていますか?」
「あら、あゆみさんじゃない。お久しぶり。」
真智子先生らしき人はあゆみさんと知り合いだったらしい。さっきまでゆいかちゃんが座っていたところに腰をおろして仲良く談笑しはじめた。たぶん同い年くらいなのだろうけど、お互いに丁寧で品を感じるしゃべり方だ。例えるなら昔のガチお嬢様のような感じ。
そんな2人に軽く会釈で別れを告げ、出口を目指した。