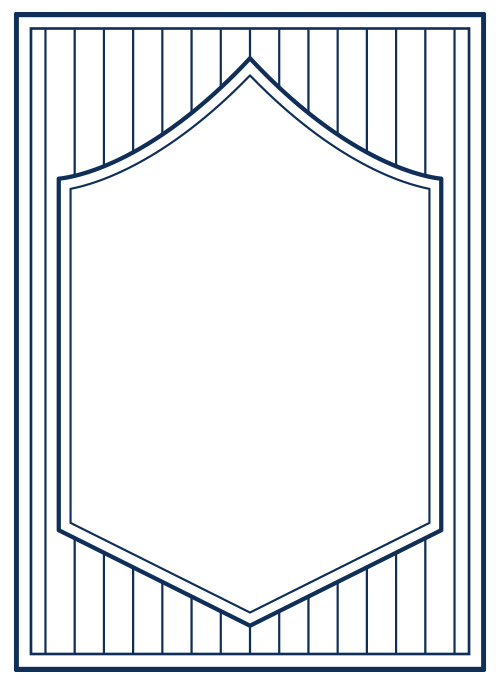三
土曜日、柊矢と共に向かったのは都内の大学だった。
「ここの研究室に俺の知り合いがいるんだ」
「知り合い? 柊ちゃんは相変わらず冷たいな~。俺達ズッ友だろ」
二人の後ろから声がして振り返ると、よれよれの白衣を羽織った男性がいた。
柊矢と同い年くらいだろうか。髪が少し乱れていて無精髭を生やしている。
「お前は小学生か。大体、柊ちゃんなんて呼ぶヤツは知り合いで十分だ」
柊矢はそう答えると、
「榊良一だ。榊、この子は俺が面倒を見てる霞乃小夜」
と紹介した。
「柊ちゃん、『さよ』って名前好きだね」
「ただの偶然だ」
「面倒見てるって、その子、高校生くらいでしょ? 柊ちゃん、両手が後ろに回るようなことしてないだろうね」
「するか」
両手が後ろに回ることってどういう意味だろう?
聞いたらまたからかわれそうだったので黙っていた。
「ま、座って」
榊は研究室に二人を招じ入れると、椅子に座るように勧めて自分も腰を下ろした。
研究室の中は本で埋め尽くされていた。
いくつもある机の上には専門書と思われる分厚い本や雑誌が積み上げられ書きかけのノートや開きっぱなしの本などが置かれていた。本にはアルファベットともアラビア語とも違う見たことのない文字が書かれているものがある。
「で、彼女紹介しに来たんじゃないでしょ」
「か、彼女じゃ……」
「お前なら分かるんじゃないかと思ってな」
柊矢はそう言うと小夜の方を振り向いた。
「夕辺の歌の歌詞、言えるか?」
「え、えっと……メーニナエイデテアーペーレーイーアデオーアキレーオス」
「なんかギリシア語っぽいけど……」
榊が首をかしげた。
「お前、俺の授業中寝てたな」
年配の男性が入ってくるなり榊の頭を分厚い本で叩いた。
「痛っ!」
「女神よ、ペーレウスの子アキレウスの怒りを歌いたまえ」
年配の男性が言った。
「え、教授、それって、えーっと……」
榊が考え込んだ。
「イーリアス!」
教授が怒鳴りつける。
「ですよね。でも、なんか違うような……」
「その子のは古典ギリシア語だ。現代ギリシア語とは読みが違う音があるんだよ。その例として俺が授業中に読んで聞かせたの聞いてなかったな」
ギリシア語のアルファベットの形や単語などの綴りは古代からほとんど変わってないものが多いため現代ギリシア語が読めれば遺跡などに彫ってある言葉の意味も分かるものが多いらしい。
ただ、発音などは古典ギリシア語と現代ギリシア語では違うものがあるということだった。
「じゃあ、ポダソーキュサキッレウスって言うのは……」
柊矢が訊ねた。これは何とか聞き取れた歌詞の一節だった。
「足速きアキレウスだな」
教授が答えた。
「古典ギリシア語って言うのはいつ頃使われてたんですか?」
「大体紀元前二千年前くらいには使われてたようだ」
「紀元前二千年……」
今から四千年前か。
「ちなみに現代ギリシア語は十一世紀頃の口語が元になってると言われているんだよ」
榊が得意げに言った。
「お前が偉そうに言うな」
教授が再度榊の頭を叩いた。
「痛っ!」
しばらく教授の話を聞いてから柊矢と小夜は研究室を辞した。
「古典ギリシア語? 四千年前ってすごいね」
柊矢と小夜の話を聞いた楸矢が驚いて言った。
「でも、なんで分かったの? 古典ギリシア語だって」
「この前、たまたまTVをつけたらイーリアスをやってたんだ。それで大学時代の知り合いが現代ギリシア文学の研究してたの思い出してな」
「けど、なんで古典ギリシア語なんだろ」
「そこまでは分からなかった」
まさか初対面の教授に友人にさえ言ってなかった歌の話をするわけにもいかず、その点に関しては聞けなかったのだ。
それに他に聞き取れた言葉をいくつか訊ねてみたがギリシア語ではない言葉もあった。
「柊矢さん達が使ってる楽器もギリシアのものですよね。関係があるんでしょうか」
「どうかな」
「まぁ、昔のギリシア語って分かっただけでも進歩だよね。何の進歩かよく分かんないけど」
確かにギリシア語だと分かったからといって歌が聴こえる理由は不明のままだ。
ホントに、何でギリシア語なんだろう。
それも大昔の。
その日、小夜が学校から帰ろうとすると歌が聴こえてきた。
主旋律を男性が歌っている。
歌うのは圧倒的に女性で、男性の声はものすごく珍しい。女性の重唱が重なり、風に乗ってビルの間を流れていく。
もしかして……。
小夜はバス停に向かわず、甲州街道を真っ直ぐに行ってKDDIビルを通り過ぎたところで右折し超高層ビル群の中に入っていった。
そこまで行くと歌っているのが中央公園だと分かった。
中央公園に行くと、ベンチに座っている二十代半ばくらいの若い男性が歌っていた。短く淡い茶色の巻き毛が風に揺れている。中性的な顔立ちをしているが間違いなく男性だ。
柊矢さんと同い年くらいかな。
遠くにいたときは男性が弾いてる楽器の音は聴こえなかったが男性は弦楽器を演奏していた。楽器には詳しくないのでよく分からないが強いて言うなら琵琶に似ている。涙滴系のボディに弦が張られている。
周りを数人の聴衆が取り囲んで聴いていた。
小夜はスマホを取り出すと柊矢にかけた。
「柊矢さん、この歌、中央公園で歌ってます」
楸矢は学校に行っていたのでメールにした。
小夜が歌を聴きながら待っていると柊矢が来た。
男性の甘いテノールがビルの間を流れていく。もう一つの風のように。
女性のコーラスがいくつも重なっているが、それはここに集まっている人達には聴こえていないだろう。
余韻を残して歌が終わった。
聴衆が散っていく。
柊矢と小夜は顔を見合わせた。
どうする?
この男性は間違いなく歌が聴こえる人だ。と言うか、歌う人だ。
声をかけるべきか。
二人が同じ事を考えて迷っていると男性の方が近付いてきた。誰かの面影があるような気がするのだが小夜には男性の知り合いはほとんどいない。
芸能人の誰かに似てるのかな。
「歌、聴いて来たの?」
男性が訊ねた。
「はい」
小夜は素直に頷いた。
「君達もムーシコスなんだね」
「ムーシコス?」
小夜が首をかしげる。
これもギリシア語?
多分、古典の。
「ムーシコスに聴こえる歌はムーシカ。君は歌う人、ムーソポイオスだよね?」
男が小夜に向かって言った。
「え? ムーシコスじゃないんですか?」
「ムーソポイオスは歌手って言う意味。君は演奏家、キタリステースだね」
男性が柊矢に言った。
「なんで演奏だって……」
男が歌っていたのだ。柊矢が歌っていてもおかしくはないはずだ。
「男性は基本的にキタリステースだからね。僕や僕の弟みたいに男のムーソポイオスは珍しいんだ」
確かに男性の歌声はほとんど聴いたことがない。
「ムーシコスってのは、ミュージシャンって意味だけど、君達や僕みたいに〝聴こえる〟人種のことを指す言葉でもあるんだ」
「だけど……あんた、楽器も弾いてたろ」
「この程度の演奏なんか簡単だからちょっと練習すれば誰でも出来るよ。でも演奏は聴こえなかったでしょ。逆に君が演奏しながら歌っても歌声は聴こえないよ」
確かに、柊矢が家にいたときには彼の弾いてる楽器の音は聴こえなかった。
「演奏が聴こえるのはキタリステースが特定の楽器を奏でたときだけ。歌声が聴こえるのはムーソポイオスが歌ったときだけなんだ」
「その楽器は何て言うんですか?」
小夜が訊ねた。
「ブズーキだよ」
「何で、歌が聴こえるヤツと聴こえないヤツがいるんだ?」
柊矢が素朴な疑問を口にした。
「言ったでしょ。人種だって。血筋だよ」
「血筋? でも、俺の祖父は聴こえなかったぞ」
「本当に? 聴こえないって一度でも言ったことある? まぁ、大分血が薄まってきてるから聴こえないこともあるかもしれないけどね。あるいはお祖母さんの方の血筋なのかもしれないし」
「…………」
確かに血筋と言われれば柊矢と楸矢の二人とも聴こえるのは納得がいく。それに祖父は人に言うなとは言ったが聴こえないとは言っていない。
柊矢が考え込んでいる間に男性は立ち去ってしまった。
「柊矢さん?」
「あ、ああ。帰るか」
男性が新宿駅の近くまで来たときビルの陰から女性が出てきた。
「椿矢、あいつらと何を話したの」
「別に」
「あの子は鍵の守人よ」
椿矢と呼ばれた男性は肩をすくめた。
「言ったはずだよ。関わる気はないって。巻き込まないでくれないかな」
そう言うと女性に背を向けて歩き出した。
椿矢が雑踏へ消えていくのを女性はじっと見つめていた。
小夜と柊矢が駐車場に向かって超高層ビル群の間を歩いていると、不意に風が変わった。
風が硬くなったように感じた。
見ると森が出現していた。風が吹いてくる方を見ると森が途切れたところに大きな池があった。強いビル風が吹いているにもかかわらず水面にはさざ波一つ立っていない。
「池も凍り付いてるんだ」
小夜が呟いた。
「凍り付いている?」
「はい。この森も、あの池も、旋律で凍り付いてるんです」
二人が森に見惚れていると、現れたときと同じように静かに消えていった。
「ムーシコス? それ何語? 何がどうなってんの?」
楸矢がハンバーグを口に運びながら言った。
「ムーシコスって言うのは自称だと思うがな」
「ふぅん。で、『僕達』って言ったんだ。つまり、ムーシコスは集団ってこと?」
「集団かどうかはともかく、複数なのは確かだろ」
柊矢、楸矢、小夜、今日の男性。それに男性の弟もムーソポイオスだと言っていた。最低でも五人は実在するということだ。
「もっと詳しく聞けば良かったのに」
「なら今度はお前が聞きにいけ」
「今日の歌の人だね。中央公園か。行ってみようかな」
楸矢は興味のありそうな顔で言った。
土曜日、柊矢と共に向かったのは都内の大学だった。
「ここの研究室に俺の知り合いがいるんだ」
「知り合い? 柊ちゃんは相変わらず冷たいな~。俺達ズッ友だろ」
二人の後ろから声がして振り返ると、よれよれの白衣を羽織った男性がいた。
柊矢と同い年くらいだろうか。髪が少し乱れていて無精髭を生やしている。
「お前は小学生か。大体、柊ちゃんなんて呼ぶヤツは知り合いで十分だ」
柊矢はそう答えると、
「榊良一だ。榊、この子は俺が面倒を見てる霞乃小夜」
と紹介した。
「柊ちゃん、『さよ』って名前好きだね」
「ただの偶然だ」
「面倒見てるって、その子、高校生くらいでしょ? 柊ちゃん、両手が後ろに回るようなことしてないだろうね」
「するか」
両手が後ろに回ることってどういう意味だろう?
聞いたらまたからかわれそうだったので黙っていた。
「ま、座って」
榊は研究室に二人を招じ入れると、椅子に座るように勧めて自分も腰を下ろした。
研究室の中は本で埋め尽くされていた。
いくつもある机の上には専門書と思われる分厚い本や雑誌が積み上げられ書きかけのノートや開きっぱなしの本などが置かれていた。本にはアルファベットともアラビア語とも違う見たことのない文字が書かれているものがある。
「で、彼女紹介しに来たんじゃないでしょ」
「か、彼女じゃ……」
「お前なら分かるんじゃないかと思ってな」
柊矢はそう言うと小夜の方を振り向いた。
「夕辺の歌の歌詞、言えるか?」
「え、えっと……メーニナエイデテアーペーレーイーアデオーアキレーオス」
「なんかギリシア語っぽいけど……」
榊が首をかしげた。
「お前、俺の授業中寝てたな」
年配の男性が入ってくるなり榊の頭を分厚い本で叩いた。
「痛っ!」
「女神よ、ペーレウスの子アキレウスの怒りを歌いたまえ」
年配の男性が言った。
「え、教授、それって、えーっと……」
榊が考え込んだ。
「イーリアス!」
教授が怒鳴りつける。
「ですよね。でも、なんか違うような……」
「その子のは古典ギリシア語だ。現代ギリシア語とは読みが違う音があるんだよ。その例として俺が授業中に読んで聞かせたの聞いてなかったな」
ギリシア語のアルファベットの形や単語などの綴りは古代からほとんど変わってないものが多いため現代ギリシア語が読めれば遺跡などに彫ってある言葉の意味も分かるものが多いらしい。
ただ、発音などは古典ギリシア語と現代ギリシア語では違うものがあるということだった。
「じゃあ、ポダソーキュサキッレウスって言うのは……」
柊矢が訊ねた。これは何とか聞き取れた歌詞の一節だった。
「足速きアキレウスだな」
教授が答えた。
「古典ギリシア語って言うのはいつ頃使われてたんですか?」
「大体紀元前二千年前くらいには使われてたようだ」
「紀元前二千年……」
今から四千年前か。
「ちなみに現代ギリシア語は十一世紀頃の口語が元になってると言われているんだよ」
榊が得意げに言った。
「お前が偉そうに言うな」
教授が再度榊の頭を叩いた。
「痛っ!」
しばらく教授の話を聞いてから柊矢と小夜は研究室を辞した。
「古典ギリシア語? 四千年前ってすごいね」
柊矢と小夜の話を聞いた楸矢が驚いて言った。
「でも、なんで分かったの? 古典ギリシア語だって」
「この前、たまたまTVをつけたらイーリアスをやってたんだ。それで大学時代の知り合いが現代ギリシア文学の研究してたの思い出してな」
「けど、なんで古典ギリシア語なんだろ」
「そこまでは分からなかった」
まさか初対面の教授に友人にさえ言ってなかった歌の話をするわけにもいかず、その点に関しては聞けなかったのだ。
それに他に聞き取れた言葉をいくつか訊ねてみたがギリシア語ではない言葉もあった。
「柊矢さん達が使ってる楽器もギリシアのものですよね。関係があるんでしょうか」
「どうかな」
「まぁ、昔のギリシア語って分かっただけでも進歩だよね。何の進歩かよく分かんないけど」
確かにギリシア語だと分かったからといって歌が聴こえる理由は不明のままだ。
ホントに、何でギリシア語なんだろう。
それも大昔の。
その日、小夜が学校から帰ろうとすると歌が聴こえてきた。
主旋律を男性が歌っている。
歌うのは圧倒的に女性で、男性の声はものすごく珍しい。女性の重唱が重なり、風に乗ってビルの間を流れていく。
もしかして……。
小夜はバス停に向かわず、甲州街道を真っ直ぐに行ってKDDIビルを通り過ぎたところで右折し超高層ビル群の中に入っていった。
そこまで行くと歌っているのが中央公園だと分かった。
中央公園に行くと、ベンチに座っている二十代半ばくらいの若い男性が歌っていた。短く淡い茶色の巻き毛が風に揺れている。中性的な顔立ちをしているが間違いなく男性だ。
柊矢さんと同い年くらいかな。
遠くにいたときは男性が弾いてる楽器の音は聴こえなかったが男性は弦楽器を演奏していた。楽器には詳しくないのでよく分からないが強いて言うなら琵琶に似ている。涙滴系のボディに弦が張られている。
周りを数人の聴衆が取り囲んで聴いていた。
小夜はスマホを取り出すと柊矢にかけた。
「柊矢さん、この歌、中央公園で歌ってます」
楸矢は学校に行っていたのでメールにした。
小夜が歌を聴きながら待っていると柊矢が来た。
男性の甘いテノールがビルの間を流れていく。もう一つの風のように。
女性のコーラスがいくつも重なっているが、それはここに集まっている人達には聴こえていないだろう。
余韻を残して歌が終わった。
聴衆が散っていく。
柊矢と小夜は顔を見合わせた。
どうする?
この男性は間違いなく歌が聴こえる人だ。と言うか、歌う人だ。
声をかけるべきか。
二人が同じ事を考えて迷っていると男性の方が近付いてきた。誰かの面影があるような気がするのだが小夜には男性の知り合いはほとんどいない。
芸能人の誰かに似てるのかな。
「歌、聴いて来たの?」
男性が訊ねた。
「はい」
小夜は素直に頷いた。
「君達もムーシコスなんだね」
「ムーシコス?」
小夜が首をかしげる。
これもギリシア語?
多分、古典の。
「ムーシコスに聴こえる歌はムーシカ。君は歌う人、ムーソポイオスだよね?」
男が小夜に向かって言った。
「え? ムーシコスじゃないんですか?」
「ムーソポイオスは歌手って言う意味。君は演奏家、キタリステースだね」
男性が柊矢に言った。
「なんで演奏だって……」
男が歌っていたのだ。柊矢が歌っていてもおかしくはないはずだ。
「男性は基本的にキタリステースだからね。僕や僕の弟みたいに男のムーソポイオスは珍しいんだ」
確かに男性の歌声はほとんど聴いたことがない。
「ムーシコスってのは、ミュージシャンって意味だけど、君達や僕みたいに〝聴こえる〟人種のことを指す言葉でもあるんだ」
「だけど……あんた、楽器も弾いてたろ」
「この程度の演奏なんか簡単だからちょっと練習すれば誰でも出来るよ。でも演奏は聴こえなかったでしょ。逆に君が演奏しながら歌っても歌声は聴こえないよ」
確かに、柊矢が家にいたときには彼の弾いてる楽器の音は聴こえなかった。
「演奏が聴こえるのはキタリステースが特定の楽器を奏でたときだけ。歌声が聴こえるのはムーソポイオスが歌ったときだけなんだ」
「その楽器は何て言うんですか?」
小夜が訊ねた。
「ブズーキだよ」
「何で、歌が聴こえるヤツと聴こえないヤツがいるんだ?」
柊矢が素朴な疑問を口にした。
「言ったでしょ。人種だって。血筋だよ」
「血筋? でも、俺の祖父は聴こえなかったぞ」
「本当に? 聴こえないって一度でも言ったことある? まぁ、大分血が薄まってきてるから聴こえないこともあるかもしれないけどね。あるいはお祖母さんの方の血筋なのかもしれないし」
「…………」
確かに血筋と言われれば柊矢と楸矢の二人とも聴こえるのは納得がいく。それに祖父は人に言うなとは言ったが聴こえないとは言っていない。
柊矢が考え込んでいる間に男性は立ち去ってしまった。
「柊矢さん?」
「あ、ああ。帰るか」
男性が新宿駅の近くまで来たときビルの陰から女性が出てきた。
「椿矢、あいつらと何を話したの」
「別に」
「あの子は鍵の守人よ」
椿矢と呼ばれた男性は肩をすくめた。
「言ったはずだよ。関わる気はないって。巻き込まないでくれないかな」
そう言うと女性に背を向けて歩き出した。
椿矢が雑踏へ消えていくのを女性はじっと見つめていた。
小夜と柊矢が駐車場に向かって超高層ビル群の間を歩いていると、不意に風が変わった。
風が硬くなったように感じた。
見ると森が出現していた。風が吹いてくる方を見ると森が途切れたところに大きな池があった。強いビル風が吹いているにもかかわらず水面にはさざ波一つ立っていない。
「池も凍り付いてるんだ」
小夜が呟いた。
「凍り付いている?」
「はい。この森も、あの池も、旋律で凍り付いてるんです」
二人が森に見惚れていると、現れたときと同じように静かに消えていった。
「ムーシコス? それ何語? 何がどうなってんの?」
楸矢がハンバーグを口に運びながら言った。
「ムーシコスって言うのは自称だと思うがな」
「ふぅん。で、『僕達』って言ったんだ。つまり、ムーシコスは集団ってこと?」
「集団かどうかはともかく、複数なのは確かだろ」
柊矢、楸矢、小夜、今日の男性。それに男性の弟もムーソポイオスだと言っていた。最低でも五人は実在するということだ。
「もっと詳しく聞けば良かったのに」
「なら今度はお前が聞きにいけ」
「今日の歌の人だね。中央公園か。行ってみようかな」
楸矢は興味のありそうな顔で言った。