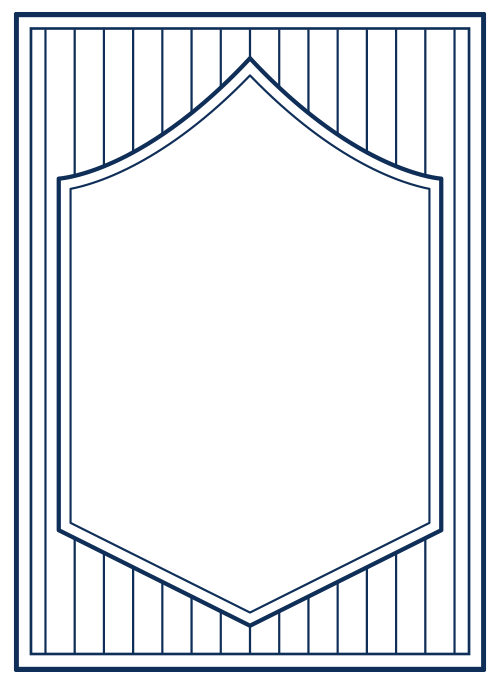一
小夜が学校から帰ると、柊矢に呼ばれた。
「ちょっと話があるんだが、いいか?」
「はい」
二人はリビングに入った。
柊矢がソファに座ったので、小夜も向かいに腰を下ろした。
「君の家なんだが……」
「はい」
小夜は身を固くした。
「火の付いたまま捨てられた煙草が原因らしい。火元の玄関先から焦げた吸い殻が見つかったそうだ」
玄関の外に置いてあった古新聞の束にタバコの火が付いたのだろうとのことだった。
小夜の家に限ったことではないが、新宿の古い住宅街というのは敷地が狭く、その敷地内ぎりぎりまで家を建てているところが多い。
しかも、どこの家も大抵は二メートルくらいの塀で囲まれている上に塀と家の間に人が通れるだけの幅がある家は少ない。
人が通れないなら裏口は作らないし、窓があってもそこから外には出られない。
小夜の祖父が逃げ遅れたのも唯一の出口である玄関が火元で外に出られなかったからだ。
「煙草……」
小夜は俯いて手を握りしめた。
煙草の火が元で家が燃えてしまった。
祖父も亡くなった。
全てを失ってしまった。
誰かが捨てた火の点いた煙草のせいで。
「……柊矢さん、私は誰を恨めばいいんですか? 何を憎めばいいんですか? 煙草ですか? 煙草会社? 煙草を吸う人?」
煙草がなければこんなことにならなかった。煙草があっても、火が付いたまま捨てる人がいなければ火事は起こらなかった。
「何を憎むのも勝手だが、憎むってのは結構エネルギーがいるもんだ。そんなことにエネルギーを使うくらいなら、もっと建設的なことをした方がいいと思うがな」
柊矢さんは大人だな。
自分はそんなに簡単に割り切れそうにない。
「本題に戻るぞ。いいか?」
「あ、はい」
小夜は慌てて顔を上げた。
確かに、恨むとか憎むとかの前にやらなければならないことがある。柊矢の言うとおり余計なことに労力を使っている暇はない。少しでも柊矢達に負担をかけないようにしなければ。
でも……。
古新聞の束?
そんなもの自分が家を出たときは置いてなかったし廃品回収は当分先だ。
雨に濡れると引き取ってもらえなくなるから当日までは外に出さないはずなのに……。
「土地をどうするか決めないといけないんだ」
「どうって?」
「まず、焼け跡のまま残しておくことは出来ない」
「はい」
それは理解できた。
「瓦礫を撤去していいか?」
「はい」
仕方ない。あれだけ燃えたのだ。何も残ってるはずがない。
「じゃ、次だ。更地にした土地はどうする?」
柊矢によると地価が高すぎて相続税の基礎控除分を大きく超えるらしい。
遺産相続の場合、不動産は時価の八割程度で計算されるのだが相続人が小夜一人と言うこともあり他の控除や特例を使っても相当額の相続税を支払うことになりそうなのだという。
古い家でローンが残ってなかったのも災いした。
相続税だけではない。そのまま持ち続けると場所が場所だけに毎年高額の固定資産税などがかかってしまうらしい。新宿駅や都庁まで徒歩十分程度の距離なのだから当然だ。
「じゃあ、手放すしかないって事ですか?」
予想していなかったわけではないとはいえショックだった。
建物は燃えてなくなってしまったとしても、せめて土地があればまたやり直せる気がしていたのだ。土地まで手放したら、本当にもう何も残らなくなる。
小夜は俯いて膝の上に置いた拳を握りしめた。
泣いたらダメだ。
ただでさえ迷惑をかけているのに、これ以上困らせるようなことは出来ない。
火災保険は建て直しにかかるお金を全額出してくれるわけではないし不足分を出せるだけのお金は小夜にはない。
生命保険で下りたお金を使ってしまえば生活費も固定資産税を払うことも出来なくなる。
かといって建物の建っていない更地のままだと固定資産税などが高すぎて毎年払い続けるのは無理とのことだった。
住宅と更地では固定資産税が違い住宅の税率はかなり軽減されが更地はそうはいかない。
地上げで不良債権になった土地が軒並み駐車場になったのも駐車料金で少しでも回収したいというのもあるだろうが固定資産税が払いきれないからでもあるのだ。
「分かりました。手続きとかはどうすれば……」
「良ければ俺が代わりにやるが。こういう手続きには慣れてるからな」
「では、お願いしてもいいでしょうか?」
小夜には他に頼れる大人はいない。
赤の他人にここまでやらせてしまうのは申し訳ないが他にどうしようもない。小夜にはどうすればいいのか全く分からないのだ。
「分かった」
柊矢はそう言うと席を立って二階の部屋へ戻っていった。
柊矢がいなくなると抑えていた涙が溢れてきた。
ひとしきり泣くと小夜は顔を洗って音楽室へ入った。
何も考えず聴こえて来る歌に身を任せるようにして歌い始めた。
柊矢は自室の椅子に座って小夜の歌声を聞いていた。
窓から差し込む光に向かって塵が舞い上がっていく。
天に向かうように。
このまま小夜の悲しみが全て天に昇って消えればいい。
一ヶ月後、祖父の遺体が帰ってきた。二十分ほどで済む行政解剖と違い、司法解剖は時間がかかるのだ。
小夜の家はもう無いので落合にある斎場の会場を借りて通夜と葬式を行った。
全ての手配は柊矢がやってくれた。小夜一人だったらどうしたらいいか分からなくて途方に暮れていたところだ。
参列者は小夜と柊矢と楸矢だけだった。近所の人や学校の友人達には知らせなかった。
葬儀の間中、ずっと祖父の死を悼んでくれてるかのような歌が聴こえていた。
小夜は骨になった祖父の骨壺を抱えて霧生家に帰ってきた。
「すみません。嫌ですよね、お骨なんて」
「何言ってるの。小夜ちゃんのお祖父さんでしょ。全然嫌じゃないよ」
「ありが……」
涙が溢れてきて、骨壺に被せられている布の上に落ちた。
小夜はその場に座り込むと泣き崩れた。
もう自分には誰もいない。
帰れる場所もない。
何も残ってない。
柊矢も楸矢も何も言わずに小夜を泣かせてくれた。
小夜は泣くだけ泣くと、泣き疲れてその場で眠り込んでしまった。
誰かが優しく抱き上げてベッドに運んでくれたのが分かった。
目が覚めるともう暗くなっていた。
大変! 夕食作ってない!
腫れぼったい目をこすりながら小夜が台所に飛び込むと、楸矢がデリバリーのパスタを食べていた。
「あ、起きたんだ。トマト&チーズのパスタで良かったかな? 何がいいか分かんなくて適当に頼んじゃった」
「すみません!」
小夜が頭を下げた。
「何が?」
「その、色々と……」
「気にしなくていいよ。それより食べなよ」
「有難うございます。それじゃ、いただきます」
小夜は大きな紙の入れ物に入っているパスタを皿に取った。
「あの、柊矢さんは?」
「先に食べて部屋に戻った」
パスタは一皿で二人分くらいあるらしく皿に取った分でお腹いっぱいで入れ物に入っていた分の半分以上残してしまった。
それを楸矢がじっと見ている。
「あ、私はもうお腹いっぱいですから……」
「いいの? 有難う」
楸矢はすぐに手を伸ばして紙の入れ物を引き寄せると、嬉しそうに食べ始めた。
小夜がデリバリーの入れ物を片付けていると柊矢が入ってきた。
「明日は学校を休んでくれ。色々手続きをしないといけないんだ」
「はい」
「学校に届けを出す必要があるなら俺が……」
「大丈夫です。自分で学校に電話をかけますから」
「そうか」
柊矢は頷くと部屋へ戻っていった。
翌朝、柊矢の車でまず大塚の監察医務院へ向かった。
「印鑑は持ってきたか?」
「はい」
印鑑も金庫に入っていて無事だったものの一つだ。
「死亡診断書を二十枚ほどもらって欲しい」
本当は解剖した遺体の場合、死体検案書というのだが、小夜の心情に配慮して死亡診断書と言う言葉を使った。もっとも、申請用紙には死体検案書と書いてあるからすぐに知られてしまうが。
「分かりました」
二人は監察医務院へ入っていくと小夜が死体検案書発行のための手続きをした。「死体検案書」という字を見て、小夜は一瞬顔をこわばらせたが、すぐに何事もなかったように手続きを終わらせた。
それから新宿区役所で住民票と戸籍謄本をやはり二十通ずつ取った。
手続きのとき柊矢から一万円札が何枚も入った封筒を渡されてびっくりしたが戸籍謄本などをとるのにかかった金額にも驚いた。
その後、柊矢の知り合いの弁護士と会ってから家庭裁判所で遺産相続の手続きをし、それから銀行や保険会社を回った。手続きの度に死体検案書や戸籍謄本などを出していたので二十通ずつあった書類はすぐになくなった。
家庭裁判所で柊矢が小夜の後見人になる手続きもしたので今日からは柊矢が小夜の正式な保護者だ。
保険会社の事務所を出ると強い風が吹いていた。その風に紛れて歌が聴こえてきた。
確か、あの夜も聴こえていたな……。
小夜の家が火事になった晩もこの歌が聴こえていて風が強かった。
柊矢がそんなことを考えているとき、突風が吹き、建物と建物の間の細い路地に立てかけられていた材木が倒れてきた。
木材が小夜に迫る。
小夜は自分に向かって倒れてくる木材を見て竦んでいた。
「危ない!」
柊矢は咄嗟に小夜をかばった。
材木のうちの一本が柊矢の肩にかすったが打ち身程度ですんだ。
「無事か」
「は、はい。有難うございます。柊矢さんは……」
「俺は何ともない」
そのとき、材木を置いていた店舗の店長らしい男が飛んできた。
盛んに頭を下げる男を適当にあしらい、柊矢は小夜を連れて立ち去りかけた。
そのとき、ふと思いついてジャケットのポケットに手を入れた。前に部屋で拾ったペンダントがあった。柊矢はそれを小夜の手を取ると握らせた。
小夜が正しい持ち主のように思えたのだ。
願わくば、これが小夜をこれ以上の不幸から守ってくれるように。
「これを持ってろ」
「え?」
小夜は手を開いてペンダントを見た。
「これ……」
「お守りだ」
「そんな大切なもの、いただけません」
「今一番必要としてるのはお前だ」
そう言って車の助手席のドアを開けて小夜を乗せると運転席側に回って車に乗り込んだ。
小夜はペンダントを掲げてペンダントヘッドを見た。白く半透明な色をしている。
何で出来てるんだろう。
珠の部分を日に透かしてみると、光を反射して光った。
綺麗……。
なんだか、あの旋律の森で落ちてきた雫と似てる気がする……。
小夜はそれを首にかけて、服の下に入れた。
途中、ファミレスで昼食を取り、最後に夕食の買い物をしてから家に戻ったのは夕方だった。
「これで大体の手続きは終わった」
「有難うございました。今から夕食の支度しますね」
小夜が学校から帰ると、柊矢に呼ばれた。
「ちょっと話があるんだが、いいか?」
「はい」
二人はリビングに入った。
柊矢がソファに座ったので、小夜も向かいに腰を下ろした。
「君の家なんだが……」
「はい」
小夜は身を固くした。
「火の付いたまま捨てられた煙草が原因らしい。火元の玄関先から焦げた吸い殻が見つかったそうだ」
玄関の外に置いてあった古新聞の束にタバコの火が付いたのだろうとのことだった。
小夜の家に限ったことではないが、新宿の古い住宅街というのは敷地が狭く、その敷地内ぎりぎりまで家を建てているところが多い。
しかも、どこの家も大抵は二メートルくらいの塀で囲まれている上に塀と家の間に人が通れるだけの幅がある家は少ない。
人が通れないなら裏口は作らないし、窓があってもそこから外には出られない。
小夜の祖父が逃げ遅れたのも唯一の出口である玄関が火元で外に出られなかったからだ。
「煙草……」
小夜は俯いて手を握りしめた。
煙草の火が元で家が燃えてしまった。
祖父も亡くなった。
全てを失ってしまった。
誰かが捨てた火の点いた煙草のせいで。
「……柊矢さん、私は誰を恨めばいいんですか? 何を憎めばいいんですか? 煙草ですか? 煙草会社? 煙草を吸う人?」
煙草がなければこんなことにならなかった。煙草があっても、火が付いたまま捨てる人がいなければ火事は起こらなかった。
「何を憎むのも勝手だが、憎むってのは結構エネルギーがいるもんだ。そんなことにエネルギーを使うくらいなら、もっと建設的なことをした方がいいと思うがな」
柊矢さんは大人だな。
自分はそんなに簡単に割り切れそうにない。
「本題に戻るぞ。いいか?」
「あ、はい」
小夜は慌てて顔を上げた。
確かに、恨むとか憎むとかの前にやらなければならないことがある。柊矢の言うとおり余計なことに労力を使っている暇はない。少しでも柊矢達に負担をかけないようにしなければ。
でも……。
古新聞の束?
そんなもの自分が家を出たときは置いてなかったし廃品回収は当分先だ。
雨に濡れると引き取ってもらえなくなるから当日までは外に出さないはずなのに……。
「土地をどうするか決めないといけないんだ」
「どうって?」
「まず、焼け跡のまま残しておくことは出来ない」
「はい」
それは理解できた。
「瓦礫を撤去していいか?」
「はい」
仕方ない。あれだけ燃えたのだ。何も残ってるはずがない。
「じゃ、次だ。更地にした土地はどうする?」
柊矢によると地価が高すぎて相続税の基礎控除分を大きく超えるらしい。
遺産相続の場合、不動産は時価の八割程度で計算されるのだが相続人が小夜一人と言うこともあり他の控除や特例を使っても相当額の相続税を支払うことになりそうなのだという。
古い家でローンが残ってなかったのも災いした。
相続税だけではない。そのまま持ち続けると場所が場所だけに毎年高額の固定資産税などがかかってしまうらしい。新宿駅や都庁まで徒歩十分程度の距離なのだから当然だ。
「じゃあ、手放すしかないって事ですか?」
予想していなかったわけではないとはいえショックだった。
建物は燃えてなくなってしまったとしても、せめて土地があればまたやり直せる気がしていたのだ。土地まで手放したら、本当にもう何も残らなくなる。
小夜は俯いて膝の上に置いた拳を握りしめた。
泣いたらダメだ。
ただでさえ迷惑をかけているのに、これ以上困らせるようなことは出来ない。
火災保険は建て直しにかかるお金を全額出してくれるわけではないし不足分を出せるだけのお金は小夜にはない。
生命保険で下りたお金を使ってしまえば生活費も固定資産税を払うことも出来なくなる。
かといって建物の建っていない更地のままだと固定資産税などが高すぎて毎年払い続けるのは無理とのことだった。
住宅と更地では固定資産税が違い住宅の税率はかなり軽減されが更地はそうはいかない。
地上げで不良債権になった土地が軒並み駐車場になったのも駐車料金で少しでも回収したいというのもあるだろうが固定資産税が払いきれないからでもあるのだ。
「分かりました。手続きとかはどうすれば……」
「良ければ俺が代わりにやるが。こういう手続きには慣れてるからな」
「では、お願いしてもいいでしょうか?」
小夜には他に頼れる大人はいない。
赤の他人にここまでやらせてしまうのは申し訳ないが他にどうしようもない。小夜にはどうすればいいのか全く分からないのだ。
「分かった」
柊矢はそう言うと席を立って二階の部屋へ戻っていった。
柊矢がいなくなると抑えていた涙が溢れてきた。
ひとしきり泣くと小夜は顔を洗って音楽室へ入った。
何も考えず聴こえて来る歌に身を任せるようにして歌い始めた。
柊矢は自室の椅子に座って小夜の歌声を聞いていた。
窓から差し込む光に向かって塵が舞い上がっていく。
天に向かうように。
このまま小夜の悲しみが全て天に昇って消えればいい。
一ヶ月後、祖父の遺体が帰ってきた。二十分ほどで済む行政解剖と違い、司法解剖は時間がかかるのだ。
小夜の家はもう無いので落合にある斎場の会場を借りて通夜と葬式を行った。
全ての手配は柊矢がやってくれた。小夜一人だったらどうしたらいいか分からなくて途方に暮れていたところだ。
参列者は小夜と柊矢と楸矢だけだった。近所の人や学校の友人達には知らせなかった。
葬儀の間中、ずっと祖父の死を悼んでくれてるかのような歌が聴こえていた。
小夜は骨になった祖父の骨壺を抱えて霧生家に帰ってきた。
「すみません。嫌ですよね、お骨なんて」
「何言ってるの。小夜ちゃんのお祖父さんでしょ。全然嫌じゃないよ」
「ありが……」
涙が溢れてきて、骨壺に被せられている布の上に落ちた。
小夜はその場に座り込むと泣き崩れた。
もう自分には誰もいない。
帰れる場所もない。
何も残ってない。
柊矢も楸矢も何も言わずに小夜を泣かせてくれた。
小夜は泣くだけ泣くと、泣き疲れてその場で眠り込んでしまった。
誰かが優しく抱き上げてベッドに運んでくれたのが分かった。
目が覚めるともう暗くなっていた。
大変! 夕食作ってない!
腫れぼったい目をこすりながら小夜が台所に飛び込むと、楸矢がデリバリーのパスタを食べていた。
「あ、起きたんだ。トマト&チーズのパスタで良かったかな? 何がいいか分かんなくて適当に頼んじゃった」
「すみません!」
小夜が頭を下げた。
「何が?」
「その、色々と……」
「気にしなくていいよ。それより食べなよ」
「有難うございます。それじゃ、いただきます」
小夜は大きな紙の入れ物に入っているパスタを皿に取った。
「あの、柊矢さんは?」
「先に食べて部屋に戻った」
パスタは一皿で二人分くらいあるらしく皿に取った分でお腹いっぱいで入れ物に入っていた分の半分以上残してしまった。
それを楸矢がじっと見ている。
「あ、私はもうお腹いっぱいですから……」
「いいの? 有難う」
楸矢はすぐに手を伸ばして紙の入れ物を引き寄せると、嬉しそうに食べ始めた。
小夜がデリバリーの入れ物を片付けていると柊矢が入ってきた。
「明日は学校を休んでくれ。色々手続きをしないといけないんだ」
「はい」
「学校に届けを出す必要があるなら俺が……」
「大丈夫です。自分で学校に電話をかけますから」
「そうか」
柊矢は頷くと部屋へ戻っていった。
翌朝、柊矢の車でまず大塚の監察医務院へ向かった。
「印鑑は持ってきたか?」
「はい」
印鑑も金庫に入っていて無事だったものの一つだ。
「死亡診断書を二十枚ほどもらって欲しい」
本当は解剖した遺体の場合、死体検案書というのだが、小夜の心情に配慮して死亡診断書と言う言葉を使った。もっとも、申請用紙には死体検案書と書いてあるからすぐに知られてしまうが。
「分かりました」
二人は監察医務院へ入っていくと小夜が死体検案書発行のための手続きをした。「死体検案書」という字を見て、小夜は一瞬顔をこわばらせたが、すぐに何事もなかったように手続きを終わらせた。
それから新宿区役所で住民票と戸籍謄本をやはり二十通ずつ取った。
手続きのとき柊矢から一万円札が何枚も入った封筒を渡されてびっくりしたが戸籍謄本などをとるのにかかった金額にも驚いた。
その後、柊矢の知り合いの弁護士と会ってから家庭裁判所で遺産相続の手続きをし、それから銀行や保険会社を回った。手続きの度に死体検案書や戸籍謄本などを出していたので二十通ずつあった書類はすぐになくなった。
家庭裁判所で柊矢が小夜の後見人になる手続きもしたので今日からは柊矢が小夜の正式な保護者だ。
保険会社の事務所を出ると強い風が吹いていた。その風に紛れて歌が聴こえてきた。
確か、あの夜も聴こえていたな……。
小夜の家が火事になった晩もこの歌が聴こえていて風が強かった。
柊矢がそんなことを考えているとき、突風が吹き、建物と建物の間の細い路地に立てかけられていた材木が倒れてきた。
木材が小夜に迫る。
小夜は自分に向かって倒れてくる木材を見て竦んでいた。
「危ない!」
柊矢は咄嗟に小夜をかばった。
材木のうちの一本が柊矢の肩にかすったが打ち身程度ですんだ。
「無事か」
「は、はい。有難うございます。柊矢さんは……」
「俺は何ともない」
そのとき、材木を置いていた店舗の店長らしい男が飛んできた。
盛んに頭を下げる男を適当にあしらい、柊矢は小夜を連れて立ち去りかけた。
そのとき、ふと思いついてジャケットのポケットに手を入れた。前に部屋で拾ったペンダントがあった。柊矢はそれを小夜の手を取ると握らせた。
小夜が正しい持ち主のように思えたのだ。
願わくば、これが小夜をこれ以上の不幸から守ってくれるように。
「これを持ってろ」
「え?」
小夜は手を開いてペンダントを見た。
「これ……」
「お守りだ」
「そんな大切なもの、いただけません」
「今一番必要としてるのはお前だ」
そう言って車の助手席のドアを開けて小夜を乗せると運転席側に回って車に乗り込んだ。
小夜はペンダントを掲げてペンダントヘッドを見た。白く半透明な色をしている。
何で出来てるんだろう。
珠の部分を日に透かしてみると、光を反射して光った。
綺麗……。
なんだか、あの旋律の森で落ちてきた雫と似てる気がする……。
小夜はそれを首にかけて、服の下に入れた。
途中、ファミレスで昼食を取り、最後に夕食の買い物をしてから家に戻ったのは夕方だった。
「これで大体の手続きは終わった」
「有難うございました。今から夕食の支度しますね」