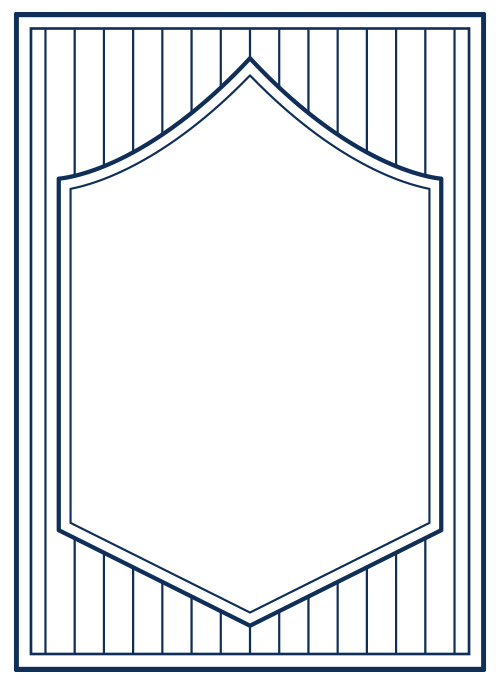四
「あの、柊矢さん? いつまで送り迎えが続くんですか?」
小夜が助手席で訊ねた。
車は明治通りを走っていた。家までそう遠くない。
沙陽は自分達ではダメだったと言っていた。
彼女が『クレーイス』と呼んでいるペンダントが偽物だからと言うのもあるのだろうが、何かの儀式のようなこともしているのかもしれない。
『あなた達』の中に小夜が入っていた。
三人全員必要ではないのなら、一番攫いやすいのは小夜だ。
まだ小夜を狙ってくる可能性があると言うことだ。
「今回のことに決着が付くまでだな。送り迎えされるのは迷惑か?」
「いえ、ただ、お仕事の邪魔になってるんじゃないかと……」
送り迎え自体は嫌ではない。
と言うか、むしろ柊矢と二人きりになれるのは嬉しい。
しかし、それが柊矢の負担になって結果的に嫌われないかが心配なのだ。
「それなら問題ない」
「でも、どうしてここまでしてくれるんですか?」
小夜は柊矢にとって、ムーシコスであること以外には縁もゆかりもない人間だ。
「前に言っただろ。祖父から一度拾った生き物は最後まで面倒を見るように言われてる」
家に帰ると夕食を作るのには少し早い時間だった。
少し歌おう。
小夜は音楽室に入ると聴こえて来るムーシカにあわせて歌い出した。
すぐに柊矢が入ってきてキタラを弾き始める。
重唱や斉唱、副旋律を歌うコーラスや演奏が次々に加わって小夜達の周りに音楽が満ちていく。
そのうちに楸矢も帰ってきて笛を吹き始めた。
透明な歌声と演奏に包まれながら歌っていると嫌なことは全て忘れられた。
きっとあの森の旋律が溶けたらこんな風に音楽が地上に満ち溢れるんだ。
斉唱と重唱、演奏、それらが重なり、風のようにどこまでも流れていく。
ムーシカが終わると丁度夕食の支度の時間だった。
これからは楸矢が音楽室でフルートの練習をする。
よその家から美味しそうな醤油の匂いが漂ってくる。
小夜はエプロンを着けながら台所に立った。歌の余韻に浸りながらジャガイモを剥こうとして手の甲の絆創膏が目に入った。
沙陽のムーシカはいつも独唱だ。
嵐の時も、それ以外の時も。
独唱のムーシカだからじゃない。
他のムーシコスが同調しないからだ。
ムーシコスは人を傷つけるためのムーシカは歌わないし、演奏しない。
だから沙陽はいつも一人で歌っている。
沙陽もムーシコスだから今のムーシカが聴こえたはずだ。
ムーソポイオスの合唱をどんな思いで聴いていたのだろうか。
本来なら、あの人だって加われるはずなのに。
柊矢から沙陽があの森に帰りたがっていると訊いた。
だがムーシコスから孤立してまで帰りたいのだろうか。
あの旋律の森に。
音楽が満ち溢れる世界は素敵だと思うけど、そこにいるのが自分一人だけでも幸せなのだろうか。
家族も友達もいない天国を楽園だと思えるのかな。
小夜がジャガイモの皮を剥いていると、か細い鳴き声が聞こえてきた。
「え?」
すごく小さくて今にも消え入りそうだけれど確かに聞こえる。
小夜はジャガイモと包丁を置くと勝手口から外に出た。外は小雨が降っている。
小夜は玄関から傘を持ち出した。
霧生家の門の近くに段ボールが置かれていた。鳴き声はその段ボールの中から聞こえてきている。子猫が四匹、段ボールの中で鳴いていた。
小夜はしゃがんで傘を段ボールに差し掛けた。
どうしよう。
居候の身で子猫を連れ帰ることは出来ない。でも、放っていくことも出来なかった。困っていると、後ろから足音が聞こえてきた。
振り返ると柊矢が立っていた。
「柊矢さん」
「何だ、子猫か」
「あ、あの、これは……」
小夜が口ごもっていると柊矢は段ボールを持ち上げた。
「帰るぞ」
「え? え? 柊矢さん、どうしてここに……」
小夜が柊矢に傘を差し掛けながら訊ねた。
「ドアが開く音がしたから様子を見に来た」
柊矢は先に立って家に向かった。
ドアを開け、傘を閉じた小夜を先に通すと玄関に段ボールを置いた。
「あの、この子達、どうするんですか?」
「うちで飼うわけにはいかないからな。貰い手を探すしかないだろ」
「柊矢さん!」
小夜が嬉しそうな顔で柊矢を見上げた。
「ミルクでもやっておけ」
「はい!」
小夜は子猫達に少しだけ温めたミルクをやると夕食の準備に戻った。
夕食の支度が出来た頃、楸矢が音楽室から出てきた。
「あれ? 猫の鳴き声」
「さっきそこに捨てられてて……」
「猫なんて久し振りだなぁ」
「猫、飼ってたことあるんですか?」
「たまにね」
たまに?
意味が分からず首を傾げていると、
「捨て猫見ると放っておけなくてさ。見つけると拾ってくるんだ。柊兄も俺も」
拾った生き物云々と言っていたのはこのことだったのか。
「でも、全部を飼うわけにはいかないからさ、いつも貰い手探して引き取ってもらってるんだ」
楸矢がフライドポテトに手を伸ばしながら言った。
「そうだったんですか」
小夜はフライドポテトの皿を取り上げながら答えた。
「ちょっと味見させてよ」
「楸矢さんのは味見じゃすまないからダメです」
そう言って取り分け用の皿にポテトを少し載せて渡した。
楸矢は、これだけ? と言いながらも美味しそうに食べていた。
「明日から猫の貰い手探ししないとね」
「楸矢さんも探してくれるんですか?」
「勿論」
「有難うございます」
小夜はそう言って楸矢の皿にフライドポテトを追加して載せた。
「猫? 欲しいけど、うち、マンションだから」
何度目かの同じ答えが返ってきた。
確かに都心では一戸建てに住んでる人間よりマンション住まいの人の方が遥かに多い。新宿区に居住している数十万人のうちの大半はマンション暮らしだ。
たまに一戸建てに住んでる子がいても家族に猫アレルギーや猫嫌いの人がいるか、猫好きは既に飼っているかで、貰い手は付かなかった。
自分が拾わせてしまった手前、何とか自力で猫の貰い手を探したかったのだが一人も見つからなかった。
がっかりして迎えに来た柊矢の車に乗った。
「どうした? 学校で何かあったのか?」
「猫の貰い手が見つからなくて……」
「あれならもう全部貰われてったぞ」
「ホントですか!?」
驚いて柊矢の顔を見た。
自分はあれだけ苦労しても見つからなかったのに。
「楸矢の友達が引き取っていった」
「楸矢さん、友達多いんですね」
「みんな楸矢の気を引きたくて貰っていったんだろ」
なるほど。
確かに猫を貰えば話しかける口実になるし、家に呼ぶ名目に使える。
楸矢さんってモテるんだ。
「あの、柊矢さん? いつまで送り迎えが続くんですか?」
小夜が助手席で訊ねた。
車は明治通りを走っていた。家までそう遠くない。
沙陽は自分達ではダメだったと言っていた。
彼女が『クレーイス』と呼んでいるペンダントが偽物だからと言うのもあるのだろうが、何かの儀式のようなこともしているのかもしれない。
『あなた達』の中に小夜が入っていた。
三人全員必要ではないのなら、一番攫いやすいのは小夜だ。
まだ小夜を狙ってくる可能性があると言うことだ。
「今回のことに決着が付くまでだな。送り迎えされるのは迷惑か?」
「いえ、ただ、お仕事の邪魔になってるんじゃないかと……」
送り迎え自体は嫌ではない。
と言うか、むしろ柊矢と二人きりになれるのは嬉しい。
しかし、それが柊矢の負担になって結果的に嫌われないかが心配なのだ。
「それなら問題ない」
「でも、どうしてここまでしてくれるんですか?」
小夜は柊矢にとって、ムーシコスであること以外には縁もゆかりもない人間だ。
「前に言っただろ。祖父から一度拾った生き物は最後まで面倒を見るように言われてる」
家に帰ると夕食を作るのには少し早い時間だった。
少し歌おう。
小夜は音楽室に入ると聴こえて来るムーシカにあわせて歌い出した。
すぐに柊矢が入ってきてキタラを弾き始める。
重唱や斉唱、副旋律を歌うコーラスや演奏が次々に加わって小夜達の周りに音楽が満ちていく。
そのうちに楸矢も帰ってきて笛を吹き始めた。
透明な歌声と演奏に包まれながら歌っていると嫌なことは全て忘れられた。
きっとあの森の旋律が溶けたらこんな風に音楽が地上に満ち溢れるんだ。
斉唱と重唱、演奏、それらが重なり、風のようにどこまでも流れていく。
ムーシカが終わると丁度夕食の支度の時間だった。
これからは楸矢が音楽室でフルートの練習をする。
よその家から美味しそうな醤油の匂いが漂ってくる。
小夜はエプロンを着けながら台所に立った。歌の余韻に浸りながらジャガイモを剥こうとして手の甲の絆創膏が目に入った。
沙陽のムーシカはいつも独唱だ。
嵐の時も、それ以外の時も。
独唱のムーシカだからじゃない。
他のムーシコスが同調しないからだ。
ムーシコスは人を傷つけるためのムーシカは歌わないし、演奏しない。
だから沙陽はいつも一人で歌っている。
沙陽もムーシコスだから今のムーシカが聴こえたはずだ。
ムーソポイオスの合唱をどんな思いで聴いていたのだろうか。
本来なら、あの人だって加われるはずなのに。
柊矢から沙陽があの森に帰りたがっていると訊いた。
だがムーシコスから孤立してまで帰りたいのだろうか。
あの旋律の森に。
音楽が満ち溢れる世界は素敵だと思うけど、そこにいるのが自分一人だけでも幸せなのだろうか。
家族も友達もいない天国を楽園だと思えるのかな。
小夜がジャガイモの皮を剥いていると、か細い鳴き声が聞こえてきた。
「え?」
すごく小さくて今にも消え入りそうだけれど確かに聞こえる。
小夜はジャガイモと包丁を置くと勝手口から外に出た。外は小雨が降っている。
小夜は玄関から傘を持ち出した。
霧生家の門の近くに段ボールが置かれていた。鳴き声はその段ボールの中から聞こえてきている。子猫が四匹、段ボールの中で鳴いていた。
小夜はしゃがんで傘を段ボールに差し掛けた。
どうしよう。
居候の身で子猫を連れ帰ることは出来ない。でも、放っていくことも出来なかった。困っていると、後ろから足音が聞こえてきた。
振り返ると柊矢が立っていた。
「柊矢さん」
「何だ、子猫か」
「あ、あの、これは……」
小夜が口ごもっていると柊矢は段ボールを持ち上げた。
「帰るぞ」
「え? え? 柊矢さん、どうしてここに……」
小夜が柊矢に傘を差し掛けながら訊ねた。
「ドアが開く音がしたから様子を見に来た」
柊矢は先に立って家に向かった。
ドアを開け、傘を閉じた小夜を先に通すと玄関に段ボールを置いた。
「あの、この子達、どうするんですか?」
「うちで飼うわけにはいかないからな。貰い手を探すしかないだろ」
「柊矢さん!」
小夜が嬉しそうな顔で柊矢を見上げた。
「ミルクでもやっておけ」
「はい!」
小夜は子猫達に少しだけ温めたミルクをやると夕食の準備に戻った。
夕食の支度が出来た頃、楸矢が音楽室から出てきた。
「あれ? 猫の鳴き声」
「さっきそこに捨てられてて……」
「猫なんて久し振りだなぁ」
「猫、飼ってたことあるんですか?」
「たまにね」
たまに?
意味が分からず首を傾げていると、
「捨て猫見ると放っておけなくてさ。見つけると拾ってくるんだ。柊兄も俺も」
拾った生き物云々と言っていたのはこのことだったのか。
「でも、全部を飼うわけにはいかないからさ、いつも貰い手探して引き取ってもらってるんだ」
楸矢がフライドポテトに手を伸ばしながら言った。
「そうだったんですか」
小夜はフライドポテトの皿を取り上げながら答えた。
「ちょっと味見させてよ」
「楸矢さんのは味見じゃすまないからダメです」
そう言って取り分け用の皿にポテトを少し載せて渡した。
楸矢は、これだけ? と言いながらも美味しそうに食べていた。
「明日から猫の貰い手探ししないとね」
「楸矢さんも探してくれるんですか?」
「勿論」
「有難うございます」
小夜はそう言って楸矢の皿にフライドポテトを追加して載せた。
「猫? 欲しいけど、うち、マンションだから」
何度目かの同じ答えが返ってきた。
確かに都心では一戸建てに住んでる人間よりマンション住まいの人の方が遥かに多い。新宿区に居住している数十万人のうちの大半はマンション暮らしだ。
たまに一戸建てに住んでる子がいても家族に猫アレルギーや猫嫌いの人がいるか、猫好きは既に飼っているかで、貰い手は付かなかった。
自分が拾わせてしまった手前、何とか自力で猫の貰い手を探したかったのだが一人も見つからなかった。
がっかりして迎えに来た柊矢の車に乗った。
「どうした? 学校で何かあったのか?」
「猫の貰い手が見つからなくて……」
「あれならもう全部貰われてったぞ」
「ホントですか!?」
驚いて柊矢の顔を見た。
自分はあれだけ苦労しても見つからなかったのに。
「楸矢の友達が引き取っていった」
「楸矢さん、友達多いんですね」
「みんな楸矢の気を引きたくて貰っていったんだろ」
なるほど。
確かに猫を貰えば話しかける口実になるし、家に呼ぶ名目に使える。
楸矢さんってモテるんだ。