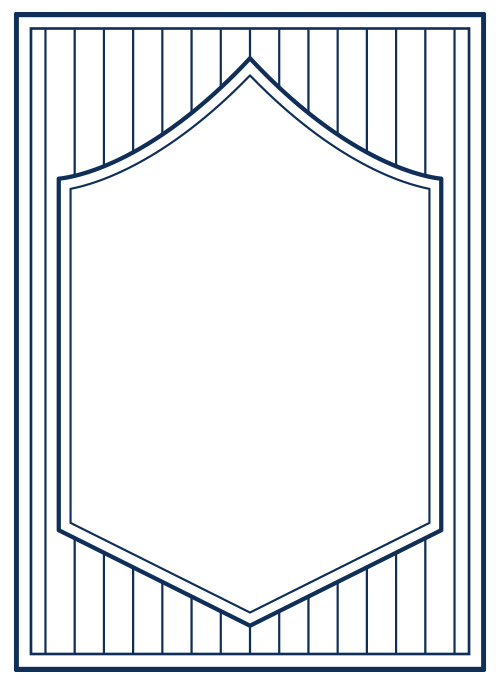三
小夜の学校の送り迎えを柊矢は本当に実行に移した。
もしかしたらあの場の勢いで言っただけかもしれない、と思ったのだが甘かった。
「小夜! 見たよ!」
「あの人、誰?」
小夜は教室に入るなり、クラスメイトに取り囲まれた。
「あれ、その包帯どうしたの?」
柊矢のことを聞こうと身を乗り出してきた清美が首の包帯に気付いて訊ねた。
「あ、これは……」
「まさかキスマーク隠してるんじゃ……」
「え~! キスマーク!?」
「あの人とそう言う関係なの!?」
クラスメイト達がどよめいた。
「清美! 変なこと言わないでよ!」
小夜が真っ赤になった。
「じゃ、どうしたの?」
「その、昨日の帰りひったくりに遭って……」
「嘘ぉ!」
「大丈夫だったの?」
「うん、どれもかすり傷」
「小夜、あの人でしょ。お守りくれた人」
小夜の傷が大したことがないと聞いて安心した途端、また柊矢に話題が戻った。
「何? お守りって」
「何のこと?」
クラスメイト達が口々に訊ねる。
清美は小夜が柊矢からお守りをもらったことをみんなにバラしてしまった。
「お守りだけじゃ安心できなくて、送り迎えまで?」
「すごい! 小夜のナイトだね!」
「そんなんじゃないってば……」
「どこに住んでる人なの?」
クラスメイトの問いに、
「小夜と……」
話そうとした清美の口を小夜は慌てて口を塞ぐ。
「あのね、あの人、後見人なの」
「後見人?」
「ほら、私のお祖父ちゃん、死んじゃったでしょ。私、他に身寄りがいないし。だから私が成人するまで保護者になってくれた人なの」
小夜がそう言うと周りにいたクラスメイト達はバツの悪そうな顔になった。
お祖父ちゃん、口実にしてごめんなさい。
小夜は胸の中で祖父に手を合わせて謝った。
それ以上誰かが口を開く前に予鈴が鳴って、みんなそそくさと席に戻っていった。
清美が小夜の手の甲を突いた。手を放せということだろう。小夜はまだ清美の口を塞いでいた。
「清美! これ以上バラさないって約束して!」
「分かった分かった」
小夜は清美から手を放すと席に着いた。
祖父の代わりに保護者になった人、と聞いてみんな柊矢の話をしなくなった。
亡くなった祖父のことに触れてしまうのを恐れているのだろう。
担任の教師から職員室に呼ばれて今朝柊矢に送られてきた事情を聞かれたが、昨日ひったくりに遭ったから後見人が用心のために送り迎えをしてくれている、と答えた。
首と手足の傷を見て信用してくれたのか、それ以上追求されることもなく解放してくれた。
教師達も孤児になった小夜に対して腫れ物を扱うように接していた。
清美達のお陰で予行演習が出来て良かった。
お祖父ちゃん、二度も口実にしてごめんなさい。
小夜は胸の中でもう一度祖父に手を合わせた。
「柊矢さん、私、放課後に友達と買い物とかしたいんですけど」
小夜は迎えの車の中で柊矢に訴えた。
「そう言うときは事前に連絡しろ」
「そうしたら迎えに来ないでくれるんですか?」
「友達と別れたところでまた連絡しろ。そこへ迎えに行く」
小夜は溜息をついた。
しかし自分の為を思ってやってくれていることを考えると、むげに断ることも出来ない。
もっとも、柊矢はどんなに拒絶しても、やると決めたら絶対やり通すだろう。
まだ一緒に暮らし始めてそんなに日数がたったわけではないが、それくらいは分かった。
それに柊矢の送り迎えはホントのことを言うとそんなに嫌ではない。
短い時間だが、柊矢と二人きりで話が出来るのは嬉しかった。
柊矢は一日中仕事をしていてお喋りが出来る機会は少ないのだ。
翌日、早速小夜は友人と出かけると連絡してきた。
ファーストフード店でおしゃべりをするだけだと言っていたし夕食の支度もあるからそんなに遅くはならないだろう。
柊矢はファーストフード店の近くに車を止めると隣の喫茶店に入った。
コーヒーが来て口を付けたとき、
「話を聞いて欲しいの」
沙陽が柊矢の側に立って言った。
「……いいだろう」
柊矢がそう答えると沙陽が向かいに座ってアメリカンを頼んだ。
「最初に言っておくと、あの子を襲わせたのは私じゃないわ」
柊矢はどうでもいいというように肩をすくめた。
馬鹿馬鹿しくて答える気にもなれなかった。
全く関係ないなら襲われたことを知っているはずがない。
ペンダントを持っていることを知っていたのは沙陽だけだし、小夜は制服の下に着けていて外からは見えなかったのだから通りすがりの男が衝動的に盗ったということもあり得ない。
沙陽は柊矢が怒ってないと思ったのか安心したように微笑んだ。
「私達の目的はあの森に帰ることなの」
「どういうことだ?」
「ムーシコスはあの森から来たの」
「俺は東京生まれの東京育ちだ」
「そうじゃなくて!」
沙陽が苛立ったように言った。
「ムーシコスの祖先はあの森に住んでたのよ。理由は分からないけど、ある日ムーシコスは森を離れた」
柊矢は黙っていた。
「私、あの森を見てきたの」
柊矢が小夜に言った、森に入って行ったきり帰ってこなかった人、というのは沙陽のことだ。
コンクールの日、沙陽を病院まで連れていって帰ってきてから超高層ビルのそばで別れ話をした。
コンクールの邪魔をしようとしたことで桂を選んだことは分かった。
仮に、あの時点でまだ桂を選んでいなかったとしても沙陽の音楽に対する拘りはかなりのものだったから、音大を中退しヴァイオリニストになることを放棄したら桂を選ぶだろうと思った。
以前から沙陽が惹かれているのは柊矢自身ではなくヴァイオリニストとしての腕のように感じていた。
桂も音楽家としては抜きん出た才能を持っていたから二股の相手が彼だと知ってその思いは強くなった。
柊矢も桂も男として好きになったのではなく音楽の才能で選ばれたような気がしたのだ。
だが柊矢は元々ヴァイオリニストを目指していたわけではない。周囲の大人達からヴァイオリニストとして将来有望だと言われていたから、それならなってもいいと思っていた程度だ。
演奏をするのが好きだから弾いていただけだし、ヴァイオリンだったのは小さい頃から習っていたからで特に拘りはなかった。
音大付属の高校に入ったのも普通の高校より音楽の時間が長いからと言うだけの理由だった。
楽器ならなんでも良かったから家で歌にあわせてキタラを弾いてるだけで満足だった。
だから、音大をやめるのに躊躇いはなかったしヴァイオリニストに未練もなかった。
仕事のほとんどは自宅でするから歌が聴こえてきたらいつでもキタラを弾ける。
柊矢にはそれだけで十分だった。
どちらかと言えばステージの上で聴衆に向かってヴァイオリンを弾くより歌にあわせてキタラを弾いている方が好きだった。
だが、それは沙陽には理解出来ないだろうと思った。
なんとなく沙陽とは考え方やものの見方が違っているような気がしていた。
だから桂と二股かけられていると分かって後腐れなく別れられると思ったのだ。
別れ話が終わる頃に森が出現した。
沙陽は自分が振ったのではなく、振られたのだと言うことに屈辱を感じたようだったが柊矢と別れることには異論がなかったようで、あっさり受け入れた。
柊矢が別れを告げると、むっとした表情ではあったものの、
「さよなら」
と言って背を向けると歩み去った。
そして森に入っていったかと思うと一緒に消えたのだ。それまで森はただ見えてるだけだと思っていたから沙陽が入っていってそのまま消えてしまったときは驚いた。
しばらく辺りを捜したが見つからなかったので沙陽の両親には、沙陽の行方が分からなくなったと連絡しておいた。警察への連絡は沙陽の両親に任せた。普通の人間には見えない森に入っていって消えた、などと言っても門前払いされるだけだし、どちらにしろ大人だからいなくなった直後では受け付けてもらえない。
この前会うまで戻っていたとは知らなかった。
「素敵なところだった」
沙陽は夢見るような表情で言った。
あの森はムーシコスを惹き付けるものがあるのだろうか。
小夜も森のことを話すときは同じような表情になる。
柊矢や楸矢は「綺麗」以上の感想は持てないから、そうするとムーシコスの中でもムーソポイオスを惹き付けるのだろうか。
だが同じムーソポイオスの椿矢も柊矢達と同じように特に魅せられている様子はない。
だとすると女性のムーソポイオスを魅了する何かがあるのだろうか。
「少し離れたところに神殿があるの。ギリシアのパルテノン神殿みたいなのが」
「あの森に帰るって言うが、あそこで生活できるのか?」
「勿論、凍り付いた旋律を溶かすのよ。そうすれば森は元に戻る。お願い、協力して」
「協力?」
「あの子の持ってたペンダントさえあれば森に帰れると思ってた。でも、私達だけではダメだった」
あれが偽物だということにはまだ気付いてないらしい。
「あなた達クレーイス・エコーの力を貸して欲しいの」
「俺達? クレーイス・エコーって何だ」
「クレーイス、あのペンダントのことだけど、鍵っていう意味よ。クレーイス・エコーっていうのは鍵の力を引き出せる者よ」
「俺達っていうのは?」
「あなたと楸矢君と、あの子」
小夜も入っているのか。
柊矢は顔をしかめた。出来ることなら小夜は巻き込みたくない。
「どうして俺達がクレーイス・エコーだって分かるんだ?」
柊矢がムーシコスだということを知ったのは嵐のときのはずだ。
「クレーイスはクレーイス・エコーの手に渡るようになっているからよ。知り合いのお祖父様がクレーイス・エコーだったけど、その人が亡くなると同時にクレーイスも消えた」
つまりクレーイスが祖父の遺品で柊矢が手に入れたと知って、柊矢と楸矢がクレーイス・エコーだと判断したのか。
そして柊矢からクレーイスを渡されたなら小夜もクレーイス・エコーということか。
確かに、小夜に渡したのはそうすべきだという気がしたからだ。
お守りと言ったのはなんとなく守ってくれそうだと思ったからそう言っただけだった。
「帰るってのはムーシコスの総意じゃなさそうだが?」
椿矢は協力する気はないと言っていた。
沙陽達の話には乗らなかったと言うことだ。
「二つに分かれてるのよ。残留派と帰還派に」
まぁ、普通に考えて、今自分が住んでいるところに満足してれば、わざわざ知らない土地に移り住もうなどとは思わないだろう。
ホモ・サピエンスはアフリカで生まれたと言われているが、だからといって人類が皆アフリカに住みたがっているわけではないのと同じだ。
「帰らないのは勝手よ。でも、帰りたいって言うのを邪魔する権利はないはずだわ」
「女子高生を襲って怪我をさせる権利だってない」
「だから、それは私じゃないって……」
「お前の一味の誰かがやったんだろ」
「一味って、そんな悪者みたいに……」
「女子高生から持ち物を奪って怪我をさせるのは十分悪者だと思うが」
沙陽が反論しようとしたとき、柊矢のスマホが振動した。
ポケットからスマホを出して電話に出る。
「ああ。分かった。今行く。そこで待ってろ」
柊矢はスマホをしまうと、それ以上は何も言わず沙陽と自分の勘定書を取ってレジに向かった。
小夜の学校の送り迎えを柊矢は本当に実行に移した。
もしかしたらあの場の勢いで言っただけかもしれない、と思ったのだが甘かった。
「小夜! 見たよ!」
「あの人、誰?」
小夜は教室に入るなり、クラスメイトに取り囲まれた。
「あれ、その包帯どうしたの?」
柊矢のことを聞こうと身を乗り出してきた清美が首の包帯に気付いて訊ねた。
「あ、これは……」
「まさかキスマーク隠してるんじゃ……」
「え~! キスマーク!?」
「あの人とそう言う関係なの!?」
クラスメイト達がどよめいた。
「清美! 変なこと言わないでよ!」
小夜が真っ赤になった。
「じゃ、どうしたの?」
「その、昨日の帰りひったくりに遭って……」
「嘘ぉ!」
「大丈夫だったの?」
「うん、どれもかすり傷」
「小夜、あの人でしょ。お守りくれた人」
小夜の傷が大したことがないと聞いて安心した途端、また柊矢に話題が戻った。
「何? お守りって」
「何のこと?」
クラスメイト達が口々に訊ねる。
清美は小夜が柊矢からお守りをもらったことをみんなにバラしてしまった。
「お守りだけじゃ安心できなくて、送り迎えまで?」
「すごい! 小夜のナイトだね!」
「そんなんじゃないってば……」
「どこに住んでる人なの?」
クラスメイトの問いに、
「小夜と……」
話そうとした清美の口を小夜は慌てて口を塞ぐ。
「あのね、あの人、後見人なの」
「後見人?」
「ほら、私のお祖父ちゃん、死んじゃったでしょ。私、他に身寄りがいないし。だから私が成人するまで保護者になってくれた人なの」
小夜がそう言うと周りにいたクラスメイト達はバツの悪そうな顔になった。
お祖父ちゃん、口実にしてごめんなさい。
小夜は胸の中で祖父に手を合わせて謝った。
それ以上誰かが口を開く前に予鈴が鳴って、みんなそそくさと席に戻っていった。
清美が小夜の手の甲を突いた。手を放せということだろう。小夜はまだ清美の口を塞いでいた。
「清美! これ以上バラさないって約束して!」
「分かった分かった」
小夜は清美から手を放すと席に着いた。
祖父の代わりに保護者になった人、と聞いてみんな柊矢の話をしなくなった。
亡くなった祖父のことに触れてしまうのを恐れているのだろう。
担任の教師から職員室に呼ばれて今朝柊矢に送られてきた事情を聞かれたが、昨日ひったくりに遭ったから後見人が用心のために送り迎えをしてくれている、と答えた。
首と手足の傷を見て信用してくれたのか、それ以上追求されることもなく解放してくれた。
教師達も孤児になった小夜に対して腫れ物を扱うように接していた。
清美達のお陰で予行演習が出来て良かった。
お祖父ちゃん、二度も口実にしてごめんなさい。
小夜は胸の中でもう一度祖父に手を合わせた。
「柊矢さん、私、放課後に友達と買い物とかしたいんですけど」
小夜は迎えの車の中で柊矢に訴えた。
「そう言うときは事前に連絡しろ」
「そうしたら迎えに来ないでくれるんですか?」
「友達と別れたところでまた連絡しろ。そこへ迎えに行く」
小夜は溜息をついた。
しかし自分の為を思ってやってくれていることを考えると、むげに断ることも出来ない。
もっとも、柊矢はどんなに拒絶しても、やると決めたら絶対やり通すだろう。
まだ一緒に暮らし始めてそんなに日数がたったわけではないが、それくらいは分かった。
それに柊矢の送り迎えはホントのことを言うとそんなに嫌ではない。
短い時間だが、柊矢と二人きりで話が出来るのは嬉しかった。
柊矢は一日中仕事をしていてお喋りが出来る機会は少ないのだ。
翌日、早速小夜は友人と出かけると連絡してきた。
ファーストフード店でおしゃべりをするだけだと言っていたし夕食の支度もあるからそんなに遅くはならないだろう。
柊矢はファーストフード店の近くに車を止めると隣の喫茶店に入った。
コーヒーが来て口を付けたとき、
「話を聞いて欲しいの」
沙陽が柊矢の側に立って言った。
「……いいだろう」
柊矢がそう答えると沙陽が向かいに座ってアメリカンを頼んだ。
「最初に言っておくと、あの子を襲わせたのは私じゃないわ」
柊矢はどうでもいいというように肩をすくめた。
馬鹿馬鹿しくて答える気にもなれなかった。
全く関係ないなら襲われたことを知っているはずがない。
ペンダントを持っていることを知っていたのは沙陽だけだし、小夜は制服の下に着けていて外からは見えなかったのだから通りすがりの男が衝動的に盗ったということもあり得ない。
沙陽は柊矢が怒ってないと思ったのか安心したように微笑んだ。
「私達の目的はあの森に帰ることなの」
「どういうことだ?」
「ムーシコスはあの森から来たの」
「俺は東京生まれの東京育ちだ」
「そうじゃなくて!」
沙陽が苛立ったように言った。
「ムーシコスの祖先はあの森に住んでたのよ。理由は分からないけど、ある日ムーシコスは森を離れた」
柊矢は黙っていた。
「私、あの森を見てきたの」
柊矢が小夜に言った、森に入って行ったきり帰ってこなかった人、というのは沙陽のことだ。
コンクールの日、沙陽を病院まで連れていって帰ってきてから超高層ビルのそばで別れ話をした。
コンクールの邪魔をしようとしたことで桂を選んだことは分かった。
仮に、あの時点でまだ桂を選んでいなかったとしても沙陽の音楽に対する拘りはかなりのものだったから、音大を中退しヴァイオリニストになることを放棄したら桂を選ぶだろうと思った。
以前から沙陽が惹かれているのは柊矢自身ではなくヴァイオリニストとしての腕のように感じていた。
桂も音楽家としては抜きん出た才能を持っていたから二股の相手が彼だと知ってその思いは強くなった。
柊矢も桂も男として好きになったのではなく音楽の才能で選ばれたような気がしたのだ。
だが柊矢は元々ヴァイオリニストを目指していたわけではない。周囲の大人達からヴァイオリニストとして将来有望だと言われていたから、それならなってもいいと思っていた程度だ。
演奏をするのが好きだから弾いていただけだし、ヴァイオリンだったのは小さい頃から習っていたからで特に拘りはなかった。
音大付属の高校に入ったのも普通の高校より音楽の時間が長いからと言うだけの理由だった。
楽器ならなんでも良かったから家で歌にあわせてキタラを弾いてるだけで満足だった。
だから、音大をやめるのに躊躇いはなかったしヴァイオリニストに未練もなかった。
仕事のほとんどは自宅でするから歌が聴こえてきたらいつでもキタラを弾ける。
柊矢にはそれだけで十分だった。
どちらかと言えばステージの上で聴衆に向かってヴァイオリンを弾くより歌にあわせてキタラを弾いている方が好きだった。
だが、それは沙陽には理解出来ないだろうと思った。
なんとなく沙陽とは考え方やものの見方が違っているような気がしていた。
だから桂と二股かけられていると分かって後腐れなく別れられると思ったのだ。
別れ話が終わる頃に森が出現した。
沙陽は自分が振ったのではなく、振られたのだと言うことに屈辱を感じたようだったが柊矢と別れることには異論がなかったようで、あっさり受け入れた。
柊矢が別れを告げると、むっとした表情ではあったものの、
「さよなら」
と言って背を向けると歩み去った。
そして森に入っていったかと思うと一緒に消えたのだ。それまで森はただ見えてるだけだと思っていたから沙陽が入っていってそのまま消えてしまったときは驚いた。
しばらく辺りを捜したが見つからなかったので沙陽の両親には、沙陽の行方が分からなくなったと連絡しておいた。警察への連絡は沙陽の両親に任せた。普通の人間には見えない森に入っていって消えた、などと言っても門前払いされるだけだし、どちらにしろ大人だからいなくなった直後では受け付けてもらえない。
この前会うまで戻っていたとは知らなかった。
「素敵なところだった」
沙陽は夢見るような表情で言った。
あの森はムーシコスを惹き付けるものがあるのだろうか。
小夜も森のことを話すときは同じような表情になる。
柊矢や楸矢は「綺麗」以上の感想は持てないから、そうするとムーシコスの中でもムーソポイオスを惹き付けるのだろうか。
だが同じムーソポイオスの椿矢も柊矢達と同じように特に魅せられている様子はない。
だとすると女性のムーソポイオスを魅了する何かがあるのだろうか。
「少し離れたところに神殿があるの。ギリシアのパルテノン神殿みたいなのが」
「あの森に帰るって言うが、あそこで生活できるのか?」
「勿論、凍り付いた旋律を溶かすのよ。そうすれば森は元に戻る。お願い、協力して」
「協力?」
「あの子の持ってたペンダントさえあれば森に帰れると思ってた。でも、私達だけではダメだった」
あれが偽物だということにはまだ気付いてないらしい。
「あなた達クレーイス・エコーの力を貸して欲しいの」
「俺達? クレーイス・エコーって何だ」
「クレーイス、あのペンダントのことだけど、鍵っていう意味よ。クレーイス・エコーっていうのは鍵の力を引き出せる者よ」
「俺達っていうのは?」
「あなたと楸矢君と、あの子」
小夜も入っているのか。
柊矢は顔をしかめた。出来ることなら小夜は巻き込みたくない。
「どうして俺達がクレーイス・エコーだって分かるんだ?」
柊矢がムーシコスだということを知ったのは嵐のときのはずだ。
「クレーイスはクレーイス・エコーの手に渡るようになっているからよ。知り合いのお祖父様がクレーイス・エコーだったけど、その人が亡くなると同時にクレーイスも消えた」
つまりクレーイスが祖父の遺品で柊矢が手に入れたと知って、柊矢と楸矢がクレーイス・エコーだと判断したのか。
そして柊矢からクレーイスを渡されたなら小夜もクレーイス・エコーということか。
確かに、小夜に渡したのはそうすべきだという気がしたからだ。
お守りと言ったのはなんとなく守ってくれそうだと思ったからそう言っただけだった。
「帰るってのはムーシコスの総意じゃなさそうだが?」
椿矢は協力する気はないと言っていた。
沙陽達の話には乗らなかったと言うことだ。
「二つに分かれてるのよ。残留派と帰還派に」
まぁ、普通に考えて、今自分が住んでいるところに満足してれば、わざわざ知らない土地に移り住もうなどとは思わないだろう。
ホモ・サピエンスはアフリカで生まれたと言われているが、だからといって人類が皆アフリカに住みたがっているわけではないのと同じだ。
「帰らないのは勝手よ。でも、帰りたいって言うのを邪魔する権利はないはずだわ」
「女子高生を襲って怪我をさせる権利だってない」
「だから、それは私じゃないって……」
「お前の一味の誰かがやったんだろ」
「一味って、そんな悪者みたいに……」
「女子高生から持ち物を奪って怪我をさせるのは十分悪者だと思うが」
沙陽が反論しようとしたとき、柊矢のスマホが振動した。
ポケットからスマホを出して電話に出る。
「ああ。分かった。今行く。そこで待ってろ」
柊矢はスマホをしまうと、それ以上は何も言わず沙陽と自分の勘定書を取ってレジに向かった。