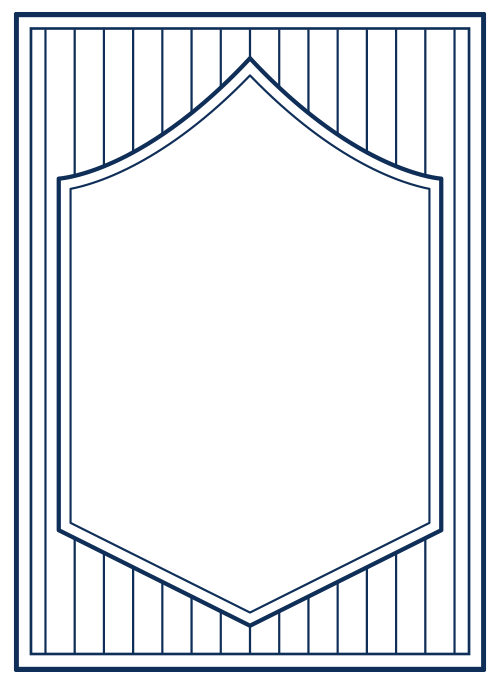一
風の中に歌が聴こえる。
いつも聴こえる美しい旋律の歌。
どこにいても聴こえるのに、どこを捜しても歌っている人間を見つけることが出来ない。
誰かが歌い始めると、それに誘われるようにして見えない歌い手達が次々と歌に加わっていく。
複数の蝶が戯れるように主旋律を歌う者が何度も交代し、それに多重コーラスが重なる。
古い賛美歌のようでもあり、どこかの国の民族音楽でもあるような独特の旋律の歌だった。
歌詞も基本的にはどこの国のものか良く分からない不思議な言語だが、稀に英語や日本語など知っている言葉のときもあった。
どの歌も、何故か懐かしく感じるのは物心ついたときから聴いているからだろうか。
この歌が聴こえるのは自分と弟の楸矢だけだ。
今まで他に歌が聴こえると言った者はいない。
歌が聴こえることを信じてくれた人も。
亡くなった祖父からは人に話してはいけないときつく言われていた。
だから、この歌のことは楸矢と二人きりの秘密にしていた。
誰かが歌っているところを見たこともない。
聴こえてくる方角も分からないから歌っている人や演奏している人を捜すすべもない。
それでも何度か捜してみたことはあったが、いつも徒労に終わっていた。
だから、捜すのを辞めて久しい。
けれど、今日の歌は違っていた。
いつもと同じように肉声は聞こえないが、それでも聴こえてくる方角が分かる。
もしかしたら今日こそ見つかるかもしれないと、新宿駅西口から歌声の方に向かって歩き出した。
あまり期待をしないようにしようと思いながらも、歌に誘われるように歩いているうちに西新宿の超高層ビル群の中にいた。
この辺は昔の建坪率で建てられているから、ビルとビルの間が大きく開いていて広々としている。欄干の下を自動車が走っていた。
強いビル風に吹かれながら歩いていると、肉声が聴こえてきた。
そのまま歩いていくと、紺色のブレザーとスカートの後ろ姿が見えた。肩より少し下の辺りで切りそろえた黒い髪が風になびいている。
顔は見えないが、その少女が歌っているのは間違いなくいつも聴こえてくる歌だ。
本当にいた……。
信じられない思いで立ち止まって見つめていると、不意に少女が振り返った。
整った顔立ちに大きな眼。美女と言いたいところだが、頬の柔らかな曲線が幼さを残しているから、まだ大人の美人と言える歳ではない。
「すまん。邪魔をする気はなかったんだ」
柊矢が謝ると、少女は頬を染め、軽く会釈をして走り去った。
あの制服は確かこの近くの高校のものだったよな。
また会えるだろうか。
柊矢は少女が去って行った方を見つめながら立ち尽くしていた。
翌日、昨日の場所へ行こうと駐車場に車を止めて歩き出すと同時に歌が始まった。
太陽が天頂からわずかに傾き、斜めに差し込む光の中の無数の塵がきらめいて、まるで街を金色のベールで覆っているようだった。
そのベールに包まれるようにして少女が歌っていた。
柊矢が行くと、少女は恥ずかしそうな表情で小さな声になったが、そのうち慣れたのか普通に歌うようになった。
声をかけたかったが、歌を聴いてもいたかったし、なんと話しかければいいかも分からず、ただ黙って聴いている事しか出来なかった。
歌が始まる頃、柊矢がいつもの場所へ行き、先に来ている少女が歌い、終わると二人は互いに言葉を交わすこともなく、それぞれ違う方向へ帰っていく。
そんな日々が続いた。
ある日、部屋を出ようとしたとき、何か小さなものを蹴飛ばした。
見ると、半透明の白い珠がついたネックレスだった。祖父の遺品の中にあったものだ。
大学のとき、付き合っていた相手に贈ろうと思っていたが、結局その機会がないまま別れてしまった。
その後はずっと見かけなかったが、机の下にでも落ちていたのだろうか。
何となくそれをポケットに突っ込むと、すぐにそのことは忘れて家を出た。
超高層ビル群の間を強いビル風が吹き抜けていく。
いつものように少女は歌っていた。
ここにいるのは少女一人だが、斉唱や重唱、副旋律のコーラスなどに、いくつもの楽器の音色が重なっている。
一曲歌い終わり、二曲目の前奏が聴こえてきたとき、不意に風の感触が変わった。風が硬くなったような気がした。
少女もそれに気付いたらしく、開きかけた口を閉ざした。
周りを見ると、超高層ビル群に重なるようにして巨大な樹々が聳え立っていた。
地面も樹や草も氷で出来てるかのように白く透き通った色をしていた。
白く半透明の樹は高さ二百メートル前後の超高層ビルと同じくらいだから相当な巨木だった。
下から見上げると、巨大な樅の木のようだ。
蟻が白いクリスマスツリーを見上げるとこんな感じに見えるのかもしれない。
そんな樹々が森のように何本も聳え立っていた。
凍り付いた樹々の天辺の辺りが淡いオレンジ色に光っていた。
不意に水滴が流れるように光が枝を伝った。
雫が落ちたように見えたとき、
「メー……エイ……デテア……ペー……」
少女が独特の旋律を呟きながら森の方へ一歩踏み出した。
柊矢は咄嗟に少女の腕を掴んだ。
少女が我に返ったようにはっとして柊矢を見上げた。そして、柊矢に掴まれている腕を見下ろすと真っ赤になった。
「男に腕を掴まれたくらいで赤くなるなんて相当な奥手だな」
少女が更に赤くなった。
「か、からかうために掴んだんですか! 離して下さい!」
辺りを見回すと、森は消えていた。
柊矢は手を離した。
「そうじゃない。あの森に入っていこうとしたから」
少女が、え? と言うように首を傾げた。
「昔、あの森に入っていった人間が戻ってこなかったんだ。だから君が入っていかないように……」
「前にもあの森を見たことがあるんですか?」
「何度かね」
「素敵なところでしたよね」
少女が夢見るような表情で言った。
確かに、見た目だけは水晶の森のようで幻想的だ。だが、二度と帰ってこられないかもしれないのに入っていくのは危険だ。
柊矢がそう言うと少女は素直に頷いた。
「もう時間だから帰りますね」
少女はそう言ってお辞儀をすると去って行った。その後ろ姿を見送ると、柊矢も駐車場に足を向けた。
霞乃小夜は家の近くまで来たところで、すぐそばの超高層ビルを見上げた。
あの樹々を覆っていたもの、あれは音楽だった。
正確には旋律が凍り付いたもの。
だから、溶けた旋律の雫が落ちてきたとき、自分の中に歌が溢れてきたのだ。
そのこと、言いそびれちゃったな。
普通の人にそんなことを言ったら正気を疑われるところだが……。
あの人、多分、〝聴こえる〟人……だよね。
また機会があったら、と思うが、自分から知らない男性に話しかける勇気はなかった。特に若い男の人には。
あの人の言うように奥手だからじゃない。
単に人見知りなだけだ。
小夜は自分に言い訳するように胸の中で呟いた。どちらにしろ話しかけられないことに変わりはないが。
あの森はまた現れるだろうか。
旋律で凍り付いた森。その旋律が溶け出したら、どんな音楽が聴こえてくるのだろう。
もう一度だけ、ビルを見上げると小夜は家の中に入っていった。
その晩は強い風が吹いていた。窓がガタガタと音を立てている。
柊矢は自分の部屋で仕事をしていた。
また歌が聴こえる。
なんだか嫌な感じのする歌だ。こういう歌は稀だ。大抵は歌詞が分からなくても聴いていると、意識と旋律が一つになって大気と溶け合ったようになり、曲が終わると清々しい気持ちになるものなのに。
歌っているのは女性一人だけだ。
これも珍しい。普通は誰かが歌うか演奏を始めるかすると次々に他の歌い手や演奏が加わっていくものだ。
まぁ、こんな歌を一緒に奏でたいと思う者がいないのは当然かもしれないが。
声に聴き覚えがあるような気がするが、あの少女以外の歌い手は知らないのだから思い過ごしだろう。あの少女の歌声ではないことは確かだ。
歌い手は当然みな違う声をしているのだが、一人が歌い始めると次々に重唱や斉唱、副旋律のコーラスが加わるので独唱はまずない。
同じ歌でも主旋律を担当するのがいつも同じ歌い手というわけではない上に、何人もいるため、声を個別に聞き分けて覚えるのは知り合いでもない限り不可能なのだ。
基本的に声質や音域が違うだけで、きれいな声で歌が上手いというのは共通しているので、声が特徴的だから覚えてしまうとか、下手すぎて覚えてしまうと言うこともない。
「柊兄、坂本さんから電話」
楸矢が一階の電話口から怒鳴った。
柊矢は机の上の子機を取った。電話は西新宿にあるアパートの管理人からだった。
「楸矢、西新宿のアパートの近くで火事が起きてるらしい。ちょっと行ってくる」
ジャケットを羽織りながら、台所でコーヒーを飲んでいる楸矢にそう言うと、車の鍵を取って家を出た。
「坂本さん」
柊矢が管理人に声をかけると、
「霧生さん、すみません、夜遅く」
頭がはげ上がった初老の管理人が謝った。
「構いませんよ。火が強いですね」
燃えているのは柊矢が所有しているアパートから二軒ほどしか離れていない、一戸建ての家だった。
柊矢が野次馬を掻き分けて火元の家の前に出ると、あの少女が立っていた。炎に照らされながら、呆然と燃えている家を見つめていた。手にエコバッグを持っている。
少女に話しかけようとしたとき、
「誰か中に残ってるか!」
消防士の声に、少女がはっとすると、袋から手を離し、家に向かって駆け出そうとした。
「おい、待て!」
咄嗟に柊矢は少女の腕を掴んだ。
「離して! お祖父ちゃんが中にいるの! お祖父ちゃん!」
少女が燃えている家に向かって手を伸ばしながら叫んだ。
「お祖父ちゃん! お祖父ちゃん!」
引き留めている柊矢の腕の中で、少女がもがきながら必死で祖父を呼んでいた。
炎は風にあおられ、ものすごい勢いで燃え上がっている。
消防士も手の施しようがないようだった。
そのとき、楽器の前奏が聴こえてきた。それに合わせて歌が始まった。次々にコーラスと演奏が加わっていく。
今までの歌声がかき消され、優しい旋律と共に強い風がやんだ。
一陣の冷たい風が吹き抜けかと思うと雨が降り出した。
雨は瞬く間に土砂降りになり、燃えさかっている炎を鎮めた。
野次馬が散っていく。
突然の大雨と、消防士達の消火活動のお陰で周囲の家が延焼することもなく火事は収まった。
しかし、少女の家は完全に燃え尽きていた。黒焦げの瓦礫がわずかに残っているだけだった。
「お祖父ちゃん……」
腕の中で少女が震えていた。
消防士達は炎が収まった瓦礫の中に入っていくと、しばらくして黒い遺体収容袋を担架に乗せて出てきた。
「お祖父ちゃん!」
少女が悲鳴を上げた。
「おい、大丈夫か……」
柊矢が声をかけるのと、少女が気を失うのは同時だった。
「おい!」
柊矢は慌てて少女を抱き留めた。
周囲を見回すと、わずかに残っていた野次馬達が覗き込んでいた。
「誰か、この子のこと知ってますか?」
「ここのうちの子だけど……」
近所の人らしい、中年の女性が焼け落ちた家に視線を向けて答えた。
「家族は?」
「お祖父さんだけよ」
それは多分、今運び出された人だろう。
そのとき、人混みを掻き分けて警官がやってきた。
警官は周囲の人達に話を聞くと、柊矢の元へやってきた。
気を失っている少女を見ると、警官は救急車を呼んだ。
すぐにやってきた救急車に、担架に乗せられた少女が運び込まれる。
一緒に乗ろうとする人がいないのを見て取った柊矢は咄嗟に、
「一緒に行きます」
と言っていた。
「坂本さん、すみません、車をお願いします」
柊矢は坂本に車の鍵を渡すと救急車に同乗した。
風の中に歌が聴こえる。
いつも聴こえる美しい旋律の歌。
どこにいても聴こえるのに、どこを捜しても歌っている人間を見つけることが出来ない。
誰かが歌い始めると、それに誘われるようにして見えない歌い手達が次々と歌に加わっていく。
複数の蝶が戯れるように主旋律を歌う者が何度も交代し、それに多重コーラスが重なる。
古い賛美歌のようでもあり、どこかの国の民族音楽でもあるような独特の旋律の歌だった。
歌詞も基本的にはどこの国のものか良く分からない不思議な言語だが、稀に英語や日本語など知っている言葉のときもあった。
どの歌も、何故か懐かしく感じるのは物心ついたときから聴いているからだろうか。
この歌が聴こえるのは自分と弟の楸矢だけだ。
今まで他に歌が聴こえると言った者はいない。
歌が聴こえることを信じてくれた人も。
亡くなった祖父からは人に話してはいけないときつく言われていた。
だから、この歌のことは楸矢と二人きりの秘密にしていた。
誰かが歌っているところを見たこともない。
聴こえてくる方角も分からないから歌っている人や演奏している人を捜すすべもない。
それでも何度か捜してみたことはあったが、いつも徒労に終わっていた。
だから、捜すのを辞めて久しい。
けれど、今日の歌は違っていた。
いつもと同じように肉声は聞こえないが、それでも聴こえてくる方角が分かる。
もしかしたら今日こそ見つかるかもしれないと、新宿駅西口から歌声の方に向かって歩き出した。
あまり期待をしないようにしようと思いながらも、歌に誘われるように歩いているうちに西新宿の超高層ビル群の中にいた。
この辺は昔の建坪率で建てられているから、ビルとビルの間が大きく開いていて広々としている。欄干の下を自動車が走っていた。
強いビル風に吹かれながら歩いていると、肉声が聴こえてきた。
そのまま歩いていくと、紺色のブレザーとスカートの後ろ姿が見えた。肩より少し下の辺りで切りそろえた黒い髪が風になびいている。
顔は見えないが、その少女が歌っているのは間違いなくいつも聴こえてくる歌だ。
本当にいた……。
信じられない思いで立ち止まって見つめていると、不意に少女が振り返った。
整った顔立ちに大きな眼。美女と言いたいところだが、頬の柔らかな曲線が幼さを残しているから、まだ大人の美人と言える歳ではない。
「すまん。邪魔をする気はなかったんだ」
柊矢が謝ると、少女は頬を染め、軽く会釈をして走り去った。
あの制服は確かこの近くの高校のものだったよな。
また会えるだろうか。
柊矢は少女が去って行った方を見つめながら立ち尽くしていた。
翌日、昨日の場所へ行こうと駐車場に車を止めて歩き出すと同時に歌が始まった。
太陽が天頂からわずかに傾き、斜めに差し込む光の中の無数の塵がきらめいて、まるで街を金色のベールで覆っているようだった。
そのベールに包まれるようにして少女が歌っていた。
柊矢が行くと、少女は恥ずかしそうな表情で小さな声になったが、そのうち慣れたのか普通に歌うようになった。
声をかけたかったが、歌を聴いてもいたかったし、なんと話しかければいいかも分からず、ただ黙って聴いている事しか出来なかった。
歌が始まる頃、柊矢がいつもの場所へ行き、先に来ている少女が歌い、終わると二人は互いに言葉を交わすこともなく、それぞれ違う方向へ帰っていく。
そんな日々が続いた。
ある日、部屋を出ようとしたとき、何か小さなものを蹴飛ばした。
見ると、半透明の白い珠がついたネックレスだった。祖父の遺品の中にあったものだ。
大学のとき、付き合っていた相手に贈ろうと思っていたが、結局その機会がないまま別れてしまった。
その後はずっと見かけなかったが、机の下にでも落ちていたのだろうか。
何となくそれをポケットに突っ込むと、すぐにそのことは忘れて家を出た。
超高層ビル群の間を強いビル風が吹き抜けていく。
いつものように少女は歌っていた。
ここにいるのは少女一人だが、斉唱や重唱、副旋律のコーラスなどに、いくつもの楽器の音色が重なっている。
一曲歌い終わり、二曲目の前奏が聴こえてきたとき、不意に風の感触が変わった。風が硬くなったような気がした。
少女もそれに気付いたらしく、開きかけた口を閉ざした。
周りを見ると、超高層ビル群に重なるようにして巨大な樹々が聳え立っていた。
地面も樹や草も氷で出来てるかのように白く透き通った色をしていた。
白く半透明の樹は高さ二百メートル前後の超高層ビルと同じくらいだから相当な巨木だった。
下から見上げると、巨大な樅の木のようだ。
蟻が白いクリスマスツリーを見上げるとこんな感じに見えるのかもしれない。
そんな樹々が森のように何本も聳え立っていた。
凍り付いた樹々の天辺の辺りが淡いオレンジ色に光っていた。
不意に水滴が流れるように光が枝を伝った。
雫が落ちたように見えたとき、
「メー……エイ……デテア……ペー……」
少女が独特の旋律を呟きながら森の方へ一歩踏み出した。
柊矢は咄嗟に少女の腕を掴んだ。
少女が我に返ったようにはっとして柊矢を見上げた。そして、柊矢に掴まれている腕を見下ろすと真っ赤になった。
「男に腕を掴まれたくらいで赤くなるなんて相当な奥手だな」
少女が更に赤くなった。
「か、からかうために掴んだんですか! 離して下さい!」
辺りを見回すと、森は消えていた。
柊矢は手を離した。
「そうじゃない。あの森に入っていこうとしたから」
少女が、え? と言うように首を傾げた。
「昔、あの森に入っていった人間が戻ってこなかったんだ。だから君が入っていかないように……」
「前にもあの森を見たことがあるんですか?」
「何度かね」
「素敵なところでしたよね」
少女が夢見るような表情で言った。
確かに、見た目だけは水晶の森のようで幻想的だ。だが、二度と帰ってこられないかもしれないのに入っていくのは危険だ。
柊矢がそう言うと少女は素直に頷いた。
「もう時間だから帰りますね」
少女はそう言ってお辞儀をすると去って行った。その後ろ姿を見送ると、柊矢も駐車場に足を向けた。
霞乃小夜は家の近くまで来たところで、すぐそばの超高層ビルを見上げた。
あの樹々を覆っていたもの、あれは音楽だった。
正確には旋律が凍り付いたもの。
だから、溶けた旋律の雫が落ちてきたとき、自分の中に歌が溢れてきたのだ。
そのこと、言いそびれちゃったな。
普通の人にそんなことを言ったら正気を疑われるところだが……。
あの人、多分、〝聴こえる〟人……だよね。
また機会があったら、と思うが、自分から知らない男性に話しかける勇気はなかった。特に若い男の人には。
あの人の言うように奥手だからじゃない。
単に人見知りなだけだ。
小夜は自分に言い訳するように胸の中で呟いた。どちらにしろ話しかけられないことに変わりはないが。
あの森はまた現れるだろうか。
旋律で凍り付いた森。その旋律が溶け出したら、どんな音楽が聴こえてくるのだろう。
もう一度だけ、ビルを見上げると小夜は家の中に入っていった。
その晩は強い風が吹いていた。窓がガタガタと音を立てている。
柊矢は自分の部屋で仕事をしていた。
また歌が聴こえる。
なんだか嫌な感じのする歌だ。こういう歌は稀だ。大抵は歌詞が分からなくても聴いていると、意識と旋律が一つになって大気と溶け合ったようになり、曲が終わると清々しい気持ちになるものなのに。
歌っているのは女性一人だけだ。
これも珍しい。普通は誰かが歌うか演奏を始めるかすると次々に他の歌い手や演奏が加わっていくものだ。
まぁ、こんな歌を一緒に奏でたいと思う者がいないのは当然かもしれないが。
声に聴き覚えがあるような気がするが、あの少女以外の歌い手は知らないのだから思い過ごしだろう。あの少女の歌声ではないことは確かだ。
歌い手は当然みな違う声をしているのだが、一人が歌い始めると次々に重唱や斉唱、副旋律のコーラスが加わるので独唱はまずない。
同じ歌でも主旋律を担当するのがいつも同じ歌い手というわけではない上に、何人もいるため、声を個別に聞き分けて覚えるのは知り合いでもない限り不可能なのだ。
基本的に声質や音域が違うだけで、きれいな声で歌が上手いというのは共通しているので、声が特徴的だから覚えてしまうとか、下手すぎて覚えてしまうと言うこともない。
「柊兄、坂本さんから電話」
楸矢が一階の電話口から怒鳴った。
柊矢は机の上の子機を取った。電話は西新宿にあるアパートの管理人からだった。
「楸矢、西新宿のアパートの近くで火事が起きてるらしい。ちょっと行ってくる」
ジャケットを羽織りながら、台所でコーヒーを飲んでいる楸矢にそう言うと、車の鍵を取って家を出た。
「坂本さん」
柊矢が管理人に声をかけると、
「霧生さん、すみません、夜遅く」
頭がはげ上がった初老の管理人が謝った。
「構いませんよ。火が強いですね」
燃えているのは柊矢が所有しているアパートから二軒ほどしか離れていない、一戸建ての家だった。
柊矢が野次馬を掻き分けて火元の家の前に出ると、あの少女が立っていた。炎に照らされながら、呆然と燃えている家を見つめていた。手にエコバッグを持っている。
少女に話しかけようとしたとき、
「誰か中に残ってるか!」
消防士の声に、少女がはっとすると、袋から手を離し、家に向かって駆け出そうとした。
「おい、待て!」
咄嗟に柊矢は少女の腕を掴んだ。
「離して! お祖父ちゃんが中にいるの! お祖父ちゃん!」
少女が燃えている家に向かって手を伸ばしながら叫んだ。
「お祖父ちゃん! お祖父ちゃん!」
引き留めている柊矢の腕の中で、少女がもがきながら必死で祖父を呼んでいた。
炎は風にあおられ、ものすごい勢いで燃え上がっている。
消防士も手の施しようがないようだった。
そのとき、楽器の前奏が聴こえてきた。それに合わせて歌が始まった。次々にコーラスと演奏が加わっていく。
今までの歌声がかき消され、優しい旋律と共に強い風がやんだ。
一陣の冷たい風が吹き抜けかと思うと雨が降り出した。
雨は瞬く間に土砂降りになり、燃えさかっている炎を鎮めた。
野次馬が散っていく。
突然の大雨と、消防士達の消火活動のお陰で周囲の家が延焼することもなく火事は収まった。
しかし、少女の家は完全に燃え尽きていた。黒焦げの瓦礫がわずかに残っているだけだった。
「お祖父ちゃん……」
腕の中で少女が震えていた。
消防士達は炎が収まった瓦礫の中に入っていくと、しばらくして黒い遺体収容袋を担架に乗せて出てきた。
「お祖父ちゃん!」
少女が悲鳴を上げた。
「おい、大丈夫か……」
柊矢が声をかけるのと、少女が気を失うのは同時だった。
「おい!」
柊矢は慌てて少女を抱き留めた。
周囲を見回すと、わずかに残っていた野次馬達が覗き込んでいた。
「誰か、この子のこと知ってますか?」
「ここのうちの子だけど……」
近所の人らしい、中年の女性が焼け落ちた家に視線を向けて答えた。
「家族は?」
「お祖父さんだけよ」
それは多分、今運び出された人だろう。
そのとき、人混みを掻き分けて警官がやってきた。
警官は周囲の人達に話を聞くと、柊矢の元へやってきた。
気を失っている少女を見ると、警官は救急車を呼んだ。
すぐにやってきた救急車に、担架に乗せられた少女が運び込まれる。
一緒に乗ろうとする人がいないのを見て取った柊矢は咄嗟に、
「一緒に行きます」
と言っていた。
「坂本さん、すみません、車をお願いします」
柊矢は坂本に車の鍵を渡すと救急車に同乗した。