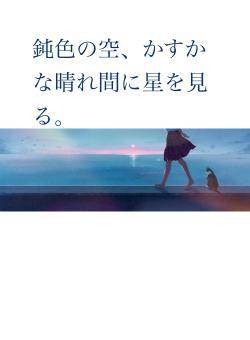その日の夜、凪から電話がかかってきた。
桜と会ったあと、メッセージを送ったのだ。
凪には助言をもらったから、報告はしなければならないと思って、「ふられました」とひとことだけ。ほかにはなんと打てばいいのか分からなかった。
画面を見ながら、出ようか迷う。
今出たら涙腺が緩んでしまいそうで、怖かった。
でも、先にメッセージを送ったのは僕だ。少し間をおいてから通話ボタンを押す。
「もしも……」
『しおー! ふられたってマジか!?』
とんでもなく大きな声が耳の中で響いて、僕は思わずスマホを遠ざけた。
「うるさ……」
『しお、ごめん。マジでごめん!』
凪はなぜだか何度も僕に謝ってくる。涙腺が緩む暇もない。
「……いや、なんで凪が謝るの」
『なんでって……だってしおが告白したの、俺がけしかけるようなこと言ったからだろ? 俺のせいじゃん!』
すんすんしている凪の声を聞きながら、僕は久しぶりに、そういえば友だちってこんな感じだったっけ、と思った。どこか懐かしいような気持ちに、胸が震えるのを感じる。
どうやら凪は、僕がふられたことに責任を感じてしまっているようだ。告白自体は僕自身が決めたことで、凪が責任を感じる必要なんてぜんぜんないのに。
……だけど、そうか。
あのとき僕は、凪に助言されて覚悟を決めたから。
僕の行動は、彼にまで影響を与えたのだ。そこまで考えてメッセージを送っていなかった。もう少し考えて、凪が気を遣わずに済むような文を送ればよかったかもしれない。
「……べつに、違うよ。僕が言いたかったから言ったんだ。凪のせいじゃない」
『でも……』
「言ってよかったと思ってるし」
呟くと、戸惑いの色を滲ませた凪の声が返ってきた。
『言ってよかった、って……告白を?』
「うん」
『……なんでだよ。ふられちゃったんだろ?』
「まぁね……でも後悔はしてないよ。今は、桜と付き合いたいっていうより、もっと知りたいって思ってる」
『そっかぁ……分かった。俺、これからもめちゃくちゃ応援するから! 相談にも乗るし!』
「うん。ありがと」
まさか、凪がこんなに泣いてくれるとは思わなかった。慰めてくれるとも。
ふられてみなければ分からなかったことだ。ふられたときは悲しかったけど、ただ悲しいだけじゃない。きっとこうやって、僕たちは大人になっていくんだろう。
「つーか、いつまで泣いてんの」
『うっ、うるせーな! 俺だって泣く気なんてなかったよ。でも、ふだんじぶんのことをぜんぜん話さないお前が告白するためにどれだけの勇気出したのかとか考えたら、勝手に涙が出てくるんだよ』
恥ずかしかったのか、凪が喚き出した。
「ははっ……大袈裟だなぁ。でも、ありがと」
笑ってはいけないのだけど、凪のふにゃふにゃした声がおかしくて、僕はしばらくお腹を抱えて笑った。
***
週末、僕は、結賀大学附属病院に向かっていた。
彼女が入院しているその病院は国立機構で、県内でも有数の大学病院である。
特に研究施設が充実していて、敷地内にはラボと呼ばれる国立科学研究所も併設され、最先端医療の研究が行われているという。
敷地内には、たくさんの外来患者や入院患者、そしてスタッフたちがいる。
僕は脇目も振らずに正面玄関に向かった。
正面玄関からなかに入り、受付に行く。
受付には女性がふたりいて、そのうちのひとり、目が合った女性に声をかけた。
髪をうしろでひとつに束ねた、穏やかそうな物腰の女性だ。
「……あの、ここに千鳥夢さんというかたが入院していると思うんですが、病室を教えていただくことはできませんか?」
訊ねると、女性は眉を下げて申し訳なさそうな表情を作った。
「申し訳ありません、こちらでそういった個人的な取次は行っておりません」
早々に断られたが、想定通りだ。
僕は続けて、用意しておいた手荷物を掲げて女性に見せる。
「その……入院の荷物を届けに来たんですけど、どうにかなりませんか。取り次いでもらえれば、分かると思うんですけど」
懇願するようにもう一度頼み込むと、受付の女性は、そばにいたもうひとりの受付の女性と困ったように顔を見合わせた。
「申し訳ございません。ですから……」
再び断られそうになったそのとき、背後から声が飛んできた。
「――ねぇ。あなたって、さくらの森の学生さんよね?」
振り返ると、スクラブ姿の女性が立っていた。看護師だろうか。
「あの……?」
困惑気味に女性を見ると、女性は柔らかく微笑んだ。
「あぁ、いきなりごめんね。夢ちゃんの名前が聞こえたから、つい」
「え、あの……もしかして、千鳥さんをご存知なんですか?」
驚いて女性に訊ねる。ようやく、女性の情報が視界から入ってきた。
歳は蝶々さんと同じくらいだろうか。細身で垂れた目元が印象的な、きれいな女性だ。
「あなた、もしかして夢ちゃんのお友だち?」
訊ねられ、唇を引き結ぶ。
彼女が言っている『夢ちゃん』という女性が桜のことかは分からない。
だが、この機会を逃してはいけない。そう、心が言っていた。
「はい」
頷くと、女性は優しく微笑んだ。
「私、奈良美和子」
「奈良……?」
「ねぇ、よかったら少し話さない?」
「あ、はい。ぜひ」
それから、僕たちは休憩スペースに移動すると、空いていたテーブルに向かい合って座った。
「これどうぞ」
奈良さんは涼太によく似た笑みを浮かべ、僕にお茶のペットボトルを差し出した。
「あ……ありがとうございます」
「実はね、私の息子もさくらの森の一年生なのよ」
その瞬間、女性の顔と僕の知り合いの顔が勝手に照合された。
「それってもしかして、奈良涼太くんですか!?」
「あら、息子を知ってるの?」
奈良さんは驚いた顔をして、僕を見つめる。
「はい。友だちです!」
なんと、彼女は涼太の母親だった。まさかこんなところで会うとは思わず、驚愕する。
そういえば、涼太は以前、母親は結賀大学附属病院に勤めている看護師だと言っていた。
「で、どうしたの? 夢ちゃんのこと知りたがってたみたいだけど」
差し出されたペットボトルを受け取りながら、僕はさっそく話を始める。
「あ……その、ここに入院してる千鳥さんに会いたくて。千鳥さん、最近学校に来れてないから」
正直に告げると、奈良さんはしばらく僕をじっと見つめてから、低い声で訊いた。
「……わざわざ、病院まで?」
ごくりと息を呑む。
「……そう、ですけど」
奈良さんは怪訝そうな顔のまま、僕をじっと見つめる。
「……そう。錦野くんは、夢ちゃんとはどういった関係なの?」
「……友だちです」
こういうとき、恋人ですと言えたら話は早かったのだろうけれど、残念ながら今の僕は、彼女とはなんの関係もない。
「……あの、彼女に込み入った事情があるのは分かってます。分かった上で聞いてます」
沈黙が落ちる。しばらくしてから、奈良さんが口を開いた。
「……私ね、彼女の担当看護師だったの」
「えっ」
さすがに声を抑えられなかった。
「彼女が病棟を移る関係で、私が彼女を担当していたのは二年前までだったから、それ以降の彼女については詳しくないのだけど……」
「……あの、彼女はなんの病気だったんですか?」
「先天性心疾患よ。幼い頃から入退院の繰り返しで、学校にもほとんど行けなくて……いろいろ我慢ばっかりしてきたはずなのに、文句ひとつ言わない優しい子でね」
奈良さんは懐かしそうに、すっと目を細めている。彼女とはかなり親しい仲だったのだろうか。
「……あの、千鳥さんはなんで病室を移動したんですか?」
「それはね、移植のためよ」
「移植?」
「そう。ドナーが見つかったってことで、その準備のために病室を移動することになったの」
――移植。
なんとなく、僕のなかで点だったものが線になったような気がする。もしかしたら、彼女が僕に名乗った『桜』という名前は、彼女に臓器を提供したドナーの名前なのかもしれない。
「でも、高校に通ってるって聞いて驚いたわ。そっか……元気になったのね、夢ちゃん」
奈良さんは、土にじわっと染み込んでいく水のように、ゆっくりと表情を変えた。心から安堵した顔だった。
けれど、僕の心は暗いまま。
なぜなら彼女は別れ際、じぶんはもうすぐいなくなると言っていたのだ。奈良さんの話が事実なら、移植は既に済んで、元気になっているはずなのに。
「……あ、それでね。彼女の今の病室は、実は私も知らないの。その代わり、彼女の担当の先生のところに案内するわ。彼女の許可が取れれば、会わせてくれると思うから」
「本当ですか!?」
奈良さんの提案に、僕は前のめりに礼を言う。
「ありがとうございます……!」
「……あなた、夢ちゃんのこと大好きなのね」
ハッと、息が漏れた。
僕は一度唇を引き結び、顔を上げる。
「……はい。好きです」
はっきりと頷くと、奈良さんはわずかに目を見開いて、そしてふっと笑った。
「そっか」
その後、僕は奈良さんに案内され、国立科学研究所――通称ラボと呼ばれる施設に入った。
桜が入院しているのは大学病院の病棟ではなく、研究所のほうらしい。
その施設はガラス張りの五階建てになっていて、僕はまるで近未来に迷い込んでしまったかのような錯覚を覚える。
僕はドキドキしながら奈良さんとエレベーターに乗り込んだ。奈良さんは慣れた手つきで五階のボタンを押す。
そうして僕たちがやって来たのは、『研究室1』というプレートがかけられた部屋だった。
奈良さんは扉を控えめにノックして、
「先生、いますか」
と、声をかける。すると、すぐに「どうぞ」という返事が返ってきた。どこか聞き覚えがあるように思えて、僕は小さく首を傾げる。
奈良さんは僕を一瞥してから、ドアノブを回し、なかへ入った。僕も続く。
「失礼します」
室内は広過ぎず、狭過ぎず。
扉の正面の奥の壁には、一面大きな楕円形の窓がはめこまれ、その先には見慣れた街の景色が広がっていた。向かって左手の壁は、一面本棚だった。難しそうな分厚い本がみっちりと詰め込まれている。
入口の扉近くには、応接用の三人がけのソファとテーブル。さらにその横には、大きめの観葉植物があった。
すんと鼻から空気を吸い込む。
入ったときに思ったが、ほんのりといい香りがする。
応接用ソファの脇に置かれた観葉植物を見る。あれだろうか。少し心が落ち着いた気がする。
そして、窓の手前にはデスクがひとつ。書類や医学書やらが雑多に積み上がっていて、その部分だけはとてもきれいとは言えない。
さらに視線を流すと、右手に『仮眠室』と書かれたプレートがかけられた扉があった。
灰色の扉を眺めていると、おもむろに扉が開いて、白衣姿の女性が顔を出した。
「美和子? どうしたの急に――」
仮眠室から出てきた女性は、僕を見るなり固まった。
果たして僕も、
「……え」
顔を出した女性を見た瞬間、声が漏れた。
扉から現れたのは、蝶々さんだった。
「……しおちゃん?」
蝶々さんは目を丸くして、僕の名前を呼ぶ。
僕のほうも戸惑いを隠せないまま、ただ蝶々さんを見つめる。頭のなかは、パニックになっていた。
どういうことだ? 奈良さんは、桜の担当医の場所へ僕を案内してくれたはず。ということはつまり――蝶々さんが、桜の担当医?
「あれ? もしかしてふたり、知り合い?」
僕たちの反応を見た奈良さんが首を傾げる。
「あぁ、うん。この子、私の甥っ子なの。それより美和子、どうしてしおちゃんとここに?」
蝶々さんは戸惑いつつ奈良さんに説明してから、訊ねた。
「実は、この子が夢ちゃんに会いたいって言うから、案内したのよ」
「夢ちゃんに?」
蝶々さんは奈良さんから僕へ視線を戻す。
「しおちゃん、もしかして……」
なにかを察したらしく、蝶々さんはこめかみを押さえたままため息をついた。
「……分かった。とりあえずそこ座って。美和子も。今、珈琲淹れるわ」
蝶々さんが応接用のソファを指す。
僕は放心しつつも、大人しくソファに座った。一方で奈良さんは、仕事中だからとお茶を断って仕事に戻っていった。
ふたりきりになると、僕は珈琲メーカーの前に立つ蝶々さんの背中に訊ねた。
「あの……蝶々さんは、千鳥夢さんっていう女の子のこと、知ってるんですか」
それまで珈琲を淹れていた蝶々さんの手が、ぴたりと止まる。
「……うん。私の患者さんだった子だからね」
蝶々さんは、振り向かないまま答えた。
「だった……?」
不穏な言い回しに眉を寄せる。
「あの子が行きたいって言った高校、しおちゃんと同じ学校だったからね、もしかしたら接点ができるかもとは思ってたんだけど……そっか。そうだったんだ」
蝶々さんは、ひとり納得したように頷き、僕のほうへ振り返った。
「しおちゃんはあの子のこと、どこまで知ってる?」
訊ねられ、僕は正直に知っていることを話した。
この病院に入院していること、半日だけ学校に来ることを許されていること、そして、なぜかは分からないけど、名前をふたつ持ってるということ。
「あと……じぶんはもうすぐいなくなるって、このあいだ言っていました。だから、僕の気持ちにはこたえられないって」
蝶々さんは動かしていた手を止め、息を吐く。
「……そっか」
蝶々さんは一度目を伏せてから、静かな声で話し始めた。
「……そうね。どこから話したらいいか分からないけど……とりあえず、しおちゃんはあの子のことを、どっちの名前で呼んでる?」
「……桜って呼んでます。彼女が、そう呼んでほしいって言ったから」
「……そっか。じゃあ、桜ちゃんじゃなくて、夢ちゃんの話からするね」
「夢ちゃんの、ほう……?」
ここでわざわざ呼びかたを分けたということは、実際に千鳥夢というひとがいるということなのだろう。
「夢ちゃんはね、今年の春に亡くなったの。臓器移植が間に合わずに」
僕は眉を寄せて、蝶々さんを見つめた。
「桜ちゃんはね、夢ちゃんのドナーだったのよ」
「桜が、ドナー……?」
臓器移植を待つ側だったのではなく、桜が、臓器を提供する側だった?
「で、でも、心臓のドナーって、脳死のひととかがなるものなんじゃ……」
「そうね。今の医療では、そう。でも、ここは研究所だからね。ふつうじゃない治療も行われる」
蝶々さんの顔に翳が落ちる。僕は息を呑んだ。
「ふつうじゃない治療って……まさか、生きているひとの心臓を移植しようとしてたんですか……? なんで? だってそんなことをしたら桜は死んじゃうし……」
というかそもそも、そんなことをしたら犯罪だ。
心臓移植とは基本的に、死んでしまったひとや脳死状態のひとから行うもの。腎臓移植などと違って、心臓はひとりの身体にひとつしかないからだ。その心臓をだれかにあげてしまったら、必然的にあげたほうは生きていられなくなる。
僕は弾かれたように立ち上がった。
「そんなの、ひと殺しといっしょじゃないですか! なんでそんなこと……!」
「落ち着いてしおちゃん。違うよ、ひとの生命を救うのが医療なんだから、健康なひとの臓器をだれかのために利用するなんてこと、ぜったいにない」
思わず詰め寄る僕を、蝶々さんは慌てて宥める。違う、というひとことに、僕は心からホッとした。
「……そう、ですよね」
全身から力が抜けていく。
そうだ。そんなの有り得ない。
そもそも彼女の家族が許すはずがない。桜の家族がどんなひとたちかは知らないけれど、桜はお姉さんのことをとても慕っているようだった。
少し考えれば分かることだった。
冷静になりたいのに、激しく鳴り続ける心臓は収まりそうにない。
「でも、じゃあなんで生きている桜がドナーになるんですか」
「……それは」
蝶々さんは苦しげに眉を寄せて、言葉を呑み込む。
「桜ちゃんは、特別な子だったから」
「特別な子……?」
どういう意味だろう。
「……ごめんね。これ以上は、言えないわ」
蝶々さんが目を伏せる。突然線引きをされ、僕はたまらず蝶々さんに食い下がる。
「ちょっと待ってください。もっと彼女のこと、教えてください」
食い下がる僕に、蝶々さんは首を振る。
そんなの困る。これでは、ただ疑問が増えただけだ。このまま引き下がるわけにはいかない。こんな中途半端なところで引いてたまるか。
「教えてください。僕は興味本位で聞いてるわけじゃない。移植をしなくてよくなったのなら、なんで彼女は今も入院してるんですか? ……なんで彼女は、もうすぐいなくなっちゃうなんて言ってるんですか?」
詰め寄ると、蝶々さんは苦しげに唇を引き結んだ。
「……知っても、どうにもならないよ。しおちゃんが辛いだけ」
「それでもいいです。辛くても、後悔するよりいい」
僕は頭を下げるが、しかし、蝶々さんは口を閉ざしたままだった。
「踏み込まなかったことを、後悔したくないんです。蝶々さんみたいに」
僕の言葉に、蝶々さんは少しだけたじろいだ。けれど、かまうもんか。気持ちが大事だと言ったのは、蝶々さんなのだ。
この街に来た頃僕は、ひととかかわる気なんてこれっぽっちもなかった。面倒だし、だれかを傷付けたくないし、傷付けられたくもなかったから。……だけど。
僕はぐっと拳を握る。
今は、違う。今は、変わりたいと思っている。
間違えたと気付いたときはどうするべきか。転んだときは、どうするべきなのか。
気付きや後悔は成長の証なのだと、彼女が教えてくれたから。
子どもだって知ってることを、すっかり忘れていた僕に。
「僕は……桜のおかげでいろんなことを思い出せました。花の色とか生き物の温度とか、匂いとか。当たり前のことだけど、見落としてしまいがちなこと、たくさん……思い出せたんです」
途中から、声が震えていた。
仔猫が小さくてふわふわしているということも、お弁当が美味しいのも、虹が儚いものだというのも。
この世のすべてが当たり前なんかじゃないということを、桜が教えてくれた。
僕の考えがだれかにとっての当たり前じゃないということ。だれかの考えが、僕のなにかを変えるかもしれないということ。
桜が、この世界の広さを教えてくれた。ひととかかわることの楽しさを思い出させてくれた。
蝶々さんは、僕の訴えを遮ることなく静かに聞いていた。
「……最近、しおちゃんはすごくいい顔するようになったなって思ってたんだ。桜ちゃんのおかげだったのね」
そっか、と蝶々さんは何度も呟いて、目元を拭った。泣いているようだった。
「……分かった。だけど、約束して。これから話すことはぜったいにだれにも話さないって」
これから聞くことは、それだけ重要なことなのだと、蝶々さんの目を見てはっきり感じる。だからといって、逃げる選択肢は僕にはなかった。
「……分かりました」
僕は力強く頷いた。
***
桜の病室は、蝶々さんの研究室と同じ五階にあった。
眩しいほど白い廊下に、人気はない。病院独特の匂いもなく、どちらかというと薬品の匂いのほうが強かった。
僕たちは、お互い黙ったまま廊下を進んだ。
蝶々さんが、とある扉の前で足を止めた。扉の横には、『立ち入り厳禁』という文字。
蝶々さんは扉を開け、なかに進む。
蝶々さんに続き、僕もおそるおそるなかに足を踏み入れる。
扉の先には病室があるものだと思っていたが、違った。さらに廊下が続いていた。窓はなく、薄暗い。
僕は蝶々さんのあとに続く。
再び蝶々さんが足を止め、向きを変える。つられるように僕も足を止めた。
壁際にネームプレートがある。『001』という数字が書かれているだけで、桜の名前らしきものはないが、蝶々さんはそのネームプレートを見て、
「ここが桜ちゃんのお部屋よ」
と言った。
僕の目の前には、大きなはめ殺しの窓ガラスがあるだけだった。
向こう側にはカーテンが備え付けられているが、今は開け放たれていて、なかがよく見える。
窓の向こうには、さっぱりとした病室が広がっていた。テレビドラマでよく見る無機質な病室そのものだ。
ここが、彼女の部屋らしい。
彼女の部屋ならば、てっきりもっと騒がしい……というか、もっと彼女の好きなものであふれているものだとばかり思っていたのだが。
病室の中央には、白いベッドが見えた。
いやに清潔そうなその白色が視界に入った瞬間、どきん、と心臓が大きく跳ねた。
震えそうになる足をおそるおそる踏み出して、窓ガラスに近付く。
僕の目に飛び込んできたのは、青白い顔でベッドに横たわる桜だった。
「桜……!」
思わず窓に手を付き、名前を呼ぶ。
ベッドの上の桜は、苦しそうに顔を歪め、胸は大きく上下していた。
最後に会ったとき、彼女は歩くことすらままならぬように見えた。
「……あの、蝶々さん。今、桜と話すことはできますか」
蝶々さんは僕の覚悟を受け取るように頷くと、扉を開けてくれた。
「……ありがとうございます」
そして、僕は桜の病室に足を踏み入れた。ゆっくりとベッドに近づく。
「……桜」
枕元に寄り、そっと声をかけると、桜はゆっくり目を開けた。
「汐風くん……?」
桜は僕を見て、目を見開く。
「……なんで、君がここにいるの」
目を見開いたまま、桜は呟くように言う。
「えっと……ごめん、いきなり。桜ともう一度ちゃんと話がしたくて、蝶々さんに入れてもらったんだ。……あ、そうそう。君がいつも話してた先生ってさ、実は僕の叔母だったんだ。知ったときはびっくりしたよ」
黙り込んだままなんの反応もない桜に、僕はそのまま話し続けることができず、口を閉じる。僕たちのあいだに、重く深い沈黙が横たわる。
緊張で、じぶんの心音がどくどくと鳴っているのが分かった。
会話って、こんなに難しかったっけ。相槌がないと、話すのってこんなに緊張するものだったっけ。
そっか。桜との会話は、いつだって和やかで楽しかったから、忘れていた。
いつもの彼女といるときではぜったいに有り得ない沈黙が落ち、僕は唇を噛み締める。
「……聞いたの? 私のこと」
「……うん」
その瞬間、桜の顔が歪んだ。
「帰って!」
桜は僕を拒絶するように背を向ける。いつも明るい彼女が声を荒らげるのは、初めてだった。
「待って、桜」
思わず桜の肩に触れると、彼女は僕の手を振り払った。
「触らないで! 私のこと知ったんでしょ。私が……ひとじゃないって、聞いたんでしょ!」
息を呑んだ。かける言葉が見つからなかった。
「なんでそんな余計なことするの……? 私……君には知られたくなかった。君にはふつうの女の子だって思われたまま、いなくなりたかった。気持ち悪いって、思われたくなかったのに……」
そう言うと、桜は目から大粒の涙を落とし始める。
桜に弾かれた手は、まだ痺れていた。
痛い。でも、きっと桜はこれまでこの何倍もの痛みに耐えて続けてきたのだろう。
じぶんの出自に。勝手に背負わされた運命に。最愛のひとを守れなかった悲しみに。それでも生きているじぶん自身に。
こんな小さな身体ひとつで、耐えていたのだ。
僕は、ついさっき蝶々さんから聞いた話を思い出す。
蝶々さんは、覚悟を決めた僕に桜のことをすべて話してくれた。医学的なことは僕にはよく分からないから、僕でも理解できるように、噛み砕いて。
結論から言うと、桜はふつうのひとではなかった。
――医療用クローン。
桜は、千鳥夢という少女のDNAから人工的に生み出されたヒトクローンだったのだ。
研究については、国から依頼を受けて始まったものだという。しかし、この国では法律上、ヒトクローンの研究は禁止されている。
政府はあくまで、クローンの臓器を移植に利用するためにヒトクローンの製造を内密に許可したのだという。
『臓器……移植』
桜がドナーだったという話に近づき、僕は息を呑む。
『ねぇ、しおちゃんは今、この国でどれだけのひとが移植を待っていると思う?』
桜のことを話すなかで、蝶々さんが不意に僕に問いかけた。
知らなかった僕は首を振る。
『この国で移植を待つ患者は、一万五千人以上いる。対して実際に移植が叶うのは、年間四百人あまり』
一万五千人中、四百人。
年間、移植が必要なひとが何人増えているのかは分からないけれど、圧倒的に分母が少ないことだけは、僕でも理解できた。
『それじゃあ、ほとんどのひとが移植をできていないってことですか?』
『そう。今、ほとんどの患者はドナーが見つからないまま、亡くなってるの。その問題の解決策として、政府は水面下で医療用クローンの研究を始めた。体細胞クローンの開発が可能になれば、患者自身の体細胞から複製した臓器を、安全に患者の疾患臓器と取り替えることができる。それは、圧倒的に臓器が足りていないこの国では、まさしく希望なの』
それで生み出されたのが桜なのだと、蝶々さんは言う。
しかし、現在の技術では、患者の細胞から臓器のみを複製することはできない。そのため臓器の器となるヒトクローンそのものを生み出す必要があり、その唯一の成功体が桜だった。
患者自身の体細胞から作った新品の臓器を、じぶんの弱ってしまった臓器と置き換える。
もともとじぶんの細胞であるため拒否反応もなく、ドナーを待つもどかしさもない。
ドナー待ちの患者にとったら、これ以上ない夢のような治療法。
たしかにそうかもしれない。
――けれど。
そんな話、到底納得できるわけがない。
『そのために桜が犠牲になるなんて、そんなのぜったいおかしいよ……! 心臓移植なんかしたら、桜は死しんじゃう。桜は人形じゃない。実験動物でもない。僕たちと同じ感情がある、命があるひとじゃないの!?』
蝶々さんは僕の叫びを受け止め、頷く。
『うん……そうだね。クローンを人間の勝手な都合で生み出して利用するのは間違ってる。だけどそれは、当事者たちから言わせれば、ただの理想でしかないのも事実』
悔しさのあまり、僕は強い口調で『そんなことない』と言おうとした。が、それより先に、蝶々さんが僕に言う。
『じゃあしおちゃんは、もし桜ちゃんが心臓の病気になって、彼女を助けるためにはクローンを作って臓器を移植するしかないってなったら、どうする?』
『えっ……』
言葉に詰まった。
『いつ現れるか分からないドナーを待っていたら、桜ちゃんは間違いなく死ぬ。だけど、クローンを使えばもしかしたら助かるかもしれない。もしその立場になったら、しおちゃんはどうする?』
僕は、蝶々さんの問いに答えられなかった。
『私は、夢ちゃんのことも桜ちゃんのことも同じくらい大好きで、大切だった。どっちも救いたかった。だけど、現時点で医療は万能じゃない。私たちは、神さまにはなれない』
分かっていた。
蝶々さんは医師として、一生懸命生きようとしている患者や桜を助けたいだけ。
だけどそれが……だれかを助けることが、ほかのだれかを犠牲にするかもしれないだなんて、考えたこともなかった。
きれいごとを言っていたのは、僕のほう……?
『しおちゃんは、トリアージって知ってる?』
聞いたことはある気がするが、意味は知らない。僕は首を横に振る。
『救命の現場で多くの負傷者がいたときはね、いのちの選別をするの』
『いのちの、選別?』
『多くのひとを助けるために、現場の状況や医師の数、その他の条件を考慮して、確実に助けるために、助けるひとに優先順位をつけるの』
――優先順位。
『助けを求めているひとがたくさんいるとき、たとえばとても重い症状のひとがいたとする。だけど、そのひとを診るには時間があまりにもかかり過ぎる。そのあいだに助けられるはずのひとが、死んでしまう。そんなことにならないように』
『じゃあ……治療に時間のかかる重症患者は、見殺しにするってこと?』
『言葉は悪いけど、そう。いのちを救うことは、時と場合によっては犠牲が伴うことがある』
『そんなの不平等だよ』
『そのとおりよ。だけど、私たちの手はふたつしかないし、できることもかぎられる。このふたつの手で、より多くのひとを助けるにはどうすればいいか、考えて決断しなきゃいけない』
『…………』
『もちろん、私たちはその選択を是とも非とも言わない。結果の判断をしていいのは、当事者だけだと思ってる。見方は、ひとによって変わるから。助かったひとは是だと言うし、犠牲になったひとたちは非と言う。難しいことを言うようだけど、なにかを選べばそこには必ず不平等が生じるの』
死を前にした人間は、なににでも縋るだろう。ハイリスクだろうが、なにかを犠牲にしようが、みんな、少しでも長く生きられるほうを選択する。たとえそれが、倫理的に間違っていたとしても……。
それを責めることが、果たして僕にできるだろうか。僕が彼らと同じ立場になったら、僕も同じ行動をするのではないか。
『死って、物語ではよく神聖化されていたり、ロマンスの要素に使われたりするけれど、本当はね』
――ただただ悲しいだけ。
蝶々さんは苦しげに顔を歪ませる。
『……それからね、もうひとつ』
最後、蝶々さんは僕に言った。
『あと一ヶ月なの』
僕は目を伏せる。
『……なにが、ですか』
聞きたくなかった。だけど、聞かなければいけなかった。この闇へ踏み込んだ僕には、その責任があった。
『桜ちゃんの、余命』
僕は、何度目か分からない目眩を覚えた。
クローンの研究はまだまだ課題だらけで、特にいちばんの大きな問題が短命であることだという。
理由は、短期間で大人と同じ大きさにまで成長させなければならないため、臓器の機能は大人と同じ大きさになっても子ども以下で、移植したとしても長くは持たないらしい。
蝶々さんの話は、僕には現実味がなさすぎて、ほとんど理解が追いつかない。
そんな僕に追い打ちをかけるように、蝶々さんはさらに言った。
――クローンは、ふつうの食事ができないのだと。だから桜はこれまで基本的に点滴で栄養補給をしていたのだと。
『……それって、どういうこと? もし、桜が食事をしたらどうなるの』
『臓器はすぐに劣化して、短命な命をさらに儚いものにするだろうね』
銃の引き金を引かれたような心地だった。
だって。
僕はこれまで彼女と、何度も食事をしている。
サイダーをあげた。お弁当のおかずもあげた。それだけじゃない。お弁当交換をして、デートのとき、オムライスを食べたりもした。
つまり、僕は。
これまでの僕の行動は、桜の命を……。
突き付けられた現実に、僕は愕然とする。
『桜は……僕のせいで死ぬの?』
じぶんの声なのに、やけに遠くに聞こえる。
頭を抱えた。なにから考えたらいいのか、もはやなにを考えていいのかすら、分からなくなる。とりあえず分かっていることは、僕が桜の命を奪っていたという事実。
『桜は……桜は』
声が震え出す。
『落ち着いて、しおちゃん』
『だって、だって……桜にお弁当をあげたのは僕だ。オムライスだって、ケーキだって……僕のせいで……桜は』
『しおちゃん、落ち着いて』
『僕が桜を殺すんだ!』
取り乱す僕を、蝶々さんが何度も呼ぶ。
『桜ちゃんはね、施設外での飲食が禁じられていること、その理由、ぜんぶちゃんと知ってた。分かったうえで破ったの。それがどういうことだか、しおちゃんは分かる?』
『僕が、なにも知らずに一緒に食べようって言ったから』
込み上げてくる涙をこらえながら言うと、蝶々さんははっきりとした声で『違うよ』と否定した。
蝶々さんが僕の話を否定するのは、これで二度目だ。
『きっと、桜ちゃんは知りたかったんだと思う。しおちゃんと同じものを見て、食べて、感情を共有したかったのよ』
『共有……?』
僕は涙を拭うこともできぬまま、呆然と蝶々さんを見る。
『桜ちゃん、お姉さんを亡くしてからずっと塞ぎ込んでたから……。でも、ある日突然、とても性格が明るくなって、いろんなことに興味を持つようになったの。夢ちゃんが亡くなって、少しした頃。ちょうど、しおちゃんがこの街に来た頃よ』
『……でも僕と出会わなかったら、桜はもっと生きられた』
蝶々さんは、
『たしかにそうかもしれない』
と言いつつ、けどね、と続ける。
『桜ちゃんはしおちゃんに出会って、初めてじぶんの人生を生きたんだと思う。生きるってね、ただ毎日を淡々と過ごすことじゃないよ。じぶんで考えて、じぶんの意思で選択する。好きなひとと好きなことをして、好きなものを食べて……そうやっていろんなことを学んで、いろんな可能性をじぶんで選択していくこと』
『でも』
膝の上に置いた手をぎゅっと握り込む。その手を、蝶々さんが優しく握った。
『しおちゃん。ひとはみんな、いつかは死ぬよ。私も、しおちゃんも。生まれてすぐ亡くなる子だっているし、死ぬことは特別なことなんかじゃない』
分かってはいても、僕の頭はどうしたって、もし、を考えてしまう。もし、僕が余計なことをしなければ。僕とさえ出会っていなければ。
黙り込んでいると、蝶々さんは続けた。
『しおちゃん。私にはもう、ふたりに時間を作ってあげることしかできない。だから、後悔しない選択をして。……ただ、しおちゃんがどんな選択をしたとしても、これだけは忘れないで。しおちゃんとの時間を選んだのは、桜ちゃん自身。彼女の意志だよ。だから、責めないで』
頭のなかは、真っ白だった。
僕は、どうするべきなのだろう……。
蝶々さんは椅子から立ち上がり、窓際へ向かう。
『お別れの選択肢があるっていうのは、贅沢なことだよ』
そうかもしれない。だけど、いきなりそんなこと言われて、受け入れられるわけがない。
虚しさが胸いっぱいに広がって、僕は唇を噛み締める。
『……蝶々さんは、しょせん他人だ』
窓に目を向け、街の景色を眺めていた蝶々さんが振り返る。
僕が言い返すとは思わなかったのだろう。少し驚いたような顔をしている。
『だってそうだろ。蝶々さんは、当事者じゃないからそんなこと言えるんだ。蝶々さんがもし僕の立場だったら、もし僕と同じ年齢で、同じ状況で当事者になってたら、冷静にお別れしようなんて思える!? 彼女は僕のせいで死ぬかもしれないのに!』
蝶々さんは苦しげに目を伏せる。
こんなの、八つ当たりだ。蝶々さんはかつての後悔を踏まえて、僕に助言してくれているのに。
……でも、だからって。大切なひとの死を受け入れるなんて……そんな選択、僕にはできない。僕はまだ、そんなに大人にはなれない。
『……そうだね。ごめんね』
蝶々さんはそれだけ言って、部屋から出ていった。
ひとりきりになった僕は、屋上に足を向けた。無感情のまま、フェンスに作られた蜘蛛の巣を眺めていた。
蜘蛛の巣には、蝶が引っかかってしまっている。蝶は逃げようと、必死にもがいていた。
僕はよろよろと立ち上がって、フェンスによじ登った。
蝶の胴体部分を掴み、蜘蛛の巣から剥がしてやろうとして、手を止める。
この蝶を助けることは、果たして正しいことなのだろうか。
今、僕がしようとしていることは、この世の理に反した行動なのではないだろうか。
蜘蛛は生きるために蝶を捕食するだけであって、いたずらに殺すわけではない。
生きるために、殺すのだ。
僕が蝶を助けたら、蜘蛛が餓死するかもしれない。でも、このままでは蝶は間違いなく蜘蛛に喰われて死ぬ。だけど、だけど……。
力なく、蝶から手を離す。蜘蛛の巣がゆらゆらと揺れた。
僕は、どうしたらいいのだろう。
桜は、夢という少女を救うために生み出された。
この方法が病気のひとたちにとっての救いであることは、理解できる。
理解できてしまうからこそ、辛い。
正しい選択って、なんなんだろう……。
考えていると、ふと彼女の声が脳内に響いた。
『――辛くない?』
いつか、彼女と交わした会話だ。
入院生活でふつうの生活を知らない彼女に、僕はついそう問いかけたのだ。
だけど、彼女はこう答えた。
『私、生まれたときからずっとこの生活だから、これが私にとっての当たり前だし。よく分かんないや』
あのとき、僕はそんなふうに答えた彼女を不憫に思った。
じぶんの境遇をほかと比較することすらできず、疑問すら抱いていない彼女を、哀れだと思った。
……だけど。
比べることになんの意味がある?
『私たち、もう友だちでしょ?』
『俯きそうになったら、桜の木を探してみて! 桜の花を見ようとすれば、顔を上げられるから!』
『学校に通ってみたくなったから転校してきたの。見てみてこの制服! どう? 似合う?』
……そうだ。
彼女の、なにが不憫だというのだろう。
彼女のなにが間違っているというのだろう。
僕はこれまで、彼女ほど生きることとまっすぐ向き合っていたひとを見たことがない。
彼女は、僕なんかより精一杯生きている。
僕がこうして彼女の生い立ちを嘆くことは、彼女の生きてきた人生をまるごと否定することになるのではないか。
少なくとも僕は、彼女に出会って変わっている。
僕のなかには今、ふたつの感情がある。
これ以上、深入りするべきではないという想いがひとつ。彼女の特別になることは、必ず死が待つ彼女には残酷なことだからだ。
もうひとつは、彼女を諦めたくないというわがままな想いだ。
どちらもきっと正しくて、間違ってる。だから、どちらも捨てる必要はないのだ。僕が選べばいいだけ。そうしたいと思うほうを。
もう一度立ち上がる。
蝶を蜘蛛の巣から剥がすと、羽根に絡まった糸を丁寧に取ってやる。
そして、青々とした空へ放った。
蝶が大きく羽ばたき、飛んでゆく。太陽へ向かって、まっすぐに。
フェンスから飛び降りると、僕は屋上を飛び出した。
正しさなんて、最初からどうだってよかった。
大切なのは、僕の気持ちだ。僕がどうしたいかだ。
僕は、どうしたい?
もし僕が今、彼女から離れる選択をしたら、桜はどうなるだろう。
きっと、あの殺風景な病室で死ぬまで過ごすのだろう。ひとりぼっちであることを、それすら運命だと受け入れて。
姉を失い、ほかに家族もなく、友だちである僕にも拒絶されて。桜はたったひとりで死ぬ。
『汐風ってすごくきれいな名前じゃん』
『桜になりたい。実を結ばなくても、世界中に愛される花に』
階段を駆け下り、蝶々さんを探した。もう一度彼女に……大好きな桜に向き合うために。
そして今、僕の前には彼女がいる。
涙で滲んだ桜の瞳は、蒼ざめた空のような、澄んだ泉のような、美しい色をしている。
とても人間離れした不思議な瞳だ。
蝶々さんは、クローンである桜には、ひと以外の遺伝子も組み込まれていると言った。
たとえば、クローンの臓器や角膜は、特定の光を当てると光るようになっているらしい。
それは、ひととクローンを確実に見分けるためだという。この先クローン臓器の移植が法律で認められた場合、救命の現場で患者の臓器が移植されたものかどうかを判別するためだとか。
だから、桜の瞳は不思議な色をしていたのだ。
僕と違う色の瞳。
だけどそれを、
「気持ち悪い、なんて思わないよ」
「うそ」
桜は、涙で潤んだ瞳できっと僕を睨む。
「本当だよ。たしかに、話を聞いたときは驚いたけど……気持ち悪いなんて思わない。だって、君は君だよ」
心からの言葉だ。
「……ねぇ君。今、じぶんがどんな顔をしてるか、気付いてる?」
「え……」
桜は、僕の問いに戸惑いが滲んだ声を漏らす。
「僕ね、君が僕に声をかけてくれたときのこと、今になってなんとなく理解できた気がするんだ」
たぶん、放っておけなかったのだ。僕が今の彼女のような、拠り所のない顔をしていたから。
「だけど僕はさ、あのとき君が僕にしてくれたように、純粋に君を助けたいって気持ちだけで動いてるわけじゃない。僕は君のことが好きだから、そういう気持ちで動いてる」
「私は……」
桜が苦しげに声を漏らす。
「だから、桜が僕を拒むのは間違ってない。僕の気持ちにこたえられないことに傷付くのは、桜だから。それに僕も、君を傷付けてることを自覚してる。それでも、僕はじぶんを貫く。君のそばにいたいから」
電話の向こうの凪と久しぶりに話をした、あの日のことを思い出す。
あの日も今と同じように怖かった。今さら謝ることに意味なんてあるのか。そもそもあっちは、僕のことなんて覚えてないんじゃないか。
だれかの心に踏み込むのは、暗闇に飛び込むことだ。
拒絶されるかもしれない。じぶんの存在を否定されるかもしれない。
だからみんな、ひととのあいだに線を引く。
だけどそれではダメなのだ。
あの日があるから、僕は今、凪と話すことができている。あの日がなければ、僕と凪は二度と交わることはなかっただろう。
凪と仲直りしてから、僕たちは毎日のようにメッセージや電話のやり取りをするようになった。
同じ学校ではないからこそ相談できることもあって、今では凪のいない日常は考えられない。
きっと、桜は今、あの日電話をかける前の僕なのだ。
「……僕、桜に会うまではなにごとにも無関心になってた」
だれかといると、ぜったいに衝突するから。またあのときのように、いじめられたくなかったから。
だから意地を張って、ひとりでいた。
でも、実際はぜんぜんそんなことはなかった。無関心でいることなんて、できやしないのだ。
桜は、未だに僕を睨んでいる。でも、僕の話を遮ろうとはしなかった。
「だけど桜は、そんな僕を受け入れてくれた。僕みたいな、陰キャで、ぼっちの僕を」
だから、僕も受け入れたい。
「……桜は僕のこと、おかしいって思う?」
ぴくり、と桜の肩がわずかに上下する。
「……汐風くんはそんなことないよ」
「でも、僕はずっとおかしいって言われて、いじめられてきた。それだからじぶんに自信なんてなかったし、最初は桜のことも信用できなかった」
だけど同時に、桜にふつうに話しかけてもらったことに、救われてもいた。
「僕は、君に見つけてもらえたから今ここにいる」
あのとき自覚した。僕は、このひとを求めていたんだと。
「……というか君って、機嫌が悪いとそうなるんだね」
桜はムッとした顔を僕に向ける。
「ん!? どういう意味!?」
「新鮮だなって。僕の知ってる君は、仔猫が好きで、ただの虹に感動して、それから少しお節介で……子どもみたいに笑う子だったからさ」
桜は瞳を潤ませたまま、不貞腐れたように頬をふくらませる。
「……子どもみたいは余計だってば」
「ごめん」
「……幻滅した?」
「まさか。新しい君が知れて嬉しい。君は君だから」
「……なにそれ」
桜がふふっと笑う。
ようやくいつもの桜に戻ってひと安心したのもつかの間、しかし桜は再び顔を曇らせた。
「桜?」
「……でも、やっぱり汐風くんとはもうこれ以上いっしょにいられないよ」
「どうして? 僕は、どんなことでも受け止めるよ」
強い口調で言うと、桜は力なく首を横に振った。
「君はなにも知らないから、そんなことを言えるんだよ」
どこか聞き覚えのある言葉にハッとする。それは、いつか僕が彼女を拒絶したときに放った言葉だった。
思わず苦笑が漏れた。
「……それって、もしかして嫌味?」
「え?」
桜が戸惑いがちに顔を上げる。
「それなら言わせてもらうけど」
と、前置きをしてから僕は桜に告げる。
「君はじぶんの生まれを気にしてるみたいだけど……僕は君が何者かなんてどうだっていいんだ。僕はただ、君が好きだからそばにいたいってだけなんだよ」
桜は目を見張る。そして、気まずそうに僕から目を逸らした。
不貞腐れたような顔をして、それから困ったように俯いた。
鼻をすする音がした。
桜は俯いたまま声を押し殺し、肩を震わせて泣いていた。
「……汐風くんは、どうしてそんなに優しいの」
「……優しくなんてないよ。今まで君が僕にくれたものを返してるだけだ」
それから桜は、ゆっくりとじぶんのルーツを話してくれた。
じぶんが夢のクローンであること、しかし夢が移植直前に亡くなってしまい、じぶんの臓器が用済みになったこと。そのため蝶々さんとラボに移り、ひっそりと入院生活を送っていたこと。
一度蝶々さんから聞いていたおかげで冷静に聞くことができたけれど、桜の口から聞くとやっぱりやるせない思いが胸に広がる。
「……私、お姉ちゃんのこと大好きだったんだ。お姉ちゃんは、私をひとりの人間として見てくれたし、桜っていう名前もくれた。……だから、お姉ちゃんの命になれるなら、私はいくらでも命を差し出すつもりだった」
「うん」
「……でも、私はお姉ちゃんを守れなかった」
私は、お姉ちゃんの命を繋ぐために生まれてきたのに。
そう呟く桜の瞳は、なにも映していない。
「……お姉ちゃんが死んでから、ずっと考えてた。私は、なんのために生まれてきたんだろう。生まれてきた意味あったのかなって」
「……そんなの」
あるに決まってる。
そう、はっきり言いたいのに、喉が張り付いてしまって、言葉がなにも出てこない。
抑揚のない淡々としたその口調は、いつもの明るい彼女の喋りかたとはかけ離れていた。
「……幸せ、なんて言葉、なんであるんだろう」
ぽつりと、桜が言った。
「え……?」
「だってふつう、幸せだったらそんな言葉は生まれないでしょ」
だからきっと、幸せなんてこの世に存在しないの。みんな、『幸せ』って言葉を無理やり当てはめて、じぶんに言い聞かせてるの。私は幸せなんだ、って。
そう、桜は言う。
そうなのだろうか。疑問を抱きながらも、否定する言葉は思い浮かばなかった。
『意味がある。ぜったい』
『君は必要だよ』
頭のなかで、彼女のかつての言葉が何度もリフレインする。
あぁ、そうか。
彼女はずっと、その言葉をほしがっていたんだ。今の彼女には、そう言ってくれるひとがいないから。
「……なんてね。こんなこと言ったら、変なひとって言われちゃうかな」
悲しげに笑うその横顔が切なくて、胸が強く絞られるようだった。
「……ねぇ、汐風くん」
「なに……?」
「やっぱり、私のことはもう忘れてほしい」
唇を噛み締める。
「……それは、できないよ」
「なんで? こんな話、受け入れなくていい。これ以上私といっしょにいたって、意味ないんだから」
「意味はあるよ。僕にはある」
「ないよ」
「君は優しいから、そう言うだろうなと思ってた。だけど僕は向き合うって決めたんだ。君は逃げてもかまわない。だれも責めない。僕も、責めない」
桜は、あのとき笑った。
僕に『忘れて』と言ったとき、桜は泣くこともなく、そう言ったのだ。どんな思いだっただろう。
それを思うだけで、胸がつまる。
「僕は勝手に、君のそばにいるって決めたよ」
「汐風くん……」
「君はどうする?」
「私は……」
桜は声を震わせて、顔をくしゃくしゃにして、言った。
「私は……私は、やっぱり汐風くんといたい……!」
汐風くんと、あたりからほぼ泣きながら。僕もつられるようにして泣きじゃくる。
この選択に、希望がないことは初めから分かっている。
ただ、それでも今は希望が見えたふりがしたい。
「……なんで汐風くんが泣いてるの」
しばらくお互い泣きじゃくって、ようやく泣き止んだ桜が言った。
僕は服の袖で目元をごしごしと拭う。けれど、拭っても拭っても視界は一向に明瞭にはならない。桜は泣き止んだのだから、僕もいつまでも泣いてるわけにはいかないのに。
「仕方ないじゃん。勝手に出てくるんだから」
そう返した瞬間、ハッとした。
つい最近、僕はこの言葉をどこかで聞いた気がする。
どこだっけ……。
『俺だって泣く気なんてなかったよ。でも、お前のこと考えてたら勝手に涙が出てくるんだよ』
……そうだ、凪だ。
凪は僕がふられたことを知ると、じぶんのことのように泣いていた。なんなら、僕のことを置いてけぼりにして泣いていた。
その声に、僕の心は動いたのだ。
これまでずっと、僕はじぶんを冷めた人間だと思っていた。
ひとりでいたほうが楽。ふつうの楽しみなんていらない。興味ない。
そう、思っていた。
でも、違った。目からあふれるあたたかいものが、それを証明している。
だれかのために……いや、好きなひとのためになら、涙はこんなにもあふれるものなのだ。胸はこんなにも、苦しくなるものなのだ。
「ねぇ、桜。僕、考えたんだ。さっき君が言っていた、生まれてきた意味ってものを」
考えたけど、やっぱり正解は分からなかったよ。そう、正直に告げる。すると桜は寂しげに目を伏せた。
「だけど、僕なりの答えは出せたよ」
桜が顔を上げた。
「君は、生まれたときからずっと、お姉さんを助けなきゃって……そう思って生きてきたんだよね」
だけど、助けられなかった。
お姉さんを助けることを使命だと信じてきた桜のその苦しみは、僕にはとても計り知れない。
……だけど。
「君の手は、お姉さんには届かなかったかもしれない。だけど、手を差し伸べてたのは、君だけじゃないと思うんだ」
「……どういうこと?」
桜が困惑気味に窓に近付いてくる。
「君と同じように、お姉さんも君に手を差し伸べてたんじゃないかな。……こんなふうに」
僕は、目の前に立つ桜の手にじぶんの手を合わせる。ぴったりと重なり合う手を、桜は見つめる。
桜は苦しげに顔を歪ませて、僕の手を離した。
「……違うよ。お姉ちゃんを助けるのは私の役目だけど、お姉ちゃんはべつに……」
やっぱり、と思った。
桜はお姉さんの死に自責の念を強く感じている。そして、桜はじぶんも守られるべき側だという概念がない。
ないなら、教えるしかない。僕が。
「桜は、お姉さんを助けられなかったんじゃない。お姉さんに助けられたんだよ」
桜が目を見張る。
「助け……られた……?」
桜は僕の言葉が理解できない子どもみたいに、ぽかんとしている。
「私が……?」
「うん、そうだよ」
桜は、じぶんは守るべき側で、守られるべき側であるだなんて、考えもしなかったのだろう。
桜は、生まれながらにじぶんが姉にとっての特効薬であると思い込んできた。いや、思わされてきた。
こんな閉鎖的な環境で生きていれば、その考えは大抵のことでは覆らないだろう。
「お姉さんは、君を守るために手を伸ばした。そして、じぶんがいなくなったあとは、蝶々さんに託したんだ。ねぇ、桜。お姉さんと過ごしたときのことをちゃんと思い出してみて。桜はずっと愛されてるし、守られてるんだよ。今も、ずっと」
そういうと、桜はまた顔をくしゃっと歪め、泣き顔を作った。その瞳に、みるみる涙の膜が張っていく。
「違うよ……お姉ちゃんは……私のせいで死んだんだよ……」
呟く声は、ひどく震えていた。
「違う。君のお姉さんは、愛する妹を助けたんだ。桜がお姉さんの死をそんなふうに思ってしまったら、お姉さんきっと悲しむよ」
「……お姉ちゃん……」
「お姉さんは、命を懸けることもいとわないほど、君のことを愛してたんだ」
「あい、されてた……私、お姉ちゃんに……っ」
桜は再び泣き出した。今度は、わんわんと声を上げて。
姉の死を受け入れているように見せかけて、しかし本当のところはずっと、その悲しみから目を逸らしていたんだろう。
桜には、お姉さんを失った悲しみを打ち明けられる相手がいない。
どれほど孤独だっただろう。
桜は、姉の死としっかり向き合うこともできないまま、ずっと孤独のなかで生きてきたのだ。
必死に上を向いて、花を見上げてきたのだ。
じぶんのせいで姉が死に、じぶんだけが生きているという現実をその身に背負いながら。
ひとりで抱えるには、少々大き過ぎる荷物だ。
じぶんが何者か、なんのために生まれたのか、生きる意味が分からなくなってしまうのも無理はない。
たしかに桜はふつうとは違うかもしれない。
ふつうのひとは、桜の存在を否定するかもしれない。
だけど、そんなことは僕にはどうだっていい。
僕がどう行動するか、その決定権を持つのは僕だけだ。
だから僕は桜に向き合う。そして、桜にとっていちばん最善の選択をする。
「……ねぇ桜。僕が出した答え、聞いてくれる?」
子どものように泣きじゃくる桜の目元を、僕は指の腹で優しく拭ってから、目を合わせた。
「桜が生まれてきたのはね、お姉さんに愛されるため。蝶々さんに守られるため。……それから、僕と出会うためだよ」
続けて、はっきりとした声で言う。彼女の心に、届くように。
「君と……出会うため……?」
「僕は君と出会って救われた。だから、今度は僕が君を守るよ」
すると、さっきまで泣いていた桜は、今度はくすくすと笑い出した。
「ふふっ……」
「おい……なんで笑うんだよ。ひとがせっかくいいことを言ってるのに」
「ふふっ……ごめん。なんか、らしくないからさ」
桜の顔に笑顔が咲く。ようやく見られた桜の笑顔に、僕はほっと息をついた。
桜は目元を拭いながら、僕に訊ねた。
「ねぇ……汐風くん。私は……生きていてもいいのかな?」
「……当たり前じゃん」
桜は少し顔を俯け、恥ずかしそうに微笑んだ。そして、顔を上げてまっすぐに僕を見た。
「……私、生きたい。気持ち悪いって思われても、みっともないって思われても、生きたい。私は、お姉ちゃんが大好きだったから。汐風くんに……好きなひとに出会えたから」
蒼ざめた深水のような瞳には、ただひとり、僕だけが映っていた。
「錦野汐風くん。私は、汐風くんのことが好きです」
生まれて初めて、受けた告白だった。
嬉しくて、飛び上がりそうになるのを必死でこらえ、負けじと言う。
「僕も、好きです」
桜は心底嬉しそうにはにかんだ。
僕はポケットをまさぐって、あるものを取り出す。
「ねぇ、これ……今度こそもらってくれるかな?」
取り出したのは、あの日突き返されてしまった、黒猫と桜のキーホルダー。
桜はほんの少し申し訳なさそうに、僕の手のなかで揺れるキーホルダーを見つめた。
「つまりその……付き合ってくれませんかってことなんだけど」
桜は一度僕を見てから、手のなかのそれへ視線を移す。そして、僕の手ごと、両手でぎゅっと包み込んだ。
「はいっ!」
桜が笑う。雨が止み、雲の隙間から覗いた太陽のような、とても晴れやかな笑顔だった。
こうして僕たちは、恋人同士となった。