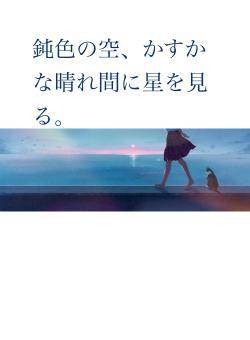凪と仲直りした日から、一週間が過ぎた。
凪とのわだかまりが解消したからといって、僕の日常がなにか変わったかといえば、特段そんなことはない。
ただ、気分はずいぶん変わった。
たとえばずっと背負い続けてきた重い荷物を下ろしたときのような、そんな開放感を毎朝感じるようになった。
制服の袖に通す腕が引っかからなくなったとか、朝食のときのお箸が軽いとか、そんなちょっとしたことだけれど。
顔を洗い、制服に着替えて一階のリビングに降りると、蝶々さんは既にメイクを終えて、家を出るところだった。
「あ、しおちゃんおはよう」
「おはようございます。……もう行くんですか?」
「うん。ちょっと今いろいろ忙しくて。しおちゃん、最近お弁当作れなくてごめんね」
蝶々さんはなんだかこのところ忙しない。
「いえ。うちの購買、結構品揃え充実してるから、毎日お昼休みが楽しみなんですよ。今日はコロッケパンにしようと思って」
「それはそれで寂しいなぁ……」と、蝶々さんは苦笑する。
「もちろん、蝶々さんのお弁当も美味しいですよ。でも、忙しいときは無理しないでください」
正直なことを言えば購買の品ぞろえなんて気にしたことはないし、そもそもコロッケパンだってあるか分からない。けれど、そんなことはどうだっていい。
大切なのは、蝶々さんが気負わずに仕事に集中できるかどうかだ。僕が来る前のように。
蝶々さんは僕の唯一の理解者だから、迷惑だけはかけたくない。重荷にだけはなりたくない。
もしそんな本音を言えば、蝶々さんは怒るだろう。でも、僕はそういうやりかたでしか、ひととうまくかかわれない。それ以外の方法を知らない。
「ありがとう。明日はちゃんと作るから。今日はコロッケパンを楽しんで」
「はーい」
「じゃ、行ってきます」
「行ってらっしゃい」
現在、彼女は結賀大学附属病院のラボという研究機関で研究員として働いているのだが、今年の四月から新たな勤務形態で働き始めたばかりだと聞いた。
僕が高校一年生であると同時に、蝶々さんも職場ではまだ一年生なのだ。いろいろと大変なのだろう。僕も甘えてばかりはいられない。
テーブルの上には、トーストとバター、それからサラダが用意されている。
普段蝶々さんが用意してくれる食事は和食が中心だが、忙しい日は洋食になる。
このことに気付いたのはつい最近だ。今までは、食事の内容なんて気にも止めなかった。というかたぶん、気にする余裕がなかった。
朝食を済ませて時計を見ると、時刻は既に八時前。そろそろ出なければ。
僕は急いで学校へ行く準備を進めた。
その日、いつもと同じ朝だと思っていた僕を待ち受けていたのは、いつもと少し違うそわそわした雰囲気のクラスメイトたちだった。
いったいなにごとだろう、と思いながらも、それを訊ねる友だちはこの教室にはいないので、僕は大人しく席に着く。
せっせと教材を机のなかに移動させていると、とんとん、と指で机を叩かれて顔を上げる。
短髪男子の顔が飛び込んできた。
僕の前の席の男子、奈良涼太だ。
「なぁ、錦野。今日さ、転校生が来るって知ってた?」
「えっ、転校生?」
奈良に話しかけられたことにも驚いたが、それよりも、転校生というワードに驚いた。
「こんな時期に?」
「らしいよ。しかも女子だって」
「……ふぅん」
寝耳に水の話だった。
「どんな子なんだろうな」
「……さぁ」
適当な相槌で返すと、奈良が呆れた視線を向けてきた。
「お前、もう少しひとに興味持てよ」
「べつに、僕には関係ないし……」
「……お前ってさぁ、中学でもそうだったの?」
一瞬、脳内が巻き戻しされて過去のトラウマが蘇った。責められたような気分になり、わずかに怯む。
違う、きっと奈良はただ疑問に思って訊ねただけ。責められてるわけじゃない。引き攣りそうになる口角をなんとか抑えて、奈良を見上げる。
「なにが?」
「……いや、べつに」
奈良も空気を察したのか、それ以上話しかけてくることなく、前を向いた。僕も、なにも気にしていないふりをして鞄から文庫本を取り出し、読書を始める。
読書を始めてもしばらく、僕の心臓はばくばくと激しく脈打っていた。
凪と仲直りをした僕だが、現在の高校では相変わらずおひとりさまをしている。
奈良のようにちょこちょこと話しかけてくる奴も数人はいるが、休み時間にひとことふたこと会話をするだけで、それ以上の仲にはならない。
もともと地元で孤立する前も、友だちは多いほうではなかった。
僕はたぶん、根本からひと付き合いには向いていないタイプなのだと思う。だから、転校生なんて僕にはこれっぽっちも関係のない話だ。
結果的に、転校生がやってきたのはうちのクラスではなかった。
転校生はとなりのクラスに配属されたらしく、朝のホームルームでそれを知ったクラスメイトたち――特に男子――は、がっかりしていた。
ホームルームが終わり、一時限目が始まるまでのあいだ、僕は再び読書にいそしんでいた。
物語が、今ちょうどクライマックスに入ったところなのだ。
今読んでいるのは、未来からやってきた女の子と現代の男の子との青春SF小説。
現代の震災で亡くなってしまうはずの男の子を救うため、女の子が時を越えて現代にやってきて奮闘するというドラマチックなラブストーリーだ。
『ねぇ、生まれ変わりって知ってる? ひとはね、死んだら生まれ変わって、またこの世界を生きるんだって。だから、僕は――』
今、僕が読んでいるところは、男の子がすべての真実を知り、未来へ帰りゆくヒロインへ想いを伝える場面なのだ。
今、まさに――。
どきどきしながら、頁をめくったときだった。
「汐風くーん!」
突然、教室中に聞こえるくらいの大きな声で名前を呼ばれ、現実に引き戻される。
顔を上げ、声がしたほうを見て、目を疑った。
「ち、千鳥さんっ?」
教室の扉のところに立っていたのは、神社で出会った女の子――千鳥さんだった。
千鳥さんは以前会ったときに着ていた白いワンピースではなく、さくらの森高校指定の紺色のセーラー服を着ている。ぴょんぴょんと嬉しそうに飛び跳ねながら、周囲の視線を気にすることもなく、僕に向かって大きく手を振っていた。
僕は目を丸くして、こちらに手を振る彼女を見つめる。
なんで、彼女がここにいるのだろう。
彼女は結賀大学附属病院に入院しているはずではないか。この前だって、ほんの数時間しか外出できない身の上であるとじぶんで言っていた。
それなのに、いる。今目の前に。
えっ、なんで?
退院したということ?
そして、たまたま僕と同じ高校だったと?
いや、そんな偶然が有り得るのか?
……と、そこまで考えて、我に返る。
教室のざわつきにおそるおそる振り返ると、クラス中の視線が刺さった。
やっぱりだ。とてつもなく注目を浴びている。僕は慌てて廊下に出る。
「なんでここに君がいるの」
語気強めに訊ねると、千鳥さんはなぜか得意げな顔をして、
「なんでってそりゃあ、転校してきたからだよ!」
思わず眉間を押さえてため息をつく。やっぱり、そういうことなのか。
「まさか、奈良が言ってた転校生って、君のことだったのか……」
変わったひとだとは思っていたけれど、まさかここまでだったとは。
「学校に行けば汐風くんに会えるものだと思ってたのに、汐風くんいないんだもん。だから探しに来たのっ!」
「ちょ、声がでかいって。ちょっと、こっちきて」
周囲からの視線にいたたまれなくなった僕は千鳥さんの話を遮り、手を取って歩き出す。
「おっ? どこ行くの、汐風くん」
「とりあえず場所を変える」
こんなところではいろんな視線が気になって、まともに話なんてできやしない。
「つーか奇跡過ぎだろ……」
思わず呟きながら、僕は彼女の手を引いて教室を出た。まさかの人物の登場に、僕の脳内は軽くパニックになっていた。
購買部近くの自動販売機の前まで来て、僕はようやく千鳥さんの手を離した。
突然連れ出された彼女はしばらくきょとんとした顔を僕に向けていたが、やがてすぐそばにあった自動販売機へと目を向けた。
「わっ! なにこれー! 高校って自動販売機まであるの!?」
相変わらず、彼女の興味はあっという間に過ぎてゆく季節のように移り気だ。
「それで……転校って、どういうことなの?」
僕は、なるべく声を押さえて千鳥さんを問いただす。
自動販売機を物珍しげな顔をして見つめていた千鳥さんが、まるでダンスでも踊るように華麗なターンを決め、僕を見た。
「そのままの意味だよ? 学校に通ってみたくなったから転校してきたの。ね、見てみてこの制服! どう? 似合う?」
千鳥さんは無邪気にセーラー服のスカートの裾を掴んで、やはり華麗なターンを決めてみせる。
「えっ? えっと……」
セーラー服の彼女は、たしかに可愛らしいとは思うけれど。
「いやいや、そんなことより君、病院に入院してるんじゃなかったの?」
「うん! してるよ。でも先生に相談したら、半日で帰ってくるなら行っていいって! その代わり、検査はきっちりやるって約束しちゃったんだけどね」
「半日だけ? じゃあ、君はこれから毎日半日だけ登校するってこと?」
「うん、そう!」
「なんでまた……」
彼女に許可を出した先生とやらも、いったいなにを考えているのか。
退院したならまだしも、彼女はまだ入院中。
入院患者に通学を許可する病院なんて、聞いたことがない。
結賀大学附属病院は、地元でもかなり有名な病院だったはずだ。
未成年の入院患者に対して無責任なことを言うようには思えない。そもそも病院には、長期入院している未成年患者のための学校があると聞いたことがある。
「君が入院してるその病院には、院内学級とかないの?」
「あるけど……それじゃダメなんだもん」
「ダメってなにが?」
訊ねた途端、千鳥さんの表情に翳りが見えた。
しまった、と思う。デリケートな部分に触れてしまったかもしれない。
千鳥さんは手と手を擦り合わせて、少し緊張気味に言った。
「だって、院内学級じゃ君がいないでしょ」
「……え、僕?」
返ってきた彼女の答えは、いささか予想外なものだった。
僕は戸惑いながら彼女を見る。彼女の青みがかった瞳は、いつ見ても不思議な魅力がある。
「君がいない学校じゃダメ。君と同じ学校に通ってみたかったの」
「僕と……どうして?」
「言ったでしょ? 君が学校で悪く言われるなら、私が否定してあげるって」
ハッとする。
たしかに、言われた。いや、だけど。
「まさか、あれ本気で言ってたの!?」
「まさか君、うそだと思ってたの? ひどーい」
「いや、うそっていうか、単なる励ましの言葉だとばかり……」
あのときの言葉は、本心ではあっても、本気ではない。ふつうはそう思う。
まさか本当に本気で転校してくるだなんて……。
「まぁなんていうか? セイシュン、ってやつをさ、君とならできる気がしたの!」
「青春って……」
「一度くらい経験してみたかったんだもん、女子高生」
「……もしかして君、学校初めてなの?」
「うん!」
彼女は無邪気に頷いた。
「……そう、だったんだ……」
なんだか申し訳なくなって、僕はそれ以上の追求をためらう。
もし病院に黙って来ているのなら、今すぐ帰したほうがいい。だけど、これ以上部外者がとやかく言うのはあまり彼女のためにはならない気がする。
だから、
「あのさ、ひとつだけ確認させて。病院には、ちゃんと連絡してるんだよね?」
「うん、それは大丈夫。ちゃんと先生の許可はもらってきてるから。制服とかもぜんぶ先生が用意してくれたんだよ!」
じっと彼女の目を見つめる。うそをついているようには見えない。
「……もしかして、迷惑だった?」
黙り込んでいると、千鳥さんが不安そうに僕の顔を覗き込んできた。
「……え……いや」
そんなことはない。嬉しい。
……だけど、なぜ彼女がここまでしてくれるのか分からない、という本音はある。
僕は、彼女にそこまでしてもらえるほどの人間じゃない。
「あ、あのね、そうは言っても、君のためだけじゃないよ! 君のためっていうか、君のためのふりを装ったじぶんのためって感じだから!」
千鳥さんは、少し慌てたような口調だった。
「ど……どういうこと?」
「本音を言うと、私、君に会うまで学校に行くのは無理って諦めてたのね。でも私、君に言ったじゃない? 『汐風くんの悪いところは、勝手に自己完結しちゃうところだと思うよ』って。言ってから気付いちゃったんだ。それ、私もだなって」
「君も?」
「うん。汐風くんみたいに学校に行くのも同い歳の友だちを作るのも、私には無理、できっこないって最初から諦めてた」
それにさ、と千鳥さんは僕を見る。
「諦めるってことは、逆を言えばそれがやりたいことなわけでしょ?」
言われてみればそうだ。
僕は、凪と仲直りするのは無理だと諦めていた。だけど、諦めていたということは、僕は心のどこかで、凪と仲直りしたかった、ということなのではないだろうか。じぶんでも知らなかった本心に気付き、ハッとする。
「今自分がやりたいって思ってることを、生い立ちとか過去のトラウマとかに邪魔されるのって、なんかいやじゃない?」
千鳥さんはそう言うと、歯を見せて笑った。その笑顔はあまりにも眩しくて、なぜか目の奥が刺激されたみたいにじんわりと熱くなった。
「……うん、そうだね」
たぶん、嬉しかったのだ。
――私もだなって。
その、ひとことが。
千鳥さんにつられて、僕も小さく笑みを漏らす。
悩んでいるのは、僕だけじゃない。分かったのはたったそれだけのことなのに、ずいぶんと僕の心は軽くなったようだった。
「……君ってほんと、変なひとだね」
「えっ! なにそれ、ひどい!」
千鳥さんは口を尖らせてふん、とそっぽを向いた。
相変わらず怒りかたが小二だな、と思いつつ、僕はポケットから財布を取り出す。自動販売機に小銭を入れ、サイダーの真下にあるボタンを押した。
ガコン、と大きな音とともにペットボトルが取り出し口に落ちてくる。
もう一度同じ工程を繰り返して、僕はふたつのサイダーを手に取った。そのうちのひとつを彼女に差し出す。
「え……くれるの?」
「うん。入学祝いってことで」
「あ、ありがと……」
千鳥さんはそろそろと手を伸ばし、僕からサイダーを受け取った。
「すごい……! なんか、水がきらきらしてるよ……!?」
「炭酸だからね。振っちゃダメだよ」
「炭酸……!!」
千鳥さんは、サイダーなんかより目をきらきらさせて、僕があげたサイダーを抱き締める。
「ありがとう。一生大切にする!」
「いや、それは炭酸が抜ける前に飲んでよ」
「あ、そっか。えへへ……あ、ねぇ汐風くん。今日のお昼休み、また会いに来てもいい?」
「でも君、午前の授業が終わったら帰るんじゃないの?」
「ここに来るまではそのつもりだったけど……汐風くんとクラス離れちゃったし、昼休みくらいしか仲良くなれるチャンスないんだもん。ダメ?」
千鳥さんは少し不貞腐れたような顔をして言う。
どきり。ストレートな表現に、異性に慣れない僕の心臓は大袈裟に反応してしまう。
「……そ、それはかまわないけど……でも、どうせなら僕とお昼食べるより、同じクラスのひとたちと仲良くなったほうがいいんじゃない? 馴染むためにも」
あくまで、彼女に気を遣ったつもりだった。
だって、僕とかかわったところで彼女に得はない。
僕は、高校に入学してからだれともかかわろうとしてこなかった陰キャの代表のようなもの。一方で、彼女は可愛くて話題の転校生。
僕なんかにこだわらず、もっと明るいひとたちと仲良くなったほうが、より楽しい学校生活を送れるだろうと思ったのだ。
今だってそうだ。
僕なんかといるところを見られたら、彼女がまわりからなにを言われるか分かったものではないし、僕といたせいで彼女にマイナスのイメージがついてしまうかもしれない。
「それは……まぁ、そうなんだけどさ」
出会ってからというもの、いつだって軽やかな返答をしてきた彼女が、珍しく歯切れの悪い反応をした。その顔を見て、ハッとする。
千鳥さんは、現在進行形で入院している。口調こそ明るいけれど、きっと心の内はいろんな不安でいっぱいのはず。唯一知り合いである僕を頼ろうとするのは、当然のことなのではないか。
周りの目を気にするより、僕はまず彼女に優しくするべきだったのではないか。
「ごめん。僕、君の気持ちも考えずに」
慌てて謝ると、千鳥さんは首を振った。
「ううん。私こそ、ごめん」
「……なんで君が謝るの?」
訊ねると、千鳥さんは自嘲気味の笑みを浮かべた。
「……だって私、汐風くんに大きな口叩いたくせにまだだれにも話しかけられてないんだ」
「……だれにも?」
「うん。思えば、病院のひとたちは生まれたときからそばにいてくれて、話しかけるのもなにかを頼むのも当たり前の日常だったから、緊張なんてしたことなかったなって。ぜんぜん知らない大勢のひとのなかに入るって、こんなに怖いことなんだね。知らなかったよ」
罪悪感が胸に広がっていく。
「だから、汐風くんはすごいよ。ちゃんと学校にいるんだもん。すごい」
呟く千鳥さんは、やはり拠りどころのない顔をしていた。
「……そんなこと、ないよ」
彼女に言われて凪と向き合って、心は見えないものだと分かっていたはずなのに。
「……君のほうが、よっぽどすごい」
しゅんとしてしまった千鳥さんに、僕は微笑みを向ける。
「僕だって怖いんだから、君が怖いのなんて当たり前だよ。新学期は毎年緊張するし、本当は今だって……強がって平気なふりしてるだけで、本当はめちゃくちゃ怖い」
「汐風くんも?」
「……うん」
たぶん、本がなかったら僕はこの学校という社会を生きていけない。
「そっか。じゃあ、私たちいっしょだね!」
ようやく彼女がいつもどおりの朗らかな笑みを浮かべる。
「うん……そうだね」
その笑みに、僕の心はまた少しだけ軽くなる。
「……じゃあ、とりあえず昼休みにここに集合ってことで。お昼は教室じゃなくて違うところで食べよう」
「えっ……いいの?」
千鳥さんの顔に、わずかに驚愕の色が滲む。
「……うん」
僕とかかわって彼女がいやな目に遭わないか、心配だけれど。こんな顔をされてしまったら、さすがに断れない。それに、彼女には恩がある。
僕なんかが彼女の役に立てるとは思わないけれど、せめて彼女に友だちができるまではそばにいよう。
頷くと、彼女は花が咲いたような笑みを浮かべた。
「やった! じゃあお昼休み、楽しみにしてるね!」
昼休みに会う約束を取り付けると、千鳥さんは軽やかな足取りでじぶんのクラスに戻っていく。
呑気なうしろ姿に小さく苦笑しながら、ふと思い出す。
「あ、お礼」
凪と仲直りできたことを思い出し、彼女が消えたほうを見る。しかし、そこにはもう千鳥さんの姿はなかった。
まぁ、昼休みに言えばいいか。
僕も彼女のあとを追い、教室へと戻るのだった。
階段の半ばあたりに差し掛かったところで、予鈴が鳴った。
急ぎ足で階段を駆け上がり、教室の扉を開ける。扉を開けた途端、クラスメイトたちの視線が一斉に僕へ向いた。三十人分の眼差しの圧に気圧されつつも、僕は足音を立てないようにして自席へと戻る。
本鈴はまだ鳴っていないため、先生の姿はまだない。セーフだ。
先生が来るまで、あと数分。続きが気になっていた文庫本をすかさず開く。……が。
「なぁなぁ錦野。さっきのって例の転校生だよな? もしかしてお前、知り合いなの?」
奈良に話しかけられてしまった。
僕は仕方なく本を閉じ、彼に応じる。
「……べつに。ただ、何度か会ったことがあるだけだよ」
目を合わせないまま答えた。しかし奈良は、僕の態度を気にする素振りはない。
「へぇーそうなんだ。なぁ、あの転校生って、名前なんて言うんだ?」
「千鳥さんだよ」
「千鳥? ふぅん、千鳥か……あれ。千鳥って、どっかで聞いたような……?」
奈良は千鳥さんの名前を聞くと、なぜか眉を寄せて考え込み始めた。
「どうかした?」
彼の反応が気になって、聞き返してみると、
「あ、そうだ。思い出した。小学校のとき、たしか同じ苗字の子がクラスにいたんだよな。うわ、懐かしいなー」
「えっ、じゃあ奈良は、千鳥さんと同じ小学校だったってこと?」
でも彼女は、学校に通うのは初めてだって言っていた気がするが……。
首を捻っていると、
「いや、さすがに別人じゃない?」
と、奈良はそう言ってあっさりと前を向いた。
***
そして、昼休み。僕は開口いちばん、疑問を呈した。
「……あのさ、今さらだけど、なんで奈良がここにいるわけ?」
僕は今、体育館の二階、折り畳まれた卓球台の裏でお弁当を食べている。
右どなりには、千鳥さん。そして、左どなりには、なぜかクラスメイトの奈良がいるのだ。
千鳥さんと約束をした昼休み、昼食を持って彼女と待ち合わせした購買部前に行くと、ちょうど購買部でパンを買っていた奈良と遭遇した。
そして、話しかけてきた奈良と話しているところに千鳥さんが登場し、なぜかそのままの流れで昼休みを三人共にすることになったというわけである。
奈良を問い詰めると、彼はのほほんとした口調で、
「まーま、細かいことはいいじゃん。あ、それとも錦野は、千鳥さんとふたりがよかったとか? もしそうだったらごめんなぁ、邪魔しちゃって!」
などと言って、からかうような眼差しを向けてくる。
「違うってば」
冷めた口調であしらってから、僕は千鳥さんを見た。待ち合わせたときから気になっていたことを訊ねる。
「……で、千鳥さんにも聞きたいんだけど、君、お昼は?」
千鳥さんは、手ぶらで待ち合わせ場所にやってきたのだ。購買でパンを買うわけでもなく、ポケットからカロリーメイトなどの栄養補給食品が出てくるわけでもない。
僕たちがご飯を食べ始めても、彼女だけは一向に昼食を取り始める気配がない。
訊ねてみれば、
「ん? ないよ?」
返答に、僕は耳を疑った。
「元々半日で帰ることになってたから、私、お昼持ってきてないんだよね!」
「……それならなんで購買で買ってこないの」
ため息混じりに言うと、千鳥さんはぽんっと手に手を置いて、なるほど! という顔をする。
「その手があったか! それじゃあ今から買いに行ってこよっかな」
と、軽やかに立ち上がる千鳥さんを、僕は真顔で止める。
「無駄だよ。もうなにも残ってないって」
「えっ、そうなの!?」
「うん。さすがにもうないだろうね」
奈良も僕の意見に賛同する。
そうなのだ。この高校の購買部は、異常なほど人気がある、若しくは異常に品数が少ないのか。とりあえず売り切れるペースがとてつもなく早いのだ。
「がーん、そんなぁ」
千鳥さんは、魂が抜けたような顔をしている。ショックを全身で表しているらしいが、お昼を食べ損ねたのだ。分からなくはない。
「とりあえず購買は無理だし、どうしようか……」
「まぁ、私のことは気にしないで食べてよ。病院に戻ったらちゃんと食べるし! もともとそのつもりだったし!」
悩んでいると、さっきまで落ち込んでいたはずの千鳥さんはケロッといつもの調子に戻っていた。
「え? いや、でも」
一瞬、変わり身の速さに拍子抜けする。まるで初めから用意していたような言い回しに感じた。
「いいのいいの! 本当に気にしないで!」
「……でも」
さすがにお腹を空かせている彼女の前でじぶんたちだけで食べるというのは、ちょっと忍びない。
そう思っていたとき、
「あ、じゃあ俺のちょっとやるよ! ほら、この唐揚げひとつどーぞ」
と、奈良が切り出した。その手があったか、と今度は僕が手に手を置く番だった。
「それなら僕も」
奈良にならって、僕も蝶々さんが作ってくれたお弁当から、玉子焼きとハンバーグをお弁当のふたにのせて渡す。
「えっ、いいよ、そんなつもりじゃなかったし」
差し出されたおかずを見ながら、千鳥さんは少し困った顔をして遠慮をする。それでも、奈良は笑顔で彼女に唐揚げが刺さった爪楊枝を差し出した。
「いいからいいから! 飯はやっぱりみんなで食べたほうが美味いじゃん?」
「えっ、そうなの? そういうもの?」
千鳥さんが意見を問うように、僕を見る。
「うん、まぁ……それに、君も食べてくれたほうが、僕たちも食べやすいし」
千鳥さんは奈良の意見に同意した僕を見て、そのまま僕の手元に視線を落とす。
「……じゃあ、ありがとう」
千鳥さんは少し申し訳なさそうな顔をしながらも、そろそろとおかずを受け取った。
千鳥さんは爪楊枝に刺さった唐揚げをゆっくりと口に持っていく。
なんとなく、僕たちはその光景を緊張気味に見つめる。
ぱくり、と彼女が唐揚げを食べる。しばらくもぐもぐしていた千鳥さんが、パッと奈良を見た。目がきらきらとしている。
「おいひい!!」
「よっしゃー!」
じぶんが作ったわけでもないだろうに、奈良は千鳥さんの反応に大袈裟に喜ぶ。その喜びように、千鳥さんも嬉しそうに笑う。
「この玉子焼きも! すごい美味しい!」
「……そっか、よかった」
なんとなく、大袈裟に喜んだ奈良の気持ちが僕にも分かった。これは蝶々さんが作ったお弁当だけど、褒められるとなぜかじぶんが褒められたみたいに嬉しくなるのだ。
ふと、じぶんを省みる。
そういえば僕は、蝶々さんにちゃんと『美味しい』って言っていただろうか。
蝶々さんはどれだけ忙しくても、必ずご飯を用意してくれる。たまに手を抜くこともあるけれど、彼女の場合はそれすらも僕に気遣わせないための配慮だろう。
……こういうのは、当たり前になっちゃダメだ。
今日は晩御飯のときに『美味しかったです』と、ひとこと言おう。そう、ひそかに心に決めた。
「ねぇ、ふたりって同じクラスなんでしょ? 仲良しなの?」
あっという間にお弁当を食べ終えた千鳥さんが、僕たちを交互に見て訊いた。
僕は箸を手を止め、首を振る。
「べつにそういうわけじゃないけど――」と、僕が否定するより先に、横から奈良が「そうだよ!」と軽い口調で返した。
「っは!?」
びゅん、と音がしそうなほど勢いよく奈良へ顔を向けると、奈良は首を傾げていた。
「え、なんだよ、俺たち友だちだろ?」
「いや、いつから……?」
「いつからって、最初から」
最初から!?
「いやいや、僕、奈良と話したの、ほぼ今日が初めてなんだけど?」
僕は奈良と友だちになった記憶など、これっぽっちもないのだが。
「でも、席前うしろじゃん?」
「席が並んでるからって友だちじゃないだろ……」
「えっ、俺は同じクラスになった時点で全員友だちだと思ってたけど?」
「どんな理屈だよ……」
「あ、それよりさ、千鳥さんって、下の名前なんて言うんだっけ?」
奈良の奔放さに若干呆れていると、彼はあっさり話題を彼女へ変えた。自由なところが彼女に若干似ている気がする。
「私? 千鳥夢だよ」
千鳥さんはまるで用意しておいた言葉を並べるように、そう答えた。
「え」
僕はといえば、思わず声が出た。
だって、彼女が名乗った名前がおかしい。彼女の名前は、桜のはずだ。
千鳥桜。
初対面のとき、彼女はそう名乗っていた……はずだ。
聞き間違えたのだろうか?
僕は困惑気味に千鳥さんを見る。彼女はといえば、困惑する僕を見てどこか気まずそうに微笑んだ。
それについて追求できる雰囲気ではない。
「へぇ、夢ちゃんかぁ……。あ、俺は奈良涼太! よろしくな」
「うん、よろしくね」
奈良は当たり前のように彼女の名乗った名前を受け入れ、呼んでいる。そして、彼女もまた当たり前のように反応していた。
桜じゃなくて、夢。
やっぱり、僕が聞き間違えたということなのだろうか。
「気軽に夢って呼んでね! ……汐風くんも、ね?」
「……あ……うん」
ぎこちなく頷きながらも、その眼差しには強い違和感を覚える。
彼女らしくない、と感じたのだ。うまく説明できないけれど。
なにも言えなくなっていると、彼女の視線がふっと僕の手元に移動した。やはり移り気のようで、彼女の興味はお弁当といっしょに持ってきた文庫本に流れたようだった。
「あっ! ねぇ、これって汐風くんの本? 私も見ていい!?」
「あ……う、うん。どうぞ」
「あっ、それ、俺も気になってた! 錦野、いつもそれすごい集中して読んでたから」
「えっ、そうだった?」
千鳥さんだけでなく、奈良も食いついたことに驚いた。
「うん! 話しかけるの悪いなって思うくらい」
奈良の言葉には、悪意も他意も感じない。
奈良の言うとおり、僕は教室ではずっとこの本を読んでいた。はまっていたというより、クラスメイトたちに話しかけられないように。
ちょっと悪いことをしたかもと反省する。
「『生まれ変わっても、また君と』……。すごい素敵なタイトル!」
「なぁ、錦野。この本って、どんな話なんだ?」
ふたりから一度に訊かれ、僕は本の表紙を見る。表紙には、一面青い世界に描かれた男女の姿とタイトル。
「これは……えっと、未来からきた女の子と、現代の男の子との青春恋愛小説だよ。ちょっとSF入ってるけど」
「未来からきた女の子と、現代の男の子の……ふぅん。そうなんだ」
千鳥さんは本の表紙をじっと見てから、顔を上げて僕を見た。
「ねぇ汐風くん、この本面白い?」
「……うん、面白いよ」
「そうなんだ。じゃあ、読み終わったら私に貸してくれない?」
「……まぁ、もう読み終わるし、いいけど」
「やったぁ! 約束ね!」
「あっ、それなら俺にも貸してよ! 夢ちゃんの次でいいから」
「分かった」
「ふふっ、楽しみだね!」
「だな! 『生まれ変わってもまた君と』なんてめっちゃエモいタイトルじゃん」
「生まれ変わっても、かぁ。ねぇ、ふたりは生まれ変わったらなにになりたい?」
相変わらず突然に、千鳥さんが言い出した。
「え?」
突然の質問に、僕は呆ける。となりで奈良が元気よく手を挙げた。
「はいはい! 俺は鳥! 鳥になりたい!」
「えっ、なんで?」
僕の問いに、奈良がすっと顔を空へ向ける。
「空飛んでみたいから!」
「あーたしかに!」
千鳥さんも嬉しそうに空を見上げる。
僕もふたりにならって空を見上げてみるけれど、あまりの太陽の眩しさに目を細めた。太陽へ手を翳し、光を遮断する。
「鳥かぁ……」
手を翳して空を仰いでいると、指の隙間を鳥の影が横切っていった。
空ってどんな感じなのだろう。
飛行機に乗ったことがないから、空から見た景色というものをいまいち想像できないけれど。
「風を切るのって、きっと気持ちいいんだろうなぁ」
想像してみる。障害物のない真っ青な空のなか、雲を抜け、風をあやつり、自在に飛ぶ鳥。たしかに気持ち良さそうだ。
「ねぇ、汐風くんは、もし生まれ変わるならなにになりたい?」
目を閉じて空想にふけっていると、千鳥さんが僕に訊いた。
「僕は……」
答えに戸惑い、僕は千鳥さんに訊き返す。
「……千鳥さんは?」
「私? 私はねぇ……まだ分かんないや」
「えっ、そうなの?」
「……うん」
少し意外だった。
明るい彼女なら、笑顔で『生まれ変わってもまた私になりたい!』とか言うかと思ったのだが。
どこか寂しげな彼女の横顔に、僕の脳裏になぜかあの神社の桜の木が過ぎった。
その横顔と、不可思議な記憶の断片が気になりながらも、僕はそれ以上深く訊ねることはしなかった。
***
昼休み終了五分前の予鈴が鳴り、僕は彼女とふたりで体育館を出た。
奈良もさっきまでいっしょにいたのだが、昼休みも後半の頃、突然次の授業の教科係であることを思い出し、準備のため一足先に教室へ戻ったのだ。
先を歩いていた千鳥さんが、振り返りながら僕に話しかける。
「涼太くん、すごくいいひとだね〜!」
僕は千鳥さんを送るため、彼女とともに昇降口へ向かっている。
「そうだね。といっても、奈良とは僕も今日初めて話したんだけど」
「えっ、そうなの? それにしてはすごく気が合ってたよ。きっと、涼太くんはずっと君に興味があったんだろうね」
「……そうかな」
「きっとそうだよ」
彼女はスカートの裾を軽やかにひるがえらせながら、僕の前を歩いていく。
彼女はいつ見ても眩しい。まるで、学校の渡り廊下がランウェイのように見えてしまう。
「それにしても、君はすごいね」
「え、なにが?」
「だって、あっという間に奈良と仲良くなってただろ」
「え、そうかな……? べつにふつうじゃない? 涼太くん、すごい話しやすかったし」
いや、ふつうではない。少なくとも、僕には無理だ。
昼休みをともにしてみて気付いた。
彼女は、驚くほど社交性がある。
僕と出会ったときもそうだったけど、ひとの懐に入るのがとにかく上手いのだ。持ち前の明るさと素直な笑顔で、あっという間に馴染んでしまう。
たぶん、それはきっと、彼女の笑顔にうそがないからなのだろう。
彼女なら、間違いなくクラスの人気者だ。朝の時点でまだだれにも話しかけられていないなんて言うから心配したのに、損した気分だ。
彼女の笑顔の前では、きっとどんなに気難しい人間でも、心を許してしまうのではないだろうか。
たとえばそう、僕とか。
「大袈裟だなぁ。汐風くんだって、すごく楽しそうに涼太くんと話してたじゃない」
「……そんなことないよ」
僕は、彼女みたいに、相手に向かって無邪気に笑いかけることはできない。まず、相手の顔色をうかがってしまう。
どんな人間か探ってしまうのだ。そうしないと気が済まない。
下駄箱からローファーを取り出す千鳥さんの横顔を見つめ、僕は意を決して口を開いた。
「……あのさ、僕……次、君に会えたら言わなきゃと思ってたんだけど」
思い切って話を切り出すと、彼女は手を止め、僕を見た。
「なあに?」
千鳥さんは、前へ流れた髪を耳にかけながら、首を傾げた。
「君に言われて、中学のときの親友に連絡したんだ。それでね……そいつと、ちゃんと仲直りできたよ」
こんな話をしたところで、彼女が覚えているかどうか分からない。なんの話? と言われたらさすがに落ち込むし、恥ずかしく消えてしまいたくなるだろう。でも、言いたい。これまで抱いたことのない、不思議な感情だった。
……だけど、それは要らぬ心配だったようで、
「えっ! えーっ!」
千鳥さんはぱっと表情を明るくして、
「仲直りできたの! そっかぁ!! すごい、よかったね!」
と、無邪気に笑った。
……どうやら、覚えていてくれたらしい。
僕は照れ臭さを感じながらも、うん、と頷く。
「……君のおかげ。ありがとう」
礼を言うと、千鳥さんは首を小さく横に振った。
「違うよ。私はなにもしてない。君がちゃんとじぶんとその友だちの両方に向き合ったからだよ」
「……そうかな」
「うん。すごい。本当にすごいよ」
優しい声音で言われて、僕は唇を引き結んだ。
嬉しくて、ほっとして、涙が出そうだ。
こんな気持ちになるのは、初めてだった。
「……正直、今さら話したところでなにも変わらないって思ってた。だけど向き合ってみて、初めて相手の本心を知ったんだ。……いろいろ辛かったし悔しかったけど、やっぱり、声を聞けて嬉しかった。あの頃僕、あいつのことが大好きだったんだって、今になってようやく思い出せた」
「……そっか」
千鳥さんが、おもむろに僕の前に立つ。僕より頭ひとつ分背が低い彼女は、僕の前に来ると、つま先立ちをした。
なんだろう、と思っていると――不意に、彼女の華奢な手が、僕の頭に乗っかった。
彼女は僕の頭をわしゃわしゃと撫で回しながら、言った。
「よくがんばりました。えらいです」
一瞬、なにをされたのか分からなくて、僕は硬直する。直後、すぐに状況を理解した身体が火照り出した。
「……いや、き、君に褒められても」
「いいじゃん。だって褒めたかったんだもん」
「…………」
彼女に触れられた部分がどうしようもなく熱くて、甘酸っぱい気持ちになる。
僕は千鳥さんから目を逸らしたまま、あのさ、と呟く。
「よかったら、なにか君にお礼がしたいんだけど」
「え、お礼?」
「うん……その、仲直りのお礼。君がいなかったら、たぶん一生凪とはすれ違ってたと思うから」
正直な言葉を吐くと、千鳥さんは嬉しそうにふふっと笑った。
「べつにいいのに。君は真面目だねぇ」
「……べつにそんなことない。ふつうだろ」
「うーん、お礼かぁ。なにがいいかな〜」
彼女は手を頭のうしろにやって、のんびりと天井を仰ぎ見る。そして、「あっ」と、なにかを思い出したように、表情を変えた。
「じゃああれがいい! お弁当!」
「お弁当?」
「うん! 汐風くんのお弁当、すごく美味しかったから! また食べたいなって!」
「それはべつにぜんぜんいいんだけど……でもあれ、僕が作ってるんじゃなくて、叔母が作ってくれてるやつなんだけど……それでもいいの?」
「もちろん! だって、それって家族の手料理ってことだよね!? うん、やっぱり私、それがいい!」
どうやら彼女は、蝶々さんのお弁当をご所望らしい。
こう言っちゃなんだが、もっと高価なものをねだられるものと思っていたから若干、というかかなり拍子抜けだ。
「手作りお弁当、私、食べるの夢だったんだ!」
「……夢って、そんな大袈裟な……まぁでも、そういうことならいいよ。但し、叔母も仕事してるし、忙しいときは僕も購買頼りだから、次お弁当持たせてくれるのがいつになるかは分からないけど」
「じゃあ、その『次』を楽しみにして毎日登校するね!」
仕方ないか、と了承すると、彼女は鼻歌を歌い始めるほどご機嫌になった。
「あんまり期待し過ぎないでね!」
彼女の弾む背中に叫んだけれど、果たして聞こえているのだろうか、と、若干不安になるのだった。
***
それから一週間後のこと。
「美味し〜い!!」
学校の中庭に、千鳥さんの歓声が響いた。
先日約束した例のお弁当を、約一週間ぶりに千鳥さんに捧げたのだ。お弁当を前にした彼女は、まるで子どものようにはしゃいで喜んだ。
「これ、本当にいいの!?」
僕は苦笑しつつ、頷いてみせる。
「君がこれがいいって言ったんだから。僕は購買のパンがあるし」
と、僕は購買で買ったクリームパンと焼きそばパンを掲げてみせる。
「うわっ、これって前にもらったのと同じ玉子焼きだよね!? え、しかもこのご飯に乗っかってるのって、もしかしてふりかけ!? わぁ、ご飯もあったかい! しかももちもちしてる〜!」
想像以上の反応に、僕と涼太は若干呆気にとられていた。
「いや、夢ちゃん大袈裟すぎでしょ。まるでご飯を初めて食べたひとみたいになってるよ」
「えっ、うそ!? ごめん! ひとりで騒いで」
まぁ、べつに騒ぐのはかまわないのだが。
「……あのさ、今さらなんだけど……千鳥さんっていつも病院食食べてるんだよね?」
おずおずと訊ねると、千鳥さんは玉子焼きを咥えながら、笑顔で頷いた。
「そうだよ」
「その……こういう食事って、しても大丈夫なの? 食事制限とか、あったりしない?」
「あー、うん! それはぜんぜん大丈夫だよっ」
その反応はいつもより歯切れが悪いように感じた。が、まぁ、彼女が大丈夫というなら大丈夫なのだろう。そう思うことにして、僕はそれ以上詮索することをやめる。
「それよりこの玉子焼き、本当に美味しいねぇ」
「……そう?」
「うんっ! 美味しいものを食べたときに言うあれ、なんだっけ。……あ、そうそう、ほっぺたが落っこちそう! っていうあれ、こういうときに使うんだねぇ」
「なにそれ」
千鳥さんは、大袈裟過ぎるくらいに僕があげたお弁当を絶賛している。
蝶々さんのお弁当は、たしかに美味しい。だけど、彼女の反応はいささか過剰な気がした。
「まぁいいや。とりあえず、あんまり食べ過ぎないでよ。僕、君の身体に責任持てないし」
「分かってるってば。なーんか、汐風くんってお母さんみたいね」
「なっ……そんなことないだろ」
「あるよー。なんていうか、小うるさい感じが」
「はぁ!? それは君が無茶ばかりしてるからで……」
僕と千鳥さんの言い合いが始まると、すかさず涼太が間に入ってくる。
「あーはいはい。分かったから。ったく、ふたりは仲良いなぁ」
まったく、千鳥さんが転校してきてからというもの、僕の学校生活はがらりと変わってしまった。
まず、にぎやかになった。
僕と千鳥さんのすぐそばには、最近仲良くなった奈良涼太の姿がある。
奈良と僕、それから千鳥さんは、初めて一緒に過ごしたあの昼休みから順調に距離を縮めていた。
特に、奈良とは入学当初とは比べものにならないほど仲良くなった。
今では、奈良のことを涼太、涼太は僕のことを汐風、とお互い名前で呼び合うほど打ち解けた。
そして、さらにもうひとり。
「――夢ちゃんてば、お弁当ひとつではしゃぎ過ぎじゃない?」
「だってこれ、本当に美味しいんだもん! 彩ちゃんも食べてみなよ」
「い、いいよ、私は……」
「いいからいいから。ほら、あーん」
千鳥さんのとなりには、女の子がいる。
ボブヘアで、背の低い女の子だ。
彼女の名前は志崎彩。
千鳥さんと同じ二組の女子で、千鳥さんいわくクラスでいちばん最初に友だちになった子らしい。
かくいう志崎さんは、千鳥さんの前では自然体だが、僕たちの前では……というか、主に涼太の前ではかなり緊張気味だ。
千鳥さんが言っていた。彼女は涼太のことが気になっているらしいと。
彼女たちの恋を応援するという名目もあって、近頃の昼休みは僕たち四人で過ごすようになっている。
あっという間に学生らしい日々を送るようになった僕だけれど、僕は今、千鳥さんのことで少しだけ悩んでいる。
それは、彼女の名前のことだ。
彼女はこの学校で、千鳥夢と名乗っているのである。僕に名乗った、『桜』という名前ではなく。
最初は聞き間違いかと思ったが、クラスメイトだけでなく、先生も彼女を『夢さん』と呼んでいるから間違いはない。
――千鳥夢。
それが、この学校での彼女の名前であった。
しかし、出会ったとき、彼女は僕に、じぶんは千鳥桜だとはっきり名乗ったのだ。
では、僕が彼女と出会ったときに教えられた名前はなんなのか。
「夢ちゃーん! 見て、四つ葉のクローバー見つけたよ! 前に見たいって言ってたっしょ!?」
「えっ! 見たい! どれどれ!?」
千鳥さんが涼太に呼ばれてベンチから立ち上げる。その反応に、不自然さはない。だけど、僕にはどうもしっくりこない。
この違和感を彼女に直接訊ねてもいいものかと悩んでいるうちに、もう一週間が経っていた。
僕は未だに、彼女の素性を知れずにいる。
ため息混じりに購買のパンにかじりつく。ふとスマホを見てハッとする。
「あれっ。千鳥さん、そろそろ帰る時間じゃない?」
「今何時?」
「十二時半」
あと数分で予鈴が鳴る。
「あーそっかぁ。じゃあそろそろ帰んなきゃ」
名残惜しそうにしながら立ち上がる彼女とともに、涼太も立ち上がった。
「昼休みってマジであっという間だよなぁ」
「ほんと。もう少し長ければいいのにね……」
「さてとっ、じゃあ汐風。俺、五限の準備あるから先戻ってるな」
「分かった」
「あっ、じゃあ私も戻ろうかな。歯磨きしたいし」
涼太が立ち上がると、志崎さんも慌てた様子で立ち上がりながら、まるで用意しておいた言葉を並べるような口調で言った。
そのあと、なにやら意味深に千鳥さんと目配せをしている。
なんとなく察して、僕はそっとしておく。
女の子には女の子なりのアプローチの方法があるのだろう。
彼女のひそやかな好意には気付かないふりをして涼太と志崎さんを見送ったあと、僕と千鳥さんはふたりで昇降口へ向かった。
その道すがら、千鳥さんが言う。
「あのね、汐風くん。彩ちゃんは好きになっちゃだめだからね」
「え、なにいきなり」
突然の話題に、僕は困惑の眼差しで千鳥さんを見る。いきなりなぜそんな話になるのだろう。意味が分からない。
「だって汐風くん、今日なんか彩ちゃんのことすごく見てたからさ」
「いや、べつにそんなことないよ。そもそも、昨日今日知り合ったばかりのひとを好きになんてならないだろ」
「……え」
千鳥さんの足が止まる。僕も歩くのをやめて彼女を見た。
「え、ってなんだよ」
「……や、べつに。でも……ふぅん、そうなんだ。ふぅん」
千鳥さんは口を尖らせている。なんだかご機嫌ななめのようだ。なぜだ?
「なんだよ、その反応」
「べつにぃ? ……あ、そうだ汐風くん。それならちょっと協力してほしいんだけどさ、今週末ってなにしてる?」
「週末? 週末は特になにも予定はないけど」
「ほんと? じゃあ日曜の朝十時、紫之宮神社に来てくれないかな?」
「まぁ、いいけど……なにかあるの?」
訊ねると、千鳥さんは、
「恋のキューピットになるんだよ!」
と、これ以上ないくらいのドヤ顔をした。
「……はっ? キューピット? いや、なにそれ?」
僕は眉を寄せ、千鳥さんを見る。
「今ね、彩ちゃんとふたりで告白大作戦を考えてるの! ほら、彩ちゃん涼太くんのこと好きでしょ? できれば海とかロマンチックなところでの告白がベストだって考えてたんだけど、それはなかなか厳しいってことで、とりあえず映画デートをすることになっててね。たぶん今頃、彩ちゃんは勇気を出して涼太くんを誘ってる頃だと思うんだよね!」
「……いや、それ僕たちになんの関係もないじゃん。デートってことはふたりで行くんだろ? それならなおさら、邪魔しちゃダメだろ」
「分かってないなぁ。陰ながらサポートするのが恋のキューピットでしょ! こっそり尾行して、ふたりが上手くいくようにサポートしてあげようよ!」
「なにそれ……ぜったい余計なお世話だよ」
というか、とてつもなく面倒くさいのだが。どうして僕が、休日にひとのデートを盗み見なきゃならないのだ。
「とにかく、日曜日に紫之宮神社の桜の木の前に集合ね! それじゃまた!」
「えっ、ちょ……!?」
慌てて呼び止めようとするけれど、彼女が昇降口を出ると同時に予鈴が鳴ってしまった。
次の授業は体育だ。本鈴が鳴る前に、着替えを済ませて体育館に行かなければならない。
「やばっ」
僕は急いで教室へ向かった。