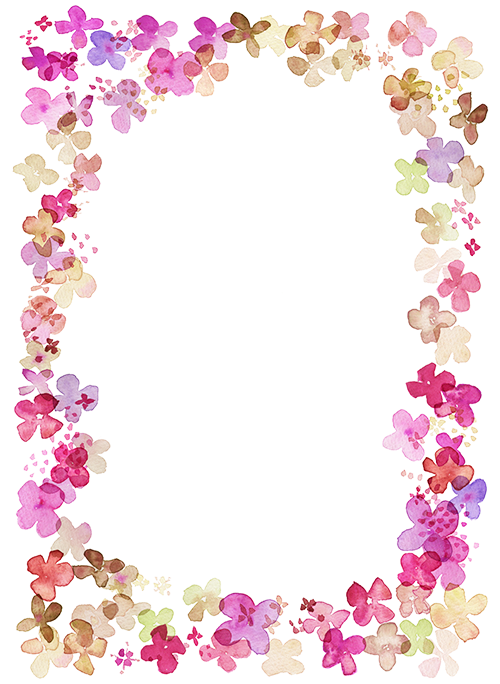その日、夏奈は王子様に出会った。
桜が咲き誇り、風で踊るように花びらが舞う日だった。
桜が伸びる先の、音楽室の二階の窓が開け放たれていて、夏奈は彼をみつけた。
真っ直ぐな黒髪に切れ長の目の、線の細い少年が窓辺でピアノを弾いていた。白いカッターシャツを喉元だけ開けていて、首を傾けながら夢見るように鍵盤をみつめていた。
桜の中、そこだけ別の世界が広がっていた。
夏奈は自分が小さなもののような気がしてしまって……恋するより、嫉妬した。
窓辺で弾く少年は、しばらくして夏奈に気づく。
彼はこちらを見て戸惑った顔をした。それが浮世離れした風貌に人間らしさを持たせて、夏奈は可笑しくなる。
あれ、もしかして私と同い年くらい? 夏奈はそんなつもりはなかったのになぜか笑ってしまった。
そうしたら彼は驚いた目をして、柔らかく表情を変えた。
現れたのは照れたような、かわいいような笑顔だった。
それが、真澄との出会いだった。
尾上真澄をもう一度みつけることは簡単だった。彼は今年ピアノ科にトップで入ってきて、先生や同級生でも噂の新入生だった。
同級生たちは、夏奈に恐る恐る問いかける。
「本当に行くの?」
「もちろん。能力のある人間からはどんどん吸収しなきゃねぇ」
夏奈はこのとき、真澄を利用してやろうというずるい心を持っていた。桜の下で彼に見惚れた自分が恥ずかしくて、そんな風に言い訳をしないとプライドが許さなかった。
ただ、同級生たちの反応だって、黄色い歓声を上げて近寄る感じではなかった。
「尾上君は王子様すぎて、ちょっと近寄りがたいかな。家も、すごくお金持ちみたいだし」
「へぇ、そうなんだ。わかる気がする」
夏奈はへらっと気楽に笑う。夏奈は、金持ちだから差別しようというわけじゃない。
夏奈は両親を亡くして施設育ちだった。夏奈を今まで苦しめたのは、同じ世界の住人がほとんどだった。もっともそれを踏みつけてでも前に出る夏奈だったから、こうして大学進学も叶ったわけだけれど。
お坊ちゃんならなおさら結構。取り入りやすそうだ。夏奈はそう考えた。
夏奈は扉を開いて部屋の中に入る。数人のピアノ科の人間がいて、遠巻きに中心のグランドピアノの方を見ていた。
流れるような旋律が部屋中に満ちている。夏奈はその聞き覚えのある音色を耳にして、弾いている人間を察した。
夏奈は身を守るために覚えた、誰にでも人好きのする笑顔を浮かべて言う。
「すばらしいね! キミのピアノ」
夏奈が手を叩くと部屋中の人間がこちらを見た。それには構わず、夏奈は中心のグランドピアノに歩み寄る。
ピアノの前に真澄はいた。突然現れた夏奈に驚きながらも、はにかんで立ち上がる。
「君、この間の」
「そうそう。覚えててくれたんだ」
「うん。君の話、あれから聞いたんだ。声楽科にすごい新入生が来たんだって」
夏奈の前に立ち上がった彼は背が高く、肩幅も広い。理想的な均整の取れた体格で、小柄さがコンプレックスの夏奈は嫉妬を覚えた。
でもそんな暗い感情は、身を守るためには決して外に見せないのを学んでいる。夏奈はぱっと笑って言った。
「やだなぁ。キミこそピアノ科にトップで入ってきたっていう真澄君でしょ? 私は声楽科の夏奈。よろしくね」
「あ……よろしく」
夏奈が手を出すと、彼は戸惑いながらも握手に応える。
夏奈は少し考えて切り出す。
「さて、真澄君。友達になってほしいなぁ」
夏奈は猫目を細めて下から誘う。
「早速だけど、ランチに行こう。ね? いいよね。よし決まり」
夏奈はにっと笑う。さて、どんな反応が返ってくるかな。夏奈はいろんな場合を想像しながら待つ。
近寄って来る女の子に慣れていて、スマートに応じるか。逆にそういう女の子が多くて警戒するか。どちらもあると思ったのだ。
「……ほんとう?」
真澄の反応は、そのどちらとも違った。
「ありがとう! うれしいよ」
真澄は女の子よりかわいく笑ってうなずいた。夏奈はそんな無邪気さに驚いて、思わず息を呑む。
「い、いいんだ?」
「僕、友達少ないんだ。誘ってくれる人がいて嬉しい」
夏奈はまだ自分の人間観察が足りなかったのかと、内心で焦っていた。
真澄は、嘘をついている感じじゃない。でもそれにしてもこんなに純粋に育って、よく今まで踏みつけられなかったなと呆れる。
夏奈は嫉妬しながら、少しだけ彼の空気に毒されてしまっている自分がいた。
真澄はさっそく行こうというので、次の土曜日の昼にランチに行った。
彼は女の子だらけのチョコレート専門店に興味津々で、あれは何、これは何と落ち着きがないくらいだった。
「一番おいしいのを私が注文してあげよう」
夏奈は意地悪心を出して、真っ先に一番苦いチョコレートを注文した。案の定、真澄はそれを口にするなり顔をしかめる。
「……苦い」
「はは。真澄君はコドモだねぇ。この苦さがいいんじゃない」
夏奈は笑い飛ばすと、話を切り出す。
「真澄君はいつからピアノを始めたの?」
「二歳からかな。夏奈さんは?」
初めて二人で行ったランチ、夏奈と真澄は音楽の話ばかりした。
話してみてすぐに気づいたのは、お互い音大に入ってきたばかりというのもあって、関心領域が限りなく近いことだった。
好きな作曲家や苦手なジャンル、中学や高校時代の経験。話は弾んでいて、ふいに夏奈と真澄は違う話に逸れた。
真澄はどうしてか、いきなり夏奈に問いかけた。
「好きな子がいたことある?」
夏奈は唐突だなと思いながら、軽く返した。
「そりゃあね。どうして?」
「僕はまだお付き合いしたことないんだ。好きです、でも付き合ってほしいわけじゃないんですって、変な言い方はされたことあるんだけど」
「うらやましいことで」
夏奈は猫目を笑いで彩って頬杖をつく。
「そうかも。真澄君は付き合ってくれそうには見えないから」
「どういうこと?」
「ありがとうって受け流されそうってこと」
夏奈がそう言うと、真澄は困ったように眉を寄せてうつむいた。
「女性に興味がないわけじゃないんだよ。でもすごく好きっていうわけじゃないのに、付き合うのは失礼かなぁって思うんだ」
「そう? 私はちょっと好きでも好きは好きだから、どこまでもお付き合いしちゃうけど」
夏奈はおどけて肩を竦める。真澄はマキアートを両手で大事そうに包みながら、忠告するように言った。
「夏奈さんは社交的すぎて、危ない目に遭わないか心配」
「あははは。もうあるもんねー」
「え、大丈夫だったの?」
真澄は目を丸くして驚いていて、夏奈はその様子がおかしくてますます笑った。
真澄はじとっとした目で夏奈を見返す。
「夏奈さん。僕のこと子供だと思ってるだろ」
「違うって。あはは」
話を聞けば聞くほど、真澄は世間の汚いものを知らなかった。夏奈がからかうとすぐにすねて、実に子どもっぽい、そして本当に取り入りやすい人だと思った。
気づいたら夏奈は意識しなくても笑顔が絶えなかった。お坊ちゃんだと馬鹿にしていたのに、真澄と話すのは楽しかった。
陽気なランチタイムだった。甘いチョコレートの香りに包まれて、時間は飛ぶように過ぎていった。
「真澄君?」
ふと真澄が片手で顔を覆って、夏奈はけげんそうに問いかける。
真澄はそれに、夏奈が信じられないようなことを返した。
「笑われるかもしれないけど、洋酒に弱くて」
夏奈は笑いはしなかったものの、驚きとともに問い返す。
「酔ったってこと?」
「そうみたい。ごめん、先に帰る……」
「ま、待って待って。気分悪い人を一人で帰さないよ。家どこ? 送る」
渋る真澄から何とか住所を聞きだして、夏奈は彼と店を出た。
二人で電車に乗っている途中、真澄はばつが悪そうに言った。
「情けない。何してるんだろ。この年で、しかも洋酒で酔うなんて」
「苦手なんだから仕方ないじゃん」
夏奈は弱っている人間に追い打ちをかけるほど悪人じゃない。あっさりと言い切って、真澄の肩を叩く。
「弱ってるなら力を貸す。今度は私を助けてくれればいいよ」
「……夏奈さんは」
真澄は何か言いかけて、くしゃっと顔を歪めた。夏奈は電車の表示を見上げていて、真澄が言いかけたことは気にしなかった。
数十分後、夏奈は巨大な屋敷の門の前に立っていた。
「何これ」
門から玄関が見えない。都心にこんな屋敷があるなんて初めて知った。それくらい、真澄の家は大きかった。
インターホンを鳴らしてしばらくすると、お手伝いさんらしい人が慌てて出てきた。
簡単に事情を話して、とりあえず家の中まで入れてもらう。
屋敷の中も想像以上で、何百万するかわからないシャンデリアや、品のいい調度で満ちた見事な家だった。
真澄は自室に下がって、夏奈は客室に通された。夏奈がお茶をご馳走になっていると、背が高く温厚そうな男性が入ってきた。
「ありがとう。真澄が世話になったね」
真澄によく似た雰囲気で、すぐに真澄の父親だとわった。
夏奈は気まずくなりながら言う。
「すみません。苦手なものを食べさせてしまって」
「いい経験だよ。あの子は友達付き合いが少なくて心配してたんだ」
別の扉からほっそりとした壮年の綺麗な女性が出てきて、彼女も優しく夏奈に声をかけてくる。
「ご迷惑をおかけしてごめんなさいね。お話に聞いています。夏奈さんですか?」
「はい、声楽科の。こちらこそご迷惑をおかけして」
ソファーにゆったりと掛ける夫婦は何ともお似合いな、おっとりとした人たちだった。夏奈はめったにお目にかかれないほどの上品な空気に目を白黒させながら、お茶を喉に流し込む。
見上げれば家族の思い出に満ちた空間だった。真澄の学校行事での写真が棚の上を所狭しとばかりに飾られ、旅先での家族写真ではみんな幸せそうに笑っている。
真澄が書いたと思われる母親の絵、父親にプレゼントしたらしい習字、そういう拙いものも丁寧に並べられており、埃一つもかかっていない。
……羨ましいと、つい思ってしまった。夏奈だってプレゼントする相手はいる。でも両親にはもう永遠に何もあげられない。
ずきりと胸が痛んで、夏奈は席を立っていた。
「帰ります。長居してすみません」
「夕食も召し上がっていかれたら?」
真澄のご両親が残念そうな顔をする。夏奈は無理におどけて返した。
「忙しない性格なもので、私」
答えを待たずにその場を去る。一秒でも早くここから出たかった。
屋敷から出たら、飛ぶように家まで帰った。狭いアパートだけど、夏奈の唯一の安息の場所へと全力で向かう。
「ただいまっ!」
息を切らして中に飛び込んだ。そこでブランケットに包まっていた双子の妹が、顔を出して言った。
「おかえり、夏奈……わぁ!」
「ただいま、ひなた!」
ぎゅっと、ひなたを抱きしめる。いつも以上に大げさな夏奈に、ひなたはころころと笑う。
「なになに、夏奈。単独リサイタルでも終わったの?」
「そ。大失敗だったよ」
夏奈はひなたを抱きしめたまま目を閉じて呼吸を繰り返す。
「やっぱりこの家が一番落ち着く」
「うん?」
「真澄って子とランチしたんだ。幸せボケした、気に食わない感じだった」
夏奈が家でだけ告げる本音を口にすると、ひなたは目を細めてうなずく。
夏奈は文句らしい言葉をつらつらと並べる。
「トップで入学したらしいし、ちょっと近づいてやろうと思ったんだけどさ」
ひなたはふふっと笑って、夏奈と額を合わせた。
よしよしと夏奈の頭を撫でながら、ひなたは子どもにするように優しく言う。
「わかった。そういうことにしておいてあげる」
「違うってば」
栗色の澄んだ瞳に夏奈を映して、ひなたは続ける。
「今日の夏奈は、いつもよりずっといい顔だけど」
ひなたは大人びた子だと思う。夏奈の薄っぺらな言い訳など簡単に見透かしてしまう。
「……違うもん」
憮然と告げて、夏奈はひなたの隣にころりと転がった。
大学一年、夏奈と真澄は、音楽と共にいつも側にいた。
夏奈は真澄を内心気にくわないと思いながら、彼の音楽は手放しで認めていた。
真澄のピアノの一音一音には翼がある。彼が弾いているとそこだけ世界が塗り変わるような錯覚を受ける。
けれど夏奈だって声楽には誇りを持っている。発表のときを待ちわびていた。
そんな折、クリスマスコンサートで夏奈に発表の機会が与えられた。
コンサート当日は朝から曇り空で、張り詰めるくらいに寒い日だった。
夏奈は自分の発表のために舞台裏で最後の調整を行っていた。
板張りの床を踏みしめて真澄がやって来ると、夏奈に言う。
「気合が入るね」
真澄は発表用の正装に上着を羽織って、指はしっかりと手袋で保護している。たぶん両親にそうするように言われたんだろうなと夏奈は思った。
夏奈はうなずいて、多少震えながら返した。
「うん、緊張してる。でもこれが始まりだと思って、頑張らなきゃ」
夏奈はプロになって、それで食べていけるようになるために音楽をやっている。まずはここで成功すると決めている。
前を見据えて深呼吸した夏奈に、ふいに真澄が言った。
「できるだけのことをすれば十分だと思うよ」
「そう、かな?」
真澄は邪気のない笑顔を見せてうなずく。
夏奈は思わずその言葉に背を押されてしまいそうになって、彼とはライバル同士だと思い直す。
夏奈は気丈に言い返す。
「私の心配してていいのかな? 真澄君の調整は?」
「僕は最後だから。観客席でゆっくりしてから行くつもり」
真澄はそこで少し言葉を切って、真顔になって言った。
「……僕がここまで来れたのは君のおかげだよ、夏奈さん」
「え?」
頬をかいて、真澄はその繊細な顔立ちに微笑を浮かべる。
「今まで一緒に音楽を楽しんでくれる友達はいなかったんだ。でも夏奈さんは初めて会った時から気安く僕に接してくれた。……嬉しかったよ」
夏奈は思わず黙ってしまった。こんなに真っ直ぐな感謝をされる筋合いはない。夏奈は利用してやろうという思いで真澄に近づいて、今だって心から彼に打ち解けたつもりはない。
真澄はそんな夏奈のずるい本心には気づいていないのか、朗らかに言う。
「夏奈さんが観客席にいてくれるんだろ? だから、今日の僕に怖いものはないんだ」
真澄に屈託ない笑顔を向けられて、夏奈はどうしていいかわからなかった。
違う、違うんだ。私は君と違って、純粋に君を応援していない。そんな弱音を、もう少しで言いそうになってしまう。
真澄は柔らかく笑って言う。
「楽しもう。そうすれば、観客も楽しんでくれるよ」
彼はまもなく去っていって、夏奈は舞台裏で順番を待つ。
今日の夏奈は、成功しようとただそれだけの気持ちでいた。見に来てくれるひなたや客たちへの配慮なんて忘れていた。
両親を亡くして、ひなたと二人で残された。笑うことも忘れていたとき、ひなたが笑ってくれたのは、音楽だった。
私はひなたの王子様になる。あの日の決意を思い出したら、緊張なんてはじけ飛んだ。
拍手が聞こえて、夏奈の前の発表が終わる。
深呼吸する。そしてゆっくりと、夏奈だけの舞台へと足を踏み入れていった。
夏奈の舞台は、もしかしたら真澄のおかげで成功したのかもしれない。
無駄な力は入らず、けれど湧き出るエネルギーのままに歌えた。いつになく響きが遠くまで届いて、喝采の音では胸が全力疾走した時よりも高鳴った。
観客席に向かってひなたと合流すると、彼女は満面の笑顔だった。
「よかった。夏奈らしい舞台だったよ」
ひなたは、どんな評論家の言葉よりも嬉しい一言を夏奈にくれた。
夏奈は照れながらうなずいて、ひなたの隣に腰を下ろす。
夏奈はちょっとすねた顔を作って言う。
「でも悔しいけど、大トリがまだこれからだからなぁ」
「お友達の真澄君?」
ひなたに言われて、夏奈は言葉を付け加える。
「ライバルだよ」
「ふふ」
二人で他愛ない会話をしながら真澄の発表を待っていた。
夏奈は母親に声楽を習って、ひなたは父親にピアノの教育を受けていた。ひなたは一つ一つのピアノ発表を、目を細めて聴いていた。
やがて真澄の出番がやって来た。
最後ということもあり、期待している人は多かっただろう。実際、観客席は満員だった。
しんと静まり返るホール。その中で、真澄は丁寧に礼をして席についた。
瞬間、彼の指先から生まれた音楽は、羽が音に姿を替えたみたいだった。
曲はショパンだった。円舞を踊るように音がホールの中に響き渡った。
さすがだと、夏奈も聞き惚れた。大ホールで聞けばそれはいつもの数倍の輝きを放っているように思えた。
あっという間に演奏は終わり、割れるような拍手喝采が真澄を包み込む。大トリにふさわしい、一分の隙もない完璧な演奏だった。
そこで隣を振り向かなければ、夏奈だって満足の内にコンサートを終えるはずだった。
「ど、どうしたの?」
夏奈の隣で、ひなたはぽろぽろと泣いていた。夏奈が何もできないでいると、ひなたはぽつりとつぶやく。
「おとうさんみたい……」
夏奈はそれを聞いて、心臓を掴まれたような気持ちになった。
震えた夏奈に気づかないのか、ひなたは残酷な言葉を続ける。
「今日一番よかった」
その言葉に、血が逆流するような衝撃があった。
彼女にとって最高の音楽を奏でられる人間は、自分のはずだった。
夏奈には、プロになって賞賛を受ける前に、ひなたの評価がほしかった。
ひなたはこくんとうなずいて言った。
「あの人にピアノを教わりたいな」
真澄への嫉妬に胸が引き裂かれるようで、夏奈は席を立っていた。そのまま寒空の下へと走り出す。
大声で泣きたかった。私からひなたを取るなんて酷いじゃないかと真澄に食ってかかりたかった。そんなことを思う自分が一番情けないのだと気づいていた。
終わったら真っ先に真澄のところへ祝いに駆けつける。そう言った約束を忘れて、夏奈は大学を飛び出していた。
町がイルミネーションに包まれ、クリスマスソングでざわめく聖夜、夏奈は光を避けるように路地を歩いていた。
大学を飛び出して一昼夜、網の目のように走る裏の路地をふらついている。
服は薄汚れて、化粧だって崩れて、だいぶ惨めな状態になっているはずだ。だけど見た目なんて今はどうでもよかった。
「負けた……」
真澄に負けた。音楽の道を突き進んできたのに、敗北の事実は凍った槌のように夏奈を打ちのめした。
初めて見た時から、彼のピアノは圧倒的だった。ひなたが彼の音楽を好きになるのも予想できた。
もしかしたらこれからだって、夏奈がどんなに努力しても、彼に負け続けるのかもしれない。
「一番じゃ……ないんだ」
一番でなければならなかったのに。夏奈にはそれができなくて、悔しくてたまらなかった。
壁に拳を叩きつける。血が滲んだが、無機物と同じ温度になっている手の表面では痛みも感じなかった。
壁にもたれながら座り込んで、路地の隙間から空を仰ぐ。
大通りから光と音楽が漏れてくる。夏奈はそこに手を伸ばす気力がない。
何をやっているんだろう。今の夏奈はかっこ悪すぎて目も当てられない。知りたくなかった真実から逃げることもできず、ただふてくされてるだけ。こんな自分じゃ、ひなたの一番になれないのもわかる。
それでも夏奈はどうすることもできず、ずいぶんと長い間そこに座り込んでいた。
「夏奈さん」
はじめは、その声が自分に向けられているとは気づかなかった。
「寒くないの? そんな薄着で」
紺色に染まった空を背中で隠して、そこに背の高い少年が立っている。そう思っただけだった。
「ほら」
だけど、それは夢や幻じゃなかった。少年は夏奈の肩に何かを被せたのだから。
「……あ」
夏奈の肩を覆っていたのは赤いコートだった。明るい太陽の色、大好きな色に、思わず顔を上げて少年を見る。
「やっとこっち見た」
見上げれば、そこに真澄がいた。寒さのせいか白い頬を少し赤くして、真澄はほっとしたように首を傾けた。
真っ白なロングコートに柔らかそうな純白のマフラーと手袋。どれを取っても高そうなのに、真澄の持つ浮世離れした雰囲気にはあつらえたように似合っている。
夏奈はのろのろとまばたきをして言う。
「……真澄君? なんで」
真澄は屈みこんで夏奈の体にコートを着せかけて言う。
「クリスマスプレゼント。夏奈さんに似合うと思って」
ライバルに送られる筋合いはない。そう思ったのに、とっさに夏奈は何も言えなかった。
それより夏奈には苛立ちがさざなみのように押し寄せてきて、焦燥のままうつむく。
「私、キミが嫌いだ」
夏奈は思わず、本音を言葉にしていた。
「妬ましい。憎らしい。ずっとそうだった」
真澄が息を呑む気配がする。構わず、夏奈は続けた。
「私にとって音楽はすべてなのに。キミは平気で私を踏み越えていく。ずるいよ」
「……ずるいのはどっちだ」
一瞬、何が起こったのかわからなかった。
ぐいっと真澄は夏奈の頬を包んで顔を上向かせる。そこで夏奈が見たのは眉を寄せて口をへの字にした真澄の顔だった。
「そんなこと、言葉にもしてくれなかったくせに」
彼でもこんな顔をするんだと驚いた。真澄は怒りで口元を震わせて、激しい口調で問い詰めた。
「どれだけ心配したと思ってるの? 行方をくらまして、何かあったんじゃないかって、不安でたまらなかった」
すねたように顔をくしゃりと歪めて、真澄は夏奈を正面からにらみつける。
「今日は終わったら、打ち上げにクリスマス会しようって約束した。僕の家でやるって言ったよね。……それ、忘れたの?」
真澄はぐいぐいと赤いコートごと夏奈を強く引く。
「……夏奈さんが来るって言ったから頑張って準備したのに。なんにも、意味なかった」
夏奈は目を見開く。真澄はなんだか泣きそうな顔になって言った。
真澄は畳みかけるように言葉を重ねる。
「一緒にコンサートのために練習してきたよね。終わったら一番に駆けつけるって約束した。その約束も、君は破った」
夏奈は真澄の勢いに押されるように、一つうなずく。
「……うん」
「クリスマス会だって二週間も前から話をしていたし、夏奈さんは絶対行くって言った」
夏奈はそれにも、こくんとうなずいた。
「うん……言ったよ」
確かに約束した。そして夏奈はそれを破った。
気が付いたら、夏奈は彼に言っていた。
「ごめん」
目を滲ませている真澄に頭を下げる。
謝るつもりなんてなかった。でも、謝らずにはいられなかった。
夏奈の中に満ちる感情は、そっか、彼には敵わなくても仕方ないかなぁという、自分でもどうにもならない気持ちだったから。
夏奈は降参とばかりに手を挙げる。
「泣くほど私に来てほしいとは知らなくて」
「泣いてないよ!」
夏奈は思ってしまった。この少年には逆らえないと。
わがままで、優しくて、一途で、傷つきやすい。天才で夏奈には手が届かない。
それでも側で見守っていたい、不思議な存在。
「今から真澄君の家行ってもいい?」
「パーティは中止したよ。何にもない」
「じゃあ一緒に出かけよう」
自分は一体何をやっているんだろう。この世界など汚いものだらけだとわかっているのに、今夏奈の目の前はとても透き通っていて、光に溢れている気がする。
夏奈はほこりを払って自分で立ち上がると、真澄に手を差し伸べる。
「どう? ライバル同士で過ごすクリスマスだって、たまにはいいでしょ?」
……それはきっと、目の前に真澄がいるから。
真澄はぶっきらぼうに夏奈に言う。
「僕の気持ち、知ってて言ってる?」
夏奈は構わず真澄の手を握って、猫目で見上げる。
「さあ、それは今夜次第かな。ね? いいでしょ。決まり」
ちらほらと白い結晶が降り始めていた。真澄の白い輪郭を飾るように、祝福のように、舞い降りていった。
真澄はぼそりとつぶやいて、夏奈の手を握り返す。
「……ずるいよ、夏奈さん」
それは恋するより嫉妬していた王子様と過ごした、初めての夜なのだった。
桜が咲き誇り、風で踊るように花びらが舞う日だった。
桜が伸びる先の、音楽室の二階の窓が開け放たれていて、夏奈は彼をみつけた。
真っ直ぐな黒髪に切れ長の目の、線の細い少年が窓辺でピアノを弾いていた。白いカッターシャツを喉元だけ開けていて、首を傾けながら夢見るように鍵盤をみつめていた。
桜の中、そこだけ別の世界が広がっていた。
夏奈は自分が小さなもののような気がしてしまって……恋するより、嫉妬した。
窓辺で弾く少年は、しばらくして夏奈に気づく。
彼はこちらを見て戸惑った顔をした。それが浮世離れした風貌に人間らしさを持たせて、夏奈は可笑しくなる。
あれ、もしかして私と同い年くらい? 夏奈はそんなつもりはなかったのになぜか笑ってしまった。
そうしたら彼は驚いた目をして、柔らかく表情を変えた。
現れたのは照れたような、かわいいような笑顔だった。
それが、真澄との出会いだった。
尾上真澄をもう一度みつけることは簡単だった。彼は今年ピアノ科にトップで入ってきて、先生や同級生でも噂の新入生だった。
同級生たちは、夏奈に恐る恐る問いかける。
「本当に行くの?」
「もちろん。能力のある人間からはどんどん吸収しなきゃねぇ」
夏奈はこのとき、真澄を利用してやろうというずるい心を持っていた。桜の下で彼に見惚れた自分が恥ずかしくて、そんな風に言い訳をしないとプライドが許さなかった。
ただ、同級生たちの反応だって、黄色い歓声を上げて近寄る感じではなかった。
「尾上君は王子様すぎて、ちょっと近寄りがたいかな。家も、すごくお金持ちみたいだし」
「へぇ、そうなんだ。わかる気がする」
夏奈はへらっと気楽に笑う。夏奈は、金持ちだから差別しようというわけじゃない。
夏奈は両親を亡くして施設育ちだった。夏奈を今まで苦しめたのは、同じ世界の住人がほとんどだった。もっともそれを踏みつけてでも前に出る夏奈だったから、こうして大学進学も叶ったわけだけれど。
お坊ちゃんならなおさら結構。取り入りやすそうだ。夏奈はそう考えた。
夏奈は扉を開いて部屋の中に入る。数人のピアノ科の人間がいて、遠巻きに中心のグランドピアノの方を見ていた。
流れるような旋律が部屋中に満ちている。夏奈はその聞き覚えのある音色を耳にして、弾いている人間を察した。
夏奈は身を守るために覚えた、誰にでも人好きのする笑顔を浮かべて言う。
「すばらしいね! キミのピアノ」
夏奈が手を叩くと部屋中の人間がこちらを見た。それには構わず、夏奈は中心のグランドピアノに歩み寄る。
ピアノの前に真澄はいた。突然現れた夏奈に驚きながらも、はにかんで立ち上がる。
「君、この間の」
「そうそう。覚えててくれたんだ」
「うん。君の話、あれから聞いたんだ。声楽科にすごい新入生が来たんだって」
夏奈の前に立ち上がった彼は背が高く、肩幅も広い。理想的な均整の取れた体格で、小柄さがコンプレックスの夏奈は嫉妬を覚えた。
でもそんな暗い感情は、身を守るためには決して外に見せないのを学んでいる。夏奈はぱっと笑って言った。
「やだなぁ。キミこそピアノ科にトップで入ってきたっていう真澄君でしょ? 私は声楽科の夏奈。よろしくね」
「あ……よろしく」
夏奈が手を出すと、彼は戸惑いながらも握手に応える。
夏奈は少し考えて切り出す。
「さて、真澄君。友達になってほしいなぁ」
夏奈は猫目を細めて下から誘う。
「早速だけど、ランチに行こう。ね? いいよね。よし決まり」
夏奈はにっと笑う。さて、どんな反応が返ってくるかな。夏奈はいろんな場合を想像しながら待つ。
近寄って来る女の子に慣れていて、スマートに応じるか。逆にそういう女の子が多くて警戒するか。どちらもあると思ったのだ。
「……ほんとう?」
真澄の反応は、そのどちらとも違った。
「ありがとう! うれしいよ」
真澄は女の子よりかわいく笑ってうなずいた。夏奈はそんな無邪気さに驚いて、思わず息を呑む。
「い、いいんだ?」
「僕、友達少ないんだ。誘ってくれる人がいて嬉しい」
夏奈はまだ自分の人間観察が足りなかったのかと、内心で焦っていた。
真澄は、嘘をついている感じじゃない。でもそれにしてもこんなに純粋に育って、よく今まで踏みつけられなかったなと呆れる。
夏奈は嫉妬しながら、少しだけ彼の空気に毒されてしまっている自分がいた。
真澄はさっそく行こうというので、次の土曜日の昼にランチに行った。
彼は女の子だらけのチョコレート専門店に興味津々で、あれは何、これは何と落ち着きがないくらいだった。
「一番おいしいのを私が注文してあげよう」
夏奈は意地悪心を出して、真っ先に一番苦いチョコレートを注文した。案の定、真澄はそれを口にするなり顔をしかめる。
「……苦い」
「はは。真澄君はコドモだねぇ。この苦さがいいんじゃない」
夏奈は笑い飛ばすと、話を切り出す。
「真澄君はいつからピアノを始めたの?」
「二歳からかな。夏奈さんは?」
初めて二人で行ったランチ、夏奈と真澄は音楽の話ばかりした。
話してみてすぐに気づいたのは、お互い音大に入ってきたばかりというのもあって、関心領域が限りなく近いことだった。
好きな作曲家や苦手なジャンル、中学や高校時代の経験。話は弾んでいて、ふいに夏奈と真澄は違う話に逸れた。
真澄はどうしてか、いきなり夏奈に問いかけた。
「好きな子がいたことある?」
夏奈は唐突だなと思いながら、軽く返した。
「そりゃあね。どうして?」
「僕はまだお付き合いしたことないんだ。好きです、でも付き合ってほしいわけじゃないんですって、変な言い方はされたことあるんだけど」
「うらやましいことで」
夏奈は猫目を笑いで彩って頬杖をつく。
「そうかも。真澄君は付き合ってくれそうには見えないから」
「どういうこと?」
「ありがとうって受け流されそうってこと」
夏奈がそう言うと、真澄は困ったように眉を寄せてうつむいた。
「女性に興味がないわけじゃないんだよ。でもすごく好きっていうわけじゃないのに、付き合うのは失礼かなぁって思うんだ」
「そう? 私はちょっと好きでも好きは好きだから、どこまでもお付き合いしちゃうけど」
夏奈はおどけて肩を竦める。真澄はマキアートを両手で大事そうに包みながら、忠告するように言った。
「夏奈さんは社交的すぎて、危ない目に遭わないか心配」
「あははは。もうあるもんねー」
「え、大丈夫だったの?」
真澄は目を丸くして驚いていて、夏奈はその様子がおかしくてますます笑った。
真澄はじとっとした目で夏奈を見返す。
「夏奈さん。僕のこと子供だと思ってるだろ」
「違うって。あはは」
話を聞けば聞くほど、真澄は世間の汚いものを知らなかった。夏奈がからかうとすぐにすねて、実に子どもっぽい、そして本当に取り入りやすい人だと思った。
気づいたら夏奈は意識しなくても笑顔が絶えなかった。お坊ちゃんだと馬鹿にしていたのに、真澄と話すのは楽しかった。
陽気なランチタイムだった。甘いチョコレートの香りに包まれて、時間は飛ぶように過ぎていった。
「真澄君?」
ふと真澄が片手で顔を覆って、夏奈はけげんそうに問いかける。
真澄はそれに、夏奈が信じられないようなことを返した。
「笑われるかもしれないけど、洋酒に弱くて」
夏奈は笑いはしなかったものの、驚きとともに問い返す。
「酔ったってこと?」
「そうみたい。ごめん、先に帰る……」
「ま、待って待って。気分悪い人を一人で帰さないよ。家どこ? 送る」
渋る真澄から何とか住所を聞きだして、夏奈は彼と店を出た。
二人で電車に乗っている途中、真澄はばつが悪そうに言った。
「情けない。何してるんだろ。この年で、しかも洋酒で酔うなんて」
「苦手なんだから仕方ないじゃん」
夏奈は弱っている人間に追い打ちをかけるほど悪人じゃない。あっさりと言い切って、真澄の肩を叩く。
「弱ってるなら力を貸す。今度は私を助けてくれればいいよ」
「……夏奈さんは」
真澄は何か言いかけて、くしゃっと顔を歪めた。夏奈は電車の表示を見上げていて、真澄が言いかけたことは気にしなかった。
数十分後、夏奈は巨大な屋敷の門の前に立っていた。
「何これ」
門から玄関が見えない。都心にこんな屋敷があるなんて初めて知った。それくらい、真澄の家は大きかった。
インターホンを鳴らしてしばらくすると、お手伝いさんらしい人が慌てて出てきた。
簡単に事情を話して、とりあえず家の中まで入れてもらう。
屋敷の中も想像以上で、何百万するかわからないシャンデリアや、品のいい調度で満ちた見事な家だった。
真澄は自室に下がって、夏奈は客室に通された。夏奈がお茶をご馳走になっていると、背が高く温厚そうな男性が入ってきた。
「ありがとう。真澄が世話になったね」
真澄によく似た雰囲気で、すぐに真澄の父親だとわった。
夏奈は気まずくなりながら言う。
「すみません。苦手なものを食べさせてしまって」
「いい経験だよ。あの子は友達付き合いが少なくて心配してたんだ」
別の扉からほっそりとした壮年の綺麗な女性が出てきて、彼女も優しく夏奈に声をかけてくる。
「ご迷惑をおかけしてごめんなさいね。お話に聞いています。夏奈さんですか?」
「はい、声楽科の。こちらこそご迷惑をおかけして」
ソファーにゆったりと掛ける夫婦は何ともお似合いな、おっとりとした人たちだった。夏奈はめったにお目にかかれないほどの上品な空気に目を白黒させながら、お茶を喉に流し込む。
見上げれば家族の思い出に満ちた空間だった。真澄の学校行事での写真が棚の上を所狭しとばかりに飾られ、旅先での家族写真ではみんな幸せそうに笑っている。
真澄が書いたと思われる母親の絵、父親にプレゼントしたらしい習字、そういう拙いものも丁寧に並べられており、埃一つもかかっていない。
……羨ましいと、つい思ってしまった。夏奈だってプレゼントする相手はいる。でも両親にはもう永遠に何もあげられない。
ずきりと胸が痛んで、夏奈は席を立っていた。
「帰ります。長居してすみません」
「夕食も召し上がっていかれたら?」
真澄のご両親が残念そうな顔をする。夏奈は無理におどけて返した。
「忙しない性格なもので、私」
答えを待たずにその場を去る。一秒でも早くここから出たかった。
屋敷から出たら、飛ぶように家まで帰った。狭いアパートだけど、夏奈の唯一の安息の場所へと全力で向かう。
「ただいまっ!」
息を切らして中に飛び込んだ。そこでブランケットに包まっていた双子の妹が、顔を出して言った。
「おかえり、夏奈……わぁ!」
「ただいま、ひなた!」
ぎゅっと、ひなたを抱きしめる。いつも以上に大げさな夏奈に、ひなたはころころと笑う。
「なになに、夏奈。単独リサイタルでも終わったの?」
「そ。大失敗だったよ」
夏奈はひなたを抱きしめたまま目を閉じて呼吸を繰り返す。
「やっぱりこの家が一番落ち着く」
「うん?」
「真澄って子とランチしたんだ。幸せボケした、気に食わない感じだった」
夏奈が家でだけ告げる本音を口にすると、ひなたは目を細めてうなずく。
夏奈は文句らしい言葉をつらつらと並べる。
「トップで入学したらしいし、ちょっと近づいてやろうと思ったんだけどさ」
ひなたはふふっと笑って、夏奈と額を合わせた。
よしよしと夏奈の頭を撫でながら、ひなたは子どもにするように優しく言う。
「わかった。そういうことにしておいてあげる」
「違うってば」
栗色の澄んだ瞳に夏奈を映して、ひなたは続ける。
「今日の夏奈は、いつもよりずっといい顔だけど」
ひなたは大人びた子だと思う。夏奈の薄っぺらな言い訳など簡単に見透かしてしまう。
「……違うもん」
憮然と告げて、夏奈はひなたの隣にころりと転がった。
大学一年、夏奈と真澄は、音楽と共にいつも側にいた。
夏奈は真澄を内心気にくわないと思いながら、彼の音楽は手放しで認めていた。
真澄のピアノの一音一音には翼がある。彼が弾いているとそこだけ世界が塗り変わるような錯覚を受ける。
けれど夏奈だって声楽には誇りを持っている。発表のときを待ちわびていた。
そんな折、クリスマスコンサートで夏奈に発表の機会が与えられた。
コンサート当日は朝から曇り空で、張り詰めるくらいに寒い日だった。
夏奈は自分の発表のために舞台裏で最後の調整を行っていた。
板張りの床を踏みしめて真澄がやって来ると、夏奈に言う。
「気合が入るね」
真澄は発表用の正装に上着を羽織って、指はしっかりと手袋で保護している。たぶん両親にそうするように言われたんだろうなと夏奈は思った。
夏奈はうなずいて、多少震えながら返した。
「うん、緊張してる。でもこれが始まりだと思って、頑張らなきゃ」
夏奈はプロになって、それで食べていけるようになるために音楽をやっている。まずはここで成功すると決めている。
前を見据えて深呼吸した夏奈に、ふいに真澄が言った。
「できるだけのことをすれば十分だと思うよ」
「そう、かな?」
真澄は邪気のない笑顔を見せてうなずく。
夏奈は思わずその言葉に背を押されてしまいそうになって、彼とはライバル同士だと思い直す。
夏奈は気丈に言い返す。
「私の心配してていいのかな? 真澄君の調整は?」
「僕は最後だから。観客席でゆっくりしてから行くつもり」
真澄はそこで少し言葉を切って、真顔になって言った。
「……僕がここまで来れたのは君のおかげだよ、夏奈さん」
「え?」
頬をかいて、真澄はその繊細な顔立ちに微笑を浮かべる。
「今まで一緒に音楽を楽しんでくれる友達はいなかったんだ。でも夏奈さんは初めて会った時から気安く僕に接してくれた。……嬉しかったよ」
夏奈は思わず黙ってしまった。こんなに真っ直ぐな感謝をされる筋合いはない。夏奈は利用してやろうという思いで真澄に近づいて、今だって心から彼に打ち解けたつもりはない。
真澄はそんな夏奈のずるい本心には気づいていないのか、朗らかに言う。
「夏奈さんが観客席にいてくれるんだろ? だから、今日の僕に怖いものはないんだ」
真澄に屈託ない笑顔を向けられて、夏奈はどうしていいかわからなかった。
違う、違うんだ。私は君と違って、純粋に君を応援していない。そんな弱音を、もう少しで言いそうになってしまう。
真澄は柔らかく笑って言う。
「楽しもう。そうすれば、観客も楽しんでくれるよ」
彼はまもなく去っていって、夏奈は舞台裏で順番を待つ。
今日の夏奈は、成功しようとただそれだけの気持ちでいた。見に来てくれるひなたや客たちへの配慮なんて忘れていた。
両親を亡くして、ひなたと二人で残された。笑うことも忘れていたとき、ひなたが笑ってくれたのは、音楽だった。
私はひなたの王子様になる。あの日の決意を思い出したら、緊張なんてはじけ飛んだ。
拍手が聞こえて、夏奈の前の発表が終わる。
深呼吸する。そしてゆっくりと、夏奈だけの舞台へと足を踏み入れていった。
夏奈の舞台は、もしかしたら真澄のおかげで成功したのかもしれない。
無駄な力は入らず、けれど湧き出るエネルギーのままに歌えた。いつになく響きが遠くまで届いて、喝采の音では胸が全力疾走した時よりも高鳴った。
観客席に向かってひなたと合流すると、彼女は満面の笑顔だった。
「よかった。夏奈らしい舞台だったよ」
ひなたは、どんな評論家の言葉よりも嬉しい一言を夏奈にくれた。
夏奈は照れながらうなずいて、ひなたの隣に腰を下ろす。
夏奈はちょっとすねた顔を作って言う。
「でも悔しいけど、大トリがまだこれからだからなぁ」
「お友達の真澄君?」
ひなたに言われて、夏奈は言葉を付け加える。
「ライバルだよ」
「ふふ」
二人で他愛ない会話をしながら真澄の発表を待っていた。
夏奈は母親に声楽を習って、ひなたは父親にピアノの教育を受けていた。ひなたは一つ一つのピアノ発表を、目を細めて聴いていた。
やがて真澄の出番がやって来た。
最後ということもあり、期待している人は多かっただろう。実際、観客席は満員だった。
しんと静まり返るホール。その中で、真澄は丁寧に礼をして席についた。
瞬間、彼の指先から生まれた音楽は、羽が音に姿を替えたみたいだった。
曲はショパンだった。円舞を踊るように音がホールの中に響き渡った。
さすがだと、夏奈も聞き惚れた。大ホールで聞けばそれはいつもの数倍の輝きを放っているように思えた。
あっという間に演奏は終わり、割れるような拍手喝采が真澄を包み込む。大トリにふさわしい、一分の隙もない完璧な演奏だった。
そこで隣を振り向かなければ、夏奈だって満足の内にコンサートを終えるはずだった。
「ど、どうしたの?」
夏奈の隣で、ひなたはぽろぽろと泣いていた。夏奈が何もできないでいると、ひなたはぽつりとつぶやく。
「おとうさんみたい……」
夏奈はそれを聞いて、心臓を掴まれたような気持ちになった。
震えた夏奈に気づかないのか、ひなたは残酷な言葉を続ける。
「今日一番よかった」
その言葉に、血が逆流するような衝撃があった。
彼女にとって最高の音楽を奏でられる人間は、自分のはずだった。
夏奈には、プロになって賞賛を受ける前に、ひなたの評価がほしかった。
ひなたはこくんとうなずいて言った。
「あの人にピアノを教わりたいな」
真澄への嫉妬に胸が引き裂かれるようで、夏奈は席を立っていた。そのまま寒空の下へと走り出す。
大声で泣きたかった。私からひなたを取るなんて酷いじゃないかと真澄に食ってかかりたかった。そんなことを思う自分が一番情けないのだと気づいていた。
終わったら真っ先に真澄のところへ祝いに駆けつける。そう言った約束を忘れて、夏奈は大学を飛び出していた。
町がイルミネーションに包まれ、クリスマスソングでざわめく聖夜、夏奈は光を避けるように路地を歩いていた。
大学を飛び出して一昼夜、網の目のように走る裏の路地をふらついている。
服は薄汚れて、化粧だって崩れて、だいぶ惨めな状態になっているはずだ。だけど見た目なんて今はどうでもよかった。
「負けた……」
真澄に負けた。音楽の道を突き進んできたのに、敗北の事実は凍った槌のように夏奈を打ちのめした。
初めて見た時から、彼のピアノは圧倒的だった。ひなたが彼の音楽を好きになるのも予想できた。
もしかしたらこれからだって、夏奈がどんなに努力しても、彼に負け続けるのかもしれない。
「一番じゃ……ないんだ」
一番でなければならなかったのに。夏奈にはそれができなくて、悔しくてたまらなかった。
壁に拳を叩きつける。血が滲んだが、無機物と同じ温度になっている手の表面では痛みも感じなかった。
壁にもたれながら座り込んで、路地の隙間から空を仰ぐ。
大通りから光と音楽が漏れてくる。夏奈はそこに手を伸ばす気力がない。
何をやっているんだろう。今の夏奈はかっこ悪すぎて目も当てられない。知りたくなかった真実から逃げることもできず、ただふてくされてるだけ。こんな自分じゃ、ひなたの一番になれないのもわかる。
それでも夏奈はどうすることもできず、ずいぶんと長い間そこに座り込んでいた。
「夏奈さん」
はじめは、その声が自分に向けられているとは気づかなかった。
「寒くないの? そんな薄着で」
紺色に染まった空を背中で隠して、そこに背の高い少年が立っている。そう思っただけだった。
「ほら」
だけど、それは夢や幻じゃなかった。少年は夏奈の肩に何かを被せたのだから。
「……あ」
夏奈の肩を覆っていたのは赤いコートだった。明るい太陽の色、大好きな色に、思わず顔を上げて少年を見る。
「やっとこっち見た」
見上げれば、そこに真澄がいた。寒さのせいか白い頬を少し赤くして、真澄はほっとしたように首を傾けた。
真っ白なロングコートに柔らかそうな純白のマフラーと手袋。どれを取っても高そうなのに、真澄の持つ浮世離れした雰囲気にはあつらえたように似合っている。
夏奈はのろのろとまばたきをして言う。
「……真澄君? なんで」
真澄は屈みこんで夏奈の体にコートを着せかけて言う。
「クリスマスプレゼント。夏奈さんに似合うと思って」
ライバルに送られる筋合いはない。そう思ったのに、とっさに夏奈は何も言えなかった。
それより夏奈には苛立ちがさざなみのように押し寄せてきて、焦燥のままうつむく。
「私、キミが嫌いだ」
夏奈は思わず、本音を言葉にしていた。
「妬ましい。憎らしい。ずっとそうだった」
真澄が息を呑む気配がする。構わず、夏奈は続けた。
「私にとって音楽はすべてなのに。キミは平気で私を踏み越えていく。ずるいよ」
「……ずるいのはどっちだ」
一瞬、何が起こったのかわからなかった。
ぐいっと真澄は夏奈の頬を包んで顔を上向かせる。そこで夏奈が見たのは眉を寄せて口をへの字にした真澄の顔だった。
「そんなこと、言葉にもしてくれなかったくせに」
彼でもこんな顔をするんだと驚いた。真澄は怒りで口元を震わせて、激しい口調で問い詰めた。
「どれだけ心配したと思ってるの? 行方をくらまして、何かあったんじゃないかって、不安でたまらなかった」
すねたように顔をくしゃりと歪めて、真澄は夏奈を正面からにらみつける。
「今日は終わったら、打ち上げにクリスマス会しようって約束した。僕の家でやるって言ったよね。……それ、忘れたの?」
真澄はぐいぐいと赤いコートごと夏奈を強く引く。
「……夏奈さんが来るって言ったから頑張って準備したのに。なんにも、意味なかった」
夏奈は目を見開く。真澄はなんだか泣きそうな顔になって言った。
真澄は畳みかけるように言葉を重ねる。
「一緒にコンサートのために練習してきたよね。終わったら一番に駆けつけるって約束した。その約束も、君は破った」
夏奈は真澄の勢いに押されるように、一つうなずく。
「……うん」
「クリスマス会だって二週間も前から話をしていたし、夏奈さんは絶対行くって言った」
夏奈はそれにも、こくんとうなずいた。
「うん……言ったよ」
確かに約束した。そして夏奈はそれを破った。
気が付いたら、夏奈は彼に言っていた。
「ごめん」
目を滲ませている真澄に頭を下げる。
謝るつもりなんてなかった。でも、謝らずにはいられなかった。
夏奈の中に満ちる感情は、そっか、彼には敵わなくても仕方ないかなぁという、自分でもどうにもならない気持ちだったから。
夏奈は降参とばかりに手を挙げる。
「泣くほど私に来てほしいとは知らなくて」
「泣いてないよ!」
夏奈は思ってしまった。この少年には逆らえないと。
わがままで、優しくて、一途で、傷つきやすい。天才で夏奈には手が届かない。
それでも側で見守っていたい、不思議な存在。
「今から真澄君の家行ってもいい?」
「パーティは中止したよ。何にもない」
「じゃあ一緒に出かけよう」
自分は一体何をやっているんだろう。この世界など汚いものだらけだとわかっているのに、今夏奈の目の前はとても透き通っていて、光に溢れている気がする。
夏奈はほこりを払って自分で立ち上がると、真澄に手を差し伸べる。
「どう? ライバル同士で過ごすクリスマスだって、たまにはいいでしょ?」
……それはきっと、目の前に真澄がいるから。
真澄はぶっきらぼうに夏奈に言う。
「僕の気持ち、知ってて言ってる?」
夏奈は構わず真澄の手を握って、猫目で見上げる。
「さあ、それは今夜次第かな。ね? いいでしょ。決まり」
ちらほらと白い結晶が降り始めていた。真澄の白い輪郭を飾るように、祝福のように、舞い降りていった。
真澄はぼそりとつぶやいて、夏奈の手を握り返す。
「……ずるいよ、夏奈さん」
それは恋するより嫉妬していた王子様と過ごした、初めての夜なのだった。