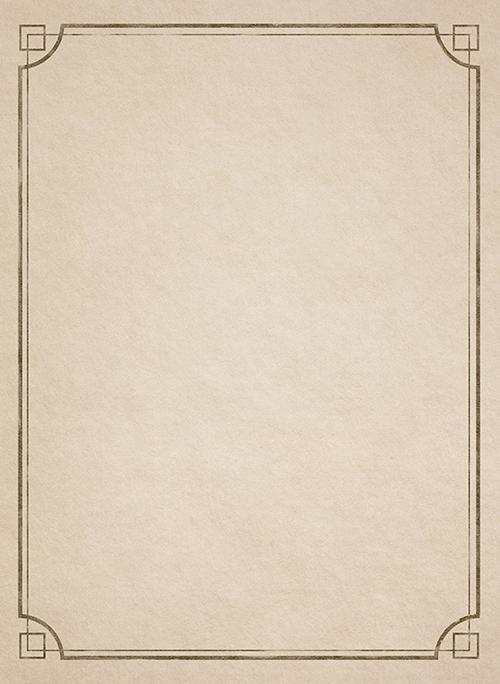この作家の他の作品
表紙を見る
高校2年生の主人公・桐島奏(きりしま かなで)は、幼い頃から「いい子」でいることを求められてきた。両親の期待に応え、教師や友人たちからも「頼れる人」として振る舞う日々。しかし、その裏では、自分の本当の感情を押し殺し、「誰かに本音を話したい」という願いを抱えている。そんな奏が出会ったのは、転校生でクラスの異端児・八神空(やがみ そら)。空は自由奔放で、周囲の目を気にせず自分の意見を堂々と言う性格だ。
ある日、奏は空に誘われて学校裏手の廃墟となった天文台へ向かう。そこには壊れかけた望遠鏡と、星座や宇宙に関する本が散乱していた。「ここで星を見よう」と言う空に戸惑いながらも、奏は次第に彼との時間の中で心を開いていく。そして、星空の下で語り合う中で、奏は自分が本当に言いたかったこと、自分らしく生きたいという想いを少しずつ吐き出していく。
しかし、空には誰にも言えない秘密があった。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
この作品をシェア
聞こえる
を読み込んでいます