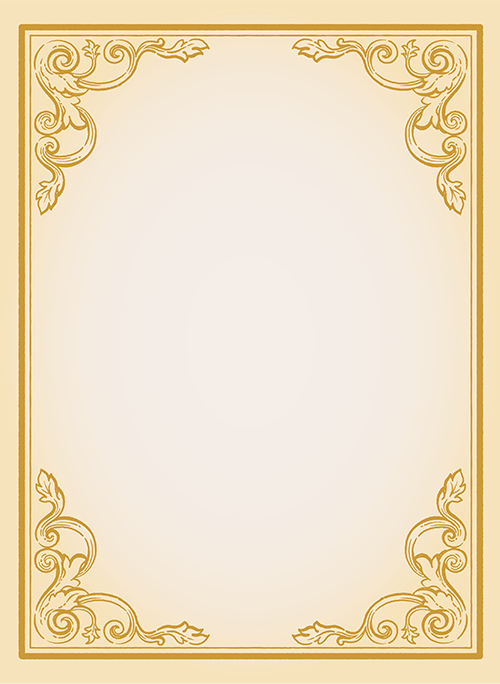犬神――強力な呪詛の力を持つ神。
犬神を祀る家は必ず栄える。
犬神に捧げる贄が尽きるまで。
それはただの言い伝えではない。
犬神家には今も尚、神が宿り一族を見守り続けている。
一度栄華を極めた者たちはその失墜を恐れ贄を捧げ続けた。
贄となるのはいずれも年若き乙女たち。
それ故、犬神に捧げられた乙女たちは贄嫁と呼ばれた。
贄嫁は犬神から決して逃げられない。
もし恐れをなして逃げ出したなら――骨も残さず喰われるのだから。
◇
「アレはどこまでも追ってくる。決して逃げられない運命なの。でも、あなたならきっと――」
そういい遺して息を引き取った母の体には、獣につけられたような噛み跡や引っ掻き傷が無数に残されていた。
そして私は天涯孤独の身になった――。
「これより婚姻の儀を執り行う」
私は今、白無垢に身を包み花嫁になろうとしている。
広間には狩衣に造面姿の男たちがずらりと並び、厳粛に淡々と事を進めていく。
「こちらを一息で飲まれよ」
男の一人に朱の杯を差し出された。
赤黒い液体が揺蕩っている。とても美味しそうには思えない。
恐る恐る一口含むと、口内に広がる鉄の味。まるで生き血のように生臭い。
思わず吐き出しそうになるのをぐっと堪え、なんとか飲みきった。
「これをもって清水沙夜を犬神家当主、犬神朔人の贄嫁とする――」
その瞬間、私は「犬神沙夜」となった。
これから先のことを考えると不安で、たまらず体が震える。
いたたまれず目を泳がすと、隣に座っていた青年と目があった。
漆黒の髪。狼のような鋭い深紅の瞳に射貫かれれば体が動かなくなる。
同じ人間とは思えないほど、恐ろしくも美しい人だった。
「お前はもう俺から逃れることはできない――俺だけの花嫁だ」
この日、私は犬神朔人の贄嫁になった――。
*
――話は半年前に遡る。
「お前が沙夜だな」
それは母の葬式が終わった直後のこと。
父と名乗る人物が突然訪ねてきたのだ。
「俺はお前の父親だ」
「……父親」
そういわれてもぴんとこない。
私はずっと母と二人きりで過ごしてきたから。
幼い頃興味本位で父のことを聞いたことがあった。
『――そうね。やっぱり気になるよね、お父さんのこと』
いつも明るい母の表情が曇った。
『いつかちゃんと話すから、その時まで待ってくれる?』
悲しそうな母を見て、子供ながらに『ああ、これは聞いちゃいけないことなんだ』と悟る。
それから私が父のことを口にすることはなくなった。
そして「その時」も母が死んだことによって永遠にくることはないのだと思っていた。
ところが父は突然現れた。
髪をきっちりと撫でつけた厳格そうな人。
密かに想像していた父親像とはあまりにもかけ離れていた。
彼は玄関先から私たちが住んでいた古く小さな部屋を一瞥すると、奥にあった母の遺骨で目をとめる。
「よく十三年も生き延びたものだな。犬神家から逃げた恩知らずが」
「……え!?」
その人は家に土足で踏み込んだかと思えば、母の骨壺を思い切り床に叩きつけたのだ。
「な、なんてことするんですか!!」
「ふん、骨も残さず喰われたか……自業自得だな」
私は思わずそれから目をそらす。
虚しく床に転がった骨壺は――空だった。
なんとも奇妙なことに火葬された母は骨も残さず消えていたのだ。
『気味が悪い。あの遺体といい……まるで呪いね』
参列者は口々に呟いてそそくさと帰っていった。
無理もない。傷だらけの亡骸に、忽然と消えた骨。私ですら驚いたのだ。
最後まで火葬場に残った私は、呆然と母がいたはずの場所を見つめながら立ち尽くしていた。
(――母さんのこと、この人はなにか知っている)
でも、いきなり骨壺を倒すような人と話なんてしたくない。
本当にこの人が父親だって保証もどこにもないのだから。
「……お引き取りください」
骨壺を拾い上げながら私は男を睨みあげる。
すると彼は目をつり上げながら、私の腕を思い切り引いた。
「なにをいっている、さっさと行くぞ。そのためにわざわざお前を迎えに来てやったんだ」
「それはこちらの台詞です! 帰る場所なんてない! 私の親はお母さんだけで……私の家はここですっ!」
腕が抜けそうなほど強く引っ張られるが、私は全体重をかけて抵抗する。
なにが起きているかさっぱり理解できない。
父親なんて知らない。私の家族は母だけなのだから。
負けじと男を睨みつけると、次の瞬間頬に鋭い痛みが走った。
「……っ!」
平手打ちされた。
一瞬耳鳴りがして、頬にじんじんと痛みが広がっていく。
「違う。それは断じて違う」
男は冷たい瞳で私を見下ろす。
それは俗物でも見るかのような。人間を見る視線ではない。
「お前は生まれた時から犬神家の人間だ。お前は決して逃げられない」
「……逃げられない」
死に際に発した母の言葉を思い出した。
床に座り込んだままの私にようやく男は膝を突き、目をあわせた。
腫れた頬なんて気にも止めず、思い切りその手で私の顔を掴み上げ強制的に目をあわせられた。
「お前、年は幾つだ」
「……十六、です」
「いいか、よく聞け沙夜。十六のお前は、一般社会ではまだ子供として扱われる。お前が幾ら拒もうと、私と共にこなければならない」
一人で生きていけるのか?
そう聞かれてすぐに頷けなかった。
母の遺産はないに等しい。高校に入ってアルバイトをはじめたけれど、収入なんて微々たるもの。とても一人では食べていけない。
そもそも後見人がいなければ、家も借りられない。住む場所も、お金だってない。
どれだけ体がこの男についていくことを拒もうと、頭はそうするしかないと理解していた。
抵抗していた腕の力が抜けていく。
「そう、それでいい。お前は逃げられない」
もう一度繰り返された。
「……やっとだ。やっと……手に入れた」
いやらしく笑みを浮かべる男。
娘に再会できた喜びではない。自分に幸福が舞い込んだときのような、零れ落ちるような笑み。
「お前は犬神様に捧げられるために生まれ落ちた贄なんだよ――」
その言葉の意味を私が理解するのはもう少し先の話だ。
*
「ちょっと、沙夜!」
「……美和さん」
背後から金切り声が聞こえ、包丁を動かしていた手を止めた。
振り返ると気の強そうな女の子が私を睨んでいる。
彼女の名前は犬神美和――この犬神家の長女だ。
「お腹空いた! まだご飯できないの!?」
「すみません。あと少しでできるのでもう少し待って――」
ちらりと台所を覗き見た美和さんがうげっと顔をしかめる。
「味噌汁に卵焼き!? なんで朝からこんなしょっぼいもの食べないといけないのよ! もー……ルミがいてくれたときはよかったのに!」
犬神家――私でも聞いたことがある名家だ。
なんでも江戸時代よりも前から続いている家系らしく、特にこの十数年は経営・政治・芸能――全ての分野でこの一族の人たちが活躍している。
そんな名家に私が引き取られてからふた月が経った。
田園調布の高級住宅街。その隅にひっそりと建つ年季の入った豪邸。
そこに父は後妻の美埜里さんと、その娘で十五歳の美和さんと暮らしていた。
今はここが私の家――といえば聞こえはいいが、実際には私は「住まわせてもらっているだけ」の居候の身。
「沙夜さん。今日は本家の人が来るからきちんと掃除をしてってお願いしたでしょう? 階段の隅に埃が溜まっていたわよ」
「申し訳ありません、美埜里さん。食事ができ次第やり直しますので……」
「まったくもう……しっかりやってちょうだい」
「……はい」
「なんであの人も、こんな子引き取ったのかしら……」
深々と頭を下げていると、後からきた義母が呆れ混じりにため息をつかれた。
キッチンから二人が去っていけば、私はほっと息を吐きながら頭を上げた。
「さあ、美和。食事が終わったら今日はとびっきりのお洒落をするわよ!」
「本家のご当主様が私に会いに来てくれるのよね!」
「ええ、そうよ。きっと貴女を迎えに来てくれたに違いないわ!」
「私、ご当主様のお嫁さんになれるのかな!?」
リビングのほうから浮き足だった二人の話が聞こえてくる。
許嫁とか婚約者とかまるでドラマの中の話を聞いているようで現実味はない。
この立派な屋敷、そして裕福そうな家族――でも私には関係のない話だ。
たとえ娘だとしても私はあの家族の輪には入れないのだから。
私はただの居候。ただの使用人だ。
朝早く起きて、この広い家の掃除をして食事に洗濯――全てのことを任されていた。
美和さん曰く、ふた月前まで「ルミ」というお手伝いさんが来ていたらしいが、今はいなくなってしまったらしい。
そのため、新しいお手伝いさんが決まるまで私が家事を一任することになったのだ。
私を無理矢理ここに連れてきた父はなにもいわない。
私の存在なんてないように、あの日以来一言も目を合わせるどころか、一切口を聞いてくれなかった。
(――……お母さん)
煮立たせてしまった味噌汁の火を止めて、私はその場に崩れ落ちた。
しゃがみ込んで、滲む涙を押し殺す。
まるで地獄だ。
お母さんがいた頃は幸せだった。
狭い家で、二人で肩を寄せ合いながら、決して裕福じゃなかったけれど笑って生きていた。
あの日常はもう戻ってこない。お母さんが死んだあの瞬間から。
これなら施設で暮らしたほうがよほど幸せだっただろう。
《逃げられない》
母も、養父もそういっていた。
それが本当だとするのなら、私は一生こんな日々を過ごすんだろうか――。
*
――数時間後、私は部屋に篭もっていた。
部屋といっても屋根裏部屋のような、小さな窓がつけられただけの狭い場所。
とってつけられたような小さな机と、薄い布団だけが私に与えられたものだった。
家に来客がきたときは私は部屋から出てはいけない約束だ。
まるで私の存在を知られたくないかのように、私はじっと息を潜めていた。
「――ご当主様がわざわざ足をお運びになるなんて。こちらから伺いましたのに」
「いいや。どうしても一度顔を出したくてね」
一階から微かに父と客人の会話が聞こえてくる。
声音からして男性――それも若く聞こえる
「――が亡くなった――……その娘は――……」
「ご当主様、花嫁を探すために美和に会いにきてくださったのでしょう!? 私の娘は優秀なんです! 器量も良く、そしてご当主様とも年が近く――」
美埜里さんのよく通り声だけがはっきりと聞こえた。
(……気持ち悪い)
甲高い猫なで声がやけに耳障りで、私は耳を塞いでその場に蹲った。
この家から出ていっても、私に行く当てもない。
助けて。助けて。こんな日々、辛すぎる。
こんなことなら私もお母さんと一緒に消えてしまいたかった――。
そんなことを考えているうちに、眠ってしまっていたらしい。
うるさく聞こえていた話し声はいつの間にかやんでいて、窓の外の日は少しだけ傾き始めていた。
(お客さんは帰ったんだろうか)
ちらりと窓の外を覗いてみると、門の外には立派な黒塗りの車が止まっていた。
それに向かって一人の男性が歩いていくのが見える。
なにやら父と義母が必死に呼び止めているようにもみえるけれど。
(……綺麗な人)
少し長めの黒髪に、すらりと通った鼻筋。
遠目から見ても顔立ちの美しさがはっきりわかる。下手な芸能人よりもよっぽど綺麗な人だ。
「――っ!」
すると、その人は何かに気づいたようにはっとこちらを見た。
少し驚いたような赤い瞳と目があった。
何故か目をそらせなかった。
そして彼は確かに私を見て微笑んだような気がした。
(まずい!)
そこで我に返った私は慌てて口を塞ぎ、窓の下に身を隠す。
どきどきと心臓が脈打つ。
(どうしよう。気づかれていたらどうしよう)
ここは二階だ。おまけに窓は小さい。声も立てていないから気づかれることなんてまずない。
でも、もし気づかれていたら――後からあの人たちになにをされるかわからない。
ガタガタと震えて縮こまっていると、車の音が遠ざかっていくのが聞こえた。
(……よかった)
窓の外を確認してみると、そこにあった車は消えていた。
ほっと息をついていると、後ろから扉が開く鈍い音が聞こえた。
「――なに、してんのよ」
「……美和、さん?」
そこには美和さんと美埜里さんが立っていた。
美和さんの目は泣き腫らしたかのように真っ赤で、美埜里さんは恨みがましく私を睨んでいる。
「姿を見せるなっていったでしょ!?」
「ちがっ……私はずっとここに……!」
美和さんに首根っこを掴まれて、美埜里さんには有無をいわさず殴られた。
「なんでご当主様はアンタなんかを! 犬神家から逃げた卑怯者のくせに!」
「っ!」
二人の目は血走っていた。
まるでなにかに取り憑かれたように、私に馬乗りになって執拗に殴ってくる。
「なんであの人もお前やあの女に執着するの!? 妻は私だけなのに! あの人の娘は美和だけなのにっ!」
「――え?」
驚いた。
殴られた痛みも忘れるほどの衝撃だった。
(――……私はあの人の娘じゃない?)
それならなんで私はここに? 私の父親は――?
「二人とも、そこでなにをしている」
冷酷な声が部屋に響いた。
父が獣のような形相で私たちを見つめていた。あまりの圧に美和さんたちは戦いて、私の上から後ずさる。
「私が娘じゃないってどういうことですか」
私は起き上がり、鼻血を拭いながらその男を睨む。
「あなたは、誰?」
「それを知る必要はない。儀式の準備は整った」
ずんずんと進んできたその人は私の腕を無理矢理引いた。
「痛いっ! 離して!」
「当主がお前の存在に気づいた。手を出される前に、手を打たねば――」
抵抗もむなしく私は階段を引きずり下ろされる。
「今からお前を嫁がせる」
「嫁ぐ!? 私はまだ十六ですよ!?」
この年で本人の意思とは関係なしに結婚だなんて、時代錯誤にもほどがある。
「案ずるな。なにも実際に婚姻するわけではない、これはただの名称。ただの契約だ」
「……は?」
理解不能だった。
私は階段を転がるように引きずられ、立ち入ることを禁じられていた地下室まで連れてこられた。
「なにが本家当主だ! 分家とて……私だって、自分の力で栄華を築く! そのために私は――」
地下の長い廊下を歩くと一番奥の部屋に投げ入れられ、扉を閉じられる。
そこは洋風な家とは異質な和室だった。
全面障子で囲まれた窓のない部屋。四隅に蝋燭の灯りがちらついており、障子に私の影がうつるなんとも不気味な空間が広がっている。
「お前が嫁ぐのはイヌガミ様だ。お前は贄嫁となるんだよ――沙夜」
「だから一体なんの話――」
扉を開けようとしていると、背後から異質な気配がして息を吞んだ。
畳を引っ掻く音がする。真後ろで生暖かい呼吸音が聞こえる。
はっはっはっ――その呼吸の速さはまるで犬のような。
暗闇の中にぎらりと光る赤い瞳。
障子に移る大きな影がゆらりとその姿を現した。
「…………ひっ」
そこにいたのは、巨大で不気味な黒い犬の化け物だった。
――グルルルルルルルル――
全身が真っ黒な毛に覆われていて、肋骨が浮き出るほど痩せ細っている。
赤い目は血走っていて、鋭い牙が覗く口からは舌が垂れ、だらしなく涎が滴り落ちている。
それは鋭い爪を畳に食い込ませ、今にも私を襲おうと、低くうなり声を上げていた。
「あ、開けてっ! ここから出してくださいっ!」
必死に扉を開けようとするが、びくりともしない。
「無駄だ。その部屋には結界を張っている」
「結界!?」
「こんな貴重な贄をみすみす手放すわけはいかない。元よりお前は当主ではなく私のものになるはずだったのに……」
扉の向こうから聞こえる養父の声はやけに冷静だった。
儀式だとか結界だとか術だとか、もうワケがわからない。
(なんとかして逃げなくちゃ――)
命の危険を感じた私は、どうにか脱出手段を探す。
だけど、この部屋には窓がない。明かりは四隅に灯された蝋燭だけが頼り。
薄暗い室内の中で、獣の瞳が私を真っ直ぐ射抜いていた。
「――ひっ」
――グアアアアアアアアッ――
恐ろしさのあまり、私が声を上げた瞬間、化物が襲いかかってきた。
振り下ろされる鋭い爪。私は寸でのところでかわしたが、左腕を掠めてしまったらしい。
「いっ……」
血が滴る腕を押さえ、よろけながら反対側へ移動して距離を取る。
その化物は畳に点々と落ちた私の血を、なんとも美味しそうに舐めているではないか。
「そのイヌガミは酷く飢えているんだ」
後ずさっていると、ごつんと足に何かが当たった。
「……っ!!」
蝋燭の明かりに照らされたのは、人。人だったもの。
女の人が転がっている。暗がりではっきりとは見えないけれど、手足が所々ちぎれて酷い臭いがする。
そういえば、美和さんが少し前に家政婦が突然いなくなったといっていたような――。
「その場しのぎの贄なんか、腹の足しにもならなかったよ」
男は扉の向こうでくつくつと笑っていた。
「うっ……」
私はとうとうあまりの恐怖でその場に腰を抜かしてしまった。
凄惨な光景に吐き気がこみ上げ、思わず嘔吐してしまう。
「た、助け……誰か……」
助けを求める声はあまりにも小さく、震えていた。
「さあ、イヌガミよ! おまえがずっと求めていた最上の贄だ!」
―グルルルルラアアアアアアアッ!―
それが合図のように、化物が私に飛びかかってきた。
畳に倒され、肩に重い足がのし掛かり、鋭い爪が食い込む。
鼻が曲がりそうなほどの獣臭でむせ返りそうになる。
(――私は、死ぬの?)
こんなことのために生まれてきたの?
私はこの化物に食べられてしまうの? お母さんのように骨も残さずに――。
(いや……)
いやだ。死にたくない。私は、こんなところで死にたくない。
「……たすけ、て」
誰でもいいから。助けて。
化物の牙が迫る中。私が最後に思い浮かべたのは――さっき二階の部屋で見かけたあの青年。
あの時、身を隠さずに「助けて」「私をここから出して」と助けを呼んでいればよかった。
そうしたら……なにかが変わっていたのだろうか。
「――――っ!」
固く目を閉じても、痛みはいつまでも襲ってこない。
「――やっと見つけた」
男の人の声がする。低くて、どこか懐かしいような――。
「あ――」
目を開けると私は男の人に抱き寄せられていた。
獣のような赤い瞳が真っ直ぐ私を見つめている。
この人は――。
「俺を呼んだのは、お前だな」
「あなた……は」
突然現れた青年を私は呆然と見上げる。
この人は、さっき家から出ていったはずの赤い瞳の男の人だ――。
「俺を本家から遠ざけ、地下に大層な結界まで張り、随分周到に隠していたようだが……」
彼は私の肩を強く抱き寄せながら、養父をぎろりと睨む。
「これはどういうことだ。申し開きがあるなら聞いてやろう、聡」
「――っ!」
放たれた殺気に、養父がびくりとたじろいだ。
「わ、私は犬神家のさらなる繁栄のためにと!」
「現在は筆頭五家以外のイヌガミの使役は禁じられているはずだ。おまけに勝手に贄まで喰らわせ、イヌガミを堕としただけでなく――」
足元に転がる亡骸を一瞥し、彼は私を見つめる。
肩を抱く手にぐっと力が込められた。
「あろうことか沙夜を贄に捧げようなど」
静かな声音。だけどそこには確かに怒りと殺気が込められていた。
「……っ! おのれ……!」
養父はぎりぎりと唇を噛み、私たちを睨む。その怒りに呼応するようにイヌガミが低く唸る。
『――ふーーーーっ』
前足を床にこすりつけながら、青年を威嚇している。
牙を見せ、口元を震わせ、今にも襲いかかろうとしているけれど――。
「……泣いてる」
ぽつりと呟いた私の言葉に青年が目を丸くしてこちらを見た。
どうして自分でもそんなことを口走ったのかわからない。でも、自分の頬に涙が伝っていることに気付く。
「苦しんでる。助けて……って」
「お前――」
先程は恐怖でなにも感じなかった。
だけど、今ははっきり聞こえてくる。
あの化物――ううん、イヌガミの感情が。心の声が。
彼は苦しんでいるだけだ。
苦しくて、痛くて、お腹が空いて……でも自分ではどうしようもできなくて。
今すぐこの苦しみから解放されたいと、救いを求めて藻掻いている。
『ぐるるるるるるるるるっ』
うなり声を上げるイヌガミの目から血の涙が零れ出す。
「……助けて。お願い、あの子を助けて」
私は涙を流しながら、思わず青年の袖を掴んだ。
「目を、閉じていろ――沙夜」
名前を呼ばれた気がすると、彼は静かに私の目を手で覆った。
暗くなる視界。次の瞬間、イヌガミが地面を蹴って襲いかかってくる。
「今、楽にしてやろう」
「――やめろおおおおおおっ!」
聞こえたのは、青年の冷静な声と養父の叫び声。
そして何かがぶつかり合う激しい音が何度か聞こえて、部屋を漂っていた禍々しい空気が消えた気がした。
「――もう、目を開けていいぞ」
そう言われて目を開けると、目の前にあのイヌガミが倒れていた。
それは眠るように目を閉じて、足先から灰のようにほろほろと崩れて消えてしまった。
「何故……何故だ! 私のイヌガミが――!」
イヌガミが消え、養父は膝から崩れ落ちきっと私を睨み付けた。
「貴様のせいだ沙夜! お前がいなければこんなことには!! 本来なら弟ではなく兄である私が――」
彼の慟哭の意図はわからない。
でも、私を恨んでいることだけは伝わった。
「耳を傾けるな。不安なら俺を見ていろ」
そういわれて視線をあげると、綺麗な顔が近くに見え、私はどこを見ていいかわからず目を泳がせる。
「犬神聡、お前の沙汰は追って伝える。二度目はないと思え」
「ぐううううっ……覚えていろ……」
殺気に怯んだ養父は顔を青ざめさせその場に崩れ落ちたのだった。
そして青年は私を抱いたまま屋敷の外に向かう。
まぶしい日差し。外の空気を吸うのはとても久しぶりに思えた。
「お前、名前は?」
「清水沙夜……」
そう告げると、彼は突然顔を近づけて私の匂いをくんくんと嗅いだ。
突然のことに私は思わず顔を赤らめる。
「お前、やはりいい香りがするな。俺の鼻に狂いはなかった」
「……え、えっ?」
そして青年はにっと笑い、こういったのだ。
「俺は犬神朔人。お前は今日から俺の花嫁だ」
「花嫁……」
「帰るぞ、月城」
「――はっ」
状況も整理できないまま、私は朔人さんに抱きかかえられたまま、養父の家を後にした。
玄関前には灰色の髪の温厚そうな青年が立っていて、私はそのまま見るからに高級そうな黒塗りの車に乗せられる。
「あ、あの……どこに向かって……」
後部座席。朔人さんの隣で縮こまりながら、私は恐る恐る尋ねた。
車は養父の家を離れ、都心の方へと向かっていた。
「屋敷に帰る。これ以上、お前をあんな穢れた場所に置いておくわけにはいかないからな」
「さっきのは一体なんだったんですか。イケニエとか、イヌガミとか……」
先程の光景が脳裏に過る。
あまりにも非現実的な体験に、私は夢でも見ていたのかと錯覚してしまう。
だけど左腕の痛みは現実で。彼が助けに来てくれなかったら今頃死んでいたのかと思うと、体が震えだした。
「あれはイヌガミ。犬神家に伝わる式神だ。きちんと飼い慣らせば有益なものだが、あの様に穢れに満ちてしまうと堕ち神となり暴走してしまう」
あの家はもうだめだな、と朔人さんは窓の外をみながらぽつりと呟く。
運転している月城さんが同意するようにこくりと頷いたのが、ミラー越しに見えた。
「その話は追々するとして……だ、沙夜」
「は、はいっ」
いきなり顔を近づけられて身じろぐ。
「お前はいつからあの家にいた」
「ひと月前に母が亡くなって、その葬儀の後に――」
経緯をかいつまんで話すと、朔人さんの眉間にみるみる皺が寄っていく。
額に手を乗せ深いため息をついた。
「抜かった……分家外れと侮っていたが、アイツも一応筆頭五家の出だったな」
「……すみません」
「何故お前が謝る。謝るべきは俺のほうだ。このひと月の間、本家を留守にしていてな。迎えが遅くなってしまって申し訳なかった」
「い、いえ……貴方が謝ることでは……」
真っ直ぐな眼差しを向けながら、朔人さんは謝罪を述べた。
朔人さんは私を助けてくれた。むしろ私は感謝すべきだというのに、どうして謝るのだろう。
申し訳なくて両手を振っていると――ぐらりと視界が歪んだ。
「あ、れ――」
急に体の力が抜ける。
前のめりに倒れかけた体を朔人さんが受け止めてくれた。
「すみま――っ」
謝ろうとして左腕に激痛が走った。
熱された鉄でも押しつけられているかのように、焼けるような痛みが走る。
「お前……あのイヌガミに傷を負わされたのか」
その視線は私の左腕に向けられる。
返事をする気力がなくて、こくりと頷くと朔人さんは小さく舌打ちをした。
「――話より手当が先だな。月城、急げ」
「畏まりました」
ぐん、と車の速度が上がる。
私はなんとか体を起こそうとするが、そのまま朔人さんは私の頭を自分の膝に乗せた。
「目を閉じて、深く呼吸をしろ。少しは痛みがマシになるはずだ。心配するな。俺が必ず助ける」
朔人さんは上着を掛けてくれて、ゆっくり背中を摩ってくれた。
その動きにあわせて呼吸をすると幾分か痛みが和らいだ気がした。
(――いい、匂い)
柔軟剤?香水?ううん、お香のような優しくてほんのり甘い香りがする。
それでも左腕の痛みは凄まじくて、いつの間にか私は意識を手放していた。
*
意識がぼんやりとしている。
誰かに抱き上げられて動いているかのような。
目を開けようと思っても、開けられない。
指一本も動かせない。ただ、左腕が熱い。
「――急ぎ、薬湯――……」
「月――筆頭……招集――」
「彼女は俺の――――――」
聴覚だけは生きていて、途切れ途切れに色々な話が聞こえる。
忙しそうに動き回る足音。水の音が聞こえる。
状況が変わっていく中で、私を抱く腕の力とあの香りだけは変わらずずっと傍にいてくれた。
(あたたかい……)
ふと、体が温かくなった。
お風呂でも入っているかのような心地よさ。つんと、薬草のような香りが鼻をつく。
「――――」
少しだけ左腕の痛みが和らいだ気がして、ゆっくりと瞼を開けた。
「――――え」
そして私は目を疑う。
私はお風呂に入っていた。正確にいうととても大きな檜風呂のような浴槽。
そこには白濁としたお湯と、薬草が浮かんでいて。そこに私は肌襦袢を着せられて浸かっている。
それにも驚いたけれど、今驚くべきはそこじゃなくて――。
「なんだ、目覚めたのか」
そこには朔人さんも一緒にいたのだから。
「――な、なななっ!」
男の人とお風呂――!?
状況を理解した瞬間、私の顔は真っ赤になって体を抱えた。
「なにを慌てている」
「だ、だって!その、私……いきなり、そんな!」
思い返せば婚約者とか、花嫁とか色々いわれていたような気がしたけれど。
だけど私はまだ十六歳で、恋愛経験なんてほぼ皆無に等しくて。
それなのにいきなりこんな状況になったら慌てるなといわれても慌ててしまう。
「なにを勘違いしている。これは治療だ」
「――へ?」
朔人さんは真面目そのもので、その視線は私の左腕に向けられている。
そのまま彼の視線をたどった私は目を丸くした。
「これ……」
襦袢の袖が捲られ素肌が露わになった左腕。
イヌガミの爪で傷付けられた二の腕の傷が、赤黒く染まっていた。
血が固まっているわけじゃない。文字通り傷口が黒く、傷の周辺は煤でもついているかのように真っ黒に染まっている。
「堕ち神に負わされた傷は『呪い傷』となって体を蝕む。このまま放っておくと、腕が腐り落ちるぞ」
「腐――」
衝撃的な言葉に私はすぐに抵抗をやめた。
「この傷は犬神家の血筋しか治すことができない。同性を呼ぶ時間がなかったからな、俺で許せ」
よく見ると朔人さんも着物を着ていて、お互い全裸ではない。本当にこれはただの治療のようだ。
(勝手に勘違いして……私ったら……恥ずかしすぎる)
「触るぞ――」
穴があったら入りたいとはまさにこのこと。
自己嫌悪に浸ろうとするのもつかの間、朔人さんの手が傷に触れた。
「――っ!」
左腕に激痛が走る。藻掻こうとすると朔人さんはがっちりと私の体を押さえつけた。
「痛むだろうが耐えてくれ。毒を抜ききらないと傷が治らない」
傷から血を掻き出すように触られる。
白いお湯が赤く黒く染まっていく。
「この湯は特別な薬湯だ。呪い傷の毒を抜き、お前の体を清めてくれる。もう少しだ――」
「っ――!」
痛みから逃れるように体を動かせば、ばしゃばしゃとお湯が揺れる。
目に涙を滲ませ、私は無意識のうちに朔人さんにしがみ付いていた。
朔人さんは私の左腕を持ち上げ、傷口に口をつけたかと思えばそのままじゅっと血を吸った。
「――よし、これでいい。よく頑張ったな」
口から血を吐き、唇の端についた血を拭いながら私を見て微笑んだ。
私は腕の痛みと、お湯の温かさと、朔人さんと二人きりの状況に頭がクラクラして――。
「――おや。ウブなヤツだな」
再び意識を失ってしまうのだった。
◇
夢を見た。
私は子供で、その目の前に大きな黒い犬がいた。
「……どうしたの?」
私の数倍も大きなその犬は、私を威嚇している。
目を血走らせて、牙を剥き出して。
誰も近づくなというように、唸っている。
「怪我……してるの?」
その犬の体は傷だらけだった。
黒い毛でよく見えないけれど、ぽたぽたと血が滴り落ちている。
毛を逆立たせ、私を拒絶しようとする彼がとても辛そうで、苦しそうで。
私はそっと手を伸ばした。
『――触ルナ!』
「――っ!」
吼えられた拍子に、牙が手の甲に当たった。
血が流れる私の手を見て、一瞬その子はたじろいだ。
「大丈夫だよ」
それでも私は手を伸ばした。
私の目からはぽろぽろと涙が零れる。
傷が痛いのもあったけれど、あまりにもその子が辛そうだったから。
「大丈夫だよ。あなたはひとりじゃないよ。わたしがいるよ」
最初はそっと鼻先に触れる。
その犬は唸るのをやめ、眉間を撫でさせてくれた。
そして彼は謝るように、私の傷をぺろりと舐める。
「おちついた? もう、大丈夫だよ」
頭を優しく撫でるとその子は気持ちよさそうに目を細めて、ゆっくりとその場に座る。
安心したように眠った彼を私はぎゅっと抱きしめた。
「うふふ……あなたは大きくて、とってもあたたかいのね……」
ふわふわで、あたたかくて、とてもいい匂いがする。
私が稀に見る夢の話。
きっと、私が知らない、私の記憶の夢――。
◇
「――あ」
目覚めると、私の手は天井に伸びていた。
つうっと顔の横を落ちていく涙。どうやら泣いていたらしい。
「今の夢……」
頭を抑えて起き上がる。
でもその夢の記憶はもう掠れ、詳細を思い出せなくなっていた。
(でも、とても懐かしい夢だった気がする)
そうひとりごち、視線をふと横にずらす。
「――え?」
目を疑った。枕元に犬がいたからだ。
シベリアンハスキーサイズの黒い犬。ハスキーというよりは狼と呼んだほうがいいかもしれない。
真っ黒でもふもふのその子は凜々しい顔をして、私の傍に座っている。
「私を守っててくれたの?」
恐る恐る手を差し出すと、その子はすり寄ってきてくれた。
もふもふで可愛い。ずっと撫でていたくなる。
「ふふ……可愛い。あったかい」
「――目覚めたようだな」
声と共に扉が開き、朔人さんが現れる。
「あ……」
それと同時に抱きしめていた黒い狼が煙のように消えていく。
「気に入ったか? 今のは俺の式神で、俺の分身だ。お前を守るためにおいておいてよかったよ」
「……分身って」
煙となった狼は朔人さんの手の中に戻っていく。
つまり私は間接的に朔人さんに抱きついていたようなもので――。
自分の行動を思いだし、思わず顔が赤くなる。
「す、すみません私……なにもしらずに……」
「なに、恥ずかしがることはない。犬がいたら撫でたくなる。人として自然な反応だ。それよりも、腕を見せてみろ」
朔人さんは私の左腕を持ち上げ、巻かれていた包帯を解く。
黒く染まっていた傷が塞がり、縫っているような針の跡が見えた。
「うん。呪いは侵食しなかったようだ。とはいえ、裂傷だから念のため縫っておいた。しばらくは安静にしていろ」
「ありがとう……ございます」
「さて、夜も更けてきた頃だが……お前も今の状況を知りたいだろう」
話をしても? と尋ねられると私はこくりと頷いた。
朔人さんがいうように、窓の外は暗くて私は長い間寝ていたようだ。
でもお陰で眠気はない。それに、自分の身になにが起きているか早く知りたかったから。
そして朔人さんは私の前に座った。
「改めて。俺は犬神朔人。この犬神家の当主だ。お前を娘と欺き引き取った聡はその分家――正確にいうとお前の父の兄。つまりは叔父にあたる」
「じゃあお父さんは……」
「お前の父親は、犬神家の数多の分家を取り締まる『筆頭五家』の当主。簡単にいえば、この犬神家の中で二番目に偉い立場だったんだよ」
「そうだったんですか……」
「おや、もっと驚くかと思ったが」
だって現実味がなさすぎる。
ずっと母と二人で暮らしてきたのに、いきなり実の父親が凄い家の偉い人だった、なんて聞かされても。そもそも――。
「私は父の顔を知りませんから……」
「そうだろうな。悟は沙夜が幼い頃に行方を眩ませてしまったのだから」
「え……?」
お父さんが行方不明? そんな話、母からは一度も――。
「その反応は……母親からはなにも聞いていないのだな」
「は、はい……お母さんから『いつかちゃんと話す』といわれただけで、それ以外のことはなにも……」
「……無理もない。母はお前を守るために、お前を連れてこの家から逃げ出したのだから。しかし、さすがは優秀なキヨミズの巫女。しっかり娘の記憶に蓋をしたようだな」
「あの……さっきからなにを話しているのかよく意味が……」
目まぐるしく続く難しい話しについていけず困惑していると、朔人さんは私をじっと見つめた。
「沙夜。お前は幼い頃の記憶を失っているだろう」
「え――そんなこと……」
いわれるがままに記憶を辿り、固まった。
小学生になる前の記憶が一切ない。物心つく前だから、とは一切関係なく。その記憶がごっそりと抜けていた。
「今まで気にしたこと……なくて……」
「そうだろうな。そういうふうに母親が呪いをかけたのだろう」
「まじない……?」
いわれて気付いた重大な違和感に私は鳥肌が止まらない。
すると朔人さんは私の腕を掴み、ぐいっと抱き寄せた。
綺麗な顔が近づいて赤い瞳に私が映る。
「お前は十年前まではこの屋敷で過ごしていた。俺の、許嫁――後の贄嫁として。だから俺はお前をずっと探していたんだよ、沙夜」
「私が朔人さんの許嫁……?」
「……本当に覚えていないようだな」
動揺する私に、朔人さんは名残惜しそうに手を離す。
「なんでお母さんは私の記憶を……ううん、お母さんは一体何者だったんですか!? 私ずっと一緒に暮らしてきたのになにもしらなくて――」
「落ち着け。順を追って説明する」
次々浮かび上がる疑問を詰めると、朔人さんは困ったように両手を挙げた。
「まず、清水家とは代々稀有な力を持つ巫女が生まれる。邪を退け、清める。中でもお前の母はその才に恵まれていた。そしてお前の父だが――」
父の話にごくりと息を吞む。
「お前の父、名は悟という。悟も分家筆頭として優れた才を秘めていた。清水の巫女と悟が婚姻を結べば犬神家は安泰だ、と。それ故、お前は生まれた時から俺の許嫁として添えられた」
「生まれた時から決まっていた? そ、そんな今の時代に……?」
「この家はそういう家なんだ。まあ、当然それをよく思わない人間もいたということだ」
あの男のようにな、と朔人さんが囁く。
それはきっと養父――叔父のことだろう。
「お前は生まれながらにしてその身を狙われた。時には命を、時には道具として。それでも両親はお前に愛情を注いでいた。だが……ある日突然悟が行方を眩ましたんだ」
「え……」
「どこに消えたのかわからない。俺でも探せなかった。その直後だ――清水がお前を連れて忽然と姿を消したのは」
「犬神家から逃げた……って」
叔父たちがいっていた言葉を思い出す。
「清水は一切の痕跡を残さなかった。我々が血眼になって探しても見つけられない……清水の巫女の力というのは末恐ろしいものだ。いや、母の力――というものかもしれないな」
そういう朔人さんの表情は尊敬の念を表していた。
「お母さんはどうしてそんなことを……」
「沙夜には平凡に生きてほしかったのだろう。『贄嫁』になんてならずに、な」
贄嫁――養父がいっていた言葉だ。
「イヌガミに捧げられる花嫁……」
あの場所での光景を思い出し、ぶるりと体が震えた。
私が朔人さんの贄嫁となるということは――。
「朔人さんは私を食べるつもりなんですか?」
怯えながら見ると、朔人さんと目が合った。
赤い瞳が光っている。獰猛な狼に睨まれたように背筋が凍り、動けなくなる。
「そうだ。いつか、俺はお前を喰う。骨も残さず……お前の母のように」
傷だらけの母の亡骸を。空っぽの骨壺を思い出す。
あんな風に私も死ぬ。怖い。
逃げなきゃいけないのに、体が動かない。
それよりも、朔人さんの瞳から目がそらせない。
朔人さんはゆっくりと私に近づいて、顎をくいと持ち上げた。
「清水沙夜。お前は俺の贄嫁だ。それは逃れることはできない。例えお前が俺の前から逃げたとしても、だ」
「……っ」
――殺される。
でも、どうせ私は行き場所がなかった。家族だってもういない。
それならここで死んで早く両親の元にいったほうが――。
「だが、いつ喰うかは俺が決める。少なくとも、今でない」
「――え」
ぽん、と頭の上に手を乗せられた。
「――月城、入れ」
「はっ」
音も立てずにふすまが開かれた。
そこにはさっき車を運転していた男の人が跪いている。
「これは月城、俺の側近だ。なにかあればこの男に頼め」
「よろしくお願い致します。沙夜様」
「え……え……?」
月城さんという人は深々と私に頭を下げる。
一体なにが起きているかわからず、私は呆然と朔人さんを見上げる。
「私は……殺されるんじゃ?」
「なんだ。そんなに死にたいのか?」
「……いえ」
首を振ると、朔人さんはふっと口角を上げた。
「母が亡くなったことで、お前の記憶にも綻びが出てくるだろう。全て思い出したとき、どうするか決めればいい。それまでは、ここはお前の家だ」
そういうと朔人さんは立ち上がり、部屋の外へと向かう。
「夜更けに悪かったな。とにかく今は休め。これから嫌がおうにも大変な日々が待っているだろうからな。お前は犬神家の嫁なのだから」
そうして朔人さんは扉に手をかけ、こちらを向き変える。
「お前は俺の贄嫁だ。だからこそ、何人たりともお前に触れさせることは許さない。お前を喰っていいのは俺だけだ。だから安心して眠るといい」
ぱたん、そうして扉が閉じられる。
「安心しろ……っていわれても」
いつか自分を喰おうとしている人物の前で、安心なんてできるものなのだろうか。
部屋に一人残された私は、一抹の不安を抱えながらため息を零すのだった。
第一章 完
犬神を祀る家は必ず栄える。
犬神に捧げる贄が尽きるまで。
それはただの言い伝えではない。
犬神家には今も尚、神が宿り一族を見守り続けている。
一度栄華を極めた者たちはその失墜を恐れ贄を捧げ続けた。
贄となるのはいずれも年若き乙女たち。
それ故、犬神に捧げられた乙女たちは贄嫁と呼ばれた。
贄嫁は犬神から決して逃げられない。
もし恐れをなして逃げ出したなら――骨も残さず喰われるのだから。
◇
「アレはどこまでも追ってくる。決して逃げられない運命なの。でも、あなたならきっと――」
そういい遺して息を引き取った母の体には、獣につけられたような噛み跡や引っ掻き傷が無数に残されていた。
そして私は天涯孤独の身になった――。
「これより婚姻の儀を執り行う」
私は今、白無垢に身を包み花嫁になろうとしている。
広間には狩衣に造面姿の男たちがずらりと並び、厳粛に淡々と事を進めていく。
「こちらを一息で飲まれよ」
男の一人に朱の杯を差し出された。
赤黒い液体が揺蕩っている。とても美味しそうには思えない。
恐る恐る一口含むと、口内に広がる鉄の味。まるで生き血のように生臭い。
思わず吐き出しそうになるのをぐっと堪え、なんとか飲みきった。
「これをもって清水沙夜を犬神家当主、犬神朔人の贄嫁とする――」
その瞬間、私は「犬神沙夜」となった。
これから先のことを考えると不安で、たまらず体が震える。
いたたまれず目を泳がすと、隣に座っていた青年と目があった。
漆黒の髪。狼のような鋭い深紅の瞳に射貫かれれば体が動かなくなる。
同じ人間とは思えないほど、恐ろしくも美しい人だった。
「お前はもう俺から逃れることはできない――俺だけの花嫁だ」
この日、私は犬神朔人の贄嫁になった――。
*
――話は半年前に遡る。
「お前が沙夜だな」
それは母の葬式が終わった直後のこと。
父と名乗る人物が突然訪ねてきたのだ。
「俺はお前の父親だ」
「……父親」
そういわれてもぴんとこない。
私はずっと母と二人きりで過ごしてきたから。
幼い頃興味本位で父のことを聞いたことがあった。
『――そうね。やっぱり気になるよね、お父さんのこと』
いつも明るい母の表情が曇った。
『いつかちゃんと話すから、その時まで待ってくれる?』
悲しそうな母を見て、子供ながらに『ああ、これは聞いちゃいけないことなんだ』と悟る。
それから私が父のことを口にすることはなくなった。
そして「その時」も母が死んだことによって永遠にくることはないのだと思っていた。
ところが父は突然現れた。
髪をきっちりと撫でつけた厳格そうな人。
密かに想像していた父親像とはあまりにもかけ離れていた。
彼は玄関先から私たちが住んでいた古く小さな部屋を一瞥すると、奥にあった母の遺骨で目をとめる。
「よく十三年も生き延びたものだな。犬神家から逃げた恩知らずが」
「……え!?」
その人は家に土足で踏み込んだかと思えば、母の骨壺を思い切り床に叩きつけたのだ。
「な、なんてことするんですか!!」
「ふん、骨も残さず喰われたか……自業自得だな」
私は思わずそれから目をそらす。
虚しく床に転がった骨壺は――空だった。
なんとも奇妙なことに火葬された母は骨も残さず消えていたのだ。
『気味が悪い。あの遺体といい……まるで呪いね』
参列者は口々に呟いてそそくさと帰っていった。
無理もない。傷だらけの亡骸に、忽然と消えた骨。私ですら驚いたのだ。
最後まで火葬場に残った私は、呆然と母がいたはずの場所を見つめながら立ち尽くしていた。
(――母さんのこと、この人はなにか知っている)
でも、いきなり骨壺を倒すような人と話なんてしたくない。
本当にこの人が父親だって保証もどこにもないのだから。
「……お引き取りください」
骨壺を拾い上げながら私は男を睨みあげる。
すると彼は目をつり上げながら、私の腕を思い切り引いた。
「なにをいっている、さっさと行くぞ。そのためにわざわざお前を迎えに来てやったんだ」
「それはこちらの台詞です! 帰る場所なんてない! 私の親はお母さんだけで……私の家はここですっ!」
腕が抜けそうなほど強く引っ張られるが、私は全体重をかけて抵抗する。
なにが起きているかさっぱり理解できない。
父親なんて知らない。私の家族は母だけなのだから。
負けじと男を睨みつけると、次の瞬間頬に鋭い痛みが走った。
「……っ!」
平手打ちされた。
一瞬耳鳴りがして、頬にじんじんと痛みが広がっていく。
「違う。それは断じて違う」
男は冷たい瞳で私を見下ろす。
それは俗物でも見るかのような。人間を見る視線ではない。
「お前は生まれた時から犬神家の人間だ。お前は決して逃げられない」
「……逃げられない」
死に際に発した母の言葉を思い出した。
床に座り込んだままの私にようやく男は膝を突き、目をあわせた。
腫れた頬なんて気にも止めず、思い切りその手で私の顔を掴み上げ強制的に目をあわせられた。
「お前、年は幾つだ」
「……十六、です」
「いいか、よく聞け沙夜。十六のお前は、一般社会ではまだ子供として扱われる。お前が幾ら拒もうと、私と共にこなければならない」
一人で生きていけるのか?
そう聞かれてすぐに頷けなかった。
母の遺産はないに等しい。高校に入ってアルバイトをはじめたけれど、収入なんて微々たるもの。とても一人では食べていけない。
そもそも後見人がいなければ、家も借りられない。住む場所も、お金だってない。
どれだけ体がこの男についていくことを拒もうと、頭はそうするしかないと理解していた。
抵抗していた腕の力が抜けていく。
「そう、それでいい。お前は逃げられない」
もう一度繰り返された。
「……やっとだ。やっと……手に入れた」
いやらしく笑みを浮かべる男。
娘に再会できた喜びではない。自分に幸福が舞い込んだときのような、零れ落ちるような笑み。
「お前は犬神様に捧げられるために生まれ落ちた贄なんだよ――」
その言葉の意味を私が理解するのはもう少し先の話だ。
*
「ちょっと、沙夜!」
「……美和さん」
背後から金切り声が聞こえ、包丁を動かしていた手を止めた。
振り返ると気の強そうな女の子が私を睨んでいる。
彼女の名前は犬神美和――この犬神家の長女だ。
「お腹空いた! まだご飯できないの!?」
「すみません。あと少しでできるのでもう少し待って――」
ちらりと台所を覗き見た美和さんがうげっと顔をしかめる。
「味噌汁に卵焼き!? なんで朝からこんなしょっぼいもの食べないといけないのよ! もー……ルミがいてくれたときはよかったのに!」
犬神家――私でも聞いたことがある名家だ。
なんでも江戸時代よりも前から続いている家系らしく、特にこの十数年は経営・政治・芸能――全ての分野でこの一族の人たちが活躍している。
そんな名家に私が引き取られてからふた月が経った。
田園調布の高級住宅街。その隅にひっそりと建つ年季の入った豪邸。
そこに父は後妻の美埜里さんと、その娘で十五歳の美和さんと暮らしていた。
今はここが私の家――といえば聞こえはいいが、実際には私は「住まわせてもらっているだけ」の居候の身。
「沙夜さん。今日は本家の人が来るからきちんと掃除をしてってお願いしたでしょう? 階段の隅に埃が溜まっていたわよ」
「申し訳ありません、美埜里さん。食事ができ次第やり直しますので……」
「まったくもう……しっかりやってちょうだい」
「……はい」
「なんであの人も、こんな子引き取ったのかしら……」
深々と頭を下げていると、後からきた義母が呆れ混じりにため息をつかれた。
キッチンから二人が去っていけば、私はほっと息を吐きながら頭を上げた。
「さあ、美和。食事が終わったら今日はとびっきりのお洒落をするわよ!」
「本家のご当主様が私に会いに来てくれるのよね!」
「ええ、そうよ。きっと貴女を迎えに来てくれたに違いないわ!」
「私、ご当主様のお嫁さんになれるのかな!?」
リビングのほうから浮き足だった二人の話が聞こえてくる。
許嫁とか婚約者とかまるでドラマの中の話を聞いているようで現実味はない。
この立派な屋敷、そして裕福そうな家族――でも私には関係のない話だ。
たとえ娘だとしても私はあの家族の輪には入れないのだから。
私はただの居候。ただの使用人だ。
朝早く起きて、この広い家の掃除をして食事に洗濯――全てのことを任されていた。
美和さん曰く、ふた月前まで「ルミ」というお手伝いさんが来ていたらしいが、今はいなくなってしまったらしい。
そのため、新しいお手伝いさんが決まるまで私が家事を一任することになったのだ。
私を無理矢理ここに連れてきた父はなにもいわない。
私の存在なんてないように、あの日以来一言も目を合わせるどころか、一切口を聞いてくれなかった。
(――……お母さん)
煮立たせてしまった味噌汁の火を止めて、私はその場に崩れ落ちた。
しゃがみ込んで、滲む涙を押し殺す。
まるで地獄だ。
お母さんがいた頃は幸せだった。
狭い家で、二人で肩を寄せ合いながら、決して裕福じゃなかったけれど笑って生きていた。
あの日常はもう戻ってこない。お母さんが死んだあの瞬間から。
これなら施設で暮らしたほうがよほど幸せだっただろう。
《逃げられない》
母も、養父もそういっていた。
それが本当だとするのなら、私は一生こんな日々を過ごすんだろうか――。
*
――数時間後、私は部屋に篭もっていた。
部屋といっても屋根裏部屋のような、小さな窓がつけられただけの狭い場所。
とってつけられたような小さな机と、薄い布団だけが私に与えられたものだった。
家に来客がきたときは私は部屋から出てはいけない約束だ。
まるで私の存在を知られたくないかのように、私はじっと息を潜めていた。
「――ご当主様がわざわざ足をお運びになるなんて。こちらから伺いましたのに」
「いいや。どうしても一度顔を出したくてね」
一階から微かに父と客人の会話が聞こえてくる。
声音からして男性――それも若く聞こえる
「――が亡くなった――……その娘は――……」
「ご当主様、花嫁を探すために美和に会いにきてくださったのでしょう!? 私の娘は優秀なんです! 器量も良く、そしてご当主様とも年が近く――」
美埜里さんのよく通り声だけがはっきりと聞こえた。
(……気持ち悪い)
甲高い猫なで声がやけに耳障りで、私は耳を塞いでその場に蹲った。
この家から出ていっても、私に行く当てもない。
助けて。助けて。こんな日々、辛すぎる。
こんなことなら私もお母さんと一緒に消えてしまいたかった――。
そんなことを考えているうちに、眠ってしまっていたらしい。
うるさく聞こえていた話し声はいつの間にかやんでいて、窓の外の日は少しだけ傾き始めていた。
(お客さんは帰ったんだろうか)
ちらりと窓の外を覗いてみると、門の外には立派な黒塗りの車が止まっていた。
それに向かって一人の男性が歩いていくのが見える。
なにやら父と義母が必死に呼び止めているようにもみえるけれど。
(……綺麗な人)
少し長めの黒髪に、すらりと通った鼻筋。
遠目から見ても顔立ちの美しさがはっきりわかる。下手な芸能人よりもよっぽど綺麗な人だ。
「――っ!」
すると、その人は何かに気づいたようにはっとこちらを見た。
少し驚いたような赤い瞳と目があった。
何故か目をそらせなかった。
そして彼は確かに私を見て微笑んだような気がした。
(まずい!)
そこで我に返った私は慌てて口を塞ぎ、窓の下に身を隠す。
どきどきと心臓が脈打つ。
(どうしよう。気づかれていたらどうしよう)
ここは二階だ。おまけに窓は小さい。声も立てていないから気づかれることなんてまずない。
でも、もし気づかれていたら――後からあの人たちになにをされるかわからない。
ガタガタと震えて縮こまっていると、車の音が遠ざかっていくのが聞こえた。
(……よかった)
窓の外を確認してみると、そこにあった車は消えていた。
ほっと息をついていると、後ろから扉が開く鈍い音が聞こえた。
「――なに、してんのよ」
「……美和、さん?」
そこには美和さんと美埜里さんが立っていた。
美和さんの目は泣き腫らしたかのように真っ赤で、美埜里さんは恨みがましく私を睨んでいる。
「姿を見せるなっていったでしょ!?」
「ちがっ……私はずっとここに……!」
美和さんに首根っこを掴まれて、美埜里さんには有無をいわさず殴られた。
「なんでご当主様はアンタなんかを! 犬神家から逃げた卑怯者のくせに!」
「っ!」
二人の目は血走っていた。
まるでなにかに取り憑かれたように、私に馬乗りになって執拗に殴ってくる。
「なんであの人もお前やあの女に執着するの!? 妻は私だけなのに! あの人の娘は美和だけなのにっ!」
「――え?」
驚いた。
殴られた痛みも忘れるほどの衝撃だった。
(――……私はあの人の娘じゃない?)
それならなんで私はここに? 私の父親は――?
「二人とも、そこでなにをしている」
冷酷な声が部屋に響いた。
父が獣のような形相で私たちを見つめていた。あまりの圧に美和さんたちは戦いて、私の上から後ずさる。
「私が娘じゃないってどういうことですか」
私は起き上がり、鼻血を拭いながらその男を睨む。
「あなたは、誰?」
「それを知る必要はない。儀式の準備は整った」
ずんずんと進んできたその人は私の腕を無理矢理引いた。
「痛いっ! 離して!」
「当主がお前の存在に気づいた。手を出される前に、手を打たねば――」
抵抗もむなしく私は階段を引きずり下ろされる。
「今からお前を嫁がせる」
「嫁ぐ!? 私はまだ十六ですよ!?」
この年で本人の意思とは関係なしに結婚だなんて、時代錯誤にもほどがある。
「案ずるな。なにも実際に婚姻するわけではない、これはただの名称。ただの契約だ」
「……は?」
理解不能だった。
私は階段を転がるように引きずられ、立ち入ることを禁じられていた地下室まで連れてこられた。
「なにが本家当主だ! 分家とて……私だって、自分の力で栄華を築く! そのために私は――」
地下の長い廊下を歩くと一番奥の部屋に投げ入れられ、扉を閉じられる。
そこは洋風な家とは異質な和室だった。
全面障子で囲まれた窓のない部屋。四隅に蝋燭の灯りがちらついており、障子に私の影がうつるなんとも不気味な空間が広がっている。
「お前が嫁ぐのはイヌガミ様だ。お前は贄嫁となるんだよ――沙夜」
「だから一体なんの話――」
扉を開けようとしていると、背後から異質な気配がして息を吞んだ。
畳を引っ掻く音がする。真後ろで生暖かい呼吸音が聞こえる。
はっはっはっ――その呼吸の速さはまるで犬のような。
暗闇の中にぎらりと光る赤い瞳。
障子に移る大きな影がゆらりとその姿を現した。
「…………ひっ」
そこにいたのは、巨大で不気味な黒い犬の化け物だった。
――グルルルルルルルル――
全身が真っ黒な毛に覆われていて、肋骨が浮き出るほど痩せ細っている。
赤い目は血走っていて、鋭い牙が覗く口からは舌が垂れ、だらしなく涎が滴り落ちている。
それは鋭い爪を畳に食い込ませ、今にも私を襲おうと、低くうなり声を上げていた。
「あ、開けてっ! ここから出してくださいっ!」
必死に扉を開けようとするが、びくりともしない。
「無駄だ。その部屋には結界を張っている」
「結界!?」
「こんな貴重な贄をみすみす手放すわけはいかない。元よりお前は当主ではなく私のものになるはずだったのに……」
扉の向こうから聞こえる養父の声はやけに冷静だった。
儀式だとか結界だとか術だとか、もうワケがわからない。
(なんとかして逃げなくちゃ――)
命の危険を感じた私は、どうにか脱出手段を探す。
だけど、この部屋には窓がない。明かりは四隅に灯された蝋燭だけが頼り。
薄暗い室内の中で、獣の瞳が私を真っ直ぐ射抜いていた。
「――ひっ」
――グアアアアアアアアッ――
恐ろしさのあまり、私が声を上げた瞬間、化物が襲いかかってきた。
振り下ろされる鋭い爪。私は寸でのところでかわしたが、左腕を掠めてしまったらしい。
「いっ……」
血が滴る腕を押さえ、よろけながら反対側へ移動して距離を取る。
その化物は畳に点々と落ちた私の血を、なんとも美味しそうに舐めているではないか。
「そのイヌガミは酷く飢えているんだ」
後ずさっていると、ごつんと足に何かが当たった。
「……っ!!」
蝋燭の明かりに照らされたのは、人。人だったもの。
女の人が転がっている。暗がりではっきりとは見えないけれど、手足が所々ちぎれて酷い臭いがする。
そういえば、美和さんが少し前に家政婦が突然いなくなったといっていたような――。
「その場しのぎの贄なんか、腹の足しにもならなかったよ」
男は扉の向こうでくつくつと笑っていた。
「うっ……」
私はとうとうあまりの恐怖でその場に腰を抜かしてしまった。
凄惨な光景に吐き気がこみ上げ、思わず嘔吐してしまう。
「た、助け……誰か……」
助けを求める声はあまりにも小さく、震えていた。
「さあ、イヌガミよ! おまえがずっと求めていた最上の贄だ!」
―グルルルルラアアアアアアアッ!―
それが合図のように、化物が私に飛びかかってきた。
畳に倒され、肩に重い足がのし掛かり、鋭い爪が食い込む。
鼻が曲がりそうなほどの獣臭でむせ返りそうになる。
(――私は、死ぬの?)
こんなことのために生まれてきたの?
私はこの化物に食べられてしまうの? お母さんのように骨も残さずに――。
(いや……)
いやだ。死にたくない。私は、こんなところで死にたくない。
「……たすけ、て」
誰でもいいから。助けて。
化物の牙が迫る中。私が最後に思い浮かべたのは――さっき二階の部屋で見かけたあの青年。
あの時、身を隠さずに「助けて」「私をここから出して」と助けを呼んでいればよかった。
そうしたら……なにかが変わっていたのだろうか。
「――――っ!」
固く目を閉じても、痛みはいつまでも襲ってこない。
「――やっと見つけた」
男の人の声がする。低くて、どこか懐かしいような――。
「あ――」
目を開けると私は男の人に抱き寄せられていた。
獣のような赤い瞳が真っ直ぐ私を見つめている。
この人は――。
「俺を呼んだのは、お前だな」
「あなた……は」
突然現れた青年を私は呆然と見上げる。
この人は、さっき家から出ていったはずの赤い瞳の男の人だ――。
「俺を本家から遠ざけ、地下に大層な結界まで張り、随分周到に隠していたようだが……」
彼は私の肩を強く抱き寄せながら、養父をぎろりと睨む。
「これはどういうことだ。申し開きがあるなら聞いてやろう、聡」
「――っ!」
放たれた殺気に、養父がびくりとたじろいだ。
「わ、私は犬神家のさらなる繁栄のためにと!」
「現在は筆頭五家以外のイヌガミの使役は禁じられているはずだ。おまけに勝手に贄まで喰らわせ、イヌガミを堕としただけでなく――」
足元に転がる亡骸を一瞥し、彼は私を見つめる。
肩を抱く手にぐっと力が込められた。
「あろうことか沙夜を贄に捧げようなど」
静かな声音。だけどそこには確かに怒りと殺気が込められていた。
「……っ! おのれ……!」
養父はぎりぎりと唇を噛み、私たちを睨む。その怒りに呼応するようにイヌガミが低く唸る。
『――ふーーーーっ』
前足を床にこすりつけながら、青年を威嚇している。
牙を見せ、口元を震わせ、今にも襲いかかろうとしているけれど――。
「……泣いてる」
ぽつりと呟いた私の言葉に青年が目を丸くしてこちらを見た。
どうして自分でもそんなことを口走ったのかわからない。でも、自分の頬に涙が伝っていることに気付く。
「苦しんでる。助けて……って」
「お前――」
先程は恐怖でなにも感じなかった。
だけど、今ははっきり聞こえてくる。
あの化物――ううん、イヌガミの感情が。心の声が。
彼は苦しんでいるだけだ。
苦しくて、痛くて、お腹が空いて……でも自分ではどうしようもできなくて。
今すぐこの苦しみから解放されたいと、救いを求めて藻掻いている。
『ぐるるるるるるるるるっ』
うなり声を上げるイヌガミの目から血の涙が零れ出す。
「……助けて。お願い、あの子を助けて」
私は涙を流しながら、思わず青年の袖を掴んだ。
「目を、閉じていろ――沙夜」
名前を呼ばれた気がすると、彼は静かに私の目を手で覆った。
暗くなる視界。次の瞬間、イヌガミが地面を蹴って襲いかかってくる。
「今、楽にしてやろう」
「――やめろおおおおおおっ!」
聞こえたのは、青年の冷静な声と養父の叫び声。
そして何かがぶつかり合う激しい音が何度か聞こえて、部屋を漂っていた禍々しい空気が消えた気がした。
「――もう、目を開けていいぞ」
そう言われて目を開けると、目の前にあのイヌガミが倒れていた。
それは眠るように目を閉じて、足先から灰のようにほろほろと崩れて消えてしまった。
「何故……何故だ! 私のイヌガミが――!」
イヌガミが消え、養父は膝から崩れ落ちきっと私を睨み付けた。
「貴様のせいだ沙夜! お前がいなければこんなことには!! 本来なら弟ではなく兄である私が――」
彼の慟哭の意図はわからない。
でも、私を恨んでいることだけは伝わった。
「耳を傾けるな。不安なら俺を見ていろ」
そういわれて視線をあげると、綺麗な顔が近くに見え、私はどこを見ていいかわからず目を泳がせる。
「犬神聡、お前の沙汰は追って伝える。二度目はないと思え」
「ぐううううっ……覚えていろ……」
殺気に怯んだ養父は顔を青ざめさせその場に崩れ落ちたのだった。
そして青年は私を抱いたまま屋敷の外に向かう。
まぶしい日差し。外の空気を吸うのはとても久しぶりに思えた。
「お前、名前は?」
「清水沙夜……」
そう告げると、彼は突然顔を近づけて私の匂いをくんくんと嗅いだ。
突然のことに私は思わず顔を赤らめる。
「お前、やはりいい香りがするな。俺の鼻に狂いはなかった」
「……え、えっ?」
そして青年はにっと笑い、こういったのだ。
「俺は犬神朔人。お前は今日から俺の花嫁だ」
「花嫁……」
「帰るぞ、月城」
「――はっ」
状況も整理できないまま、私は朔人さんに抱きかかえられたまま、養父の家を後にした。
玄関前には灰色の髪の温厚そうな青年が立っていて、私はそのまま見るからに高級そうな黒塗りの車に乗せられる。
「あ、あの……どこに向かって……」
後部座席。朔人さんの隣で縮こまりながら、私は恐る恐る尋ねた。
車は養父の家を離れ、都心の方へと向かっていた。
「屋敷に帰る。これ以上、お前をあんな穢れた場所に置いておくわけにはいかないからな」
「さっきのは一体なんだったんですか。イケニエとか、イヌガミとか……」
先程の光景が脳裏に過る。
あまりにも非現実的な体験に、私は夢でも見ていたのかと錯覚してしまう。
だけど左腕の痛みは現実で。彼が助けに来てくれなかったら今頃死んでいたのかと思うと、体が震えだした。
「あれはイヌガミ。犬神家に伝わる式神だ。きちんと飼い慣らせば有益なものだが、あの様に穢れに満ちてしまうと堕ち神となり暴走してしまう」
あの家はもうだめだな、と朔人さんは窓の外をみながらぽつりと呟く。
運転している月城さんが同意するようにこくりと頷いたのが、ミラー越しに見えた。
「その話は追々するとして……だ、沙夜」
「は、はいっ」
いきなり顔を近づけられて身じろぐ。
「お前はいつからあの家にいた」
「ひと月前に母が亡くなって、その葬儀の後に――」
経緯をかいつまんで話すと、朔人さんの眉間にみるみる皺が寄っていく。
額に手を乗せ深いため息をついた。
「抜かった……分家外れと侮っていたが、アイツも一応筆頭五家の出だったな」
「……すみません」
「何故お前が謝る。謝るべきは俺のほうだ。このひと月の間、本家を留守にしていてな。迎えが遅くなってしまって申し訳なかった」
「い、いえ……貴方が謝ることでは……」
真っ直ぐな眼差しを向けながら、朔人さんは謝罪を述べた。
朔人さんは私を助けてくれた。むしろ私は感謝すべきだというのに、どうして謝るのだろう。
申し訳なくて両手を振っていると――ぐらりと視界が歪んだ。
「あ、れ――」
急に体の力が抜ける。
前のめりに倒れかけた体を朔人さんが受け止めてくれた。
「すみま――っ」
謝ろうとして左腕に激痛が走った。
熱された鉄でも押しつけられているかのように、焼けるような痛みが走る。
「お前……あのイヌガミに傷を負わされたのか」
その視線は私の左腕に向けられる。
返事をする気力がなくて、こくりと頷くと朔人さんは小さく舌打ちをした。
「――話より手当が先だな。月城、急げ」
「畏まりました」
ぐん、と車の速度が上がる。
私はなんとか体を起こそうとするが、そのまま朔人さんは私の頭を自分の膝に乗せた。
「目を閉じて、深く呼吸をしろ。少しは痛みがマシになるはずだ。心配するな。俺が必ず助ける」
朔人さんは上着を掛けてくれて、ゆっくり背中を摩ってくれた。
その動きにあわせて呼吸をすると幾分か痛みが和らいだ気がした。
(――いい、匂い)
柔軟剤?香水?ううん、お香のような優しくてほんのり甘い香りがする。
それでも左腕の痛みは凄まじくて、いつの間にか私は意識を手放していた。
*
意識がぼんやりとしている。
誰かに抱き上げられて動いているかのような。
目を開けようと思っても、開けられない。
指一本も動かせない。ただ、左腕が熱い。
「――急ぎ、薬湯――……」
「月――筆頭……招集――」
「彼女は俺の――――――」
聴覚だけは生きていて、途切れ途切れに色々な話が聞こえる。
忙しそうに動き回る足音。水の音が聞こえる。
状況が変わっていく中で、私を抱く腕の力とあの香りだけは変わらずずっと傍にいてくれた。
(あたたかい……)
ふと、体が温かくなった。
お風呂でも入っているかのような心地よさ。つんと、薬草のような香りが鼻をつく。
「――――」
少しだけ左腕の痛みが和らいだ気がして、ゆっくりと瞼を開けた。
「――――え」
そして私は目を疑う。
私はお風呂に入っていた。正確にいうととても大きな檜風呂のような浴槽。
そこには白濁としたお湯と、薬草が浮かんでいて。そこに私は肌襦袢を着せられて浸かっている。
それにも驚いたけれど、今驚くべきはそこじゃなくて――。
「なんだ、目覚めたのか」
そこには朔人さんも一緒にいたのだから。
「――な、なななっ!」
男の人とお風呂――!?
状況を理解した瞬間、私の顔は真っ赤になって体を抱えた。
「なにを慌てている」
「だ、だって!その、私……いきなり、そんな!」
思い返せば婚約者とか、花嫁とか色々いわれていたような気がしたけれど。
だけど私はまだ十六歳で、恋愛経験なんてほぼ皆無に等しくて。
それなのにいきなりこんな状況になったら慌てるなといわれても慌ててしまう。
「なにを勘違いしている。これは治療だ」
「――へ?」
朔人さんは真面目そのもので、その視線は私の左腕に向けられている。
そのまま彼の視線をたどった私は目を丸くした。
「これ……」
襦袢の袖が捲られ素肌が露わになった左腕。
イヌガミの爪で傷付けられた二の腕の傷が、赤黒く染まっていた。
血が固まっているわけじゃない。文字通り傷口が黒く、傷の周辺は煤でもついているかのように真っ黒に染まっている。
「堕ち神に負わされた傷は『呪い傷』となって体を蝕む。このまま放っておくと、腕が腐り落ちるぞ」
「腐――」
衝撃的な言葉に私はすぐに抵抗をやめた。
「この傷は犬神家の血筋しか治すことができない。同性を呼ぶ時間がなかったからな、俺で許せ」
よく見ると朔人さんも着物を着ていて、お互い全裸ではない。本当にこれはただの治療のようだ。
(勝手に勘違いして……私ったら……恥ずかしすぎる)
「触るぞ――」
穴があったら入りたいとはまさにこのこと。
自己嫌悪に浸ろうとするのもつかの間、朔人さんの手が傷に触れた。
「――っ!」
左腕に激痛が走る。藻掻こうとすると朔人さんはがっちりと私の体を押さえつけた。
「痛むだろうが耐えてくれ。毒を抜ききらないと傷が治らない」
傷から血を掻き出すように触られる。
白いお湯が赤く黒く染まっていく。
「この湯は特別な薬湯だ。呪い傷の毒を抜き、お前の体を清めてくれる。もう少しだ――」
「っ――!」
痛みから逃れるように体を動かせば、ばしゃばしゃとお湯が揺れる。
目に涙を滲ませ、私は無意識のうちに朔人さんにしがみ付いていた。
朔人さんは私の左腕を持ち上げ、傷口に口をつけたかと思えばそのままじゅっと血を吸った。
「――よし、これでいい。よく頑張ったな」
口から血を吐き、唇の端についた血を拭いながら私を見て微笑んだ。
私は腕の痛みと、お湯の温かさと、朔人さんと二人きりの状況に頭がクラクラして――。
「――おや。ウブなヤツだな」
再び意識を失ってしまうのだった。
◇
夢を見た。
私は子供で、その目の前に大きな黒い犬がいた。
「……どうしたの?」
私の数倍も大きなその犬は、私を威嚇している。
目を血走らせて、牙を剥き出して。
誰も近づくなというように、唸っている。
「怪我……してるの?」
その犬の体は傷だらけだった。
黒い毛でよく見えないけれど、ぽたぽたと血が滴り落ちている。
毛を逆立たせ、私を拒絶しようとする彼がとても辛そうで、苦しそうで。
私はそっと手を伸ばした。
『――触ルナ!』
「――っ!」
吼えられた拍子に、牙が手の甲に当たった。
血が流れる私の手を見て、一瞬その子はたじろいだ。
「大丈夫だよ」
それでも私は手を伸ばした。
私の目からはぽろぽろと涙が零れる。
傷が痛いのもあったけれど、あまりにもその子が辛そうだったから。
「大丈夫だよ。あなたはひとりじゃないよ。わたしがいるよ」
最初はそっと鼻先に触れる。
その犬は唸るのをやめ、眉間を撫でさせてくれた。
そして彼は謝るように、私の傷をぺろりと舐める。
「おちついた? もう、大丈夫だよ」
頭を優しく撫でるとその子は気持ちよさそうに目を細めて、ゆっくりとその場に座る。
安心したように眠った彼を私はぎゅっと抱きしめた。
「うふふ……あなたは大きくて、とってもあたたかいのね……」
ふわふわで、あたたかくて、とてもいい匂いがする。
私が稀に見る夢の話。
きっと、私が知らない、私の記憶の夢――。
◇
「――あ」
目覚めると、私の手は天井に伸びていた。
つうっと顔の横を落ちていく涙。どうやら泣いていたらしい。
「今の夢……」
頭を抑えて起き上がる。
でもその夢の記憶はもう掠れ、詳細を思い出せなくなっていた。
(でも、とても懐かしい夢だった気がする)
そうひとりごち、視線をふと横にずらす。
「――え?」
目を疑った。枕元に犬がいたからだ。
シベリアンハスキーサイズの黒い犬。ハスキーというよりは狼と呼んだほうがいいかもしれない。
真っ黒でもふもふのその子は凜々しい顔をして、私の傍に座っている。
「私を守っててくれたの?」
恐る恐る手を差し出すと、その子はすり寄ってきてくれた。
もふもふで可愛い。ずっと撫でていたくなる。
「ふふ……可愛い。あったかい」
「――目覚めたようだな」
声と共に扉が開き、朔人さんが現れる。
「あ……」
それと同時に抱きしめていた黒い狼が煙のように消えていく。
「気に入ったか? 今のは俺の式神で、俺の分身だ。お前を守るためにおいておいてよかったよ」
「……分身って」
煙となった狼は朔人さんの手の中に戻っていく。
つまり私は間接的に朔人さんに抱きついていたようなもので――。
自分の行動を思いだし、思わず顔が赤くなる。
「す、すみません私……なにもしらずに……」
「なに、恥ずかしがることはない。犬がいたら撫でたくなる。人として自然な反応だ。それよりも、腕を見せてみろ」
朔人さんは私の左腕を持ち上げ、巻かれていた包帯を解く。
黒く染まっていた傷が塞がり、縫っているような針の跡が見えた。
「うん。呪いは侵食しなかったようだ。とはいえ、裂傷だから念のため縫っておいた。しばらくは安静にしていろ」
「ありがとう……ございます」
「さて、夜も更けてきた頃だが……お前も今の状況を知りたいだろう」
話をしても? と尋ねられると私はこくりと頷いた。
朔人さんがいうように、窓の外は暗くて私は長い間寝ていたようだ。
でもお陰で眠気はない。それに、自分の身になにが起きているか早く知りたかったから。
そして朔人さんは私の前に座った。
「改めて。俺は犬神朔人。この犬神家の当主だ。お前を娘と欺き引き取った聡はその分家――正確にいうとお前の父の兄。つまりは叔父にあたる」
「じゃあお父さんは……」
「お前の父親は、犬神家の数多の分家を取り締まる『筆頭五家』の当主。簡単にいえば、この犬神家の中で二番目に偉い立場だったんだよ」
「そうだったんですか……」
「おや、もっと驚くかと思ったが」
だって現実味がなさすぎる。
ずっと母と二人で暮らしてきたのに、いきなり実の父親が凄い家の偉い人だった、なんて聞かされても。そもそも――。
「私は父の顔を知りませんから……」
「そうだろうな。悟は沙夜が幼い頃に行方を眩ませてしまったのだから」
「え……?」
お父さんが行方不明? そんな話、母からは一度も――。
「その反応は……母親からはなにも聞いていないのだな」
「は、はい……お母さんから『いつかちゃんと話す』といわれただけで、それ以外のことはなにも……」
「……無理もない。母はお前を守るために、お前を連れてこの家から逃げ出したのだから。しかし、さすがは優秀なキヨミズの巫女。しっかり娘の記憶に蓋をしたようだな」
「あの……さっきからなにを話しているのかよく意味が……」
目まぐるしく続く難しい話しについていけず困惑していると、朔人さんは私をじっと見つめた。
「沙夜。お前は幼い頃の記憶を失っているだろう」
「え――そんなこと……」
いわれるがままに記憶を辿り、固まった。
小学生になる前の記憶が一切ない。物心つく前だから、とは一切関係なく。その記憶がごっそりと抜けていた。
「今まで気にしたこと……なくて……」
「そうだろうな。そういうふうに母親が呪いをかけたのだろう」
「まじない……?」
いわれて気付いた重大な違和感に私は鳥肌が止まらない。
すると朔人さんは私の腕を掴み、ぐいっと抱き寄せた。
綺麗な顔が近づいて赤い瞳に私が映る。
「お前は十年前まではこの屋敷で過ごしていた。俺の、許嫁――後の贄嫁として。だから俺はお前をずっと探していたんだよ、沙夜」
「私が朔人さんの許嫁……?」
「……本当に覚えていないようだな」
動揺する私に、朔人さんは名残惜しそうに手を離す。
「なんでお母さんは私の記憶を……ううん、お母さんは一体何者だったんですか!? 私ずっと一緒に暮らしてきたのになにもしらなくて――」
「落ち着け。順を追って説明する」
次々浮かび上がる疑問を詰めると、朔人さんは困ったように両手を挙げた。
「まず、清水家とは代々稀有な力を持つ巫女が生まれる。邪を退け、清める。中でもお前の母はその才に恵まれていた。そしてお前の父だが――」
父の話にごくりと息を吞む。
「お前の父、名は悟という。悟も分家筆頭として優れた才を秘めていた。清水の巫女と悟が婚姻を結べば犬神家は安泰だ、と。それ故、お前は生まれた時から俺の許嫁として添えられた」
「生まれた時から決まっていた? そ、そんな今の時代に……?」
「この家はそういう家なんだ。まあ、当然それをよく思わない人間もいたということだ」
あの男のようにな、と朔人さんが囁く。
それはきっと養父――叔父のことだろう。
「お前は生まれながらにしてその身を狙われた。時には命を、時には道具として。それでも両親はお前に愛情を注いでいた。だが……ある日突然悟が行方を眩ましたんだ」
「え……」
「どこに消えたのかわからない。俺でも探せなかった。その直後だ――清水がお前を連れて忽然と姿を消したのは」
「犬神家から逃げた……って」
叔父たちがいっていた言葉を思い出す。
「清水は一切の痕跡を残さなかった。我々が血眼になって探しても見つけられない……清水の巫女の力というのは末恐ろしいものだ。いや、母の力――というものかもしれないな」
そういう朔人さんの表情は尊敬の念を表していた。
「お母さんはどうしてそんなことを……」
「沙夜には平凡に生きてほしかったのだろう。『贄嫁』になんてならずに、な」
贄嫁――養父がいっていた言葉だ。
「イヌガミに捧げられる花嫁……」
あの場所での光景を思い出し、ぶるりと体が震えた。
私が朔人さんの贄嫁となるということは――。
「朔人さんは私を食べるつもりなんですか?」
怯えながら見ると、朔人さんと目が合った。
赤い瞳が光っている。獰猛な狼に睨まれたように背筋が凍り、動けなくなる。
「そうだ。いつか、俺はお前を喰う。骨も残さず……お前の母のように」
傷だらけの母の亡骸を。空っぽの骨壺を思い出す。
あんな風に私も死ぬ。怖い。
逃げなきゃいけないのに、体が動かない。
それよりも、朔人さんの瞳から目がそらせない。
朔人さんはゆっくりと私に近づいて、顎をくいと持ち上げた。
「清水沙夜。お前は俺の贄嫁だ。それは逃れることはできない。例えお前が俺の前から逃げたとしても、だ」
「……っ」
――殺される。
でも、どうせ私は行き場所がなかった。家族だってもういない。
それならここで死んで早く両親の元にいったほうが――。
「だが、いつ喰うかは俺が決める。少なくとも、今でない」
「――え」
ぽん、と頭の上に手を乗せられた。
「――月城、入れ」
「はっ」
音も立てずにふすまが開かれた。
そこにはさっき車を運転していた男の人が跪いている。
「これは月城、俺の側近だ。なにかあればこの男に頼め」
「よろしくお願い致します。沙夜様」
「え……え……?」
月城さんという人は深々と私に頭を下げる。
一体なにが起きているかわからず、私は呆然と朔人さんを見上げる。
「私は……殺されるんじゃ?」
「なんだ。そんなに死にたいのか?」
「……いえ」
首を振ると、朔人さんはふっと口角を上げた。
「母が亡くなったことで、お前の記憶にも綻びが出てくるだろう。全て思い出したとき、どうするか決めればいい。それまでは、ここはお前の家だ」
そういうと朔人さんは立ち上がり、部屋の外へと向かう。
「夜更けに悪かったな。とにかく今は休め。これから嫌がおうにも大変な日々が待っているだろうからな。お前は犬神家の嫁なのだから」
そうして朔人さんは扉に手をかけ、こちらを向き変える。
「お前は俺の贄嫁だ。だからこそ、何人たりともお前に触れさせることは許さない。お前を喰っていいのは俺だけだ。だから安心して眠るといい」
ぱたん、そうして扉が閉じられる。
「安心しろ……っていわれても」
いつか自分を喰おうとしている人物の前で、安心なんてできるものなのだろうか。
部屋に一人残された私は、一抹の不安を抱えながらため息を零すのだった。
第一章 完