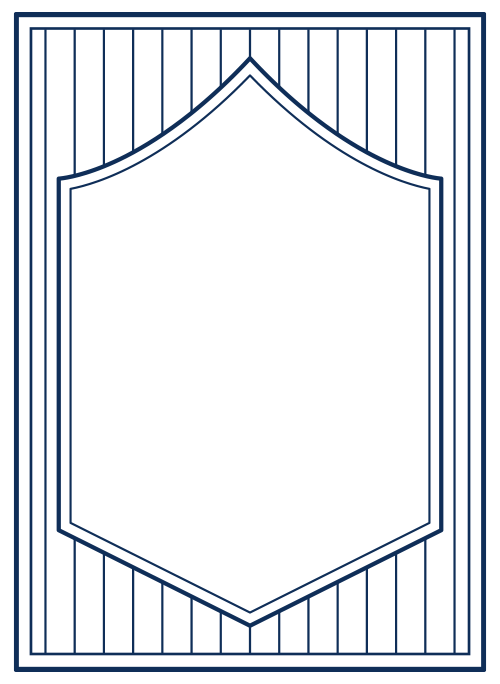一
よもや、この美少女がこんな我儘な性格だとは思いもよらなかった。
ハイラル教の悪魔は堕ちた天使だと言う話だがミラを見せれば誰でも納得するに違いない。
アスラル教には悪魔がいないのが残念だ。
神の使い――神徒――はいるがハイラル教の「天使」とは少し意味合いが違う。
「またミラ様がやってるぜ」
「ラース様もキシャル様を特別扱いしてるし」
「セネフィシャル様も可愛い女の子には逆らえない、か」
ったく!
ラースの評判まで落ちてるじゃないか!
ミラは窓際にいた。
窓を乗り越えて抜けだそうとしたところを神官長に捕まったのだろう。
こんな下級神官も通るところで神官長にまで口答えして……。
カイルは憤然としてミラに向かっていった。
「こんなとこで何やってんだよ!」
「あんたには関係ないでしょ!」
「場所をわきまえろよ!」
「知らないわよ!」
「神殿長やラースまで悪く言われてるんだそ!」
「私が言わせてるわけじゃないでしょ!」
「お前のせいだろ!」
「やめな……!」
「そこまで」
ラースの落ち着いた声が聞こえた途端、全員が黙り込んだ。
本来ならラースの上司であるはずの神官長まで口を噤んでしまった。
「神官長、ここは私が」
神官長は肩の荷が下りたというような表情で奥へ戻っていった。
「カイル、君は執務室へ戻りなさい」
「はい」
「ミラ、君も自分の部屋へ行きなさい」
素直にラースの言葉に従おうと踵を返したカイルは驚いて足を止めた。
自室へ帰れというのは何もしなくていいという意味だからサボるのも神殿を抜け出すのも自由という事だ。
ミラはすぐにどこかへ行ってしまった。
「ラース! それでは……!」
「いいから執務室へ行きなさい」
抗議しようとしたカイルをラースはやんわりと止めた。
「ですが……!」
「ミラの心配をするのは君の仕事ではない」
口を出すなと言っているのだ。
「他の神官達からなんて言われてるか知ってるんですか!?」
「ミラを任されたのは私だ」
ラースはカイルの抗議を取り合わずに行ってしまった。
なんでミラだけ……。
カイルは拳を握り締めた。
翌日、カイルはマイラと神殿に向かって歩いていた。
風が草を揺らしながら草原を渡っていく。
二人はレラスの町にいた病人を治しに行った帰りだった。
そのとき向こうからミラが歩いてきた。
「ミラ! また勝手に抜け出してきたな!」
「それが何よ」
カイルの言葉にミラが言い返す。
マイラも無言でミラを睨んでいる。
そこへ背後から足音が聞こえてきた。
振り返ると初老の男が近付いてくる。
橙色の敷布のような服。
セルケト教の神官?
なんでセルケト神官がこんなところに……。
カイルは首を傾げた。
セルケト教というのは世界は対立する二つのものから出来ている、という考えの二神教だ。
この辺はアスラル教かハイラル教が大半を占めていてセルケト教徒は珍しい。
その他、有象無象の民間信仰も多々あるからセルケト神官ではないかもしれないが。
「あなたは?」
男はカイルの問いに答えず、反対に、
「ケナイのマイラというのはどっちだ?」
と訊ねてきた。
「ケナイにいたマイラは私、ケナイから来たマイラはそっち」
ミラがマイラに視線を向けた。
男がミラとマイラを見比べる。
「なるほど、替え玉か。二人揃ってなければ騙されるところだった」
替え玉?
カイルが眉を顰めたとき、マイラが唇を噛かんで拳を握り締めた。
そうか……。
ミラはケナイではマイラと呼ばれていた。
最初、今のマイラは〝アスラル神の化身〟であるミラ(以前はマイラ)にあやかって同じ名前にしたのかと思ったが、よく考えたら同い年なのだからそれは考えづらい。
生まれたばかりの頃に既にマイラの恩恵が知られていたのなら無くはないかもしれないが。
知らなかったとしたら小さな村で同い年の子に同じ名前を付けるだろうかと疑問に思っていたのだ。
それでマイラに訊ねたら本名は違うのだが、ここに入ったら何故かマイラと名乗るように言われたのだとか。
普通、神官になったからと言って改名はしない。
同じ村の出身で同い年の強い魔力を持つ少女。
人目を欺く為に二人の名前を変えたのだ。
「〝素晴らしきもの〟ミラ、か……」
男が皮肉な笑みを浮かべ、マイラは逆に侮辱されたような表情になった。
確かにマイラから〝素晴らしきもの〟のミラになったのだとしたらマイラを名乗らされる事になった彼女にとっては屈辱だろう。
「レラスのセネフィシャルのやりそうな事だな」
男はそう言うとミラに手を伸ばした。
「ケナイのマイラ、一緒に来てもらおう」
「悪いがお断りする」
突然ラースの声が聞こえてきた。
男の腕が止まる。
カイル達が振り返ると後ろにラースが立っていた。
「うちの神官に用があるなら神殿長に話を通して頂こう」
「レラスのセネフィシャルか」
ラースと男は一瞬睨み合った。
二人の魔力が高まる。
すぐに男は視線を逸らした。
「今日のところは帰る事にしよう」
そう言うと男は去っていった。
二
数日後、カイルは書類を抱えて執務室へ向かっていた。
これは本来ミラがやるべき仕事である。
ミラにやらせようとしたのだが散々口論した末に逃げられてしまった。
「失礼します」
カイルが部屋へ入っていくとラースは書類から顔を上げた。
「ありがとう。そこへ置いといてくれ」
ラースはこれがミラの仕事だと知っているにも関わらずカイルが持ってきたのを見ても何も言わなかった。
「ラース、ミラを何とかして下さい」
つい恨みがましい口調になってしまった。
けれど自分が慕っている相手が別の人を贔屓しているのを見るとどうしても妬ましく思ってしまう。
ラースが苦笑した。
「カイル、ミラは少々我儘かもしれないが……」
「少々どころじゃありません」
「悪い子じゃないんだ」
「仕事をサボってるのに?」
「ちょっと訳ありでね。本当は良い子なんだ。仲良くしてくれ」
「冗談じゃありません!」
反射的に強い口調で言い返してしまい、すぐに後悔した。
「すみません。でもミラがあの調子じゃ……」
ラースは溜息を吐いた。
「分かった。なんとかしよう」
ラースが身振りで下がるように促した。
カイルもそれ以上は何も言わずに部屋を出た。
翌日、カイルはミラが神殿を抜け出そうとしているところを捕まえた。
ラースには放っておくように言われたが、やはり知らんふりは出来ない。
「ミラ! いい加減にしろよ!」
「そっちこそ!」
「ラースに迷惑掛けるなよ!」
「あんたには関係ないでしょ!」
「お前がサボってる仕事、誰がやってると……!」
「君達、ちょっといいか」
いつの間にかラースが側に来ていた。
カイルとミラが口を噤む。
ラースは二人を連れて奥へと向かった。
その間、ミラは不機嫌な顔で黙りこくっていた。
カイルは横目でミラの方を窺った。
これが、ちょっとでも良いなと思っていた女の子だとは……。
ミラがこんなに可愛くなければ誰もラースや神殿長が色香に惑わされてるなんて思わないだろうに。
ラースは上級神官用の執務室へ入ると二人の方を向き直った。
カイルとミラは互いに離れた場所に立つ。
「カイル、ミラ。同僚なんだし、そろそろ仲良くなってもいい頃じゃないか?」
「冗談じゃないわよ!」
「それはこっちの台詞だ!」
「二人とも……」
喧嘩になりそうな二人の間に入ったラースがガブリエラに視線を走らせた。
見るとガブリエラは本で顔を隠して笑いを堪えている。
「ミラ」
ラースの声が僅かに厳しくなった。
ミラが渋々といった様子でラースを見上げ、ついでに軽く両手を上げた。
「分かったわよ。喧嘩はしない。それでいいでしょ」
「私は君達に仲良くしてほしいんだ」
「絶対にイヤ!」
「喧嘩しないだけじゃダメなんですか?」
「どうしても嫌か?」
「どうしてもイヤ!」
「カイル?」
ラースはカイルに訊ねるように首を傾げた。
「僕がいいって言ってもミラが……」
「じゃあ、ミラが仲良くするって言ったら仲良くしてくれるんだね」
「え……まぁ」
ミラが余計な事を、という顔で睨む。
「ミラ」
ラースがミラに向き直った。
神官長にまで口答えするミラが素直に言うことを聞くとは思えないが……。
「イヤよ」
やっぱり……。
「ミラ、命令だ」
ラースがきっぱりと言った。
断固拒否するかと思ったが、
「……はい」
ミラは承服した。
思い切り不服そうだったが。
カイルは信じられない思いで二人を交互に見た。
ラースの命令には従うのか……。
と言う事は今まで仕事をしろと命じた事がなかったのだ。
少なくともラースは。
仕事をさせる気がないならなんで神官にさせておくんだ?
「約束だ。仲良くしてくれ」
ラースは満足した様子で部屋から出ていった。
見るとガブリエラもいつの間にかいなくなっていた。
ミラのお守りを押し付けられたという事か……。
カイルは肩を落とした。
カイルが見張っていればラースの負担は減るだろうが……。
「ラースったら、子供か何かと勘違いしてんじゃないの?」
それまで神妙な顔をしていたミラはラースがいなくなった途端、態度が変わった。
元に戻ったと言うべきか……。
「ったく、あんたのせいで出掛けられなかったじゃない」
ミラは捨て台詞を吐くと女性神官用の居住区の方へと帰っていった。
やっぱりあんな約束するんじゃなかった……。
翌日、カイルは神殿の奥へ向かっていた。
上級神官用の執務室で勉強するためだ。
最初、いつもの場所で外を眺めていた。
が、下級神官も通る廊下のため嫌でも噂話が耳に入ってしまうのだ。
さっきも初っ端からラースの嫌な噂を聞かされてしまった。
ラースがミラといい仲だの、神殿長とラースがミラを取り合ってるだの、果てはガブリエラとラースとミラの三角関係なんて言うのまで……。
どうして恋愛が御法度の神官がそういう事を言うんだよ!
それもこれもミラのせいで……。
苛々しながら歩いていると視界の隅にミラを捉えた。
見なかった事にしようか……。
だがミラがいなくなればラースが心配するだろう。
「どこに行くの?」
ミラはカイルを無視し掛けてラースとの約束を思い出したらしい。
「どこだっていいでしょ」
返事だけはあった。
しかしそのまま行ってしまう。
カイルはミラの後を追い掛けた。
「待てよ」
「随いてこないでよ」
「でも仲良くしろって……」
「仲良くしたいわけ? 私と」
カイルは言葉に詰まった。
「いい? お互い近くにいなければ仲良くする必要もないでしょ。分かったらあっち行って」
我儘だからといってバカとは限らない。
悪知恵だけは働くようだ。
三
ミラは炊事場へと入っていった。
つまみ食いか? と思って中を覗くとミラは真っ直ぐ勝手口を目指している。
炊事場ならラースや神官長達が通り掛かる心配はないからだろう。
カイルは溜息を吐いてミラの前に出ると扉を押さえた。
「ミラ……」
「邪魔しないでよ」
「そうはいかないよ。君が一人でいなくなるとラースが心配するだろ」
「じゃあ、あんたも来る?」
「冗談じゃないよ」
「ならどいてよ」
「ダメだ」
ミラはしばらく黙ってカイルの顔を見詰めていた。
読心術なんか出来なくても悪巧みをしているのは分かる。
「ここで魔法対決してみる?」
「喧嘩はしない約束だろ」
「喧嘩じゃなくて魔法の練習」
「いいけど。僕は負けないと思うよ」
下級や中級と違い、全部で七人の上級神官は七段階に分かれている。
神殿長はその名の通り神殿の長だから一番上として次が神官長、そして副神官長である。
副神官長の下が四大神徒と言って神の使者である神徒の名を神聖名が肩書きとして持っている。
この四人は同僚だが一応順列のようなものがあってセネフィシャルが統率者で次がエンメシャル、アンシャル、キシャルと続く。
これは実力順でもある。
レラス神殿ではセネフィシャルがラース、エンメシャルがガブリエラ、アンシャルがカイル、キシャルがミラだ。
つまりカイルの方が実力があるから順番が上、と言えなくもない。
カイルとミラにそのまま当て嵌まるかは微妙なところなのだが少なくともカイルが負けることはないはずだ。
「別に勝ち負けは関係ないでしょ。練習だもの」
カイルが首を傾げた。
「でも、ここで私が本気出したら炊事場が壊れちゃうわね。今日は全員夕食なしかしら」
「なっ……!」
「二人で仲良く魔法の練習したって聞いたらラースも喜んでくれるわよ。建物が壊れたとしても共同責任よね」
ミラが無邪気を装った可愛い笑顔で悪魔のような台詞を吐いた。
こいつ……!
ハイラル教の教えは正しいらしい。
悪魔は堕ちた天使だという点に関しては。
ミラの力は知っている。
ケナイ山を吹き飛ばしたなんて噂が立つくらいだ。
試験なしで上級神官になったからといって実力が無いわけではない。
悪魔の本領発揮と言うところか……。
こいつ、入るとこ間違えたんじゃないのか?
カイルはミラを睨みながら戸から離れた。
「ありがと」
ミラは嬉々として戸口から出ていった。
このまま扉を閉めて二度と神殿に入れないようにしてしまいたい。
けどラースが……。
なんでこんなのを気に掛けるのか理解に苦しむが、とにかくラースを心配させたくない。
カイルは渋々ミラの後に続いた。
カイルが追い掛けてくるのに気付いたミラが嫌そうな顔で振り返った。
「なんで随いてくるの?」
「誘ってくれたの君だよ」
ミラが小声で「やなヤツ」とかなんとか言っているのが聞こえた。
「あのさ、外套着なくていいの?」
「外套~?」
「外出する時は着用するって決まりが……」
「ああ、そうだったわね。じゃあ、取ってきてよ。私の分も」
カイルは白けた表情でミラを見詰めた。
ミラが軽く肩を竦める。
「言ってみても損はないと思ったのよ。引っ掛かってくれれば儲けものだし」
我儘だからといってバカとは限らない。
しかし自分勝手な上に悪知恵が働くのは始末が悪い。
ミラは真っ直ぐ町の方へ向かっていた。
「いつも、どこで何してるの?」
「人助けよ。主に治療だけど」
「治療? そんなの神殿に来れば……」
「宗教上の理由で異教の神殿には頼めないって人だっているでしょ」
「そういうのはその人が信仰しているところに……」
「魔術禁止の教団やお金取るとこだってあるのよ」
「アスラル神殿に頼めない人がアスラル教の神官に頼むの?」
「神官には頼めなくてもただの魔術師には頼めるでしょ」
カイルは呆れてミラを見た。
ミラは涼しい顔で歩いている。
「ミラ、それは詐欺……」
「詐欺じゃないわよ。私はそのうち神殿を出て魔術師としてやっていくんだから。未来の魔術師なんだから嘘じゃないでしょ」
そうだろうか……?
甚だ疑問が残るところだ。
ミラを詐欺師にしないためにも神殿に閉じこめておくのは正解なのかもしれない。
「私は各国の王様がこぞって問題解決を頼みに来るような一流の魔術師になるのよ!」
君に頼んだら却って問題が大きくなるんじゃないの?
そう言い掛けてラースとの約束を思い出して話を変えた。
「君、魔物退治とかもしてる?」
「してるけど小物ばかりよ。この辺には殆どいないし」
カイルは少し考えてから思い切って、
「魔物の中にさ……倒れるとき喋ったヤツ、いた?」
と訊ねた。
「ああ、お祈りしたヤツね」
「お祈り?」
「教典読んだヤツのこと言ってんじゃないの?」
「そうだけど……」
カイルは自分が倒した魔物だけではなかった事で安心した。
「死ぬ直前に改心して天国へ行こうだなんて考えが甘いのよね」
「は……?」
「だいたい改心すれば天国へ行けるって言うのはハイラル教じゃない。アスラル教の教典読んだってしょうがないのに」
「…………」
「ハイラル教も寛大よね。あそこの天国って悪いヤツだらけで善人が入れなくなっちゃってんじゃないの?」
ミラの口調には僅かにバカにしたような響きがあった。
四
神殿から町までは大して距離はない。
元々神殿は町外れに建っているのだから町の中心まで、と言った方が正しいだろう。
「よぉ、キシャル」
人通りが多くなってくるにつれミラに声を掛けてくる者が多くなってきた。
けど……。
キシャル?
神官だってこと内緒だって言ってなかったか?
「おじさん、具合どう?」
「いいよ。ありがとな」
ミラが愛想良く手を振りながら人混みを擦り抜けていく。
カイルは後を追うので精一杯だった。
「キシャル、これ持っていっておくれ」
食べ物屋から出てきた女性がミラに包みを手渡した。
包みからは美味しそうな匂いが漂ってくる。
「この間のお礼だよ」
「気にしなくていいのに」
「ただじゃ心苦しいからね」
「じゃあ、遠慮なく」
ミラは笑顔で受け取った。
女性は店内の客に催促されて中に戻っていった。
こうして笑ってるところは間違いなく可愛いのに。
別にそういう風を装っているようにも見えない。
多分、これが本来のミラなんだろうけど……。
だったら神殿でのあの態度はなんなのか。
いや、それよりも……。
「ミラ、どうして皆、君のことキシャルって呼んでるの?」
「私はキシャルじゃない」
「神官だってこと内緒じゃなかったの?」
「名前はマズいのよ。ちょっと訳ありで……。あんたもここではミラって呼ばないで」
カイルは眉を顰めた。
一体、何をしでかしたんだ……?
ケナイ山を吹き飛ばしたとまではいかなくても、それに近い事はやっているのかもしれない。
「ね、これ、その辺で食べちゃいましょ」
ミラがカイルの袖を引っ張った。
「キシャル、ここ使ってくれ」
露店でスープを売っている男性がミラの言葉を聞いて脇に置いてあるテーブルを指した。
「ありがと」
ミラはカイルを連れて露店の脇に置かれている簡単な作りの椅子に腰掛けた。
カイルもテーブルを挟んだ向かいに座る。
露店の男性は二人にスープを出してくれた。
目の前のテーブルも椅子と同じように木製の粗末なものだった。
表面は擦れて黒光りしている。
こぼれた汁や食べかすで黒ずんだテーブルの上を虫が飛び回っていた。
「あ、フォークが一個しかない」
包みを開いたミラが言った。
中身はざく切りの野菜を炒めた料理のようだ。
スープの方は香辛料の利いた赤い汁に細かく刻まれた黄色や緑の野菜が彩りを添えている。
油の浮いたスープは予想よりもあっさりしていて少し辛いのだが微かな甘みも混じっていた。
「じゃあ、かわりばんこね」
ミラはフォークで野菜炒めを一口食べるとカイルにフォークをよこしてきた。
断るのも悪いし、何より美味しそうだったので素直に受け取る。
「キシャル、その子、友達かい?」
露店の男性が声を掛けてきた。
「そうよ、仲良しなの」
カイルは思わずむせそうになりながらミラにフォークを返した。
美味しい……。
考えてみれば神殿の食事は質素を旨としている。
量も少ないし、こういうところの食事に敵うわけがない。
でも材料は同じだと思うんだけど……。
町中の安い食堂の料理だ。
高級料理とは言い難い。
それより……。
カイルはフォークを口に運んでいるミラに目を戻した。
ミラが夕食抜きでも平気なのはこういうわけか。
無断外出した場合、夕食の時間までに帰らなければ食事抜きだ。
ミラはよく夕食抜きを言い渡されていたが一向に堪えた様子がなかった。
ここへ来る度にこうして誰かが食べさせてくれるなら神殿に帰る頃にはお腹一杯になっているだろう。
平気な訳だ。
神殿の食事より美味しいし……。
食べてる間にも町の人間が入れ替わり立ち替わりやってきた。
ミラはその度に食事を中断して病気やケガを治している。
「キシャル、ちょっといいかい」
年配の女性がミラの側にやってきた。
「どうしたの?」
「あたしじゃないんだけど……何日か前から魔術師を捜してる人がいるんだよ」
女性は通りの向こうを指した。
髭を生やした体格のいい中年の男性が若い女性と話している。
若い女性はこちらに目を向けていた。
「ありがとう」
ミラが女性に礼を言って立ち上がるのと、中年の男性がこちらを向くのは同時だった。
中年の男性は、若い女性に感謝するように手を挙げるとこちらへ向かって歩き出した。
半信半疑の表情を浮かべているのはミラが子供だからだろう。
他を当たる事にしてくれればいいんだけど……。
町の人の治療くらいならともかく、あまり厄介な事を頼まれるのは困る。
ミラがケガでもしたら何のためにカイルが見張りに付けられたのか分からなくなる。
髭の男性が近付いてくると、ミラは自分が座っていたところを勧めた。
男性はちょっと躊躇ってからミラが座っていたベンチに座る。
ミラはカイルの隣に腰を下ろした。
「私はネルウィンと申します。アイオン村の村長代理でして……」
「私達は魔術師の……」
「僕は違います」
間髪を入れずにカイルが否定するとミラが睨んだ。
カイルは知らん顔をした。
詐欺の片棒を担ぐ気は無い。
ネルウィンは戸惑った様子で二人の顔を交互に見た。
少し疑わしそうな視線を向けている。
ミラの方もそれが分かったらしい。
「ね、話すだけ話してよ。私には出来そうにないと思ったら神殿に案内するから」
神殿という言葉にネルウィンが反応した。
「実は、村の近くに魔物が出るようになったんです。今まで何人も腕自慢の人間が倒しに行ったんですが誰一人帰ってきませんでした」
「それ、どんなヤツなんですか?」
カイルは眉を顰めて訊ねた。
「分かりません。姿を見た者はいないんです。せいぜい恐ろしげな唸り声を聞いた者が何人かいるだけで……」
「どうして神殿に相談に行かないんですか?」
「いちいち口出さないでよ」
ミラが再びカイルの足を蹴って小声で囁いてきた。
カイルはそれを無視してネルウィンに話を促した。
ネルウィンは気不味そうに目を伏せた。
「うちは村全体がハイラル教で……」
どうやらミラが言っていた〝異教徒には頼めない〟口らしい。
ハイラル教は唯一絶対神を信仰していて異教徒を悪魔の手先と見做している。
そして魔法は「奇蹟」とされているから一部の神官を除いて禁止されているのだ。
魔法を使える神官は魔物退治が出来るらしいが人数が少ないため助けを求めてもすぐには来てもらえない。
「教団に依頼して大分経ちましたが未だに来て頂けません。犠牲者は増える一方です。それで破門を覚悟でアスラル教の神殿にお願いしようかと……」
「それなら、ただの魔術師の私が……」
「神殿はそこの道を真っ直ぐ行ったところです」
ミラとカイルは同時に言ってから睨み合った。
「余計な口出ししないでって言ったでしょ! 私が頼まれたのよ!」
「神殿に頼みに来たって言ったじゃないか! これはラースかガブリエラに頼んだ方がいいよ」
「そんな事したら破門になっちゃうのよ。可哀想じゃない。ハイラル教の人にとって魂が救われるかどうかは大問題なんでしょ」
ハイラル教で魂が救われなくなってしまったならアスラル教に改宗すればいいかというとそうはいかない。
アスラル教は来るものは拒まずだ。
だから改宗するのは自由だが、アスラル教には「魂の救済」という概念が無い。
元が原始的な農耕社会で自然を崇拝していたものだからだ。
アスラル教とはあくまでも大地母神に豊作を祈り、日照りの時には水神に雨乞いをし、冷害の時には太陽神に日照を願うという現世利益の宗教なのだ。
アスラル教での死とは万物の創造者である大地母神アスラルの胎内(土)へ還る事であり、還った者は再び生まれてくる。
あの世というものが存在しないから天国も地獄も無い。
普通、魂の救済とは天国へ行く事だ。
死後に天国に行きたいならアスラル教徒になっても意味が無いのだ。
「任せて。私、これでも今までに何度も魔物を倒してきたのよ」
ミラはネルウィンの方を向いて言った。
「これ以上厄介事を抱え込むのが嫌なら神殿へ行った方がいいですよ」
「邪魔しないでったら!」
「お前のせいでラースにまで変な噂が立ってるんだぞ!」
「変な噂が立てられてるのは私だけじゃないわよ! 自分は関係ないようなこと言わないでよね!」
虚を衝かれたカイルはミラの顔を見返した。
「僕が誰と……」
「ラースや神殿長に決まってるでしょ」
「僕、男だぞ!」
「だからでしょ! 異性との恋愛は御法度だもの。当然相手は同性って事になるじゃない」
「な……!」
あまりの事に絶句した。
首から上の血が沸騰したように熱くなった。
耳まで紅潮しているのが分かった。
まさか自分もミラと同じように思われているとは考えてもみなかった。
皆今までそういう目で自分を見ていたのか?
ラースやガブリエラも知っているんだろうか?
そう思うと恥ずかしくて身動きも出来なかった。
神殿へ帰ってもラース達とまともに顔を合わせられる自信がない。
これからどうすればいいのかも分からない。
「……じゃあ、そういう事で」
「よろしくお願いします」
動揺したカイルが硬直している間にミラとネルウィンの話は決まってしまった。
よもや、この美少女がこんな我儘な性格だとは思いもよらなかった。
ハイラル教の悪魔は堕ちた天使だと言う話だがミラを見せれば誰でも納得するに違いない。
アスラル教には悪魔がいないのが残念だ。
神の使い――神徒――はいるがハイラル教の「天使」とは少し意味合いが違う。
「またミラ様がやってるぜ」
「ラース様もキシャル様を特別扱いしてるし」
「セネフィシャル様も可愛い女の子には逆らえない、か」
ったく!
ラースの評判まで落ちてるじゃないか!
ミラは窓際にいた。
窓を乗り越えて抜けだそうとしたところを神官長に捕まったのだろう。
こんな下級神官も通るところで神官長にまで口答えして……。
カイルは憤然としてミラに向かっていった。
「こんなとこで何やってんだよ!」
「あんたには関係ないでしょ!」
「場所をわきまえろよ!」
「知らないわよ!」
「神殿長やラースまで悪く言われてるんだそ!」
「私が言わせてるわけじゃないでしょ!」
「お前のせいだろ!」
「やめな……!」
「そこまで」
ラースの落ち着いた声が聞こえた途端、全員が黙り込んだ。
本来ならラースの上司であるはずの神官長まで口を噤んでしまった。
「神官長、ここは私が」
神官長は肩の荷が下りたというような表情で奥へ戻っていった。
「カイル、君は執務室へ戻りなさい」
「はい」
「ミラ、君も自分の部屋へ行きなさい」
素直にラースの言葉に従おうと踵を返したカイルは驚いて足を止めた。
自室へ帰れというのは何もしなくていいという意味だからサボるのも神殿を抜け出すのも自由という事だ。
ミラはすぐにどこかへ行ってしまった。
「ラース! それでは……!」
「いいから執務室へ行きなさい」
抗議しようとしたカイルをラースはやんわりと止めた。
「ですが……!」
「ミラの心配をするのは君の仕事ではない」
口を出すなと言っているのだ。
「他の神官達からなんて言われてるか知ってるんですか!?」
「ミラを任されたのは私だ」
ラースはカイルの抗議を取り合わずに行ってしまった。
なんでミラだけ……。
カイルは拳を握り締めた。
翌日、カイルはマイラと神殿に向かって歩いていた。
風が草を揺らしながら草原を渡っていく。
二人はレラスの町にいた病人を治しに行った帰りだった。
そのとき向こうからミラが歩いてきた。
「ミラ! また勝手に抜け出してきたな!」
「それが何よ」
カイルの言葉にミラが言い返す。
マイラも無言でミラを睨んでいる。
そこへ背後から足音が聞こえてきた。
振り返ると初老の男が近付いてくる。
橙色の敷布のような服。
セルケト教の神官?
なんでセルケト神官がこんなところに……。
カイルは首を傾げた。
セルケト教というのは世界は対立する二つのものから出来ている、という考えの二神教だ。
この辺はアスラル教かハイラル教が大半を占めていてセルケト教徒は珍しい。
その他、有象無象の民間信仰も多々あるからセルケト神官ではないかもしれないが。
「あなたは?」
男はカイルの問いに答えず、反対に、
「ケナイのマイラというのはどっちだ?」
と訊ねてきた。
「ケナイにいたマイラは私、ケナイから来たマイラはそっち」
ミラがマイラに視線を向けた。
男がミラとマイラを見比べる。
「なるほど、替え玉か。二人揃ってなければ騙されるところだった」
替え玉?
カイルが眉を顰めたとき、マイラが唇を噛かんで拳を握り締めた。
そうか……。
ミラはケナイではマイラと呼ばれていた。
最初、今のマイラは〝アスラル神の化身〟であるミラ(以前はマイラ)にあやかって同じ名前にしたのかと思ったが、よく考えたら同い年なのだからそれは考えづらい。
生まれたばかりの頃に既にマイラの恩恵が知られていたのなら無くはないかもしれないが。
知らなかったとしたら小さな村で同い年の子に同じ名前を付けるだろうかと疑問に思っていたのだ。
それでマイラに訊ねたら本名は違うのだが、ここに入ったら何故かマイラと名乗るように言われたのだとか。
普通、神官になったからと言って改名はしない。
同じ村の出身で同い年の強い魔力を持つ少女。
人目を欺く為に二人の名前を変えたのだ。
「〝素晴らしきもの〟ミラ、か……」
男が皮肉な笑みを浮かべ、マイラは逆に侮辱されたような表情になった。
確かにマイラから〝素晴らしきもの〟のミラになったのだとしたらマイラを名乗らされる事になった彼女にとっては屈辱だろう。
「レラスのセネフィシャルのやりそうな事だな」
男はそう言うとミラに手を伸ばした。
「ケナイのマイラ、一緒に来てもらおう」
「悪いがお断りする」
突然ラースの声が聞こえてきた。
男の腕が止まる。
カイル達が振り返ると後ろにラースが立っていた。
「うちの神官に用があるなら神殿長に話を通して頂こう」
「レラスのセネフィシャルか」
ラースと男は一瞬睨み合った。
二人の魔力が高まる。
すぐに男は視線を逸らした。
「今日のところは帰る事にしよう」
そう言うと男は去っていった。
二
数日後、カイルは書類を抱えて執務室へ向かっていた。
これは本来ミラがやるべき仕事である。
ミラにやらせようとしたのだが散々口論した末に逃げられてしまった。
「失礼します」
カイルが部屋へ入っていくとラースは書類から顔を上げた。
「ありがとう。そこへ置いといてくれ」
ラースはこれがミラの仕事だと知っているにも関わらずカイルが持ってきたのを見ても何も言わなかった。
「ラース、ミラを何とかして下さい」
つい恨みがましい口調になってしまった。
けれど自分が慕っている相手が別の人を贔屓しているのを見るとどうしても妬ましく思ってしまう。
ラースが苦笑した。
「カイル、ミラは少々我儘かもしれないが……」
「少々どころじゃありません」
「悪い子じゃないんだ」
「仕事をサボってるのに?」
「ちょっと訳ありでね。本当は良い子なんだ。仲良くしてくれ」
「冗談じゃありません!」
反射的に強い口調で言い返してしまい、すぐに後悔した。
「すみません。でもミラがあの調子じゃ……」
ラースは溜息を吐いた。
「分かった。なんとかしよう」
ラースが身振りで下がるように促した。
カイルもそれ以上は何も言わずに部屋を出た。
翌日、カイルはミラが神殿を抜け出そうとしているところを捕まえた。
ラースには放っておくように言われたが、やはり知らんふりは出来ない。
「ミラ! いい加減にしろよ!」
「そっちこそ!」
「ラースに迷惑掛けるなよ!」
「あんたには関係ないでしょ!」
「お前がサボってる仕事、誰がやってると……!」
「君達、ちょっといいか」
いつの間にかラースが側に来ていた。
カイルとミラが口を噤む。
ラースは二人を連れて奥へと向かった。
その間、ミラは不機嫌な顔で黙りこくっていた。
カイルは横目でミラの方を窺った。
これが、ちょっとでも良いなと思っていた女の子だとは……。
ミラがこんなに可愛くなければ誰もラースや神殿長が色香に惑わされてるなんて思わないだろうに。
ラースは上級神官用の執務室へ入ると二人の方を向き直った。
カイルとミラは互いに離れた場所に立つ。
「カイル、ミラ。同僚なんだし、そろそろ仲良くなってもいい頃じゃないか?」
「冗談じゃないわよ!」
「それはこっちの台詞だ!」
「二人とも……」
喧嘩になりそうな二人の間に入ったラースがガブリエラに視線を走らせた。
見るとガブリエラは本で顔を隠して笑いを堪えている。
「ミラ」
ラースの声が僅かに厳しくなった。
ミラが渋々といった様子でラースを見上げ、ついでに軽く両手を上げた。
「分かったわよ。喧嘩はしない。それでいいでしょ」
「私は君達に仲良くしてほしいんだ」
「絶対にイヤ!」
「喧嘩しないだけじゃダメなんですか?」
「どうしても嫌か?」
「どうしてもイヤ!」
「カイル?」
ラースはカイルに訊ねるように首を傾げた。
「僕がいいって言ってもミラが……」
「じゃあ、ミラが仲良くするって言ったら仲良くしてくれるんだね」
「え……まぁ」
ミラが余計な事を、という顔で睨む。
「ミラ」
ラースがミラに向き直った。
神官長にまで口答えするミラが素直に言うことを聞くとは思えないが……。
「イヤよ」
やっぱり……。
「ミラ、命令だ」
ラースがきっぱりと言った。
断固拒否するかと思ったが、
「……はい」
ミラは承服した。
思い切り不服そうだったが。
カイルは信じられない思いで二人を交互に見た。
ラースの命令には従うのか……。
と言う事は今まで仕事をしろと命じた事がなかったのだ。
少なくともラースは。
仕事をさせる気がないならなんで神官にさせておくんだ?
「約束だ。仲良くしてくれ」
ラースは満足した様子で部屋から出ていった。
見るとガブリエラもいつの間にかいなくなっていた。
ミラのお守りを押し付けられたという事か……。
カイルは肩を落とした。
カイルが見張っていればラースの負担は減るだろうが……。
「ラースったら、子供か何かと勘違いしてんじゃないの?」
それまで神妙な顔をしていたミラはラースがいなくなった途端、態度が変わった。
元に戻ったと言うべきか……。
「ったく、あんたのせいで出掛けられなかったじゃない」
ミラは捨て台詞を吐くと女性神官用の居住区の方へと帰っていった。
やっぱりあんな約束するんじゃなかった……。
翌日、カイルは神殿の奥へ向かっていた。
上級神官用の執務室で勉強するためだ。
最初、いつもの場所で外を眺めていた。
が、下級神官も通る廊下のため嫌でも噂話が耳に入ってしまうのだ。
さっきも初っ端からラースの嫌な噂を聞かされてしまった。
ラースがミラといい仲だの、神殿長とラースがミラを取り合ってるだの、果てはガブリエラとラースとミラの三角関係なんて言うのまで……。
どうして恋愛が御法度の神官がそういう事を言うんだよ!
それもこれもミラのせいで……。
苛々しながら歩いていると視界の隅にミラを捉えた。
見なかった事にしようか……。
だがミラがいなくなればラースが心配するだろう。
「どこに行くの?」
ミラはカイルを無視し掛けてラースとの約束を思い出したらしい。
「どこだっていいでしょ」
返事だけはあった。
しかしそのまま行ってしまう。
カイルはミラの後を追い掛けた。
「待てよ」
「随いてこないでよ」
「でも仲良くしろって……」
「仲良くしたいわけ? 私と」
カイルは言葉に詰まった。
「いい? お互い近くにいなければ仲良くする必要もないでしょ。分かったらあっち行って」
我儘だからといってバカとは限らない。
悪知恵だけは働くようだ。
三
ミラは炊事場へと入っていった。
つまみ食いか? と思って中を覗くとミラは真っ直ぐ勝手口を目指している。
炊事場ならラースや神官長達が通り掛かる心配はないからだろう。
カイルは溜息を吐いてミラの前に出ると扉を押さえた。
「ミラ……」
「邪魔しないでよ」
「そうはいかないよ。君が一人でいなくなるとラースが心配するだろ」
「じゃあ、あんたも来る?」
「冗談じゃないよ」
「ならどいてよ」
「ダメだ」
ミラはしばらく黙ってカイルの顔を見詰めていた。
読心術なんか出来なくても悪巧みをしているのは分かる。
「ここで魔法対決してみる?」
「喧嘩はしない約束だろ」
「喧嘩じゃなくて魔法の練習」
「いいけど。僕は負けないと思うよ」
下級や中級と違い、全部で七人の上級神官は七段階に分かれている。
神殿長はその名の通り神殿の長だから一番上として次が神官長、そして副神官長である。
副神官長の下が四大神徒と言って神の使者である神徒の名を神聖名が肩書きとして持っている。
この四人は同僚だが一応順列のようなものがあってセネフィシャルが統率者で次がエンメシャル、アンシャル、キシャルと続く。
これは実力順でもある。
レラス神殿ではセネフィシャルがラース、エンメシャルがガブリエラ、アンシャルがカイル、キシャルがミラだ。
つまりカイルの方が実力があるから順番が上、と言えなくもない。
カイルとミラにそのまま当て嵌まるかは微妙なところなのだが少なくともカイルが負けることはないはずだ。
「別に勝ち負けは関係ないでしょ。練習だもの」
カイルが首を傾げた。
「でも、ここで私が本気出したら炊事場が壊れちゃうわね。今日は全員夕食なしかしら」
「なっ……!」
「二人で仲良く魔法の練習したって聞いたらラースも喜んでくれるわよ。建物が壊れたとしても共同責任よね」
ミラが無邪気を装った可愛い笑顔で悪魔のような台詞を吐いた。
こいつ……!
ハイラル教の教えは正しいらしい。
悪魔は堕ちた天使だという点に関しては。
ミラの力は知っている。
ケナイ山を吹き飛ばしたなんて噂が立つくらいだ。
試験なしで上級神官になったからといって実力が無いわけではない。
悪魔の本領発揮と言うところか……。
こいつ、入るとこ間違えたんじゃないのか?
カイルはミラを睨みながら戸から離れた。
「ありがと」
ミラは嬉々として戸口から出ていった。
このまま扉を閉めて二度と神殿に入れないようにしてしまいたい。
けどラースが……。
なんでこんなのを気に掛けるのか理解に苦しむが、とにかくラースを心配させたくない。
カイルは渋々ミラの後に続いた。
カイルが追い掛けてくるのに気付いたミラが嫌そうな顔で振り返った。
「なんで随いてくるの?」
「誘ってくれたの君だよ」
ミラが小声で「やなヤツ」とかなんとか言っているのが聞こえた。
「あのさ、外套着なくていいの?」
「外套~?」
「外出する時は着用するって決まりが……」
「ああ、そうだったわね。じゃあ、取ってきてよ。私の分も」
カイルは白けた表情でミラを見詰めた。
ミラが軽く肩を竦める。
「言ってみても損はないと思ったのよ。引っ掛かってくれれば儲けものだし」
我儘だからといってバカとは限らない。
しかし自分勝手な上に悪知恵が働くのは始末が悪い。
ミラは真っ直ぐ町の方へ向かっていた。
「いつも、どこで何してるの?」
「人助けよ。主に治療だけど」
「治療? そんなの神殿に来れば……」
「宗教上の理由で異教の神殿には頼めないって人だっているでしょ」
「そういうのはその人が信仰しているところに……」
「魔術禁止の教団やお金取るとこだってあるのよ」
「アスラル神殿に頼めない人がアスラル教の神官に頼むの?」
「神官には頼めなくてもただの魔術師には頼めるでしょ」
カイルは呆れてミラを見た。
ミラは涼しい顔で歩いている。
「ミラ、それは詐欺……」
「詐欺じゃないわよ。私はそのうち神殿を出て魔術師としてやっていくんだから。未来の魔術師なんだから嘘じゃないでしょ」
そうだろうか……?
甚だ疑問が残るところだ。
ミラを詐欺師にしないためにも神殿に閉じこめておくのは正解なのかもしれない。
「私は各国の王様がこぞって問題解決を頼みに来るような一流の魔術師になるのよ!」
君に頼んだら却って問題が大きくなるんじゃないの?
そう言い掛けてラースとの約束を思い出して話を変えた。
「君、魔物退治とかもしてる?」
「してるけど小物ばかりよ。この辺には殆どいないし」
カイルは少し考えてから思い切って、
「魔物の中にさ……倒れるとき喋ったヤツ、いた?」
と訊ねた。
「ああ、お祈りしたヤツね」
「お祈り?」
「教典読んだヤツのこと言ってんじゃないの?」
「そうだけど……」
カイルは自分が倒した魔物だけではなかった事で安心した。
「死ぬ直前に改心して天国へ行こうだなんて考えが甘いのよね」
「は……?」
「だいたい改心すれば天国へ行けるって言うのはハイラル教じゃない。アスラル教の教典読んだってしょうがないのに」
「…………」
「ハイラル教も寛大よね。あそこの天国って悪いヤツだらけで善人が入れなくなっちゃってんじゃないの?」
ミラの口調には僅かにバカにしたような響きがあった。
四
神殿から町までは大して距離はない。
元々神殿は町外れに建っているのだから町の中心まで、と言った方が正しいだろう。
「よぉ、キシャル」
人通りが多くなってくるにつれミラに声を掛けてくる者が多くなってきた。
けど……。
キシャル?
神官だってこと内緒だって言ってなかったか?
「おじさん、具合どう?」
「いいよ。ありがとな」
ミラが愛想良く手を振りながら人混みを擦り抜けていく。
カイルは後を追うので精一杯だった。
「キシャル、これ持っていっておくれ」
食べ物屋から出てきた女性がミラに包みを手渡した。
包みからは美味しそうな匂いが漂ってくる。
「この間のお礼だよ」
「気にしなくていいのに」
「ただじゃ心苦しいからね」
「じゃあ、遠慮なく」
ミラは笑顔で受け取った。
女性は店内の客に催促されて中に戻っていった。
こうして笑ってるところは間違いなく可愛いのに。
別にそういう風を装っているようにも見えない。
多分、これが本来のミラなんだろうけど……。
だったら神殿でのあの態度はなんなのか。
いや、それよりも……。
「ミラ、どうして皆、君のことキシャルって呼んでるの?」
「私はキシャルじゃない」
「神官だってこと内緒じゃなかったの?」
「名前はマズいのよ。ちょっと訳ありで……。あんたもここではミラって呼ばないで」
カイルは眉を顰めた。
一体、何をしでかしたんだ……?
ケナイ山を吹き飛ばしたとまではいかなくても、それに近い事はやっているのかもしれない。
「ね、これ、その辺で食べちゃいましょ」
ミラがカイルの袖を引っ張った。
「キシャル、ここ使ってくれ」
露店でスープを売っている男性がミラの言葉を聞いて脇に置いてあるテーブルを指した。
「ありがと」
ミラはカイルを連れて露店の脇に置かれている簡単な作りの椅子に腰掛けた。
カイルもテーブルを挟んだ向かいに座る。
露店の男性は二人にスープを出してくれた。
目の前のテーブルも椅子と同じように木製の粗末なものだった。
表面は擦れて黒光りしている。
こぼれた汁や食べかすで黒ずんだテーブルの上を虫が飛び回っていた。
「あ、フォークが一個しかない」
包みを開いたミラが言った。
中身はざく切りの野菜を炒めた料理のようだ。
スープの方は香辛料の利いた赤い汁に細かく刻まれた黄色や緑の野菜が彩りを添えている。
油の浮いたスープは予想よりもあっさりしていて少し辛いのだが微かな甘みも混じっていた。
「じゃあ、かわりばんこね」
ミラはフォークで野菜炒めを一口食べるとカイルにフォークをよこしてきた。
断るのも悪いし、何より美味しそうだったので素直に受け取る。
「キシャル、その子、友達かい?」
露店の男性が声を掛けてきた。
「そうよ、仲良しなの」
カイルは思わずむせそうになりながらミラにフォークを返した。
美味しい……。
考えてみれば神殿の食事は質素を旨としている。
量も少ないし、こういうところの食事に敵うわけがない。
でも材料は同じだと思うんだけど……。
町中の安い食堂の料理だ。
高級料理とは言い難い。
それより……。
カイルはフォークを口に運んでいるミラに目を戻した。
ミラが夕食抜きでも平気なのはこういうわけか。
無断外出した場合、夕食の時間までに帰らなければ食事抜きだ。
ミラはよく夕食抜きを言い渡されていたが一向に堪えた様子がなかった。
ここへ来る度にこうして誰かが食べさせてくれるなら神殿に帰る頃にはお腹一杯になっているだろう。
平気な訳だ。
神殿の食事より美味しいし……。
食べてる間にも町の人間が入れ替わり立ち替わりやってきた。
ミラはその度に食事を中断して病気やケガを治している。
「キシャル、ちょっといいかい」
年配の女性がミラの側にやってきた。
「どうしたの?」
「あたしじゃないんだけど……何日か前から魔術師を捜してる人がいるんだよ」
女性は通りの向こうを指した。
髭を生やした体格のいい中年の男性が若い女性と話している。
若い女性はこちらに目を向けていた。
「ありがとう」
ミラが女性に礼を言って立ち上がるのと、中年の男性がこちらを向くのは同時だった。
中年の男性は、若い女性に感謝するように手を挙げるとこちらへ向かって歩き出した。
半信半疑の表情を浮かべているのはミラが子供だからだろう。
他を当たる事にしてくれればいいんだけど……。
町の人の治療くらいならともかく、あまり厄介な事を頼まれるのは困る。
ミラがケガでもしたら何のためにカイルが見張りに付けられたのか分からなくなる。
髭の男性が近付いてくると、ミラは自分が座っていたところを勧めた。
男性はちょっと躊躇ってからミラが座っていたベンチに座る。
ミラはカイルの隣に腰を下ろした。
「私はネルウィンと申します。アイオン村の村長代理でして……」
「私達は魔術師の……」
「僕は違います」
間髪を入れずにカイルが否定するとミラが睨んだ。
カイルは知らん顔をした。
詐欺の片棒を担ぐ気は無い。
ネルウィンは戸惑った様子で二人の顔を交互に見た。
少し疑わしそうな視線を向けている。
ミラの方もそれが分かったらしい。
「ね、話すだけ話してよ。私には出来そうにないと思ったら神殿に案内するから」
神殿という言葉にネルウィンが反応した。
「実は、村の近くに魔物が出るようになったんです。今まで何人も腕自慢の人間が倒しに行ったんですが誰一人帰ってきませんでした」
「それ、どんなヤツなんですか?」
カイルは眉を顰めて訊ねた。
「分かりません。姿を見た者はいないんです。せいぜい恐ろしげな唸り声を聞いた者が何人かいるだけで……」
「どうして神殿に相談に行かないんですか?」
「いちいち口出さないでよ」
ミラが再びカイルの足を蹴って小声で囁いてきた。
カイルはそれを無視してネルウィンに話を促した。
ネルウィンは気不味そうに目を伏せた。
「うちは村全体がハイラル教で……」
どうやらミラが言っていた〝異教徒には頼めない〟口らしい。
ハイラル教は唯一絶対神を信仰していて異教徒を悪魔の手先と見做している。
そして魔法は「奇蹟」とされているから一部の神官を除いて禁止されているのだ。
魔法を使える神官は魔物退治が出来るらしいが人数が少ないため助けを求めてもすぐには来てもらえない。
「教団に依頼して大分経ちましたが未だに来て頂けません。犠牲者は増える一方です。それで破門を覚悟でアスラル教の神殿にお願いしようかと……」
「それなら、ただの魔術師の私が……」
「神殿はそこの道を真っ直ぐ行ったところです」
ミラとカイルは同時に言ってから睨み合った。
「余計な口出ししないでって言ったでしょ! 私が頼まれたのよ!」
「神殿に頼みに来たって言ったじゃないか! これはラースかガブリエラに頼んだ方がいいよ」
「そんな事したら破門になっちゃうのよ。可哀想じゃない。ハイラル教の人にとって魂が救われるかどうかは大問題なんでしょ」
ハイラル教で魂が救われなくなってしまったならアスラル教に改宗すればいいかというとそうはいかない。
アスラル教は来るものは拒まずだ。
だから改宗するのは自由だが、アスラル教には「魂の救済」という概念が無い。
元が原始的な農耕社会で自然を崇拝していたものだからだ。
アスラル教とはあくまでも大地母神に豊作を祈り、日照りの時には水神に雨乞いをし、冷害の時には太陽神に日照を願うという現世利益の宗教なのだ。
アスラル教での死とは万物の創造者である大地母神アスラルの胎内(土)へ還る事であり、還った者は再び生まれてくる。
あの世というものが存在しないから天国も地獄も無い。
普通、魂の救済とは天国へ行く事だ。
死後に天国に行きたいならアスラル教徒になっても意味が無いのだ。
「任せて。私、これでも今までに何度も魔物を倒してきたのよ」
ミラはネルウィンの方を向いて言った。
「これ以上厄介事を抱え込むのが嫌なら神殿へ行った方がいいですよ」
「邪魔しないでったら!」
「お前のせいでラースにまで変な噂が立ってるんだぞ!」
「変な噂が立てられてるのは私だけじゃないわよ! 自分は関係ないようなこと言わないでよね!」
虚を衝かれたカイルはミラの顔を見返した。
「僕が誰と……」
「ラースや神殿長に決まってるでしょ」
「僕、男だぞ!」
「だからでしょ! 異性との恋愛は御法度だもの。当然相手は同性って事になるじゃない」
「な……!」
あまりの事に絶句した。
首から上の血が沸騰したように熱くなった。
耳まで紅潮しているのが分かった。
まさか自分もミラと同じように思われているとは考えてもみなかった。
皆今までそういう目で自分を見ていたのか?
ラースやガブリエラも知っているんだろうか?
そう思うと恥ずかしくて身動きも出来なかった。
神殿へ帰ってもラース達とまともに顔を合わせられる自信がない。
これからどうすればいいのかも分からない。
「……じゃあ、そういう事で」
「よろしくお願いします」
動揺したカイルが硬直している間にミラとネルウィンの話は決まってしまった。