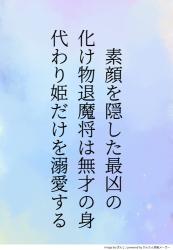この街の天気は、非常に移ろいやすいことで有名だ。
科学の力を持ってしてもその原因は解明できず、気象予報士の間では、まるで予測不可能だと恐れられている。
✳︎
水瀬沙雨は、鉄壁の無表情を崩さぬまま、クラスメイトといっても顔と名前程度しか知らない目の前の少年に冷たい声音で告げた。
「和泉。……あたしと、付き合ってくれない?」
体育館裏に、沈黙が舞い降りた。
涼を含んだ十月の風が、沙雨の真っ直ぐに伸びた黒い髪をなびかせる。
沙雨は、和泉日向に振られることを望んでいた。
というよりも、振られなければおかしい。
高校に入学してもう半年経つが、二人は、一度もまともに会話をしたことがないからだ。
この告白は、最初から振られるためだけのもの。
物陰から息をひそめ、この明らかに様子のおかしい告白をニヤニヤと眺めている彼女たちの、見せ物になるために。
「うん、良いよ」
「……は?」
「だから、告白の返事だよ。僕たち、付き合おうか」
「な……なにを言っているの? あんた、頭おかしいんじゃないの」
「ひどいな。告白してきたのは、君なのに」
沙雨には、目の前でくすくすと笑っている少年が、理解の及ばない生物に見えた。
なんで? どうして、そんなにあっさりと受け入れるの?
得体の知れない恐怖に、脇から汗が滲み出て、眩暈までしてくる。
きっと、この一部始終を目撃している彼女たちも、予想外の展開に開いた口が塞がらないことだろう。
「もしかして……あんたも」
あたしのこと、馬鹿にしてるの?
沙雨の震える唇からやっとのことで漏れ出たのは、言葉ではなく、か細い息だけだ。
空は、いつの間にか、どんよりと厚い雲に覆われていた。
今にも、雨が降り出しそうだ。
「これからよろしくね、水瀬さん」
和泉は、怯える沙雨を見つめながら、ひだまりのような笑みを浮かべた。
✳︎
家族で夕飯を食べ終えた後、沙雨は妹の沙夜を自分の部屋へ呼び出した。
今日の放課後に起きた珍妙な出来事を、誰かに話さずにはいられなかったからだ。
妹に余計な心配はかけぬよう、罰ゲームとして嫌々告白させられたという詳細は伏せた。
「えええっ! お姉ちゃん、彼氏ができたの⁉︎」
「う、うーん。あたしもよく分かんないんだけど……からかわれてるだけだと思う」
今年で中学二年生になる妹は、ベッドに腰掛けて足をぷらぷらさせながら、大きな瞳を瞬かせている。
「……ほんとにヘンな奴。大人しそうに見えるのに」
「その人すごいなぁ……」
「はあ?」
「見る目があるのかもしれないよ! お姉ちゃんの分かりづらい魅力に、ちゃんと気がついてるってこと!」
それは事の詳細を知らない沙夜の妄想だろう。
なにせ、沙雨はこれまで和泉と接点すらなかったのだから。人格を知られようがない。
「沙夜は、テニス部どう? 順調?」
強引に話題を変えた。
これ以上和泉の話を続けて、どうしてそんな状況になったのかまで沙夜に知られるのは避けたかったから。
「うん! この前も試合に勝ったよ!」
「そっか、それは良かった」
嬉しそうに笑う紗夜の小麦色にやけた肌を見つめながら、キャンドルを灯されたように温かい気持ちになった。
昔の妹は、太陽を知らぬ白い肌をしていたのだ。
病弱で、ろくに外に出ることも叶わなかったから。
しかし今の紗夜は、小学時代に命の危機にさらされていたとは思えないほど回復し、テニスまでできるようになった。
妹を想って、泣いてばかりいた日々が懐かしい。
沙夜が、無事に健康を取り戻してくれて本当に良かったと、沙雨はあらためて思った。
*
その翌朝。
沙雨はいつもどおり澄ました顔をして教室に入った。
何食わぬ顔で席についたが、内心は、動揺と焦りとではちきれそうになっていた。
和泉日向。
彼の考えていることが、まるで分からない。
なぜ彼は、沙雨の告白を受け入れたりしたのだろう。
あんな、あからさまに罰ゲームでさせられていると分かる、情緒もへったくれもない告白を。
「水瀬さん、おはよう」
「っ!」
「そんなに怯えないでよ。幽霊じゃないんだから」
気がつけば、心中に思い浮かべていた人物が目の前にいて、沙雨は顔を強張らせた。
「わっ! 和泉、マジで水瀬に話しかけてるじゃん」
「ウケるんですけど! まさか、本気で付き合っちゃった系? 隠キャ同士、心通じ合っちゃったんかなぁ」
「ってことは、ウチら、キューピッドじゃん! きゃはははっ!」
教室の隅から聞こえてくる彼女達の笑い声に、沙雨は耳まで燃えるように熱くなってうつむいた。
このままでは、彼女達の標的が、沙雨ばかりでなく和泉にまで飛び火するかもしれない。
沙雨は膝の上で震える手を握りこみながら、のほほんと話しかけてきた和泉を睨みつけた。
「…………あたしにこれ以上関わらないで。目障りなの、あたしの前から消えて」
なんのつもりで、和泉が沙雨の告白を受け入れたのかは分からない。
でも、もしそれが憐憫の情からくる行動なのだとしたら、余計なおせっかいだ。
彼は、不憫な沙雨のヒーローにでもなったつもりなのだろうか。
沙雨には、自分が無愛想でとっつきづらいという自覚がある。
明らかに浮いているし、いじめられても仕方がないと諦めているのだから、放っておいてほしいのに。
和泉は、柔らかい笑みを崩さない。
「いやだよ、君が付き合おうって言ったんだから」
だけど、その穏やかな声には、有無を言わせない強さがあった。
「責任を取って、せめて、クリスマスまでは付き合ってよ。そうしたら、君の言う通りちゃんと消えるから」
なんとか言い返そうとしたが、言葉が見つからなかった。
教室の窓の外には、昨日と同じく、今にも泣き出しそうな分厚い灰色の雲が垂れこめていた。
*
和泉日向の諦めは、すこぶる悪かった。
沙雨が徹底的に無視を決めこんでいるというのに、来る日も来る日も、馬鹿みたいな笑顔で挨拶してくる。
風に吹かれたらよろけてしまいそうな線の細い身体をしているくせに、その心の豪胆さは計り知れなかった。
朝、昼休み、放課後。
和泉は、いつも一人でいる沙雨に近づいてきては、あの太陽みたいな笑顔を向けてくる。
頑固な沙雨も、冬の色を帯びはじめた十一月には、根負けしそうになっていた。
気がつけば、和泉のことを考えている。
大人しそうに見えて、意外と、肝が太いところ。
クラスの女子にいじめられている沙雨と関わることに、全く恐怖心を抱いていなさそうなところ。
そういえば、彼との奇妙な関係が始まってから、彼女たちに高圧的に絡まれることが減った。
最近の彼女たちの興味は、沙雨と和泉の奇妙な根性比べに移っているようだ。
ある放課後。下駄箱で上履きからローファーに履き替えながら、沙雨は独り言を漏らしていた。
「……和泉ってほんとヘンなやつ」
「お!? やっと僕に興味を持ってくれた?」
「ぎゃあっ!」
驚きすぎて、ヘンな声が出た。
和泉はあられもない悲鳴をあげた沙雨を見て目を丸くした後、歌うように笑った。
「ははっ。水瀬さん、そんな声も出るんだね。新発見だなぁ」
「…………」
「ねえ、そろそろ僕のこと無視するのを諦めてくれない?」
「……なんで、よ」
いつしか和泉と真正面から対峙するのがどんどん怖くなっていった。
最近、彼のことを考えると、胸が締めつけられたようになって息苦しい。
「どうして……どうして、諦めてくれないの。あたしが……かわいそう、だから?」
声が震えた。
声だけじゃない、身体の芯から震えている。
――お願いだから、かわいそうで見ていられないからだと言って。あたしを失望させてよ。これ以上、心を揺さぶるようなことを言わないで。
和泉は、うつむく沙雨を、濁りのない瞳で見つめながら微笑んだ。
「ちがうよ。僕はね、水瀬さんに告白された時、君と関わるきっかけが持てて嬉しかったんだ。だから、嫌々告白させられたんだろうなって分かっていたけど、チャンスだと思って頷いてしまった。しつこくてごめんね、水瀬さん」
ダメだ。
もう、涙腺が持ちそうにない。
その瞬間、沙雨は無我夢中で走って、和泉の前から逃げ出した。
「……っっ。ほんっとうになんなの、アイツ。なんで、なんであんなやさしいことを言うの」
沙雨が和泉に取った態度は、ずっと最低の極みだったのに。
垂れこめていた分厚い雲から、一斉に細い雨が降り出した。傘も持たず、濡れることもかまわないでひたすら駅を目指して駆け抜ける。沙雨の白い頬を、幾筋もの涙と雨が交じり合って、流れ落ちた。
沙雨が家にたどり着いた頃には、すっかり濡れ鼠になっていた。
*
その翌朝。
和泉は、めげずに沙雨へ挨拶をしてきた。
「おはよう、水瀬さん」
その顔がいつもより嬉しそうな気がして、胸が高鳴るのを止められない。
昨日あんな一方的に逃げ出したのに、それでも彼は、沙雨を見捨てなかった。
そのことを、たまらなく喜んでしまっている。もう、隠しきれないほどに。
「……負け、よ」
「え?」
「だから……あたしの負けって言ったの」
照れ隠しにそっぽを向いて言ったら、和泉が心の底から嬉しそうな顔をしたから、ますます胸が苦しくなった。
「やっとだ。やっと、君をつかまえた」
和泉ときちんと向き合うようになってからの日々は、今までの灰色に沈んでいた学校生活が嘘だったかのように楽しくなった。
屋上でお昼ご飯を食べたり。
図書室で一緒に勉強をしたり。
コンビニで買ったアイスを食べながら、駅まで一緒に歩いたり。
その全てが、嬉しくて、楽しくて、心が弾んで。
「僕ね、いま、一生分の幸せをもらっている気がする」
「はあ? ……お、大袈裟すぎ、だし」
「最近、よく雨が降るよね」
「えっ?」
「僕さ、雨が好きなんだ」
「……へえ、あたしは嫌いだけど。傘差さなきゃいけないし、濡れるし、いろいろ面倒じゃん。和泉はほんとに変わってるね」
「うん。それでも僕は、雨が好きだよ」
彼がきっぱりと断言した時、胸がぎゅっと締め付けられた。
最近、和泉にやさしくされると、胸が詰まるほどの幸せを感じて泣きそうになってしまう。だけど沙雨は、頑なに彼の前では泣かず、彼と別れた後に人目を忍ぶように涙を流した。
最近、この街には、よく雨が降る。
やさしく街を包み込むような、あたたかい雨だ。
✳︎
二人の幸せな日々は、そう長く続かなかった。
凍てつくように寒い十二月に入った頃。
放課後、階段の踊り場で、彼女たちが話している傍を通りかかった。
「なんかさー、アイツら最近フツーに良い感じじゃね?」
「こうなってくると、和泉とかいうひょろ男もうぜえな」
あまりの衝撃に、身体がふらついた。
ついに、沙雨が恐れていたことが現実になってしまったのだ。
早く、和泉を遠ざけなければ。彼にまで被害が及ぶ前に、早く。
「待って! あ、あたしは……和泉のことなんて、なんとも思ってないよ」
彼女たちには嘘だとバレバレだろうが、それで良い。
「ストーカーっぽいし、迷惑だから……もうじき、適当に振ろうと、思って、いて」
笑え。笑うんだ。
顔が強張っていても、惨めでも良い。
なぜなら、彼女たちの大好物は、いけ好かない沙雨の不幸だから。
でも、泣くのだけは、堪えろ。
今ここで泣いたら、孤立してでも不愛想を貫いた沙雨の今までの苦労が、ぜんぶ水の泡になってしまう。
「ストーカーっぽい、か……」
「和泉っ!」
階段の下で、困ったように眉尻を下げた和泉が苦笑いしているのが目に入った時、沙雨の心臓はナイフで滅多刺しにされたように痛んだ。
その日、街には激しい雨が降り続いた。
*
結果的にとはいえ和泉に酷い言葉を投げつけてしまった翌朝、彼は学校に来なかった。
それから一週間経っても、彼の席は空いたままで、沙雨はひどい不安に襲われた。
気になって、担任の教師に理由を聞いたが、風邪をこじらせているらしい。
沙雨は、和泉の家も、連絡先すらも知らない。
あんなに一緒にいたのに、お見舞いの言葉一つすら届けることができないなんて。ちっぽけな意地をはって、自分から連絡先を聞こうとしなかった過去の自分を殴りたくなった。
沙雨は、また、教室で一人ぼっちとなった。
一人でいることには、慣れている。
一人でいる限り、人前で泣くことは絶対にない。
なのに。それなのに。
馬鹿みたいに、和泉のことばかり考えている。
和泉に会いたい。
会って、あの言葉は真っ平な嘘だったって、ちゃんと謝りたい。
和泉が学校に来なくなってから二週間が経った時、担任の教師が、申し訳なさそうな顔をして沙雨に頭を下げてきた。
「ごめんなさい、水瀬さん。和泉くんは、実は風邪ではないんです」
「えっ」
「本当は……入院しています。本人に、お見舞いとか湿っぽい雰囲気が苦手だから、クラスの誰にも言わないでほしいと口封じされていたんです。ですが……あまりにも辛そうな水瀬さんの顔を見ていたら、本当にこのままで良いのか分からなくなってしまって。黙っていて、ごめんなさい」
教えてもらった病院に、急いで駆けつけた。
病室内の一室に和泉というプレートがかかっているのを発見し、その部屋の引き戸を勢いよく開いた瞬間、沙雨は絶句した。
「いず、み……?」
目の前の光景を、信じたくなかった。
病室の白いベッドで何本ものチューブに繋がれている彼は、まるで、余命幾ばくかの病人のようだ。
「水瀬さん……。来て、くれたんだ。せんせーから、聞いたの?」
「ねえ。これ、は……なに?」
「そんな顔をしないでよ、水瀬さん。クリスマスまでには消えるって、最初に言ったでしょ」
「っっ」
ダメだ。
ずっとずっと、誰にも悟られぬよう、我慢していたのに。
堪えきれず、沙雨の瞳から涙が幾筋も伝った。
その瞬間、窓の外で、沙雨の涙に呼応するように細い雨が降り始めた。
和泉は窓の外の雨を見つめながら、口元をほころばせた。
「やっぱり、僕の思っていた通りだったんだ。水瀬さん。君が泣くと、本当に雨が降るんだね」
息が止まるかと思うほど、驚いた。
「どう、して」
和泉は、気がついていたの? そうだとしたら、いつから?
「黙っていてごめんね。僕はね、中学の時から、君のことが気になっていたんだよ」
「それって、どう、いう……」
彼は、やさしい声音で語った。
✳︎
僕は、昔から、雨が好きだった。
雨が降っている時だけは、外で遊びまわる友達たちに嫉妬しなくてすんだから。
どうしてこんな病弱な身体で生まれてきたんだろうって、己の運命を嘆かずにいられたから。
中学時代は、入院ばかりだった。
なんとか卒業はできたけど、ろくに学校へも通えなかった。
このまま僕の人生に楽しいことなんて一つも起こりやしないって塞ぎこんでいた時に、僕は、君のことを知った。
君はその頃、この病院に入院してきた妹さんのお見舞いにきていた。
僕は、毎日欠かさずお見舞いにきている君を、この部屋の窓から眺めていた。
病院から帰っていく君はいつだって大事な妹の回復を願っていたのだろう、肩を震わせて泣いていた。
そして、君が泣いている日は、いつも雨が降っていた。
最初は、偶然だろうと思っていた。
でも、君がすすり泣き始めると、決まって雨が降る。しかも、君はまるであらかじめそうなることが分かっているかのように、雨が降るより前に傘を差すんだ。
僕は、いつしか想像するようになった。
僕が好きなこの街の雨をもたらしているのは、君なんじゃないかって。
もちろん中学生の考えついた突拍子もない妄想なんだけど、そうだったら良いなぁって。
妹想いなやさしい君の涙は、あたたかくて、綺麗だったから。
他人のことを想って泣く君に、僕はたぶん、恋をしていたんだ。
*
病室の窓を、大粒の雨が叩きつける。
「最近は体調が幾分かマシになっていたから、高校には運良く通えていた。そして僕は、奇跡的に君と同じクラスになったんだ。最初は君が病院で泣いていた時とは別人のように無表情だったから驚いた。変わってしまったんじゃないかって不安に思っていたけど、ちがったんだ。君は、不愛想にならざるをえなかったんじゃないかな。君が泣くと、雨が降る。それを誰かに知られるのが恐ろしくて、ずっと人前で泣かないように頑張っていたんじゃない?」
涙が止まらない。窓の外の雨脚も、どんどん強くなる。
「本当はね、君が、クラスの一部の女子に心無い言葉を浴びせられていたことにも前から気がついていた。でも、君と話すこともままならないのに、どうやって手を差し伸べたら良いのか分からなくて途方に暮れていた。役立たずで、ごめん。でもね、彼女たちには感謝もしてるんだ。君にとっては冴えない僕に告白するなんて罰ゲーム以外のなにものでもなかっただろうけど、僕は、君と関わる最後のチャンスを絶対に手放してはいけないって覚悟を持てたから」
沙雨はずっと、自分は雨をもたらす気味の悪い人間なのだと信じて疑っていなかった。
家族以外の誰にも、この秘密を知られてはならないと思っていた。
「水瀬さん。諦めて、僕と付き合ってくれて本当にありがとう。とても楽しい時間だった。もう、この世に思い残すことはないよ」
本当の自分のことを分かってくれる他人など、出逢えるわけがないと諦めていたのに。
「あははっ。外、土砂降りだねぇ」
「和泉っ! ずっと、ずっと……感じ悪くして、ごめん。酷いことをたくさん言って、ごめん。あたしね、和泉のこと、ストーカーだなんてこれっぽっちも思ってないよ。だって、あたしは、あたしは……和泉のことがっ、大好き、だからっ」
「ふふ、やっと素直になったね。でもね、あれは本心じゃないって分かっていたから大丈夫だよ。タイミング悪く学校に行けなくなって、ごめんね。でも……僕に遺された時間はもう少ないから、君に会うべきなのか分からなかった。僕は、君の重荷にだけはなりたくないから」
「お願いっ。お願い、だから……そんな、最期みたいなこと言わないでよ。まだ、クリスマスきてないじゃん。ねえっ……いなく、ならないでよ……」
窓の外で降りしきる滝のような雨を眺めながら、彼は泣きそうに顔をゆがめて笑った。
「お願いを聞いてあげられそうになくて、ごめんね。ねえ、水瀬さん……ううん、沙雨。僕は、不器用でやさしい君のことが大好きだった。これからは、ちゃんと人前でも泣いてね。僕がいなくなった後も、思いきり甘えられる人を見つけてね。でも、時々は……僕のことを想って、雨を降らせてくれたら嬉しいなぁ、なんてね」
和泉日向は、それから数日後に、クリスマスを待たずして眠るように息を引き取った。
その日は、この街が沈んでしまいそうなほどの記録的な大雨が降った。
*
この街の天気は、予測不可能だ。
もうじき、再び寒い冬が巡ってくる。
和泉日向があまりにも若くしてこの世を去った日から、そろそろ一年が経とうとしていた。
黒い質素なワンピースを身に纏った水瀬沙雨は、彼の墓標の前に立ちながら、人目も憚らず涙を流していた。
今日も、この街の雨は降り止みそうにない。【完】
科学の力を持ってしてもその原因は解明できず、気象予報士の間では、まるで予測不可能だと恐れられている。
✳︎
水瀬沙雨は、鉄壁の無表情を崩さぬまま、クラスメイトといっても顔と名前程度しか知らない目の前の少年に冷たい声音で告げた。
「和泉。……あたしと、付き合ってくれない?」
体育館裏に、沈黙が舞い降りた。
涼を含んだ十月の風が、沙雨の真っ直ぐに伸びた黒い髪をなびかせる。
沙雨は、和泉日向に振られることを望んでいた。
というよりも、振られなければおかしい。
高校に入学してもう半年経つが、二人は、一度もまともに会話をしたことがないからだ。
この告白は、最初から振られるためだけのもの。
物陰から息をひそめ、この明らかに様子のおかしい告白をニヤニヤと眺めている彼女たちの、見せ物になるために。
「うん、良いよ」
「……は?」
「だから、告白の返事だよ。僕たち、付き合おうか」
「な……なにを言っているの? あんた、頭おかしいんじゃないの」
「ひどいな。告白してきたのは、君なのに」
沙雨には、目の前でくすくすと笑っている少年が、理解の及ばない生物に見えた。
なんで? どうして、そんなにあっさりと受け入れるの?
得体の知れない恐怖に、脇から汗が滲み出て、眩暈までしてくる。
きっと、この一部始終を目撃している彼女たちも、予想外の展開に開いた口が塞がらないことだろう。
「もしかして……あんたも」
あたしのこと、馬鹿にしてるの?
沙雨の震える唇からやっとのことで漏れ出たのは、言葉ではなく、か細い息だけだ。
空は、いつの間にか、どんよりと厚い雲に覆われていた。
今にも、雨が降り出しそうだ。
「これからよろしくね、水瀬さん」
和泉は、怯える沙雨を見つめながら、ひだまりのような笑みを浮かべた。
✳︎
家族で夕飯を食べ終えた後、沙雨は妹の沙夜を自分の部屋へ呼び出した。
今日の放課後に起きた珍妙な出来事を、誰かに話さずにはいられなかったからだ。
妹に余計な心配はかけぬよう、罰ゲームとして嫌々告白させられたという詳細は伏せた。
「えええっ! お姉ちゃん、彼氏ができたの⁉︎」
「う、うーん。あたしもよく分かんないんだけど……からかわれてるだけだと思う」
今年で中学二年生になる妹は、ベッドに腰掛けて足をぷらぷらさせながら、大きな瞳を瞬かせている。
「……ほんとにヘンな奴。大人しそうに見えるのに」
「その人すごいなぁ……」
「はあ?」
「見る目があるのかもしれないよ! お姉ちゃんの分かりづらい魅力に、ちゃんと気がついてるってこと!」
それは事の詳細を知らない沙夜の妄想だろう。
なにせ、沙雨はこれまで和泉と接点すらなかったのだから。人格を知られようがない。
「沙夜は、テニス部どう? 順調?」
強引に話題を変えた。
これ以上和泉の話を続けて、どうしてそんな状況になったのかまで沙夜に知られるのは避けたかったから。
「うん! この前も試合に勝ったよ!」
「そっか、それは良かった」
嬉しそうに笑う紗夜の小麦色にやけた肌を見つめながら、キャンドルを灯されたように温かい気持ちになった。
昔の妹は、太陽を知らぬ白い肌をしていたのだ。
病弱で、ろくに外に出ることも叶わなかったから。
しかし今の紗夜は、小学時代に命の危機にさらされていたとは思えないほど回復し、テニスまでできるようになった。
妹を想って、泣いてばかりいた日々が懐かしい。
沙夜が、無事に健康を取り戻してくれて本当に良かったと、沙雨はあらためて思った。
*
その翌朝。
沙雨はいつもどおり澄ました顔をして教室に入った。
何食わぬ顔で席についたが、内心は、動揺と焦りとではちきれそうになっていた。
和泉日向。
彼の考えていることが、まるで分からない。
なぜ彼は、沙雨の告白を受け入れたりしたのだろう。
あんな、あからさまに罰ゲームでさせられていると分かる、情緒もへったくれもない告白を。
「水瀬さん、おはよう」
「っ!」
「そんなに怯えないでよ。幽霊じゃないんだから」
気がつけば、心中に思い浮かべていた人物が目の前にいて、沙雨は顔を強張らせた。
「わっ! 和泉、マジで水瀬に話しかけてるじゃん」
「ウケるんですけど! まさか、本気で付き合っちゃった系? 隠キャ同士、心通じ合っちゃったんかなぁ」
「ってことは、ウチら、キューピッドじゃん! きゃはははっ!」
教室の隅から聞こえてくる彼女達の笑い声に、沙雨は耳まで燃えるように熱くなってうつむいた。
このままでは、彼女達の標的が、沙雨ばかりでなく和泉にまで飛び火するかもしれない。
沙雨は膝の上で震える手を握りこみながら、のほほんと話しかけてきた和泉を睨みつけた。
「…………あたしにこれ以上関わらないで。目障りなの、あたしの前から消えて」
なんのつもりで、和泉が沙雨の告白を受け入れたのかは分からない。
でも、もしそれが憐憫の情からくる行動なのだとしたら、余計なおせっかいだ。
彼は、不憫な沙雨のヒーローにでもなったつもりなのだろうか。
沙雨には、自分が無愛想でとっつきづらいという自覚がある。
明らかに浮いているし、いじめられても仕方がないと諦めているのだから、放っておいてほしいのに。
和泉は、柔らかい笑みを崩さない。
「いやだよ、君が付き合おうって言ったんだから」
だけど、その穏やかな声には、有無を言わせない強さがあった。
「責任を取って、せめて、クリスマスまでは付き合ってよ。そうしたら、君の言う通りちゃんと消えるから」
なんとか言い返そうとしたが、言葉が見つからなかった。
教室の窓の外には、昨日と同じく、今にも泣き出しそうな分厚い灰色の雲が垂れこめていた。
*
和泉日向の諦めは、すこぶる悪かった。
沙雨が徹底的に無視を決めこんでいるというのに、来る日も来る日も、馬鹿みたいな笑顔で挨拶してくる。
風に吹かれたらよろけてしまいそうな線の細い身体をしているくせに、その心の豪胆さは計り知れなかった。
朝、昼休み、放課後。
和泉は、いつも一人でいる沙雨に近づいてきては、あの太陽みたいな笑顔を向けてくる。
頑固な沙雨も、冬の色を帯びはじめた十一月には、根負けしそうになっていた。
気がつけば、和泉のことを考えている。
大人しそうに見えて、意外と、肝が太いところ。
クラスの女子にいじめられている沙雨と関わることに、全く恐怖心を抱いていなさそうなところ。
そういえば、彼との奇妙な関係が始まってから、彼女たちに高圧的に絡まれることが減った。
最近の彼女たちの興味は、沙雨と和泉の奇妙な根性比べに移っているようだ。
ある放課後。下駄箱で上履きからローファーに履き替えながら、沙雨は独り言を漏らしていた。
「……和泉ってほんとヘンなやつ」
「お!? やっと僕に興味を持ってくれた?」
「ぎゃあっ!」
驚きすぎて、ヘンな声が出た。
和泉はあられもない悲鳴をあげた沙雨を見て目を丸くした後、歌うように笑った。
「ははっ。水瀬さん、そんな声も出るんだね。新発見だなぁ」
「…………」
「ねえ、そろそろ僕のこと無視するのを諦めてくれない?」
「……なんで、よ」
いつしか和泉と真正面から対峙するのがどんどん怖くなっていった。
最近、彼のことを考えると、胸が締めつけられたようになって息苦しい。
「どうして……どうして、諦めてくれないの。あたしが……かわいそう、だから?」
声が震えた。
声だけじゃない、身体の芯から震えている。
――お願いだから、かわいそうで見ていられないからだと言って。あたしを失望させてよ。これ以上、心を揺さぶるようなことを言わないで。
和泉は、うつむく沙雨を、濁りのない瞳で見つめながら微笑んだ。
「ちがうよ。僕はね、水瀬さんに告白された時、君と関わるきっかけが持てて嬉しかったんだ。だから、嫌々告白させられたんだろうなって分かっていたけど、チャンスだと思って頷いてしまった。しつこくてごめんね、水瀬さん」
ダメだ。
もう、涙腺が持ちそうにない。
その瞬間、沙雨は無我夢中で走って、和泉の前から逃げ出した。
「……っっ。ほんっとうになんなの、アイツ。なんで、なんであんなやさしいことを言うの」
沙雨が和泉に取った態度は、ずっと最低の極みだったのに。
垂れこめていた分厚い雲から、一斉に細い雨が降り出した。傘も持たず、濡れることもかまわないでひたすら駅を目指して駆け抜ける。沙雨の白い頬を、幾筋もの涙と雨が交じり合って、流れ落ちた。
沙雨が家にたどり着いた頃には、すっかり濡れ鼠になっていた。
*
その翌朝。
和泉は、めげずに沙雨へ挨拶をしてきた。
「おはよう、水瀬さん」
その顔がいつもより嬉しそうな気がして、胸が高鳴るのを止められない。
昨日あんな一方的に逃げ出したのに、それでも彼は、沙雨を見捨てなかった。
そのことを、たまらなく喜んでしまっている。もう、隠しきれないほどに。
「……負け、よ」
「え?」
「だから……あたしの負けって言ったの」
照れ隠しにそっぽを向いて言ったら、和泉が心の底から嬉しそうな顔をしたから、ますます胸が苦しくなった。
「やっとだ。やっと、君をつかまえた」
和泉ときちんと向き合うようになってからの日々は、今までの灰色に沈んでいた学校生活が嘘だったかのように楽しくなった。
屋上でお昼ご飯を食べたり。
図書室で一緒に勉強をしたり。
コンビニで買ったアイスを食べながら、駅まで一緒に歩いたり。
その全てが、嬉しくて、楽しくて、心が弾んで。
「僕ね、いま、一生分の幸せをもらっている気がする」
「はあ? ……お、大袈裟すぎ、だし」
「最近、よく雨が降るよね」
「えっ?」
「僕さ、雨が好きなんだ」
「……へえ、あたしは嫌いだけど。傘差さなきゃいけないし、濡れるし、いろいろ面倒じゃん。和泉はほんとに変わってるね」
「うん。それでも僕は、雨が好きだよ」
彼がきっぱりと断言した時、胸がぎゅっと締め付けられた。
最近、和泉にやさしくされると、胸が詰まるほどの幸せを感じて泣きそうになってしまう。だけど沙雨は、頑なに彼の前では泣かず、彼と別れた後に人目を忍ぶように涙を流した。
最近、この街には、よく雨が降る。
やさしく街を包み込むような、あたたかい雨だ。
✳︎
二人の幸せな日々は、そう長く続かなかった。
凍てつくように寒い十二月に入った頃。
放課後、階段の踊り場で、彼女たちが話している傍を通りかかった。
「なんかさー、アイツら最近フツーに良い感じじゃね?」
「こうなってくると、和泉とかいうひょろ男もうぜえな」
あまりの衝撃に、身体がふらついた。
ついに、沙雨が恐れていたことが現実になってしまったのだ。
早く、和泉を遠ざけなければ。彼にまで被害が及ぶ前に、早く。
「待って! あ、あたしは……和泉のことなんて、なんとも思ってないよ」
彼女たちには嘘だとバレバレだろうが、それで良い。
「ストーカーっぽいし、迷惑だから……もうじき、適当に振ろうと、思って、いて」
笑え。笑うんだ。
顔が強張っていても、惨めでも良い。
なぜなら、彼女たちの大好物は、いけ好かない沙雨の不幸だから。
でも、泣くのだけは、堪えろ。
今ここで泣いたら、孤立してでも不愛想を貫いた沙雨の今までの苦労が、ぜんぶ水の泡になってしまう。
「ストーカーっぽい、か……」
「和泉っ!」
階段の下で、困ったように眉尻を下げた和泉が苦笑いしているのが目に入った時、沙雨の心臓はナイフで滅多刺しにされたように痛んだ。
その日、街には激しい雨が降り続いた。
*
結果的にとはいえ和泉に酷い言葉を投げつけてしまった翌朝、彼は学校に来なかった。
それから一週間経っても、彼の席は空いたままで、沙雨はひどい不安に襲われた。
気になって、担任の教師に理由を聞いたが、風邪をこじらせているらしい。
沙雨は、和泉の家も、連絡先すらも知らない。
あんなに一緒にいたのに、お見舞いの言葉一つすら届けることができないなんて。ちっぽけな意地をはって、自分から連絡先を聞こうとしなかった過去の自分を殴りたくなった。
沙雨は、また、教室で一人ぼっちとなった。
一人でいることには、慣れている。
一人でいる限り、人前で泣くことは絶対にない。
なのに。それなのに。
馬鹿みたいに、和泉のことばかり考えている。
和泉に会いたい。
会って、あの言葉は真っ平な嘘だったって、ちゃんと謝りたい。
和泉が学校に来なくなってから二週間が経った時、担任の教師が、申し訳なさそうな顔をして沙雨に頭を下げてきた。
「ごめんなさい、水瀬さん。和泉くんは、実は風邪ではないんです」
「えっ」
「本当は……入院しています。本人に、お見舞いとか湿っぽい雰囲気が苦手だから、クラスの誰にも言わないでほしいと口封じされていたんです。ですが……あまりにも辛そうな水瀬さんの顔を見ていたら、本当にこのままで良いのか分からなくなってしまって。黙っていて、ごめんなさい」
教えてもらった病院に、急いで駆けつけた。
病室内の一室に和泉というプレートがかかっているのを発見し、その部屋の引き戸を勢いよく開いた瞬間、沙雨は絶句した。
「いず、み……?」
目の前の光景を、信じたくなかった。
病室の白いベッドで何本ものチューブに繋がれている彼は、まるで、余命幾ばくかの病人のようだ。
「水瀬さん……。来て、くれたんだ。せんせーから、聞いたの?」
「ねえ。これ、は……なに?」
「そんな顔をしないでよ、水瀬さん。クリスマスまでには消えるって、最初に言ったでしょ」
「っっ」
ダメだ。
ずっとずっと、誰にも悟られぬよう、我慢していたのに。
堪えきれず、沙雨の瞳から涙が幾筋も伝った。
その瞬間、窓の外で、沙雨の涙に呼応するように細い雨が降り始めた。
和泉は窓の外の雨を見つめながら、口元をほころばせた。
「やっぱり、僕の思っていた通りだったんだ。水瀬さん。君が泣くと、本当に雨が降るんだね」
息が止まるかと思うほど、驚いた。
「どう、して」
和泉は、気がついていたの? そうだとしたら、いつから?
「黙っていてごめんね。僕はね、中学の時から、君のことが気になっていたんだよ」
「それって、どう、いう……」
彼は、やさしい声音で語った。
✳︎
僕は、昔から、雨が好きだった。
雨が降っている時だけは、外で遊びまわる友達たちに嫉妬しなくてすんだから。
どうしてこんな病弱な身体で生まれてきたんだろうって、己の運命を嘆かずにいられたから。
中学時代は、入院ばかりだった。
なんとか卒業はできたけど、ろくに学校へも通えなかった。
このまま僕の人生に楽しいことなんて一つも起こりやしないって塞ぎこんでいた時に、僕は、君のことを知った。
君はその頃、この病院に入院してきた妹さんのお見舞いにきていた。
僕は、毎日欠かさずお見舞いにきている君を、この部屋の窓から眺めていた。
病院から帰っていく君はいつだって大事な妹の回復を願っていたのだろう、肩を震わせて泣いていた。
そして、君が泣いている日は、いつも雨が降っていた。
最初は、偶然だろうと思っていた。
でも、君がすすり泣き始めると、決まって雨が降る。しかも、君はまるであらかじめそうなることが分かっているかのように、雨が降るより前に傘を差すんだ。
僕は、いつしか想像するようになった。
僕が好きなこの街の雨をもたらしているのは、君なんじゃないかって。
もちろん中学生の考えついた突拍子もない妄想なんだけど、そうだったら良いなぁって。
妹想いなやさしい君の涙は、あたたかくて、綺麗だったから。
他人のことを想って泣く君に、僕はたぶん、恋をしていたんだ。
*
病室の窓を、大粒の雨が叩きつける。
「最近は体調が幾分かマシになっていたから、高校には運良く通えていた。そして僕は、奇跡的に君と同じクラスになったんだ。最初は君が病院で泣いていた時とは別人のように無表情だったから驚いた。変わってしまったんじゃないかって不安に思っていたけど、ちがったんだ。君は、不愛想にならざるをえなかったんじゃないかな。君が泣くと、雨が降る。それを誰かに知られるのが恐ろしくて、ずっと人前で泣かないように頑張っていたんじゃない?」
涙が止まらない。窓の外の雨脚も、どんどん強くなる。
「本当はね、君が、クラスの一部の女子に心無い言葉を浴びせられていたことにも前から気がついていた。でも、君と話すこともままならないのに、どうやって手を差し伸べたら良いのか分からなくて途方に暮れていた。役立たずで、ごめん。でもね、彼女たちには感謝もしてるんだ。君にとっては冴えない僕に告白するなんて罰ゲーム以外のなにものでもなかっただろうけど、僕は、君と関わる最後のチャンスを絶対に手放してはいけないって覚悟を持てたから」
沙雨はずっと、自分は雨をもたらす気味の悪い人間なのだと信じて疑っていなかった。
家族以外の誰にも、この秘密を知られてはならないと思っていた。
「水瀬さん。諦めて、僕と付き合ってくれて本当にありがとう。とても楽しい時間だった。もう、この世に思い残すことはないよ」
本当の自分のことを分かってくれる他人など、出逢えるわけがないと諦めていたのに。
「あははっ。外、土砂降りだねぇ」
「和泉っ! ずっと、ずっと……感じ悪くして、ごめん。酷いことをたくさん言って、ごめん。あたしね、和泉のこと、ストーカーだなんてこれっぽっちも思ってないよ。だって、あたしは、あたしは……和泉のことがっ、大好き、だからっ」
「ふふ、やっと素直になったね。でもね、あれは本心じゃないって分かっていたから大丈夫だよ。タイミング悪く学校に行けなくなって、ごめんね。でも……僕に遺された時間はもう少ないから、君に会うべきなのか分からなかった。僕は、君の重荷にだけはなりたくないから」
「お願いっ。お願い、だから……そんな、最期みたいなこと言わないでよ。まだ、クリスマスきてないじゃん。ねえっ……いなく、ならないでよ……」
窓の外で降りしきる滝のような雨を眺めながら、彼は泣きそうに顔をゆがめて笑った。
「お願いを聞いてあげられそうになくて、ごめんね。ねえ、水瀬さん……ううん、沙雨。僕は、不器用でやさしい君のことが大好きだった。これからは、ちゃんと人前でも泣いてね。僕がいなくなった後も、思いきり甘えられる人を見つけてね。でも、時々は……僕のことを想って、雨を降らせてくれたら嬉しいなぁ、なんてね」
和泉日向は、それから数日後に、クリスマスを待たずして眠るように息を引き取った。
その日は、この街が沈んでしまいそうなほどの記録的な大雨が降った。
*
この街の天気は、予測不可能だ。
もうじき、再び寒い冬が巡ってくる。
和泉日向があまりにも若くしてこの世を去った日から、そろそろ一年が経とうとしていた。
黒い質素なワンピースを身に纏った水瀬沙雨は、彼の墓標の前に立ちながら、人目も憚らず涙を流していた。
今日も、この街の雨は降り止みそうにない。【完】