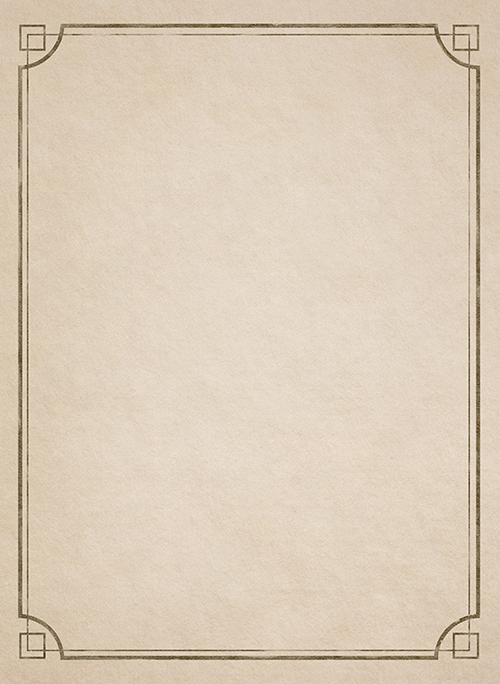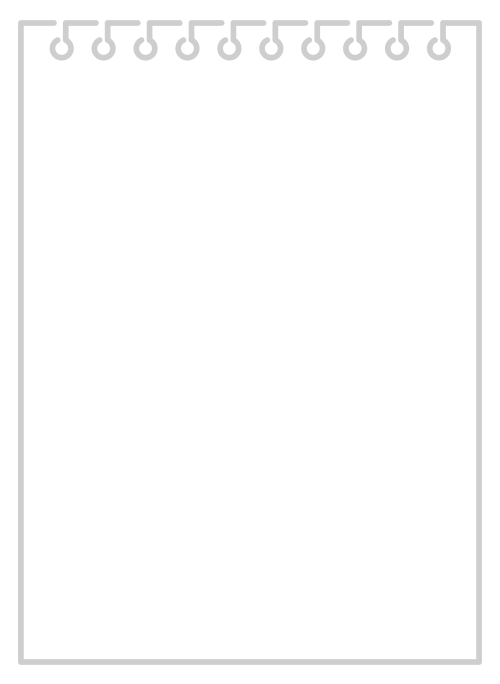ーーーー
部員の1人が学校に来なくなったことは3人とも知っていた。自分たちがおこなったことが原因だと薄々気づいていた。
だが、それを肯定してしまうと犯罪者になった気分になるため気にしないように、何事もなかったように学校生活を送った。
ーーーベースギターの畑愛子はしばらく学校に来ていない。
先生に呼ばれて、事情を聞かれるかと思ったがしばらくそれはなかった。何かあったことは明白だったのに。
ただ、部活はしばらくするなと顧問の坂木からとめられ、バンドの大会にでるのはやめようという話になった。ボーカルである池尻咲は納得はいっていなかったが、渋々頷いた。
3人は、言い聞かせている。
ーーーー本人が、上手くなりたいと願ったから、アドバイスをしてあげただけだ、と。
「ねえ、きっと今からあのこと聞かれるんだよね」
咲が2人にそう問いかける。
3人は部室に呼ばれた。
そして、電気もつけずに部室で待っている。
あのことから約2週間ほどが経って、坂木から部室に来るように言われたのだ。
「愛子のことだとは限らないでしょ」
そう言ったのは、ギターの香澄だ。
否定はしていながらも、額には少し汗が滲んでいる。
「そもそも、あのあと愛子ってどうなったんだろう」
ドラムの凛が俯き加減で2人にそう問いかける。不安そうな、今にも罪悪感で押しつぶされそうな顔である。
咲は、その罪悪感が自分に伝染してこないように軽く笑った。
「普通に家に帰ったんじゃない?なんか問題起きてたら私たちすぐに呼び出しくらってたって。しかも、あの時やりたいって言ったのは愛子だよ」
「足まで縛って、逃げられないようにするなんて、そんなの、いじ」
「私は」
凛の言葉を遮るように咲が大きな声を出した。
「私は、ただ、上手くなって欲しかっただけ。このメンバーでもっと高みを目指したかったの」
静かな部室に咲の強い言葉が響き渡った。
愛子を陥れたい、いじめたいなんてそんなエゴであんなことはしない。ただ、上手くなってほしい、もっと自分の理想に近づける音作りをしたい。そう思ったから、音楽経験豊富な橋田にアドバイスを求めたのだ。
いい方法があると、そう言われた。
視界をさえぎり、音に集中できる環境をつくる。何度も何度も曲を聴き、一音一音を耳に刻んでいく。
そうしていれば、自分の中にその曲が落とし込まれるのだと橋田は言った。
逃げたいと思っても、逃げられない環境まで持っていってでも曲を落とし込むのだと。
「愛子は、音楽から逃げたんだよ」
咲はそう言った。2人は何も言わなかった。
代わりに、部屋の戸があく。
3人が顔を戸の方に向けた瞬間、表情が困惑の色に染まった。
そんなことを気にしていないかのように、戸を閉めて中に入ってきたその男は、くるりと3人に背を向け戸の外に向かって言葉を放つ。
「九条、やれ」
外から「はいよ!」と声がして何かが戸にぶつかる音がする。そして後ろの方の戸も同じような音がして、3人はますます困惑した。
3人の前に立った男は、音楽の先生である。
「なんで、音代先生」
「坂木先生には荷が重すぎるからな、とでも言っておくよ」
咲の問いに、さらりとそう答えた音代はおもむろに3人の座っている周りを歩き回る。
そして、
ーーーーガン!!!
と、荒々しく教卓を蹴った音代。
いきなり響いたそれに3人はびくりと肩を上げ、短い悲鳴をあげた。
「な、なに、っ」
そして、次は、爪で黒板を引きずり、キーっという不快な音がそこに響き3人は耳をふさいだ。
そして、音代は無言のままCDプレイヤーを3人の足元におき、音量を最大限に大きくする。
「言っておくが、おれはこういうやり方は嫌いだ」
そう言った後、再生ボタンを押した。
爆音でそこに響き渡る不協和音。
低い唸り声に聞こえる音や、悲鳴に聞こえる音、音が音になっていないものがそこに響き渡る。
「なんなの!こわいんだけど!行こう!!」
咲が立ち上がり、そう言って戸に向かう。
2人も追いかけたが、咲は気づいた。
戸が開かないのだ。
「咲、どうしたの」
「開かない!」
凛が咲の身体を荒々しくどかし、戸を揺らすが開かない。
先ほどの音は、戸を内側から開けられないように何かを引っ掛けた音だった。
試しに後ろの戸も開けようとしたが、同じく開かない。
この現状から逃れられないと悟った3人は再び耳を塞ぐ。耳をつんざく爆音のため、手の壁は何の意味も持たなかった。
耳に響き渡る不協和音。
頭がおかしくなりそうである。
「いや!もうやめてよ!!」
戸の近くにへたり込んだ3人。
息が荒くなり、香澄は吐きそうなのか口に手を押さえた。
咲は、それをみてぎゅっと香澄を抱きしめる。人の温もりを感じ音から逃れたかった。
凛も同じように2人の方に駆け寄る。
そして、しばらくしてやっと音が止まった。
音代が音を止めたのだ。
「よかったな、助けを求めたら音が止む状況で」
静かになったそこに、音代の低い声が響く。
「先生がこんなことしていいと思ってんの、体罰だよ」
「俺はただ人間が不快になる音を奏でただけだ。俺のこれが体罰ならお前らのやったことは何なんだ?」
その問いかけに3人はぐっ、と喉がつまらせる。
「お前らのやったこと」それは愛子にたいしてやったことだと3人とも理解している。
音代は、3人の前にまできてしゃがんだ。
そして蔑むような瞳で3人を見下ろす。
「20世紀にはいり、CIAでテロリストたちにおこなわれた拷問のやり方の1つに、音楽による拷問があったのを知ってるか」
「ご、うもん?」
咲が顔を顰める。音代は「知らなかったのか」と額に手を添えた。
「視界をさえぎり、何度も何度も同じ曲を爆音で聴かせる。その空間は逃げたくても逃げられない。のちに人間は精神的に追いやられていくんだ。外傷はないから拷問にはもってこいのやり方だったんだろうな」
「それって」
凛がおそるおそる口を開いた。
「そうだ、お前たちがやったことは、拷問」
息をのんだ。
自分たちのやったことは、音楽の押し付けどころか精神的においやるための拷問に他ならなかったのだ。
たかが音楽だろうとなめていたが、今の精神が崩壊しそうな不協和音がまだ耳に残っており、納得せざるを得なかった。
逃げたいのに、逃げられない。
耳を塞いでも、唸り声のような音や悲鳴に近い音が鼓膜を揺らす。
愛子も、強制的に音楽を耳に入れることで、精神的に追いやれてしまったのか。
「愛子は、どうなったの」
香澄が音代にそう問う。
「音楽から逃れるために、飛び降りたよ。そこから」
「え、」
「幸い、命には別状はないらしいがまだ病院にいる。骨折もしているからしばらくベースは弾けないな。本人は音楽は辞めたいって言ってる」
「なんですぐに私たちに」
ーーー私たちに言わなかったのか、ではない。私たちのせいにしなかったのだろうか。
自分のせいではないとずっと言い聞かせてきた。押し付けではない。協力して同じ目標に向かいたかっただけだったのに。
「自分でやるって言ったから、3人を責めるなと言っていた」
音代の言葉に、3人は顔をくしゃりと歪ませた。
そう言わせるように誘導させたのは自分たちだったからだ。罪悪感からか目に水が溜まっていく。
「拷問のことを知らなかったにしろ、畑がお前らを責めなくても、俺は責めるぞ。音楽への冒涜だからな」
愛子に、咲は一度「音楽への冒涜」と蔑んだことかある。
その言葉を自分に向けられる時がくるとは思わなかった。悔しい。こんなやり方をしてしまった自分が。
「ごめんなさい」
咲がそう呟くと、2人も小さな声で謝罪の言葉をもらした。
「音楽への謝罪として受け取るが、畑にはちゃんと1人の人間を精神的に追いやったことにたいしてちゃんと謝れよ」
その言葉に3人が頷く。そして3人で手を支えながら立ち上がり、「明日愛子に謝りに行こう」と約束を交わす。
そして、その様子に安堵の息をはいたあと、音代は咲の方に目を向けた。
「誰かに、相談したのか」
「え?」
「バンドのこと」
それに咲は言いづらそうに口を開く。
「橋田くんに、相談しました。
完璧に曲を仕上げるためのコツみたいなことをきいたらこういうやり方をしたらいいって。
橋田くんも、それが拷問に近いことだなんて思っていないと思います」
庇っているというつもりはなく、音楽による拷問なんて、知っていたら自分に教えないだろうと咲は思っているので本心だった。
たいして音代は「そうか」と解せない顔で頷く。
ひとまず、これ以上音楽の闇を刻ませるのはよそうと音代は思った。
「同じ方向に全員が向くことは難しいが、音楽を奏でるものは全員音楽が好きなのは確かだ。あまりこだわるのもよくないからな。適度に自由にやれよ」
アドバイスをはいて、音代はそこを出ようとするが、当然戸はあかない。
終わったあと、九条に開けるように頼むのを忘れていたのだ。
力技で開けようとするが、九条は音代の言いつけをちゃんと守っていた。
少々気性が荒くなった人間があけようとしても開かないようにしっかり閉めろと。
そして、おそらく九条は役割を果たし、意気揚々と帰って行った。
主人公が最終回で復讐を果たし、かっこいい感じで去っていくのを想像していた音代は彼女たちの方を振り向けないでいた。
残されている3人も微妙な顔をしているのが、音代には分かる。
ちなみに、スマホは職員室に忘れてきている。
帰ってくるのがおそいと坂木が痺れをきらしておそらく迎えにくるだろう。
だが、それまでここで何をするのか。
「あのー、音代先生」
「なんだ」
「よかったら、私たちの音楽聴いてくれませんか、オリジナルはないので、カバー曲ばかりですが」
凛が気をつかうように音代にそう言った。
音代は何事もなかったかのように振り返り腕を組む。
ーーーそうだ、何事も会話だ。
自分と彼女たちの会話の方法は、音楽しかない。
畑にたいして、いや、音楽にたいしてどんな思いで向き合っているか理解するにはいい機会である。
「俺は、坂木先生のように生ぬるいことは言わないからな、さっさと楽器の準備しろ」
「はい!」
教育者としてできることは彼女たちがこれ以上音楽の闇に、引きずり込まれないように向き合うことである。