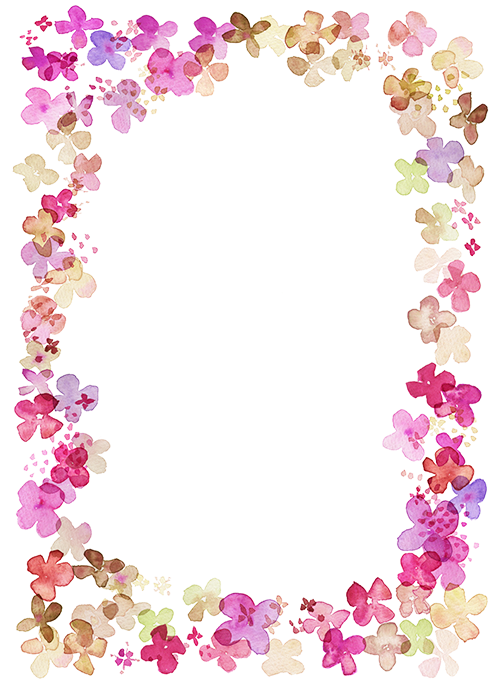湯殿で目を閉じていたサジャは、心配そうな侍女の声に首を横に振った。
やんわりと笑って、続けてと声をかける。
サジャの体を隅々まで侍女たちが清めていく。耳の後ろ、足の指、そして衣服に隠された場所まで指は伸びる。
いつもは触れないところまで清める理由、それがわからないほどサジャは子どもではない。
十六歳の誕生日の今宵、これからサジャは皇帝の寝所を訪れるように命じられている。皇帝の好む香水を忍ばされて、初夜の花嫁の白い薄絹に包まれる。
サジャは体から力を抜いて、虚空に漂うように思いを馳せた。
まぶたを閉じると、幼い頃自分を囲んでいた里が見えた。優しかった精霊たちの笑顔を忘れたことはない。
青い森の中、血に濡れた精霊たちを踏みしめながらサジャを抱き上げた青年。
君は私のものになるんだよ。まだ彼が皇帝と呼ばれていることも知らず、サジャは反射的にしがみついた。
それが十年前のことになる。
サジャが皇帝の寝所に侍って一刻が経ったが、皇帝はまだ現れなかった。
侍女たちはしきりに酒を勧めたり他愛のない話題を振ったりして、サジャを和ませようとする。それをサジャはいつものように穏やかに聞いて微笑んでいた。
緊張しているのはむしろ侍女たちのように思えた。サジャが別段の抵抗もなく皇帝を受け入れるつもりで侍っているのが、彼女らは不気味でならないらしかった。
部屋の外に使者がやって来たらしい。侍女が取り次いだ手紙がサジャの手に渡る。
花の蔓で巻かれた手紙を開くと、サジャは文面に目を通す。
それは熱を帯びた恋文だった。
遅れてすまない。もうしばらく待ってほしい。私は君が心安く過ごせるよう、常に君の身の回りを清めていたいんだ。わかってくれるね?
今のうちに私にねだるものを考えておくといい。愚かしいほどに何でも叶えてみせよう。
愛している、サジャ。文面の最後は幾度となく腕の中でささやかれた言葉で、その熱をサジャは理解できない。
君はいつも健やかでなければと、皇帝はたびたびサジャの身辺を清める。サジャを遠ざけるべきと進言した者を遠ざけ、サジャを精霊界に還すべきと主張する者を……永遠に帰らぬ者とする。
侍女たちが殊更今夜緊張しているのはそういうことなのだろう。サジャはグラスを置いて侍女たちに微笑む。
下がっていいという合図に、侍女たちはあからさまに安心したようだった。静かに寝所から下がっていく。
一人になったサジャは椅子から立ち上がった。窓を開いて、宵の風を感じる。
窓の外には大理石で組まれた小さなあずまやがある。一面に薄く水が張られて、土ではなく水だけで花が育てられている。
サジャが帝国に連れてこられてまもなくの頃、彼女もここで育てられていた。
精霊の中で育ったサジャは服を着ることを知らず、ひがな一日水や木と遊んで過ごしていた。当初皇帝はそんなサジャの生活を変えることはせず、箱の中で愛玩動物を飼うようにサジャを愛でていた。
けれど臣下たちはいずれサジャが成長して皇帝の寵を受け、皇子を産んだとき、国母が愛玩動物では皇帝の権威が地に落ちると考えたようだった。せめて淑女の教育を受けさせた上で、病弱を理由に後宮から出さないこととしてはとの臣下からの懇願を、皇帝は受け入れた。
サジャは素直に教育を受けたが、精霊の中で培った感性はそのままだった。知識はただの知識で、今も水や木の方がサジャの感覚に近しい。
陽光の中の睡蓮の花のようにまどろみ、誰も、皇帝さえも世界の住民ではない。
それは寂しいことなの? そう思ったとき、後ろから抱き寄せられた。
若々しく、純真で狂気じみたほど澄んだ黒い瞳の青年。皇帝は自らの腕でサジャを外界から閉ざすと、その唇に口づけた。
怯えたように身をすくめたのは一瞬。サジャは目を閉じて、自分を育てた人が夫となる日を受け入れた。
君はたぶん生涯、恋を知らないだろう。閨の中で皇帝は言った。
精霊の中で育った君に、私の劣情は理解できない。私は野蛮なその熱で、柔い花のような君にずっと恋焦がれてきた。
けれど君はもう私のものとなった。どこかに行き失せることはできない。
愛している、サジャ。
夫となった人の目覚めの言葉を、サジャは青い朝の中で聞いていた。
やんわりと笑って、続けてと声をかける。
サジャの体を隅々まで侍女たちが清めていく。耳の後ろ、足の指、そして衣服に隠された場所まで指は伸びる。
いつもは触れないところまで清める理由、それがわからないほどサジャは子どもではない。
十六歳の誕生日の今宵、これからサジャは皇帝の寝所を訪れるように命じられている。皇帝の好む香水を忍ばされて、初夜の花嫁の白い薄絹に包まれる。
サジャは体から力を抜いて、虚空に漂うように思いを馳せた。
まぶたを閉じると、幼い頃自分を囲んでいた里が見えた。優しかった精霊たちの笑顔を忘れたことはない。
青い森の中、血に濡れた精霊たちを踏みしめながらサジャを抱き上げた青年。
君は私のものになるんだよ。まだ彼が皇帝と呼ばれていることも知らず、サジャは反射的にしがみついた。
それが十年前のことになる。
サジャが皇帝の寝所に侍って一刻が経ったが、皇帝はまだ現れなかった。
侍女たちはしきりに酒を勧めたり他愛のない話題を振ったりして、サジャを和ませようとする。それをサジャはいつものように穏やかに聞いて微笑んでいた。
緊張しているのはむしろ侍女たちのように思えた。サジャが別段の抵抗もなく皇帝を受け入れるつもりで侍っているのが、彼女らは不気味でならないらしかった。
部屋の外に使者がやって来たらしい。侍女が取り次いだ手紙がサジャの手に渡る。
花の蔓で巻かれた手紙を開くと、サジャは文面に目を通す。
それは熱を帯びた恋文だった。
遅れてすまない。もうしばらく待ってほしい。私は君が心安く過ごせるよう、常に君の身の回りを清めていたいんだ。わかってくれるね?
今のうちに私にねだるものを考えておくといい。愚かしいほどに何でも叶えてみせよう。
愛している、サジャ。文面の最後は幾度となく腕の中でささやかれた言葉で、その熱をサジャは理解できない。
君はいつも健やかでなければと、皇帝はたびたびサジャの身辺を清める。サジャを遠ざけるべきと進言した者を遠ざけ、サジャを精霊界に還すべきと主張する者を……永遠に帰らぬ者とする。
侍女たちが殊更今夜緊張しているのはそういうことなのだろう。サジャはグラスを置いて侍女たちに微笑む。
下がっていいという合図に、侍女たちはあからさまに安心したようだった。静かに寝所から下がっていく。
一人になったサジャは椅子から立ち上がった。窓を開いて、宵の風を感じる。
窓の外には大理石で組まれた小さなあずまやがある。一面に薄く水が張られて、土ではなく水だけで花が育てられている。
サジャが帝国に連れてこられてまもなくの頃、彼女もここで育てられていた。
精霊の中で育ったサジャは服を着ることを知らず、ひがな一日水や木と遊んで過ごしていた。当初皇帝はそんなサジャの生活を変えることはせず、箱の中で愛玩動物を飼うようにサジャを愛でていた。
けれど臣下たちはいずれサジャが成長して皇帝の寵を受け、皇子を産んだとき、国母が愛玩動物では皇帝の権威が地に落ちると考えたようだった。せめて淑女の教育を受けさせた上で、病弱を理由に後宮から出さないこととしてはとの臣下からの懇願を、皇帝は受け入れた。
サジャは素直に教育を受けたが、精霊の中で培った感性はそのままだった。知識はただの知識で、今も水や木の方がサジャの感覚に近しい。
陽光の中の睡蓮の花のようにまどろみ、誰も、皇帝さえも世界の住民ではない。
それは寂しいことなの? そう思ったとき、後ろから抱き寄せられた。
若々しく、純真で狂気じみたほど澄んだ黒い瞳の青年。皇帝は自らの腕でサジャを外界から閉ざすと、その唇に口づけた。
怯えたように身をすくめたのは一瞬。サジャは目を閉じて、自分を育てた人が夫となる日を受け入れた。
君はたぶん生涯、恋を知らないだろう。閨の中で皇帝は言った。
精霊の中で育った君に、私の劣情は理解できない。私は野蛮なその熱で、柔い花のような君にずっと恋焦がれてきた。
けれど君はもう私のものとなった。どこかに行き失せることはできない。
愛している、サジャ。
夫となった人の目覚めの言葉を、サジャは青い朝の中で聞いていた。