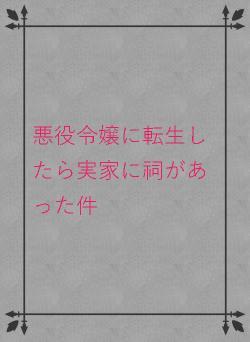特に操る内容が複雑であればあるほど、触れている時間は長くなる。魔術をかけている間に対象の方から、更に深い接触を求められるかもしれないと、姉たちも言っていた。
震える体を月冥が強く抱きしめる。美蘭は無意識に、彼の胸に頬を寄せた。
「でも他に方法がないの……」
「私はこの国を変えようと仲間を募ってきた。貴族の子息の多くは、私に賛同している。兵も宰相のやり方に納得していない者も多い。正当な皇帝として私は宰相を追放できるよう計画をしている。それに君も加わってほしい、美蘭一人が犠牲になる必要なんてないんだよ」
優しい言葉に頷きたくなる。
けれど反乱を起こすにしても、すぐにとはいかないだろう。
迷う美蘭の肩を掴み、月冥が瞳を覗き込む。その青の瞳は、月明かりの中でも宝石のように輝いていた。
まるで明るい未来を見通しているようだと、美蘭はぼんやりと思う。
「それに君には、他の男と口づけなんてしてほしくない」
「えっ?」
至近距離で見つめてくる月冥に、美蘭は赤面する。
「一目見た瞬間に、君に恋をした。こんなにも愛らしい姫は初めて見た」
「そんな、うそよ。私、そんなこと一度も言われたことない」
「焔の神に誓う。君はこの国のどの姫よりも愛らしい。どうか私の妻になってくれないか?」
恐ろしく整った顔で愛を告げられ、美蘭は戸惑う。
頷いてしまいたいけれど、それはきっとしてはいけないことだ。何より月冥と翠国を守る為には、自分の気持ちを抑えなくてはならない。
「月冥の気持ちは、とても嬉しいわ。けど私は、貴方も国も守りたいって思ってる」
「美蘭」
「お願い、聞いて。私はもう一つだけ、使える魔術があるの……私は、今生きている王族の魔術を一度だけ他者に扱う許可が出せるわ」
「他者に魔術を渡せるという事か?」
問われて美蘭は頷く。これは王族の中でも禁忌とされる魔術だ。持って生まれる者は、百年に一人だと言い伝えられている。
「父は、勇気の魔術。協力してくれる兵士を心身共に鼓舞できるわ。一人で大きな木を引き抜けるくらい、力が強くなるの。母は慈愛の魔術。傷ついた兵を瞬きの間になおしてしまうのよ」
二人の姉と、他にも祖父達や血縁のある貴族の魔術を使えるようになるのだと告げる。
「そのようなことができるのなら、あの宰相を倒すのは容易い――」
「私は貴方に、この国と翠国の未来を託したいの」
驚いたように美蘭を見つめていた月冥だが、すぐに表情を曇らせた。
「申し出は嬉しいが、美蘭。君はまだ隠し事をしているね?」
青い瞳は全てを見透かしているようだ。美蘭は覚悟を決めて、口を開く。
「与える魔術は、とても強い力だから……互いに想い合っていなければ私の寿命を奪うことになるの」
小さな窓から差し込む月明かりの下、美蘭は流れる涙を拭うこともなく月冥に告げた。
「貴方になら、私の全部をあげる。だから、絶対に翠国を滅ぼすことは止めさせて」
「そんな事はさせない。君も生きるんだ」
「最初から帰れるなんて思ってなかったわ。だから大丈夫」
「何が大丈夫ものか。君を失ってまで、力を手に入れたくはない」
大きな掌が、美蘭の頬を包み込む。
「君が私を愛してくれているなら、寿命を奪うことはないんだね?」
「そう、だけど……月冥は……それに、私達出会ったばかりなのよ?」
頬を赤らめ唇を尖らせる美蘭の頬に、月冥が唇を寄せた。
「私は君に一目惚れしたよ。君は……私は好みではないかな?」
「そんなことない!」
うっかり本音を口にすると、月冥が心から嬉しそうに笑う。年相応の青年らしい明るい笑顔に、美蘭もつられて笑ってしまう。
「美蘭、愛してる。全てが上手くいったあかつきには、我が伴侶となってほしい」
「いいわ。月冥に嫁いであげる」
この魔術を持って生まれた者は、使った直後死に至ったと翠国の歴史書には書かれていた。
けれど美蘭は、躊躇無く目蓋を閉じる。
「愛してる、愛しい美蘭……」
唇に柔らかな感触を感じた次の瞬間、美蘭は意識を失った。
*****
「あの時は本当に驚いたよ」
「だって、初めてだったんだもの……」
宰相を追放し、無事に焔国の皇帝の座についた月冥が、側に立つ美蘭を抱き寄せる。
王宮にある塔からは、都の町並みが一望できるのだ。
一見立派な皇都だが、そこに住む人々は長年の重税で苦しんでいると月冥が教えてくれた。
賄賂で私腹を肥やしていた貴族達は宰相と共に追放したので、これからは良くなっていくはずだ。
「まさか口づけで気絶するなんて」
「仕方ないでしょ! 恥ずかしかったの!」
「これからは気絶しないように、訓練をしないといけないね」
本気なのか冗談なのか、月冥はくすくすと笑っている。
先帝と宰相の無茶な政のせいで、焔国の民は疲弊していた。どうやら重税で生活できなくなり、逃げ出した民の代わりに近隣国を襲い、奴隷として使っていたらしい。
これからは連れた来られた人々を故郷へと帰し、正常な政に舵を切らなくてはならない。道のりは険しいが月冥ならばやってのけるだろう。
そして美蘭も、翠国の両親に事の顛末を手紙で送り、できる限りの支援を頼んだ。
「美蘭、君が側にいてくれて本当に良かった」
自分の存在が月冥の希望となっているのだと、未だに信じられない。
「本当に私でいいの?」
「私には君だけだよ、美蘭。今後は後宮も廃するつもりだ」
美蘭ただ一人だけを愛するのだと告げられ、赤面してしまう。これからは二人で、この焔国の皇帝、皇妃として歩んで行く。
「私も愛してるわ、月冥」
あの夜、出会った運命は明るい未来を目指して動き始めた。
震える体を月冥が強く抱きしめる。美蘭は無意識に、彼の胸に頬を寄せた。
「でも他に方法がないの……」
「私はこの国を変えようと仲間を募ってきた。貴族の子息の多くは、私に賛同している。兵も宰相のやり方に納得していない者も多い。正当な皇帝として私は宰相を追放できるよう計画をしている。それに君も加わってほしい、美蘭一人が犠牲になる必要なんてないんだよ」
優しい言葉に頷きたくなる。
けれど反乱を起こすにしても、すぐにとはいかないだろう。
迷う美蘭の肩を掴み、月冥が瞳を覗き込む。その青の瞳は、月明かりの中でも宝石のように輝いていた。
まるで明るい未来を見通しているようだと、美蘭はぼんやりと思う。
「それに君には、他の男と口づけなんてしてほしくない」
「えっ?」
至近距離で見つめてくる月冥に、美蘭は赤面する。
「一目見た瞬間に、君に恋をした。こんなにも愛らしい姫は初めて見た」
「そんな、うそよ。私、そんなこと一度も言われたことない」
「焔の神に誓う。君はこの国のどの姫よりも愛らしい。どうか私の妻になってくれないか?」
恐ろしく整った顔で愛を告げられ、美蘭は戸惑う。
頷いてしまいたいけれど、それはきっとしてはいけないことだ。何より月冥と翠国を守る為には、自分の気持ちを抑えなくてはならない。
「月冥の気持ちは、とても嬉しいわ。けど私は、貴方も国も守りたいって思ってる」
「美蘭」
「お願い、聞いて。私はもう一つだけ、使える魔術があるの……私は、今生きている王族の魔術を一度だけ他者に扱う許可が出せるわ」
「他者に魔術を渡せるという事か?」
問われて美蘭は頷く。これは王族の中でも禁忌とされる魔術だ。持って生まれる者は、百年に一人だと言い伝えられている。
「父は、勇気の魔術。協力してくれる兵士を心身共に鼓舞できるわ。一人で大きな木を引き抜けるくらい、力が強くなるの。母は慈愛の魔術。傷ついた兵を瞬きの間になおしてしまうのよ」
二人の姉と、他にも祖父達や血縁のある貴族の魔術を使えるようになるのだと告げる。
「そのようなことができるのなら、あの宰相を倒すのは容易い――」
「私は貴方に、この国と翠国の未来を託したいの」
驚いたように美蘭を見つめていた月冥だが、すぐに表情を曇らせた。
「申し出は嬉しいが、美蘭。君はまだ隠し事をしているね?」
青い瞳は全てを見透かしているようだ。美蘭は覚悟を決めて、口を開く。
「与える魔術は、とても強い力だから……互いに想い合っていなければ私の寿命を奪うことになるの」
小さな窓から差し込む月明かりの下、美蘭は流れる涙を拭うこともなく月冥に告げた。
「貴方になら、私の全部をあげる。だから、絶対に翠国を滅ぼすことは止めさせて」
「そんな事はさせない。君も生きるんだ」
「最初から帰れるなんて思ってなかったわ。だから大丈夫」
「何が大丈夫ものか。君を失ってまで、力を手に入れたくはない」
大きな掌が、美蘭の頬を包み込む。
「君が私を愛してくれているなら、寿命を奪うことはないんだね?」
「そう、だけど……月冥は……それに、私達出会ったばかりなのよ?」
頬を赤らめ唇を尖らせる美蘭の頬に、月冥が唇を寄せた。
「私は君に一目惚れしたよ。君は……私は好みではないかな?」
「そんなことない!」
うっかり本音を口にすると、月冥が心から嬉しそうに笑う。年相応の青年らしい明るい笑顔に、美蘭もつられて笑ってしまう。
「美蘭、愛してる。全てが上手くいったあかつきには、我が伴侶となってほしい」
「いいわ。月冥に嫁いであげる」
この魔術を持って生まれた者は、使った直後死に至ったと翠国の歴史書には書かれていた。
けれど美蘭は、躊躇無く目蓋を閉じる。
「愛してる、愛しい美蘭……」
唇に柔らかな感触を感じた次の瞬間、美蘭は意識を失った。
*****
「あの時は本当に驚いたよ」
「だって、初めてだったんだもの……」
宰相を追放し、無事に焔国の皇帝の座についた月冥が、側に立つ美蘭を抱き寄せる。
王宮にある塔からは、都の町並みが一望できるのだ。
一見立派な皇都だが、そこに住む人々は長年の重税で苦しんでいると月冥が教えてくれた。
賄賂で私腹を肥やしていた貴族達は宰相と共に追放したので、これからは良くなっていくはずだ。
「まさか口づけで気絶するなんて」
「仕方ないでしょ! 恥ずかしかったの!」
「これからは気絶しないように、訓練をしないといけないね」
本気なのか冗談なのか、月冥はくすくすと笑っている。
先帝と宰相の無茶な政のせいで、焔国の民は疲弊していた。どうやら重税で生活できなくなり、逃げ出した民の代わりに近隣国を襲い、奴隷として使っていたらしい。
これからは連れた来られた人々を故郷へと帰し、正常な政に舵を切らなくてはならない。道のりは険しいが月冥ならばやってのけるだろう。
そして美蘭も、翠国の両親に事の顛末を手紙で送り、できる限りの支援を頼んだ。
「美蘭、君が側にいてくれて本当に良かった」
自分の存在が月冥の希望となっているのだと、未だに信じられない。
「本当に私でいいの?」
「私には君だけだよ、美蘭。今後は後宮も廃するつもりだ」
美蘭ただ一人だけを愛するのだと告げられ、赤面してしまう。これからは二人で、この焔国の皇帝、皇妃として歩んで行く。
「私も愛してるわ、月冥」
あの夜、出会った運命は明るい未来を目指して動き始めた。