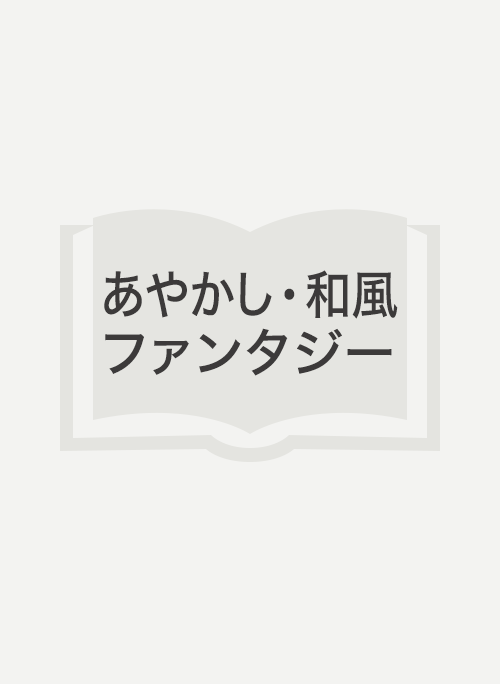「……ん」
千冬は身体のところどころに違和感を覚えてゆっくりと意識を戻した。
瞼も頭も石のように重く感じて、全身が怠い。
(ここは……)
ぼやける視界が数秒かけてはっきりすると自分がおかれている状況を理解しようと辺りを見渡す。
壊れた家具や埃を被った箱などが置かれていて、物置小屋のようだった。
ふと視線を動かすと大きくヒビが入っている鏡に自分の姿が映る。
「えっ……!?」
そこでようやく縄で両手と足首を縛られていることがわかった。
解こうと動かすが、きつく縛られており、ひとりではびくともしない。
「誰か!助けて……!」
小屋の中には詩乃も護衛の男性たちもいない。
見知らぬ場所にひとりきりで途端に心細くなる。
声が出たのが不幸中の幸いで必死に大声で助けを求める。
すると小屋の扉が軋む音を出しながらゆっくりと開かれた。
(よかった……!誰かが助けに来てくれたのね)
安堵したのも束の間、小屋の中に入ってきて自分の前に現れた人物に目を疑った。
「ごきげんよう、お姉さま。随分早いお目覚めね」
そこにいたのは恐ろしいほど美しい笑みを浮かべた妹の依鈴だった。
対面した瞬間、蓋をしていたつらい記憶が次々と蘇る。
「永遠に眠っていてもよかったのに」
その後ろから目を覚ました千冬を睨みつけながら継母の依里恵が入ってくる。
「依鈴さん、依里恵さん……」
どうしてここにいるのか訳もわからず、ぽろりと口からこぼれ落ちる。
名前を呼んだ瞬間、ふたりは眉をさらに吊り上げた。
「あなたなんかが気安く名前を呼ばないで!」
依里恵はずかずかと近づくと扇子を取り出して千冬の頬を叩く。
「うっ……!」
じんわりと叩かれた箇所から痛みが広がる。
嶺木にいた頃は叩かれることなど慣れていたはずなのに久しぶりに感じる痛みに泣きそうになった。
手で抑えようとするが縄で縛られているため、それも不可能だ。
そんな千冬の様子に依鈴は何か可笑しいものでも見たかのように、くすくすと笑いを堪えている。
「何度見てもこの光景は最高ね。お姉さまも懐かしいでしょう?」
縛られたままだと抵抗もできず、されるがままだ。
何か喋ったら叩かれるかもしれないと恐怖に怯えるが聞かずにはいられなかった。
「ここはどこですか?かくりよ國は認められた者しか入れないのでは……」
話の途中で依里恵が千冬の首を掴む。
「ぐっ……」
掴む手に少しずつ力が加わり息が苦しくなる。
何とか呼吸をしようとするが、緩めようとしない手のせいで一度も酸素が入らない。
「呪いの子の分際で私たちに質問だなんて生意気なのよ!」
強烈な怒鳴り声が鼓膜を揺らし、思わず瞳を強く閉じる。
こんなにも怒りをぶつけられるのは初めてで感じたことのない恐怖心を覚える。
浮かべていた笑みを消すと依鈴はゆっくりと千冬の周りを歩き出す。
余裕のある雰囲気がさらに怖さをかき立てる。
「鬼城さまの花嫁に選ばれて調子に乗ってしまったのかしら」
「どうしてそれを……!」
鬼である灯璃の花嫁に選ばれたことは継母たちには伝えていない。
通常の家族ならば、こんなにも喜ばしい出来事はすぐに報告する。
しかし虐げてきた彼女たちに報告しようとは一度も思わなかった。
家を出てきた時点で縁は切ったと考えていたし、鬼城家が与える恩恵を私利私欲のために使ってしまうと思ったからだ。
このままでは立場を利用されて最悪の事態を招いてしまう。
青ざめている千冬を見てふたりはにやりと口角を上げた。
「このまま何もせず、ただ没落するのを待つなんて絶対嫌」
「こんな出来損ないに誰が謝罪しろって?そんなの死ぬ方がマシよ」
ふたりの言葉を繋ぎ合わせていくと、ひとつの予想にいきつく。
謝罪しなければ没落させるなんて言ってくれる相手はただひとりしかいない。
(もしかして灯璃さまはわたしの嶺木家での扱いを知っていたの?)
しかも、いつの間にか継母たちに忠告していたとは初耳だ。
あやかしの最高位である鬼とはいえ、挑発すればどのような危険が及ぶかわからないのに身を挺して守ってくれていたのだ。
(あえてわたしに話さなかったのは心配させたくなかったから?)
嶺木家に行って、宣戦布告をしてきたと言えば、千冬が何も手を出されていないか、迷惑をかけてごめんなさいと謝罪して色々と責任を感じてしまうからだ。
彼の表に出していなかった配慮がとても嬉しく、つらさとはまた別の意味で泣きそうになる。
(いつもならただ叩かれるのを耐えるだけ。でもわたしも強くならなくちゃいけない。守ってくれた灯璃さまのためにも)
勇気を出して俯いていた顔を上げるとまっすぐに継母たちを見た。
「何よ、その目は!」
「虫唾が走るわ!やめてちょうだい!」
依鈴は右頬を、依里恵は左頬を思い切り叩く。
パンッパンッと乾いた音が二回、小屋の中で響いた。
「うっ……ぐ……」
うめき声をあげて千冬は床に倒れ込んだ。
弱めることのない力にもうあと数回叩かれたら意識を失うと確信した。
すると再び、古びた扉が開く。
「あらあら。派手に暴れていますわね」
この状況に似合わないのんびりした上品な声の先に視線を向けると、赤色の生地に蝶々の模様がはいった着物を纏っている女性が倒れている千冬を見ている。
赤い瞳で精巧に作られた人形のように美しい。
しかし過去に会った記憶はなく誰だかまったくわからない。
それにこんなにも綺麗な人に会ったら忘れるわけがない。
「貴方は……?」
掠れながらも小さな問いかけは彼女に聞こえたようだ。
洗練された所作でお辞儀をすると艶やかな唇が開かれる。
「はじめまして。私は鬼の一族、鬼川薫子と申します。灯璃さまの元婚約者ですわ」
「こんやくしゃ……?」
その一文字が脳内を支配する。
彼女が鬼だから驚いたわけでもない。
灯璃の元婚約者ということに動転しているのだ。
一度もそんな話は聞いたことがないし、人間の花嫁が見つかったことでする必要もないのだろう。
そもそも灯璃は周囲の男性と比べたら結婚をすべき年齢をとうに越えている。
それに鬼城家の当主で鬼帝ならば婚約者のひとりくらいいてもまったくおかしくない。
そんなこと簡単に想像できるのに今までしてこなかった自分の方が馬鹿に思えてくる。
「あの、ここはどこなのですか?それにどうして鬼である貴方さまが依鈴さんと依里恵さんと共にいらっしゃるのですか?」
嶺木家があやかしどころか鬼の家と関係をもっているなんて聞いたことがない。
聞きたいことが山ほどあって頭の処理が追いつかない。
「ここは我が鬼川家が所有する敷地の廃墟同然の小屋。貴方さまを恨んでいたお二人と協力をして誘拐し、灯璃さまから引き離すためですわ」
「誘拐……?もしかしてあの時の香りでわたしたちを気絶させたのですか?」
「ええ。私の術を使えば眠らせる香りくらい簡単に作れます」
身体を痺れさせ強烈な眠気を誘うあの香りは鬼の妖術が込められた香りだったのだ。
「し、詩乃さんは……!?護衛の方たちはどこにいらっしゃるのですか?」
特に詩乃の身体は老いているため、あのままでは悪影響を与えるかもしれないと不安に駆られる。
「今頃、鬼城家の人間たちに助けられていることでしょう。帰宅が遅いことに不審に思って。でも……」
薫子はじりじりと千冬に近づくと、膝を折って冷酷な瞳で見下した。
「貴方さまが灯璃さまの花嫁を辞退しない限り、彼らは眠ったままですわ。お返事を聞くために貴方さまの術は解いてあげたの」
「そんな……」
幸せだった日常から一気に地獄へ突き落とされたように目の前が真っ暗になる。
お前の瞳は不幸を招くと言われても、出逢った鬼城家のあやかしたちはそんなこと言わなかった。
愚かな自分のせいで今も苦しんでいるひとたちがいる。
詩乃たちを思えば『灯璃の花嫁にはならない』と一言話すだけですべて解決する。
ただそれだけでいいのに、灯璃の温かな笑顔が脳裏を離れない。
(以前のわたしだったら、すぐに諦めていた。でも……)
頬にはまだ叩かれた痛みが残り、床からは冷気が伝わる。
千冬は重たい頭を必死に起こして薫子を見つめる。
「……です」
「え?よく聞こえないわ」
首を絞められたせいであまり声が出ない。
早く答えを出さない千冬に薫子は自らの足でトントンと床を叩き、苛つきを隠せないようだ。
千冬はできる限りいっぱいに息を吸って胸の中の想いを言葉にした。
「嫌です……!花嫁は辞退しません!」
「なっ……!貴方のような娘が鬼城家の女主人になれるわけがないでしょう!?」
薫子にとって予想外の答えに美しい見た目に反して怒号に近い声をあげる。
傍で聞いていた依鈴や依里恵も続けて声を荒げた。
「鬼城さまを薫子さまに返せば、私を鬼の一族の男性と結婚できるようにしてくださる約束なのよ!」
「貴方の未来なんかより依鈴や嶺木家の未来の方が大切なのよ!それくらい考えればすぐにわかるのに、愚かな……!」
依里恵は草履で千冬の頭を床に押しつける。
「ぐっ……」
感じたことのない痛みでだんだんと気持ち悪くなる。
このまま暴行を受けていれば命が危ないと危機感を抱くが、花嫁を諦める言葉が口から出ることはなかった。
(依里恵さんたちの言うとおり、依鈴さんと比べたらわたしなんかいなくなっても誰も困らない。ずっとそう思っていた。あの方と出逢うまでは……)
何もかも諦めていた自分に灯璃は居場所をくれた。
居場所だけではない。
愛も希望も与えてくれた。
大切なことを教えてくれたあの温もりのある場所へこれから先もずっといたい。
ここで倒れるわけにはいかないと不思議と身体に力が入る。
草履で押さえつけられるのを必死に抵抗する。
(ここから出て、詩乃さんたちを助ける……!)
なお諦めない千冬に薫子は前髪を掴んで持ち上げた。
「灯璃さまは私と結婚するのよ!さっさと花嫁の座を渡すと言いなさい!」
千冬は最後の力を振り絞って口を開いた。
「わたしが鬼城灯璃の花嫁です!」
人生で初めてこんなにも大きな声を出したと思う。
小屋の中に響き渡ったあと、僅かな静寂が訪れた。
薫子は掴んでいた前髪をパッと離すと近くに置いてあった剪定バサミを持つ。
鋭い刃先がこちらを向くと、すぐにこれからされるであろう彼女の行動がわかってしまって背筋が凍った。
「もういいわ。貴方がこの世からいなくなればいいだけよ。そしたら灯璃さまはまた私のものに……」
剪定バサミを持つ手がゆらりと揺れたかと思うと次の瞬間、開いた刃先が喉に向かって勢いよく差し出される。
(嫌……!)
恐怖で思わず目を瞑ったとき、バンッと大きな音を立てながら小屋の扉が開かれる。
おそるおそる目を開けると剪定バサミは喉の直前で止まっていた。
そして逆光の中、現れたのは……。
「千冬!」
隊服を身に纏った灯璃だった。
後ろには副隊長の蓮司を初めとした妖特務部隊の隊員が数名立っている。
「と、灯璃さま……。結界を張って位置は隠したのにどうしてここが……」
薫子は先ほどとはうって変わって顔を青ざめさせている。
かなり動揺しているのか手から剪定バサミが落ちる。
「私の力をみくびるな。あのような脆い結界などすぐに解ける。数日前から鬼川家周辺で怪しい動きも察知していた。念のため千冬に式神をつけておいて正解だった」
灯璃は倒れている千冬の元へ駆け寄るとすぐに縄を解き、抱きしめた。
千冬の背中からは居場所を特定するための白い紙でできた式神がひらりと出てきて消えていく。
いくつかのかすり傷ができた頬を撫でて切ない声を震わす。
「遅くなってすまない、千冬」
千冬は薄れゆく意識を精いっぱい保ちながら首を横に振った。
「助けに来てくださると信じていましたから……。わたし、諦めませんでしたよ」
にっこりと安心させるように微笑む千冬に灯璃はもう一度強く抱きしめると、抱きかかえたまま立ち上がった。
「彼女らを捕らえよ」
その指示で蓮司や隊員たちが一斉に三人を捕らえる。
「いやっ!」
「離して!」
依鈴や依里恵は抵抗するが男性の力に勝てるはずもなく、すぐに縛られて連行されていく。
反対に薫子は何故か落ち着いていてされるがままだった。
暴れても、もう無理なのはわかっているからだろうか。
ぐったりとした千冬を灯璃はしっかりと抱きかかえながら小屋を出ていく。
薫子の横を通り過ぎるとき、弱々しい声が灯璃の耳に届いた。
「本当にその娘でよろしいのですか?」
「私の花嫁は千冬だけだ。お前の処遇は後日伝える。厳しいものだと覚悟しておけ」
氷のように凍てつく言葉に薫子はそれ以上何も言わなかった。
灯璃は一瞥すると外に待たせている自動車に向かって歩き出したのだった。
千冬は身体のところどころに違和感を覚えてゆっくりと意識を戻した。
瞼も頭も石のように重く感じて、全身が怠い。
(ここは……)
ぼやける視界が数秒かけてはっきりすると自分がおかれている状況を理解しようと辺りを見渡す。
壊れた家具や埃を被った箱などが置かれていて、物置小屋のようだった。
ふと視線を動かすと大きくヒビが入っている鏡に自分の姿が映る。
「えっ……!?」
そこでようやく縄で両手と足首を縛られていることがわかった。
解こうと動かすが、きつく縛られており、ひとりではびくともしない。
「誰か!助けて……!」
小屋の中には詩乃も護衛の男性たちもいない。
見知らぬ場所にひとりきりで途端に心細くなる。
声が出たのが不幸中の幸いで必死に大声で助けを求める。
すると小屋の扉が軋む音を出しながらゆっくりと開かれた。
(よかった……!誰かが助けに来てくれたのね)
安堵したのも束の間、小屋の中に入ってきて自分の前に現れた人物に目を疑った。
「ごきげんよう、お姉さま。随分早いお目覚めね」
そこにいたのは恐ろしいほど美しい笑みを浮かべた妹の依鈴だった。
対面した瞬間、蓋をしていたつらい記憶が次々と蘇る。
「永遠に眠っていてもよかったのに」
その後ろから目を覚ました千冬を睨みつけながら継母の依里恵が入ってくる。
「依鈴さん、依里恵さん……」
どうしてここにいるのか訳もわからず、ぽろりと口からこぼれ落ちる。
名前を呼んだ瞬間、ふたりは眉をさらに吊り上げた。
「あなたなんかが気安く名前を呼ばないで!」
依里恵はずかずかと近づくと扇子を取り出して千冬の頬を叩く。
「うっ……!」
じんわりと叩かれた箇所から痛みが広がる。
嶺木にいた頃は叩かれることなど慣れていたはずなのに久しぶりに感じる痛みに泣きそうになった。
手で抑えようとするが縄で縛られているため、それも不可能だ。
そんな千冬の様子に依鈴は何か可笑しいものでも見たかのように、くすくすと笑いを堪えている。
「何度見てもこの光景は最高ね。お姉さまも懐かしいでしょう?」
縛られたままだと抵抗もできず、されるがままだ。
何か喋ったら叩かれるかもしれないと恐怖に怯えるが聞かずにはいられなかった。
「ここはどこですか?かくりよ國は認められた者しか入れないのでは……」
話の途中で依里恵が千冬の首を掴む。
「ぐっ……」
掴む手に少しずつ力が加わり息が苦しくなる。
何とか呼吸をしようとするが、緩めようとしない手のせいで一度も酸素が入らない。
「呪いの子の分際で私たちに質問だなんて生意気なのよ!」
強烈な怒鳴り声が鼓膜を揺らし、思わず瞳を強く閉じる。
こんなにも怒りをぶつけられるのは初めてで感じたことのない恐怖心を覚える。
浮かべていた笑みを消すと依鈴はゆっくりと千冬の周りを歩き出す。
余裕のある雰囲気がさらに怖さをかき立てる。
「鬼城さまの花嫁に選ばれて調子に乗ってしまったのかしら」
「どうしてそれを……!」
鬼である灯璃の花嫁に選ばれたことは継母たちには伝えていない。
通常の家族ならば、こんなにも喜ばしい出来事はすぐに報告する。
しかし虐げてきた彼女たちに報告しようとは一度も思わなかった。
家を出てきた時点で縁は切ったと考えていたし、鬼城家が与える恩恵を私利私欲のために使ってしまうと思ったからだ。
このままでは立場を利用されて最悪の事態を招いてしまう。
青ざめている千冬を見てふたりはにやりと口角を上げた。
「このまま何もせず、ただ没落するのを待つなんて絶対嫌」
「こんな出来損ないに誰が謝罪しろって?そんなの死ぬ方がマシよ」
ふたりの言葉を繋ぎ合わせていくと、ひとつの予想にいきつく。
謝罪しなければ没落させるなんて言ってくれる相手はただひとりしかいない。
(もしかして灯璃さまはわたしの嶺木家での扱いを知っていたの?)
しかも、いつの間にか継母たちに忠告していたとは初耳だ。
あやかしの最高位である鬼とはいえ、挑発すればどのような危険が及ぶかわからないのに身を挺して守ってくれていたのだ。
(あえてわたしに話さなかったのは心配させたくなかったから?)
嶺木家に行って、宣戦布告をしてきたと言えば、千冬が何も手を出されていないか、迷惑をかけてごめんなさいと謝罪して色々と責任を感じてしまうからだ。
彼の表に出していなかった配慮がとても嬉しく、つらさとはまた別の意味で泣きそうになる。
(いつもならただ叩かれるのを耐えるだけ。でもわたしも強くならなくちゃいけない。守ってくれた灯璃さまのためにも)
勇気を出して俯いていた顔を上げるとまっすぐに継母たちを見た。
「何よ、その目は!」
「虫唾が走るわ!やめてちょうだい!」
依鈴は右頬を、依里恵は左頬を思い切り叩く。
パンッパンッと乾いた音が二回、小屋の中で響いた。
「うっ……ぐ……」
うめき声をあげて千冬は床に倒れ込んだ。
弱めることのない力にもうあと数回叩かれたら意識を失うと確信した。
すると再び、古びた扉が開く。
「あらあら。派手に暴れていますわね」
この状況に似合わないのんびりした上品な声の先に視線を向けると、赤色の生地に蝶々の模様がはいった着物を纏っている女性が倒れている千冬を見ている。
赤い瞳で精巧に作られた人形のように美しい。
しかし過去に会った記憶はなく誰だかまったくわからない。
それにこんなにも綺麗な人に会ったら忘れるわけがない。
「貴方は……?」
掠れながらも小さな問いかけは彼女に聞こえたようだ。
洗練された所作でお辞儀をすると艶やかな唇が開かれる。
「はじめまして。私は鬼の一族、鬼川薫子と申します。灯璃さまの元婚約者ですわ」
「こんやくしゃ……?」
その一文字が脳内を支配する。
彼女が鬼だから驚いたわけでもない。
灯璃の元婚約者ということに動転しているのだ。
一度もそんな話は聞いたことがないし、人間の花嫁が見つかったことでする必要もないのだろう。
そもそも灯璃は周囲の男性と比べたら結婚をすべき年齢をとうに越えている。
それに鬼城家の当主で鬼帝ならば婚約者のひとりくらいいてもまったくおかしくない。
そんなこと簡単に想像できるのに今までしてこなかった自分の方が馬鹿に思えてくる。
「あの、ここはどこなのですか?それにどうして鬼である貴方さまが依鈴さんと依里恵さんと共にいらっしゃるのですか?」
嶺木家があやかしどころか鬼の家と関係をもっているなんて聞いたことがない。
聞きたいことが山ほどあって頭の処理が追いつかない。
「ここは我が鬼川家が所有する敷地の廃墟同然の小屋。貴方さまを恨んでいたお二人と協力をして誘拐し、灯璃さまから引き離すためですわ」
「誘拐……?もしかしてあの時の香りでわたしたちを気絶させたのですか?」
「ええ。私の術を使えば眠らせる香りくらい簡単に作れます」
身体を痺れさせ強烈な眠気を誘うあの香りは鬼の妖術が込められた香りだったのだ。
「し、詩乃さんは……!?護衛の方たちはどこにいらっしゃるのですか?」
特に詩乃の身体は老いているため、あのままでは悪影響を与えるかもしれないと不安に駆られる。
「今頃、鬼城家の人間たちに助けられていることでしょう。帰宅が遅いことに不審に思って。でも……」
薫子はじりじりと千冬に近づくと、膝を折って冷酷な瞳で見下した。
「貴方さまが灯璃さまの花嫁を辞退しない限り、彼らは眠ったままですわ。お返事を聞くために貴方さまの術は解いてあげたの」
「そんな……」
幸せだった日常から一気に地獄へ突き落とされたように目の前が真っ暗になる。
お前の瞳は不幸を招くと言われても、出逢った鬼城家のあやかしたちはそんなこと言わなかった。
愚かな自分のせいで今も苦しんでいるひとたちがいる。
詩乃たちを思えば『灯璃の花嫁にはならない』と一言話すだけですべて解決する。
ただそれだけでいいのに、灯璃の温かな笑顔が脳裏を離れない。
(以前のわたしだったら、すぐに諦めていた。でも……)
頬にはまだ叩かれた痛みが残り、床からは冷気が伝わる。
千冬は重たい頭を必死に起こして薫子を見つめる。
「……です」
「え?よく聞こえないわ」
首を絞められたせいであまり声が出ない。
早く答えを出さない千冬に薫子は自らの足でトントンと床を叩き、苛つきを隠せないようだ。
千冬はできる限りいっぱいに息を吸って胸の中の想いを言葉にした。
「嫌です……!花嫁は辞退しません!」
「なっ……!貴方のような娘が鬼城家の女主人になれるわけがないでしょう!?」
薫子にとって予想外の答えに美しい見た目に反して怒号に近い声をあげる。
傍で聞いていた依鈴や依里恵も続けて声を荒げた。
「鬼城さまを薫子さまに返せば、私を鬼の一族の男性と結婚できるようにしてくださる約束なのよ!」
「貴方の未来なんかより依鈴や嶺木家の未来の方が大切なのよ!それくらい考えればすぐにわかるのに、愚かな……!」
依里恵は草履で千冬の頭を床に押しつける。
「ぐっ……」
感じたことのない痛みでだんだんと気持ち悪くなる。
このまま暴行を受けていれば命が危ないと危機感を抱くが、花嫁を諦める言葉が口から出ることはなかった。
(依里恵さんたちの言うとおり、依鈴さんと比べたらわたしなんかいなくなっても誰も困らない。ずっとそう思っていた。あの方と出逢うまでは……)
何もかも諦めていた自分に灯璃は居場所をくれた。
居場所だけではない。
愛も希望も与えてくれた。
大切なことを教えてくれたあの温もりのある場所へこれから先もずっといたい。
ここで倒れるわけにはいかないと不思議と身体に力が入る。
草履で押さえつけられるのを必死に抵抗する。
(ここから出て、詩乃さんたちを助ける……!)
なお諦めない千冬に薫子は前髪を掴んで持ち上げた。
「灯璃さまは私と結婚するのよ!さっさと花嫁の座を渡すと言いなさい!」
千冬は最後の力を振り絞って口を開いた。
「わたしが鬼城灯璃の花嫁です!」
人生で初めてこんなにも大きな声を出したと思う。
小屋の中に響き渡ったあと、僅かな静寂が訪れた。
薫子は掴んでいた前髪をパッと離すと近くに置いてあった剪定バサミを持つ。
鋭い刃先がこちらを向くと、すぐにこれからされるであろう彼女の行動がわかってしまって背筋が凍った。
「もういいわ。貴方がこの世からいなくなればいいだけよ。そしたら灯璃さまはまた私のものに……」
剪定バサミを持つ手がゆらりと揺れたかと思うと次の瞬間、開いた刃先が喉に向かって勢いよく差し出される。
(嫌……!)
恐怖で思わず目を瞑ったとき、バンッと大きな音を立てながら小屋の扉が開かれる。
おそるおそる目を開けると剪定バサミは喉の直前で止まっていた。
そして逆光の中、現れたのは……。
「千冬!」
隊服を身に纏った灯璃だった。
後ろには副隊長の蓮司を初めとした妖特務部隊の隊員が数名立っている。
「と、灯璃さま……。結界を張って位置は隠したのにどうしてここが……」
薫子は先ほどとはうって変わって顔を青ざめさせている。
かなり動揺しているのか手から剪定バサミが落ちる。
「私の力をみくびるな。あのような脆い結界などすぐに解ける。数日前から鬼川家周辺で怪しい動きも察知していた。念のため千冬に式神をつけておいて正解だった」
灯璃は倒れている千冬の元へ駆け寄るとすぐに縄を解き、抱きしめた。
千冬の背中からは居場所を特定するための白い紙でできた式神がひらりと出てきて消えていく。
いくつかのかすり傷ができた頬を撫でて切ない声を震わす。
「遅くなってすまない、千冬」
千冬は薄れゆく意識を精いっぱい保ちながら首を横に振った。
「助けに来てくださると信じていましたから……。わたし、諦めませんでしたよ」
にっこりと安心させるように微笑む千冬に灯璃はもう一度強く抱きしめると、抱きかかえたまま立ち上がった。
「彼女らを捕らえよ」
その指示で蓮司や隊員たちが一斉に三人を捕らえる。
「いやっ!」
「離して!」
依鈴や依里恵は抵抗するが男性の力に勝てるはずもなく、すぐに縛られて連行されていく。
反対に薫子は何故か落ち着いていてされるがままだった。
暴れても、もう無理なのはわかっているからだろうか。
ぐったりとした千冬を灯璃はしっかりと抱きかかえながら小屋を出ていく。
薫子の横を通り過ぎるとき、弱々しい声が灯璃の耳に届いた。
「本当にその娘でよろしいのですか?」
「私の花嫁は千冬だけだ。お前の処遇は後日伝える。厳しいものだと覚悟しておけ」
氷のように凍てつく言葉に薫子はそれ以上何も言わなかった。
灯璃は一瞥すると外に待たせている自動車に向かって歩き出したのだった。