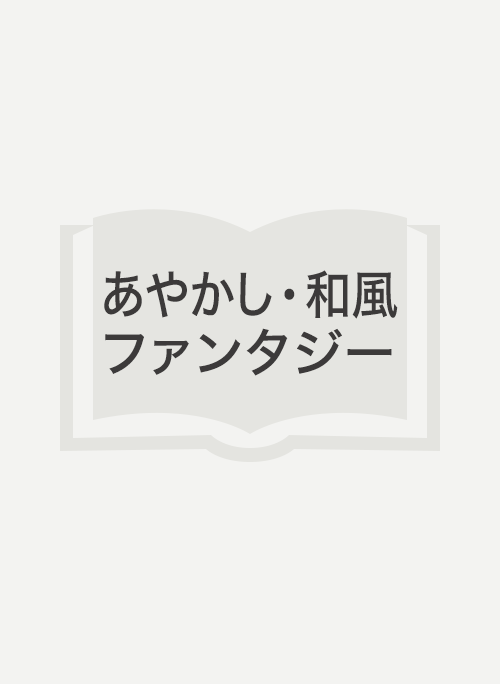「今日も少し帰りが遅くなる」
「仕事がお忙しいのですね。お身体は大丈夫ですか?」
最近、灯璃は妖特務部隊の仕事が多忙を極めているようだ。
屋敷に帰宅するのは日付が変わる時間が多く、共に夕食を食べられていない。
最初は灯璃が帰宅するまで食べずに待っていると伝えたが、気にしないでほしいと何度も言われ、ひとりで食事をすることが多くなった。
一緒に暮らしているとはいえ、まだ正式に結婚はしていないので部屋も別々。
大丈夫だとは言うけれど本当に睡眠もとれているのかわからない。
夜だけでなく、今日のように早朝から出勤することも増えているため灯璃の身体が心配になる。
玄関で靴を履き仕事先へ向かおうとする灯璃は振り返ると千冬を安心させるようにしっかりと頷いた。
「私は何も問題はない。それより千冬こそ平気か?今日も早く起きて弁当を作ってくれたのだろう?」
「わたしにできることと言えばこれくらいですから」
「千冬の料理はとても美味しくて弁当はありがたいのだが、このあとは部屋で勉強もするのに無理していないか」
正直、身体は重く眠気もある。
でも朝から晩まで働き詰めの灯璃の方が疲れているに決まっている。
そんな彼の前で弱音など吐いていられない。
「わたしは平気です。きちんとお休みもいただいておりますし」
「少しでも具合が悪ければすぐに使用人たちに言うのだぞ」
「かしこまりました」
笑顔で頷くが、何でも我慢してしまう千冬の性格を知っているからか、まだ彼の中の不安は拭いきれていないようだ。
「……いってくる」
「いってらっしゃいませ」
灯璃は踵を返すと玄関から外へ出て行った。
見送りが終わり、自室へ戻るために廊下を歩く。
(灯璃さまはああ言っていたけれど、きっとお疲れよね。お弁当作りの他に何かできることはないかしら)
彼のためにといったらなるべく早く花嫁修業を終えることだが、それだけではない他の何かもしたい。
一生懸命、頭を回転させて考えを巡らせると、先日読んだ雑誌の内容を思い出す。
(そういえば雑誌に贈り物の特集が掲載されていたわ……。日頃からお世話になってばかりだしお店で灯璃さまに選んでもいいかもしれない)
先日、灯璃が町を案内してくれたおかげで、ある程度お店の目星はついている。
しかも今日は青空が澄み渡ってお出かけ日和だ。
勉強は午後から取り組もうと予定を変更させて千冬はお世話係の詩乃の元へ急いだ。
詩乃に事情を話し、外出の許可をもらった千冬は身支度を整えて自動車に乗り込み、町へ向かっていた。
外出をする際は必ず灯璃か護衛の者と共にしなくてはいけない。
それだけ花嫁は大切な存在なのだ。
この自動車には千冬と詩乃、運転手しかいないが、護衛を担当する男性たちは後ろからついて見守るそうだ。
建ち並ぶ店が見えたところで自動車が路肩に止まる。
千冬と詩乃は降りると賑わう町へ歩き出す。
こっそり後ろを見ると護衛の男性たちは陰から様子を伺っていた。
邪魔にならないようにしてくれているのかその心遣いが嬉しかった。
「千冬さまからの贈り物……。きっと喜んでくださりますよ」
「そうだとよいのですが。灯璃さまはどのようなものがお好みなのでしょう?」
一緒に暮らし始めてからしばらく経ち、知ったつもりでいるが、いざ贈り物を選ぶとなると難しい。
深く考えこんでいると詩乃は朗らかな笑みを浮かべながら口を開いた。
「贈り物をしてお礼をしたいというお気持ちが大切だと私は思いますよ。あまり難しく考えなくとも相手を想えば自然とぴったりの物を選べますわ」
「……はい!そうですね」
詩乃はいつも的確に、相手に寄り添った答えを返してくれる。
いつしか千冬も彼女に信頼を寄せていた。
談笑をしながら歩いていると、少し先に大通りが見えてくる。
(町へ来るのも久しぶりね。……あら?)
どこからか甘い香りが漂い、鼻腔をくすぐる。
甘いだけではない、薬のようなツンとした変わった匂いだ。
「この香りは……」
強く、特徴のありすぎる香りに思わず手で口元を抑える。
「うっ……」
隣から苦しそうな声が聞こえたかと思うと詩乃の身体がぐらりと揺れる。
「詩乃さん!」
手を伸ばし支えようとするが何故か腕が痺れて動かない。
困惑しているうちに詩乃は地面にバタリと力なく倒れる。
付き添いの護衛の男性たちに助けを求めようと振り返るが彼らも同じように倒れ込んでいた。
「どうして……」
全員が同時に倒れるなんて、どう考えてもおかしい。
せめて大通りに行けば助けを呼べるはずだと足を前へ進めようとするが、力が入らず、その場に崩れ落ちる。
「だ、れ、か……」
僅かに声が出たが風に掻き消されて誰にも届くことはない。
だんだんと視界が歪み、どうにか意識を保とうとするが襲いかかる眠気に勝てない。
(灯璃さま……)
千冬は薄れゆく意識の中、灯璃のあの優しい表情を浮かべる。
まるで、このまま離ればなれになってしまいそうで胸が苦しくなった。
会いたい、その願いも虚しく、千冬は意識を手放したのだった。
「仕事がお忙しいのですね。お身体は大丈夫ですか?」
最近、灯璃は妖特務部隊の仕事が多忙を極めているようだ。
屋敷に帰宅するのは日付が変わる時間が多く、共に夕食を食べられていない。
最初は灯璃が帰宅するまで食べずに待っていると伝えたが、気にしないでほしいと何度も言われ、ひとりで食事をすることが多くなった。
一緒に暮らしているとはいえ、まだ正式に結婚はしていないので部屋も別々。
大丈夫だとは言うけれど本当に睡眠もとれているのかわからない。
夜だけでなく、今日のように早朝から出勤することも増えているため灯璃の身体が心配になる。
玄関で靴を履き仕事先へ向かおうとする灯璃は振り返ると千冬を安心させるようにしっかりと頷いた。
「私は何も問題はない。それより千冬こそ平気か?今日も早く起きて弁当を作ってくれたのだろう?」
「わたしにできることと言えばこれくらいですから」
「千冬の料理はとても美味しくて弁当はありがたいのだが、このあとは部屋で勉強もするのに無理していないか」
正直、身体は重く眠気もある。
でも朝から晩まで働き詰めの灯璃の方が疲れているに決まっている。
そんな彼の前で弱音など吐いていられない。
「わたしは平気です。きちんとお休みもいただいておりますし」
「少しでも具合が悪ければすぐに使用人たちに言うのだぞ」
「かしこまりました」
笑顔で頷くが、何でも我慢してしまう千冬の性格を知っているからか、まだ彼の中の不安は拭いきれていないようだ。
「……いってくる」
「いってらっしゃいませ」
灯璃は踵を返すと玄関から外へ出て行った。
見送りが終わり、自室へ戻るために廊下を歩く。
(灯璃さまはああ言っていたけれど、きっとお疲れよね。お弁当作りの他に何かできることはないかしら)
彼のためにといったらなるべく早く花嫁修業を終えることだが、それだけではない他の何かもしたい。
一生懸命、頭を回転させて考えを巡らせると、先日読んだ雑誌の内容を思い出す。
(そういえば雑誌に贈り物の特集が掲載されていたわ……。日頃からお世話になってばかりだしお店で灯璃さまに選んでもいいかもしれない)
先日、灯璃が町を案内してくれたおかげで、ある程度お店の目星はついている。
しかも今日は青空が澄み渡ってお出かけ日和だ。
勉強は午後から取り組もうと予定を変更させて千冬はお世話係の詩乃の元へ急いだ。
詩乃に事情を話し、外出の許可をもらった千冬は身支度を整えて自動車に乗り込み、町へ向かっていた。
外出をする際は必ず灯璃か護衛の者と共にしなくてはいけない。
それだけ花嫁は大切な存在なのだ。
この自動車には千冬と詩乃、運転手しかいないが、護衛を担当する男性たちは後ろからついて見守るそうだ。
建ち並ぶ店が見えたところで自動車が路肩に止まる。
千冬と詩乃は降りると賑わう町へ歩き出す。
こっそり後ろを見ると護衛の男性たちは陰から様子を伺っていた。
邪魔にならないようにしてくれているのかその心遣いが嬉しかった。
「千冬さまからの贈り物……。きっと喜んでくださりますよ」
「そうだとよいのですが。灯璃さまはどのようなものがお好みなのでしょう?」
一緒に暮らし始めてからしばらく経ち、知ったつもりでいるが、いざ贈り物を選ぶとなると難しい。
深く考えこんでいると詩乃は朗らかな笑みを浮かべながら口を開いた。
「贈り物をしてお礼をしたいというお気持ちが大切だと私は思いますよ。あまり難しく考えなくとも相手を想えば自然とぴったりの物を選べますわ」
「……はい!そうですね」
詩乃はいつも的確に、相手に寄り添った答えを返してくれる。
いつしか千冬も彼女に信頼を寄せていた。
談笑をしながら歩いていると、少し先に大通りが見えてくる。
(町へ来るのも久しぶりね。……あら?)
どこからか甘い香りが漂い、鼻腔をくすぐる。
甘いだけではない、薬のようなツンとした変わった匂いだ。
「この香りは……」
強く、特徴のありすぎる香りに思わず手で口元を抑える。
「うっ……」
隣から苦しそうな声が聞こえたかと思うと詩乃の身体がぐらりと揺れる。
「詩乃さん!」
手を伸ばし支えようとするが何故か腕が痺れて動かない。
困惑しているうちに詩乃は地面にバタリと力なく倒れる。
付き添いの護衛の男性たちに助けを求めようと振り返るが彼らも同じように倒れ込んでいた。
「どうして……」
全員が同時に倒れるなんて、どう考えてもおかしい。
せめて大通りに行けば助けを呼べるはずだと足を前へ進めようとするが、力が入らず、その場に崩れ落ちる。
「だ、れ、か……」
僅かに声が出たが風に掻き消されて誰にも届くことはない。
だんだんと視界が歪み、どうにか意識を保とうとするが襲いかかる眠気に勝てない。
(灯璃さま……)
千冬は薄れゆく意識の中、灯璃のあの優しい表情を浮かべる。
まるで、このまま離ればなれになってしまいそうで胸が苦しくなった。
会いたい、その願いも虚しく、千冬は意識を手放したのだった。