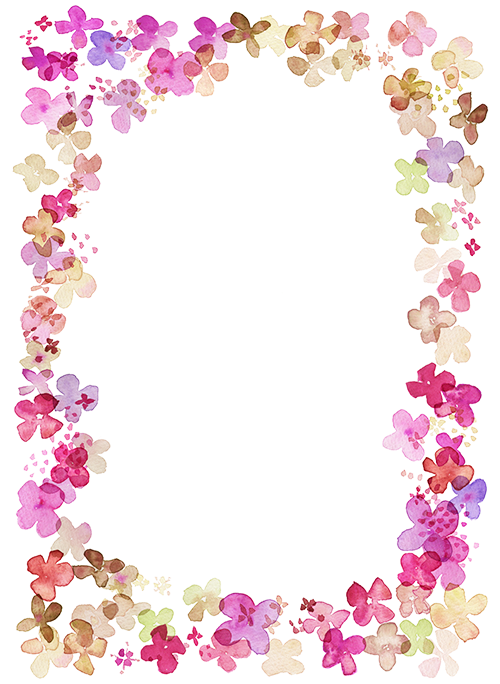石の床にうずくまったままリランは目を固く閉じて、やがて顔を上げた。
「助けてくれたのは二度目ね」
リランが顔を上げればそこには、豹の耳と尻尾を持つ獣僕がいる。
「カイ……と呼んでもいい?」
弟のカイに生き写しの獣僕は、リランの言葉に考え込んだようだった。
リランはその後の言葉をある程度予感していた。姿形は弟にそっくりだが、彼のまとう空気は懐かしい弟と同じではない。
豹の獣僕は弟にはなかった牙を覗かせて、リランに苦笑してみせた。
「この体はいろいろな獣が混じっています。そういう名前も、過去にはあったのですが」
リランは彼の面差しに弟を見るが、それは彼の過去の一つらしかった。
獣僕は様々な個体と混ざって生きていく。きっと弟のカイは、そうすることで命をつないだのだ。
(また会えただけでもうれしい)
リランはうつむいて泣き笑いの顔になると、うなずいてひととき時の流れを思っていた。
今のリランと彼は、姉弟だった頃から百年経っている。けれどリランの中で弟への愛おしさは少しも色あせていなかった。
そんな複雑な表情で過去を思い返しているかつての姉に、彼もしばらくの間言葉を考えあぐねているようだった。
やがて彼は心を決めたようにうなずいて、リランに言う。
「呼びたければカイと呼んでくださってもいいですよ。僕もリランと呼びます」
「ありがとう。うれしいわ」
ふいにカイは一礼してリランを見下ろした。
そこに弟のものではない従者としての彼を見て、リランは身を引き締める。
カイは瞳に畏れを宿しながら、慎重に言葉を選んで告げた。
「リラン、僕はあなたを迎えに来ました。……皇帝陛下があなたに会いたがっておいでです」
不思議そうに見返したリランに、カイは続ける。
「百年前、あなたは皇帝陛下の血を浴びました。けれど、それまでにもそれからも、他に陛下の血を得た者たちはたくさんいたのです」
カイは目を鋭くしてリランに言う。
「血を受けた者たちは次々と眠りについていくのに、あなたは逆に目覚めた。陛下はあなたに興味を抱いていらっしゃいます」
「私自身もなぜ目覚めたのかわからないわ」
リランはチュンヒに聞いた皇帝陛下のことを思い出す。
皇帝陛下に愛されるのはたやすいことではないと言っていた。リランも会ったことがない皇帝陛下を愛するはずがない。
「……でも私も皇帝陛下にお話ししたいことがある」
リランがそう答えると、カイは安心したようにほっと息をついた。
カイはリランをみつめて少し考えると、優しく告げた。
「お召し替えをいたしましょう」
リランがカイの視線の先を追うと、あちこち焼け焦げた無残な服に気づいた。
リランは困ったように口ごもって苦笑する。
「このまま……というわけにはいかないかしら。私、百年前からこの服しか持ってきていないの」
リランは首を傾げてカイに問いかける。
「覚えているかしら? この服はあなたが、私の結婚式のために買ってくれたの」
カイは目を伏せて沈黙する。そんな彼に、リランは袖口を押さえながら言う。
「両親が亡くなったばかりであまりお金もなかったはず。とても嬉しかったの」
カイが覚えているかどうか、リランはそれ以上確かめようとは思わなかった。
リランは首を横に振って、明るい目でカイを見上げる。
「……でもあなたに再会できたことが何よりの宝物ね。さ、着替えて出かけましょう!」
カイは遠いものを探すようにリランをみつめかえしてから、先に立って歩き始めた。
リランは部屋に戻って適当な服を探し始めたものの、すぐに難航してしまった。
(うーん。私が着たら、服に申し訳ないような気がするわ……)
貧乏性に胸を痛めながら、リランはこんなときこそカイの意見を訊きたかった。けれど彼は律儀にも部屋の外で待っていて、リランは一人で衣装棚と悪戦苦闘する。
ここに来てから一月、本を読んだり獣僕と話をしたりして、一応正装がどんなものかはわかっている。けれど村娘だった頃にそんな豪勢な格好はしたことがない。
(……皇帝陛下といえば、私を馬車に引っかけた方)
そう思うと今更ながらに恐ろしい気もして、リランはごくりと息を呑む。
リランはふるふると首を横に振って思う。
(いいえ、そこは命の恩人と思いましょう!)
リランはきりっと顔を引き締めて心に決める。
衣装棚を見回して、リランは一つの服を選び取っていた。
見渡せば、石造りの階段が螺旋状に下へ下へと続いていた。
ゆらめく蝋燭とはためく壁掛けだけが風の向きを伝える。リランはぬるい風が遥か下方から昇ってきていることを感じていた。
先を行くカイが振り向いてリランに言う。
「もうじきです」
リランはうなずいて、カイに遅れないようについていく。
どこからかざわめきが風に運ばれてきて、リランは目を細めた。カイの豹の耳もぴくりと動いて、彼は階段を降りながら答える。
「今日は宴の日なのです。妃たちも起きて集まっています」
「そんな高雅の席に、村娘の私が混じってしまっていいのかしら?」
リランが問いかけると、カイは振り向いてリランを見上げながら言う。
「リランは美しいですよ。古代の衣もよくお似合いです」
カイがうなずいてくれたリランの服は、古い時代に天女の衣装と言われたものだった。
桃色と水色の混じった不思議な絹織物に縫い目はなく、まるで羽のように重みを感じない。
「そうでしょう? 私は百歳のおばあちゃんだもの!」
リランはくすっと笑って、裾をひらりと動かしてみせた。
リランはふと思い当って首を傾げた。
(でも皇帝陛下も百年前から生きていらっしゃる。だとしたらずいぶんお年の方なのかもしれないわね)
ふるさとの老人たちを思い出しながら、リランはひとりうなずいた。
やがて先を行くカイが足を止めて、両開きの扉の前で顎を上げた。
「扉を開けてください。リラン妃をお連れしました」
扉の向こうに広がった光景はまぶしくはなかったのに、リランは自然と目を細めた。
本の中でしか見たことがない、宮殿の大広間のような空間だった。香が立ち込める中、石の床に紅色のじゅうたんが敷かれている。壁に灯った無数の灰色の光は、リランが立ち入ると生き物のようにざわめいた。
カイは尻尾を一振りしてゆっくりと歩み始めて、リランもそれに続く。
(不思議……。温かいような、冷たいような空気)
夢の中にいるような気持ちで、リランは足を前へと進める。
中央のじゅうたんを踏んで前へと進む。両脇の暗闇からは何人もの忍び笑いが漏れているのに、姿はどこにも見えない。
息をつくほんの短い間のようでもあり、一日歩きとおしたような長い歩みのようでもある、そんな感覚があった。
やがてカイが身を屈めたのにならって、リランも膝をつく。
階段の上にある玉座に誰かの足先が見えたが、リランもすぐに頭を下げたので顔を見ることはできなかった。
「陛下、お連れしました」
頭を下げたまま、ためらいがちにカイが口を開いたときだった。
リランは顔を上げたつもりはなかったのに、誰かに顎を掴まれたように顔が上げさせられた。
しかも顔を上げたのに、相変わらず玉座に座る誰かの姿は見えない。
どういう怪奇現象かわからないまま、闇の中にぱっくり開いた洞窟に飲み込まれるような、そんな重圧がリランを包み込む。
「えっ……こわい」
リランはぽろっと本音をこぼしていた。
カイがうろたえたように振り向く。リランもあまりにうかつに過ぎた自分の言葉を後悔するも、自分の心のどこを探しても本音だったと思う。
ふと玉座で誰かが笑った気配がした。リランの顎をつかむ力も消えて、体を包んでいた重圧から自由になる。
リランがまばたきをするうちに、玉座の誰かはいなくなっていた。
カイはほっと安堵の息をついて、リランに声をかける。
「陛下は席を外されたようです。リラン、僕はここで」
リランは不安を浮かべた目でカイを見てしまったらしい。カイは淡く笑うと、困ったように言った。
「獣僕は宴を楽しむ立場にないのです。一緒に……月を臨める者ではないのですよ」
月と聞いたとき、リランは遠い日に弟と交わした約束を思い出した。
けれどカイはそう告げたきり、薄闇の中に消えて行ってしまった。
リランが立ち上がると、そこはさざなみのように囁き声が飛び交っていた。薄暗がりに人影が現れては消える。
(カイ、昔から優しい子だった。村が襲われる前だって、無理やり私を帝都に連れ去ったりはしなかった)
リランはうつむいて、まだやはり彼の中には弟がいるのだと思った。
(そうね。新しいことが楽しみ。それが私だったはず)
リランは自分の信条を思い返して、笑顔を浮かべる。
「行きましょう」
たとえ空元気でも、それがいつしか自分そのものになるように自分を変えていこう。リランはそう思って胸を張る。
(まあ、美味しそう)
少し歩めば花のように卓が並び、その上には湯気の立ちのぼる肉料理や香草がたっぷりと使われた野菜の椀物が置いてあった。
「あの、取っていいのですか?」
傍らに立つ獣僕に問いかけると、彼は困惑したように言葉を詰まらせた。
ふと辺りを見回すが、誰も食に興じる者はいない。
広間は全体的に暗く、端の方は真っ暗だ。囁くような声は聞こえるが、椅子も見当たらない。
そのとき、鐘が響き始めた。
リランの目は突如広がった光景に見開かれる。
(え……)
音楽が近づく音も気配すらなかったというのに、前に振り向いた時にはもう、眼前で華やかな楽団が勢揃いしていた。
西方の旅芸人のような極彩色の衣装、奇妙な形状の笛や弦楽器で紡がれる不思議な音階。中心で舞う踊り子は、風を飲み込む巨大な布を幾重にも複雑に絡めながら、地に足などついていないかのように奔放に空を駆ける。
先ほどとは全く空気が変わっていた。リランには体の感覚が次第になくなっていくような気がして、やがて人形のように座り込む。
踊り子は七色の布を一枚ずつ脱ぎ捨てていき、その隙間からとろけるようなはちみつ色の細腕が覗いた。ひらりと妖しく布がはためく度に、伸びやかな足、腕に浮かび上がる赤い刺青、女性らしい豊満な胸元、異形の証である黒と赤の交じり合った蝙蝠の翼が一つずつ晒されていく。
鈴と腕輪の擦れる音が響く。
「醜イ、妃メ……汚らわシイ」
リランは踊り子がその艶やかな唇に侮蔑を刻んだのを見た。
(アイシラ妃……!)
視界が点滅して、リランは思わず床に手をついていた。
体が熱く、力が入らない。辺りに漂う香りと暗がりから漏れる囁きが、リランの意識を捻じ曲げていく。
淀んだ空気がたちこめて、毒の霧のようにリランを包み込む。
気が付けば周囲で無数の妃たちが踊っていた。けれど彼女らの足は地に着かず、もう終わりのない世界で舞っているだけ。
アイシラの高らかな嘲笑が円舞のようにリランの聴覚を飲み込み、絶え間ない頭痛に視界が閉ざされていく。
ふいにアイシラの投げた短剣が、リランに向かって飛んだ。
「リラン……!」
リランはそれを避けることができなかった。けれどリランの前に横切った影が、リランの代わりにそれを受け止めた。
「……カイ?」
肩に怪我を負ってうずくまる獣僕を、リランは信じられないものを見るように捉える。
リランはうずくまって、獣僕を助け起こす。
「どうして戻ってきたの。カイ……!」
「……どうしてか、自分でもわから、ない」
獣僕は血に濡れた口元に、弱弱しく笑みを刻む。
「でもまだ、望んでいるんです。あなたと見る月を……」
「話さないで、カイ。すぐに手当を!」
リランは慌てて服を裂いて手当をしようとしたが、カイは首を横に振った。
「大丈夫。獣僕はここにいる限り、何度でも蘇るんです……」
その言葉通り、彼の傷口は今にも塞がろうとしていた。流れた血だけが彼の服に痕跡を残していた。
カイは怪我が癒えたのに苦しそうな表情で目を閉じる。
「眠る時間です、妃たちも獣僕も。夜が明けたら、また変わらない日を演じるために……」
深夜に鳴る鐘は、まもなく終わろうとしていた。静かに残響を残して、後は消えゆくだけに思えた。
アイシラ妃も既に姿を消していた。辺りで踊っていた妃たちも、もう気配すら残っていない。
静けさに落ちた世界で、リランは眠る弟をそっと横たえた。
リランは顎を上げて、首を横に振る。
「……ううん。カイ、私と世界の向こうに行きましょう」
渾身の力を振り絞って、リランは立ち上がる。
息を吸い込み、馴染んだ拍子を思い出せば、そこに恐れはない。
リランは袖を広げ、桃色と水色の衣をはためかせて堂々と踊り始める。
村娘だった頃から、体を動かすことは何より好きだった。風の鳴る丘で、川のほとりで、無心になって踊っていた。
「謳え、この世の喜びを。祭りは楽し、娘はうつくし」
手拍子と共に歌えば、ここが百年後の世界であることも、元いた村がもうないことも忘れた。自分はリランのままで、この後百年経ってもリランでいるのだと誇りを持っていられる。
「私は踊る。世界が終わろうとも。いつか臨む月を求めて……!」
歌い終わったとき、どこかで拍手が聞こえた。
その出所を知ろうとしてリランが顔を上げたとき、水面に出たように視界が晴れた。
リランはひとり、水晶の中のような透明な箱の中に立っていた。
(あら? ここは)
むせ返る甘い香りも囁き声も圧迫感もなかった。
自分の足音すら耳に響かない静寂の中、リランは自分の体が空気に溶け込んでしまうかのような虚無感を味わう。
(誰もいないのかしら)
そっと、リランは水晶の扉を開いた。瞬間、掠めるようにリランの頬を風が撫でる。
大きな窓の元に、一人の青年が腰掛けてリランを見下ろしていた。
銀色の長い髪が暗闇の中で輝いている。その隙間から見える肩や背中の輪郭、足までの線はそれだけで燐光を放つようにしなやかで、リランには生きた存在であることなどとても信じられなかった。
たとえるなら汚れたものをすべて落とした水晶の輝き。それは人ではなく、天の住人に近いように見えた。
「……皇帝陛下?」
リランが思わず問いかけると、青年は一つうなずく。
「お若いのですね……」
リランがつい本音を告げてしまうと、皇帝は酷薄な笑みを浮かべた。
窓から降りて、皇帝はリランの前に立つ。背が高く、手足の長い彼は、優美な獣のようでもあった。
皇帝は静寂に馴染むような声で告げる。
「眠りに呑まれず、ここまで来た妃はお前が初めてだ」
皇帝は手を差し伸べてリランに問う。
「褒美をやろう。私に次ぐ皇妃となるか? それとも永遠の命が欲しいか?」
リランはひととき皇帝を正面からみつめて考え込んだ。
自分が本当に欲しいもの。それはいつだってリランの中に、宝箱に閉じ込めるようにして存在していた。
やがてリランは心を決めて告げる。
「私と弟を空中楼閣から出してください」
皇帝はその言葉に少し驚いたようだった。
「外は魔鬼たちが闊歩する。私の血を受けたお前でも、生きていくには易くないぞ」
リランは微笑んでうなずいた。
「それでもいいのです。新しい世界で、弟と月を見に行けるなら」
「……お前は」
皇帝は息を呑んで、リランに問う。
「私はお前のような柔らかい心の持ち主を待っていた。お前ならば私と共に、滅んだ世界を楽しめるだろう?」
彼の君はリランへ、凄艶な微笑を向けて囁いた。
リランは首を横に振って、彼の君を見上げて告げる。
「新しい世界に出て、生きていきます。それが終わった後の世界でも、楽しく、自分らしく」
リランは皇帝に歩み寄って、祈るように手を組んだ。
「私を再生させてくださった皇帝陛下。どうか私の願いを聞き入れてくださいませ」
皇帝は惜しむようにリランを見下ろして、彼からもリランに一歩歩み寄った。
「……子どもはいつか、親の手を離れていってしまうものだな」
彼の君は屈みこんでリランの顎を取った。
リランは自分に触れる、自分の作り主とも言える人を愛しく感じていた。
「よかろう……。願いを叶えてやる。目を閉じよ、リラン」
名前を呼ばれて、リランは目を閉じた。
まぶたの裏に光が漏れていて、闇に覆われた中でも輝くものがあるのを知った。
彼の君は優しくリランに口づけた。その途端、リランは世界が反転していくのを感じた。
星が流れるように、淡く、丸い月の光をみつめながら、リランは新しい世界に吸い込まれて行った。
「助けてくれたのは二度目ね」
リランが顔を上げればそこには、豹の耳と尻尾を持つ獣僕がいる。
「カイ……と呼んでもいい?」
弟のカイに生き写しの獣僕は、リランの言葉に考え込んだようだった。
リランはその後の言葉をある程度予感していた。姿形は弟にそっくりだが、彼のまとう空気は懐かしい弟と同じではない。
豹の獣僕は弟にはなかった牙を覗かせて、リランに苦笑してみせた。
「この体はいろいろな獣が混じっています。そういう名前も、過去にはあったのですが」
リランは彼の面差しに弟を見るが、それは彼の過去の一つらしかった。
獣僕は様々な個体と混ざって生きていく。きっと弟のカイは、そうすることで命をつないだのだ。
(また会えただけでもうれしい)
リランはうつむいて泣き笑いの顔になると、うなずいてひととき時の流れを思っていた。
今のリランと彼は、姉弟だった頃から百年経っている。けれどリランの中で弟への愛おしさは少しも色あせていなかった。
そんな複雑な表情で過去を思い返しているかつての姉に、彼もしばらくの間言葉を考えあぐねているようだった。
やがて彼は心を決めたようにうなずいて、リランに言う。
「呼びたければカイと呼んでくださってもいいですよ。僕もリランと呼びます」
「ありがとう。うれしいわ」
ふいにカイは一礼してリランを見下ろした。
そこに弟のものではない従者としての彼を見て、リランは身を引き締める。
カイは瞳に畏れを宿しながら、慎重に言葉を選んで告げた。
「リラン、僕はあなたを迎えに来ました。……皇帝陛下があなたに会いたがっておいでです」
不思議そうに見返したリランに、カイは続ける。
「百年前、あなたは皇帝陛下の血を浴びました。けれど、それまでにもそれからも、他に陛下の血を得た者たちはたくさんいたのです」
カイは目を鋭くしてリランに言う。
「血を受けた者たちは次々と眠りについていくのに、あなたは逆に目覚めた。陛下はあなたに興味を抱いていらっしゃいます」
「私自身もなぜ目覚めたのかわからないわ」
リランはチュンヒに聞いた皇帝陛下のことを思い出す。
皇帝陛下に愛されるのはたやすいことではないと言っていた。リランも会ったことがない皇帝陛下を愛するはずがない。
「……でも私も皇帝陛下にお話ししたいことがある」
リランがそう答えると、カイは安心したようにほっと息をついた。
カイはリランをみつめて少し考えると、優しく告げた。
「お召し替えをいたしましょう」
リランがカイの視線の先を追うと、あちこち焼け焦げた無残な服に気づいた。
リランは困ったように口ごもって苦笑する。
「このまま……というわけにはいかないかしら。私、百年前からこの服しか持ってきていないの」
リランは首を傾げてカイに問いかける。
「覚えているかしら? この服はあなたが、私の結婚式のために買ってくれたの」
カイは目を伏せて沈黙する。そんな彼に、リランは袖口を押さえながら言う。
「両親が亡くなったばかりであまりお金もなかったはず。とても嬉しかったの」
カイが覚えているかどうか、リランはそれ以上確かめようとは思わなかった。
リランは首を横に振って、明るい目でカイを見上げる。
「……でもあなたに再会できたことが何よりの宝物ね。さ、着替えて出かけましょう!」
カイは遠いものを探すようにリランをみつめかえしてから、先に立って歩き始めた。
リランは部屋に戻って適当な服を探し始めたものの、すぐに難航してしまった。
(うーん。私が着たら、服に申し訳ないような気がするわ……)
貧乏性に胸を痛めながら、リランはこんなときこそカイの意見を訊きたかった。けれど彼は律儀にも部屋の外で待っていて、リランは一人で衣装棚と悪戦苦闘する。
ここに来てから一月、本を読んだり獣僕と話をしたりして、一応正装がどんなものかはわかっている。けれど村娘だった頃にそんな豪勢な格好はしたことがない。
(……皇帝陛下といえば、私を馬車に引っかけた方)
そう思うと今更ながらに恐ろしい気もして、リランはごくりと息を呑む。
リランはふるふると首を横に振って思う。
(いいえ、そこは命の恩人と思いましょう!)
リランはきりっと顔を引き締めて心に決める。
衣装棚を見回して、リランは一つの服を選び取っていた。
見渡せば、石造りの階段が螺旋状に下へ下へと続いていた。
ゆらめく蝋燭とはためく壁掛けだけが風の向きを伝える。リランはぬるい風が遥か下方から昇ってきていることを感じていた。
先を行くカイが振り向いてリランに言う。
「もうじきです」
リランはうなずいて、カイに遅れないようについていく。
どこからかざわめきが風に運ばれてきて、リランは目を細めた。カイの豹の耳もぴくりと動いて、彼は階段を降りながら答える。
「今日は宴の日なのです。妃たちも起きて集まっています」
「そんな高雅の席に、村娘の私が混じってしまっていいのかしら?」
リランが問いかけると、カイは振り向いてリランを見上げながら言う。
「リランは美しいですよ。古代の衣もよくお似合いです」
カイがうなずいてくれたリランの服は、古い時代に天女の衣装と言われたものだった。
桃色と水色の混じった不思議な絹織物に縫い目はなく、まるで羽のように重みを感じない。
「そうでしょう? 私は百歳のおばあちゃんだもの!」
リランはくすっと笑って、裾をひらりと動かしてみせた。
リランはふと思い当って首を傾げた。
(でも皇帝陛下も百年前から生きていらっしゃる。だとしたらずいぶんお年の方なのかもしれないわね)
ふるさとの老人たちを思い出しながら、リランはひとりうなずいた。
やがて先を行くカイが足を止めて、両開きの扉の前で顎を上げた。
「扉を開けてください。リラン妃をお連れしました」
扉の向こうに広がった光景はまぶしくはなかったのに、リランは自然と目を細めた。
本の中でしか見たことがない、宮殿の大広間のような空間だった。香が立ち込める中、石の床に紅色のじゅうたんが敷かれている。壁に灯った無数の灰色の光は、リランが立ち入ると生き物のようにざわめいた。
カイは尻尾を一振りしてゆっくりと歩み始めて、リランもそれに続く。
(不思議……。温かいような、冷たいような空気)
夢の中にいるような気持ちで、リランは足を前へと進める。
中央のじゅうたんを踏んで前へと進む。両脇の暗闇からは何人もの忍び笑いが漏れているのに、姿はどこにも見えない。
息をつくほんの短い間のようでもあり、一日歩きとおしたような長い歩みのようでもある、そんな感覚があった。
やがてカイが身を屈めたのにならって、リランも膝をつく。
階段の上にある玉座に誰かの足先が見えたが、リランもすぐに頭を下げたので顔を見ることはできなかった。
「陛下、お連れしました」
頭を下げたまま、ためらいがちにカイが口を開いたときだった。
リランは顔を上げたつもりはなかったのに、誰かに顎を掴まれたように顔が上げさせられた。
しかも顔を上げたのに、相変わらず玉座に座る誰かの姿は見えない。
どういう怪奇現象かわからないまま、闇の中にぱっくり開いた洞窟に飲み込まれるような、そんな重圧がリランを包み込む。
「えっ……こわい」
リランはぽろっと本音をこぼしていた。
カイがうろたえたように振り向く。リランもあまりにうかつに過ぎた自分の言葉を後悔するも、自分の心のどこを探しても本音だったと思う。
ふと玉座で誰かが笑った気配がした。リランの顎をつかむ力も消えて、体を包んでいた重圧から自由になる。
リランがまばたきをするうちに、玉座の誰かはいなくなっていた。
カイはほっと安堵の息をついて、リランに声をかける。
「陛下は席を外されたようです。リラン、僕はここで」
リランは不安を浮かべた目でカイを見てしまったらしい。カイは淡く笑うと、困ったように言った。
「獣僕は宴を楽しむ立場にないのです。一緒に……月を臨める者ではないのですよ」
月と聞いたとき、リランは遠い日に弟と交わした約束を思い出した。
けれどカイはそう告げたきり、薄闇の中に消えて行ってしまった。
リランが立ち上がると、そこはさざなみのように囁き声が飛び交っていた。薄暗がりに人影が現れては消える。
(カイ、昔から優しい子だった。村が襲われる前だって、無理やり私を帝都に連れ去ったりはしなかった)
リランはうつむいて、まだやはり彼の中には弟がいるのだと思った。
(そうね。新しいことが楽しみ。それが私だったはず)
リランは自分の信条を思い返して、笑顔を浮かべる。
「行きましょう」
たとえ空元気でも、それがいつしか自分そのものになるように自分を変えていこう。リランはそう思って胸を張る。
(まあ、美味しそう)
少し歩めば花のように卓が並び、その上には湯気の立ちのぼる肉料理や香草がたっぷりと使われた野菜の椀物が置いてあった。
「あの、取っていいのですか?」
傍らに立つ獣僕に問いかけると、彼は困惑したように言葉を詰まらせた。
ふと辺りを見回すが、誰も食に興じる者はいない。
広間は全体的に暗く、端の方は真っ暗だ。囁くような声は聞こえるが、椅子も見当たらない。
そのとき、鐘が響き始めた。
リランの目は突如広がった光景に見開かれる。
(え……)
音楽が近づく音も気配すらなかったというのに、前に振り向いた時にはもう、眼前で華やかな楽団が勢揃いしていた。
西方の旅芸人のような極彩色の衣装、奇妙な形状の笛や弦楽器で紡がれる不思議な音階。中心で舞う踊り子は、風を飲み込む巨大な布を幾重にも複雑に絡めながら、地に足などついていないかのように奔放に空を駆ける。
先ほどとは全く空気が変わっていた。リランには体の感覚が次第になくなっていくような気がして、やがて人形のように座り込む。
踊り子は七色の布を一枚ずつ脱ぎ捨てていき、その隙間からとろけるようなはちみつ色の細腕が覗いた。ひらりと妖しく布がはためく度に、伸びやかな足、腕に浮かび上がる赤い刺青、女性らしい豊満な胸元、異形の証である黒と赤の交じり合った蝙蝠の翼が一つずつ晒されていく。
鈴と腕輪の擦れる音が響く。
「醜イ、妃メ……汚らわシイ」
リランは踊り子がその艶やかな唇に侮蔑を刻んだのを見た。
(アイシラ妃……!)
視界が点滅して、リランは思わず床に手をついていた。
体が熱く、力が入らない。辺りに漂う香りと暗がりから漏れる囁きが、リランの意識を捻じ曲げていく。
淀んだ空気がたちこめて、毒の霧のようにリランを包み込む。
気が付けば周囲で無数の妃たちが踊っていた。けれど彼女らの足は地に着かず、もう終わりのない世界で舞っているだけ。
アイシラの高らかな嘲笑が円舞のようにリランの聴覚を飲み込み、絶え間ない頭痛に視界が閉ざされていく。
ふいにアイシラの投げた短剣が、リランに向かって飛んだ。
「リラン……!」
リランはそれを避けることができなかった。けれどリランの前に横切った影が、リランの代わりにそれを受け止めた。
「……カイ?」
肩に怪我を負ってうずくまる獣僕を、リランは信じられないものを見るように捉える。
リランはうずくまって、獣僕を助け起こす。
「どうして戻ってきたの。カイ……!」
「……どうしてか、自分でもわから、ない」
獣僕は血に濡れた口元に、弱弱しく笑みを刻む。
「でもまだ、望んでいるんです。あなたと見る月を……」
「話さないで、カイ。すぐに手当を!」
リランは慌てて服を裂いて手当をしようとしたが、カイは首を横に振った。
「大丈夫。獣僕はここにいる限り、何度でも蘇るんです……」
その言葉通り、彼の傷口は今にも塞がろうとしていた。流れた血だけが彼の服に痕跡を残していた。
カイは怪我が癒えたのに苦しそうな表情で目を閉じる。
「眠る時間です、妃たちも獣僕も。夜が明けたら、また変わらない日を演じるために……」
深夜に鳴る鐘は、まもなく終わろうとしていた。静かに残響を残して、後は消えゆくだけに思えた。
アイシラ妃も既に姿を消していた。辺りで踊っていた妃たちも、もう気配すら残っていない。
静けさに落ちた世界で、リランは眠る弟をそっと横たえた。
リランは顎を上げて、首を横に振る。
「……ううん。カイ、私と世界の向こうに行きましょう」
渾身の力を振り絞って、リランは立ち上がる。
息を吸い込み、馴染んだ拍子を思い出せば、そこに恐れはない。
リランは袖を広げ、桃色と水色の衣をはためかせて堂々と踊り始める。
村娘だった頃から、体を動かすことは何より好きだった。風の鳴る丘で、川のほとりで、無心になって踊っていた。
「謳え、この世の喜びを。祭りは楽し、娘はうつくし」
手拍子と共に歌えば、ここが百年後の世界であることも、元いた村がもうないことも忘れた。自分はリランのままで、この後百年経ってもリランでいるのだと誇りを持っていられる。
「私は踊る。世界が終わろうとも。いつか臨む月を求めて……!」
歌い終わったとき、どこかで拍手が聞こえた。
その出所を知ろうとしてリランが顔を上げたとき、水面に出たように視界が晴れた。
リランはひとり、水晶の中のような透明な箱の中に立っていた。
(あら? ここは)
むせ返る甘い香りも囁き声も圧迫感もなかった。
自分の足音すら耳に響かない静寂の中、リランは自分の体が空気に溶け込んでしまうかのような虚無感を味わう。
(誰もいないのかしら)
そっと、リランは水晶の扉を開いた。瞬間、掠めるようにリランの頬を風が撫でる。
大きな窓の元に、一人の青年が腰掛けてリランを見下ろしていた。
銀色の長い髪が暗闇の中で輝いている。その隙間から見える肩や背中の輪郭、足までの線はそれだけで燐光を放つようにしなやかで、リランには生きた存在であることなどとても信じられなかった。
たとえるなら汚れたものをすべて落とした水晶の輝き。それは人ではなく、天の住人に近いように見えた。
「……皇帝陛下?」
リランが思わず問いかけると、青年は一つうなずく。
「お若いのですね……」
リランがつい本音を告げてしまうと、皇帝は酷薄な笑みを浮かべた。
窓から降りて、皇帝はリランの前に立つ。背が高く、手足の長い彼は、優美な獣のようでもあった。
皇帝は静寂に馴染むような声で告げる。
「眠りに呑まれず、ここまで来た妃はお前が初めてだ」
皇帝は手を差し伸べてリランに問う。
「褒美をやろう。私に次ぐ皇妃となるか? それとも永遠の命が欲しいか?」
リランはひととき皇帝を正面からみつめて考え込んだ。
自分が本当に欲しいもの。それはいつだってリランの中に、宝箱に閉じ込めるようにして存在していた。
やがてリランは心を決めて告げる。
「私と弟を空中楼閣から出してください」
皇帝はその言葉に少し驚いたようだった。
「外は魔鬼たちが闊歩する。私の血を受けたお前でも、生きていくには易くないぞ」
リランは微笑んでうなずいた。
「それでもいいのです。新しい世界で、弟と月を見に行けるなら」
「……お前は」
皇帝は息を呑んで、リランに問う。
「私はお前のような柔らかい心の持ち主を待っていた。お前ならば私と共に、滅んだ世界を楽しめるだろう?」
彼の君はリランへ、凄艶な微笑を向けて囁いた。
リランは首を横に振って、彼の君を見上げて告げる。
「新しい世界に出て、生きていきます。それが終わった後の世界でも、楽しく、自分らしく」
リランは皇帝に歩み寄って、祈るように手を組んだ。
「私を再生させてくださった皇帝陛下。どうか私の願いを聞き入れてくださいませ」
皇帝は惜しむようにリランを見下ろして、彼からもリランに一歩歩み寄った。
「……子どもはいつか、親の手を離れていってしまうものだな」
彼の君は屈みこんでリランの顎を取った。
リランは自分に触れる、自分の作り主とも言える人を愛しく感じていた。
「よかろう……。願いを叶えてやる。目を閉じよ、リラン」
名前を呼ばれて、リランは目を閉じた。
まぶたの裏に光が漏れていて、闇に覆われた中でも輝くものがあるのを知った。
彼の君は優しくリランに口づけた。その途端、リランは世界が反転していくのを感じた。
星が流れるように、淡く、丸い月の光をみつめながら、リランは新しい世界に吸い込まれて行った。