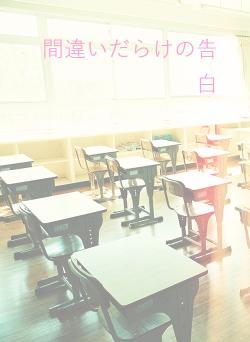私がまさかココから逃走しようなんて、誰も思っていないのだろう。
本当に完璧な人払いは、周囲に誰もいなかった。私はこっそりと数枚の服と持てるだけの金品を荷物に詰めると、私はそっと部屋を出た。物語の影響力なんて冗談じゃない。
「さぁて、どこに逃亡しようかな~」
異世界でしかないこの世界は、私にとってはどこに行ってもある意味同じなのよね。でもどうせ逃げるのなら、見つからないとこにしないといけないわ。連れ戻されても困るし。
んーーーーー。どうしようかなぁ。
「あーでも、近場は田舎ばっかりだし。職探しも困るかもしれないわね。お金だっていつまでもつか分からないし。それなら木を隠すなら森ということで、隣国である帝国まで逃げちゃおぅ」
ふっふふーん。せっかくだし異世界を満喫しないとね。それに何て言ったって、ココは私の大好きな中華風異世界だし。食べ物もおいしいし、服も好きなのよね。
翠蘭ってキャラも、可愛くて見た目は好きだったんだけど。やってたことは小姑過ぎるのよね。確かヒロインちゃんへの陰口から始まって、虫を部屋に大量に入れてみたり、食べ物に異物を混ぜたり。
それでもめげない彼女に最終的には毒を盛る。それが女官の口からバレて、あっけなく処刑。うん。絶対そんなバッドエンドなんて回避よ、回避。
さぁ、楽しい異世界観光を楽しもう~。
◇ ◇ ◇
「ってもう。本当になんなよの!」
異世界観光を楽しむ余裕などどこへ行ってしまったのか、国を出てからというものめんどくさいことばかりだ。まず国境を超えるのに通行手形が必要というのが盲点だった。
警備兵に身分を明かすわけにもいかず、困っていたところに来た商団の馬車に乗せてもらえた。だけどさすがは商人。一番高価な簪をとられてしまった。
残りの宝石たちであとどれだけ過ごせるかと思っていた矢先、これだ。
「おねーちゃん、一杯一緒にって言ってるだけだろ」
「……やめてください」
酔っぱらった大柄の男二人が、スラリとした長身で切れ長のやや青みがかった黒い瞳の女性の手を掴み、道端で揉めている。
私が進みたい道の方向をちょうど邪魔しており、通り過ぎることも出来ない。邪魔すぎる。ただでさえこっちは結構頭に来てるのに、迷惑過ぎるでしょう。
進むことが出来ずにどうしようか考えていると、その綺麗な女性と目があった。その瞳が明かに私に助けを求めている。もーーーーー。こういう面倒ごとは極力回避したいのに。
私は一度深くため息をつくと、諦めて前を見た。
「彼女、嫌がってますけど?」
「なんだお前。お前みたいなちんちくりんに用はないんだよ」
「そうだ。子どもはおうちに帰って、寝てろ!」
私をちらりと見た二人は、大きく悪態をつきゲラゲラと下品に笑い出す。まぁね。乳もないですし? 身長も大きくはないわよ。だけどクマみたいな初対面の男たちに、そこまで言われるほど私も不細工ではないわよ。
「……ウザ」
「ああん? なんだって?」
「だーかーら、ウザいって言ったのよ! ああ、こんな言葉知らないんだっけ」
この世界にウザいってあるのかな。私は思わず鼻でふんって笑ってやれば、男たちは顔を真っ赤にして女性の手を離しこちらにゆっくりと近づいてくる。
「だれかーーーーーーー!! 強盗よ!!」
出せるだけの大きな声を張り上げたあと、私は男たちの脇をすり抜け女性の腕を掴んだ。そしてそのまま、走り出す。
急に何が起こったのか理解できない男たちを置き去りに、私たちは日が傾きかけた町の中を駆け抜けて行った。
本当に完璧な人払いは、周囲に誰もいなかった。私はこっそりと数枚の服と持てるだけの金品を荷物に詰めると、私はそっと部屋を出た。物語の影響力なんて冗談じゃない。
「さぁて、どこに逃亡しようかな~」
異世界でしかないこの世界は、私にとってはどこに行ってもある意味同じなのよね。でもどうせ逃げるのなら、見つからないとこにしないといけないわ。連れ戻されても困るし。
んーーーーー。どうしようかなぁ。
「あーでも、近場は田舎ばっかりだし。職探しも困るかもしれないわね。お金だっていつまでもつか分からないし。それなら木を隠すなら森ということで、隣国である帝国まで逃げちゃおぅ」
ふっふふーん。せっかくだし異世界を満喫しないとね。それに何て言ったって、ココは私の大好きな中華風異世界だし。食べ物もおいしいし、服も好きなのよね。
翠蘭ってキャラも、可愛くて見た目は好きだったんだけど。やってたことは小姑過ぎるのよね。確かヒロインちゃんへの陰口から始まって、虫を部屋に大量に入れてみたり、食べ物に異物を混ぜたり。
それでもめげない彼女に最終的には毒を盛る。それが女官の口からバレて、あっけなく処刑。うん。絶対そんなバッドエンドなんて回避よ、回避。
さぁ、楽しい異世界観光を楽しもう~。
◇ ◇ ◇
「ってもう。本当になんなよの!」
異世界観光を楽しむ余裕などどこへ行ってしまったのか、国を出てからというものめんどくさいことばかりだ。まず国境を超えるのに通行手形が必要というのが盲点だった。
警備兵に身分を明かすわけにもいかず、困っていたところに来た商団の馬車に乗せてもらえた。だけどさすがは商人。一番高価な簪をとられてしまった。
残りの宝石たちであとどれだけ過ごせるかと思っていた矢先、これだ。
「おねーちゃん、一杯一緒にって言ってるだけだろ」
「……やめてください」
酔っぱらった大柄の男二人が、スラリとした長身で切れ長のやや青みがかった黒い瞳の女性の手を掴み、道端で揉めている。
私が進みたい道の方向をちょうど邪魔しており、通り過ぎることも出来ない。邪魔すぎる。ただでさえこっちは結構頭に来てるのに、迷惑過ぎるでしょう。
進むことが出来ずにどうしようか考えていると、その綺麗な女性と目があった。その瞳が明かに私に助けを求めている。もーーーーー。こういう面倒ごとは極力回避したいのに。
私は一度深くため息をつくと、諦めて前を見た。
「彼女、嫌がってますけど?」
「なんだお前。お前みたいなちんちくりんに用はないんだよ」
「そうだ。子どもはおうちに帰って、寝てろ!」
私をちらりと見た二人は、大きく悪態をつきゲラゲラと下品に笑い出す。まぁね。乳もないですし? 身長も大きくはないわよ。だけどクマみたいな初対面の男たちに、そこまで言われるほど私も不細工ではないわよ。
「……ウザ」
「ああん? なんだって?」
「だーかーら、ウザいって言ったのよ! ああ、こんな言葉知らないんだっけ」
この世界にウザいってあるのかな。私は思わず鼻でふんって笑ってやれば、男たちは顔を真っ赤にして女性の手を離しこちらにゆっくりと近づいてくる。
「だれかーーーーーーー!! 強盗よ!!」
出せるだけの大きな声を張り上げたあと、私は男たちの脇をすり抜け女性の腕を掴んだ。そしてそのまま、走り出す。
急に何が起こったのか理解できない男たちを置き去りに、私たちは日が傾きかけた町の中を駆け抜けて行った。