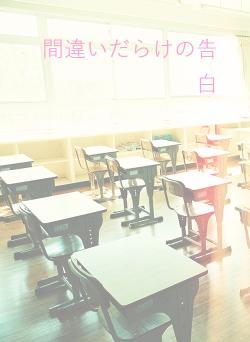「うむ。そうだな……この娘にしよう」
短くそう言った皇帝は、広場の一番隅で小さくなっていた私を軽々と担いだ。
「えええ?」
自分でも何が起こったのか理解できず、思わす私は素っ頓狂な声を上げた。しかし声を上げたのは私だけではない。広間に集められていた他のお妃候補たちや、陛下の後ろを着いて歩いていた宦官すらも同じ反応だった。
それも無理はないだろう。この中の誰一人として、私が選ばれるなんて思いもしなかったはずだから。
「お、恐れ多くも陛下……」
まるで荷物のように肩に担がれた私は身じろぎしながら、絞るように声を上げた。
「どうした? ああ、担ぎ方が気に食わなかったのか。すまぬな。女子など担いだこともないものだからな」
「いいいい、いえ、そういうわけではないのです!」
「そうなのか? だが確かにこれでは顔が見れぬな。こうしたほうがいいか」
殿下はそう言いながら、私を横向きに抱え直した。すまぬな? えええ。今、すまぬって陛下はおっしゃられたの?
皇帝が謝るとか、絶対にダメでしょう。も、もうどう頑張っても不敬罪で処刑される未来しか見えないし。何が起こっているの。ど、どうしてこんなことになったのよ。
「で、どうしたというのだ。ああ、名前を聞いておらぬな」
「あの、名前……名前は蓮花と申します」
「おお、蓮の花か。良い名前だ」
「ありがとうございます」
生まれて初めて自分の名前を母親以外に褒められたわ。嬉しい……って、今はそうじゃないわ。その前にちゃんと言わないと。
「ああ、いえそうではなくてですねぇ!」
「どうした? 俺の腕の中でそのように身じろぎなどして。そんなに恥ずかしいのか?」
恥ずかしいに決まっているじゃない! 分かってます? 今この状況。
陛下はなぜか小動物でも愛おしむような瞳で私を見て下さっているけど、周りはぽかんと口を開け、何が起きたのか分からないという顔をしているのですよ!
なんて不敬罪極まりないし、陛下に言えるわけもない。でもきっと陛下は知らないだけ。私が何なのか、を。だからきっとコレを言えば諦めて下さるわ。
「陛下、僭越ながら私は無色……この国において、稀なる霊力を持たない者なのです!」
そう。霊力こそが全ての世界のおいて、霊力を持たない私には人権などないに等しかった。だから今回のことだって……ほんの物見遊山のつもりだったというのに。
国内にその御触書が出されたのはほんの一か月ほど前。前皇帝が今帝に滅ぼされ、後宮の全てを総入れ替えするという文で始まっていた。
後宮にいた妃は、子を成した者以外は全て親元へと返されたらしい。そして新たな妃と女官を集めるために、国中の年頃の娘たちは期日までに後宮前の広間に集まれとのことだった。
幾分横暴な御触書ではあったが、誰も逆らうものなどこの国にはいない。だって、今帝は血塗られ皇帝とまで揶揄されるほどの残虐非道な皇帝だったから……。
ただ集まった者には幾ばくかの禄と米がもらえるという特典に飛びついた自分を殴ってやりたい気分よ。あの村ではずっと、人々に無視され続けてきたんだし。
御触書なんて読ませてもらえなかったから知りませんでしたって、言うべきだったわ……。
後悔先に立たず。私はそんな言葉を思い浮かべながら、ココに来る前のことを一人思い出していた。
短くそう言った皇帝は、広場の一番隅で小さくなっていた私を軽々と担いだ。
「えええ?」
自分でも何が起こったのか理解できず、思わす私は素っ頓狂な声を上げた。しかし声を上げたのは私だけではない。広間に集められていた他のお妃候補たちや、陛下の後ろを着いて歩いていた宦官すらも同じ反応だった。
それも無理はないだろう。この中の誰一人として、私が選ばれるなんて思いもしなかったはずだから。
「お、恐れ多くも陛下……」
まるで荷物のように肩に担がれた私は身じろぎしながら、絞るように声を上げた。
「どうした? ああ、担ぎ方が気に食わなかったのか。すまぬな。女子など担いだこともないものだからな」
「いいいい、いえ、そういうわけではないのです!」
「そうなのか? だが確かにこれでは顔が見れぬな。こうしたほうがいいか」
殿下はそう言いながら、私を横向きに抱え直した。すまぬな? えええ。今、すまぬって陛下はおっしゃられたの?
皇帝が謝るとか、絶対にダメでしょう。も、もうどう頑張っても不敬罪で処刑される未来しか見えないし。何が起こっているの。ど、どうしてこんなことになったのよ。
「で、どうしたというのだ。ああ、名前を聞いておらぬな」
「あの、名前……名前は蓮花と申します」
「おお、蓮の花か。良い名前だ」
「ありがとうございます」
生まれて初めて自分の名前を母親以外に褒められたわ。嬉しい……って、今はそうじゃないわ。その前にちゃんと言わないと。
「ああ、いえそうではなくてですねぇ!」
「どうした? 俺の腕の中でそのように身じろぎなどして。そんなに恥ずかしいのか?」
恥ずかしいに決まっているじゃない! 分かってます? 今この状況。
陛下はなぜか小動物でも愛おしむような瞳で私を見て下さっているけど、周りはぽかんと口を開け、何が起きたのか分からないという顔をしているのですよ!
なんて不敬罪極まりないし、陛下に言えるわけもない。でもきっと陛下は知らないだけ。私が何なのか、を。だからきっとコレを言えば諦めて下さるわ。
「陛下、僭越ながら私は無色……この国において、稀なる霊力を持たない者なのです!」
そう。霊力こそが全ての世界のおいて、霊力を持たない私には人権などないに等しかった。だから今回のことだって……ほんの物見遊山のつもりだったというのに。
国内にその御触書が出されたのはほんの一か月ほど前。前皇帝が今帝に滅ぼされ、後宮の全てを総入れ替えするという文で始まっていた。
後宮にいた妃は、子を成した者以外は全て親元へと返されたらしい。そして新たな妃と女官を集めるために、国中の年頃の娘たちは期日までに後宮前の広間に集まれとのことだった。
幾分横暴な御触書ではあったが、誰も逆らうものなどこの国にはいない。だって、今帝は血塗られ皇帝とまで揶揄されるほどの残虐非道な皇帝だったから……。
ただ集まった者には幾ばくかの禄と米がもらえるという特典に飛びついた自分を殴ってやりたい気分よ。あの村ではずっと、人々に無視され続けてきたんだし。
御触書なんて読ませてもらえなかったから知りませんでしたって、言うべきだったわ……。
後悔先に立たず。私はそんな言葉を思い浮かべながら、ココに来る前のことを一人思い出していた。