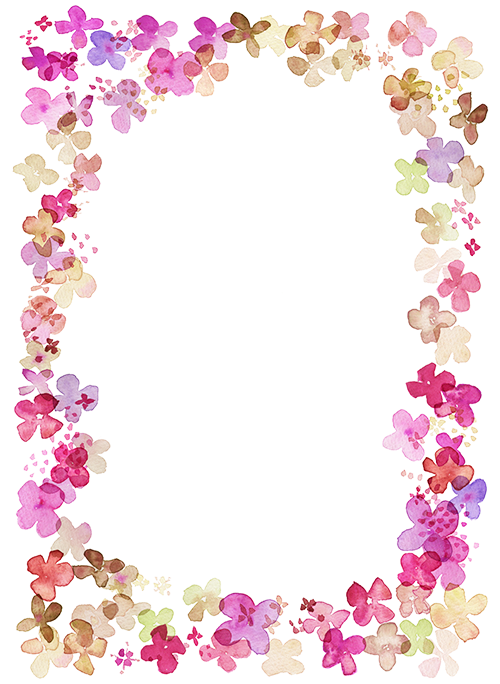天人の存在を信じるも信じないも、そこは見るからに人間ではない者たちが行き交っていた。
まず彼らはだいたい空を飛んでいて、浮きながら果物を食べていたり、一跳びで木に上ったりしていて、しかもあんまり働いていなかった。
「お兄さん、桃饅食べる?」
「感謝する。気持ちだけいただこう」
下界からやって来た瑠璃帝に、敵対的どころかとても親切だった。やれ桃饅だ干菓子だとふるまってくれたが、果たしてここの食べ物を口にして人間のままでいられる自信がなかったので、ありがたくお断りした。
「最近下界から来た女人?」
「最近って? 百年くらい?」
ただ瑠璃帝が平凡妃を探すのは難航を極めた。天人たちは時間感覚が鈍く、男女の別もそれほどこだわっていないので、ただでさえ特徴の薄い平凡妃は埋もれてしまっていた。
「豊穣の女神様に訊いてみたら? 丘の上にお住まいだよ」
幸いだったのは、天人の里はそれほど広くないことだった。まもなく瑠璃帝は、里一体を見渡せる小高い丘にやって来た。
そこには花鳥風月の細工が鮮やかな、見覚えのある門が瑠璃帝を見下ろしていた。
「宝珠宮によく似ている」
瑠璃帝はぽつりとつぶやいたが、門はひとりでに開いて彼を招き入れた。
中に入ってみると、ハスの花が点々と水に浮かんでいた。十人ほどの天女たちが、ハスの上をひょいひょい渡り歩いて遊んでいる。
「……ん?」
そこで、瑠璃帝は少女の一人に目を留めて声を上げる。
「平凡妃!」
天人たちはみな似た顔をしているが、だからといって昼も夜も考え続けた瑠璃帝の執念は伊達ではなかった。
瑠璃帝が鋭く呼ぶと、その少女はわかりやすく驚いて、ハスから足を踏み外した。
「危ないよぉ」
だが天女たちはくすくすと笑ってその少女の袖をつまむと、ハスの上に戻してくれる。
天女たちは少女に首を傾げて問いかける。
「友だち?」
「……違うよ」
少女はそう答えて、ふいに恐れるような目で瑠璃帝を見た。
その目は嵐の中に消えた、あの日の平凡妃の目だった。
天女たちはもう一つ少女に問いかける。
「恋人?」
「ちが……」
それにも違うと言いかけた少女に、瑠璃帝は声を上げた。
「夫になるはずだった者だ」
瑠璃帝がそう言うと、少女はごくんと息を呑んだ。
瑠璃帝はハスの上を渡って少女の前まで来ると、確信を持って問いかける。
「平凡妃だな?」
沈黙は一瞬で、彼女は目を逸らしながらぼそりと言う。
「……ばれてしまっては仕方がない」
平凡妃は不敵に笑ったが、それは苦々しい笑みだった。
「やーいやーい」
周りの天女たちは冷やかすように平凡妃に笑ってから、点々とハスの上を渡って去っていく。
二人きりになってからも、しばらくお互い無言だった。平凡妃はあの夜のことを思いだしているのか、なんだか気恥ずかしそうだった。
瑠璃帝は心を落ち着けて平凡妃に問いかける。
「この里の天人たちは、そなたによく似ているな」
平凡妃はうなずいて、ええまあ、と続ける。
「見たままです。ある日、女神様から仲間にならないかとお誘いがありまして」
平凡妃は思い出すように言葉を続ける。
「一月でこの里に来ることを条件に、いたずらじみた妖術を授かりました」
「そなたと過ごした一月は、実に楽しかった」
瑠璃帝が本音のままに言うと、平凡妃はほほえむ。
「それは幸いです。最後に一旗上げようと、私も大いに遊ばせてもらいましたのでね」
平凡妃はふいにうつむいて、ぽつりと言う。
「まあばれてしまったとおり、私は単なる未通娘ですが……えっ!」
平凡妃の言葉が終わる前に、瑠璃帝はいきなり彼女を横抱きにした。
「な、何をなさるのですか!」
「わかっていよう。ここへはそなたを連れて帰りに来たのだ」
「いや、ですから! 帰っても私は、もう妖術が使えず……!」
「それでよい」
瑠璃帝は平凡妃と額が触れる距離に顔を寄せて言った。
「私はそなたが欲しいのだ。……妖術は無くていい」
瑠璃帝はじっと平凡妃をみつめて笑う。
「馬鹿馬鹿しいくらいに本気だ。どうやら私は、そなたを愛してしまったらしい」
「……愛、ですと?」
平凡妃はそんな瑠璃帝を見て、ぽかんと呆れ顔になった。
瑠璃帝はうなずいて平凡妃の頬に触れる。
「そうとも。私は皇帝なのでな。私が望んだら拒否権はないのだ」
瑠璃帝は平凡妃を抱いたまま踵を返すと、そのままつかつかと歩き出す。
平凡妃はうろたえて、言葉を探してうんうん言っていたが、やがて観念したようにため息をつく。
「……奇特な御方だこと」
「そなたに言われたくないぞ」
平凡妃は嫌味ではなく本心からそうつぶやいたが、やがて小さく笑った。
「さて、この怪異をどう渡っていきましょうか……」
そのとき、二人の渡っていたハスがたわんで揺らぐ。
あ、と二人が声を上げたときは遅かった。
ハスは一瞬で溶けて、二人は湖に放り出されていた。
湖は温かく母の腹の中のように静かで、その中で瑠璃帝は声を聞いた。
「平凡妃には、あなたに妖術を使わないと約束してもらったけれど」
それは遠い日に聞いた、姉の宝珠公主の声に似ていた。
彼女はふふっと笑って言葉を続ける。
「……面白いくらいに大いに心を乱してくれたようだから、よいことよ」
瑠璃帝の意識と共に声は遠のいていって、霧の中を飛んだような心地だった。
瑠璃帝は手を伸ばして平凡妃の背中をつかまえると、はぐれないようにとぎゅっと彼女を抱き寄せた。
まず彼らはだいたい空を飛んでいて、浮きながら果物を食べていたり、一跳びで木に上ったりしていて、しかもあんまり働いていなかった。
「お兄さん、桃饅食べる?」
「感謝する。気持ちだけいただこう」
下界からやって来た瑠璃帝に、敵対的どころかとても親切だった。やれ桃饅だ干菓子だとふるまってくれたが、果たしてここの食べ物を口にして人間のままでいられる自信がなかったので、ありがたくお断りした。
「最近下界から来た女人?」
「最近って? 百年くらい?」
ただ瑠璃帝が平凡妃を探すのは難航を極めた。天人たちは時間感覚が鈍く、男女の別もそれほどこだわっていないので、ただでさえ特徴の薄い平凡妃は埋もれてしまっていた。
「豊穣の女神様に訊いてみたら? 丘の上にお住まいだよ」
幸いだったのは、天人の里はそれほど広くないことだった。まもなく瑠璃帝は、里一体を見渡せる小高い丘にやって来た。
そこには花鳥風月の細工が鮮やかな、見覚えのある門が瑠璃帝を見下ろしていた。
「宝珠宮によく似ている」
瑠璃帝はぽつりとつぶやいたが、門はひとりでに開いて彼を招き入れた。
中に入ってみると、ハスの花が点々と水に浮かんでいた。十人ほどの天女たちが、ハスの上をひょいひょい渡り歩いて遊んでいる。
「……ん?」
そこで、瑠璃帝は少女の一人に目を留めて声を上げる。
「平凡妃!」
天人たちはみな似た顔をしているが、だからといって昼も夜も考え続けた瑠璃帝の執念は伊達ではなかった。
瑠璃帝が鋭く呼ぶと、その少女はわかりやすく驚いて、ハスから足を踏み外した。
「危ないよぉ」
だが天女たちはくすくすと笑ってその少女の袖をつまむと、ハスの上に戻してくれる。
天女たちは少女に首を傾げて問いかける。
「友だち?」
「……違うよ」
少女はそう答えて、ふいに恐れるような目で瑠璃帝を見た。
その目は嵐の中に消えた、あの日の平凡妃の目だった。
天女たちはもう一つ少女に問いかける。
「恋人?」
「ちが……」
それにも違うと言いかけた少女に、瑠璃帝は声を上げた。
「夫になるはずだった者だ」
瑠璃帝がそう言うと、少女はごくんと息を呑んだ。
瑠璃帝はハスの上を渡って少女の前まで来ると、確信を持って問いかける。
「平凡妃だな?」
沈黙は一瞬で、彼女は目を逸らしながらぼそりと言う。
「……ばれてしまっては仕方がない」
平凡妃は不敵に笑ったが、それは苦々しい笑みだった。
「やーいやーい」
周りの天女たちは冷やかすように平凡妃に笑ってから、点々とハスの上を渡って去っていく。
二人きりになってからも、しばらくお互い無言だった。平凡妃はあの夜のことを思いだしているのか、なんだか気恥ずかしそうだった。
瑠璃帝は心を落ち着けて平凡妃に問いかける。
「この里の天人たちは、そなたによく似ているな」
平凡妃はうなずいて、ええまあ、と続ける。
「見たままです。ある日、女神様から仲間にならないかとお誘いがありまして」
平凡妃は思い出すように言葉を続ける。
「一月でこの里に来ることを条件に、いたずらじみた妖術を授かりました」
「そなたと過ごした一月は、実に楽しかった」
瑠璃帝が本音のままに言うと、平凡妃はほほえむ。
「それは幸いです。最後に一旗上げようと、私も大いに遊ばせてもらいましたのでね」
平凡妃はふいにうつむいて、ぽつりと言う。
「まあばれてしまったとおり、私は単なる未通娘ですが……えっ!」
平凡妃の言葉が終わる前に、瑠璃帝はいきなり彼女を横抱きにした。
「な、何をなさるのですか!」
「わかっていよう。ここへはそなたを連れて帰りに来たのだ」
「いや、ですから! 帰っても私は、もう妖術が使えず……!」
「それでよい」
瑠璃帝は平凡妃と額が触れる距離に顔を寄せて言った。
「私はそなたが欲しいのだ。……妖術は無くていい」
瑠璃帝はじっと平凡妃をみつめて笑う。
「馬鹿馬鹿しいくらいに本気だ。どうやら私は、そなたを愛してしまったらしい」
「……愛、ですと?」
平凡妃はそんな瑠璃帝を見て、ぽかんと呆れ顔になった。
瑠璃帝はうなずいて平凡妃の頬に触れる。
「そうとも。私は皇帝なのでな。私が望んだら拒否権はないのだ」
瑠璃帝は平凡妃を抱いたまま踵を返すと、そのままつかつかと歩き出す。
平凡妃はうろたえて、言葉を探してうんうん言っていたが、やがて観念したようにため息をつく。
「……奇特な御方だこと」
「そなたに言われたくないぞ」
平凡妃は嫌味ではなく本心からそうつぶやいたが、やがて小さく笑った。
「さて、この怪異をどう渡っていきましょうか……」
そのとき、二人の渡っていたハスがたわんで揺らぐ。
あ、と二人が声を上げたときは遅かった。
ハスは一瞬で溶けて、二人は湖に放り出されていた。
湖は温かく母の腹の中のように静かで、その中で瑠璃帝は声を聞いた。
「平凡妃には、あなたに妖術を使わないと約束してもらったけれど」
それは遠い日に聞いた、姉の宝珠公主の声に似ていた。
彼女はふふっと笑って言葉を続ける。
「……面白いくらいに大いに心を乱してくれたようだから、よいことよ」
瑠璃帝の意識と共に声は遠のいていって、霧の中を飛んだような心地だった。
瑠璃帝は手を伸ばして平凡妃の背中をつかまえると、はぐれないようにとぎゅっと彼女を抱き寄せた。