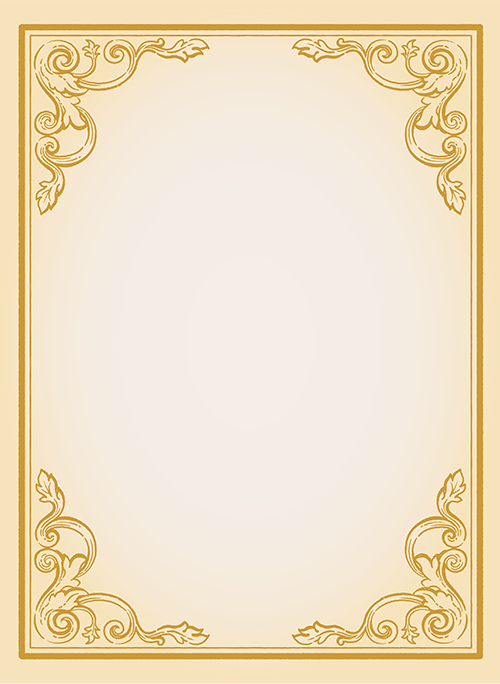篠宮レナは、二番目に好きな人と付き合っている。
彼氏の西沖翔真はバレー部のエースで、とても背が高い。そのうえ勉強ができて性格も穏やか、さらには顔立ちも綺麗。誰もが羨む完璧な彼氏だった。
一方レナの一番好きな人は美術部の幽霊部員で、背はレナとあまり変わらない。勉強は中の下で、苦手な科目では赤点を取ることさえあった。性格は気まぐれでだらしなく、顔立ちも普通。どうひいき目に見たって、翔真の方が格好良い。
けれどレナは、子供のころからずっと小谷大夢のことが好きだった。
「レナ、今日の帰りはどうするの? 翔真君と一緒?」
いつの間にかホームルームが終わっていたらしい。後ろからポンと肩を叩かれて、レナは弾かれたように顔を上げた。
「もしかして、ボーっとしてた? 寝不足?」
「あー……うん、そう。ちょっと昨日、英語の予習に手間取って」
ふぅんと金崎唯子が小さく呟くが、細められた目はレナの言葉を疑っているようだった。
しばらく無言でレナを見ていた唯子だったが、諦めたようにヒラリと手を振った。黙秘モードに入ったレナは、何があっても絶対に言わないと経験上知っていたのだ。
「まぁ、良いわ。それで、今日の放課後の予定は?」
「特に何もないと思うけど、唯子は大夢と予定あるでしょ?」
確か今日は、図書館で勉強をすると言っていたはずだ。
唯子の口がヘの字に曲がり、視線が左斜め下に落ちる。軽く膨らんだ頬はすぐにしぼみ、また膨らむ。気に入らないことがあると、思い切り不貞腐れた顔をする。唯子は昔からそうだった。
「また喧嘩したの?」
「喧嘩とかじゃなくてぇ」
語尾が間延びして、最後は吐き捨てるようにプツリと消える。これも、唯子の機嫌が悪い時によくする口調だった。
「どうせまた、唯子がわがまま言ったんでしょう?」
「そんなんじゃないよぅ」
「嘘だね。自分が悪いってわかってるけど認められない時の口調してるもん」
幼馴染なんだから、お見通しだよ。そんな気持ちを込めて肩をすくめれば、唯子は観念したように机に突っ伏して他愛もない恋人同士の喧嘩を愚痴り始めた。
唯子は、大夢と付き合っているのだ。
唯子は大夢のことが好きなのだと気付いたのは、小学校も折り返しの時だった。
低学年よりは学校に慣れて、けれど高学年のお兄さんお姉さんはまだどこか怖くて。校舎を駆け回る自由とともに、責任と言う名の不自由さを感じ始め、社会と言うものが分かってきた、そんな微妙な時期だった。
いつも男子と張り合い、ガキ大将のように暴れまわっていた唯子が、バレンタインのチョコを作りたいと言ってきたのだ。
「レナ、いつも作ってるでしょ? 今年は、あたしも一緒に作っても良い?」
「もちろん、良いけど……誰にあげるの?」
唯子が、少しだけ伸びた前髪を指先でつまむ。レナの記憶の中の唯子は、いつもショートカットだった。
「えっと、お父さんとお兄ちゃんと、お母さんにもあげる。あと、結人にも」
結人は唯子の弟だ。たしか、今年幼稚園生になったばかりのはずだ。
名前を上げるたびに指が折りたたまれ、今は小指だけがピンと空をさしている。
「それと、レナにもあげる」
無邪気な笑顔で、最後の指がたたまれる。しかしすぐに、再び小指が空をさした。
「あとは……大夢、かな。ほ、ほら、毎年チョコ欲しいチョコ欲しいって言ってるのに、レナ以外誰もあげてないの可哀想だし。レナは幼馴染だからあげてるだけなんだろうけど、大夢が勘違いしたら……ね。レナは可愛いから……。だから、今年はあたしもあげて、ホワイトデーに三倍返ししてもらおうかなって!」
駅前にできたばかりのケーキ屋のクッキーが美味しそうだけれど、高くてなかなか手が出ないからと、言い訳のようにつぶやいている。視線は落ち着きなく左右に揺れており、もじもじと手足が動いている。
やけに甲高い声で早口でまくし立てる唯子の顔は、トマトのように真っ赤だった。
「唯子……」
大夢が好きなの? そう言いかけて、つばを飲み込む。
唯子がどんな切っ掛けで、子分のように扱っていた大夢を好きになったのかは分からない。しかし、唯子の目は恋をしていた。
そう、絶対に勘違いなどではない。唯子は本気で好きなのだ。だって唯子の目は、レナの目と同じだから。
幼稚園の頃からずっと大夢のことを見てきたレナと、今の唯子は同じ顔をしているのだから。
(私、大夢のことが好きなの)
心の中で告白をする。
もしも口に出して言ったら、唯子はどんな顔をするだろう?
きっと彼女は、うろたえる。レナが本気で言っているのかどうか顔色をうかがって、嘘を言っていないと理解したら、不自然なくらい明るく笑って「じゃあ、チョコあげるのやめようかな」と言うだろう。
そして彼女は、レナと大夢から距離を取る。
正直者の唯子は自分の気持ちに嘘をつくことができず、一緒にいる辛さに耐え切れなくなり、そっと幼馴染の輪を抜けるだろう。
物心つく前からずっと一緒だったのに。三人仲良しの幼馴染だったのに。
「……唯子、お菓子作りできるんだっけ?」
「いや、出来ないからレナに教えてもらおうとしてるんだけど」
「もしかして、湯せんから教えないといけない?」
「湯せん? チョコレート作るのに、お湯は必要ないでしょ? だって溶けちゃうし」
レナは大げさにため息をつき、手の施しようがありませんと言うように両手を上げて頭を振った。お湯なんて使ったら溶けてなくなっちゃうと言い張る唯子の顔を注意深く観察する。
どうやら彼女は、レナがしばし沈黙したことを不審に思ってはいないようだった。
どんなチョコを作りたいのか話し合いながら、レナは頭の中で冷静に今の状況を分析していた。
大夢は唯子のことが好きなはずだ。でもそれは、幼馴染としての好きであって、特別な好きではない。いつか特別へと変わる可能性を秘めた好きだ。
「形はどうしようかな。星も良いし、動物も良いな。レナの家、ウサギの型はあるんだっけ?」
「あるよ。それに、ハートも」
唯子の顔が赤くなる。レナは足元に視線を落とすと、目についた小石を蹴った。
レナは嘘をつくのが得意だった。自分を騙すのも、感情から目をそらすのも。
(小さいころから一番近くにいたから、好きだと思ってるだけなのかもしれない)
レナが今大夢に抱いている気持ちは、ただの錯覚かもしれない。
(幼馴染だから大夢を好きになっただけで、大夢だから好きになったわけじゃない)
仲良しな三人組の幼馴染という形を守るために、屁理屈をこねて大夢への気持ちに蓋をする。
幼馴染の好きと、恋愛の好きが混ざってしまっただけ。大夢でなければいけない理由はない。
何度も何度も自分に嘘をつく。
レナの嘘は、誰でも騙せてしまう。たとえ相手が自分自身だとしても、嘘をつき続ければ本当になってしまうのだと、また一つ嘘を重ねる。
中学に入り、レナは翔真に告白され、付き合うことになった。
だって、翔真は完璧だから。非の打ちどころのない、素敵な男の子だから。
(誰でも好きになってしまうから。私も、好きになってしまったから)
嘘をつく。でも、翔真に対する気持ちは嘘とは言い切れなかった。
一緒にいれば安心するし、笑顔を向けられると胸が高鳴る。指先が触れただけでも、ジワリと幸せが全身に広がる。
レナは翔真のことが好きだった。その気持ちに、嘘はなかった。でも同時に、自分につき続けた嘘が心の奥底で溜まり、どうにもできない黒い感情となって消えることなく漂っていた。
唯子が大夢に告白したのは、レナが翔真と付き合い始めて数か月が経った後だった。
唯子の長い愚痴を聞き終え、レナは裁判官のように厳かに判決を言い渡した。
「唯子が悪い」
「うぅぅ……そうやっていつもレナは大夢の味方をするぅ」
「別に大夢の味方はしてないよ。総合的に考えて、唯子が悪いって結論に至っただけ」
唸り声をあげる唯子の髪が、肩から滑り落ちる。小学校の時はあれほどショートにこだわっていたのに、今ではレナと同じくらい髪が長い。
昇降口の掃除に行っていた大夢が帰ってきたのが見え、唯子の腕をつつく。
「ほら、早いところ仲直りしてきなよ」
「うぅ……そ、そうだ。今日もレナ、翔真君と一緒に帰るんだよね? 久々に翔真君に挨拶しようかな!」
顔を上げた唯子が、翔真の名前を強調しながらそんなことを言う。教室の隅で帰り支度をしていた大夢の肩が震えたのが、視界の端にうつった。
仏頂面の大夢が大股でこちらに近づいてくる。
唯子は翔真を使って大夢の気を引きたいのだろうが、変に拗れてしまう可能性がある。
「翔真、今日は音楽室の掃除があるって言ってたよ。遅くなるだろうから、先に帰りなよ」
大夢にアイコンタクトを投げるが、翔真が来るほうが早かった。どうやら音楽室の掃除は、レナが考えるよりもずっと早く終わったらしい。
唯子が立ち上がり、翔真の元へ走っていく。
「久しぶりだね翔真君。今日も相変わらずイケメンだね!」
いつもよりオクターブ高い声で可愛らしく小首を傾げる唯子と、不機嫌さを隠しもせずに睨みつける大夢を交互に見て、翔真は微笑んだ。
同い年ながらも、翔真はどこか達観している部分があった。人の感情を読み取るのが上手く、理解力も高かった。
翔真はすぐに、唯子の子供っぽい振る舞いの理由と、大夢の幼い支配欲による嫉妬心に気づいたようだった。
「惟子ちゃんも大夢も、久しぶり」
「ねえねえ翔真君、今度暇なときに、ダブルデートしようよ! 大夢ももちろん良いよね?」
「……俺は別に、翔真たちさえ良ければ良いよ。久しぶりにレナとも遊びたいし」
今度は大夢が唯子を試す。
何度も一緒に遊び、なんならお風呂すら一緒に入っていたような幼馴染に対して、今さら嫉妬することはないだろう。そう思っていたレナだったが、唯子の口はヘの字に曲がっていた。
視線が左斜め下に落ち、頬が収縮を繰り返す。気に入らないことがあるときに、唯子はいつもああやって不満を顔に出す。
(唯子は私にも嫉妬するんだ……)
惟子はレナが長年つき続けた「大夢に特別な感情は抱いていない」と言う嘘を信じているはずなのに。
校庭を並んで歩く大夢と唯子の後ろ姿を、教室の窓から見下ろす。
傾き始めた陽が世界をオレンジ色に染め、二人の姿をセピアに色づけていた。
視線に気づいたのか二人がそろって振り返り、大きく手を振る。レナは小さく手を振り返すと、仲良く繋がれた手をジっと見つめた。
二人は、いつもそうだった。喧嘩とまでは言い切れない小さな諍いは、解決をしないまま何となく落ち着いてしまう。どちらが悪いのか分からないまま終わるため、どちらも自分が悪かったかもしれないと言う負い目を感じ、相手に譲歩する。双方が譲歩した分だけ、仲は深まる。
しかし、相手にも悪いところがあったと言う不満の火種は消えることなくくすぶっており、すぐにまた火がついてしまう。きっとまた二人は、曖昧な解決をするために喧嘩をするのだろう。
「また今度、四人で遊ぼうな」
ポンポンと頭を撫でられ、レナは翔真を見上げた。慈愛に満ちた眼差しは、母親が子供を見つめる時のそれに似ていた。
おそらく翔真は勘違いをしている。
仲の良かった幼馴染三人組から一人残され、寂しがっていると考えているのだ。
些細な表情の変化を見逃さず、気持ちを思いやることができる翔真だからこそ、レナの横顔からそう推測したのだろう。
翔真もレナの嘘を信じている。
大夢に対して、大切な幼馴染と言う以上の感情はないのだと言ったレナの言葉を、素直に信じている。
(私は、嘘が上手いから……)
小さく唇を尖らせ、不満げな顔を作る。この時重要なのは、あからさまな不機嫌顔を作らないことだ。レナは感情を表情にあまり出さないタイプだから、思わず出てしまったほんの少しの不満程度で良い。
「そうだね……」
「今週の土日、唯子ちゃんと大夢が暇なら、どっか行こうか?」
翔真が苦笑しながらレナの頭を撫でる。
高台の図書館に、隣町の遊園地、電車で一時間ほどのところにある水族館。次々と出てくる案に、レナは機嫌が良くなったフリをした。
「あとで唯子たちに週末の予定をきいてみるよ」
「今週がダメなら、来週でも良いから」
楽しみだなと、胸の前で手を合わせて微笑む。
幼馴染でいることを選んだ今、校庭を並んで歩く二人の間に割って入って、三人で仲良く帰ることもできる。セピアの景色に、レナがいても違和感はない。
「駅前に新しくできたイタリアンに行くのも良いかも。唯子も大夢も、パスタ好きだから」
唯子がホワイトデーのお返しに指定したあのケーキ屋は、去年閉店してしまった。クッキーもケーキも美味しかったけれども、値段が高かったのだ。
美味しさとお金を天秤にかけ、お金を取った人が多かった。ただ、それだけだ。
人は時に、選ばないといけない。どちらも欲しくても、どちらかしか手に入らないことがたくさんあるのだ。
(でも私は、どちらも手に入れた。素敵な彼氏も、仲の良い二人の幼馴染も)
レナの脳裏に、遠い日の思い出がよみがえる。
まだ幼稚園に通っていた頃、レナはお絵描きが好きだった。一度集中してしまうと、周りが見えなくなって何時間でも描いていた。
あの日は、花壇のヒマワリを描いていた。大きく開いた黄色い花と、雲一つない青空の対比が綺麗で、レナは炎天下の中夢中になって色鉛筆を動かしていた。
「レナ、麦茶っ!」
砂場で遊んでいた唯子が声を上げ、レナは手を止めた。この頃の惟子は、近々弟が生まれてお姉さんになるのだと張り切っていて、友達を相手に姉の予行演習をしていた。特にレナに対しては過保護だった。
いつの間にか隣に置いてあった水筒に驚き、慌てて顔を上げる。視界が暗いことに気が付いた。青い空が白い日傘で切り取られていた。
日傘を持って立つ大夢と目が合う。その頬は、リンゴのように赤い。
「ひろ君?」
「えっと……日傘、先生に借りたんだ。レナちゃんが熱中、症……に、なるかもしれないから」
新しく覚えたばかりの言葉なのか、たどたどしく発音された熱中症は、間延びして別の意味に聞こえた。
「ひろ君ずっと見てたの? 遊びに行きたかったよね。ごめんね?」
「うぅん、大丈夫。ぼくね、お絵かき苦手なんだ。だから、レナちゃんがお絵かきしてるの見てるの好きなんだ」
大夢が照れくさそうにはにかむ。真っ白な歯、細められた目、優しい眼差し。ふっと、息が詰まった。心臓が早鐘を打ち、キューっと掴まれたような痛みを感じる。
あの時の光景は、火照った顔の熱さすら鮮明に思い出せる。
(でもきっとあれは、熱中症になりかけてただけ)
自分を納得させるべく、嘘をつく。あの時の感情は、淡い初恋などではないと。
ギュっと目をつぶれば、瞼の裏に淡い桜の花びらが映った。去年の春、中学に入学してすぐの日のことだ。
「レナ……一緒に美術部に入らないか?」
惟子のいない帰り道だった。大夢はひどく真剣な表情でそう言うと、立ち止まった。
通学路の桜並木は満開で、ハラハラと花びらが散っていた。足元には桜の絨毯が敷かれており、車道を車が通過するたびに巻き上げられては踊っていた。
大夢の目は、バレンタインのチョコを作ろうと誘ってきた惟子の目と同じだった。
誰かに恋をしているときの目。その相手が誰なのか、レナは分かっていて顔をそらした。
「大夢、絵描くの苦手でしょ?」
「これから得意になるよ」
あの時、大夢と一緒に美術部に入っていたら、どんな今があったのだろうか。
少なくとも、二番目に好きな人と付き合ってはいなかったかもしれない。
でもレナは、幼馴染の形を壊したくなかった。
「そう、頑張ってね」
「レナは入部しないのか?」
「うん、ごめんね。……私もう、絵を描くの飽きちゃったから」
精一杯の笑顔で、嘘をつく。大夢には悟られるかもしれないと、頭の隅では思いながらも。
大夢が何かを言う。けれどそれは、トラックが通過した音でかき消された。
ずっと、待ってるから。
かすかに聞こえた声を、聞こえなかったことにして。
今の関係を変えないために、今日も私たちは、嘘をつく。
彼氏の西沖翔真はバレー部のエースで、とても背が高い。そのうえ勉強ができて性格も穏やか、さらには顔立ちも綺麗。誰もが羨む完璧な彼氏だった。
一方レナの一番好きな人は美術部の幽霊部員で、背はレナとあまり変わらない。勉強は中の下で、苦手な科目では赤点を取ることさえあった。性格は気まぐれでだらしなく、顔立ちも普通。どうひいき目に見たって、翔真の方が格好良い。
けれどレナは、子供のころからずっと小谷大夢のことが好きだった。
「レナ、今日の帰りはどうするの? 翔真君と一緒?」
いつの間にかホームルームが終わっていたらしい。後ろからポンと肩を叩かれて、レナは弾かれたように顔を上げた。
「もしかして、ボーっとしてた? 寝不足?」
「あー……うん、そう。ちょっと昨日、英語の予習に手間取って」
ふぅんと金崎唯子が小さく呟くが、細められた目はレナの言葉を疑っているようだった。
しばらく無言でレナを見ていた唯子だったが、諦めたようにヒラリと手を振った。黙秘モードに入ったレナは、何があっても絶対に言わないと経験上知っていたのだ。
「まぁ、良いわ。それで、今日の放課後の予定は?」
「特に何もないと思うけど、唯子は大夢と予定あるでしょ?」
確か今日は、図書館で勉強をすると言っていたはずだ。
唯子の口がヘの字に曲がり、視線が左斜め下に落ちる。軽く膨らんだ頬はすぐにしぼみ、また膨らむ。気に入らないことがあると、思い切り不貞腐れた顔をする。唯子は昔からそうだった。
「また喧嘩したの?」
「喧嘩とかじゃなくてぇ」
語尾が間延びして、最後は吐き捨てるようにプツリと消える。これも、唯子の機嫌が悪い時によくする口調だった。
「どうせまた、唯子がわがまま言ったんでしょう?」
「そんなんじゃないよぅ」
「嘘だね。自分が悪いってわかってるけど認められない時の口調してるもん」
幼馴染なんだから、お見通しだよ。そんな気持ちを込めて肩をすくめれば、唯子は観念したように机に突っ伏して他愛もない恋人同士の喧嘩を愚痴り始めた。
唯子は、大夢と付き合っているのだ。
唯子は大夢のことが好きなのだと気付いたのは、小学校も折り返しの時だった。
低学年よりは学校に慣れて、けれど高学年のお兄さんお姉さんはまだどこか怖くて。校舎を駆け回る自由とともに、責任と言う名の不自由さを感じ始め、社会と言うものが分かってきた、そんな微妙な時期だった。
いつも男子と張り合い、ガキ大将のように暴れまわっていた唯子が、バレンタインのチョコを作りたいと言ってきたのだ。
「レナ、いつも作ってるでしょ? 今年は、あたしも一緒に作っても良い?」
「もちろん、良いけど……誰にあげるの?」
唯子が、少しだけ伸びた前髪を指先でつまむ。レナの記憶の中の唯子は、いつもショートカットだった。
「えっと、お父さんとお兄ちゃんと、お母さんにもあげる。あと、結人にも」
結人は唯子の弟だ。たしか、今年幼稚園生になったばかりのはずだ。
名前を上げるたびに指が折りたたまれ、今は小指だけがピンと空をさしている。
「それと、レナにもあげる」
無邪気な笑顔で、最後の指がたたまれる。しかしすぐに、再び小指が空をさした。
「あとは……大夢、かな。ほ、ほら、毎年チョコ欲しいチョコ欲しいって言ってるのに、レナ以外誰もあげてないの可哀想だし。レナは幼馴染だからあげてるだけなんだろうけど、大夢が勘違いしたら……ね。レナは可愛いから……。だから、今年はあたしもあげて、ホワイトデーに三倍返ししてもらおうかなって!」
駅前にできたばかりのケーキ屋のクッキーが美味しそうだけれど、高くてなかなか手が出ないからと、言い訳のようにつぶやいている。視線は落ち着きなく左右に揺れており、もじもじと手足が動いている。
やけに甲高い声で早口でまくし立てる唯子の顔は、トマトのように真っ赤だった。
「唯子……」
大夢が好きなの? そう言いかけて、つばを飲み込む。
唯子がどんな切っ掛けで、子分のように扱っていた大夢を好きになったのかは分からない。しかし、唯子の目は恋をしていた。
そう、絶対に勘違いなどではない。唯子は本気で好きなのだ。だって唯子の目は、レナの目と同じだから。
幼稚園の頃からずっと大夢のことを見てきたレナと、今の唯子は同じ顔をしているのだから。
(私、大夢のことが好きなの)
心の中で告白をする。
もしも口に出して言ったら、唯子はどんな顔をするだろう?
きっと彼女は、うろたえる。レナが本気で言っているのかどうか顔色をうかがって、嘘を言っていないと理解したら、不自然なくらい明るく笑って「じゃあ、チョコあげるのやめようかな」と言うだろう。
そして彼女は、レナと大夢から距離を取る。
正直者の唯子は自分の気持ちに嘘をつくことができず、一緒にいる辛さに耐え切れなくなり、そっと幼馴染の輪を抜けるだろう。
物心つく前からずっと一緒だったのに。三人仲良しの幼馴染だったのに。
「……唯子、お菓子作りできるんだっけ?」
「いや、出来ないからレナに教えてもらおうとしてるんだけど」
「もしかして、湯せんから教えないといけない?」
「湯せん? チョコレート作るのに、お湯は必要ないでしょ? だって溶けちゃうし」
レナは大げさにため息をつき、手の施しようがありませんと言うように両手を上げて頭を振った。お湯なんて使ったら溶けてなくなっちゃうと言い張る唯子の顔を注意深く観察する。
どうやら彼女は、レナがしばし沈黙したことを不審に思ってはいないようだった。
どんなチョコを作りたいのか話し合いながら、レナは頭の中で冷静に今の状況を分析していた。
大夢は唯子のことが好きなはずだ。でもそれは、幼馴染としての好きであって、特別な好きではない。いつか特別へと変わる可能性を秘めた好きだ。
「形はどうしようかな。星も良いし、動物も良いな。レナの家、ウサギの型はあるんだっけ?」
「あるよ。それに、ハートも」
唯子の顔が赤くなる。レナは足元に視線を落とすと、目についた小石を蹴った。
レナは嘘をつくのが得意だった。自分を騙すのも、感情から目をそらすのも。
(小さいころから一番近くにいたから、好きだと思ってるだけなのかもしれない)
レナが今大夢に抱いている気持ちは、ただの錯覚かもしれない。
(幼馴染だから大夢を好きになっただけで、大夢だから好きになったわけじゃない)
仲良しな三人組の幼馴染という形を守るために、屁理屈をこねて大夢への気持ちに蓋をする。
幼馴染の好きと、恋愛の好きが混ざってしまっただけ。大夢でなければいけない理由はない。
何度も何度も自分に嘘をつく。
レナの嘘は、誰でも騙せてしまう。たとえ相手が自分自身だとしても、嘘をつき続ければ本当になってしまうのだと、また一つ嘘を重ねる。
中学に入り、レナは翔真に告白され、付き合うことになった。
だって、翔真は完璧だから。非の打ちどころのない、素敵な男の子だから。
(誰でも好きになってしまうから。私も、好きになってしまったから)
嘘をつく。でも、翔真に対する気持ちは嘘とは言い切れなかった。
一緒にいれば安心するし、笑顔を向けられると胸が高鳴る。指先が触れただけでも、ジワリと幸せが全身に広がる。
レナは翔真のことが好きだった。その気持ちに、嘘はなかった。でも同時に、自分につき続けた嘘が心の奥底で溜まり、どうにもできない黒い感情となって消えることなく漂っていた。
唯子が大夢に告白したのは、レナが翔真と付き合い始めて数か月が経った後だった。
唯子の長い愚痴を聞き終え、レナは裁判官のように厳かに判決を言い渡した。
「唯子が悪い」
「うぅぅ……そうやっていつもレナは大夢の味方をするぅ」
「別に大夢の味方はしてないよ。総合的に考えて、唯子が悪いって結論に至っただけ」
唸り声をあげる唯子の髪が、肩から滑り落ちる。小学校の時はあれほどショートにこだわっていたのに、今ではレナと同じくらい髪が長い。
昇降口の掃除に行っていた大夢が帰ってきたのが見え、唯子の腕をつつく。
「ほら、早いところ仲直りしてきなよ」
「うぅ……そ、そうだ。今日もレナ、翔真君と一緒に帰るんだよね? 久々に翔真君に挨拶しようかな!」
顔を上げた唯子が、翔真の名前を強調しながらそんなことを言う。教室の隅で帰り支度をしていた大夢の肩が震えたのが、視界の端にうつった。
仏頂面の大夢が大股でこちらに近づいてくる。
唯子は翔真を使って大夢の気を引きたいのだろうが、変に拗れてしまう可能性がある。
「翔真、今日は音楽室の掃除があるって言ってたよ。遅くなるだろうから、先に帰りなよ」
大夢にアイコンタクトを投げるが、翔真が来るほうが早かった。どうやら音楽室の掃除は、レナが考えるよりもずっと早く終わったらしい。
唯子が立ち上がり、翔真の元へ走っていく。
「久しぶりだね翔真君。今日も相変わらずイケメンだね!」
いつもよりオクターブ高い声で可愛らしく小首を傾げる唯子と、不機嫌さを隠しもせずに睨みつける大夢を交互に見て、翔真は微笑んだ。
同い年ながらも、翔真はどこか達観している部分があった。人の感情を読み取るのが上手く、理解力も高かった。
翔真はすぐに、唯子の子供っぽい振る舞いの理由と、大夢の幼い支配欲による嫉妬心に気づいたようだった。
「惟子ちゃんも大夢も、久しぶり」
「ねえねえ翔真君、今度暇なときに、ダブルデートしようよ! 大夢ももちろん良いよね?」
「……俺は別に、翔真たちさえ良ければ良いよ。久しぶりにレナとも遊びたいし」
今度は大夢が唯子を試す。
何度も一緒に遊び、なんならお風呂すら一緒に入っていたような幼馴染に対して、今さら嫉妬することはないだろう。そう思っていたレナだったが、唯子の口はヘの字に曲がっていた。
視線が左斜め下に落ち、頬が収縮を繰り返す。気に入らないことがあるときに、唯子はいつもああやって不満を顔に出す。
(唯子は私にも嫉妬するんだ……)
惟子はレナが長年つき続けた「大夢に特別な感情は抱いていない」と言う嘘を信じているはずなのに。
校庭を並んで歩く大夢と唯子の後ろ姿を、教室の窓から見下ろす。
傾き始めた陽が世界をオレンジ色に染め、二人の姿をセピアに色づけていた。
視線に気づいたのか二人がそろって振り返り、大きく手を振る。レナは小さく手を振り返すと、仲良く繋がれた手をジっと見つめた。
二人は、いつもそうだった。喧嘩とまでは言い切れない小さな諍いは、解決をしないまま何となく落ち着いてしまう。どちらが悪いのか分からないまま終わるため、どちらも自分が悪かったかもしれないと言う負い目を感じ、相手に譲歩する。双方が譲歩した分だけ、仲は深まる。
しかし、相手にも悪いところがあったと言う不満の火種は消えることなくくすぶっており、すぐにまた火がついてしまう。きっとまた二人は、曖昧な解決をするために喧嘩をするのだろう。
「また今度、四人で遊ぼうな」
ポンポンと頭を撫でられ、レナは翔真を見上げた。慈愛に満ちた眼差しは、母親が子供を見つめる時のそれに似ていた。
おそらく翔真は勘違いをしている。
仲の良かった幼馴染三人組から一人残され、寂しがっていると考えているのだ。
些細な表情の変化を見逃さず、気持ちを思いやることができる翔真だからこそ、レナの横顔からそう推測したのだろう。
翔真もレナの嘘を信じている。
大夢に対して、大切な幼馴染と言う以上の感情はないのだと言ったレナの言葉を、素直に信じている。
(私は、嘘が上手いから……)
小さく唇を尖らせ、不満げな顔を作る。この時重要なのは、あからさまな不機嫌顔を作らないことだ。レナは感情を表情にあまり出さないタイプだから、思わず出てしまったほんの少しの不満程度で良い。
「そうだね……」
「今週の土日、唯子ちゃんと大夢が暇なら、どっか行こうか?」
翔真が苦笑しながらレナの頭を撫でる。
高台の図書館に、隣町の遊園地、電車で一時間ほどのところにある水族館。次々と出てくる案に、レナは機嫌が良くなったフリをした。
「あとで唯子たちに週末の予定をきいてみるよ」
「今週がダメなら、来週でも良いから」
楽しみだなと、胸の前で手を合わせて微笑む。
幼馴染でいることを選んだ今、校庭を並んで歩く二人の間に割って入って、三人で仲良く帰ることもできる。セピアの景色に、レナがいても違和感はない。
「駅前に新しくできたイタリアンに行くのも良いかも。唯子も大夢も、パスタ好きだから」
唯子がホワイトデーのお返しに指定したあのケーキ屋は、去年閉店してしまった。クッキーもケーキも美味しかったけれども、値段が高かったのだ。
美味しさとお金を天秤にかけ、お金を取った人が多かった。ただ、それだけだ。
人は時に、選ばないといけない。どちらも欲しくても、どちらかしか手に入らないことがたくさんあるのだ。
(でも私は、どちらも手に入れた。素敵な彼氏も、仲の良い二人の幼馴染も)
レナの脳裏に、遠い日の思い出がよみがえる。
まだ幼稚園に通っていた頃、レナはお絵描きが好きだった。一度集中してしまうと、周りが見えなくなって何時間でも描いていた。
あの日は、花壇のヒマワリを描いていた。大きく開いた黄色い花と、雲一つない青空の対比が綺麗で、レナは炎天下の中夢中になって色鉛筆を動かしていた。
「レナ、麦茶っ!」
砂場で遊んでいた唯子が声を上げ、レナは手を止めた。この頃の惟子は、近々弟が生まれてお姉さんになるのだと張り切っていて、友達を相手に姉の予行演習をしていた。特にレナに対しては過保護だった。
いつの間にか隣に置いてあった水筒に驚き、慌てて顔を上げる。視界が暗いことに気が付いた。青い空が白い日傘で切り取られていた。
日傘を持って立つ大夢と目が合う。その頬は、リンゴのように赤い。
「ひろ君?」
「えっと……日傘、先生に借りたんだ。レナちゃんが熱中、症……に、なるかもしれないから」
新しく覚えたばかりの言葉なのか、たどたどしく発音された熱中症は、間延びして別の意味に聞こえた。
「ひろ君ずっと見てたの? 遊びに行きたかったよね。ごめんね?」
「うぅん、大丈夫。ぼくね、お絵かき苦手なんだ。だから、レナちゃんがお絵かきしてるの見てるの好きなんだ」
大夢が照れくさそうにはにかむ。真っ白な歯、細められた目、優しい眼差し。ふっと、息が詰まった。心臓が早鐘を打ち、キューっと掴まれたような痛みを感じる。
あの時の光景は、火照った顔の熱さすら鮮明に思い出せる。
(でもきっとあれは、熱中症になりかけてただけ)
自分を納得させるべく、嘘をつく。あの時の感情は、淡い初恋などではないと。
ギュっと目をつぶれば、瞼の裏に淡い桜の花びらが映った。去年の春、中学に入学してすぐの日のことだ。
「レナ……一緒に美術部に入らないか?」
惟子のいない帰り道だった。大夢はひどく真剣な表情でそう言うと、立ち止まった。
通学路の桜並木は満開で、ハラハラと花びらが散っていた。足元には桜の絨毯が敷かれており、車道を車が通過するたびに巻き上げられては踊っていた。
大夢の目は、バレンタインのチョコを作ろうと誘ってきた惟子の目と同じだった。
誰かに恋をしているときの目。その相手が誰なのか、レナは分かっていて顔をそらした。
「大夢、絵描くの苦手でしょ?」
「これから得意になるよ」
あの時、大夢と一緒に美術部に入っていたら、どんな今があったのだろうか。
少なくとも、二番目に好きな人と付き合ってはいなかったかもしれない。
でもレナは、幼馴染の形を壊したくなかった。
「そう、頑張ってね」
「レナは入部しないのか?」
「うん、ごめんね。……私もう、絵を描くの飽きちゃったから」
精一杯の笑顔で、嘘をつく。大夢には悟られるかもしれないと、頭の隅では思いながらも。
大夢が何かを言う。けれどそれは、トラックが通過した音でかき消された。
ずっと、待ってるから。
かすかに聞こえた声を、聞こえなかったことにして。
今の関係を変えないために、今日も私たちは、嘘をつく。