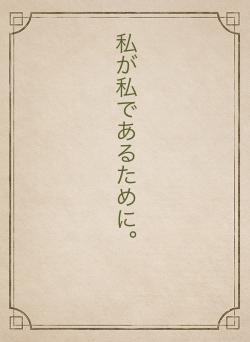目が覚めると一番に視界に飛び込んできたのは彼女の笑顔だった。
「……今何時?」
「もう六時。先生、先に職員室戻ったよ、那月くん描いてる途中で寝落ちしちゃったの覚えてる?倒れたかと思っちゃったけど、寝息聞こえてさ。いやぁ、あれは笑ったなぁ」
僕は寝落ちしたまま一時間、ぐっすり寝ていたらしく、もう下校時間だった。
「じゃあ、一緒に帰ろう!暗くなる前に」
「え、あ、…うん」
昨日、夜遅くまで新作の制作をしていたからだろうか。霧がかかったみたいにぼやぼやする頭を起こして、椅子から立ち上がった時、少しふらついて床に倒れ込んだ。
「な、那月くん!?大丈夫?立てる?」
僕は彼女の肩を借りて立ち上がった。
「……ごめん」
「ん?なんで那月くん謝るの?」
「…だって、迷惑、かけてるし」
そう言うと、彼女は優しく微笑んだ。その瞳に夕陽が反射して、ガラス玉のように煌めく。
「全然、迷惑なんて思ってないよ。友達でしょ?」
「……あ、ありがとう」
その後、大丈夫だと言ったけど、彼女は僕を家まで送ってくれた。
「……今何時?」
「もう六時。先生、先に職員室戻ったよ、那月くん描いてる途中で寝落ちしちゃったの覚えてる?倒れたかと思っちゃったけど、寝息聞こえてさ。いやぁ、あれは笑ったなぁ」
僕は寝落ちしたまま一時間、ぐっすり寝ていたらしく、もう下校時間だった。
「じゃあ、一緒に帰ろう!暗くなる前に」
「え、あ、…うん」
昨日、夜遅くまで新作の制作をしていたからだろうか。霧がかかったみたいにぼやぼやする頭を起こして、椅子から立ち上がった時、少しふらついて床に倒れ込んだ。
「な、那月くん!?大丈夫?立てる?」
僕は彼女の肩を借りて立ち上がった。
「……ごめん」
「ん?なんで那月くん謝るの?」
「…だって、迷惑、かけてるし」
そう言うと、彼女は優しく微笑んだ。その瞳に夕陽が反射して、ガラス玉のように煌めく。
「全然、迷惑なんて思ってないよ。友達でしょ?」
「……あ、ありがとう」
その後、大丈夫だと言ったけど、彼女は僕を家まで送ってくれた。