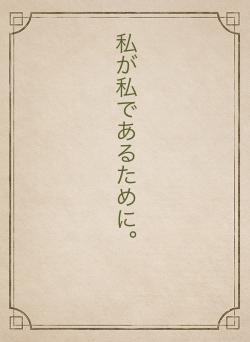話をひと通り聞いたあと、彼女はもう一度僕に謝罪した。
「ごめん……。私、那月くんのこと、何も知らなくて、あんなこと言っちゃった。無責任だった」
けど、と彼女は続く言葉を紡ぐ。
「……いつもの風景画を描いてる那月くんを見ると、どこか苦しそうに見えた。何かにとらわれてるみたいな、そんな感じ。私にできることがあるならなんでもやりたくて」
「……」
「だって___」
___私と君は補色(ともだち)でしょ?
彼女が放ったその言葉は、僕の心に大きく響いて、刺さっていた何かをとってくれたみたいだった。
「……ありがとう」
何十秒経っただろうか。僕がうっすらと滲む視界を手の甲で拭い、やっと彼女にそう言うと彼女は最後に見た時と変わらない、底抜けに明るく誰よりも尊い笑顔で
「どういたしまして」
と言った。