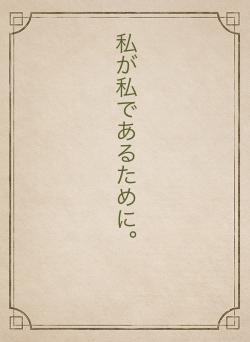彼女の目に、僕はどういう風に映っただろうか。
僕は気付くと彼女を一人、中庭に残して買ったものも持たずにあてもなく走り出していた。
「な、那月くん…!」
と呼び止める彼女の声は聞こえなかったことにして。
午後からの授業は、正直さっぱり頭に入らなかった。というか聞く気すら失せていた。
僕は窓の外を見る。葉の割合が六、七割となった葉桜がふと目に留まる。それが余計に彼女のことを思い出させた。
僕は目を瞑る。そうして彼女のことを考えているうちに意識は奥深くに沈んでいった____。
『那月、絵は好きか?』
いつだったか、笑顔で僕にそう問いかけ、頷くとさらに笑い、一緒に絵を描いてくれた父さんのことを思い出した。
父さんは画家だった。僕はそんな父さんに憧れ、幼い頃から真似をするように絵を描いていた記憶がある。
まだ幼い僕は何にもとらわれず、自由に線を描く。あの時の絵を描く目的は、完成したものを見せた時の母さんと父さんの笑顔が見たかったからだ、確か。
ただ、あの日、僕が家族で行った旅行先の風景画を世界的なコンクールに出し、金賞をとってからだ。少しずつ、家族の形が崩れていったのは。
僕は気付くと彼女を一人、中庭に残して買ったものも持たずにあてもなく走り出していた。
「な、那月くん…!」
と呼び止める彼女の声は聞こえなかったことにして。
午後からの授業は、正直さっぱり頭に入らなかった。というか聞く気すら失せていた。
僕は窓の外を見る。葉の割合が六、七割となった葉桜がふと目に留まる。それが余計に彼女のことを思い出させた。
僕は目を瞑る。そうして彼女のことを考えているうちに意識は奥深くに沈んでいった____。
『那月、絵は好きか?』
いつだったか、笑顔で僕にそう問いかけ、頷くとさらに笑い、一緒に絵を描いてくれた父さんのことを思い出した。
父さんは画家だった。僕はそんな父さんに憧れ、幼い頃から真似をするように絵を描いていた記憶がある。
まだ幼い僕は何にもとらわれず、自由に線を描く。あの時の絵を描く目的は、完成したものを見せた時の母さんと父さんの笑顔が見たかったからだ、確か。
ただ、あの日、僕が家族で行った旅行先の風景画を世界的なコンクールに出し、金賞をとってからだ。少しずつ、家族の形が崩れていったのは。