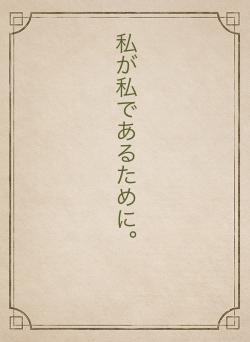「君のことが、好きです―—」
彼女が発したその言葉だけが、病室に響いた。
「―—え」
「あ、…ごめんね。今日会ったばっかりなのに何言ってるんだろう。あはは…。それに、もういつ死ぬか分かんないような人にこんなこと言われてもね…」
そう言う瑞季の目にはうっすらと涙が滲んでいた。
「瑞季……」
「…死にたく、ない。もっともっと生きて、巡くんとたくさん話したかった。まだまだやりたいことだって、あったのに」
シーツに染みを作って涙を零す彼女を、気づくと俺は腕の中に閉じ込めていた。
「巡、くん…?」
「絶対、また会いに来るから。それまで、絶対待ってて」
守れるかもわからない儚くて脆い約束なのに、俺は絶対、と言わずにはいられなかった。
「……うん」
俺は瑞季の耳元で一言呟く。「好きだよ」と。
それから三日後、瑞季が十七歳で生を終えたという知らせが届いた。それは柔らかな彼女の字ではなく、プリントされた無機質な字だった。
「……瑞季」
俺は部屋に閉じこもって、彼女からもらった手紙を両手に抱きしめ、涙が枯れるくらい泣いた。
彼女が発したその言葉だけが、病室に響いた。
「―—え」
「あ、…ごめんね。今日会ったばっかりなのに何言ってるんだろう。あはは…。それに、もういつ死ぬか分かんないような人にこんなこと言われてもね…」
そう言う瑞季の目にはうっすらと涙が滲んでいた。
「瑞季……」
「…死にたく、ない。もっともっと生きて、巡くんとたくさん話したかった。まだまだやりたいことだって、あったのに」
シーツに染みを作って涙を零す彼女を、気づくと俺は腕の中に閉じ込めていた。
「巡、くん…?」
「絶対、また会いに来るから。それまで、絶対待ってて」
守れるかもわからない儚くて脆い約束なのに、俺は絶対、と言わずにはいられなかった。
「……うん」
俺は瑞季の耳元で一言呟く。「好きだよ」と。
それから三日後、瑞季が十七歳で生を終えたという知らせが届いた。それは柔らかな彼女の字ではなく、プリントされた無機質な字だった。
「……瑞季」
俺は部屋に閉じこもって、彼女からもらった手紙を両手に抱きしめ、涙が枯れるくらい泣いた。