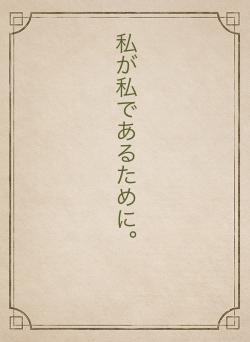俺は書き終わった手紙を封筒に入れてまた家を出た。いつものルートで郵便局に行き、切手を買ってそれを貼り、ポストの中に入れる。
瑞季はさっき手紙にも書いてあったとおり、あまり体調が芳しくないようだった。手紙でも読んで少しでも喜んでくれればいいけど。……って何を考えているのだろうか。
今に始まったことではないが、やっぱりなんだか瑞季のことを考えると自然と頬が緩むというかなんというか……。俺は”周”じゃないから会えないって分かってるけど、もしも会えるんなら…って思ってしまう。瑞季と文字ではなく、言葉で話せるのなら。瑞季の声を聞けるのなら。瑞季の姿を一目見られるのなら。
―—会いたい。
「えー、今日の授業では、三角関数の応用を……」
窓を眺めていると、そんな声が教室の檀上からぼんやりと聞こえた。わりと好きなはずの数学の授業も全然頭に入ってこない。
俺の頭の中にあるのは瑞季のことだった。会いたい。けど、瑞季が文通してるのはやっぱり、俺自身でもなくて。なんていうんだろう。俺なのは俺なんだけど、”周”のフリをしてる俺っていうか。
「えー、じゃあこの問題を…千門」
「……」
「千門ー?…千門!」
「えっ、あ、はい!…ってなんでしたっけ?」
ぼーっとしていたせいで何をしているのかさっぱりな俺を見て、数学教師は小さくため息を吐く。
俺はなんとかごまかした。
瑞季はさっき手紙にも書いてあったとおり、あまり体調が芳しくないようだった。手紙でも読んで少しでも喜んでくれればいいけど。……って何を考えているのだろうか。
今に始まったことではないが、やっぱりなんだか瑞季のことを考えると自然と頬が緩むというかなんというか……。俺は”周”じゃないから会えないって分かってるけど、もしも会えるんなら…って思ってしまう。瑞季と文字ではなく、言葉で話せるのなら。瑞季の声を聞けるのなら。瑞季の姿を一目見られるのなら。
―—会いたい。
「えー、今日の授業では、三角関数の応用を……」
窓を眺めていると、そんな声が教室の檀上からぼんやりと聞こえた。わりと好きなはずの数学の授業も全然頭に入ってこない。
俺の頭の中にあるのは瑞季のことだった。会いたい。けど、瑞季が文通してるのはやっぱり、俺自身でもなくて。なんていうんだろう。俺なのは俺なんだけど、”周”のフリをしてる俺っていうか。
「えー、じゃあこの問題を…千門」
「……」
「千門ー?…千門!」
「えっ、あ、はい!…ってなんでしたっけ?」
ぼーっとしていたせいで何をしているのかさっぱりな俺を見て、数学教師は小さくため息を吐く。
俺はなんとかごまかした。