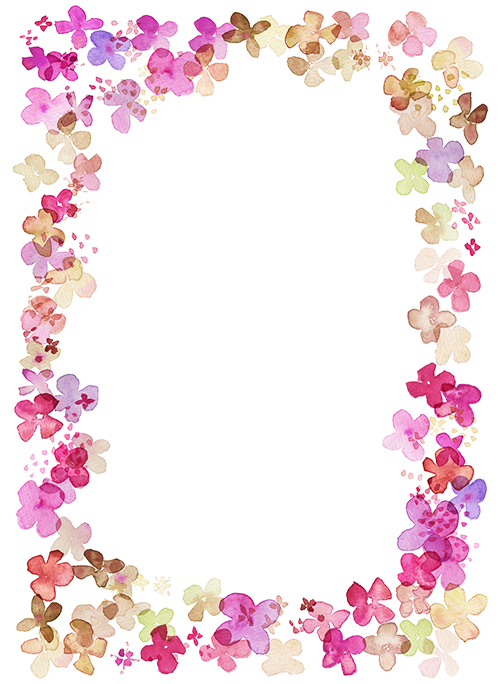初めてコーヒーと夕音に出会ったのは、私が小学三年生のとき。
その頃私はある事情から学校に通わず、家の中でピアノばかり弾いていた。家族が心配そうに見守るまなざしの中、他にどうしたらいいのかわからなかった。
「律、グランドピアノを弾きに行かない?」
暑さが静まる日暮れ時のことだった。兄の響生が大学から帰って来るなり私を外出に誘った。
私はうつむいて言う。
「……やだ。怖い」
「ここから五分くらいの、兄ちゃんと仲のいい友達の家なんだ。お父さんが喫茶店をやってるけど、今は休憩時間でお客さんは誰もいないよ」
響生は私の手を取って、その手を持ち上げながら言う。
「兄ちゃんが手をつないでて、離さないから。帰りたくなったら、すぐ連れて帰る」
ね、行こうよ。響生は明るく笑った。
響生は我の強いところがあって、年もずいぶん上だから苦手な時期もあった。
でも私が家に閉じこもってからわかった。響生は私が気づかなかっただけで、ずっと私を守ってくれていた。
「うん。手、つないでて」
私が手を握り返すと、響生は笑顔のまま少しだけ目を伏せて、うなずいた。
久しぶりの外は日差しがまぶしくて、空気の匂いも夏と秋がまじりあっていた。最後に家の外に出た頃は、まだ肌寒さを感じる淡い春の空気だった。
私は響生の背中に隠れるようにしながら歩いた。ひぐらしの声が辺りに立ち込めていた。
響生が立ち止まったのは、彼の言う通り家から五分くらいのところにある喫茶店だった。レンガの壁を緑のカーテンが覆い、レトロな空気の漂う、褐色の建物。「休憩中」の札がかかっている。
「こんにちは」
カランコロンと鈴を鳴らして、響生は店の中に入る。
そのとき、ピアノの音が聞こえた。知らない曲のはずなのに、懐かしい旋律だった。
同時に立ち込める不思議な香り。ちょっと苦そうで、大人っぽい匂いだった。
「友達が弾いてるんだよ」
足を止めた私を安心させるように、響生は私を振り向いて手を握りなおすと、手を引いて歩いていく。
お店には確かにお客さんはいなかった。奥に向かうと、グランドピアノの前で誰かが座っているのが見えた。
夕陽が窓から差し込んで、その人の横顔を映し出す。
はじめはお兄さんだと思った。長い黒のエプロンを巻き、白いシャツに黒いベスト。深い紅色のタイを締めて、大人っぽかった。
けれど服装に反して短い黒髪は柔らかそうで、全体を形作っている輪郭が繊細だったから。曲が終わった頃には、とても綺麗な女の子だとただ見とれていた。
「邪魔してごめん。夕音」
ユネ。まるで西洋人形のような名前の響きも、彼女の浮世離れした雰囲気にはぴったりに思えた。
「別に。あまり気乗りしない曲だったの」
夕音という響生の友達は、そっけなく言って椅子から立ち上がる。
そのとき、彼女は私の存在に気づいたようだった。少しだけ首を傾げて、小麦色の瞳で私を見やる。
「その子は妹さん?」
気まぐれな猫がのぞきこむような、そんな仕草だった。私はとっさに顔を伏せて、響生の手をぎゅっと握りしめた。
「うん。グランドピアノを弾かせてやってほしいんだ」
「いいけど、学校の音楽室にだってグランドピアノはあるでしょう?」
響生はそれ以上説明しなかった。でも一拍だけ、二人の間に言葉ではないやりとりがあったようだった。
夕音は滑るようにピアノの横に動くと、椅子の位置を上げてくれる。脇に置いてあった楽譜の束を持ち上げると、それをグランドピアノの上に広げた。
「律ちゃん。何が弾きたい?」
響生はほほえんで、行っておいでと目で私に合図する。
自然に響生の手を離すことができたのは、響生と夕音の間にあった温かい空気に背中を押されたからだった。
「知っている曲はある?」
私がおずおずとピアノに近づくと、夕音は楽譜をめくって見せてくれる。響生も私の頭上からのぞきこんで言った。
「ショパンの夜想曲。これ、律が好きな曲だな」
「大人っぽい曲が好きね」
夕音は思わずといったように笑う。一見すると冷たそうな容姿だったけど、その笑い方はかわいらしくて私もちょっと笑い返した。
私はいくつか夕音から楽譜を借りて、グランドピアノを弾き始める。もう響生の手を握っていなくても、他人と同じ部屋にいられる気がした。
夕音と響生は私から数歩離れたカウンターで、私を見やりながらぽつぽつと話をしていた。
「時々でいいから、律をここに迎えてやってくれないか」
響生が言っていた。
「俺たち家族は、律が家にこもりきりでも構わない。でもみんな日中は仕事や学校に出ていて、律は家で一人なんだ。寂しいんじゃないかと思って」
切れ端のように響生の声が耳に入って来る。
「いいお兄さんね」
夕音は苦笑して付け加える。
「いい彼氏ではないけどね」
「ごめん」
謝った響生に、夕音はくすくすと笑った。
「そこが響生のかわいいところよ」
夕音は立ち上がってカウンターの中に入っていく。そこでカップと何かの道具を出して、料理らしいことを始めた。
「律ちゃんも来てごらん」
気が付けば私はピアノを弾く手を止めて、じっと夕音がすることをみつめていた。
夕音に呼ばれて、私は店内を横切る。響生に手伝ってもらって少し高いカウンターの椅子によじ登った。
夕音はお湯を沸かす傍らで茶褐色の豆を挽いて、さっきの変わった道具に注ぐ。
「これはなあに?」
「コーヒーよ」
それはこの喫茶店中に満ちている匂いと、同じ匂いがした。苦そうで、けれど気になって仕方がない香りだった。
コポコポと鳴るお湯の音、じわりと盛り上がる茶褐色の渦。小学三年生の私には不思議の世界そのもので、目が離せない。
「コーヒー……」
「飲んでみる?」
夕音はカップにその飲み物を注いで私に差し出す。私はためらいながらカップを両手で包んだ。
一口飲んで、私はあまりの苦さに絶句する。せっかく作ってもらったものでもそれ以上一口も飲めなくて、私はカップをカウンターに置いた。
「ごめんなさい」
「いいのよ。私も初めてのときは苦くてだめだったわ」
そう言いながら、夕音と響生はおいしそうにコーヒーを飲む。私はそれがうらやましくて、置いたままどうしようもできないカップを苦い目で眺めた。
「律も大きくなったら飲めるようになるよ」
響生が何気なく言う。
ふいに私の中に真っ暗な気持ちが押し寄せた。
私は口をへの字にしてつぶやく。
「……大きくなんてなりたくない。私、「出来の悪い子」なんでしょ」
響生から表情が消える。
「おばあちゃんがよく言ってた。お父さんは出来が悪かったって。お母さんは性格が悪かったって。私も将来、出来の悪い大人にしかならないって」
「律!」
響生は私の両肩を押さえて言い返した。
「ばーちゃんは口の悪い人だったんだ。律のお父さんもお母さんも立派な人だった。律はこれからどんな大人にだってなれる!」
「だって、おばあちゃんが言ったもの……」
両親を幼い日に亡くした私は、祖母の元で育った。繰り返し祖母がこぼした言葉は、私の中で絶対の真実だった。
その絶対の祖母が亡くなった去年の春から、私は外に出られなくなった。引き取ってくれた叔父の家族は優しくしてくれたけど、私は今も人前に出るのが怖い。
「違う。違うんだよ、律」
本当は私の従兄である響生は、泣きそうな顔で首を横に振る。私は響生から目を逸らした。
響生は私を抱き上げて膝に乗せると、しばらくあやすように揺らしていた。
「律ちゃん」
ふいにカウンターの向こうから、夕音が私に声をかけた。
夕音は一つのカップを用意していた。そこには生クリームのたっぷり乗った、香りのいい飲み物が満ちていた。
「飲んでごらん。きっとおいしいわ」
カップの縁には、可愛いふくろうの陶器細工が私をみつめていた。夕音はそれをちょんとつついて、私にカップを差し出す。
私は恐る恐るカップを持ち上げて一口飲む。
「……おいしい」
ほんの少し苦かったけど、でも甘くて頬がほころんだ。私が冷ましながらちょっとずつ飲んでいると、夕音と目が合った。
夕音の目は、テレビで見るようなかわいいお姉さんとは違う。目じりまでの線がすらっとしていて、その奥にある瞳は澄み切っていてどきりとする
「律ちゃんが飲んでいるのもコーヒーなのよ」
「え?」
でもその目で笑いかけられると、まるで天使にほほえみかけられたような気持ちになった。
「生クリームとお砂糖をたっぷり入れているからわかりにくいだけ。でもごまかしてるわけじゃないの。今の律ちゃんにとっては、そのコーヒーの方がおいしいのよ」
夕音はまっすぐに私をみつめる。
「甘いものがおいしい。それは素敵な時間。でもそのうち、苦いものも悪くないって思う。たとえば……」
ふっと夕音と私の距離が近くなる。
頬に優しい体温が触れた。夕音の柔らかい鼻が、耳をかすめた。
「私のように悪いお姉さんも、いつか好きになるかもしれないわよ?」
私の頬にキスをした夕音は、悪戯っぽく喉を鳴らして笑った。
私はかあっと顔を赤くしてうつむく。夕音、と響生がとがめるように名前を呼ぶ。夕音はくすくす笑いながらカウンターに頬杖をついた。
「またおいで、律ちゃん」
私が目だけを上げると、夕音はカップに指を置いて首を傾ける。
「コーヒーを淹れてあげるわ」
口の中に残ったかすかな苦味が、心地よく体の中に入っていく気がしていた。
今の一番好きな時間は、帰国の合間のひとときのコーヒータイム。
「午後から寄ってもいい?」
「あら、今日帰国だったの」
成田空港から夕音の喫茶店に電話をかけると、彼女はゆったりと笑う。
「うん。帰っておいで」
夕音はすっかり母親の口調になっていて、感慨深い。響生と結婚してもう十年になるけど、未だに彼女は私の悪いお姉さんだった。
楽譜と衣装、数日分の日用品だけスーツケースに入れて海外を転々としていると、時々自分の居所を忘れそうになる。そういうとき、夕音と響生に会うことにしている。
新幹線で二時間、最寄り駅に降りる。夏の日差しが明るく、田園を金色に照らし出していた。
カランコロンと鈴を鳴らして、「休憩中」の札のかかった懐かしい喫茶店に入る。
奥に行っているのか、夕音の姿はなかった。代わりに、一生懸命グランドピアノを弾いている小学生くらいの女の子がいた。
私はほほえんで、邪魔をしないようにカウンターの隅に座ってその音色を聞いていた。
曲が終わったら、拍手をする。女の子はびっくりしたように立ち上がった。
「お姉さん、この間テレビで見た!」
私は困って苦笑する。
「私のこと覚えてないんだ。そっか、前会ったときは三年くらい前だもんね」
「ねえ、どうしたらお姉さんみたいにピアノ上手になるかな?」
女の子はしょんぼりした様子で自分の手を見下ろす。
「全然上手にならないの。私、ピアノ弾いてていいのかな」
私は少し考えてカウンターから降りると、女の子に歩み寄ってその前で屈みこむ。
「美音ちゃんがピアノのことを好きなら、いつだって弾いていいの。それは素敵な時間なんだから。苦い時も、たくさんあるかもしれないけど……」
夕音と響生の娘、今年小学三年生の彼女に、私は言葉を贈る。
「それだっていつか、黄金の時間になるよ。……私も、そうだったようにね」
ぽんと愛しい子の頭をなでて、私は笑った。
その頃私はある事情から学校に通わず、家の中でピアノばかり弾いていた。家族が心配そうに見守るまなざしの中、他にどうしたらいいのかわからなかった。
「律、グランドピアノを弾きに行かない?」
暑さが静まる日暮れ時のことだった。兄の響生が大学から帰って来るなり私を外出に誘った。
私はうつむいて言う。
「……やだ。怖い」
「ここから五分くらいの、兄ちゃんと仲のいい友達の家なんだ。お父さんが喫茶店をやってるけど、今は休憩時間でお客さんは誰もいないよ」
響生は私の手を取って、その手を持ち上げながら言う。
「兄ちゃんが手をつないでて、離さないから。帰りたくなったら、すぐ連れて帰る」
ね、行こうよ。響生は明るく笑った。
響生は我の強いところがあって、年もずいぶん上だから苦手な時期もあった。
でも私が家に閉じこもってからわかった。響生は私が気づかなかっただけで、ずっと私を守ってくれていた。
「うん。手、つないでて」
私が手を握り返すと、響生は笑顔のまま少しだけ目を伏せて、うなずいた。
久しぶりの外は日差しがまぶしくて、空気の匂いも夏と秋がまじりあっていた。最後に家の外に出た頃は、まだ肌寒さを感じる淡い春の空気だった。
私は響生の背中に隠れるようにしながら歩いた。ひぐらしの声が辺りに立ち込めていた。
響生が立ち止まったのは、彼の言う通り家から五分くらいのところにある喫茶店だった。レンガの壁を緑のカーテンが覆い、レトロな空気の漂う、褐色の建物。「休憩中」の札がかかっている。
「こんにちは」
カランコロンと鈴を鳴らして、響生は店の中に入る。
そのとき、ピアノの音が聞こえた。知らない曲のはずなのに、懐かしい旋律だった。
同時に立ち込める不思議な香り。ちょっと苦そうで、大人っぽい匂いだった。
「友達が弾いてるんだよ」
足を止めた私を安心させるように、響生は私を振り向いて手を握りなおすと、手を引いて歩いていく。
お店には確かにお客さんはいなかった。奥に向かうと、グランドピアノの前で誰かが座っているのが見えた。
夕陽が窓から差し込んで、その人の横顔を映し出す。
はじめはお兄さんだと思った。長い黒のエプロンを巻き、白いシャツに黒いベスト。深い紅色のタイを締めて、大人っぽかった。
けれど服装に反して短い黒髪は柔らかそうで、全体を形作っている輪郭が繊細だったから。曲が終わった頃には、とても綺麗な女の子だとただ見とれていた。
「邪魔してごめん。夕音」
ユネ。まるで西洋人形のような名前の響きも、彼女の浮世離れした雰囲気にはぴったりに思えた。
「別に。あまり気乗りしない曲だったの」
夕音という響生の友達は、そっけなく言って椅子から立ち上がる。
そのとき、彼女は私の存在に気づいたようだった。少しだけ首を傾げて、小麦色の瞳で私を見やる。
「その子は妹さん?」
気まぐれな猫がのぞきこむような、そんな仕草だった。私はとっさに顔を伏せて、響生の手をぎゅっと握りしめた。
「うん。グランドピアノを弾かせてやってほしいんだ」
「いいけど、学校の音楽室にだってグランドピアノはあるでしょう?」
響生はそれ以上説明しなかった。でも一拍だけ、二人の間に言葉ではないやりとりがあったようだった。
夕音は滑るようにピアノの横に動くと、椅子の位置を上げてくれる。脇に置いてあった楽譜の束を持ち上げると、それをグランドピアノの上に広げた。
「律ちゃん。何が弾きたい?」
響生はほほえんで、行っておいでと目で私に合図する。
自然に響生の手を離すことができたのは、響生と夕音の間にあった温かい空気に背中を押されたからだった。
「知っている曲はある?」
私がおずおずとピアノに近づくと、夕音は楽譜をめくって見せてくれる。響生も私の頭上からのぞきこんで言った。
「ショパンの夜想曲。これ、律が好きな曲だな」
「大人っぽい曲が好きね」
夕音は思わずといったように笑う。一見すると冷たそうな容姿だったけど、その笑い方はかわいらしくて私もちょっと笑い返した。
私はいくつか夕音から楽譜を借りて、グランドピアノを弾き始める。もう響生の手を握っていなくても、他人と同じ部屋にいられる気がした。
夕音と響生は私から数歩離れたカウンターで、私を見やりながらぽつぽつと話をしていた。
「時々でいいから、律をここに迎えてやってくれないか」
響生が言っていた。
「俺たち家族は、律が家にこもりきりでも構わない。でもみんな日中は仕事や学校に出ていて、律は家で一人なんだ。寂しいんじゃないかと思って」
切れ端のように響生の声が耳に入って来る。
「いいお兄さんね」
夕音は苦笑して付け加える。
「いい彼氏ではないけどね」
「ごめん」
謝った響生に、夕音はくすくすと笑った。
「そこが響生のかわいいところよ」
夕音は立ち上がってカウンターの中に入っていく。そこでカップと何かの道具を出して、料理らしいことを始めた。
「律ちゃんも来てごらん」
気が付けば私はピアノを弾く手を止めて、じっと夕音がすることをみつめていた。
夕音に呼ばれて、私は店内を横切る。響生に手伝ってもらって少し高いカウンターの椅子によじ登った。
夕音はお湯を沸かす傍らで茶褐色の豆を挽いて、さっきの変わった道具に注ぐ。
「これはなあに?」
「コーヒーよ」
それはこの喫茶店中に満ちている匂いと、同じ匂いがした。苦そうで、けれど気になって仕方がない香りだった。
コポコポと鳴るお湯の音、じわりと盛り上がる茶褐色の渦。小学三年生の私には不思議の世界そのもので、目が離せない。
「コーヒー……」
「飲んでみる?」
夕音はカップにその飲み物を注いで私に差し出す。私はためらいながらカップを両手で包んだ。
一口飲んで、私はあまりの苦さに絶句する。せっかく作ってもらったものでもそれ以上一口も飲めなくて、私はカップをカウンターに置いた。
「ごめんなさい」
「いいのよ。私も初めてのときは苦くてだめだったわ」
そう言いながら、夕音と響生はおいしそうにコーヒーを飲む。私はそれがうらやましくて、置いたままどうしようもできないカップを苦い目で眺めた。
「律も大きくなったら飲めるようになるよ」
響生が何気なく言う。
ふいに私の中に真っ暗な気持ちが押し寄せた。
私は口をへの字にしてつぶやく。
「……大きくなんてなりたくない。私、「出来の悪い子」なんでしょ」
響生から表情が消える。
「おばあちゃんがよく言ってた。お父さんは出来が悪かったって。お母さんは性格が悪かったって。私も将来、出来の悪い大人にしかならないって」
「律!」
響生は私の両肩を押さえて言い返した。
「ばーちゃんは口の悪い人だったんだ。律のお父さんもお母さんも立派な人だった。律はこれからどんな大人にだってなれる!」
「だって、おばあちゃんが言ったもの……」
両親を幼い日に亡くした私は、祖母の元で育った。繰り返し祖母がこぼした言葉は、私の中で絶対の真実だった。
その絶対の祖母が亡くなった去年の春から、私は外に出られなくなった。引き取ってくれた叔父の家族は優しくしてくれたけど、私は今も人前に出るのが怖い。
「違う。違うんだよ、律」
本当は私の従兄である響生は、泣きそうな顔で首を横に振る。私は響生から目を逸らした。
響生は私を抱き上げて膝に乗せると、しばらくあやすように揺らしていた。
「律ちゃん」
ふいにカウンターの向こうから、夕音が私に声をかけた。
夕音は一つのカップを用意していた。そこには生クリームのたっぷり乗った、香りのいい飲み物が満ちていた。
「飲んでごらん。きっとおいしいわ」
カップの縁には、可愛いふくろうの陶器細工が私をみつめていた。夕音はそれをちょんとつついて、私にカップを差し出す。
私は恐る恐るカップを持ち上げて一口飲む。
「……おいしい」
ほんの少し苦かったけど、でも甘くて頬がほころんだ。私が冷ましながらちょっとずつ飲んでいると、夕音と目が合った。
夕音の目は、テレビで見るようなかわいいお姉さんとは違う。目じりまでの線がすらっとしていて、その奥にある瞳は澄み切っていてどきりとする
「律ちゃんが飲んでいるのもコーヒーなのよ」
「え?」
でもその目で笑いかけられると、まるで天使にほほえみかけられたような気持ちになった。
「生クリームとお砂糖をたっぷり入れているからわかりにくいだけ。でもごまかしてるわけじゃないの。今の律ちゃんにとっては、そのコーヒーの方がおいしいのよ」
夕音はまっすぐに私をみつめる。
「甘いものがおいしい。それは素敵な時間。でもそのうち、苦いものも悪くないって思う。たとえば……」
ふっと夕音と私の距離が近くなる。
頬に優しい体温が触れた。夕音の柔らかい鼻が、耳をかすめた。
「私のように悪いお姉さんも、いつか好きになるかもしれないわよ?」
私の頬にキスをした夕音は、悪戯っぽく喉を鳴らして笑った。
私はかあっと顔を赤くしてうつむく。夕音、と響生がとがめるように名前を呼ぶ。夕音はくすくす笑いながらカウンターに頬杖をついた。
「またおいで、律ちゃん」
私が目だけを上げると、夕音はカップに指を置いて首を傾ける。
「コーヒーを淹れてあげるわ」
口の中に残ったかすかな苦味が、心地よく体の中に入っていく気がしていた。
今の一番好きな時間は、帰国の合間のひとときのコーヒータイム。
「午後から寄ってもいい?」
「あら、今日帰国だったの」
成田空港から夕音の喫茶店に電話をかけると、彼女はゆったりと笑う。
「うん。帰っておいで」
夕音はすっかり母親の口調になっていて、感慨深い。響生と結婚してもう十年になるけど、未だに彼女は私の悪いお姉さんだった。
楽譜と衣装、数日分の日用品だけスーツケースに入れて海外を転々としていると、時々自分の居所を忘れそうになる。そういうとき、夕音と響生に会うことにしている。
新幹線で二時間、最寄り駅に降りる。夏の日差しが明るく、田園を金色に照らし出していた。
カランコロンと鈴を鳴らして、「休憩中」の札のかかった懐かしい喫茶店に入る。
奥に行っているのか、夕音の姿はなかった。代わりに、一生懸命グランドピアノを弾いている小学生くらいの女の子がいた。
私はほほえんで、邪魔をしないようにカウンターの隅に座ってその音色を聞いていた。
曲が終わったら、拍手をする。女の子はびっくりしたように立ち上がった。
「お姉さん、この間テレビで見た!」
私は困って苦笑する。
「私のこと覚えてないんだ。そっか、前会ったときは三年くらい前だもんね」
「ねえ、どうしたらお姉さんみたいにピアノ上手になるかな?」
女の子はしょんぼりした様子で自分の手を見下ろす。
「全然上手にならないの。私、ピアノ弾いてていいのかな」
私は少し考えてカウンターから降りると、女の子に歩み寄ってその前で屈みこむ。
「美音ちゃんがピアノのことを好きなら、いつだって弾いていいの。それは素敵な時間なんだから。苦い時も、たくさんあるかもしれないけど……」
夕音と響生の娘、今年小学三年生の彼女に、私は言葉を贈る。
「それだっていつか、黄金の時間になるよ。……私も、そうだったようにね」
ぽんと愛しい子の頭をなでて、私は笑った。